�ǂ��ł����B
�݂Ȃ�����{����ǂ�ŁA�K���ɂȂ�܂��B

�{�̏Љ�
���̗F�l��������������A�ւ�����肵���{�̏Љ�ł��B
�����ł͍ŋ߂̂��̂������Љ�܂��B
����܂ł̈ꗗ�\�̏����Ȃǂ��N���b�N����ƏЉ���⒘�҂���̃��b�Z�[�W���ǂ߂܂��B
<����܂ł̏Љ��ʈꗗ��
|
(�ŐV�̏Љ�Ђł��j �u�g���^�`�[�t�G���W�j�A�̎d���v �u�J�C�[��4.0-�X�^���t�H�[�h��
��ƂɃC�m�x�[�V�������N�����v |
���L���X��ʂ��āA ���^��R�[�i�[ |
���u���ɂ����낵�����۔ƍ߂̘b�v�i�����o�Ł@1300�~�j
�_���s�Ȃ���́u���ɂ����낵�����۔ƍ߂̘b�v�i�����o�Ł@1300�~�j�����Љ�܂��B
�{���̏o���_�ɂȂ��������Ɋւ��ẮA�����_�����炨�b�����������Ȃ���A�����ɂ��ĂĂ��Ȃ����Ȃ�����̂ł����A�����̃T�����ʼn��߂Ď��グ�����Ǝv���Ă��܂��B
�܂��͏o�ŎЂɂ��{���̏Љ�����ǂ݂��������B
�{���́A���{�̃G�����E�u���R�r�b�`�Ƃ�������A���҂̎��O�̎����ł��B ���{�ł́A���łɊ������̂�����ƁA�Ƃ�킯���ۋƊE�ɁA�͂ނ����l�͂��܂���B ��e�̌�ʎ��̂����������ɁA�������N�ی��𗘗p����`�Ō�ʎ��̂̕⏞������̂͂��������̂ł͂Ȃ����ƒ��҂��咣����ƁA�s���ߕ߁E�l�ߔ�Q�ƂȂ��Ă��܂��܂����B�����������������܂��B �{����ǂ�ŁA�s���ȗ���ɂ�����Ă���u��ҁv�ɂ��āA���Ѝl���Ă������������ł��B
�G�����E�u���R�r�b�`�B
�W�����A�E���o�[�c�剉�̉f��u�G�����E�u���R�r�b�`�v���ς��l�����Ȃ��Ȃ��ł��傤�B
�������܂������A���������Ă݂�ƁA�������ɒ��҂��_������ɂ͂����������͋C������܂��B���R�ɏo�����Ă��܂��������@�艺���Ă��������ɁA�����\���Ōł߂��A�s�J�����ɕ����Ă�����{�̎Љ�ɂԂ����Ă��܂��A�ǂ�ǂ�Ɛ[�̂߂肵�Ă����_������ɂ́A�ނ���G�����E�u���R�r�b�`�ȏ�̃p���[�������܂��B
�{���ɂ́A�����_�����A�ˑR�̕�e�̌�ʎ��̂���A�������N�ی����ނ��ދ��呹�ۉ�Ђ̔ƍ߂Ɋ������܂�A�{������߂Ă����ߒ��������ɕ`����Ă��܂��B���������u�����ҁv�̓{��̑Ώۂ͂ǂ�ǂ�L����A�����ċ��Z�Ȃ܂ł��܂ފ������v�ɂ��u�Љ�I�ƍ߁v�ɒ��ނ��ƂɂȂ��Ă����Ƃ����A�����Ɛ[����������������̏��ł��B
�����Ŏ�������Ă���̂́A�P�ɑ��ۋƊE�̘b�ɂƂǂ܂�܂���B
���Ƃ��A�{���ł͓��ʖ��Ԗ@�l�̘b���o�Ă��܂����A�����Ɍ��݂̓��{�Љ�̖{�����_�Ԍ����Ă��܂��B���ׂė����ɗ��ߎ���A�J���Ǝ����͑S�������ɂȂ��Ă���Ƃ����v�������Ȃ���{�̌o�ώЉ�̎������A�ł��B
�������A�قƂ�ǂ̐l�����������d�g�݂ɑg�ݍ��܂�Ă��邽�߂ɁA�������Ȃ��Ƃ��u���������v�Ƃ��������Ȃ��Ȃ��Ă���B���̎d�g�݂�ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƁA�_������͗����オ���Ă���킯�ł��B�܂��ɁA���m���Ŏ��������߂����l�����Ƃ͈Ⴄ�A�u�����ҁv�Ȃ�ł͂̍s���ł��B
���������s���̌��ʁA�_�����g���A�u�����i�ׁv�Ƃ�������A�Њd�ړI�̃X���b�v�i�ׂ̑Ώۂɂ����̂ł����A����������{�̎i�@�E�̖��������Ă��܂��B
���������S���ĕ�点�čs�����邽�߂́A���������́u�ی��v��u�i�@�v�Ƃ����Љ�̎d�g�݂��A�����̖ړI�Ƃ͑S���^���̉^�p������Ă��錻�����_�Ԍ����Ă��܂��B
�_������́A�P�ɖ���N���Ă��邾���ł͂���܂���B�g�̂��͂��čs�����Ă��܂��B���Ƃ��A��ʎ��̑��۔ƍߑ�ψ���𗧂��グ����A�u���X���b�v�@����v�̐��芈�����Ăт������肵�Ă��܂��B
�{���́u���Ƃ����v�̈ꕶ���Љ�܂��B
���܂܂ō����̖ڂ���I���ɉB������Ă����s���s�ׂ̕s�K�ؐ�����ш�@�����������A�s�����@�̓��e�����s���i�ׂ̑ΏۂƂ��邱�Ƃɂ���ĕs�K�ؐ����@���𑁊��ɐ������邱�Ƃ͍����̌����`���̐����������Ƌ~�ςɂƂ��Ă��ɂ߂đ傫�ȈӋ`��L���܂��B
�u�B������Ă����s���s�ׂ̕s�K�ؐ�����ш�@���v�̉����B
�_������̊��������̂��������̈�ɂȂ�Ǝv���A���ɉ����ł��邩���l���Ă��܂����A�܂��͖{���̏Љ��n�߂邱�Ƃɂ��܂����B
�_������ɗ���œ����̃T�������J�Â������Ǝv���Ă��܂��B
�܂����ē������Ă��炢�܂��B
���w�g���^�`�[�t�G���W�j�A�̎d���x�i�k�쏮�l�@�u�k�Ѓ��V���@880�~�j
�g���^�̌o�c�ƌ����A�����ጸ��i���Ǘ��ɗD�ꂽ�g���^���Y�����������ɓ��ɕ����т܂����A������́u�g���^�̋����v�͎��X�ƃq�b�g���i�ݏo���g���^���i�J�������ł���A���̒��S�I�������ʂ����`�[�t�G���W�j�A�i�b�d�j���x�ł��B
���N�g���^�ŁA�`�[�t�G���W�j�A�Ƃ��āA�V�Ԃ��J�����Ă����k�쏮�l����́A���ꂩ��̐��n�����o�ώЉ�ɂ����ẮA���̐��i�J���V�X�e����������Ƃ̊��͂̍������낤�ƍl���Ă��܂��B
�u���݁A���E��Ȋ����鋐��h�s��Ƃf�`�e�`�̓g���^�̂b�d���x��O��I�Ƀx���`�}�[�N���A�v���_�N�g�}�l�W���[���x�Ƃ��ē������A�傫�Ȑ��ʂɌq���Ă��邱�Ƃ͈ӊO�ƒm���Ă��Ȃ��B�v���_�N�g�}�l�W���[���x�̌����A�{�Ƃ͂��̓g���^�̂b�d���x���v�Ɩk�삳��͌����܂��B
�܂�A���m�Â����ƂɂƂǂ܂炸�A�g���^�̂b�d���x�ɂ͂��ꂩ��̊�ƌo�c�̊��͂̌���̃q���g������Ƃ����킯�ł��B
�k�삳��́A�g���^��10�N�ԁA�`�[�t�G���W�j�A�Ƃ��Đ������̐V�Ԃ̊J���Ɏ��g��ł��܂����B������������̎��H��ʂ��Ē~�ς��Ă����̌��m���A�킩��₷���܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�{���̒��S�́A�k�삳��̑̌����琶�܂ꂽ�b�d�P�V���i����������A�q�b�g���i�J���̃|�C���g�j�̏Љ�ł��B���̑�1���́A�u�Ԃ̊��J���͏�M���A�b�d�͐Q�Ă��o�߂Ă��Ƒn���i�̎������v��������v�ł��B���ꂾ���ǂނƁA�k�삳��͂����̖җ�Ј��̂悤�Ɏv����������܂��A�����ł͂���܂���B����ɑ���17����ǂ�ł��炤�ƁA�k�삳��́u�������Ƃ̓N�w�v���邢�́u������N�w�v���킩���Ă��炦��ł��傤�B
�u��l�ł������̐l���K���ɂ����蕨���J���������v�Ƃ����̂��k�삳��̖������������ł����A����͌���������A�u�����ԃ��[�J�[�̐l�ԂƂ��ĉ��Ƃ��ł��Ȃ��̂��v�ƍl���Â��邱�Ƃł����B���̂��߂ɖk�삳��́A�d���̂������A�܂��Â���Ɋւ������A�V�N�w���w��A��Q�Ҏ{�݂�K�₵���肵�Ă��܂����B��Ђ̒��ɂ��邾���ł́A�V�������i�͌�����܂���B
�{���ɂ́A���������k�삳��̖��ւ̎��g�݂���̓I�ɏЉ��Ă��܂��B
����͑傫���ς��A�uHOW�v����uWHAT�v�ւƎЉ���߂���̂��ς���Ă��Ă���BWHAT�ݏo���������鉿�l�n���̎d�g�݂������A���ꂩ��̊�Ƃ̊��͂ɂȂ����Ă����A�Ɩk�삳��͌����܂��B
�g���^���n��グ�Ă����b�d�̃V�X�e���́A���ꂩ��̎���A���[�J�[�����ł͂Ȃ��T�[�r�X������܂ނ��܂��܂Ȋ�ƂɂƂ��Ė��ɗ����낤�ƍl�����k�삳�A����̎��H�m��ɂ����Ȃ����J�����{���ɂ́A�͂������Ă��Ă�����{�̊�Ƃ�����������q���g����������悤�Ɏv���܂��B
���i�J���̂��߂̃e�L�X�g�Ƃ��Ă��Q�l�ɂȂ�ł��傤���A�ނ��낱�ꂩ��̓��������l����悤�ȓǂݕ����ʔ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���u�S�䂽���ȎЉ�@�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�Ƃ͉����v�i���^��@���㏑�с@1500�~�j
���������������炱���ǂ�łق����{������܂�
��Ƃ̎В��Ƃ��������̂������A�Љ�ւ̓���������ڎw�������슈���ɂ��ϋɓI�Ɏ��g��ł�����^�炳�P�O�O���ڂ̖{�u�S�䂽���ȎЉ�v�����㏑�т���o�ł��܂����B���ꂩ��̎Љ�r�W�����Ǝ������̐��������l���鎦�������荞�܂ꂽ�{�ł��B
�V�^�R���i�ŎЉ�̂���������߂Ė���Ă��邢�܁A�܂��Ɏ��X���o�ł��Ƃ����܂��B�����̐l�ɓǂ�ł������������Ǝv���A�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
15�N�O�A�������́A�h���b�J�[�̈��w�l�N�X�g�\�T�G�e�B�x�̖₢�����ɉ������A���T�[�u�b�N�Ƃ��āw�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�x���o�ł��Ă��܂��B
http://cws.c.ooco.jp/book-kiroku.htm#1jou3
�������A�ŋ߂̓��{�́A�������̃r�W�����Ƃ͔��ɁA�S���������u�n�[�g���X�E�\�T�G�e�B�v�ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ��������͊����̌���Ŏ������Ă���悤�ł��B����ɁA�R���i�����ŁA�l�Ɛl�Ƃ̂Ȃ��肳����������Ȃ��Ă��Ă���B�����炱���A�u�S�䂽���ȎЉ�v�Ƃ��Ẵn�[�g�t���E�\�T�G�e�B�����߂Ėڎw���ׂ����ƍl���A�O����S�ʉ��e�����w�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B2020�x�Ƃ��Ė{�����o�ł����̂ł��B
�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�Ƃ́A�u������l�X���K���ɂȂ낤�Ƃ��A�v�����A���ӁA�����A�����A�����ċ����Ƃ��������̂����������l�����Љ�v���ƈ������͒�`���Ă��܂��B�����������A�u�l�Ɛl���������������Љ�v�ł��B
�ŋ߂̓��{�̎Љ�́A�ǂ��������������Ă��āA�y��������܂���B�t�F�C�X�u�b�N�̂����ł��A�l�K�e�B�u�Ȉӌ���l�̑�������������̂������A�u������v�ǂ��납�u�₵���v�ɏP���邱�Ƃ������ł��B�����ŁA�u�l�Ɛl���������������Љ�v��ڎw���Đ����Ă��鎄�Ƃ��ẮA�{���𑽂��̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���������킯�ł��B
�Љ�̃r�W�����́A����܂ł����܂��܂Ȑl����������Ă��܂����A���������l�����̃r�W������v�����A�ƂĂ��킩��₷�������E�������Ă���̂��{���̓��F�ł��B���̈����ǂ߂A�Љ�ɂ��Č��ꂽ��v�ȍl���ɐG����܂��B
�������A�������炵���A���Ƃ��A�u���l���v�u���ݕ}���v�u�z�X�s�^���e�B�v�u�Ԓ������v�u���V�a���v�Ƃ��������_����c�_����������Ă��āA�����ǂ�ł��邤���Ɏ��R�ƈ������́u�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�v�̐��E�Ɉ������܂�Ă����܂��B
�Â��āA���̎Љ�̍���Ƃ��Ȃ�N�w��|�p�A�@��������A�u��������S�̋����̂ցv�Ƃ����r�W�����ւƓ�����Ă����܂��B�@�������̐l�ɂ͂��Гǂ�łق����Ƃ���ł��B�@������炸�ɎЉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B
�ŋ߁A�Љ�̑S�̑��������ɂ����Ȃ��Ă��܂����A�{����ǂނƁA�Љ�Ƃ������̂������₷���Ȃ�Ǝv���܂��B���Ȃ��Ƃ��A�Љ�Ǝ����̐��������l����q���g����������͂��ł����A�u�S�䂽���ȁv�Ƃ͈�̉��Ȃ̂����l����ޗ�������������炦��Ǝv���܂��B
�������̌l�I�Ȗ�������Ă���̂��e�ߊ������Ă܂��B�������ɂƂ��āu�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�v�̏ے��̈�͌��̂悤�ł��B�������ł������Ă��܂����A�������̓��i�e�B�b�N�i�������j�Ȃ̂ł��B
���Ȃ݂ɁA���̓t�F�C�X�u�b�N�����X�����Ă��܂����A���V���l�M�҂ł��̂ŁA���ɂƂ��Ẵn�[�g�t���E�\�T�G�e�B�̎���͂��V���l�ł��B
�܂�����Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������ł����A�������̒���n�[�g�t���E�\�T�G�e�B���x�[�X�ɁA�����ɂƂ��Ẵn�[�g�t���E�\�T�G�e�B���\�z���Ă݂�̂��ʔ����ł��傤�B
�����������ɓ����ŃT����������Ă��炦��悤�ɗ���ł݂悤�Ǝv���Ă��܂��B
��B�ɂ��Z�܂��Ȃ̂łȂ��Ȃ��������@��������Ȃ��̂ł����B
�����ǂ܂ꂽ��A���Њ��z�����Ă��������B
���u�J�C�[��4.0-�X�^���t�H�[�h��
��ƂɃC�m�x�[�V�������N�����v�i�`���K�v�@�T�j�[�E�v���X�@1500�~�j
��Ƃ����ꂩ��ς��Ă������Ƃ��������ɒ��N���g�܂�Ă���`���K�v����̐V���ł��B
�`������̒���͈ȑO�ɂ��Љ���Ă��炢�܂������A����͊`�������ۂɎ��g������ӂ�ɏЉ�Ȃ���A����܂ł̎��H�m�����߂āA�̌n�I�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B
�u�J�C�[���v�����ƌ����A���m�Â��茻��ł̃R�X�g�팸��Y���̌���Ƃ����C���[�W�������Ǝv���܂����A�`������̖ڎw���u�J�C�[���v�́A��ƂɃC�m�x�[�V�������N���������ł��B
�ł�����{���̏������A�w�J�C�[��4.0-�X�^���t�H�[�h���@��ƂɃC�m�x�[�V�������N�����x�Ƃ���Ă��܂��B
�`������́A���������Ă��܂��B
�J�C�[���Ƃ������{���̋Z�p�́A������������Ȃ��V���v���ȋZ�p�ł���A�������^�p����Ɛ��Y����i���͂������̂��ƁA�V���i��V�}�[�P�b�g�������ݏo���Ă��܂��������s�v�c�ȋZ�p�Ȃ̂ł��B�����Ă���͓��{�ɂ����ł��Ȃ����ʂȋZ�p�ł��B�ł����琳�����J�C�[�����ł��Ă��Ȃ���Ђ��������̓��{�̒��������Ƃ̏́A�ƂĂ����������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
���̓J�C�[���w�������̃R���T���^���g�ł��B�����Ď��̎w����ł͂��̂��������Ƃ����ʂɋN���Ă��܂��B
�{���ł��Љ��Ă��܂����A�܂��Ɂu���������Ɓv���A�`������͂����ȉ�Ђň����N�����Ă��܂��B
����̃J�C�[���ɂ͂Ƃǂ܂�܂���B
��Ђ��̂��̂��傫���ς�����łȂ��A�ٕ���̃q�b�g���i�����܂ꂽ��A�V�����}�[�P�b�g�����@���ꂽ�肷�邱�Ƃ����邻���ł��B
�`������͑S�g�D�����^�̌o�c���v�����ƌ����Ă��܂����A���̌����͉͂�Ђ��x���Ă���S���̗͂ł��̂ŁA�傫�Ȏ��������ȂǕs�v�ł��B
���@�̂悤�Șb�ł����A���̎��g�ݕ��@�͂���߂ĊȒP�Ȃ̂ł��B
�|�C���g�́A�В��Ȃnjo�c�g�b�v�ƌ���œ����l�X�������ڐ��ɗ����āA��̂ƂȂ��Ď��g�ނ��Ƃł����A������ǂ�����Đi�߂邩�A�����Čo�c�Ƃ͉����i�o�c�҂̖����Ƃ͉����j���A�{���ɂ͋�̓I�ɏ�����Ă��܂��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���{�ł��̂ŁA��Ђ̌o�c�Ɋւ���Ă�����ɂ͂����߂ł��B
��Ђ����ł͂Ȃ��A�m�o�n��s���̕��ɂ��������߂ł��B
���w�������z���閼���K�C�h�x�i���^�璘�@���㏑�с@1400�~�j
���^�炳��́u�������z����v�V���[�Y�̑�3�e���o�ł���܂����B
���㏑�т���o�ł��ꂽ�w�������z���閼���K�C�h�x�i1400�~�j�ł��B
�Ǐ��A�f��ɑ����A����͖����ł��B����́u���t�͐l����ς�����͂������Ă���v�B
��������ʂȊ����̒��ŏo�������A�l����ς���͂������t���P�O�O�W�߂āA���ꂼ��Ɉ������̎v����Y���������W�ł��B
�V�^�R���i�E�C���X�ŁA���E���Ɂu���̕s���v���������Ă��錻�݁A�u���̕s���v�����z���錾�t���W�߂��{�����㈲���邱�ƂɁA�������͑傫�Ȏg���������Ă���Ə�����Ă��܂����A�܂��Ɏ��X���o�łŁA���Б����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
100�̃��b�Z�[�W���炢���Ȃ��Ƃ���������܂����A�����Ǝ����ɂƂ��ĐS�ɂ��Ƃ�Ɨ����錾�t��������͂��ł��B�����āA�����錳�C��������ł��傤�B
�܂�100�̌��t��ʓǂ���ƁA���N�A���Ɛ��̌���Ɋւ���Ă��Ă���������̐[�����b�Z�[�W���`����Ă��܂��B
�������̎����ςɂ�����钘��͂���܂ł����̃z�[���y�[�W�ł�������Љ���Ă�����Ă��Ă��܂����A�������̎����ς��т�3�̐M�O���A�{���̍Ō�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B
���̂R�Ƃ́A�u���͕s�K�ł͂Ȃ��v�u���ʊo��Ɛ�����o��v�u���͍ő�̕����v�ł��B
���������M�O�Ɋ�Â��đI�ꂽ100�̖����ɂ́A���ꂼ��Ɂu�l����ς���́v����߂��Ă��܂��B���̎����ɂ����A��������Ɗ��݂��߂āA��������͂������o���Ăق����Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA�����u�������z����v�V���[�Y�̎���2�����������㏑�т���o�ł���Ă��܂��B�悩�����畹���Ă��ǂ݂��������B
�w�������z����Ǐ��K�C�h�x
�w�������z����f��K�C�h�x
���u21���I�̕��a���@�v�i��{���@�O�ꏑ�[�@2300�~�j
���N�̌��@�L�O���́A�V�^�R���i�̉A�ɉB�ꂪ���ł������A�������������ł�������A���Б����̐l�ɓǂ�ł������������{���Љ���Ă��炢�܂��B
�R���i��@�ւ̑Ώ��̎d�����A�ς���Ă��邩������܂���B
�����̃T�����̏�A�̈�l�A��{������́A���N�A���a��l���̖��Ɏ��g��ł��Ă��܂����A���߂āu���a�v�Ɋւ��邱��܂ł̘_�l�������u21���I�̕��a���@�v���O�ꏑ�[���獡���o�ł��܂����B
���Ȃ�S�x�̍����_�l�ł����A��{����̓Ǝ��̎��_�Ǝ��Ԃ������Ď��g��ł����n���Ȋ����̐��ʂ̂������ŁA�ǂݏI����ƁA�Ȃɂ������o�������Ȃ�A���H�I�ȃ��b�Z�[�W�����������P���ł��B
�����ɐ�{����̓��{�����@�������Ă��f�ڂ���Ă��܂��B
��{����́A�����{�����́u�푈���̂��́v�u�푈���ł��鍑�Ɓv��ے肷��u���o�v�������]�����Ă��܂��B�������A���ꂪ�A�����J����́u���������@�v�̌��@�X���ƂȂ��������ƂŁA���{�l�͕��a�����������Ɓu���o�v���Ă��܂��A���́u���o�v�ՓI�ȗ��O�i�v�z�j�ɂ��Ă��Ȃ��������Ƃ���ɂ��܂��B
�����Ă��̂܂܂��ƁA���̕��a�̊��o���������A���{�̕��a�^���͎�����ɂ����E�ɂ��L�����Ă����Ȃ��B���������āA�푈�̌���ʂ��Ċl���������{�����̐��́u���o�v�Ɂu���S�X�v�Ƃ��Ắu���t�v��^���Ă�����v�z�ɂ��A����ɂ���𐢊E�ɔ����邱�Ƃ��}�����ƌ����܂��B
�����āA�����������ƂɌ����āA�s�����N�������Ƃ����̂��A�{���̃��b�Z�[�W�ł��B
�{���̑тɂ́A�u������A�����̐l�X�ɂ��p���ł��炦��^�����\�z���邽�߂Ɂv�Ə�����Ă��܂��B
��{����́A���{�����̐��́u���o�v�����߂��̕��a�́A�u�ϊv��v������V�������l�v�������Ƃ����܂��B�܂�A�푈���������ł͕��a�͎������Ȃ��̂ł��B
���̂��߂ɁA��{����́A�u�푈���̂��́v��ے肷��V�����_���A�u�푈���ł��鍑�Ɓv��ے肷��V�����_�����A���a��`�A�v���A��{�I�l���A�Љ�_��Ƃ����������A���X�ƓW�J���Ă����܂��B
�����āA���������_�l�܂��āA�Ō�ɓ��{�̌����ς��Ă������߂ɁA�V�������a���@�ƐV�����^���̎�̂ɂ��āA��̓I�ɒ��Ă��܂��B
�ޏ��Ƃ͂��Ȃ������Ⴂ�܂��̂ŁA�V�����C�Â��������͂��ł��B
�b������ɂ킽��̂ŁA�ȒP�ɂ͓��e�Љ�ł��܂��A���ɍŌ�́u21���I�̕��a���@�v�𑽂��̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�ł���A��{����̌��@�������Ă����ڒʂ��������������ł��B
��{����̌��@�������ẮA�������������I�ł��B
�����@�͑�P�́u�V�c�v����n�܂�܂����A��{���Ă̑�P�͂́u�l����э����̌����y�ы`���v�ŁA�l����������n�܂�܂��B����͋ߑ㌛�@�̃X�^�C���ł��B
���́A�����@�̑�Q�́u�푈�̕����v�ɂ������R�͂��A�u���q�R�ƍ��ۋ��́v�ƂȂ��Ă��āA���q�R�i���q���ł͂���܂���j�̕ێ���搂��Ă��邱�Ƃł��A
�u���a���@�v�Ȃ̂Ɏ��q�R��F�߂�̂��Ǝv���l������ł��傤���A���̈Ӑ}��ǂ߂A���Ԃ�[������l�͑����ł��傤�B�����ɍ��߂�ꂽ��{����̎d�|���ɂ́A���͎�̈٘_�������Ȃ�����A�������[�����܂����B
������ɂ���A�����Ȃ��Ƃ��l����������{�ł��B
�R���i����������������������A��{����̉������Ă��ޗ��ɂ��Ȃ���A���{�����@��b�������T���������ЂƂ��J�Â������Ǝv���܂��B
�� �u�O���^�̂˂����v�i���@�����e�B�i�E�L�������j���@�������X�@980�~�j
�������͂��܁A17�̏����Ɂu���Ȃ��������b���Ă���̂́A�����̂��Ƃƌo�ϔ��W�����܂ł������Ƃ������Ƃ��b����B�p���������Ȃ���ł��傤���I�v�Ǝw�E����Ă��܂��B
�����̖��O�̓O���^�B
���̖��O�ƁA�{��Ɣ߂��݂ɖ������\��Ɖs���₢�����́A�����̐l�̋L���ɂ܂��V�����ł��傤�B
�X�E�F�[�f���̃O���^�E�g�D���x������́A�n�����g����H���~�߂邽�߂Ɂu�����łł�����@�v�Ƃ��āA�w�Z�֍s�����ɍ���c�����O�ŁA�ЂƂ�ōR�c�X�g���C�L���n�߂܂����B
�������炢�܂�A�O���^�̃��b�Z�[�W�͐��E���ɍL�����Ă��Ă��܂��B
�����āA��N�X���ɍ��A�ŃX�s�[�`���������ɔ�����ꂽ�̂��A��L�̌��t�ł��B
�O���^����͂�����A�X�C�X�̃_�{�X�ōs��ꂽ���E�o�σt�H�[�����N������i�_�{�X��c�j�ł��X�s�[�`���s���܂����B
�O���^����̓X�E�F�[�f���̃X�g�b�N�z�����ɏZ��ł��܂����A��������X�C�X�̃_�{�X�ɂ͔�s�@���g�킸�ɁA���H��30���Ԃ����čs���������ł��B
��s�@�������Ɋ��ɕ��ׂ������邩���n�m���Ă��邩��ł��B
�O���^����̕�e�͍��ۓI�Ɋ��Ă���I�y���̎肾�����ł����i���{�ɂ��������Ƃ����邻���ł��j�A�O���^����ɐ�������āA���܂͔�s�@�̎g�p����߁A�C�O�ł̌�������߂������ł��B
��������ς����̂ł��B
���̃O���^����̂��Ƃ��Љ��u�q�������v�̖{���������X����o�ł���܂����B
�F�l�������Ă��Ă��ꂽ�̂ŁA���������ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�u���w�Z���w�N�ȏ�v���ΏۂƂ���Ă��܂����A��l�ł��킩��{�ł��B
���́A��l�����q�������̂ق����lj�͂��D��Ă���Ǝv���Ă��܂����A���̖{�͂��Ԃ��w�𑲋Ƃ����l�ł��A�����ł��m�����c���Ă���Ȃ�A�����ł���ł��傤�B
�������A�{�����������Ă���̂́A�������肵���m���Ǝv�l�͂��܂������Ă��Ȃ��q�ǂ������ł��B
�{���̕\���ɂ́A�u�n�����܂���@�����ɐ�����@��l�ɂȂ�܂ő҂K�v�Ȃ�ĂȂ��v�Ə�����Ă��܂��B
�q�ǂ��������ł��邱�Ƃ́A��l����������������܂��B
�ł��A�O���^����̕�e�������Ă���Ă���悤�ɁA��l�����ɂ��ł��邱�Ƃ�����B
�{���𑗂��Ă��Ă��ꂽ�F�l�́A�u���̖{�́A�C�g���̃��b�Z�[�W�{�ł͂Ȃ��A�O���^���g�������ĐV�����������������A���ꂩ��̐V����ւ̃G�[���ƂƂ炦�܂��v�Ə����Ă��܂����B
�������ɂ������Ǝv���܂��B
�����āA�n�������ɑΏ�����ɂ́A�������̐�������₢�����Ȃ�������܂���B
�r�o�K�X�K��������Ȃǂƌ����Ă������A�����͌����Ă��Ȃ��ł��傤�B
�������A�l�Ԃł���A�N�ɂł��ł��邱�Ƃ�����͂��ł��B
�ł͎������ɉ����ł��邩�B
�܂��͍����̂������āA���̖{���ēǂނ��Ƃ���n�߂܂��傤�B
�����ēǂ�A���̖{���߂��ɂ���q�ǂ������ɂ����܂��傤�B
���̖{��ǂq�ǂ������������Ƃ������@�������Ă���܂��B
�������������������A��l�ɂ��ł��邱�Ƃ������Ă��邩������܂���B
���Б����̐l�ɓǂ�ŁA��������ς���_�@�ɂ��Ăق����ł��B
���u�E���q�́@���邢�����̃G�l���M�[�v�i�܌����j�@�V�]�_�@1800�~�j
�����T�������Ԃ̐܌����j����̐V���u�E���q�́@���邢�����̃G�l���M�[�v�i�V�]�_�j���o�ł���܂����B�h�C�c�̒E�����ϗ��ψ�����o�[�̃~�����_�E�V�����[�Y�������{�ɂ��}�����A�e�n�ōs�����u�����s���Ƃ̘b�������Ȃǂ̋L�^���܂Ƃ߂����̂ł��B�܌����A�����ɍŐV�̏��⒍�߂��Ă��˂��ɕ�L���Ă���Ă��܂��B
�E��������ɓ]�����h�C�c���A���ۂɂǂ��ς���Ă��Ă��邩����̓I�ɓ`����Ă��܂��B
����̐������ɂ����H�I�ȃq���g�����炦��{�Ȃ̂ŁA�����̐l�ɓǂ�ł������������A�Љ���Ă��炢�܂��B
�����́A3.11�̕����������̌�b��ɂȂ����A���������̂���o�t���ɂ������傫�ȊŔu���q�� ���邢�����̃G�l���M�[�v�Ƃ����W��������������̂ł��B
�P�Ɂu�E���q�́v�ł͂Ȃ��A�����Ɍ����Ẵr�W��������̓I�Ɍ���Ă��܂��B
���肪�w�~�����_�E�V�����[�Y����ƍl����u���{�̐i�ނׂ����v�x�ƂȂ��Ă��܂����A�������ł͂Ȃ��A���̐i�ߕ��Ɋւ��Ă���̓I�Ɍ���Ă��܂��B
�Ƃ�킯�A���Z���Ƃ̑Θb�ŌĂт������Ă���~�����_����̃��b�Z�[�W�͎��H�I�ŁA��������l���X�������H���ׂ����e�ł��B
��NGO�̖��c�ĉԂ����E���ŁA�u�������ǂ�����̂��B����͒P�Ȃ�G�l���M�[�̖�肾���łȂ��A�����`�̖��ł���A�������̕�炵��ƁA���̖��ł���A�������▢���̐���ɉ����c�����Ƃ����I���̖��ł��邱�Ƃ��A���̖{�́A�����ĉ��������܂����Ȃ��A���Ղ����m�łƂ������t�Ŏw�������Ă���Ă���v�Ə����Ă��܂����A�܂��ɂ��̒ʂ�B�Ƃ������A���Гǂ�ł������������Ǝv���܂��B
�֑��ɂȂ肩�˂܂��A�������Ɉ�ۓI���������Ƃ��R�����Љ�܂��B
�h�C�c�ł́A���܁A�u�G�l���M�[�������v��u�G�l���M�[�����g���v���L�����Ă��܂��B���R�G�l���M�[�ɓ�������Ƃ������Ƃ́A�n��̐����̖������l���邱�Ƃł���A�E�����Ƃ����G�l���M�[�]���͌ٗp�̑n�o�ɂȂ����Ă��邻���ł��B
����́A�z�^�E�����^�̌o�ςւƌo�ς�Y�Ƃ̘g�g�݂�ς��A�l�X�̓�������ς��邱�Ƃɂ��Ȃ����Ă���悤�ł��B
�܂��A����n��͕��́A����n��̓\�[���[�Ƃ����悤�ɁA���R���n�̍����������R�G�l���M�[�̎x���������W�J����邱�ƂŁA�\���n�搮�����n�܂��Ă���悤�ł��B����܂ł̂悤�Ȓn��J���Ƃ͔��z���S���Ⴂ�܂��B
�����̐i�ߕ��Ɋւ��Ă��A�傫�ȕω�������悤�ł��B�~�����_����́A������u�h�C�c�̂����ЂƂ̊v���v�ƕ\�����Ă��܂��B
�E���������܂�����A����𐄐i���Ă������߂ɁA���{�ƍ�������������ƂȂ��d�g�݂�����ꂽ�����ł��B�����āA�����̐M����ɂ͎s�������Ƃ̌𗬂��K�v�ł���Ƃ����l���ŁA���ځA�����ɌĂт����Đ����ւ̎Q�����������������ł��B
�~�����_����́A�u�E�����͖����`�̂�����Ƃ����т��Ă���v�ƌ����Ă��܂����A�E������ʂ��āA�h�C�c�ł̓f���N���V�[���₢������Ă���悤�ł��B
�o�σp���_�C���A�n��J���p���_�C���A�����Đ����p���_�C���B
���̂R�̃p���_�C���V�t�g���ǂݎ��܂����A����Ƀ~�����_����́u�ϗ��v�Ƃ��u�v���e�X�g�v�Ƃ����l�ԂƂ��Ă̐������ɂ����y����Ă��܂��B
�w�Ԃ��Ƃ����肾������̓��e�ł����A����炪�ƂĂ����ՂȐ������t�ŏ�����Ă��܂��B
�����āA�~�����_����́u�O�����ɖڂ̑O�̏���ЂƂ��P���A�����Ɍ������Ă��ǂ��ϊv���Ă����v�p������傫�Ȍ��C�����炦�܂��B
�Ō�ɂ�����ƒ����ł����A�~�����_���t�N�V�}�̍��Z�������Ƃ̃g�[�N�Z�b�V�����ō��Z�������ɘb�������b�Z�[�W�����p���܂��B
�u�����̂Ȃ�������ƁA�����`����Ȃ���ł���B���Ȃ������̎���͑�ςȂ��Ƃ��n�܂��Ă���B�����`�������Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��A���������̖������������邽�߂ɂ��v
�u�F�������̍l���Ă��邱�Ƃ������m�̂������`�n�v
�u�����Ȉӌ������邩��A����������Ɣ������Ȃ��ƁA�����`�������Ă��܂��v
�i���Z����������A���������ɂł��邱�Ƃ͂��邩�Ɩ���āj�u�����̒n��̐����ƂɎ莆���o�������Ƃ���܂����H�@���������łȂ��č��Z�݂̂�Ȃ������ƂɎ莆�������đ���B���{�Ɏ莆�����������Ƃ���܂����B��������ǂ��ł��傤���B�����Ă��̎莆��V���Ђ�W���[�i���X�g�ɑ�������ǂ��ł����v
�@�����A�܌�����ɓ����ŃT����������Ă��炨���Ǝv���܂����A�܂��͂��Ж{����ǂ�ł��炦����ꂵ���ł��B
�����{������肳�ꂽ�����́A�܌�����ɒ��ڂ��A������������A�ŁA�������݂�1800�~�ő����Ă���邻���ł��B
���ɂ��A������������ΐ܌�����̘A��������`�����܂��B
���u���̓��{�ց@���a��`�錾�v�i���z�АV�� 1000�~�j
������}�c���������M�F����Ɣ��R�F�I�v���������u���̓��{�ց@���a��`�錾�v��������炢�܂����B
�V���Ȑ����V�X�e�����������邽�߂̎��H�錾�̏��ł��B
���������������o�Ă������Ƃɑ傫�Ȋ��҂������܂��B
�������A���̗��O���u���a��`�v�Ƃ����̂͂��ꂵ���b�ł��B
���́A�ȑO���珑���Ă���悤�ɁA���a��`�҂ł��B
���̂��������͑�w�S�N�̎��Ɍ����f��u�A�����v�ł��B
�e�L�T�X�Ɨ��^���̒��ōs��ꂽ�A�����̍Ԃ̍U�h���`�����f��ł��B
�����ŁA�W������E�F�C��������f�r�[�E�N���P�b�g���A�u���p�u���b�N�ƕ����������ŐS�����v�Ƃ����Z���t�Ɋ��������̂ł��B
http://cws-osamu.cocolog-nifty.com/cws_private/2005/05/post_b721.html
�ȗ��A����������������厖�ɂ��Ă��܂��B
�g�N���B���́u�A�����J�̖����`�v�ɂ��A���p�u�b���N�̐��_�������܂��B
�c�O�Ȃ���A���܂͑傫���ώ����Ă��܂����B
�Q�O�P�U�N�ɖ���}����̂������̐V�������O�ɁA�u���勤�a�}�v���Ă������Ƃ�����܂����A�c�O�Ȃ���u���a�v�͒N���g���܂���ł����B
http://cws-osamu.cocolog-nifty.com/cws_private/2016/03/post-f9c1.html
����Ȃ��Ƃ��������̂ŁA�傫�Ȋ��҂������āA�����ǂ܂��Ă��炢�܂����B
����́A�O�����ł��������Ă��܂��B
����}�������A��ƕ����g�������Čo�����A���̌�ɏP�������������̂悤�ȕێ畜�ØH���ƁA����Ȍo�ω^�c�𑱂��鎩���}���{���������āA����������T�ς��Ȃ���Ђ����玩�Ȃ̕ېg�ɏI�n�����}���͂̂���o���A���������J�I�X�̂Ȃ���7�N�ԍl�����������ʂł���B
�����Ė{�҂́A���̕��͂���n�܂�܂��B
�ߘa���N�X���g���@��X�͒�A���s�A���͂̊������}�A���Ԑ����𗣂�āA�V�������������W�c��g�D����B���̖��̂́u���a�}�v�Ƃ���B
�Â��āA���a�}�̍��ƖڕW�₻����������邽�߂̐V���Ȑ����V�X�e�����Љ��Ă��܂��B
���a�}�́A���Ƃ̖ڕW�Ƃ��āA�����̍K���̎������f���܂��B
�����Ă��̎����̂��߂ɁA���`�E�����E��z�E�F����4�̌������Ă��Ă��܂��B
���ƖڕW�⍑�Ƒ̐��ɂÂ��āA��̓I�Ȑ��̌n�I�ɏЉ��Ă��܂��B
���܂��܂Ȗ���c�_�ւ̖ڔz�肪����Ă��āA���������H�I�ł킩��₷���A���a�}�̖ڎw�����Ƃ��悭�킩��܂��B
���܂̐����̖��܂��čl�����Ă���̂ŁA�V�����������l����e�L�X�g�Ƃ��Ă����E�߂ł��܂��B
�C�y�ɓǂ߂�{�i�V���j�ł��̂ŁA���Б����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�ƁA���������������ŁA����Ȏ����������܂��B
���҂��傫������������������܂��A���ɂ͂��������̕�����Ȃ����c��܂����B
�������������̂́A���̕��͂ł��B
���{������ɒǂ�����ł���̂́u�x���v�ɂ���B
���̕x�����\�ɂ�����̂������A�u�����v�ł���B
����܂ł̓��{�́A�����ېV�ȗ��́u�x�������v�������ɂ��Ă��܂������A���ꂱ������肾�Ǝw�E���Ă���킯�ł��B
�ƂĂ������ł��܂����A�������琭���̋c�_���n�߂�p���ɂ��������܂��B
�����ېV���ɂ��A�u�x�������v�ɑΛ����āu�x�������v���c�_����Ă��܂������A���̋��a�}�́u�x���L���v��W�Ԃ��Ă���悤�ł��B
�����ǂ�ŁA������ƍ��������Ă��܂��܂����B
�����̃p���_�C���]��̎����ɗ��Ă���ƍl���Ă��鎄�ɂ́A��͂�]���^�́u�ߑ㍑�Ɓv�X�L�[���ł̋c�_�ɂ��������̕�����Ȃ��������Ă��܂����̂ł��B
���������A�u�x���v��u�����v����肾�Ǝw�E���Ȃ���A�u�x���L���v�Ɓu�x���v����Ɍ���Ă��܂��B
���߂āu�����x���v�Ɣ��z��ς��Ăق��������C�����܂��B
�����Ɋւ��Ă͒��o�ς��u���S�v�Ƃ��Ă��܂����A�����ł���͂��͋��K�o�ς̂悤�ł���A�V�����u�����v�T�O�ւ̔��z�̓]��͂��܂����Ă��܂���B
���́A���낻��u���Ɓv���甭�z���鐭����o�ςł͂Ȃ��A�����Ҍl���N�_�Ƃ��Ĕ��z���鐭����o�ςւƎ��_�ƃx�N�g�����P�W�O�x�]�ׂ����Ǝv���Ă��܂����A�{���Ō������a�����͂ǂ��������܂ł͑z�肵�Ă��Ȃ��悤�ł��B
����ɁA�u�����̖ڕW��l�ԑ���`�i�s�[�v���E�t�@�[�X�g�����j�ɒ�߂�v�Ƃ���悤�ɁA�������I�Ȃ��̂����݂��Ă��āA���݂̐����Ƃ̈Ⴂ�����܂茩���Ă��܂���B
���`�E�����E��z�E�F����4�̌������A�u�F���v���̂����A����������ɂ͊댯�ȁu�v���X�`�b�N���[�h�v�ł��B
���������Ǝ��͖{���̒�Ăɔ����Ă���悤�Ɋ����邩������܂��A�����ł͂���܂���B
�����̐�����ς���ɂ́A���P�^�̊����������Ă�����ׂ��ł����A�v���I�Ȋ����������Ă������Ǝv���Ă��܂��B
����܂œ����ŁA�V����������o�ς��e�[�}�ɂ����T����������Ă��܂����A�p���_�C���]��̂悤�Șb�͂قƂ�Ǔ`���Ȃ����Ƃ��̌����Ă��܂��B
�{���ɂ͂��܂��܂Ș_�_���̓I�Ȓ�Ă��܂܂�Ă��܂��B
���݂̐������T�ς��A���ӎ������߂�ɂ́A�����ޗ����R�ς݂ł��B
���������A�V���Ȓ�Ă̏����ǂ�ǂ�o�ł���A���������{�Ɋ�Â��ċc�_���L���邱�ƂŁA�����͕ς���Ă����͂��ł��B
�l�b�g�ɂ́A�u���a�}�̍L��v���ł��Ă��āA�L���Q���҂����Ƃ߂Ă��܂��B
http://kyowa-to.jp
�{����ǂ�ŁA��������������A�Q�����Ă݂Ă��������B
���u�Љ�I�Z�[�t�e�B�l�b�g�̍\�z�v�i�i���v���q�ҁ@���{�N�ف@1500�~�j
�����s�҂Ɋւ�������ς�炸�Â��Ă��܂��B
��肪���݉�����Ă����̂͂����Ƃ��Ă��A���ς�炸�u�����s�ҁv���̂��̂ɖڂ��s���߂��āA�Љ�S�̂ւ̎��삪�L�����Ă����Ȃ��̂��c�O�ł��B
���������X���́A�قڂ��ׂĂ̎Љ���Ɍ����邱�Ƃł����A�����͎����Ƃ��đΏ����Ă����Ƃ��āA���̔w�i�ɂ���Љ�S�̂̏ւ̎���Ǝ���̐������̌������Ƃ���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����Ɋ֘A���āA�P���̖{���Љ���Ă��炢�܂��B
�q�ǂ��̕n�����ӎ���������i�������̂��߂̎Љ�I�Z�[�t�e�B�l�b�g�����グ�Ă���u�Љ�I�Z�[�t�e�B�l�b�g�̍\�z�v�ł��B
��b�ɂȂ����̂́A�������琭�����̊��v���q�������i�߂Ă����u����i�������̂��߂̎Љ�I�Z�[�t�e�B�l�b�g�V�X�e���`���Ɋւ��鑍���I�����v�ł��B
�����̖ړI�́A�q�ǂ��̕n���ȂǁA�ƒ�̎Љ�o�ϓI�w�i�ɗR�����鋳��i���̊g�傪�Љ��艻���Ă��钆�ŁA���O���ɂ����鐭�����̌��ʂ⑽�l�ȃp�[�g�i�[�̘A�g�ɂ��Z�[�t�e�B�l�b�g�`���̎�����Q�l�ɁA�킪���̎{��Ɏ�����m���̒v�ł��B
���́A�{���̏o�łɊւ�����u�Љ��v�ҏW���̋ߓ��^�i���炱�̖{���Ă��炢�A�ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�u�Љ�I�Z�[�t�e�B�l�b�g�v�Ƃ����ƁA�����̐l�͍���҂��Q�ҁA���邢�͎��Ƃ�a�C�⎖�̂ŁA�������ێ��ł��Ȃ��Ȃ����l�̖����C���[�W���邩������܂���B
�������A�{���Ŏ�舵���Ă���̂́A�q�ǂ��̕n���⋳��i���̖��ł��B
�������A���ۂ̌��n��ނ����ƂɁA�A�����J�A�t�����X�A�C�M���X�̎��Ⴊ����������グ���Ă��āA�ƂĂ������ɕx��ł��܂��B
���킹�ē��{�̎�������L������ŏЉ��Ă��܂��B
���ۓI�Ȑ����_�ł͂Ȃ��A�����̎��Ⴉ�琭��̕��������������Ă���Ƃ��낪�ƂĂ������ł��܂��B
�q�ǂ��̖��́A�u�ی�ҁv��u�ƒ�v�A����ɂ́u�w�Z�v�Ƃ������݂ɉB����Ď��Ȃ��Ȃ������Ă��Ȃ���ɁA�����҂������グ�ɂ������߁A����̏œ_�ɂ͂Ȃ�ɂ����ł����A�q�ǂ��̖��́u�q�ǂ������̖��v�ł͂Ȃ��A�Љ�̎������ے�����Ɠ����ɁA���̎Љ�̖�������������u�Љ�S�̖̂��v�ł��B
�Љ�̂Ђ��݂́A�q�ǂ��̎��ӂŘI�o���Ă��܂�����A�q�ǂ��̍K����n�������Ă����ƁA�Љ�̖����������Ă��܂��B
�t�Ɍ����A�q�ǂ��̐��E����A�����̎Љ�̉\���������Ă��܂��B
�ł�����A���ׂĂ̐���̋N�_�́u�q�ǂ��v�ł���ׂ��ł͂Ȃ����ƁA���͎v���Ă��܂��B
�{���́A�����������_����A�ƂĂ������ɕx�ށA���H�I�ȏ����Ǝv���܂��B
�������u�Љ�I�Z�[�t�e�B�l�b�g�v�Ƃ��Ă��邽�߁A�����������e���`��邩�ǂ����s��������A���ꂪ�{�����Љ��C�ɂȂ������R�ł��B
�����̎Љ�I�Z�[�t�e�B�l�b�g�c�_�ɂ́u�q�ǂ��v���厲�ɂ����c�_�����Ȃ��Ɗ����Ă��鎄�Ƃ��ẮA�{������������̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
���Ⴊ�ӂ�ɏЉ��Ă��܂��̂ŁA�ǂ݂₷���A���H�I�ł��B
����͐��{��s���@�ւ����Ő��܂�Ă������̂ł͂���܂���B
�����̊S�⓭���������A�����ς��Ă����܂��B
���̈Ӗ��ł��A�������ĊW�҂����łȂ��A�����̐l�����ɖ{����ǂ�łق����Ǝv���܂��B
���{�ł́A�u�q�ǂ��̕n�����N�v�Ƃ����2008�N����A10�N�ȏオ�߂��Ă��܂����A���Ȃ��q�ǂ���������芪�����͉��P����Ă���悤�ɂ͎v���܂���B
������Z�[�t�e�B�l�b�g�ƌ����A�ǂ����Ă�����҂ɖڂ����������ł����A�q�ǂ��������N�_�ɂȂ�ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�ł���A���̃e�[�}�ł̃T�������J�������̂ł����A�ǂȂ�������Ă���܂��B
���u�C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V�����o�c�v�i���������ҁ@�o�c�A�o�Ł@2000�~�j
�������������̃C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V�����o�c������̐��ʂ��{�ɂȂ�܂����B
���̌�����̂��Ƃ͐������炨�������Ă��܂������A�r���ň�x�A�����ł��T���������Ă��炢�܂����B
���̕���́A���Ă͎������C���e�[�}�Ƃ��Ď��g��ł������ƂȂ̂ŁA�����[���ǂ܂����Ă��炢�܂����B
�{���ł́A�C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V�������A�u�o�c�헪�̌��ʓI�Ȏ��s�Ɍ����āA�g�D�œ����l�X�̒m���A�ԓx�A�s�����p���I�ɋ������邽�߂Ɍv�悳�ꂽ�g�D�I�ȃR�~���j�P�[�V���������v�ƒ�`���A�u�g�b�v�}�l�W�����g���C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V�����������o�c�̒��j�I��ƍs���̈�Ƃ��đ����A����I�Ȍo�c�̎d�g�݁i�d�|���j�ɑg�ݍ��݁A�o�c�헪�����ʓI�Ɏ��s���邱�Ɓv���u�C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V�����o�c�v�i�h�b�o�c�j�Ƒ����Ă��܂��B
�����āA���{�ƃA�����J�̊��21�Ђ������ނ��A�C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V���������̎d�g�݂Ǝ��H���Љ��ƂƂ��ɁA�u�Ј��̃��`�x�[�V�����v�u��ƕ����v�u���Ɛ헪�v�u��ƕϊv�v�Ƃ������A��ƂɂƂ��Ă̐헪�ۑ�ɍ��킹�āA�C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V�����o�c���H�̎��g�ݕ�����̓I�ɏЉ�Ă��܂��B
����ɁA���H�҂̂��߂ɁA�Ō�̏͂ł́A�������ʂ܂����u���ʓI�Ȑ헪���s�ɖ𗧂R�~���j�P�[�V������@�Q�S�v���̌n�I�ɐ�������Ă��܂��B
�����Ď��Ђ̎��h�b�i�C���^�[�i���E�R�~���j�P�[�V�����j�c�[������x�A�I�����Ă݂���ǂ����ƒ��Ă��܂��B
��Ƃ͂��܂��܂ȃR�~���j�P�[�V�����c�[���������Ă��܂����A���̑̌��ł͂قƂ�ǂ̊�Ƃ��������o���o���ɂƂ炦�āA���ʓI�ɓW�J���Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
���ɂ͂���炪���݂��Ɍ��ʂ�W�������Ă��邱�Ƃ�������悤�ł��B
����������������ł��A��Ƃ̃p�t�H�[�}���X�͔���I�ɏ㏸����͂��ł��B
���e�͓ǂ�ł��炤�����Ȃ��̂ł����A���������ł����_���������Љ�܂��B
�܂��{���̊���A�Г������ł͂Ȃ��A�Љ������ɓ���ẮA�\����������u�l�v���N�_�ɂ��Čo�c���l���悤�Ƃ��Ă���p���ł��B
���ʂȌ��������A�n���ݏo���悤�ȃR�~���j�P�[�V�����̎d�|�������߂��Ă���Ƃ����{���̃��b�Z�[�W�ɋ������܂��B
���̈Ӗ��ŁA�P�Ȃ�u�Г��L��v��u�C���i�[�R�~���j�P�[�V���������v�ł͂Ȃ��A�܂��Ɂu�o�c�v�̎��삪�g�ݍ��܂�Ă��܂��B
�����Ă��ꂪ���l�ݏo���A�Ђ��Ă͊�Ɖ��l�ɂ܂łȂ����Ă����Ƃ����킯�ł����A���̍ۂ́u��Ɖ��l�v���P�Ȃ�����I�Ȋ�Ɖ��l�ł͂Ȃ��u�l��Љ�̍K���ɂȂ���։v�≶�b�Ƃ����Ӗ������x�l�t�B�b�g�v�ƍl�����Ă���_�ɂ��������܂��B
�����ł̃T�����ł���x���グ���悤�ɁA�u�x�l�t�B�b�g�E�R�[�|���[�V�����v�̓������������L�����Ă��Ă��܂����A���{�̎��_����ł͂Ȃ��A�Љ�̎��_�����Ɖ��l���Ƃ炦�Ă������Ƃ����A�����ڂŌ�����Ƃ̋��݂ɂȂ��Ă����͂��ł��B
�R�~���j�P�[�V���������������u���l�v�ݏo������ɂ�����o�c���l���邽�߂̊i�D�̋��ȏ��ƌ�����ł��傤�B
��ƂɊւ��l�ɂ͂��Ђ��E�߂��܂����A��Ƃ݂̂Ȃ炸�A�����̂�m�o�n�ɂ������l�����ɂ��Q�l�ɂȂ�͂��ł��B
���u���^�Ƌ����̌o�ϗϗ��w�v�i�܌˂��Ƃȁ@�}���o�Ńw�E���[�J�@3800�~�j
�ƂĂ������ł���{�ɏo��܂����B
�L�@�_�Ƃ̗��Ƃ��Ēm�����ʌ����쒬�ɂ��鑚���_��̋��q���o����̎��H�����ƁA�����Ɋւ��Ȃ���A�����ɐ����Ă���l�����̃��C�t�X�g�[���[���x�[�X�ɁA�V�����������i�V�����Љ�̂�����j����������A�ӗ~�I�Ȗ{�ł��B
�u���^�Ƌ����̌o�ϗϗ��w�v�Ƃ��������ɂ��������Ђ��ł��܂��l������Ǝv���܂����A���܂��܂Ȑl�̋�̓I�Ȑ������┭�������S�ɂȂ��Ă���̂ŁA����̐������ƂȂ��ēǂ�ł����܂��B
�v��I�Ɍ����A�l�Ԃ̐��̑S�̐������邽�߂̎��H�̏��ł��B
�����ǂ݂������Ƃ��ɂ́A������Ƌ����܂����B
�����B�i�X�́u���҂̊�Ƃ́A�������ɉ������Ăт����鑶�݂Ƃ��Ă����Ɍ��O���Ă���v�Ƃ������t��A�C���C�`�̃R�����B���B�A���e�B�i���������j�Ƃ��������t���o�Ă�������ł��B
�������A���������ȕ��͂������Ɗo�債���Ƃ���ɁA���x�͋��q�����ނƂȂ���̂��邳�܂��܂ȗ���̐l�����ɑ���C���^�r���[�ɂ���ĕ`���o����鐶�X�������C�t�X�g�[���[���n�܂�܂��B
���̂����肩��A�������܂��悤�Ɉ�C�ɓǂ�ł��܂��܂����B
���Ȃ݂ɁA�����B�i�X�ƃC���C�`�̌��t�́A�{���̕`���o�����E�̎厲�ɂȂ��Ă��܂��B
������̊�́A�|�����j�[�́u�o�ς��Љ�W�ɖ��ߖ߂��v�Ƃ�������ł��B
���������Ɖ���������Ɋ����邩������܂��A�����������Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A�ނ��낻�������T�O�Ɏ��̂�^���A������̎������̐������ɂȂ��Ă����Ƃ����̂��A���҂̈Ӑ}�ł��B
���q���o���Ȃ��L�@�_�ƂɎ��g�̂��́A����߂Ė��m�ł��B
�ے�������q����̌��t���ŏ��ɏo�Ă��܂��B
�u�����S�ł�肤�܂��������A���ŏ���҂Ɉ���ł��炤���Ƃ��A���̂����₩�Ȗ]�݂ł���A���ꂪ�\�łȂ��悤�Ȕ_�Ƃ͂��܂�ɂ��݂��߂Ȃ̂ł͂Ȃ����B���̂悤�Ȃ��Ƃ���������Ă͂��߂āA�����̊�т��^�̊�тɂȂ�Ǝv���Ă����̂ł���v�B
�܂�o���_�́A���q����̐������тւ̎v���Ȃ̂ł��B
���́A�����ɁA��������͏o�Ă��Ȃ��u�ق���́v�������܂��B
�������u���̖{�������_�Ƃ��s���Ă����̂ł́A�ړI�̐������Ȃ肽���Ȃ��Љ�̎d�g�݂ƂȂ��Ă��܂��Ă���v�Ƃ����Љ�̌����̑O�ŁA���q����̂��܂��܂Ȋ������n�܂��Ă����܂��B
���̎��g�݂́A���s�����萬�������肷��̂ł����A�����Ȏ��s����̌��ʁA���݁A�s�����Ă���̂��A���K�_��ł͂Ȃ��A�u���琧�v�Ƃ����d�g�݂ł��B
�u���琧�v�Ƃ́A�o�������̂�����҂ɑ��^���A����ւ̎ӗ�́u����҂̑��Ŏ��R�Ɍ��߂Ă��������v�Ƃ����`�ŁA���Y�҂Ə���҂��Ȃ����Ă����A�Ƃ����d�g�݂ł��B
���̂Ȃ���́A���݂������悭�m�肠���A�u����Ƃ��̊W�v�Ɉ���Ă������ƂŁA�o���ɑ傫�Ȑ����̈��S��������Ă���B
�����āA���̂₨���̂��Ƃ�����l�̂Ȃ��肪�L�����Ă����B
�V�����������A�V�����Љ�̂�����̃q���g�������ɂ���B
�_������u���琧�v�Ɓu����Ƃ��̊W�v�ɏW���{���̓��e�́A�ȒP�ɂ͏Љ�ł��܂��A
�o�ŎЂł���w�E���[�J�̃T�C�g�ɂ������ŁA�T�v�͂��߂邩������܂���B
https://www.heureka-books.com/books/396
�܂��{���̑тɏ�����Ă�����R�߂���̐��E�����A�{���̓I�m�ȗv��ɂȂ��Ă��܂��B
�u�L�@�_�Ƃɂ���Ď��R�Ƙa�����A���i�����Ȃ����ʂ𐬗������邱�Ƃɂ���ĉݕ��̎������玩�R�ɂȂ�B����������������A�Ƃ�̔_���̉c�݂����Ȃ���A�{���͐l�Ԃ����R�ɐ����邽�߂̍����I�ȉۑ����Ă���v�B
�܂�A�{���͎��R�ɐ����邽�߂̐�����������������Ă���̂ł��B
��������܂��܂Ȑ���������̓I�ɗᎦ���Ȃ���ł��B
�����āA���R�Ȑ������ɂƂ��đ�Ȃ̂́q�ӔC�E���R�E�M���r���j�ɂ������������Ƃ������b�Z�[�W�ɂȂ����Ă����܂��B
���t��P�ɕ��ׂ������ł͂���܂���B
�܌˂���́A�u�ӔC�v�u���R�v�u�M���v�̌��t�̈Ӗ�����������Ƌᖡ���A������Ȃ��čl���Ă��܂��B
���q����́u���Ƃ̐��E�ɐ����Ă��Ȃ��v�Ǝ�����ʒu�Â��Ă��邻���ł����A�܌˂�����܂��A�ʂ̈Ӗ��Łu���Ƃ̐��E�ɐ����Ă��Ȃ��v�l���Ɗ����܂����B
�{���̃L�[���h�́A�����ɂ���悤�ɁA�u���^�v�u�����v�u�ϗ��v�ł��B
������������O�����ދ��Ȍ��t�ł����A���́u���s��v����������ƒn�ɑ��t���Č���Ă��܂��B
���������ꂪ�傫�ȕ����n���Ă�����肩�A�l�������邱�Ƃ̈Ӗ��������`���Ă���̂ł��B
�����悤�Ȍ��t����ׂ��A�����������{�Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B
���Ƃ��u�ϗ��v�B
�ϗ��Ɋւ���{��ǂ�Ŏ��͂�����a���������Ă��܂��܂��B
���̎��ۂ̐������ɂȂ����Ă��Ȃ�����ł��B
�ϗ��iethics�j�Ƃ������t�̌ꌹ�ł���M���V�A��̃G�g�X�́A�u�˂���v�u�Z�ݏ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�܂�A���̐l�̐������ł̕�炵��ʂ��Č`�Â�����u�������v��u�U�镑�����v�A����������A�ǂ���������K�ɕ�点�邩�̃��[���Ƃ��ׂ����l�̊���u�ϗ��v���ƁA���͍l���Ă��܂��B
�܌˂���́A���Ԃ������Ӗ��Łu�o�ϗϗ��w�v�Ƃ������t��I�̂ł��傤�B
�����ȗ��z�ȂǂƂ͖����̘b�ŁA�u�����ɑP�������邩�v�����҂̊S�ł��B
�����āA���ꂼ�ꂪ�P�������Ă���ΎЉ�͖L���ɂȂ�ƁA���Ԃ�m�M���Ă���̂ł��傤�B
�����A�����m�M���Ă����l�ł��B
�����₷�������߂邱�Ƃ��u�ϗ��v�ƍl����A���̃J�M�ƂȂ�̂́u���^�v�Ɓu�����v���Ɛ܌˂���͌����܂��B
�����ł��܌˂���͑ދ��Ȓ�`�ɂ͖������Ă��܂���B
���^�Ƃ́u���҂Ƃ̊W����L���ɂ��邱�Ɓv�ł���A�u�����v�Ƃ́u����Ƃ��̊W�v�Ő����邱�Ƃ��Ƃ����̂ł��B
������ɂ��u�o��v���K�v�ł��B
���ꂾ���ŁA�{���͑ދ��ȁu���^�v��u�����v���������{�ł͂Ȃ����Ƃ��킩���Ă��炦��Ǝv���܂��B
���łɌ����A�����ɂ�������Q�̌��t�A�u�o�ρv�Ɓu�w�v�ɂ��Ă��A�܌˂���́A�O�҂́u�I�C�R�m�~�N�X�i�Ɛ��j�v�u�o���ϖ��v�Ƒ����A��҂Ɋւ��Ă��A�����܂��ȁu���t�v�����ł͕s�\�����Ǝw�E���Ă���悤�ȋC�����܂��B
�ȏ�̂��Ƃ́A���̏���ȉ��߂ł��̂ŁA�܌˂���͎����邩������܂���B
�������A�{����ǂ�ł���ƁA�ޏ��̐[���Ď��H�I�Ȗ��ӎ��ƐV�����w�ւ̈ӗ~��������Ƃ���Ŋ����܂��B
�Ƃ���ŁA�����B�i�X�́u��v�͂ǂ���������Ă���̂��B
�����ɍ��߂�ꂽ���b�Z�[�W�́u�l�̑����̑��d�v�ł���A�ق�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����́A����������l�Ԃōs����Ƃ������Ƃł��B
�l�����݂��Ȃ���A�ق�Ƃ��̃R�~���j�P�[�V�������������Ȃ��B
�����āA�C���C�`�̃R�����B���B�A���e�B��T�u�V�X�e���X�T�O�́A�܂��Ɂu����Ƃ��̊W�v�ɋ������Ă��܂��B
�܌˂��u�I���Ɂv�ɏ����c�������͂��A���������ł����A���p�����Ă��炢�܂��B
����V�X�e���̒��Ō��ꊇ�Ǘ�����Ă����悤�Ȑ��E�ŁA���R�ƕs���ɂȂ����Ă���l�Ԃ����̑������������^���́A�������̐����Ɛ��������A���Y�ƍĐ��Y�A���R�A�ӔC�A�M���ɂƂ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��s���ȗv�f�Ȃ̂ł���B���̈Ӗ��ɂ����āA���Ƃ����ׂĂ̐l���A�����S�̂��u����Ƃ��v�̊W���ō\�z���邱�Ƃ͕s�\�ł������Ƃ��Ă��A���̂悤�ȊW���̂Ȃ����E�ł́A�������͐����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ����낤�B
�W���̂Ȃ����E�Ő����邱�Ƃɑ����̐l����炳��Ă��Ă��錻�݂̎Љ�ɏ����ł���a���������Ă���l�ɂ́A���ЂƂ��ǂ�ł������������{�ł��B
�����ƐV�����C�Â������q���g����Ǝv���܂��B
�����āA�ł���Ȃ�A�܌˂��c�������b�Z�[�W�i�{���́u�����Ɂv�Ɏ�����Ă��܂��j�������p���l������邱�Ƃ�S�������Ă��܂��B
�����ȏ�Ɏ�ϓI�ȁA�����������Љ�ɂȂ��Ă��܂������A���������֑����B
���҂̐܌˂��ƂȂ���ɂ́A���͎c�O�Ȃ��炨�����@��������܂����B
�����O�͂��������Ă��܂������A�܂������������{��������Ă����Ƃ͒m��܂���ł����B
�܌˂��ƂȂ���́A�{�����d�グ����A�S���Ȃ�܂����B
����ł��Ȃ������̂��A�S��A�c�O�ł��B
�{����ǂ�A�ǂ�Ȑl�������̂��낤�Ǝv���Ă�����A���̌�A��@����܌˂���̔�������A�Ȃ����ʐ^�������Ă��܂����B
�l�͉�ׂ��l�ɂ͕K������̂��Ƃ������̊m�M�́A������������܂����B
���u�F�m�ǂɂȂ��Ă��������傤�ԁI�v�i���c�a�q�@���ԏ��X�@1600�~�j
�Q�N�قǑO�ɏo�ł��ꂽ�{�Ȃ̂ł����A��͂葽���̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���A���߂ďЉ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�����Ɂu�F�m�ǁv�Ƃ���܂����A����ɂ�����炸�ɁA���܂��܂Ȑl�ɓǂ�łق����B
�ǂނƂ����Ɛ��E���L����A�����₷���Ȃ�A�����v��������ł��B
�������F�m�ǂɊւ���Ă���l�ɂ́A��������̊w�т����邱�Ƃ͌����܂ł�����܂��B
�{���́A�Ō�t�ł���A�F�m�ǂ̋`�����삵�Ŏ�����o�������铡�c�a�q���A45�ŃA���c�n�C�}�[�a�Ɛf�f����Ă����10�N�Ԃ̎���̌o�����x�[�X�ɁA�u�F�m�ǂɂȂ��Ă��������傤�ԂȎЉ�v�������Ă������ƌĂт������{�ł��B
�ŏ��ǂƂ��́A�u�F�m�ǁv�Ƃ��������Ɏ�������Ă��܂��C�Â��Ȃ������̂ł����A������߂ēǂ܂��Ă��������A�{���͎Љ�̂�����⎄�����̐������ւ̃��b�Z�[�W�̏����ƋC�Â��܂����B
���c����͖{���̒��ŁA�u�l�����Ƃ��Ắw�F�m�ǖ��x�v�Ə����Ă��܂��B
�����Ō���Ă���̂́A�F�m�ǂɂȂ��Ă����v�Ȑ����������ł͂Ȃ��A���Ƃ��F�m�ǂɂȂ��Ă����K�ɕ�点��悤�ȎЉ���������邽�߂̎�������l�ЂƂ�̐������ł��B
�F�m�ǂƂ͖������Ǝv���Ă���l���ӂ��߂āA�����̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
����20�N�قǑO����A�u�N�����C�����悭��点��Љ�v��ڎw���u�R���P�A�����v�ɁA�l�Ƃ��Ă����₩�Ɏ��g��ł��܂��B
�����ň�ԑ厖�ɂ��Ă���̂́A�u�l�̑����̑��d�v�Ƃ������Ƃł��B
�u�P�A�v���A�u����I�ȍs�ׁv�ł͂Ȃ��u�o�����ɓ��������W�v�Ƒ����Ă��܂����B
�ŋ߂ł́A�}�j���A���I�ȉ����t���P�A�ł͂Ȃ��A�����Ҍl�̎v�����N�_�ɂ��������S�̂Ɏ�����L�����n��i�����j��P�A�Ƃ������z���L���肾���Ă��܂����A����͂܂��Ɂu�N�����C�����悭��点��Љ�v�ɂȂ����Ă����Ǝv���Ă��܂��B
�N�����C�����悭�A�Ƃ����Ӗ��́A��Q���ӎ����Ȃ��ł��ނ悤�ȂƂ����Ӗ��ł��B
�������u�F�m�ǁv��u����v���A��Q�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Љ�ł��B
�e���r�ȂǂŁA2025�N�ɂ́u����҂̂T�l�ɂP�l���F�m�ǁv�ȂǂƂ����ڋq�n�������ɗ���Ă��܂����A�����������Ƃɂ͎��͑S���S������܂���B
�������A�R���P�A�����̗���̒��ŁA�u�݂�Ȃ̔F�m�Ǘ\�h�Q�[���v��ʂ��āA�Љ�ɏΊ���L���Ă������Ƃ����v���W�F�N�g�ɂ͎Q�������Ă�����Ă��܂��B
���̏W�܂�ŁA���͂����A�����g�͔F�m�Ǘ\�h�����F�m�ǂɂȂ��Ă��C�����悭��点�Ă�����Љ�̂ق���ڎw�������A�����Ď����ł������Ȃ�悤�ɐ����Ă���Ɣ������Ă��܂��B
���c����̂����u�F�m�ǂɂȂ��Ă��������傤�ԂȎЉ�v������̂́A���Ԃ�����l�ЂƂ�ł��B
�����v���āA�����łł��邱�ƂɎ��g��ł��܂����A�{����ǂ�ŁA�ƂĂ����C�Â����܂����B
���c����́A����ɏ����Ă��܂��B
�u��l�̐l�Ƃ��Ċւ�葱���Ă����l����������A�Ǘ����邱�Ƃ͂���܂���v
�u���ɂ́A�A���c�n�C�}�[�a�ɂȂ��Ă�����܂łǂ���ւ���Ă����F�l�����l�����܂��B���肪�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B���̂��Ƃ���l�̐l�Ƃ��Č��Ă���Ă���Ǝ������Ă��܂��v
�u��葽���̐l�Əo��A�����̗����l�ƂȂ����Ă���ƁA�l����L���ɂ���\�����L�����Ă����Ǝv���̂ł��v
��Ȃ̂́A�����Ȑl�Ƃ̎x�������Ȃ������ĂĂ����Ƃ������Ƃł��B
���c����́A���������l�������u�p�[�g�i�[�v�ƌĂ�ł���悤�ł��B
���c���Ăт����Ă��邱�Ƃ͂��������܂��B
�����炵�������邱�ƁA���̂��߂ɂ͂�������ƎЉ�Ɋւ���Ă������ƁB
�p�^�[�������ꂽ�u�F�m�ǂɂȂ��Ă���̐l�����[�g�v�Ȃǂɏ]���Ă͂����Ȃ��B
�����A�u�F�m�ǂ̐l�ւ̕Ό��������炵�������邱�Ƃ�W���Ă���v�̂ł���A���l�C���ɂ���̂ł͂Ȃ��A���������Ό��̂���܂���g�������Ď����Ă����B
���̂��߂ɂ��A�����炵����������厖�ɂ��邱�Ƃ�����Ɠ��c����͌����܂��B
�����āA�u�����������Ɏ������̂��Ƃ����߂Ȃ��Łv�Ǝ咣���Ȃ�������Ȃ��B
�S���狤�����܂��B
�u�����������Ɏ������̂��Ƃ����߂Ȃ��Łv�Ƃ݂�Ȃ������o���A�Љ�͂����ƖL���ɂȂ��Ă����܂��B
�{���Ō���Ă��铡�c����̃��b�Z�[�W�ɂ́A�n�b�Ƃ������邱�Ƃ����������̂ł����A�Ƃ�킯���̌��t�̓n�b�Ƃ������܂����B
�u�����g�A�A���c�n�C�}�[�a�������`���9�N�ԉ�삵�Ă��āA���̑�ς��͐g�ɐ��݂đ̌����Ă��܂��B����ǂ����̓A���c�n�C�}�[�a�̊��Җ{�l�Ƃ��Ă̗���ŁA���҂������Ƃ��ɂ͂킩��Ȃ������w�{�l�̐��E�x���킩���Ă��炢�����Ǝv���܂��v
����́A�P�A�����ŁA�����ׂ�₷�����Ƃ����ł��B
�����҂łȂ���킩��Ȃ����Ƃ�����B
����̂��߂Ǝv���Ă��邱�Ƃ��A��������������邱�ƂɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ�������܂���B
�{���́A���c����̑f���Ȑ������o������Ă���̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���B
�l�̐������Ƃ��ċ����ł��邱�Ƃ������ł��B
���c���u�K���v�Ȃ̂́A�������𐽎��ɐ����Ă��邩��ł��傤�B
���c����́A�F�m�ǂɊւ��鐢�Ԃ̕Ό����Ȃ����Ă��������Ƃ������Ă��܂��B
������ƒ����ł����A���p�����Ă��炢�܂��B
�u�F�m�ǂւ̕Ό����������܂܂ł͖{�l�����͂̐l���A�����āA�Љ�S�̂��s�K���ɂȂ�̂��Ǝv���܂��B�������������L�߂邱�Ƃ��ł���̂́A�F�m�ǂ̐l�A��l��l�Ȃ̂ł͂Ǝv���܂��B�ł�����A�����̑̌��𐢊Ԃɓ`���邱�ƂŁA�u���ꂩ��F�m�ǂɂȂ�l�X�������i�K�Ŏ������g�𗝉����A�����̎���ɂ���l�X�ƂƂ��ɂ��ǂ������ł���H�v�̕K�v�����l���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�Ǝv���܂��v
�u�������������L�߂邱�Ƃ��ł���̂́A�F�m�ǂ̐l�A��l��l�v�A�S�ɋ����܂��B
���c����́A�u�{�����A�A���c�n�C�}�[�a�ƂƂ��ɐ����Ă��鎄����A���ꂩ��F�m�ǂɂȂ邩������Ȃ��F����Ƃ��̃p�[�g�i�[�ɂȂ���X�ւ̃q���g�ɂȂ�Ƃ��ꂵ���v�Ə����Ă��܂����A�{���ɂ͂�������̃q���g������܂��B
���Б����̐l�����ɖ{����ǂ�ł������������ł��B
��������̂��ƂɋC�Â����Ă����{�ł��B
���̖{���Љ�Ă��ꂽ��������Ɋ��ӂ��܂��B
���w�������u�����l�v�u�x���l�v�x�i����N�Y�@���{�o�ϐV���o�Ŏ�
1500�~�j
��N���A���N�̗F�l�̌o�c�R���T���^���g����N�Y�������ɗ����̂ł����A���̎��ɁA��N�o�ł��ꂽ�V���w�������u�����l�v�u�x���l�v�x�������Ă��Ă���܂����B
���コ��́A�v���Z�X�E�R���T���e�B���O�̎��_�ŁA���N�A�g�D�J���Ɏ��g��ł���A�_���I�ȔM�����̃v���t�F�b�V���i���ł��B
����܂ł��������̌o�c�W�̏��Ђ��o�ł��Ă��܂����A���̎咣�́A�����g�̎��̌��Ɋ�Â��Ă��܂��̂ŁA���������̓I�����H�I�ł��B
���̉��コ�A�u�l�v�̓������x���ɏd�_��u���Ă܂Ƃ߂��̂��A�{���ł��B
�g�D�J���̏o���_�ł���l�̐������x�����悤�Ƃ����̂�����̃e�[�}�ł��B
��������́A�u�l�Ԃ̐����v�Ƃ́u�V���ȓ�������������l�֎������g���ς�邱�Ɓv���Ƒ����Ă��܂��B
���ɂ͂ƂĂ������ł��鑨�����ł��B
���̑������ɁA���₳��̌o�c�v�z��R���T���e�B���O���O���Ïk����Ă��܂��B
�V���ȓ�������������l�����̏W�܂����g�D�́A�����Ă����Ă����������Ɠ����o���B
���ꂱ�����A��������̍l����A�l���N�_�Ƃ����g�D�J���̃|�C���g�ł��B
�������A���ۂɂ́A�V�����u���������v�����邱�Ƃ͂����ȒP�Ȃ��Ƃł͂���܂���B
�g�D�̒��ɂ���ƁA���܂��܂Ȏ������u����������v���Ƃ̑������ɂȂ��Ă��܂�����ł��B
��������₳��́u7�̔Y�݁v�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B
���̔Y�݂������Ă��ɂ͂ǂ�����������B
���ꂪ�{���Œ���Ă���u���̂V�́i�ȂȂ肫�j�v���f���Ƃ����l�Ԑ����@�ł��B
���܂��܂Ȍ���ŁA���܂��܂Ȑl�����ƒ��N�ڂ��Ă�����������̑̌��m��̌n�����A�N���������ɍ������u�C�Â���́v�����߂���g�݂��ł���悤�ɂ����̂��A���̃��f���ł��B
�u���̂V�́v�Ƃ́A�M�]�́A�����́A�C�Ɨ́A���ʗ́A�̌��́A���F�́A�D�]�͂ł��B
���V�������t������܂����A��Ȃ��Ƃ́A�����̂V�̗͂��A���݂Ɋ����������W�łȂ���A�S�̂Ƃ��ďz���Ă���d�g�݂ɋC�Â����Ƃł��B
���̎d�g�݂܂��āA�����̓��ӂȁu�́v��������Ă����A���R�Ɩ����Ȃ��A�u���̂V�́v������A�l�ԗ͂����܂��Ă����B
�{���ł́A���̂V�̗͂����߂Ă������@�����H�I�ɐ�������Ă��܂��B
�ڂ������e�͖{�������ǂ݂��������B
�u���̂V�́v���f���̏o���_�́u�M�]�́v�ɂȂ��Ă��܂��B
�u�M�]�́v�Ƃ́A�u�䂭�́v������������͂����܂��B
�d����ʂ��āA�����]��ł���u�z���v��u����v�A���ꂪ���܂��܂Ȃ��̂��䂫�t���A������܂��䂫�t�����Ă����A���ꂱ�����������邽�߂̏o���_���ƁB
������u�u�v�Ƃ����Ă�������������܂���B
�������A�u�z���v�͎���̒��ɂ��邾���ł͑傫���͖c���ł����܂���B
�u���̂V�́v���f���̂V�Ԗڂ́u�D�]�́v�B
�u�D�]�́v�́A����̖ڂ̑O�ɂ��錻�����悭����͂�����������͌����܂��B
�l�͎��炪�u���ꂽ���̒��ŁA���҂Ɗւ��Ȃ���A�������Ă���B
�����ɁA����̑��݂�������A�������肾���Ă����B
�����Ɗ��i���ҁj�́A��̂ł���A���i���W�ɂ���B
�܂�A����̑z�����������悭���Ă������ƂŎ��炪�������A���i��Ёj�͐������Ă����B
���ꂱ�����A�l���N�_�ɂ����g�D�J���ł���A�p�����Ă����������g�D�Â��肾�Ƃ����킯�ł��B
�u�M�]�́v����u�D�]�́v�Ɍ����Ắu���̂V�́v���ǂ��Ȃ���A�ǂ��z���Ă������́A�{����ǂ�ł�������Ƃ��l�����������B
�{���̓r�W�l�X�}���Ɍ����ď����ꂽ�{�ł����A��Ђ̒��ł̐������ɂƂǂ܂���̂ł͂���܂���B
���́u���̂V�́v���f���́A�������ł��傫�Ȏ�����^���Ă���܂��B
�l���N�_�Ƃ���Љ��g�D�ɂ��Ă������Ƃ��ۑ�ɂ��Ă��鎄�ɂ́A�ƂĂ������ɕx�ޖ{�ł��B
��Ɛl�ɂ͂������A�Љ��L���ɂ��Ă��������Ǝv���Ă���l�ɂ��A�����߂��܂��B
�����{����ǂ�ł��������c�_��[�߂����Ƃ�������������������������A������������Ăт��āA�Ǐ���I�T��������悵�܂��B
�{��ǂ܂�āA�S�������ꂽ���͎��ɂ��A�����������B
���u�^�l�Ɠ����v�i�g�c���Y�@�z�n���ف@1600�~�j
�����̃T�����ŁA��q�@���`�q�g�݊����̃T�������J�����Ǝv���A�����_��̋��q�F�q����ɘb��҂̑��k�����܂����B
�F�q����͂����ɋg�c���Y�������Ƒ�������A�g�c����̐V�����Љ��܂����B
�ǂ�ł݂āA���E�ł͊e�n�ł��܁A�H�̎��_����_�Ƃ��ς�肾�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ�m��܂����B
�����v���Ă����̂Ƃ͋t�̕����ł��B
���߂Ă������Ƃ����E�ł͎n�܂��Ă���B
�q�ǂ������͋~���邩������Ȃ��B
������ƌ��C���o�Ă��܂����B
�����ɋg�c����ɃT���������肢���܂����i2��10���ɊJ�×\��j�B
���킹�Ă��̖{���A�����̐l�ɓǂ�łق����Ȃ�܂����B
�{�̓��e�́A�����̗��\���ɏ�����Ă��镶�͂��Ȍ��ŕ�����₷���ł��̂ŁA������ƒ����ł������p�����Ă��炢�܂��B
��`�q�g�݊����卑�A�����J�͂������A���[���b�p�A���e���A�����J�A���V�A�A�����A�؍��܂ŁA���E���̕�e��Ƒ����A�_��Ђ��̔_�Ƃ��������Ď�q�����A�_�Y������H�H�i�̎���₢�����_����]�����n�܂��Ă���B
�Ȃ��A���{������v�_�Y����q�@���p�~����A�������Ƃ��Đ��E����������_��̐H�i�ւ̎c������K���ɘa����Ă����̂��A�ɘa�̎������Ȃ����{�̑�胁�f�B�A�ł͕���Ȃ��̂��B
���E�̒����ɋt�s�����ȓ��{�̔_����H�i���S����ɑ��āA�^�l�Ɠ����̐[���Ȃ���ւ̋C�Â�����A�x�J��炷�B��l�ЂƂ肪���X���H�ł���������ւ̓��������{�B
���Ȃ݂ɖ{���̕���́A�u�L�@��ƒ����ۂ����{��ς���v�ł��B
����́A�g�c����̑̌��܂������b�Z�[�W�ł�����܂��B
�g�c����́A����̑�a��L�@��ō��������̂ł��B
���łɓ����̕\�\���̕��͂����p�����Ă��炢�܂��B
���E���Ō�������얞�A�A�g�s�[�A�ԕ��ǁA�w�K��Q�A���a�Ȃǂ��A�����ۂ̗���ɂ��邱�Ƃ��킩���Ă��Ă���B����ǂ��A���X�������Ǝq�ǂ����������ɂ���H�ׂ��̂��A�P�ʋۂ��E���u�����v�̍ő�̏�ǂɂȂ��Ă��邱�Ƃ͈ӊO�ƒm���Ă��Ȃ��B
�g�c���������̕a�C��ʂ��āA���̂��ƂɋC�Â��A�H������ς��邱�Ƃɂ���đ�a�����������̂ł��B
�_�ƐH�A�����Đ����͐[���Ȃ����Ă���B
���̂��Ƃ𑽂��̐l�ɒm���Ă��炢�����āA�g�c����͖{�����������̂ł��傤�B
�{���ɂ͂Q�̃��b�Z�[�W�����߂��Ă��܂��B
��́A���E�ł��ܔ_����]�����n�܂��Ă��邪�A���̎���͕�e�𒆐S�Ƃ������ʂ̐����҂������Ƃ������ƁB
�܂�A�_���̕ϊv�͐�������Ƃł͂Ȃ��A�����҂ł��鎄�����ɂ����N������̂��Ƃ������Ƃł��B
�c�O�Ȃ�����{�ł͂������������͂܂����݉����Ă��Ă��܂���B
��q�@���p�~����A��`�q����ɂ���Ĕ_�Ƃ��ς���ꂻ���Ȃ̂ɁA�}�X���f�B�A�������҂��܂��傫�Ȗ��Ƃ��ĂƂ炦�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�ł��t�Ɍ����A�����������҂������o���A�_���͕ς��Ƃ������Ƃł�����܂��B
������́A�_���ϊv��҂����Ƃ��A���ꂼ��̐����҂ł��ł��邱�Ƃ�����Ƃ������ƁB
�g�c����͍Ō�́u���Ƃ����v�ŁA���̋�̓I�ȕ��@���Ă��˂��ɐ������Ă��܂��B
�{���̍���ɂ͂�����̑傫�ȃ��b�Z�[�W������Ă��܂��B
���݂̍H�ƌ^�Љ�ւ̌��O�ł��B
����𒊏ۓI�ɂł͂Ȃ��A���Ƃ��u���Y���v��u�o�c�v�Ƃ����T�O�������ɕ�������������Ă��邩�A�Ƃ����悤�ɋ�̓I�Ɍ���Ă��܂��B
��ƌ^�_�ꂪ���Y���Ă���̂́u�_�Y���v�ł͂Ȃ��u���i�v���A�Ƌg�c����͏����Ă��܂����A�_�ƂƂ͉��Ȃ̂��A�������I�ɖ₤�Ă���̂ł��B
����͌����܂ł��Ȃ��A�������̐������ւ̖₢�����ł�����܂��B
�����Ă��ꂪ�A���Ԃ�O�ɏ������Q�̃��b�Z�[�W�ɂȂ����Ă���̂ł��B
�{���͂����ȒP�ɓǂ߂�{�ł͂���܂��A�����ɍ��߂�ꂽ�g�c����̃��b�Z�[�W�͐��X�����`����Ă��܂��B
�������������Ǝ~�߂āA�܂��͎����łł��邱�Ƃ���������Ǝ��H���Ă����B
����Ȍ��ӂ��N�������Ă����{�ł��B
�����̐l�ɓǂ�ł������������āA�Љ���Ă��炢�܂����B
2��10���ɂ͓����ŋg�c����̃T�������J���܂��B
�{����ǂ�ŁA���Ђ��Q�����������B
���u���A���Y���̘V��v�i�������܂��悱
��������o�� 1800�~�j
���A���Y���̘V��A�h�L�b�Ƃ��鏑���ł��B
�����̘V������A���Y���ōl���������ɂ́A���X�ɂ��āA�x�����邱�Ƃ������̂ł����A���҂́A�V��������炵�����������Ɗ肢�A�V��Ɖ����V���~���[�V�������Ȃ���A�S���̐�i�I�ȉ��{�݂�L�[�p�[�\���ɉ�ɍs���A������܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�����������Ҏ��g�̖��ӎ������ƂȂ��������āA�P�Ȃ������Ƃ͈Ⴄ���X�������`����Ă���̂��A�{���̓�����������܂���B
���͂͂�����Ƃ��Ȃ�Ă��Ȃ��Ƃ�����Ȃ��킯�ł͂���܂��A���ꂪ�܂����C�u����ł��܂��B
�ŏ��ɓ��{�̉��ی����x�̊T�v�Ƃ��̎��ۂ��Ȍ��ɏЉ��Ă��܂��B
�����ǂނ����ł��A������Ƒ��̘V��̔����ɂȂ�ł��傤�B
�����ŁA���ی��̃P�A�v�����͎����ō쐬�ł��邱�Ƃ��w�E����Ă��܂��B
�Â��āA���҂́A���ۂ̉��ی��̃P�A�v�����������i�Ƒ��j�ō쐬�����l�����ɒ��ڃC���^�r���[���A���̑̌��k�X�����Č����Ă��܂��B
�����āA���T�[�r�X�Ɏ��g��ł���l�����ɂ��C���^�r���[���A�u���̗ǂ����v�Ƃ͉������A�����Җڐ��ōl���Ă����܂��B
�����܂œǂނƁA������Ƒ��̘V��̉��ɂ��ẴC���[�W�������ł���悤�ɂȂ�A���l���Ƃł͂Ȃ��A�������ƂƂ��čl������悤�ɂȂ�͂��ł��B
���҂̘V��ւ̎���́A���ɂƂǂ܂�܂���B
�^�[�~�i���P�A�Ɋւ��Ă����҂͂ӂ���̕��i�f�B�O�j�e�B�Z���s�[�Ɏ��g�ޏ��X�N�i����ƃ`���v�����̓��䗝�b����j�ɃC���^�r���[���A�V��̐������Ɏ�����^���Ă���܂��B
�����Ŏ�������Ă���̂́A�����邱�Ƃ̉��l�ƐM�̈Ӗ��ł��B
���̂��ӂ���̃C���^�r���[�����邱�ƂŁA�V��̃��A���Y���͂܂��܂����������Ƃ��Ă��܂��B
�������A���ꂾ���ł͏I���܂���B
�Ō�Ɂu���̎����䂽���ɂ��Ă����10���̖{�v���Љ��܂��B
�����őI��Ă���{���A���ɂ͂ƂĂ������[�������̂ł����A�^�C�g���́u���̎��v�ł͂Ȃ��u�V��v�ł��u�l���v�ł������悤�ȏЉ�Ԃ�ł��B
���҂́u��l�̎������v�̐[���v���������܂����B
���͎��͒��҂̖k������Ƃ͂����炭�O�ɂ����������ł��B
���������W�܂�ŁA�킸������̌��t������肵�������ł��B
�����Ă��̎��ɖ{���������������̂ł����A���������ƂȂ��Â��������Ƃ�����A���炭���̏�ɒu�����ςȂ��ł����B
���C�Ȃ��J�����̂��Ō�̏͂ŁA�����ǂ�ŁA����I���Ǝv���āA�ǂ݂������̂ł��B
�ʔ����Ĉ�C�ɓǂ�ł��܂��܂����B
�������Șb�ł����A�Ō�̏͂��珇���O�Ɍ������ēǂ̂ł����A����Ȗ{�̓ǂݕ��������̂͏��߂Ăł��B
���҂͖{�����u�V�����K�C�h�v�ɂȂ�Ǝv���ď������Ə����ɏ����Ă��܂��B
�������Ɂu�V�����K�C�h�v�ł͂���܂����A����ȏ�ɒ��҂̎v�����`����Ă��܂��B
������������A�Y�݂Ȃ��琶���Ă���k������̎�������������Ȃ��ƁA�ǂݏI����ĂӂƎv���܂����B
�����ɐ����Ă���l����͊w�Ԃ��Ƃ͂�������܂��B
�{���̒ꗬ�ɂ́A��������������Ɛ����邱�Ƃ̊��߂��������܂��B
�����̕���́Amemento mori�A�u����Y���ȁv�ł��B
�ǂ݂�����A�u�����ӎ����ĖL���ɐ����悤�v�ł��B
���W�҂����ł͂Ȃ��A���܂��܂Ȑl�����ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�����ė~�������A��������̃C���^�r���[��̌��������҂̎咣�����������m�肽���C�����܂��B
�k������̑�2��ڂ����҂������ł��B
���̎��ɂ́A���Б����������Ɩ��邭���Ăق����Ƃ����̂�����Ȏ��̊�]�ł��B
�����x�݂ɓǂނɂ͂�����Ƃӂ��킵���Ȃ���������܂��A�C����������ǂ�ł��������B
�l���������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��{�ł��B
���u���݂͂��̂܂܂ł�����Ȃ����v�i����a�s�@�d�g�Ё@1200�~�j
��N�o�ł��ꂽ�{�ł����A�������čŋߓǂ܂��Ă��炢�܂����B
�M�҂͓����̃T�����ɂ����X�Q�����鐼��a�s����ł��B
���̖{�̂��Ƃ͈ȑO�����������Ă��܂����B
���₳��́A���邱�Ƃ����������ŁA�����ɂ���f���Ɍf�����Ă���u���t�v�ɊS�������o���������ł��B
�ӎ����Ă����̌f����ǂނƁA�����ɂ͎��ɂ��܂��܂ȃ��b�Z�[�W��������Ă��邱�Ƃɉ��߂ċC�����������ł��B
�����������t�́A�K���������̂����̏Z�E�̃I���W�i���ł͂Ȃ��̂ł����A���̌��t��I���_�ɂ͂��̂����̏Z�E�̎v�������߂��Ă��܂��B
�����Ő��₳��́A�����������b�Z�[�W�Ɂu�V���v�Ɩ������܂����B
���V����Љ�Ɍ����Ă̂��������b�Z�[�W�ł��B
�Ȃ��ɂ́A�Ӗ����悭�킩��Ȃ����̂��������悤�ŁA�����������ɂ͐��₳��͂����ɔ�э���ŁA���Z�E�ɘb���悤�ɂȂ����悤�ł��B
���������u�V���v����������W�܂�܂����B
����ŁA��ۓI�Ȃ��̂�I��ŁA�����ɐ��₳��̊��z����������ł܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�^�C�g���́u���݂͂��̂܂܂ł�����Ȃ����v�B
����́A���₳��������́u�V���v���瓾���u���̌��t�v��������܂���B
����A�u���Ȃ��������v�̌��t�Ƃ����ׂ���������܂��A�܂�����͂���Ƃ��āA�{���ɏЉ��Ă���P�O�O�́u�V���v�́A���ꂼ��Ɏ��Ɏ����ɕx�ނ��̂ł��B
�����āA���₳��̉�����A�ƂĂ��ʔ����ł��B
���Ȃ݂ɁA�����ɂȂ������t�́A�H�c�s�ɂ��鐼�P���Ɍf������Ă����V���������ł��B
�{���̑тɁu�Y�݂̂X���͂���ʼn����I�v�Ƃ���܂����A����͂�����ƕۏ����˂܂����A�{����ǂނƁA�u�Y�݂��܂��l����L���ɂ��Ă���邩������Ȃ��v�Ƃ������ƂɋC�Â��邩������܂���B
��������A�Y�݂Ȃlj�������K�v�͂Ȃ��ƊJ������邩������܂���B
�Ȃɂ���u���݂͂��̂܂܂ł�����Ȃ����v�Ȃ̂ł�����B
����ȏЉ�Ɩ{���̖ʔ������`���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ŁA���ۂ̖V�����������Љ�܂��傤�B
�u�~���S�T�x�{�ɂȂ�v
�u�n�[�h���͍���������قǁA������₷���Ȃ�v
�u�ł��Ȃ��̂ł����A���Ȃ��̂ł����v
�u�e�̂������Ƃ��ʎq���A�e�̂܂˂͕K������B
�u�l�����s���l�܂�̂ł͂Ȃ��A�����̎v�����s���l�܂�̂��v
�u�u�����Ƃ������A�����������A�]�_�Ƃ������v�Ɖ]���Ȃ���A����Ƀe���r���C�h�V���[�����ŊςĂ��邨�O�͂����ƈ����I�I�v
�u�n�R�Ƃ͏������������Ă��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��A�����ɗ~�����肢���炠���Ă��������Ȃ����Ƃł��v
�u�ɂ��茝�ł͈���͏o���Ȃ��v
�ǂ��ł��傤���B
������Ƌ����������Ă����������ł��傤���B
�������{���̖ʔ����́A���������V���𐼍₳�ǂ��~�߂����ł��B
�ǂ��ʔ����̂��A����͖{����ǂ�ł��炤��������܂���B
�l���ɔY��ł�������A�Y�݂ɋC�Â��Ă��Ȃ��K���ȕ����A�C���������琥�ǂ݂��������B
����Q�t�̂���������Q����ގ��ԂŁA���Ԃ�ǂ߂�ł��傤�B
�ƂĂ��ǂ݂₷���A�l�ɂ���Ă͐l���ɂƂ��Ă̂��������̂Ȃ����������炦�邩������܂���B�����Ƃ��A�l�ɂ���Ă͒P�Ȃ�ɂԂ��ŏI��邩������܂��A����͕ۏ̌���ł͂���܂���B
���̖{���ޗ��ɁA�߂������ɓ����ŁA�u�V���T�����v���J�����Ǝv���܂��B
�Q���҂ɁA�߂��̂����ŁA�C�ɂȂ�u�V���v�������Ă��Ă��炢�A�݂�ȂŁu�V���v�i�]�������Ǝv���Ă��܂��B
�N���N�n�Ɏ��Ђ����ꂽ��A����f�������Ă��������B
���u�l�Ԑ����d�^��Ƒ���`�o�c�v�i�V�O�f�Y�E���G�@���O�o�ŎЁ@1500�~�j
�F�l�̏�{�m�q����i���݊�����Ёj���ҏW���͂����A�����H������Ђ̌o�c���Љ���{�ł��B
�ŋ߁A�b��ɂȂ��Ă���u�e�B�[���g�D�v���A���H�I�ɗ������邱�Ƃ̂ł��镛�ǖ{�̂悤�ȓ��e�ł��̂ŁA�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
���҂́A�����H�В��̐��G����ƐV�����o�c�_����Ă���V�O�f�Y����ł��B
�V�O���A���ꂩ��̊�ƌo�c���f���Ƃ��Ắu�l�Ԑ����d�^��Ƒ���`�o�c�v�i�����̂���ł����j���T�����A���̎���Ƃ��Ă̐����H�̌o�c�ɂ��Đ������X�����Љ������Ƃ����\���ł��B
�V�O����̊T���̂Ƃ���ŁA�t���f���b�N�E�����[�́u�e�B�[���g�D�v�ł͂��܂�ڂ������y����Ă��Ȃ��u�e�B�[���g�D�v�̎���ɂȂ�Ј��̈ӎ��̐������f�����A�P���E�E�B���o�[�̃g�����X�p�[�\�i���S���w�ɂ܂ők���ĉ������Ă��܂��B
�����ǂނƁA�e�B�[���g�D�̃C���[�W���������炩�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B
�����H�͓����ɂ���i�b�g�E�t�@�C���p�[�c������Ђł����A�u���{�ł������ɂ�������Б�܁v���͂��߁A��������̌o�c�܂���܂��Ă��܂��B
����ŗ]���鍐���ꂽ�Ј����A����ڑO�ɂ��āA������x�A��Ђɍs�������ƌ������Ƃ����G�s�\�[�h���Љ��Ă��܂����A�Ј��̂X�����u���j���ɉ�Ђɍs�������v�Ǝv���Ă��邻���ł��B
��������{�^�̉Ƒ��o�c�ł����A���Ă̂悤�ȉƕ����^�ł͂Ȃ��A��l�ЂƂ�̎Ј����l�ԂƂ��đ�Ɉ�����Ƃ����Ӗ��ŁA�u�V�����Ƒ���`�v�Ƒ�������ƓV�O����͒��ڂ��Ă���킯�ł��B
�����ł́A�Ƒ���l�ЂƂ肪��ɂ���A�o�c�҂Ə]�ƈ��͐l�ԓI�ȏ㉺�W�͂Ȃ��A�������ԂƂ��đ��d�������W���ڎw����Ă��܂��B
�C�o���E�C���C�`�������g�R�����B���B�A���e�B�h�i���������j�Ɋ�Â��g�D�Ƃ����Ă������ł��傤�B
�{����ǂ�ł݂�ƁA�����H�͂܂��u�ƕ����I�v�Ȃ��̂��犮�S�ɂ͔����o�Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂����A�����炱���A�u�l�Ԑ����d�v�Ƃ͉������l����ޗ����ӂ�Ɋ܂܂�Ă��܂��B
�V�O����́A�u�ƕ����^�Ɛl�Ԑ����d�^�̈Ⴂ�𖾂炩�ɂ���A���{�̊�ƌo�c�̗��j���킩��A����ǂ����������ɔ��W������ׂ��������炩�ɂȂ�܂��v�Ə����Ă��܂����A�����������Ƃ�O���ɁA�{�����������S���邾���łȂ��A�ᔻ�I�ɓǂނƁA�u�e�B�[���g�D�v���l���镛�ǖ{�ɂȂ�Ǝv���܂��B
�ᔻ�I�Ƃ����Ӗ��́A�ے�I�Ƃ����_����Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B
�l���Ȃ���ǂނƂ������Ƃł��̂ŁA���������܂���悤�ɁB
�����܂ł�����܂��A�g�D�͌l�ł͂ł��Ȃ����Ƃ��������邽�߂̎d�g�݂ł����A�ŋ߂͂��̎d�g�݂ł���͂��̑g�D�ɁA�l���g���Ă��܂��悤�ȁA�{���]�|���N�����Ă��܂��B
����̕ω��̒��ŁA�g�D�̍\�����O�͕ω����Ă����˂����܂���B
�����������Ƃ��l���邽�߂ɂ��A��ƊW�҂ɂ͂��Ђ����߂���1���ł��B
�ł���A���̖{���ޗ��ɂ����T�������ł��J�Â��悤�Ǝv���Ă��܂��B
�{����ǂ�ł������������z�Ȃǂ����Ă��炦����ꂵ���ł��B
���u���{�u�@�v�����_�v�i�����ח��@���@�K�@3000�~�j
�{���́A�u�t�]�̔��z�ɂ��@���v�v�ɂ���ē��{��ς��邽�߂̏���Ⳃł��B
�Ƃ����Ɖ���������ł����A���ʂɐ������Ă���l�ł���A�N�ł��u�ӂ�ӂ�v�Ƃ��Ȃ����Ȃ���y�����ǂ߂鏈��Ⳃ����ڂ��ꂽ�{�ł��B
�u���k�v�I�ȗv�f�����߂��Ă��āA�ǎ҂͂����邱�Ƃ�����܂���B
���҂̈�������́A���̑�w����̗F�l�ł����A�Ő�E�����ł��L���ȁA�����ċ�̓I�Ȓ�Ċ�������������Ƃ��Ă���A�Ȃ��������Ƃ̌����ȁA���m�I�Ȋw�҂ł��B
���ɁA��������́u�ϐl�v�Ƃ��]����܂����A�������́u�ϐl�v���u�ϊv�̐l�v�Ɠǂݑւ��āA�ϐl�ł��邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�u�����@�w�v�Ƃ����V��������̑n�n�҂ŁA���̕���ł���������̐�发�������Ă��܂��B
�u�����@�w�v�Ƃ����̂́A���ݖ��ƂȂ��Ă���@���x����̓I�Ɏ��グ�A���̗��@�����I�ȉ��P������w�₾�����ł��B
��������ɂ��Ȃ����̓I�Ȓ����N�ɂȂ�����H�@�w�ƌ����Ă������ł��傤�B
�@�w�Ƃ����ƁA���ɂ͕~���������ł����A����ł���Ύ��ɂ��S������܂��B
�Ƃ������A���̎p���́A�u�@�Ƃ͉����v�Ƃ����A���̊�{�I�ȊS�ۑ�ɂȂ����Ă��܂��̂ŁA�܂��Ɏ��̊S���ł�����܂��B
���Ȃ݂ɁA�����g�́A�ŋ߁u�@�v�Ƃ������̂ɁA�قƂ�NJS�������Ă��Ă��܂��B
�����@�w���Ŋw�̂́u���[�K���}�C���h�i�@�̐��_�j�v�ł����A���̎��_�ōl����ƁA�ŋ߂̖@�ɂ́u�S�v������̂��ƁA���v���Ă��܂��̂ł��B
���{�͂ق�Ƃ��ɖ@�����ƂȂ̂��낤���Ƃ����^�₳���A���Ɋ����܂��B
����Ȏ��̂悤�Ȑ��̂Đl�I�ȂЂ˂��ꂽ�p���ł͂Ȃ��A�����ɉʊ��Ɏ��g��ł���̂��A��������ł��B
��发�������������A���������܂��܂ȂƂ���Ŕ��\���Ă����A���{�Љ�������Ă���a���̖@�I����Ⳃ̏W�听���{���ł��B
�{���̑тɁu�a���ɉՂ܂�Ă���@�Ɛ����h��������@Dr.�����̎����J�n�I�v�Ə�����Ă��܂����A���̉��������Ԃ�́A���ɂ͂�����Ƌ����ł��Ȃ����̂�����܂����A�����ɂ����A�{���̐^��������܂��B
�N������a���Ȃ��ǂ߂�悤�Ȃ��̂́A�ǂމ��l���������l������܂���B
��������́A���{�̖@���w�Ɋւ��āA����Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B
�@���w�ł́A���������A�u�^���v�Ƃ����������j��w�����j���Ȃ��Ɗ�����B
����ʐ�������A�O���@������A�����Ă܂Ƃ߂�Ƃ������̂������B
��������V�w���͏o�Ă��邪�A����ł��A�V�K�̍l�����͏��Ȃ��B
�܂����������ē����ł��B
�����Ĉ�������͌����܂��B
�M�҂́A�@���ƂƂ��āA���{�̖@���x�����܂������Ă���̂��A�s�����ǂ�����Ή��P�ł���̂���O���ɁA�����ɂ��^��o�H�p�������āA�����I�ȏ㌤�����Ă����B
�����������_�ŁA�܂Ƃ߂�ꂽ�̂��{���ł��B
����������������̌��t�����p�����Ă��炢�܂��B
�����āA����������A������Ƃ��ẮA�ʂ��Ղł͂Ȃ��A�t�]�̔��z�ŁA���邢�́A��肵���ǂ܂Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���߂ē��ǂނƂ��A��ґ���ł͂Ȃ��A�����I�Ȓ��ԈĂ�����Ƃ��A���邢�͋��s�����ł͂Ȃ��\�t�g�����f�B���O�����݂�Ƃ������̂ł���B
���̂悤�Ȍ����́A�@�w�E�ł͑O�Ⴊ�Ȃ��V���������J�Ă������̂ŁA���܂��\���ȕ]���͂���Ă��Ȃ��i����ǂ��납�A�l�ʑ^�̂�������Ȃ��j���A���ꂱ�������{�̖@�w�҂̎g���ł���ƐM���Ă���B
�ǂ��ł����B�@�������̐l���A������Ɠǂ݂����Ȃ�ł��傤�B
�ڎ������ł�15�ł�����قǁADr.�����̎�p�̃��X�́A�Љ�ׂĂɌ������Ă��܂��B
��P�͂́u����E���t�E�ٔ����̂��肩���v�B�Â��āu�Љ��襍��������v�u�Ő����v�v�u��Õ����v�u���ی�v�u��w�v�u���̑��g�ӎG�L�v�ƍL������ɂ킽���Ę_���W�J����Ă��܂��B
�������A�����ɂ́A�^�}�ƍّ̐��������Ȃ��@�V�X�e���A�u�������͍̂�蒼���v�Ƃ��u�I�����s�b�N�͖��ʁv�Ƃ��A�j�����x���ɂ���ȁi���N��10�A�x�͑唽�j�A�u�����ɂ����A��Ô�ʎg��������J�ȁv�A����ɂ́u�o�J�قǖׂ����t�E�ٌ�m�V�X�e���v�A���S�l�̍č����ז�����⑰�N���A���ȏȂ͔p�~����ȂǂƂ��������Ƃ�������Ă��܂��B
Dr.�����́A���������Ԃ肪�킩��ł��傤�B
�ł���A�܂��́u�͂��߂Ɂv��ǂ�ł��炢�A��͊S���ɍ��킹�ďE���ǂ݂��Ă��炤�̂������Ǝv���܂��B
�u�͂��߂Ɂv�ɁA��������̐��������킩�镶�͂�����̂ŁA���p�����Ă��炢�܂��B
�Љ�Ȋw�Ғ��Ԃł́A�����̌������̂ɂ�������炸���ς�炸�u���q�͑��v�ŁA�����͈��S�ł���Ƃ����g���̌�����������A��_�E�W�H��k�ЂⓌ���{��k�Ђ��g�߂ɋN���Ă���ւ����A�����́u�w��v�ɖv��������A�L�������̔�Вn�ɂ��Ȃ���A�픚�҂Ɋ��Y�����ƂȂ��A���a�Ȋw������Ĉ̂��Ȃ��Ă���l�����Ȃ��Ȃ��B
�M�҂ɂ́A�ނ�͖��̋ꂵ�݂Ȃǒm��]�n���Ȃ��悤�Ɍ�����B�i�����j
�M�҂̐�U�̍s���@�w�W�҂́A�������炨���~��������̂ŁA�ǂ����Ă��������̔��z�ɂȂ肪���ł���B
�������������I�Ɣ��肵�����ł��B
��������̐l�������Ȃ�`����Ă���ł��傤�B
�ގ��g�́A�u�Ƃ��̐̂Ɍ�p�w�҂P�ނ��A��w�ɂ������Ȃ��̂ŁA�u������݁v���Ȃ��A���ȏȔᔻ���܂߁A�M�O�ɏ]�������������Ă���v�ƌ����Ă��܂��B
�܂��A������݂������Ă��������Ă����Ǝv���܂����i���̂��߂ɎЉ�̎嗬�h����O���ꂽ�Ɩ{�l�͌����Ă��܂��j�B
������ƍ����Ȃ̂��C�ɂ���܂��A������{�́u�@�I�����T�v�ƍl����Ή䖝�ł������ł��B
�������A�X�̖��̏����������{���̃��b�Z�[�W�ł͂���܂���B
�u�t�]�̔��z�v�Ŋ�łȖ@���������A�����������ς���Ă��邱�ƁB�u�w��v�Ƃ͉����A�w�ԂƂ͉����A�Љ���悭���Ă������߂ɂł��邱�Ƃ͉����A�ȂǂƂ������Ƃւ̃q���g���A���̋C�ɂȂ�Γǂݎ��܂��B
�A�W�e�[�V�������܈ӂ���Ă��邩������܂���B
�����ǂǎ҂��A�g�߂ȕa����Dr.�������̎�����Ƃ��n�߂�ƁA���{�������ƏZ�݂₷���Ȃ邩������܂���B
�@�̐��_���h���Ă��邩������܂���B
�ł�����{���́A����Ӗ��ŁADr.�����̎����p�w�K�u���ł�����̂ł��B
�����̐l�ɓǂ�ł��炢�A�����̐l�Ɏ������͂��߂Ăق����B
����ȈӖ��ŁA�{���𐄑E���܂��B
���Ȃ݂ɁADr.�����̓����T������10��12���̖�J�Â��܂��B
�܂������]�Ȃ�����܂��B
�Q������]�̕��͎����āA���A�����������B
���u���w�C�g�E���V���R��`�̔�]���_�v�i���a�c�W�@���Y�Ё@2000�~�j
�u��]�̖��͂�����ċv�����B�����A�{���ɂ����ł��낤���H�@�ہA�Ƒ吺�Ō��������v�Ƃ����A���a�c����̔M�����b�Z�[�W����{���͎n�܂�܂��B
�o�ŎЂ���́A�u���w�E�E�v�z�E����̔����E�������K���́q�֒f�r�̕��|�]�_�W�v�ƏЉ��Ă��܂����A���҂̉��a�c�W���u2008�N����2018�N�܂ŏ����Ă����u�����w�v�ƃ|�X�g�R���j�A���Ȗ��������]�_���A������{�̕Ǐ������ł��Ŕj����Ƃ��鎋�����琸�I�v�����]�_�W�ł��B
����́u���ܓǂ܂��ׂ��q���w�r�Ƃ͉����v�B
�قƂ�ǂ̍�i��ǂ�ł��Ȃ����Ƃ��ẮA�����߂̈ӎ��������Ȃ���{����ǂ݂܂����B
���a�c����́A��i���Ă�ł��Ȃ��l�ւ̐S�z������Ă���̂ł����A����ł����Ɏ��グ��ꂽ��i��ǂ݂����Ȃ�܂��B
�܂��A���ꂪ�]�_�̈�̎g���ƌ��p�Ȃ̂ł��傤���B
����́A�A�C�k�����E����E�����ȂǁA����u������{�̕Ӌ��v����́u�Ӑg�́q���r�v�ł����A�������Ă�����́A�����E�G�Ŗ��@�I�ɐ�������Ă��鎄�����ł��B
���̉s�����́A���ɂ����Ȃ�s���h�����Ă��܂����B
���a�c����̐[���m�Ƌ����v���A�����āu�₦���{��v����������u�M���{�v�ł��B
���a�c����̔�]���_�ւ̎����́A�Ȃ��Ȃ��������ł��B
�u�����̌��Ђɂ����˂炸�A�P�Ǝ҂̊ϓ_���畗����������s�ׂ���]�v���ƌ����A�u��]�Ƃ������E��̓I�Ȓm�̃X�^�C���v���c���ɋ�g���āA�u�����ƃV�j�V�Y�����ςݏd�Ȃ�A�ǂɖ����Ă���v����Љ�̎��Ԃ������������Ă����˂Ȃ�Ȃ��A�ƌ����܂��B
�������A���݂̔�]�͉��a�c����̊��҂ɉ����Ă��Ȃ��B
�u���Ĕ�]�Ƃ́A�A�J�f�~�Y���ƃW���[�i���Y���̒J�ԂɈʒu���A���҂��ˋ����錾���v�Ƃ��āA�V��������̑n���������Ă������A�����̔�]�́A�A�J�f�~�Y���ƃW���[�i���Y���ƈꏏ�ɂȂ��āA�u�������͂����߂�ނ̊�]�[���I�ȕ���v�̒����������ƁA�������w�E���܂��B
�������A��]�́u���́v�ǂ��납�A�ϋɓI�ȁu���B����v��S���Ă���B
�������������I�ƁA�N�b����Ȃ��A�v�킸�����o�������Ȃ��Ă��܂��܂��B
���w��v�z�̍��{�ɍ������u�ǂ����炩�s�ӂɂ���Ă��Đl�Ԃ�h���Ԃ�悤�Ȕ��z�v���琶�܂�錾�t���A�^��ɑ~��������O�ɔc�����A������J�e�S���C�Y�̖\�͂����ރ_�C�i�~�Y�����N�����Ă������Ƃ��A���|��]���ƁA���a�c����͌����܂��B
���t�̗͂��A�u�����瑤�v�ŁA��̂Ƃ��Ċm�M���Ă���B
�u��]�Ƃ́A��Ɏ��Ƃ̑Θb�ł���A�I���̂Ȃ��i���ł�����v�Ƃ������Ă��܂��B
������܂��S�ɋ����܂��B
�������ŋ߂̎��́A���w��]�_���牓�̂��Ă��Ă��܂��B
20�N�قǑO����A�����������̂����܂��~�߂��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ł��B
�u���㕶�w�͐�������Љ����ڂ�����A���҂��ӎ����邱�ƂȂ����ނ̓���H���Ă��܂����v�Ƃ������a�c����̎w�E�ɁA����̑ӑĂ����~����悤�ȋC�����܂������A���̏ɂ����Ă��Ȃ��A���a�c����͕��w���]�̈Ӌ`���m�M���Ă���B
�����āA�u���̂悤�Ȓm�I���y�ɑ��ꂵ���������A���������t�A���Ȃ킿�q���w�r�Ƃ͉�����͍��v���A�����錻��������߂ɁA�{���Ɏ��g��ł���B
�䂪�g���Ȃ݂āA�傢�ɔ��Ȃ������܂����B
�{���̗��_�I�ȉ��䍜�́u�|�X�g�R���j�A���Y���v�A������u�|�X�g���I������v�A���n��`�ł͂Ȃ��A�܂��Ɂu���܁A�����v�ɂ���A���n��`�ł��B
�����ł͂����v�������Ȃ��̂ł����A�����������玄�����łɂ��̏\���ȏZ�l�Ȃ̂�������Ȃ��B
���ꂪ�ŋ߂́A���̉}���ς�s���̍�����������܂���B
��������₢�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�{���Ŏ��グ���Ă����i�̂��Ȃ�̕������A�u�k�C�����w�v�ł��B
�Ȃ����a�c����͖k�C���ɂ������̂��B
����́A���������{�́u�Ӌ��v������ł��B
�u�Ӌ��Ƃ́A�ߑ㍑�Ƃ����W�𐋂���ۂɁA�������ʂ�u�����v�̔����ȂǁA��̂Ă�ꂽ�������I�悷��ꏊ�B�w�k�̑z���́x���ڎw���̂́A���̖�������ڂ����炳���A�ł��邾�����k�Ɏv�l���߂��点�Ă������Ƃ��v�Ɖ��a�c����͌����܂��B
�Ӌ��ł́A���߂�ꂽ�ߋ��Ɍ㉟������Č��݂̖{�����I�悵�Ă���B
�����āA�������疢���̓������ɕ�����Č����Ă���B
�����ɉ��a�c����͐V�����n����������̂ł��傤�B
���Ȃ݂ɁA�����A����Ӗ��ł́u�Ӌ��̏Z�l�v���ӎ����Ă��܂��̂ŁA�����͂���Ȃ�Ɍ����Ă���Ǝv���Ă��܂��B
�������A�Ӌ��͂܂��A�ƑP�ɂ��ׂ�₷���B
�{���ł́A�Ō�Ɂu����v���킸���Ɏ��グ���Ă��܂��B
�����Ɏ��͑傫�ȈӖ��������܂����B
�ŏ��ɉ�������A���a�c����́u�r�e�]�_�v�Ɏ��g��ł���ƌ������悤�ȋC�����܂��B
���̂r�e�́A�u�g�v�ف����@�h�i�X�y�L�����[�V�����j�������Ɍ����Ƃ͈قȂ鐢�E������r�e�i���X�y�L�����C�e�B���E�t�B�N�V�����j�v���A���Ԃ�Ӗ����Ă��܂��B
�����ɖ��v�����Z����̂ł͂Ȃ��A�v�ق̐��E�ɂ��V�Ȃ�������Ȃ��B
�����ɉ��a�c����̃��b�Z�[�W���������̂ł��傤���A���̎��ɂ͋C�Â��܂���ł����B
�����V���Ă��܂������̂ł��B
�Ⴂ����A�����r�e�̐��E���y����ł��܂������A�ǂ������̍��̗]�T�������Ă��Ă��܂��B
����́A�����ȈӖ��ł́u�V���v�ɂ��A�{���͋C�Â����Ă���܂����B
�����o���ɂ��ꂽ�Ƃ��Ă̐l�Ԃ𐧓x�I�ɗ��ߎ���Ă������ƂɁA�ǂ��Λ����ׂ����B
�����Ƌ��K�ƃV�X�e���ō\�����ꂽ�Ǘ��Љ���ǂ������Ă������B
���a�c����́A���Ƃ������₢�����Ă��܂��B
�����āA�����ƔY�߂ƒǂ�����ł���B
���ꂪ�l�ԂƂ������̂��낤�ƁA�����̂ł��B
���_�̂��悤������܂���B
�V�l�ɂ́A���Șb�Ȃ̂ł����A�����Ă͂����Ȃ��B
���������Ӗ��ł́A�����錳�C��^���Ă����{�ł�����܂��B
���Ȃ�n�[�h�Ȗ{���Ǝv���܂����A�Љ���悭�������Ǝv���Ă�����ɂ͓ǂ�łق����{�ł��B
�������̏Љ�Ő\����Ȃ��̂ł����A���̂��Ɗ�]�̂��������]�_�W�ł��B
���u�A�C�k�����ے�_�ɍR����v�i���a�c�W
�}�[�N�E�E�B���`�F�X�^�[�ҁ@�͏o���[�V�Ёj
�{����2015�N�A�܂�R�N�O�ɏo�ł���܂����B
���܂���Љ��̂͂ǂ����Ƃ��v���܂������A�����̎Љ���炵�āA���̓��e�͂܂��܂����l�������Ă��Ă���Ǝv���A�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
���҂͕��|�]�_�Ƃ̉��a�c�W����B
���͈�x��������Ă��܂��A�Ȃ������a�c�����̌�A�����Ă��Ă��ꂽ�̂��{���ł��B
���炭�u���Ă����̂ł����A�ǂ݂�������A���r���[�Ȏp���ł͓ǂ߂Ȃ��{���Ƃ킩��܂����B
�Ғ��҂̉��a�c����̎v�����A�����`����Ă��܂����B
�ǂݏI�����̂͂��Ȃ�O�ł����A����܂��v���v����ǂݒ����܂����B
���߂āA�u�ǂ܂��ׂ��{�v���Ǝv���܂����B
�����ʂ�A�u�A�C�k�����ے�_�ɍR����v�Ƃ����̂��A�{���̓��e�ł����A�ҏW�̃R���Z�v�g�́A�u�A�C�k�����ے�_�ւ̃J�E���^�[�����̒��x�[�X�ɂ��A���݁A�����Ŋ��Ă����Ƃƌ����҂������A���������̐�啪��^�S�̈�Ɉ�������`�ŃA�C�k�ɂ��Č�邱�ƂŁA�����ǂ݉����Ă������v�Ƃ������̂ł��B
�Ă��˂��ɏ�����Ă���̂ŁA�A�C�k�ɂ��Ă��܂�m���̂Ȃ��l�ɂ��ǂ݂₷�����e�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ɁA�A�C�k�ɂ܂��w�C�g�X�s�[�`�̌����A�C�k�̒u����Ă�����A�L���W�]�̂Ȃ��ŁA�T�ςł���悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
�ŏ��ɁA�Ҏҁi���a�c�W vs�}�[�N�E�E�B���`�F�X�^�[�j�̑Βk���u����Ă��܂����A�����Ŗ{���̑S�̑��ƕ������Ƃ��Ă̎���������Ă��܂��B
�Â���23�l�̐l���A���ꂼ��̊S�̈悩��A���R�ȋc�_��W�J���Ă��܂��B
���̂������ŁA�u�A�C�k���v���A���ɗ��̓I�ɁA���邢�͎��i�ǎҁj�̐����Ƃ̂Ȃ������������قNj�̓I�Ɍ����Ă���Ɠ����ɁA�������̎Љ�����Ă�������s���̌��ĉۑ肪��������Ă��܂��B
�܂�A�A�C�k�����Ȃ���A�������̐�����������Ă�����e�ɂȂ��Ă��܂��B
����͂ƂĂ��L�����Ă��܂��B
���Ƃ��A���R���J����́A�i�`�X����̃h�C�c�̐��_��w����D���w�▯���q���w�̊댯�������Ȃ���A����ɂȂ���悤�Ȍ`�ŁA�u���Ɓv�Ƃ͉������������Ă���Ă��܂��B
�e�b�T�E���[���X���X�Y�L����́A����𐢊E�ɍL���A�o�ς̃O���[�o�����̐i�ޒ��ŁA���E�e�n�ł��r�O��`�Ɛl�퍷�ʂɊ�Â���U�����������قǑ��債�Ă��Ă��邪�A���{�̃C���^�[�l�b�g��ɂ����āA�l�퍷�ʂɂ���U�����A�Њd�⋺���̌��t������}�Ɋg�債�Ă��邱�Ƃ́A���E�e�n�̌X���ɋt�s���Ă���Ǝw�E���܂��B
����ɁA���{�̃w�C�g�X�s�[�`�̓����́A���ʓI�ȃ��g���b�N���^�[�Q�b�g�Ƃ���͈͂��L���葱���Ă��邱�Ƃ��w�E���A�u�ŏ��͖k���N�Ɗ؍��A�����A���x�̓A�C�k�c�B���ɗ���̂͂��������N�ł��傤�H�v�Ɩ₢�����Ă��܂��B
������q����́A�����Ȃ�ƂȂ������Ă������Ƃ����t�ɂ��Ă���܂����B�u�����͂��߂āu��Z�������v���ӎ������̂́A�A�����J��Z���������B��Ŏc�E�Ȃ̂́A�ނ��됪���ґ��̔��l�̂ق��������Ƃ����F�������܂ꂽ�v�B�A�����J�Ő������ē������o�������ł��B
����ɁA������͂���Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B�u��r�I�D��I�ȃi���@�z���́A�킢���D�܂Ȃ��z�r��������Ɋ������y�n�ւƒǂ�����Ă����v�B�e�b�T�E���[���X���X�Y�L����̖₢�����ɏd�˂čl����ƕs�C���ł��B
���Ȃ݂ɁA������́uChief Seattle's speach�v��|��ҏW���āA�G�{�i�w���͋��͑�n�x�j�ɂ����l�ł����A���̊G��`�����̂��F�l�̎萳�삳��ł��B�f���炵���G�ł��B
����K�i����́A�w�C�g�X�s�[�`�ɂ��āA�u���t�͐l���E�����A�l�����v�Ə����Ă��܂����A�u�������A�C�k�͌��t�̖��ł��邩�炱���A���t�̗͂�m���Ă���v�Ƃ������Ă��܂��B
���邳��̕��͂�ǂ�ŁA���̓w�C�g�X�s�[�`�����ł͂Ȃ��A���w�C�g�X�s�[�`�ɂ����錾�t�̗�����v���o���܂��B
�ǂ����ŊԈ���Ă���C�����܂����A�{���̏�����݂͂�Ȍ��t��厖�ɂ��ď����Ă��܂��̂ŁA���S���ēǂ�ł����܂��B
����Ȋ����œ��e�ɂ��ď����Ă�������肪����܂���B
�Ƃ�����23�l����̃��b�Z�[�W�́A��������v�����������Ă��܂��B
�����Ă���炪���U���Ȃ���A�ǎ҂ɖ₢�����Ă���̂́A����ȎЉ�ɐ����Ă��Ă����̂ł����A�Ƃ������Ƃł��B
���̓A�C�k�ɂ���̂ł͂���܂���B
�A�C�k�̖�肪�A�������̐�������Љ�̂�����̂���������₢�����Ă���Ă���B
������C�Â����Ă����̂ł��B
���Б����̐l�ɓǂ�ł��炢�����āA�R�N�O�̖{�ł����A�Љ���Ă��炢�܂����B
�Ȃ��A�Ȃ��{�����Љ�����Ȃ������̗��R�́A�ŋߏo�ł��ꂽ���a�c�W����́u���w�C�g�E���V���R��`�̔�]���_�v�i���Y�Ёj��ǂ���ł��B
���a�c����̎Ⴂ��M�Ɉ��|���ꂽ�̂ƁA���|�]�_�Ƃ����d���̈Ӗ��ɋC�Â����Ă��炢�܂����B
���́u���w�C�g�E���V���R��`�̔�]���_�v�́A�ǂݏI���̂�1�T�Ԉȏォ�����Ă��܂��������ɁA�\�������ł����Ƃ͌����܂��A�����ƂĂ���Ȃ��Ƃ��v���o�����Ă���܂����B
���a�c�W����̐��E�ɂ��Ă����͂͂���܂��A����������҂�����̂��Ɗ������܂����B
���̖{���A�܂��Љ���Ă��炨���Ǝv���܂��B
�\���əł��Ă��Ȃ��̂ŁA�Љ��\�͂͂Ȃ��̂ł����B
���u�q�ǂ��m�o�n�����Q�O�P�W�v�i���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�ҁ@�G�C�f��������
2500�~�j
���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[���A�Q���ڂɂȂ�u�q�ǂ��m�o�n�����Q�O�P�W�v���o�ł��܂����B
�n�����ɗ�炸���e���[�����Ă���̂ŁA���̊������O���ɏ���Ă������Ƃ��킩��܂��B
�q�ǂ��W�̂m�o�n�͂ƂĂ������A���̑S�̑��͂Ȃ��Ȃ������Ă��܂��A�������������̌p���I�Ȕ�����ʂ��āA���܂��܂ȕ���̊��������₩�ɂȂ����Ă������Ƃ����҂���܂��B
��P���Ɠ������A�����͑傫���u���_�҂Ɓu���H�ҁv�ɕʂ�Ă��܂��B
���_�҂ł́A�n����������R�N�Ԃ̊ԂɋN�������A�傫�ȕω��ɂ��ĉ������Ă��܂��B
�܂��͖@�I���̕ω��ɂ��āA�m�o�n�@�A���������@�A�����{�@�̉����Ƃ��̖��_���������Ă��܂��B
�s�������̎��_����A�����̕������Ɋւ���ᔻ�I�Ȏw�E����������ƍs���Ă��܂��B
�s���A��������H�Ғ��S�̎�ɂ�锒���ł��邱�Ƃ̋��݂ƌ����Ă����ł��傤�B
�m�o�n�����́A�@�I���ɑ傫���e������܂����A�����̓��������^�̂��̂Ƃ��ĎI�ɑ�����̂ł͂Ȃ��A�ނ���@�I����\���I�ɕς��Ă������Ƃ��m�o�n�̑傫�Ȏg���ł��B
�X�̂m�o�n�Ƃ��ẮA�Ȃ��Ȃ����������g���͉ʂ����܂��A���������Ӗ��ł��A�������������Â���̈Ӗ��͑傫���ł��傤�B
�q�ǂ��W�̂m�o�n���Ȃ��ł����q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�̍ő�̖����͂����ɂ���悤�Ɏv���܂��B
�X�̂m�o�n�͂ǂ����Ă��ڐ�̖��̑Ή��ɒǂ�ꂪ���ł����A���₩�ɂȂ����Ă������ƂŁA�q�ǂ��̎��_����̖@�I���̐����ɂ��ւ���Ă������Ƃ��ł���͂��ł��B
���_�҂ł́A�@�I���ƕ���ŎЉ���̕ω������グ���Ă��܂��B
���R���A���a�����A�r�m�r�ɑ�\���������A����ɂ͎q�ǂ��̕n���ւ̋�̓I�Ȏ��H�Ƃ��čL���肾���Ă���q�ǂ��H���Ȃǂ̓����Ȃǂ��A���p�I�Ɍ���Ă��܂��B
���H�҂́A��P���Ɠ������A�̈�ʂɋ�̓I�Ȋ����������H�҂̘_�l���W�J����Ă��܂��B
����������H�܂������̂Ȃ̂ŁA�����͂������܂��B
����́A�k�C�������B�܂őS���ɂ킽���Ă��܂��B
��P�������A���M�҂̊�Ԃꂪ�L�����Ă���̂��A���ꂵ���O�i�ł��B
�Ȃ��A�����҂Ƃ��āA�W�@��Ȃǂ��f�ڂ���Ă��܂��B
���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[��\�̏�����́A�u���s�ɂ悹�āv�ŁA�������P���Ōf�����ҏW���j��厖�ɂ����Ə����Ă��܂��B
����́A�u�S���̎q�ǂ��m�o�n�����̑S�̑������P�ł��邱�Ɓv�Ɓu�S���ɓ_�݂���q�ǂ��m�o�n�Ƀq���g�𓊂������闝�_�Ǝ��H���Љ�邱�Ɓv�̂Q�ł��B
���́u�����v�������p�����Ă������Ƃ����A���ܕK�v�Ȃ��ƂƊm�M���Ă��鏬����̎v���́A�����ɐ[�܂�L�����Ă���悤�ł��B
�ǂݕ��Ƃ��Ă��A�����Ƃ��Ă��A���x�̍����A�������ƂĂ��ǂ݂₷�������ł��̂ŁA�q�ǂ��W�̂m�o�n�Ɋւ��l�͂������ł����A�����̐l�ɓǂ�łق��������ł��B
�m�o�n�̃l�b�g���[�N�����锒���̌p�����s�́A�߂��炵�������ł����A�X�̖��Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA�����������������ɂȂ����āA�Љ�ւ̏�M�����Ă��������������A�s���Љ����ĂĂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��鎄�Ƃ��ẮA�������Ă������������ł��B
���ЂƂ������̐l�ɒm���Ă��炢�A���̔�������������ɍL���Ă�����Ǝv���܂��B
�����A���̂��߂ɂ��������̉ۑ�͂���悤�Ɏv���܂��B
���͑�P���̏Љ�ɍۂ��āA�����̓��e�Ƃ��āA�Q�̗v�]���������Ă��炢�܂����B
�ЂƂ́A�u�̈�������H�҂������A���̎q�ǂ�������Љ���ǂ��l���Ă��邩��b�������悤�ȍ��k��v�B
�����ЂƂ́A�u�q�ǂ��ɂƂ��Ă̊����̏�ł���Љ���A�q�ǂ������͂ǂ����Ă���̂��Ƃ����q�ǂ������̐��v�B
������c�O�Ȃ��炻���������̂͂��Ȃ����܂���ł������A��Q����ǂ�ł�������������Ƃ�����܂��B
����́A�����Ӑ}����Ă���悤�ɁA�q�ǂ������̐��E��q�ǂ��m�o�n�����̐��E�����Ղł���悤�ɁA���̔�����}�����ł��Ȃ����낤���Ƃ������Ƃł��B
�}�������邱�ƂŁA�����Ă��邱�Ƃ������ł����A����ȏ�ɐ}�������邱�ƂŁA�q�ǂ��m�o�n�����ɍ~�苂��ł��Ȃ��l�����̗����͐i�ނł��傤�B
�n�������܂߂��Q���̔������ޗ��ɂ��āA�q�ǂ����E�̓������Ր}�I�ɐ}�������郏�[�N�V���b�v�⌤����Ȃǂ��ł���A�����Ǝq�����E�������ƌ����Ă���悤�ȋC�����܂��B
���ꂾ���̔��������邱�ƂɁA�W�҂݂̂Ȃ��ǂ�قǂ̋�J�����ꂽ���������͂킩��҂Ƃ��āA���������v�]��\������̂́A�����������S�O�͂���܂����A�t�ɂ��ꂾ���̋�J������Ɍ��ʓI�ȃ��b�Z�[�W�ɂ��Ă������߂ɂ��A��R���ɂ͂��������������Г���Ă������������Ǝv���܂��B
���������ł��������ł��̂ŁA���Ђ�������p�����t�H�[������W�܂���A�̈���ēW�J���Ă����Ă������������Ƃ��v���܂��B
���Б����̐l�ɓǂ�ł����������������ł��B
�ł���Έ�x�A�����ł����̔������ޗ��ɃT��������悵�����Ǝv���܂��B
�q�ǂ����E������A���ꂩ��̓��{�������Ă��܂��̂ŁB
���u���B��Q�ɐ��܂�ā@���ǎ��ƕ��17�N�v�i���i���P�@�������_�V�Ё@1600�~�j
�L���ɐ��������Ǝv���Ă���A���ׂĂ̐l�ɓǂ�łق����{�̂��Љ�ł��B
�u�g���\�~�[�̎q�v�u�ċz��̎q�v�ƁA����܂œ�a�̎q�ǂ��ƕ�e�Ƃ̊W�����ɁA�l�Ԃ̑f���炵���Ɗ낤�����A�[���D�����₢�����Ă������i���P����i�����O�Ȉ�j���A����͒m�I��Q���Ƃ��̕�e�����グ�܂����B
�{���̑тɂ́A�u�c������̃v���Ƃ��Ċ���ꂪ�A���ǎ���������A���Ԉ�ʂ́u���z�̎q��āv���玩�R�ɂȂ��čs����Ղ�`�����Ӑg�̃��|���^�[�W���v�Ƃ���܂����A�m�I�x��̂��鎩�ǂ̒j�̎q�i�E���N�j��17�N�Ԃ��e����̕����������ƂɁA���i���܂Ƃ߂����̂ł��B
���i����́u���Ƃ����v�ŁA�u�m���t�B�N�V������������ŏd�v�Ȃ̂́A�M�҂̎�ޗ͂ƕ\������͂ł��邪�A����ȏ�ɑ厖�Ȃ̂́A��ނ���l�Ԃ̌��͂�������Ȃ��v�Ə����Ă��܂��B
���́A����ȏ�ɑ�Ȃ̂́A�u�M�҂ƌ��l�̐M���W�v�ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�{���ł́A����ł���u��v�̎v���⌾�t���A���ɑf���ɁA�����o���̂܂�����Ă��āA�����قǂł��B
�����ɂ͎��U�����u���t�v�͂���܂��A�ւ�ɉ��������M�҂̎v�����݂ŕ�܂ꂽ�u���t�v���Ȃ��B
�����Ă��錾�t���A���ɐ��X�����A�Ƃ��Ă��錾�t�Ȃ̂ɒ�R�Ȃ��S�ɓ����Ă���B
���̈���Łu��v�Ɍ�����ꂽ���͂̐����A�܂�Ŏ����Ɍ�����ꂽ�悤�ɁA�S�ɓ˂��h����A���ꂵ���Ȃ�����߂����Ȃ����肷��̂ł��B
�{���̂�����Ƃ���ŁA�u��v�ƕM�҂̐M���W�������܂��B
���Ɉ��S���ēǂ߂邾���ł͂Ȃ��A�ǂ�ł��鎩�����A��a���Ȃ����̐��E�ňꏏ�ɐ����Ă���悤�ȋC�ɂȂ�̂́A�M�҂̗����ʒu���P�Ȃ�ώ@�҂ł͂Ȃ�����ł��傤�B
������A�ǂ�ł���ق��܂ł��A�u��v�Ɓu�����v���Ă��܂��ė܂��o�Ă��܂��B
���͖{����d�Ԃ̒��œǂ�ł����̂ł����A�R��قǁA�܂����炦���܂���ł����B
�{�ɏo�Ă����i���A���܂萶�X�����A�܂�Ŏ����̂��Ƃ̂悤�Ɋ���������ł��B
�u��v�̎v���ɕM�҂��������A����ɓǎ҂܂œ������Ă��܂��B
��������i����̑傫�ȊS�́A�u��e�v�ł��B
�l����e����Ƃ͂ǂ��������Ƃ��B
�������]�_�I�ɂł͂Ȃ��A����܂ł̍�i�Ɠ����悤�ɁA���i����͂��������Ɂu�����v��u���čl���Ă��܂��B
��������ꂪ�悭�킩��܂��B
����ɍ���́A�����ɂ�����̎��_�������܂����B
�u���ʁv�Ƃ��������ł��B
���i����́A�{����ʂ��āA���ǂ̐��E�̈�[�𖾂炩�ɂ��A�������̓����u���ʁv�Ƃ������l��̈Ӗ���₢���������Ə����Ă��܂��B
�u���ʁv�Ƃ������������������ƁA���E�͖L���ɋP���Ă��܂��B
�u��e�v�́u���ʁv����̉���ɐ[���Ȃ����Ă��܂��B
���̂��Ƃ��{���ɂ́A��̓I�Ɍ���Ă��܂��B
���Ƃ��A������ƒ����ł������p�����Ă��炢�܂��i���͂������ς��Ă��܂��j�B
�m�荇���̕�e�ɁA�E�����̕ۈ牀�ł̎ʐ^���������B���펙�������ɂ��ꂢ�ɐ��ĉ̂��̂��Ă���B�E�����͌��̕��̏��ŊG�{���L���ł���B�u����Ȃӂ��ɁA�����̎q�݂͂�Ȃƈꏏ�ɉ̂�����A�W�c�s�������Ȃ��̂�v�B��͒Q���悤�ɑ��k�������������B���͂��̕�e�́A���g���A�X�y���K�[�nj�Q�i�m�\������Ȏ��ǁj�������B�]���ėE�����̋C������������B�������Ă�������t�œ`���Ă����B�u���̈��ɕ���ł���q�����A�{���ɕs�v�c�˂��B�ǂ����ē����i�D�����ĉ̂��Ă���̂�����H�@���Ŗ{��ǂ�ł����������ۂNJy�����̂Ɂv�B���̌��t����ɂ͏Ռ��������B�������A�����͌���҂̎��_�ł����A�䂪�q�̐��E�����Ă��Ȃ������̂��B
���B��Q�̓�Q�Ƃ����A�Ռ��I�Șb���o�Ă��܂��B
�����Ɂu���ʁv�ɍ��킹�悤�Ƃ��錋�ʁA���a�⎩���_�o�����ǂȂǂ̐��_��Q�ǂ��Ă��܂����Ƃ�����܂��B
����ł͒m���Ă��Ă��A�e�͂킪�q�����Ƃ����Ă�肽���āA�����������Ă��܂��B
�������A����͎q�ǂ����߂ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���ꂪ���ɂǂ��������ʂɂȂ邩�B
�ꂪ����ɐS��C�t�����̂́A���܂��ܓ��@�a���Ŋ_�Ԍ����a���̕��i�ł����B
���̏�ʂ́A�ǂ�ł��āA���̐S�͓�����܂����B
�nj�������ĖY����Ȃ��قǁA����ȃC���[�W���c��܂����B
��e�Ƃ͕��ʂ̎�������̎��R�ɂȂ��āA���݂���M�����������ƂȂ̂ł��B
����́A�u���B��Q�̐��E�v�Ɍ������b�ł͂Ȃ��B
����ɋC�Â��ƁA���E�͈���Č����Ă���B
�ǂ݂�������A�������܂�Ĉ�C�ɓǂ�ł��܂��{�ł��B
�E���N�ƕ�Ƃ�17�N�Ԃ́A��������̋C�Â��Ɛ�����͂��A�ǂސl�ɗ^���Ă����B
���̖{�͏����̒ʂ�A���B��Q���ƕ�Ƃ̕���ł��B
�������A�ǂ݂悤�ɂ���ẮA�N�ɂł����Ă͂܂鎦������������U��߂��Ă���B
�l�Ƃǂ��ւ�邩�A�M������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��A�K���Ƃ͉��Ȃ̂��A������Ƃ͂ǂ��������Ƃ��B
����̖��Ƃ��āA�������牽���w�Ԃ��Ƃ������_�œǂނƁA�R�̂悤�ȃq���g�����炦��͂��ł��B
�����́u���B��Q�v�Ƃ������t�ɂƂ��ꂸ�ɂ��ׂĂ̐l�ɁA�ǂ�łق����Ǝv���R���ł��B
���Ȃ݂ɁA10��6���ɁA�����ŏ��i����ɃT���������Ă��炢�܂��B
���i����̐l���ɐG���ƁA����ɖ{���̃��b�Z�[�W��[���~�߂���ł��傤�B
���S�̂���l�͎��ɘA�����Ă��������B
���u���o��i�ׂƌ����ق̎��R�v�i������q/�������F/���V�����Ғ�
�G�C�f���������j
���́A�����́u�Љ��v�̂�����ɑ傫�Ȉ�a��������܂��B
������ς�钆�ŁA�u�Љ��v�i�w�Z����������ł����j�̑�������ς��Ă������Ƃ��K�v���Ǝv���܂����A��x�ł����g�g�݂͂����ȒP�ɂ͕ς��܂���B
���܂��ɁA�������_����̍s���哱�́u�^����Љ��E�^������Љ��v�A�u�����̈ӎ������߂�i���������j���߂̋���^�̊����v�����S���A�������͎����̎���L����i�܂肠��Ӗ��ł̎Љ��}�����ށj�u���U�w�K�^�̎Љ��v�ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B
�������A�Љ�����܂Ő��n���A�l�X�̈ӎ���������ς���Ă��Ă��钆�ŁA���낻�낻��������������������A�ނ���������]�����āA�����������҈�l�ЂƂ肪����ɂȂ��āA�u���݂��Ɋw�э����Љ��v�u�܂���Љ�����������ň�ĂĂ����Љ�n���^�̊����v�ɂ��Ă����i�K�ɗ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����͓����ɁA��������l�ЂƂ�̎Љ��s���������߂Ă������Ƃł�����܂��B
�����ŁA3�N�قǑO�ɁA�u�݂�Ȃ̎Љ��l�b�g���[�N������v��F�l�����Ɨ����グ�܂����B
�������c�O�Ȃ���A���̎��݂͍��܂����܂܁A�������ē����o�����ɂ��܂��B
�Ƃ��낪�A�Љ��̒n�k�ϓ��́A����ł͍L���肾���Ă���悤�ł��B
���̖{��ǂ�ŁA�傫�Ȍ��C�����炢�܂����B
���̈���ŁA��͂���߂āu�Љ��v�̑�������ς��Ă������Ƃ̕K�v�����������܂����B
�����ň�l�ł������̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���A�{�����Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�������s�̂�������ق̔o��T�[�N���őI�ꂽ�G�傪�A�����Ȃ�f�ڂ����͂��́u�����ق����v�ւ̌f�ڂ����ۂ����Ƃ��������i2014�N6���j�́A�o���Ă�����������ł��傤�B
���̑ΏۂɂȂ����o��́A�u�~�J��Ɂw������x�̏����f���v�B
���̋傪�A�u�Љ��̐����I�������v�Ƃ������R�ŁA�s������f�ڋ��ۂ��ꂽ�̂ł��B
�o��̍�҂ƒ��Ԃ����͍s���Ɉًc�\�����Ă��A���̎x���҂��L���肾���܂����B
�������A�s���ƍs���Ƃ̘b�������́A���܂��������ɁA�i�ׂɂ܂Ŕ��W���A�u���o��s�f�ڎ����v�Ƃ��č��Ȃ������Ă���̂ł��B
��R�Ŕs�i�����s���͍T�i���A�����ٔ����ɂ��T�i�R�̔������A���̂U���P�W���ɏo����܂��B
�o��T�[�N���̐l�����₻�̉����c�̐l�����́A���̐��N�A�Љ��@���͂��߁A���܂��܂Ȃ��Ƃ��w�тȂ���A�u�������Ȃ��Ƃ����������v�Ǝ咣���Ă��܂����B
�����L���m���Ă��炤���߂̌��J�C�x���g�Ȃǂ��J�Â��Ă��܂����B
�V����e���r�ł����グ���܂����̂ŁA�����̃T�����ł��b��ɂȂ������Ƃ͂���܂����A���́A����ȓ������L�����Ă��邱�Ƃ����m�炸�ɁA�ŋ߂ł͖Y��Ă��܂��Ă������Ƃ�傢�ɔ��Ȃ��܂����B
�{���́A���������u���o��i�ׁv�����̃h�L�����^���[�ł��B
����18���̍��ٔ����ɍ��킹�ċً}�o�ł���܂����B
�����̂���ˑR�A���s�s�Ȉ��͂��������������A����ɗ}�����邱�ƂȂ��A���ʂ���Λ����A�����قŏZ�����w�ё�����Ӗ����Ċm�F����ƂƂ��ɁA�\���̎��R����銈���ւƍL�����Ă������o�܂��A�����Ɋւ�������܂��܂Ȑl�����́u�v���v���܂߂āA���̓I�ɏЉ��Ă��܂��B
�{������A���̎������猩���Ă���ŋ߂̓��{�̎Љ�́u���₤���v�ƁA���H������ʂ��Ẵ��b�Z�[�W���`����Ă��܂��B
������҂́u����70�N�O�̗l�Ȏ���ɋt�߂�͐���߂�ł��v�ƁA2015�N7���̒�i�ɂ������Ă̌Ăт������ɏ����Ă��܂��B
�܂��A���Č����ِE�������������A���鎖���Ɋ֘A���āA���ĎЉ��Ɛ����̊W�ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ������Ƃ��Љ��Ă��܂��B
�u�������̐����Ɋւ���b��́A���̂قƂ�ǂ������ɂ�����邱�Ƃ��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B�����ɂ�����鎖�����A�����I���Ƃ������R�Ō����ي����̂Ȃ��ŋ֎~�����Ƃ�����A�l�Ԃ̎��ȋ��犈���Ƃ��Ă̎Љ��͐������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�v
�܂����������ł��B
�o��̌f�ڋ��ۂ̗��R�͂����܂��Ȃ��w������x����莋���ꂽ�̂ł��B
�����������@�����炵�Ȃ�������Ȃ��s���E�����A���@�����Ƃ������Ƃɔے�I�Ƃ����A���ꂾ�����������̗ϗ��ӔC�ɔ�����悤�Ȃ��Ƃ����X�Ƃ܂���ʂ�悤�ɂȂ��Ă��錻���́A�ς��Ă����˂����܂���B
��l�ł������̐l�ɖ{����ǂ�ł������������Ǝv���܂��B
�U���ɂ́A�{�����e�[�}�ɂ����T�������ŊJ�Â���\��ł��B
�܂��A�Љ��̃x�N�g���]�������u�݂�Ȃ̎Љ��l�b�g���[�N�v���A�Ē��킵�悤�Ǝv���o���Ă��܂��B
�������ĉ�����l��������A���Ђ��A�����������B
�Ȃ��A�{���̖ڎ��͎��̒ʂ�ł��B
���̍��ԂɁA���̖�肩�猩���Ă���d�v�ȁu�L�[���[�h�v�̉��������܂��B
�y��T�́z���o��s�f�ڈꉽ����肩�H�|
�y��U�́z���o��s�f�ڑ��Q���������������̌����咣�ƒn�ٔ���
�y��V�́z���o��i�ׂ̑��_�Ɖۑ�
�y��W�́z�Љ��{�݂̊w�т̎��R����邽�߂�
�y�����z�������i�S���j�^�ٌ�c�����^���o��s�������c����
���u�b�N���b�g�u�����J���ANPO/NGO�̃`�������W�v�i���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�ҁ@400�~�j
�R�N�O�Ɂu�q�ǂ��m�o�n�����v���������{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[���A�u�b�N���b�g�̊��s�Ɏ��g�݂����A���̑�P�����o�ł���܂����B
���ꂪ�u�����J���ANPO/NGO�̃`�������W�v�ł��B
���Б����̐l�ɓǂ�ł������������āA���Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
���́A�u�����J���iChild Labor�j�v�Ɓu�q�ǂ��̎d���iChild Work�j�v���킯�čl�����Ă��邱�Ƃ�{���Œm��܂����B
�u�����J���v�͋`�������W����J���A�L�Q�E�댯�ȘJ���̂��ƂŁA�h�k�n���ɂ������ւ���������݂����A���{����y���Ă��邻���ł��B
����A�u�q�ǂ��̎d���v�́A������錠���⌒�N�I�Ȕ��B��W���邱�ƂȂ��A�w�Z�ɍs���Ȃ���Ƃ̎�`���╨����Ȃǂ̃A���o�C�g�����邱�ƁB
�O�҂͎q�ǂ��̈炿��W���A��҂͎q�ǂ��̈炿���x��������̂Ƃ����Ă������ł��傤�B
������čl���邱�Ƃ���A���Ԃ���̏��݂������Ă���Ǝv���܂����A���E�ɂ͂܂��܂��u�����J���v�������̂������ł��B
���̌�����ς��悤�Ɠ����o�����u�q�ǂ������v�ɂ���āA���܁A���E�͕ς�肾���Ă��܂��B
�������A�����o�����Ƃ͂����A�����ɂ͑����̖�肪�R�ςł��B
�{���͂������������Ɏ��g��ł���m�f�n�t���[�E�U�E�`���h�����E�W���p���E�W���p���iFTCJ�j�̃����o�[�𒆐S�ɂ����W�܂�̋L�^�����Ƃɍ\�������u�b�N���b�g�ł��B
http://www.ftcj.com/
�ƂĂ������[���̂́AFTCJ�̕����A�q�ǂ��W�̂m�o�n�Ŋ������Ă����҂������A����̊����ƌq���Ȃ���A�z��������Ă���Ƃ���ł��B
�ƂĂ����������������Ƃ肪�A��������`����Ă��܂��B
�{���̊��Ɋւ�������{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�̐X����́A�{���́u�͂��߂Ɂv�ŁA�u�n��Ŋ�������m�o�n�A�C�O�̌���ƍ������Ȃ����ۂm�f�n�A�ǂ��������œ����m���M���邱�Ƃ́A��Ȗ����̈�ł��v�Ə����Ă��܂����A�������ɂ͌����Ȃ��u����v�͂�������܂��B
���ɁA�q�ǂ������̐��E�́A��l�����ɂ͂Ȃ��Ȃ������܂���B
�q�ǂ������̖����A�q�ǂ�����������Ŋւ��Ȃ���A�ς��Ă����B
���̂��Ƃ������Ƒ����̐l�������m��A�q�ǂ������̎��g�݂͂����Ƒ傫�ȓ����ɂȂ��Ă������낤�B
�m�邱�Ƃ��牽�����͂��܂�B
�X����́A�����l���Ă���悤�ł��B
�Ƃ���ŁA�A�W�A�A�A�t���J�Ȃǂ̎����J���̖��́A���������{�l�ɂƂ��Ă͉����b���Ǝv���l��������������܂���B
�������A�����Ă����ł͂Ȃ��ƁA����Ɋւ���Ă���l�����͌����ł��傤�B
�A�W�A�A�A�t���J�A����ĂȂǂ̎����J���̔w�i�ɂ́A�o�ς̃O���o���[�[�[�[�V����������܂��B
����́A�ނ����i���̈���ł�������{�l���i�߂Ă��邱�Ƃł��B
�����āA���̓����́A�����ɂ����Ă��u�q�ǂ��̕n���v�Ɓu��l�̕n���v�ݏo���Ă��܂��B
�����������_����A�q�ǂ���������̃��b�Z�[�W���~�߂�ƁA�܂��ɂ��̖��͎������̐������ɂȂ����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂��B
�����ȃu�b�N���b�g�ŁA�R�[�q�[�P�t���ōw���ł��A�R�[�q�[�^�C���̎��ԂœǂݏI���邱�Ƃ��ł��܂��B
���Ђ��ǂ݂�����������ꂵ���ł��B
�{�����w���������l�́A���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�̐X����(QZP13433@nifty.com)�Ƀ��[���ł��A�����������B
���邢�́A�����̎��̃I�t�B�X�ɗ��Ă��炦��A���ځA�w�����Ă��炦�܂��B
�܂����̃u�b�N���b�g���e�[�}�ɂ��������ł̃T�������T���Q�O���ɗ\�肵�Ă��܂��B
�����Ԃ�����A���Ђ��Q�����������B
���u��w�����{�C�ōl����q�ǂ��̕��ی�v�i�[���Y�E�ݖ{���˕ҏW�@�w���Ё@2018�j
�ȑO�A�q�炿�l�b�g�ł��ꏏ�����[���Y���A�w�������Ȃǂƈꏏ�Ɏ��g��ł��銈����{�ɂ��܂����B
�[�삳��́A�u�q�ǂ�����������Ă�������L���ɂ��邱�Ɓv�����C�t���[�N�ɂ��Ă��܂��B
�����ƍ��킹�āA�q�ǂ����_�̎��H�������A�q�ǂ����҂����ƈꏏ�Ɏ��g��ł���p���ɁA�ƂĂ��������Ă��܂��B
���܂͐X���̍O�O��w���U�w�K���猤���Z���^�[�̐搶�Ȃ̂ŁA�Ȃ��Ȃ���@��͂���܂��A�[�삳��̍ŋ߂̊������ł�����{����ǂ�ŁA�ނ̎p�����܂������ς���Ă��Ȃ����Ƃ��ƂĂ����ꂵ�������܂����B
�����ȈӖ��ŁA�{���͎����ɕx��ł��܂��̂ŁA�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�{���̎���́A����������킩��悤�ɁA��w���ł��B
�{���̏Љ�ɂ��������Ă���܂����B
��w�����n��ɏo�čs���A�q�ǂ���̖̂L���ȕ��ی���l����B
�O�O��w�̊w���Ƌ����̌�����g��Ԃ���"�̖��͓I�Ȋ����̐��X���Љ�B
�n��̎q�ǂ��𖣗��������̊����ƁA�q�ǂ���̂̓��������̋�̂�T��B
��w�̒n��v�����l����ۂɂ��Q�l�ɂȂ����B
�܂��ɂ��������{�ł��B
�n��ŁA�q�ǂ������Ɋւ��l�ɂ́A���Гǂ�łق����ł��B
����A�܂��ւ���Ă��Ȃ���҂����ɂ��ǂ�łق����ł��B
���łɁA��l�����ɂ��B
�q�ǂ��ւ̌������ς�邩������܂���B
�[�삳��́A�ҏW��\�̂ЂƂ�Ƃ��āA��1�͂ŁA��w���w�����n��Љ�ƌ��������C���ꂩ��̒n��Љ�̒S����Ƃ��Ă�10�ォ��20��O���̐��N���ǂ̂悤�Ȉ炿�����Ă���̂��C�ɂ��āA�����Ǝ��،�������̍l�@�ƒ����݂Ă��܂��B
�w�Z�ł��Ȃ��ƒ�ł��Ȃ��A��R�̋�ԂƂ��Ă̒n��Љ��[�삳��́u�G�s�\�[�h�ƃt�@���^�W�[���A�����鐢�E�v�Ə����Ă��܂��B
�q�ǂ������́C�q�ǂ����m�Łu�V�ԁv���Ƃ�ʂ��āu���������E�킭�킭�E�h�L�h�L�v���Ȃ���u�炿�����v���u�q�炿�v���c��ł���ƁA�[�삳��͌����܂��B
�u�q��āv�Ƃ����\���ɏ�����a���������Ă��鎄�Ƃ��ẮA�u�炿�����v�u�q�炿�v�Ƃ������z�́A�ƂĂ������ł��鑨�����ł��B
�������A�Ɛ[�삳��́A���܂̏ւ̊뜜��\�����Ă��܂��B
���������q�ǂ����m�ŌJ��L������u����I�v�u�����v�̐��E�ł���͂��̕��ی�E�w�Z�O�A�����ĉƒ�O�̐��E���A��l�́u���l�ρv���N������Ă��Ă���Ƃ����̂ł��B
�V�т̒��Ɂu�w�K�v��u���ʁv���v�������悤�ɂ��Ȃ��Ă��Ă���B
������u���ی�̊w�Z���v�ł��B
�[�삳�������{���������ł��A�q�ǂ������ɂ́A�u��Ƃ�̂Ȃ��v�u�s���̓��������X���v�u�����Ɏ��M���Ȃ��v�Ƃ����X���������Ă��Ă���ƌ����܂��B
���̂܂܂ł́A�ƒ�̍����⋳�����ł̑��ꂵ���l�ԊW���瓦��C�f�ɂȂ��M�d�ȋ@��ł������R�̐��E���q�ǂ���������D����̂ł͂Ȃ����Ɛ[�삳��͐S�z���܂��B
�ł́A�ǂ������炢�����B
�v���C���[�N�ƃR�~���j�e�B���[�N�����p���āA����������ς��Ă�����̂ł͂Ȃ����B
�[�삳��́A���������v���ŁA�U�N�O�ɁA�w���E����������u��Ԃ���|Love for Children�v�𗧂��グ�܂��B
�g��Ԃ���h�ł́A�u���ی�͊w�Z�ł͂Ȃ����Ɓv�u�w�Z�̐搶�̂悤�Ȏw���͂��Ȃ����Ɓv�u�q�ǂ���M���Č���邱�Ɓv���ɁA���܂��܂Ȋ����Ɏ��g��ł��܂��B
�{���́A���́g��Ԃ���h�����o�[�����S�ɂȂ��Ă܂Ƃ߂��������ł�����܂��B
�g��Ԃ���h�����o�[�̑�w�������̎��H���A�ނ�{�l�ɂ���ă��A���ɕ���Ă��܂��B
�����āA��������������n��̐l�������ǂ������Ă��邩���A���܂��܂ȗ��ꂩ���e����Ă��܂��B
����ɂ́A�����������H����A��w���̎q�ǂ��̒n�抈���̉\��������Ă��āA
�n��Љ�ɂƂ��Ă̑�w�̖������l�����ł��A��������̎����������܂��B
����Ƃ͉����A�q�炿�x���Ƃ͉������l����q���g����������܂��B
���܂��܂Ȏ��_�ɂ���Č���Ă���{�ł��̂ŁA�����ȓǂݕ����ł��܂��B
���ꂩ��́g��Ԃ���h�̊����ɑ傫�ȊS�������Ă��܂��B
�������������̂ŁA�Q���ł��Ȃ��̂��c�O�ł����B
�q�ǂ������ɊS�̂���l�����ɂ��E�߂̂P���ł��B
���u�h���b�J�[�������Ă����l���������o�c�V�̌����v�i�����O��@�Y�Ɣ\����w�o�ŕ��@1800�~�j
�o�c�̒��S�́u�l�Ԃ̑����v�ɂ���ׂ����A�Ƃ����h���b�J�[�̌o�c�v�z�ɂقꍞ�A�W���Y�~���[�W�V�����ł�����o�c�R���T���^���g�̑����O��������߂ď����グ���A����߂Ď��H�I�Ȍo�c���[�_�[�w�쏑�ł��B
�h���b�J�[�o�c�_��ǂ��͑����ł��傤���A�{���͂�����ƈِF�̃h���b�J�[�����Ƃ����Ă����ł��傤�B
�ǂ����u�ِF�v���Ƃ����A�{���̓h���b�J�[�̌o�c�_�̏Љ�Ƃ��������A�h���b�J�[�̍��Əo��������ґ����O��̍����A����܂ł̎��H�̂Ȃ��琶�݂������A�Ǝ��̃h���b�J�[�v�z���H�o�c�̏��Ȃ̂ł��B
��������́A�{���̒��ł��������Ă��܂��B
�{���̃}�l�W�����g�w�̑����́A�h������h���b�J�[�̎v�z����C���X�s���[�V�����āA���̃A�[�g�E�����E���_���E�̊w�т��R���T���e�B���O�̌���œ����E���������̂ł��B
�܂荰�̋��������̒��Ő��܂ꂽ�C���X�s���[�V�������A���̏��݂������Ƃ�����ł��傤�B
������̍���ɂ���̂́A�h���b�J�[�̎v�z�ł��B
�h���b�J�[�̌o�c���_����w�l�͑����ł��傤���A��������̊w�т͂�����u�E�]�I�v�ŁA�m�M�I�ŁA���̍�����w�̂ł��B
�������E�\�z�����h���b�J�[���_�́A�{����ǂ�ł��炤��������܂��A�ꌾ�Ō����A���̂悤�ɂȂ邩������܂���B
�o�c�́A�u�l�Ԃ̑����v��u���a�Ŏ��R�ȎЉ�v���������邽�߂̂��̂ł���A�����g�D�̗��v���グ�邽�߂̂��̂ł͂Ȃ��B
�������A�l�Ԃ̑����ƕ��a�Ǝ��R�ȎЉ�����A��Ƃ����C�ɂ��Ă����A���ʓI�ɋƐт��オ���Ă����B
��Ƃ͐l�ɂ���Ď��̂��n��グ���Ă��܂����A�Љ�ɂ���Ďx�����Ă��邩��ł��B
�����ɂ́A�l�Ɗ�ƂƎЉ�O�ʈ�̂ƂȂ����o�c�̑�����������܂��B
�����������O���A��������͂���܂ł̂��܂��܂Ȏ��H�̒�����A�ɂ߂Ă킩��₷���V�̌����ɑ̌n�����A��̓I�ȍs���菇�Ƌ�̓I�ȃc�[���ŁA�N�������H�ł���悤�ɁA���������Ă���Ă���̂ł��B
�������A�m���Ă��邾���ł͂��߂��ƌ����āA�Ō�Ɂu���E�����ǂ����̂ɂ��邽�߂ɁA�����s���Ȃ����I�v�ƁA�ǎ҂̍��̃X�C�b�`�������Ă����̂ł��B
�h���b�J�[�Ƒ�������̍��ɔw���������ꂽ��A�����Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B
��������́A�����̓��{�̏ɑ傫�Ȋ�@���������Ă��܂��B
�����炱���A��Ƃ̌o�c���[�_�[�̐l�����Ɍ����āA�{�����������ɂ����Ȃ������̂ł��B
��������́A���[�_�[�V�b�v�Ƃ͌��͂ł͂Ȃ��A�����l���������A���ʂ��グ��u�ӔC�v���ƌ����܂��B
�{����ǂl�����ɂ́A���������^�̃��[�_�[�Ƃ��Ă̎���̃X�C�b�`���N�������A�l�ƎЉ���K���ɂ��Ă������߂ɂ����A����̑g�D�̐��ʂ��グ�Ăق����Ƒ�������͊���Ă��܂��B
�����Ă��ꂱ�����A�l�Ԓ��S�̌o�c������h���b�J�[�̊肢���Ɗm�M���Ă���̂ł��B
�u���[�_�[�ɁA���������Ƃ����Ȃ����B�l�ƎЉ���K���ɂ��Ȃ����B�����푈�̋N���Ȃ��A���R�ŕ��a�ȎЉ�����Ȃ����B�Ɣށi�h���b�J�[�v�͍�����i���Ă��܂��v�ƁA��������͏����Ă��܂��B
�{���̖ڎ��͎��̒ʂ�ł����A�V�̌������ƂɁA���{�菇�Ǝ��H�c�[����������Ă��܂��̂ŁA���̋C�ɂȂ�����ɂł����H�ɂȂ�����A�ƂĂ����H�I�ȏ����ł��B
�����āA���H���邱�ƂŁA�����炭�h���b�J�[�̗��O���̌��ł���ł��傤�B
������������A����͍ŋ߂́i�l��Q������ȁj��ƌo�c�Ƃ͎��Ă���悤�ň���Ă��āA�܂������Ȃ���Ƃ����C�ɂ��A�ƐтɂȂ����Ă����͂��ł��B
��ƂɊւ���Ă�����͂������ł����A�s����m�o�n�Ɋւ���Ă���l�ɂ��A���ЂƂ��ǂ�ł��������A���H�Ɏ��g��ł��������������Ǝv���܂��B
������������A���H��ʂ��Đ��������ς�邩������܂���B
�Ȃɂ���h���b�J�[�Ƒ�������̍����������Ă��܂�����B
���� �@ �@�h���b�J�[�Ƃ̏o�
�����P�@�@�ڋq�u���̌����F�}�[�P�e�B���O�J���p�j�[
�����Q�@�@�ϊv�E�i���̌����F�C�m�x�[�V�����J���p�j�[
�����R�@�@���ʂ��グ�錴���F�v���_�N�e�B�u�J���p�j�[
�����S�@�@�w�K����g�D�̌����F���[�j���O�J���p�j�[
�����T�@�@���[�_�[�m���̌����F���[�_�[�V�b�v�J���p�j�[
�����U�@�@�g���E�����̌����F�~�b�V���i���[�J���p�j�[
�����V�@�@�l�������������F�}�l�W�����g�J���p�j�[
�ŏI���`�@�����E���ȁE�s���̏́F���Ȃ��̐^�̃��[�_�[�V�b�v�ɉ�����
���Љ�ۏ��̂ē��{�ւ̏��������i�{�c�G�@�����̌����Ё@1100�~�j
��Ð��x���v�ɐ��͓I�Ɏ��g��ł���{�c�G���A�ƂĂ����₷���{�������Ă���܂����B
���Ј�l�ł������̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
�{�c����́A��M�̐l�ł��B
���������v�����������āA�b�ɂ��Ă����Ȃ��l�����Ȃ��킯�ł͂���܂��A������Ƃ��b���A�݂�ȋ�������͂����Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�{�c����̎v�����A���Б����̐l�ɒm���Ăق����āA�����ł��邱�Ƃ͂Ȃ����ƍl���Ă����̂ł����A���̖{���L�߂Ă������ƂɁA�܂��͐s�͂������Ǝv���܂��B
�{�c����́A�O�Ȉ�Ƃ��Ĉ�ÂɎ��g�ނނ������A���{�̈�Ð��x��Љ�ۏᐧ�x�������̎��_������v���Ă������߂̊����Ɏ��g�܂�Ă��Ă��܂��B
�ꎞ���́A�e���r�Ȃǂł����Ȃ蔭������Ă��܂����̂ŁA�����m�̕������Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B
��������������i�߂邤���ɁA�{�c����̎v���́A��Â�Љ�ۏ�ɂƂǂ܂炸�A�����������A�܂�Љ�̂��̂̂������ς��Ă����Ȃ���Ƃ����v���ɂ܂ōL����A�җ���_�@�ɁA�Љ���ɐ�O���ׂ��A�O�Ȉ�����ނ����̂ł��B
�ȗ��A��ÂƓ��{�Đ��̂��߂̍u���⎷�M�Ȃǂ̏�M�ɉ����āA���L���s���̘A�т�ڎw���đ����̎s�������ւ̎Q���ɑS�͂𓊂��Ă��Ă��܂��B
�����̃T�����ł����b���Ă��������Ă��܂����A�����Ǝ��Ԃ������āA�����̐l�ɕ����Ăق����Ƃ����v���Ă��܂����B
�ł�����{�����o�ł��ꂽ���Ƃ́A�ƂĂ����ꂵ�����Ƃł��B
�{���ł́A�{�c���`���������Ƃ̈ꕔ���Ƃ͎v���܂����A�{�c���Ȃ��l����ς��Ă܂ł��̊����Ɏ��g��ł���̂��A�����Ė{�c����ԓ`���������Ƃ͉����A���ƂĂ������ɂ킩��₷��������Ă��܂��B
�v���͂������Ă��܂����A�P�Ɂu�v���v�����Ō���Ă���̂ł͂���܂���B
��Ì���ł̑̌��ƍL�����삩��̃f�[�^�Ɋ�Â��āA���{�̂ǂ������ʼn���ς���Έ�Â�Љ�ۏႪ�[������̂����A�L������Ɛ[�����@�̂��ƂɓW�J���Ă���̂ł��B
��̓I�ȓ��e�́A�{����ǂ�ł������������̂ł����A�{�c���A�Ȃ��������������𑱂����Ă����̂��̗��R���Љ���Ă��炢�܂��B
����́A�u���߂��ɖ���߂�v�悤�ɓw�߂Ă������炾�ƁA�{�c����͌����܂��B
�����āA���̖{���𖾂�߂邽�߂̂S�̎��_�Ƃ��āA�u�S�̑���c������v�u�V���b�N�E�h�N�g�������x�����ȁv�u���j�Ɋw�ׁv�u �O���[�o���X�^���_�[�h�Ɣ�r����v�������Ă��܂��B
����́A�ŋ߁A���������Ƃ�����Ύ��������Ȏp���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�����Ă��������S�̎��_�����������߂ɂ́A�l�����ՂɂȂ��|�C���g�ɂȂ�̂ŁA���ɐU���Ȃ����f�B�A�E���e���V�[�����߂Ȃ�������Ȃ��ƌĂт����܂��B
����Ɋ֘A���āA�{�c����́A�u���{�̊w�Z�́A�l���Ȃ��l�Ԃ�5�̕��@�Ő��ݏo���Ă���v�Ƃ����A��،X�邳��Ƃ����l�̃u���O���Љ�A���̂悤�ɏ����Ă��܂��B
������ƒ����ł������p�����Ă��炢�܂��B
�u�����̓��{�l�͊��Ⴂ���Ă��邪�A�o����ƍl����͕ʂł���v�Ɨ�؎��͋������A�u���{�ł͍�����8�����T�����[�}���̂��ߊw�Z�̏d�v�Ȏg���͏�i�̌������Ƃ��悭�����āA�����������A����ꂽ���Ƃ𒉎��ɍs���A�s���������Ă��فX�Ɠ����A�W�c������D�悷��悤�ɋK�i�����邱�Ɓv�Ɠ��{�̋�����꓁���f�ɂ��Ă��܂��B�m���ɋ��炱�������ƂɂƂ��ēs���̂悢�l�ԂY�ł���V�X�e���ł��B�U��Ԃ�Έ�Ô�}���̍���̌��ʂ̐�i���ŏ��̈�t���̒��ŁA�ƒ���]���ɂ��Ă܂ŖفX�Ɠ����Ă��������A�u����ꂽ���Ƃ𒉎��ɍs���A�s���������Ă��فX�Ɠ����A�W�c������D�悷��v�Ƃ����A�l���Ȃ�����̎����������̂ł��B
�u�I���Ɂv�Ŗ{�c�������Ă��邱�Ƃɂ��S���狤�����܂��̂ŁA�����������ƒ����ł������p�����Ă��炢�܂��B
�������ǂ��Ȃ�Ȃ���Έ�Â͂������Љ�ۏ�⋳����ǂ��Ȃ�Ȃ��A���̈�O�œZ�߂��̂��{���ł��B��������{���u�������ɍl���閯�卑�ƂƂ��Ďq�⑷�̐���Ƀo�g���^�b�`�ł���悤�A����������u�l���Đ����ɊS�����l�v�𑝂₷���Ƃ�ڕW�ɍu����s��������簐i�������Ǝv���܂��B
���̃��b�Z�[�W���A���͂�������Ǝ~�߂悤�Ǝv���܂��B
�����A�����Ƃ͎��͐������̂��Ǝv���āA�T�����T�J�Â��Ă��܂��B
�{���͖{�c�������Ă��Ă���u���̃G�b�Z���X���x�[�X�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���̂ŁA���Гǂ�łق����ł��B
�����ċ���������A�܂��ɐl�ɂ����ЏЉ�Ă��������B
�܂��{�c����͂����ȂƂ���ōu�������Ă��܂��̂ŁA�@�����ΐ��������������B
�{�c����́A���l���W�܂�Θb�ɍs���Ă������Ƃ܂ł���������Ă��܂��B
�{���ɂ͏o�Ă��Ȃ��A���ɂ͂�����Ɗ����Ă��܂��悤�ȁA�S�a�ފy�����W���[�N�≡���b����������̂ŁA���Ђœǂނ̂Ƃ͈�����ʔ����Ǝ���������܂��B
�����ȈӖ��ő����̐l�ɓǂ�ł������������Ǝv���Ă��܂��B
���u�ό���i�����߂����āv�i�c�씎�ȁ@�����o�ώЁ@1600�~�j
�u�ό��J���v���e�[�}�ɂ����n�������̂̒n�抈�������L�����Ă��܂��B
�����Z��ł����t���̉䑷�q�s���A���N�O�Ɋό��ɗ͂����邽�߂ɁA�O��������Ƃ��̗p���A�ό��s���ɗ͂����o���܂����B
�������A���̐i�ߕ��͎��ɂ͂ǂ�����a��������܂��B
�u�`�����v�d���ŁA�u�`���鉿�l�v�Ɓu�ւ����v�̖��������ア�C�����܂��B
�䑷�q�s�����ł͂���܂���B
�ό��Ƃ������Ƃ����Ⴆ�Ă���Ƃ����v���Ȃ��悤�Șb�����Ƃ͏��Ȃ�����܂���B
�ȑO�A�n��U���A�h�o�C�U�[�Ƃ������������Ă��āA����ό��n�Ɋւ�������Ƃ�����܂����A�ό��̑������͐l�ɂ���Ă܂������Ⴄ���Ƃ�Ɋ����܂����B
�����g�́A�u�ό��v�Ƃ́A���̒n����P�������Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B
�P�����ƌ����Ă��A���h�Ȏ{�݂�����Ƃ��A�h��ȃC�x���g������Ƃ��������Ƃł͂���܂���B
�v�́A�݂�Ȃ��Z�݂Â������Ǝv���悤�ȁi�s�������Ȃ�悤�Ȃł͂���܂���j���͓I�Ȓn��ɂ��Ă������Ƃł͂Ȃ��̂��B
�܂�A�ό��Y�ƂƂ́A�ό��q�̂��߂ɂ���̂ł͂Ȃ��A�����ɏZ��ł���l�����̂��߂ɂ���̂��낤�Ǝv���܂��B
�n��́A�{�݂⎩�R�������Ő��藧���Ă���킯�ł͂���܂���B
��ԑ�Ȃ��Ƃ́A�����ɏZ��ł���l�����̐����������o�������A���͋C�B
�����ɕ�炵�Ă���l�������݂�ȍK�������Ȃ�A������K�ꂽ�l�������K���ɂȂ�ł��傤�B
���̌��ʁA������u�ό��q�v�������Ă���B
����ȋC�����܂��B
����Ȏv���������Ă������ɁA�o������̂����̖{�ł��B
�F�l�̏�{�m�q���ւ�����{�ł��B
�{���͒��N�A�i�s�a�i���{��ʌ��Ёj�Ŋό��Y�Ƃ̔��W�Ɏ��g��ł����c�씎�Ȃ���i���{���s�Ƌ����j���A�V��������Ɍ����Ắu�c�[���Y���v�̉��l�Ɩ������A�Љ�ɖ₢���������ł��B
�c�삳��́A�c�[���Y�����u�������V�R�̊ό����s�v�����A�u�l�X�̗����n�o���A�𗬁A����𑣂��ƂƂ��ɐV���ȉ��l�ς�n��o�������v�ƒ�`���Ă��܂��B
��������A�o�ϊ����Ƃ��Ă̊ό��Y�Ƙ_�ł͂Ȃ��A�Љ���Ƃ��Ă̍L���L�������������W�J���Ă��܂��B
�c�[���Y���ɂ́A�ٗp�݁A�o�ς𐬒�������͂����ł͂Ȃ��A�P��i�߁A���a�ȎЉ���\�z����Ƃ����͂�����Ƃ����̂��A�c�삳��̊m�M�ł��B
����́A�c�삳��̒��N�̊�������̊m�M�ł��傤�B
�ƂĂ��[���ł��܂��B
���Ȃ݂ɁA��N�i2017�N�j�̖K���O���l���͂Q�W�U�X���l�ƌ����A���{�o�ςւ̔g�y���ʂ����܂��Ă��܂��B
�������o�ό��ʂ����ł͂���܂���B
����ɂ���āA���{�Ƃ������ւ̗�����e���݂��L����ƂƂ��ɁA���������{�l���܂��A���l�Ȑ��E�̑��݂ɐG��A�u�ӎ��̕ǁv���J����A���ꂪ���a�ɂȂ����Ă����Ƃ����킯�ł��B
�ƂĂ������ł��܂��B
�����������_����l����Ɩ��������Ă��܂��B
���{�l�́A�����̖��͂���������ƔF���ł��Ă��邾�낤���Ɠc�삳��͖���N���܂��B
�������͂����ƁA���{�̗��j�╶����m��Ȃ�������܂���B
�����Ă��ꂪ���E�ɂƂ��āA���邢�͖����ɂƂ��āA�ǂ�ȉ��l������̂�����������ƍl���Ȃ��Ƃ��A�c�삳��͂��������܂��B
���Ƃ��Ă̗��ꂾ���łȂ��A���E���猩�����{�̒n��Ƃ��čl���Ă݂܂��傤�B
���{�͗B��̔픚���ŁA�����{��k�Ђł͕����������̂ɂ��������܂����B
�����̎����������Ȃ���A�l�K�e�B�u�ł͂Ȃ��|�W�e�B�u�ɔ��M���Ă��������ɗ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�����āA�u���{�̍������ɂ��镶���ƁA���a�����߂鐸�_���ǂ������o�����A����͓����I�����s�b�N�E�o�������s�b�N�Ɍ����ĐV�������b�Z�[�W��ł��o�����������ł�����܂��v�Ƃ������Ă��܂��B
���́A�ŋ߂̂悤�ȒP�Ȃ�o�ϊ����ɂȂ��Ă��܂����I�����s�b�N�̊J�Âɂ͔ے�I�ł����A�����������ƂɎ��g�ނ̂ł���A�I�����s�b�N�ɂ��傫�ȉ��l�����������܂��B
����ɓc�삳��́A2015�N�̍��A�T�~�b�g�ō̑����ꂽ�����\�ȊJ���ڕW�iSDGs�j�Ɍ������āA�c�[���Y���łł��邱�Ƃ͂�������Ǝ咣���܂��B
�����Ă���Ɍ����āA�i�s�a�́u��O�̑n�Ɓv�Ɏ��g��ł��邱�Ƃ��Љ�Ă��܂��B
�����ŕ\������Ă���i�s�a�̂��ꂩ��̎��Ɨ̈�́A�u�l�̐����̎��̌���v�u�����I�Ȓn��Љ�̔��W�v�u��Ƃ̎Љ�I���l�̌���v�̂R�ł��B
�܂��ɁA�ό�����c�[���Y���ւƂi�s�a�����悵�ĕς�肾���Ă���킯�ł��B
����ɔ�ׂāA���{�̎����̂̊ό�����̈ӎ��͑傫���x��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�{���́A����ɂ���ʂ�A�u���{�̃c�[���Y���Y�Ƃ̉ʂ����ׂ������v���������{�ł����A���̑�5�́w�����ς��邱�̍��̖����E�l�̐������x�ɏے������悤�ɁA�������̐������ɂ������Ȏ�����^���Ă���܂��B
�ό��Ƃ͉������l����1���Ƃ��Ă����߂��܂��B
���u�����������L�v�i�g�����ȁ@�R�~�[������Ё@1800�~�j
�`�s�l�i���������a���@�j�𗘗p�������Ƃ̂���l�Ȃ�A����������ɂ��Ă��鏬���ȃ~���[�������m���Ǝv���܂��B
����Ȃ̂ɍL�p�Ɍ�����s�v�c�ȋ��ł��B
�ŋ߂͒n���S�̒ʘH�Ȃǂɂ��L���g���āA�Փ˖h�~�Ȃǂɖ𗧂��Ă��܂��B
���̃~���[�������Ă���̂��A�R�~�[������Ђł��B
�����Ƃ��A�R�~�[�̎В��̏��{�R����ɁA�R�~�[�͉��������Ă����Ђł����Ɛu���ƁA�����͕���������Ă����Ђ��Ɠ�����͂��ł��B
�R�~�[�ɂ͂�������̕��ꂪ����̂ł��B
���̃R�~�[���A�o�Ŏ��Ƃ��n�߂܂����B
����������ЂƂ��āA�����̐l�ɓǂ�łق����u����v��{�ɂ��āA��������Ǝc���Ă��������Ɏ��g�݂����A�Ƃ����̂��o�Ŏ��ƂɎ��g�݂��������R�ł��B
�Q���ɂQ���̖{���o�ł���܂����B
�P���́A����䍲�q����́u���̂Ȃ��L���v�̕����ł��B
���̖{���ł����͓̂����̃T�������W���Ă��܂��̂ŁA���ɂ͎v���o�̐[���{�ł��B
�����Ă����P�����A�����ŏЉ��u�����������L�v�ł��B
����̈�l�́A����ɂ��鎙���{��{�݁u���牀�v�������̓��{��������ł��B
�����Q�x�قǂ�����Ă��܂��B
���̂�������̓��{�K�M����ɂ͂���������Ƃ�����܂��A�܂����������������킯�ł�����܂���B
���̖{��ǂ�Œm�����̂ł����A�ԐړI�ɂ͂����₩�ȂȂ��肪���ɂ��������̂ł��B
�{���́A���w�ň��������Ă����푈�ǎ����������Ƃ����G�s�\�[�h����n�܂�܂��B
�����āA���̊�������n�܂��������{��{�݁u���牀�v�̑����҂�������w�ɍ��i����Ƃ����G�s�\�[�h�ŏI����Ă��܂��B
���̊ԁA70�N�B
���{�̎Љ�͑傫���ς��A�l�X�̉��l�ς��ς��܂����B
�s�킩��o�ϕ������o�āA���݂ɂ�����܂ŁA�q�ǂ������Ɋւ���Ă������{���q�̓��L�́A�����ɁA����70�N�̓��{�Љ�̏��j�ł�����܂��B
����̕ω��́A���܂��܂ȃG�s�\�[�h�╃�q���̌����ɂ��ǂݎ��܂����A���Ɉ�ۓI�������̂́A���牀�T�O���N�L�O���ɁA�K�M���������A�u���́A�����̂��̂����Ŏq�������Ă����̂ł����v�Ƃ������t�ł����B
���H����o�Ă����A���̌��t�ɂ͐[���Ӗ��������܂��B
�{���Ɉ�т��Ēʒꂵ�Ă���e�[�}�́A�u�Ƒ��v�u����v�u�K���v�ł��B
��Ќǎ��R�l�������Ɉ�����莙���{��{�݂��n�߂����Z�E�ƁA���̒��j�Œ��쌧�����Z�Z�����C���{��{�݂��p�����Q��ڏZ�E�̊�����ʓǂ���ƁA�����Љ�̉��l�ς̕ω����ǂݎ��A��������u�Ƒ��v��u����v�A����Ɂu�Љ�v�ɑ���l�����̕ω��������Ă���Ɠ����ɁA������ĕς��Ȃ����̂ւ̋C�Â��������܂��B
�����Ɉӎ�������Ă��镃�q���̊ԂŁA�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ肪�������̂��A�ƂĂ�����������܂����A���ړI�Ȃ��Ƃ�͂��܂�o�Ă��Ȃ��̂͂�����Ǝc�O�ł��B
�܂��A���̘b�����S�ɂȂ��Ă��܂����A���̂��Ƃň�����Q��ڌ������A����̕ω��̂Ȃ��ʼn����l���A���ꂩ����ǂ��W�]���Ă��邩�́A����������܂��B
���҂́A�u�Ƒ��Ƃ͉����A�ƒ�Ƃ͉��������ł��l���邫�������ɂȂ��Ă��炦����肪�����v�Ə����Ă��܂����A�u�e�q�W�̂�����v��u�q�ǂ��̎����v�Ƃ͉����ɂ��Ă��A���𓊂������Ă��܂��B
��������𒆐S�ɂ������҂����҂��Ă��܂��B
���u�H�́A�����킹�̎�v�i���Βm�}�@�ԓ`�Ё@1500�~�j
���͗��������邱�Ƃ͂قƂ�ǂ���܂���B
�Ȃɂ͐旧����܂������A�K���ɖ��Ɠ������Ă���̂ŁA�Ȃ����p�Ɏc���Ă��ꂽ�G�v�������A10�N�����܂����A�g��ꂽ���Ƃ�����܂���B
������ƌ����āA�C���X�^���g���͍D���ł͂���܂���B
�O�H�͎��X���܂����A��{�I�ɂ͎�Â��藿������{�̐��������Ă��܂��B
�������Ȃ���A�쎀���Ă��Ă����������͂���܂���B
������́A�H���������킹�̎�ł���A�����̊�{���ƌ����܂��B
�����āA���������邱�Ƃ̑���Ɗy�������L���Ă��������ƌ����Ă��܂��B
���̍����A���ɂ������Ɨ������ł���ƌ����āA���̖{�𑗂��Ă��Ă���܂����B
�]�v�Ȃ����b�ł����A�D�ӂɂ͕��Ȃ�������܂���B
�ł�����ǂނ����ł͂Ȃ��A���H���Ă���Љ���������Ǝv���Ă�����A��͂�x���Ȃ��Ă��܂��܂����B
�Ȃɂ��뗿���͋��ǂ��납�A���̋C���F���Ȃ̂ł��B
�������Ȃ�Ƃ��A���̖{�ɂ��������Ċ�{�̊�{�͎����ł���Ă݂܂����B
��{�̊�{�Ƃ́A���������A�ʂ˂��A�ɂ���g���Ắu�d�ˎρv�ł��B
���ǂ낭���ƂɁA���Ƃ��ȒP�ɁA���ł��ł��܂����B
�����Ĕ����������������܂����B
������ƍK���ȋC���ɂȂ�܂����B
�����A�݂Ȃ��u���₩�ɍK���ɐ��������v�Ȃ�A���̖{�����E�߂��܂��B
�H�Ɏ��g�݂��������������͔���������Ō����������Ƃł��B
�v�̕a�C���������߂ɁA�����ĕv�̎��ʂɂ��Ȃ����߂ɁA������́A�H�ƌ��N�ɂ��Ă�������̖{��ǂ݁A�̌����d�ˁA�u�H�v�̑��������������悤�ɂȂ�܂����B
�u�H�͐������v�Ƃ��u�H�͂��̂��v�Ƃ������Ƃ��A�P�Ɍ��t�����ł͂Ȃ��A�S�ꂻ�����Ǝv���Ă����̂ł��B
�����āA���������̂��u�����킹�ɐ����邽�߂̐H�v�B
���ꂱ�����A�v�̎��ʂɂ͂��Ȃ����Ƃ��ƋC�Â����̂ł��B
�{���A�H�͐l�������킹�ɂ�����́B�������y������邱�Ƃ͂��̑����B
���ꂪ������̍l���ł��B
�ł�����A��l�ł������̐l�ɁA�u�����킹�ɐ����邽�߂̐H�v��`���Ă��������ƍl�����̂ł��B
������́A�����͊y�����ł��Ȃ�������Ȃ��ƌ����Ă��܂����A�������Ɏ��ɂ��ł��闿���@�ł��B
������́u���̗����͓K�������v�Ƃ����A�������̕��ʂȂǂ͂�������Ă��Ȃ��̂ł��B
������͂��������Ă��܂��B
�������@�͍ŏ����猈�߂����A���̖�����Ă��̎���Ԃ����Ǝv���������̎d������������̂ł��B�i�����j�������������Ɠ����ŁA�����□�t���������łȂ���Ƃ�����肷����̂͗����̕����������Ă��܂��Ǝv���܂��B
�����̒��S���ɂ���̂́A������Ƒ��̐S�Ƒ̂ɂƂ��Ċ�тƂȂ闿���ƍl���܂��B�i�����j��Ɏ����̐S�Ƒ̂̐����B�S���x�����������ł͂���܂���B�G�߂₻�̎��̑̒��Ȃǂł������Ă��܂��B�N��ɂ���Ă��ς��܂��B���ł͂Ȃ��A��Ɏ����̑̂Ɍ��������Θb�����Ȃ����邱�Ƃł��B�̂������Ƌ����Ă���܂��B
�u�K���v�ɂ́A�ƂĂ��[���Ӗ������߂��Ă���̂ł��B
�����āA������́A�����͎������g�Ɍ����������Ƃ�������Ȃ��Ƃ����܂��B
�������A�ŋ߂́A�������y��������Ă��邾���ł͂����킹�ɂȂ�Ȃ��������o�Ă����A�ƍ�����͌����܂��B
���܂�ɂ��s���R�ȐH�ו��������Ȃ�A���͐H�ׂ����̂ŕa�C�ɂȂ��Ă����悤�ɂȂ��Ă��܂�������ł��B
�����āA�H��ʂ��Ă����킹�ɐ����邽�߂́u�H����̖��a�w�v����܂��B
����͎���3�̒�����Ȃ��Ă��܂��B
�@���R�i���˂�j������ʂ��āu�������y�����v�Ǝv���č�邱��
�A���a�̂��߂̉A�z�u����ʂ��āu�����̎厡��͎������g�v�Ƃ������o��������
�B�q�ǂ�������䏊�ɗ������邱�Ƃ́A�����̖��a�ɂȂ���Ƃ�������
���Ă��ꂩ���͖{�������ǂ݂��������B
�Ō�ɁA���������������̕��͂����p���܂��B
��������������̂��u���������ˁv�Ƃ����ĐH�ׂ邱�ƂŁA�݂�Ȃ������킹�ɂȂ��Ă����B�u�H�v���Ă������͂������Ă���Ǝv���܂��B����ȁu�H�v�̎��J�������Ƃ����Ƒ厖�ɂ��Ăق����ł��B�������Ă����Ăق����ł��B�u�H�v�͂��ׂĂ��Ȃ��Ă����܂��B���ׂĂ������킹�ɕς��Ă����͂��u�H�v�͎����Ă��܂��B
����������Ƃ������������Ă݂āA���̂��Ƃ����͎������܂����B
�ǂ��ł����B
�݂Ȃ�����{����ǂ�ŁA�K���ɂȂ�܂��B

���u����̗��������v�i�����C�@���u���[�o�Ł@2017�j
16���I���̃|���g�K�����̐��E�n�}�ɂ́A�����嗤�̓��ɉ��������`����A���̗S�̖̂��Ƃ��āA�u�����v���Ӗ�����|���g�K���ꂪ�L����Ă����A�Ƃ������Ƃ������z�q����́u�푈�܂Łv�Ƃ����{�Œm��܂����B
���̗̈�̓��̖����u���{�v�����������ł��B
���{�́A�����i����j�̈ꕔ���Ƃ̔F�����A�����̐��E�ɂ������Ƃ������ƂɂȂ�A�Ɖ�������͏����Ă��܂��B
�����܂ł��Ȃ��A�����̗����͓��{�Ƃ͕ʂ̍��Ƃł����B
���̂��Ƃ�m���āA���߂ĉ���̂��Ƃׂ����Ȃ������ɁA����ݏZ�̏�������w����̗��������x�i���u���[�o�Łj���͂��܂����B
�s�v�c�Ȃقǂ̃^�C�~���O�Ȃ̂ŁA��C�ɓǂ܂��Ă��炢�܂����B
�����āA1793�N�ɏo�ł��ꂽ���ł́w�A�����J���E�G���T�C�N���y�f�B�A�x��1797�N�́w�G���T�C�N���y�f�B�A�E�u���^�j�J�x�ɂ́A�u�����Ƃ̓A�W�A�̋��傩�L��Ȓ鍑�𐬂����X�̖��O�ł���B���̍����͕����J������A�A�W�A�ɍL���鑼�̖�؍��ƍ������Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ə�����Ă������Ƃ�m��܂����B
�܂��܂�����̂��Ƃ�m�肽���Ȃ�܂����B
�{���́A19���I�ɗ����ɂ���Ă����g����h�̐l�����̍q�C�L�≓���L�Ȃǂ̋L�^��ǂ݂Ȃ���A���n��K�₵�Ă܂Ƃ߂��A��������̗��j�I�s�G�b�Z�C�ł��B
�P�Ȃ�L�^�̏Љ�ł͂���܂���B
����������A���Ƃ����ŁA�u�Ƃ���ǂ����E���Č������痣��A�z���̐��E�ɗV�v�Ə����Ă��܂����A��������̐l����l�������f���ɏo�Ă��āA�G�b�Z�C�Ƃ��Ă��ʔ����B
���ɉ����ɊO��Ȃ�����A����̉�����ւ̉s���ڐ������������郁�b�Z�[�W�����߂��Ă��܂��B
�C�y�ɓǂ߂�{�ł����A�ǂݏI����ƌ��݂̉���̏ւ̋����◝�����[�߂���悤�ȁA����ȏ�������̎v�����`����Ă��܂��B
���{���J���������y���[�́A���{�ɗ���O�ɗ����Ɋ���Ă��܂����A���̂��Ƃ����͖{���ŏ��߂Ēm��܂����B
�y���[�́A�������ƂĂ��d�����Ă��āA���{�ɂ͂Q����`���Ă��܂��A�����ɂ͂T�����e���Ă������Ƃ��A���߂Ēm��܂����B
�{���̕���́u�y���[�ȑO�ƃy���[�Ȍ�v�Ƃ���܂��B
���̎��_�͎R���h�S����̒�������w�A�Ə�������͏����Ă��܂����A����ɂÂ��āA�u���\�Ȍ�����������A�y���[�ȑO�A�o�W���E�z�[���̍q�C�L�͐a�m�I�i�p�������ς��͂��܂茩���Ȃ��j�A�y���[�͗��\�ҁi�C�͊O���j�B����ɂ���ƁA�y���[�̂��������ł��܂���ʂ��Ă���A�Ɗ�����v�Ə����Ă��܂��B
���́A���̒Z�����͂ɏ�������̋����v���������܂��B
��������́A�N���t�H�[�h�́u�K�����L�v�܂��āA�������u���`�v�ƕ��Ԏ��R�f�Ս`�ɂȂ��Ă����\����z�����A���������Ȃ�����A100�N��̓��Đ푈�ł͗��������ɉp�ČR��n�������A����������{�ւ̔����@���A����ї��������낤�ƌ����܂��B
�����Ă��̌�ŁA�u�ČR�̉Î�[��n������{�{�y�ɑ���j�U�������ł��\�Ƃ���������v���o������v�Ə����Ă��܂��B
�N�����܂���ɂ��Ȃ����Ƃł����A���ɂ͂ƂĂ��^�����������������錾�t�ł��B
����̊�n�́A������k���N����łȂ��A�u���{�{�y�v�ɂ��������Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ�������܂���B
�ʔ����G�s�\�[�h���ЂƂЉ�Ă����܂��B
1816�N�A���������Ɋ�`�A�ߔe��40�]���ԑ؍݂����p���l�o�W���E�z�[���́A�A���r���ŁA�Z���g�w���i�ɗ�����Ă����i�|���I���̂Ƃ���ɗ�������������ł��B
�o�W���E�z�[���̕��́A�m���w�Z�Ńi�|���I���Ɠ����ł����B
�ނ́w�q�C�L�x�ɂ́A�u�����ł͕����p�����A�ݕ���m��Ȃ��A�܂��c��̖��O�����������Ƃ��Ȃ��A�ƃz�[�������ƁA�i�|���I���͑�����A���������܂ŕ��������Ƃ����v�Ə�����Ă��邻���ł��B
�����ăi�|���I���́A���������������ł��B
�u���̂悤�ȉR�͎~�߂Ă��炢�����B�����������Ă��邱�̐��̒��ɕ���������Ȃ�����������͂����Ȃ��B���킪�Ȃ���A���̖����͂ǂ̂悤�ɐ푈������̂��v�B
���ꂩ��w�Ԃ��Ƃ͂������肻���ł��B
���u�瓹�́u�������v�|�l�ԓ��A�W�O�N�̂���݁v�i���v�Ԑi�@�o�g�o�@2000�~�j
������{�������Ռݏ������Ŋ�����ЃT�����[�̑n�Ǝ҂ł��鍲�v�Ԑi���A�n��50���N���@�ɁA�����g�́u�l�ԓ��v�ւ̕��݂�U��Ԃ�A�V��ɂȂ���u�瓹�v�Ɛl�Ԑ������߂邽�߂̓��ł���u�l�ԓ��v�̐^�����܂Ƃ߂����ł��B
���v�Ԃ���́A���{�̗��j��l���A�@���Ȃǂ̌����ƁA����̈̐l�Ƃ̌𗬂Ȃǂ�ςݏd�˂邱�ƂŁA�����́u�������v�i�w�킪�l���́u�������v�xhttp://cws.c.ooco.jp/books.htm#071216�j�����������Ă��܂����A����͂��������ɐ[�߂āA���{�l�Ƃ��ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ�������������Ă���Ă��܂��B
�{���̏ڂ������e�Љ�́A���v�ԗf�a����̃u���O�����ǂ݂��������B
http://d.hatena.ne.jp/shins2m+new/20171030/p1
���v�Ԑi����́A���N�A�������Վ��Ƃ�ό����ƂɎ��g�܂�Ă��܂����A�������v�Ԃ���ɂ�������̂́A�k��B�s�̊ό������Ấu�z�X�s�^���e�B�v���e�[�}�ɂ����V���|�W�E���ł����B
�����ł��b�������Ă��炢�A���̌�A���v�Ԃ��o�c����T�����[�����K�˂��܂����B
���ꂪ���������ŁA���q����̍��v�ԗf�a����Ƃ̌𗬂��n�܂����̂ł����A���̍��͍��v�Ԑi���A���������傫�ȗ��O�̂��ƂɎ��ƓW�J����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂���ł����B
����̖{��ǂ܂��Ă�����āA�p�������Ȃ��炻��ɋC�Â����̂ł����A�����Ō���Ă��邱�Ƃ̑����́A�܂������Ⴄ�A�v���[�`�ł����A���̊����ɒʂ��Ă��邱�Ƃ������A�ƂĂ��������܂����B
�{���̓��e�Ɋւ���Љ�́A�f�a����̃u���O�����Ђ��ǂ݂������������̂ł����A�����C�Â����Ă���������Ƃ��Q�����Љ�Ă����܂��B
�ЂƂ́A���{�̕����ɂ͂���߂ă|�W�e�B�u�Ȏv�z�����߂��Ă���Ƃ������Ƃւ̋C�Â��ł��B
���v�Ԃ���̐M���́A�u�������z�ɂƂ炦�āA���邭�y�������������Ɛ�����B�����ɂ͕K�������Ђ炯��v�Ƃ������Ƃ������ł��B
�|�W�e�B�u�ɐ����邱�ƂŁA�l�͐l�����ꂵ�߂�l�ꔪ��������ł���Ƃ����̂ł��B
�����āA���������|�W�e�B�u�V���L���O���x���镶�������{�ɂ͂��邱�ƂɋC�Â����Ă���܂��B
���Ƃ��A�ʎ�S�o�́A����߂ă|�W�e�B�u�ȈӖ���������̂ŁA�|�W�e�B�u�V���L���O���������邽�߂̗L�͂Ȏ�i�ł�����ƌ����܂��B
���������A�ʎ�S�o�������Ă��܂����A����ɂ͂܂������C�Â��܂���ł����B
�����������Ă݂�Ɣ[���ł��܂��B
�u�E���E���Ƃ������A���{�̌ݏ��̂��߂̑g�D���܂��A�Ƃ炦�悤�ɂ���Ă̓|�W�e�B�u�V���L���O���x���Ă����d�g�݂ł��B
�����l����A���{�̊������Օ������܂��ɂ����ł��B
���������u�a�̕����v�́A�܂��ɐl�����C�ɂ�����d�g�݂Ƃ������܂��B
�����ЂƂ́A���������u�a�v�̕����𐢊E�ɍL�߂Ă������ƂŁA���E�ɕ����������炷���Ƃ��ł���Ƃ����C�Â��ł��B
���v�Ԃ��A�������Վ��Ƃ�ό����ƂɎ��g��ł��邱�Ƃ̈Ӗ����悭�킩��܂����B
���v�Ԃ���́A���łɂ������������𐢊E�ɍL���Ă���������i�߂Ă��܂��B
���́A�ŋ߂̓��{�̊ό��Y�Ƃ̐i�ߕ��ɂ͈�a���������Ă��܂������A���v�Ԃ���̂悤�ȗ��O�Ɋ�Â��ēW�J����̂ł���A�ƂĂ��傫�ȈӖ��������Ă��܂��B
�����Ċ������Վ��ƂƊό��Ƃ́A�[���Ȃ����Ă��邱�Ƃɂ��C�Â����Ă��炢�܂����B
�ƂĂ��ǂ݂₷���{�ł��B
�w�瓹�́u�������v�x�Ƃ��������ŁA������ƍ���������l�����邩������܂��A���������l����傫�ȃq���g���A�����ɏ�����Ă��܂��B
�S�̂�����͂��Ђ��ǂ݂��������B
���u������Љ�ۏ���v��ǂ݉����v�i�Љ�ۏᐭ����ҁ@�����̌����Ёj
����A�����̃T�����ŁA�������͉��P����Ă������ŁA�Љ�ۏᐭ��̗�������Ƃ���������������A�����̌���̐^���������ɂ���Q���҂ɂ����Ȃ߂��܂����B
���ꂩ�猩��ƁA�������������s�����傫�����P����Ă���Ƃ����̂ł��B
�������ɂ���������Ɣ��_�͂ł��܂���B
�ł��ǂ����Ɉ�a�������������Ă��܂��B
���������̒��œǂ������A�ƂĂ������ł��郁�b�Z�[�W�̑����{�ł����B
�{���́A���{�����̎Љ�ۏᐭ�������҂ɏœ_�ĂĂ��̖{����ǂ݉����ƂƂ��ɁA
������ɔ������鐶���������������ŁA�����ς��Ă������߂ɂ͎s���ɂ����v���K�v���Ǝ咣���Ă��܂��B
�ƂĂ������ł�����e�ł��B
������Љ�ۏ�Ɍ��炸�A���������S�̂Ɍ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�O�̂��߂Ɍ����A�����s�����傫�����P����Ă���Ƃ�������̐l�̈ӌ��Ɉ٘_�͂Ȃ��̂ł��B
�ǂ��炪���������Ƃ������ł͂Ȃ��A���Ԃ�ǂ�����������Ǝv���܂��B
���̏�ŁA�������A���ʓI�Ȏ��_�������Ȃ��ƌ����▢���͌����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B
�������́A��ґ���́��~�Ŕ��f�������ł����A����������̈٘_���������邱�Ƃ͂悭���邱�Ƃł��B
���̈Ӗ��ŁA�{���͂ł��邾������̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
�u����̐l�v�Ƃ������t�ɂ́A���ׂĂ̍���҂��܂߂Ă��܂��B
�����̎��M�҂�������Љ�ۏ�̖������܂��܂ȋ�̓I�Ȑ������_���o�Ă��܂����A�{���̊�{�p���͑�P�͂́u������Љ�ۏ�ɐ��މۑ�ƒn�拤���Љ�̖{���v�i�œc�p���j�Ŏ�����Ă��܂��B
���Ƃ��A����ȕ��Ɍ��݂̐���͌������ᔻ����Ă��܂��B
���{�����̉��ł͕��Î�`�I�E�ێ��`�I����C�萬�Ɏ��{����Ă��邪�A�Љ�ۏᕪ��ɂ����Ă��A�Ƒ���`�A�R�~���j�e�B�w�̈ˑ������߂鎩���E�����E���ݕ}������{�Ƃ����Љ�ۏ��̂Đ��S�ʓI�ɑł��o����Ă���B
�Ⴆ�A�����J���Ȃɒu���ꂽ�u�w�䂪���E�ۂ��Ɓx�n�拤���Љ�����{���v�i2016�N7���ݒu�j���A�Љ�ۏ��̂Ă̐擱���߂Ă���ƌ�����B
�������A�����{���́A�u�n�拤���Љ�v�̖��̉��ɁA�n��ɐ��N���邠����ۑ�E����n��Z���������E��������{�ɉ������Ă����Ƃ��Ă��邪�A���̕������́A�����������I�ӔC�̂��Ƌ�������Љ�ۏᐧ�x�̊�Ղ�h�邪���d��Ȍ�T��Ƃ����˂Ȃ��B
�u�n�拤���Љ�v�Ƃ����A�����ڎw�����r�W�������������A�u�Љ�ۏ������A�Ď����Ƃ֕ϖe����댯����s��ł���v�Ɛh��Ɏw�E����Ă��܂��B
������ɎQ�������F�l����A�u�w�䂪���E�ۂ��Ɓx�n�拤���Љ�v�̃r�W�����̘b�������ɂ́A�����������Ȃ�����A���{������Ȃ��Ƃ������o�����ƂɈ�a��������܂����B
�{����ǂ�ŁA���̈�a���Ɋm�M�����Ă܂����B
�œc����́A�u���Ƃ��Ď����Ă��邾���ł́A���������S�ɂ͓����ł��Ȃ����Ƃ���A��i�i�`�ԂƂ��āA�u�Z�����݂̊Ď��V�X�e���Ɩ����v���u���\�z�����悤�Ƃ��Ă���B���ꂪ�A�܂������u����ŗבg���x�v�Ƃ��Ắu�n�拤���Љ�v�ł͂Ȃ��낤���v�Ə����Ă��܂����A����قǂ̌������ڂ��K�v�Ȃ̂��ƋC�Â����Ă��炢�܂����B
��a���͕��u���Ă��Ă͂����Ȃ��̂ł��B
��������������̂́A�u���N�����Љ�̌`���Ɏ�����V���ȎY�Ɗ����̑n�o�y�ъ������A�i�����j�����ʂ����䂪���o�ς̐�����}��v���ƂƂ��A�u���N�E��Áv������A�o�ϐ����̓���ƈʒu�Â��Ă���B�l�Ԃ̐����E�����̍������Ȃ�������Y�Ɖ����邱�Ƃ́A���i�Ƃ��Ă̌��N�E��Õ�����w���ł���҂Ƃł��Ȃ��҂Ƃ̊i�����g�傳���A�����̌��N�j��𐄂��i�߂邱�Ƃɂ����Ȃ�Ȃ����A���N�E��Âɂ�����l���v�z�E�ϗ��ς����@�����˂Ȃ��Ƃ��킴��Ȃ��v�Ƃ����w�E�ł��B
�����Ă��̖��́A��T�͂́u����ҕ����u���v�v�Ǝs�ꉻ�E�Y�Ɖ��v(�]���t)�ւƈ����p����܂��B
�����ł̎咣�͎��������ƑO����v���Ă������ƂŁA20�N�قǑO�ɎG���Ȃǂł����������Ƃ�����܂��B
http://cws.c.ooco.jp/siniaronnbunn1.htm
������Ԋ뜜���Ă���̂́A�u�Ďs�ꉻ�v�̗���ł��B
���ی����x�͉��̎Љ�ƌ����Ȃ���A�����s�ꉻ���Ă��܂��܂����B
����ɂ���āA�����́u���P�v���ꂽ��������܂��A����ꂽ���̂��傫���悤�Ɏv���܂��B
���̏͂́A�䂪�ӂ���Ǝv���Ȃ���ǂ݂܂����B
�{���̍Ō�́A�u�s���ɂ����v�̕K�v���v�i�{�c�G�j�ł��B
���͖{���́A���M�҂̂��ЂƂ�ł�����{�c����ɂ����������̂ł����A��t�������{�c����͈�t�����߂Ă܂ŁA�Љ���悭���悤�Ƃ��������Ɏ��g��ł��܂��B
�{�c����́A�u���܍�����̎Љ�ۏ������u�Љ�ۏ��}���Ǝs�ꉻ�E�Y�Ɖ��v�̗�����~�߂邽�߂ɂ́A�s���ɂ����v���s���ł���v�Ə����Ă��܂��B
�{�͓͂ǂ�ł��āA�{�c����̔M���v�����`����Ă��܂��B
�����Ԃ��Ȃ��l�́A���̖{�c����̓{��̏͂����ł����Гǂ�łق����ł��B
���u��{�����Ɋw�ԕ̌o�c�v�i�c���G�i�����Ғ��@���F�ف@2017�j
��{�����̕v�z�́A�_���~�ς̘g���ĕ��L������ɐZ�����A�����܂Ŗ��X�Ƒ��Â��Ă���ƌ����Ă��܂��B
���ۂɁA�a��h��A�L�c�Z�g�A�����K�V���A�y���q�v�ȂǁA�����̌o�ϐl��g�D�ɂ��e����^���Ă��Ă��܂��B
�{���́A�����������{�ɂ�����o�ρE�o�c�v�z�̌��^�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��u�v�z�v������̊�ƌo�c�ɂȂ��Ȃ���A��̓I�����H�I�ɏЉ�Ă��܂��B
�ŋ߂̊�ƕs�ˎ��̕ɐG��邽�тɁA���{�̌o�c���O�͂ǂ��ɍs���Ă��܂����̂��낤���Ǝv�����Ƃ��ẮA�o�c�Ɋւ��l�����ɁA���܂����v�z���w��łق����Ǝv���܂��B
�{���͓�{�����̐��������w�ѕv�z������ƂƂ��ɁA����̊�Ƃ̎��H����v�z��ǂ݉����Ƃ������@�ŁA���_�Ǝ��H����̉��������w��{�����Ɋw�ԁu�v�̌o�c�x����Ă��܂��B
�����̃G�s�\�[�h���ƌo�c�̎��H�Ⴊ��������Љ��Ă���̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
�{���̖`���ɁA����{�ЎВ��̐Y�����ꂳ�u��{�����̐l�Ǝv�z�ƈ�̎��H�v����e���Ă��܂����A�Y������͒��N�A�|��s�̎s���Ƃ��ĕv�z�����H���Ă����l�ł��B
���̓��ʋ@�\��30�łقǂ̏��_�ł����A�v�z�̊T�_�Ƃ��āA�ƂĂ��Ȍ��ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B����ɂ��A�f�g�p�̃_�j�G���E�b�E�C���{�[�f�������́A��{�����������J�[���̂悤�Ȉ̂��l���������ƕ]�����A�V�����{�͑����̍ĔF����K�v�Ƃ��Ă���Ǝ咣���Ă��������ł��B
�Â��āA��1���ł͓�{�����̐������Ɋw�ԂƂ��āA�u��~�ρv�u�����v�u�ΘJ�v�u���x�v�u�����v�Ƃ����A�����̍l�����A����̊�Ƃ̌o�c�ۑ�ł���u�X�e�[�N�z���_�[�E�}�l�W�����g�v�u�R���v���C�A���X�v�u�ڋq�����v�u�]�ƈ������v�u��@�Ǘ��v�Ƃ����������Ƃ̌o�c�ۑ�ɂȂ����ďЉ��܂��B
����ɁA��Q���ł́A��{�����̋����̎��H����Ƃ��āA���c�Lj�Y�A�a��h��A��ؖ{�K�g�A�L�c���g�A���V�ё��Ȃǂ����グ���A����ɈɓߐH�i��i�K�C���[�x���Ȃǂ̕o�c�Ɏ��g��ł����Ƃ��Љ��Ă��܂��B
������ł̐��ʂ̈�Ƃ��āA�o�c�`�F�b�N���X�g���Q�l�ɂȂ�܂��B
�{���ł�����Ă��܂����A�����́A�r�p�����y�n������ɂ́A�܂������ɏZ�ޔ_���́u�S�v�̕������o���_���ƍl���Ă��܂����B
������u�S�c�J���v�ł��B
�ŋ߂̊�Ƃ̕s�ˎ����ɂ��A���̂��Ƃ��v���o���܂��B
��Ƃ����ł͂���܂���B
�����̎v�z����H����w�Ԃ��Ƃ͂�������܂��B
���Б����̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
���u�Ȃ��A�ꗬ�̐l�͂���c���܂��ɂ���̂��H�v�i���^��@����Ɂ@1400�~�j
���̒��Łu�ꗬ�v�ƌ�����l�ɂ͋��ʓ_������B
����́A����c���܂��ɂ��邱�ƁB
���ꂪ�{���̏o���_�ł��B
�{���́u�ւ��l���v�𑗂邽�߂̋Ɉӏ��ł��B
���邢�͐l���Ɂu�������Ɓv���Ăэ��݁A�������l�����邽�߂̎w�쏑�ł��B
����ȑ�w�ɂ��킸�ɁA���������C�ʼn߂����邽�߂̃q���g���ƌ����Ă������ł��傤�B
������Ƃ�������Ă���̂ł͂Ȃ��A�u����c���܁v���h�����Ƃ����ŁA�l���͕ς���Ă���A�Ƃ������b�Z�[�W�̏��ł�
���҂̈��^�炳��́A��Ђ̌o�c�҂ł�����܂��B
�o�c�҂Ƃ��āA�������ɂ��Ă��邱�Ƃ��u����c���܂��h���v���Ƃ������ł��B
����c���܂����ŋ��̐��������c�A�ƈ������͎��̂悤�Ɍ����܂��B
�u����c���܂��h���v���Ƃ́A�킽���̌o�c�҂Ƃ��Ė��������������Ă���܂��B
���̂��߂ɁA���̎d�������Ă���̂��B
���̂��߂ɁA���̉�Ђ����ꂽ�̂��B
�킽���͖������Ƃ��ɁA�K���_�I�Ɏ�����킹�A���⎩�����܂��B
���ꂱ���A�킽���ɂƂ��Ă̏������ɂق��Ȃ�܂���B
����c���܂Ɂu���̍l���͊Ԉ���Ă��܂��v�Ɩ₤���炱���A�킽���͓���傫����邱�ƂȂ��A����܂ŕ���ł���ꂽ�̂��Ǝv���Ă��܂��B
�������ɐ�����w�j��^���Ă���̂́u����c���܁v�Ȃ̂ł��B
�ł͂��́u����c���܁v�Ƃ͂���Ȃ̂��B
�����Č����I�Ȑ�c�������w���Ă���̂ł͂���܂���B
�������͂��������Ă��܂��B
�������u���Ȃ��v�Ƃ������݂́A���Ȃ����g�Ȃ̂ł����A����ŁA���Ȃ������̂��̂ł͂���܂���B
�K���A���Ȃ��ɂȂ����l�̌����p���ł��܂��B
����c���܂��ӎ�����A���Ԑ����u���܁v����g�傳��āA���j�𖡕��ɂ��A����Ɂu�i���v�𖡕��ɂ�����̂ł��B
��c���ɂ���l�́A�i���Ȃ鐢�E���瓾����u�i���́v���l������̂��Ƃ�����ł��傤�B
�u����c���܂��h�����Ɓv�́A���j��F���ɍL���鐶���͂̃p���[�̌���ƂȂ��邱�Ƃƌ����Ă�������������܂���B
�����Ă�������u�i���́v�āA���̂����P�������Ƃ��ł���B
�������́A�u�킽�������͐_�╧�A���邢�͂���c���܂Ƃ����A�����Ȃ��͂ɂ���Ďx�����Ă��܂��v�Ə����Ă��܂����A�x���N�\���̃G�����E�r�^�[�����v���o���܂��B
�ƂĂ����Ղɏ�����Ă��܂����A�����ɍ��߂��Ă���������̎v���́A�ƂĂ��[���ł��B
�����邱�Ƃ̈Ӗ���₢�����Ă���{�ł�����܂��B
�{����ǂ�ŁA�u�ꗬ�Ƃ͉����v�u�����Ƃ͉����v�Ɋւ��Ă��A���Ўv����[�߂Ăق����ł��B
���u�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�v�i�א삠���@�z�n���ف@2015�j

10�N�ȏ�O���u�I�[�v���u�b�N�E�}�l�W�����g�v�Ƃ����{�̖|����o�ł����Ă��炢�܂����B
�I�[�v���u�b�N�Ƃ́A��Ђ̍��������Ј��Ɍ��J���A��ЋƐт��Ј��ɃV�F�A���镶�������낤�Ƃ����l���ł��B
�������ꂪ�����ł���A��Ƃ݂͂�Ȍ��C�ɂȂ邾�낤�Ƃ����v���Ŗ|�܂����B
���͌o�c�w�Ŋw�u���L�ƌo�c�̕����v�Ƃ����l���ɂ����Ƌ^�������Ă��܂����B
���ꂪ��Ђ��������������ő�̗��R�ł͂Ȃ����B��������u�ٗp�v�Ƃ�����l�ԓI�ȊW�����܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����̂ł��B
�����́A�u�n�a�l�v���ʼn�Ђ͕ς��v�Ƃ����������̂ł����A�c�O�Ȃ���̗p����܂���ł����B
�n�a�l�̓I�[�v���u�b�N�E�}�l�W�����g�̗��ł����A�l�a�n(Management Buyout)���܈ӂ����Ă��܂����B
���̌�A10�N�ȏソ���Ă���ł����A���{���[�U�[�̋ߓ�����ɉ�܂����B
�ߓ�����́AManagement Buyout�ǂ��납�AManagement & Employee Buyout�����������o�c�҂ł��B
�������܂������A�n�a�l��|������̎v���͂�݂�����܂���ł����B
��Ƃ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̓������^�t�ɓ����Ă���̂ɁA���������̒��߂������Ă�������ł��B
�Ƃ��낪�A��T�A���́u�I�[�v���u�b�N�E�}�l�W�����g�v��ǂ������ӂ���A�����ɖK�˂Ă��܂����B
�]�ƈ����L���Ƌ���̍א삳��Ə���ł��B
�����Ă��̎��ɂ����������̂��A���́u�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�v�ł��B
�ǂ�ł��āA�u�I�[�v���u�b�N�E�}�l�W�����g�v��A���Ԃƈꏏ�Ɍ����������Ă������̂��Ƃ��v���o���܂����B
�א삳���̎v���ɁA�v���Ԃ�ɐ̂̎v������݂������Ă��܂����B
�Ƃ����悤�Ȃ��ƂŁA�o�ł��ꂽ�̂͂Q�N�O�ł����A�����̐l�ɂ��̖{��ǂ�ł������������āA�����ŏЉ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�Ƃ������t�������Ƃ��Ȃ��������Ȃ��Ȃ��ł��傤�B
�v�͏]�ƈ��݂�Ȃ���Ђ̊��������Ă��āu���������̉�Ёv�u�݂�Ȃ̉�Ёv���Ǝv����悤�ȉ�Ђł��B
�{���ɂ��A���łɉp�Ăł͊m���Ȓ����ɂȂ��Ă���r�W�l�X���f���ŁA�č��ł́A���łɖ��Ԍٗp��10�����u�]�ƈ����劔��v�̃R�[�I�E���h�E�r�W�l�X���Ƃ����܂��B
�����Ă���������Ƃ́A���v���������������āA�������Ј��݂�Ȃ��n�b�s�[�A��Ђ̎������������ƌ����܂��B
����������Ђ����ۂɂ������@���Ă����א삳���������̂ł�����A�ԈႢ����܂���B
�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X���������邽�߂̎O��̐_��́A�u��L�v�u�v���t�B�b�g�E�V�F�A�v�u�I�[�i�[�V�b�v�E�J���`���[�v���ƍא삳��͌����܂��B
�P�ɎЈ������������L��������킯�ł͂���܂���B
���Ɨ��v�i�o����ł����j�����L����A�������݂�Ȃ��u�����̉�Ёv�Ǝv���Ďd���Ɏ��g�ށB
���ꂪ������Ƃł��Ă���A�g�D�́u���������v�Łu���Ȃ₩�v�Ȃ��̂ɂȂ�͂��ł��B
���{���܂Ŏ��������ŏo���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�A�����Ƃ��Ɂu���������̉�Ёv�ł�����A�o����g���̂��T�d�ɂȂ�܂����A���v���グ���т����܂�܂��B
�Ȃɂ����A�o���҂̊�F�����������Ďd��������K�v�͂���܂���B
�Ȃɂ������͎����Ȃ̂ł�����B
�Ǘ��Ȃǂ��Ȃ��Ă��A���ꂱ�������I�ɁA�����Č��ʓI�ɓ����o���ł��傤�B
�ŋ߂̊�Ƃ̂悤�ɁA�Ј��̐��_��Q�ŔY�ނ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
���������_�ł��A��Ɗ����̐��Y���͍��܂肷���A���ʂȃR�X�g���S�����Ȃ��Ȃ�܂��B
�א삳��͍����̊�Ƃœ����l�����ɂ��āA�u�����̐l�ɂƂ��āu�d���v�Ɓu�����킹�v�����т��Ȃ����̂ɂȂ�A�u�������Ɓv�Ɓu���������v�̊Ԃ��������̂ɂȂ��Ă��܂����v�Ə����Ă��܂��B
�����A�����ɂ����A�����̊�Ƃ̍��{�I��肪����悤�Ɏv���܂��B
�������A��Ђ̏o���҂ɂȂ�A�ӎ������g�ݕ����S���ς��ł��傤�B
�炢�����y�����Ȃ邩������܂���B
�d�����y�����Ȃ���A���Y����d���̎������܂�ł��傤�B
�u��Ђ̂��߁v�Ɓu�����̂��߁v�u�Љ�̂��߁v���Ȃ����Ă����A�d���̐��Y����i���͍��܂�͂��ł��B
���̖{��ǂ�ŁA�I�����_�̉�Ђ̂��Ƃ��v���o���܂����B
�I�����_�́A���������u�������v�u���������v��傫���ς��āA�o�ς��Љ�����C�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�d������Ђ̐��x�ɍ��킹��̂ł͂Ȃ��A�����̐����ɍ��킹�āA�Ζ���d�����I�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��܂��B
���̌��ʁA�o�ς����C�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�������ƂɍK���������Ă���l��������Ɛ��Y���͍��܂�ł��傤���A����������œ�����A���ʂȎd���△�ʂȌo��͌�������̂ł��傤�B
�݂�Ȃ��y�����Ȃ�A�g�̂�_���āA��Ђɕ��S�������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�́A�܂��ɂ��������ݏo���Ă����͂��ł��B
�א삳��́A�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�͌�p�҂ɔY�ރI�[�i�[�o�c�҂ɂƂ��ẮA�l���`�ɑ��鎖�ƌp����Ƃ��Ă����ʓI���ƌ����܂��B
���łɂ����������k�ɂ�����Ă��邻���ł��B
�R�[�I�E���h���̐i�ߕ��́A��Ƃɂ���Ĉ���Ă���ƍא삳��͌����܂��B
�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�́u�Ј����I�[�i�[�ɂȂ��Ă��܂��v�Ƃ����A�P�������ȃr�W�l�X���f���ł����A���ۂɂ́A���̃r�W�l�X���f������������̂́A���l�ȉ��l�ς����l�Ԃł��B
�����P�ɁA���{�����Ј��ŃV�F�A��������Ƃ����b�ł͂���܂���B
����𐬌�������̂́A���i����l�����́u�K�b�g�E�t�B�[�����O�v���ƌ����܂��B
����������A�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�͒P�ɘ_�������ł͂Ȃ��A�l�ԓI�v�f���傫�ȈӖ������Ƃ������Ƃł��B
�א삳��́A�u�R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�̓K�b�g�E�t�B�[�����O�ɂ���Ď��������W���郂�f���ł���A�����ɂ��̃��f�����̂���l�ЂƂ�̃K�b�g�E�t�B�[�����O�ɍ�p����v�Ə����Ă��܂��B
������ƒ����ł����A�א삳��̌��t�����p�����Ă��炢�܂��B
�Ј������̓R�[�I�E���h�E�r�W�l�X�E���f���ɐg��Z���āA�u�d���Ƃ͉��Ȃ̂��v�u�����͎d����ʂ��ĉ����������̂��v�u�����킹�Ƃ͉��Ȃ̂��v�Ƃ��������I�Ȏ���ɒ��ʂ���B�l�ɂ���ăK�b�g�E�t�B�[�����O���������ɋ��U������A�ŏ��͂킯���킩��Ȃ��Ǝv���Ă������A����K�b�g�E�t�B�[�����O���N���b�V�F���h���Ă����肷��B�܂��������U���Ȃ��l������B�u���f���v�͐l��I�Ԃ��A�l���u���f���v��I�ԁB
�א삳��̎v�����`����Ă��܂��B
�א삳��͍Ō�ɂ����₢�����܂��B
�{���͂��Ȃ��̃K�b�g�E�t�B�[�����O�ɋ��������낤���B
���ɂ͋����Ă��܂��܂����B
�א삳��̔M����M�ɂ͎��������܂��A�����Ȃɂ��ł��邩���l�������Ǝv���܂��B
�Ȃ��Ȃ�A�������{�ɃR�[�I�E���h�E�r�W�l�X���L�����Ă����A���{�̌o�ς͌��C�ɂȂ�Љ�ɂ��Ί炪�L�����Ă����Ǝv������ł��B
�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X��ς��Ȃ���A��Ƃ͕ς���Ă����Ȃ��B
�����v���Ă��鎄�ɁA�傫�Ȍ��C�����ꂽ�{�ł��B
���Б����̐l�ɓǂ�ł������������{�ł��B
�I�[�i�[�o�c�҂͂����ɂł���肩����܂����A���Ƃ̌o�c�҂����͂��̐��_����w�Ԃ��Ƃ���������܂��B
�����ĎႫ�N�ƉƂ������Ⴍ�Ȃ��N�ƉƂ������A���̋C�ɂȂ�����ɂł�����ł���r�W�l�X���f���ł��B
�߂������ɁA�א삳��ɓ����ŃT���������Ă��炢�����Ǝv���Ă��܂��B
���u�ʎ�S�o
���R��v(���㏑�с@���^��@1000�~)
���^�炳�u�ʎ�S�o�v�̎��R����㈲���܂����B
�������͈ȑO�ɂ�����������̍��{�o�T�́u���o�v�̎��R���������Ă��܂��B
���̎��Ɠ������A�{��������ݏZ�̎ʐ^�ƈ��c�~�v����̎ʐ^�ƈ������̎��R�Ȗ�Ƃ����⑫����b���A�킩��₷���W�J����Ă��܂��B
�������̎��R��Ƃ��̕\�����@�́A��C�́w�ʎ�S�o�錮�x�ɁA���̃x�[�X������ƁA�������͖{�𑗂��Ă��Ă��ꂽ�莆�ɏ�����Ă��܂����B
�w�ʎ�S�o�錮�x�ŁA��C�́u��v���u�C�v�A�u�F�v���u�g�v�ɂ��Ƃ��Đ����Ă��邻���ł��B
�{���ł��A���ꂪ�ƂĂ��킩��₷��������Ă��܂��B
���ɂƂ��Ĉ�ԐV�N�������̂́A�ʎ�S�o�̒��ɏ�����Ă���u�^���v�̑������ł����B
�܂�A�u㹒�㹒��A�g��㹒��A�g���m㹒��A���F�k�d�v�̎��R��ł��B
�^���ł��̂ŁA�܂��ɖ����ʒq�̐��E�ł����A������������͑N�₩�ɓǂ݉����Ă��܂��B
���ɂƂ��ẮA�u�ڂ��炤�낱�v�ł����B
���́A�����A�S�Ȃ̈ʔv�̑O�Ŕʎ�S�o����u���Ă��܂����A�������̉��߂ɂ͂܂������C�Â��܂���ł����B
�{����ʂ��āA�ʎ�S�o�̐^���ɂӂ��ƁA��������������Ă���悤�ɁA�u���͕s�K�ł͂Ȃ��v���Ƃ��[���ł��邩������܂���B
��C�́u�C�v�Ɓu�g�v�̎ʐ^�Ƃ�����g������̐������ƂĂ������͂�����܂��B
���Ȃ݂ɁA�w�ʎ�S�o�@���R��x�̃v�����[�V����������������͂����Ă��܂��B
���Ђ������������B
https://www.youtube.com/watch?v=r00AKzL_YpA&feature=youtu.be
�ƂĂ����ꂢ�ȏ��Ђł��B
�g�߂ɒu���Ă��������ŁA���p������悤�ȋC�����܂��B
���ɊJ���A�S�̕�����������ł��傤�B
���茳�ɒu���P���Ƃ��Ă��E�߂ł��B
���u�d����F�v�i⨎��Y�@�n�N�Ё@1500�~�j
�}�g�R�[�ŕS����炵�����Ă���N�w�҂�⨎��Y����̒Z�ҏ����W�ł��B
�Ȃ��N�w�҂������H�Ǝv���邩������܂��A�������̈�l�ŁA���̂��߂��炭�͊��̏�ɕ��u����Ă��܂����B
�������ӂƋC�ɂȂ��ēǂ݂�������A�Ȃ�����C�ɓǂ�ł��܂��܂����B
�{�̑т����߂ēǂ�A����������Ă��܂����B
�}�g�R�[�ŏA�_���Ă���34�N�B���̊ԁA�S����炵���^���Ă��ꂽ�����ƕ����ɋ�����ꂽ���̂̌����ɂ���āA�_�Ƃ̂��ƁA���̂��ƁA�ߑ�̗��j�A�����ςȂǁA�������̕��͂\���Ă��܂����B�����������͂́A�Ђ�����_���̐��m�����������߂����߁A����̕�����}���Ă��܂��B���̂��߁A�{���㈲���邽�тɒZ�҂̕���������Ă��܂����B���̏����W�́A������܂ŏ����Ă����{�̑}���G�̂悤�Ȃ��̂ł��B
�N�w�҂̑}���G�̂悤�Ȗ{�B
�ƂĂ��[�����܂����B
�����č��x�́A�}���G�ł͂Ȃ��A���͂̂ق���ǂ݂����Ȃ�܂����B
�������A�}���G�����ł����炩�ɑ傫�ȃ��b�Z�[�W���`����Ă��܂��B
�ނ���{�҂́A�}���G�̐������Ȃ̂�������Ȃ��ƁA�u������Ƃ������Ɓv��ǂ�Ŋ����܂����B
����������A���ɂ͑}���G�ɓ����邱�̖{�̂ق����f�R�ʔ��������̂ł��B
�{���ɂ͂T�҂̍�i�����^����Ă��܂��B
���̂�����������ꂼ��ɁA���������������Ă��܂��قǂ́A�傫�ȃ��b�Z�[�W��^���Ă���܂��B
�������A���̐S�𑛂������̂́A�Ō�́u���̏D���v�ł����B
���Ԃ�͎����ǂu������Ƃ������Ɓv�̑}���G�ł��傤�B
�u������Ƃ������Ɓv�ł́A�\�V���[���̌���_������Ɍ���Ă��܂��B
�������ꂪ�Ȃ�������A�l�͐l�ɂȂ��̂��A�Ƃ����̂������̃��b�Z�[�W�̈�ł����A�u���̏D���v�͂��̉�������܂���B
�������A���ɂ͂��܂������ł����Ɂi�����炱���S���������̂ł����j�A�����������܂킵���C�����c�����̂ł��B
�����Ɍ����A����͖₤�Ă͂����Ȃ��₢�Ȃ̂ł��B
�Ȃ��₤�Ă͂����Ȃ��̂��́A�u���̏D���v��ǂ߂Ζ��炩�ł��B
���߂čl����ƁA���̑}���G�͂�͂蕪�ʒm�̂������߂��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�������A�����ɂ����A���҂��_���ł͌��Ȃ����������ʒq�̐��E���f�o����Ă���B
������ƂĂ��ʔ����A�����ɕx��ł���B
���҂������l�����̂��A�v�������炷�Ƃǂ�ǂ�L�����Ă����܂��B
�u���̏D���v�̂Ȃ��ɁA�l�i���h���X���Ƒ��҃i�[�K�Z�[�i�̉�b���łĂ��܂��B
������ƒ����ł������p���܂��B
�w�剤��A���Ȃ��͉��ɂȂ��܂����H�x
�w�킵�͍��N35�ɂȂ�x
�w�������剤��A���Ȃ��͂����Ƃ����Ɛ������Ȃ��قǍ���ł��B���Ȃ��̓��̂͂�������35�ƌ����Ă������̂ł����A���Ȃ��̐S�͐��܂ꂽ�Ƃ��ɂ��Ƃ��Ǝ����Ă������̂ł��A���܂�Ă���̂킸���Ȍo������������̂ł��Ȃ��B�����ߋ�������̑c�悽���̉c�݁A���Ȃ킿�Ƃ��i�[�}�E���[�p�̒��ɒ~�ς���A�`������č��ꂽ���̂Ȃ̂ł��B�i�[�}�E���[�p���Ԏq�̂Ƃ��ɂ��Ȃ��̓��̂ɏh���āA���Ȃ��̐S�����̂ł��B�����Ď������͎����̋Ƃɂ���ăi�[�}�E���[�p�������炩�ł��ς��A��������̐���ɓ`���Ă����܂��B�������Đl�Ԃ̐S�͐��ォ�琢��ւƗ��]���Ă����B�剤��A���́A�i�[�}�E���[�p�̌`���Ƃ��Đl�Ԃ̐S�����ォ�琢��ւƗ��]���Ă������Ƃ�։�Ƃ����̂ł��x�B
�i�[�}�E���[�p�Ƃ́u���t�Ƃ��̑Ώۂł���`������́v�������ł��B
�܂��Ƀ\�V���[���̃V�j�t�B�A���ƃV�j�t�B�G�ł��B
����͖{���ɂ���T�̒Z�҂̈�ł��B
�T�͂��ꂼ��ɑS���Ⴄ�b�ł��B
��������A����̐��������i�����Ӗ��Łj�₢�������悤�ȋC�����܂��B
�l�Ƃ͉����A������Ƃ͉����B
����Ȃ��Ƃ��l�������Ȃ�悤�ȁA��������̃��b�Z�[�W���ǂݎ��܂��B
�Ō�́u���̏D���v�͂Ƃ������A���̂S�҂͂ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
������Ǝ��Ԃ��ł������Ԃɓǂ߂�悤�ȒZ�҂ł��̂ŁA�悩������ǂ�ł��������B
�l����������ƕς�邩������܂���B
�R�����Y���X����̍w��

���u�ċz��̎q�v�i���i�����@���㏑�ف@1600�~�j
�����ȁE�����O�Ȃ̌l�J�ƈ�̏��i��������̐V��ł��B
���i����́u�^���̎q�@�g���\�~�[�v�͈ȑO�����ł��Љ�܂������A�����ɏ��������o�ꂷ��S�[�V�F�a�̗���N������̎���ł��B
���i����͒��N�A��V����a�̎q�ǂ������ƌ𗬂��Ă��Ă��܂����A
���i�����g�̐��E���ǂ�ǂ�L�����Ă���̂��{������ǂݎ��܂��B
���i����́A���[���ł��������Ă��܂����B
���̂��сA�V�����{�������܂����B
�u�ċz��̎q�v�ł��B
��V����a�i�S�[�V�F�a�j�ɂ��Q�N�̖��Ƃ��ꂽ�j�̎q���A�l�H�ċz���t���Ď���ɕ�炵�A����14�ɂȂ�܂��B
�Q������ňӎ��͖R�����A�ċz��̗͂Ő����Ă��܂��B
�Ƃ�����A�ŏd�ǂ̏�Q���ɑ��āA�u�ߎS�v�Ƃ����C���[�W���������˂܂���B
�Ƃ��낪�A�����ɕ����������s���Ă݂�ƁA�ނ͖L���Ȑ��E�̒��ɐ����Ă��܂����B
�{����ǂނƁA����N�͖L���Ȑ��E�ɏZ��ł��邾���ł͂Ȃ��A�܂��̐l������L���ɂ��Ă��邱�Ƃ��`����Ă��܂��B
�����āA���̖{��ǂނƁA���̖L���������������������Ă��炦��悤�ȋC�����܂��B
���i�����̖{���������������ɂȂ����̂́A����N�̕�e���������u�������y�����v�Ƃ����ꌾ�����������ł��B
���̌��t�ɗU�����܂��悤�ɁA�S�N�ԁA���i����͗���N�Ƒ��ƌ𗬂�[�߁A�����ɖL���Ȑ��E�������Ă����̂ł��B
�����ĂЂƂ��[�����đO�ɐi�݂Ȃ���A�����g�̍l�����₢�����Ă����B
���i����̎��E�͂ƂĂ��L���Đ[���A���܂��܂Ȗ�肪�₢������Ă����܂��B
�ǎ҂��܂������̍l���������₢�������͂��ł��B
���҂̕���ɂƂǂ܂炸�ɁA����̐������ɂȂ����Ă����B
����Ȃ�������̃��b�Z�[�W���܂܂ꂽ�G��ł��B
�P�Ȃ��Q���̕���ł͂���܂���B
�{���̎��M�Ɏ��g�݂Ȃ���A���i����͂����Ɓu�l�Ƃ͉����낤�H�v�u�l�Ԃ̑����Ƃ͉����낤���H�v�ƍl���������Ƃ����܂����A
���̂ЂƂ̓������{���ɂ͎�����Ă��܂��B
�����n�b�Ƃ����Ƃ�������������Љ�܂��B
�l�H�ċz������邱�ƂɂȂ�������N���A����ɘA��߂����ǂ����Ɋւ��āA�Ƒ��ɂ͖����͂Ȃ������ƌ����܂��B
�u�a�@�͕a�l��f�鏊�ŁA���Â�����ꏊ�B�����Ă����̂ł���A���̏ꏊ���a�@�ł����͂����Ȃ��v�Ƃ����̂��A��e�̍l���ł����B
���ꂾ���ǂނƌ�����ꂻ���ȋC�����܂����A�����ɂ͕a�@�Ƃ͉����Ƃ����A�����������܂�l���Ă��Ȃ��傫�Ȗ₢����������܂��B
����Ɋւ��Ă͐�T�A�����ł��Љ���u���{�a�@�j�v�̏Љ�L���ł�������ƐG�ꂽ���ł��B
�������́A�a�@�Ƃ͉�������������ƍl�������ׂ������ɂ��Ă��܂��B
�Ȃ�����N�̗��e�͐h���������ł��āA�y�����Ȃ��̂��B
��e�����������Ă��܂��B
�u�i�����悤�ȏ̎q�ǂ���������ĂĂ����j��e���������������E�C�Ƃ����邳���A���ɓ��@���Ă���q�ǂ��̉Ƒ��ɓ`���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���̃o�g�����Ȃ����Ƃ������̖����ł͂Ȃ����v�B
�����ɂ́A�l���Ȃ���Ӗ����A���邢�͐l��������Ӗ����A��������Ǝ�������Ă��܂��B
���ׂĂ̐l�����C�ɂ��郁�b�Z�[�W���A���ɂ͓ǂݎ��܂��B
����ɁA�u�h���v�Ɓu�y�����v�͖���������̂ł͂Ȃ��̂ł��B
������ƃh�L�b�Ƃ���b���o�Ă��܂��B
�d�x�S�g��Q�̒��ł��ЂƂ���Ǐd���A�������ŋꂵ�����ɂȂ��a�̎q�ǂ��ɐڂ�����t�̑̌��k�ł��B
���܂�̑�ς��ɁA���̈�t�́A�u����͂�����ƉƑ��ɂ͐h���B���݂ǂ�ɂȂ��Ă܂œ������Ƃ͂�߂悤�v�ƍl���܂��B
���ꂪ�A�Ƒ��ɂ����҂ɂ��悩��Ǝv�����̂ł��B
��������Ɏ��ÂɎ��g�݂܂����A�Ō�̍Ō�܂ł��̎q�̕a�C�Ɠ������Ƃ͂��Ȃ������B
���̎q���S���Ȃ����Ƃ��A�Ƒ��́u���̎q�����āA�������A�ƂĂ��K����������ł��v�Ɨ܂��ׂȂ���Ԃ₢�������ł��B
��t�́A���̌��t�ɁA�u����������Ɛ������Ăق��������Ƃ����ӂ߂�C�����v�������������ł��B
���e�̐^��ƂƂ��ɁA��t�̋�Y�������܂��B
���y���⑸�����ɂ��Ȃ���ƁA�ƂĂ��d�����𓊂������Ă��܂��B
�K���Ƃ͉����낤���Ƃ����₢���o����܂��B
�K��Ō���n�߂Ė�13�N�ɂȂ鏬�R�Ō�t�̌��t�͍l���������܂��B
�Q�����Љ�܂��B
�u���������l�Ԃ��āA�h���ɂ���Ƃ��A�ꂵ�݂̒��ɂ�����Ƃ����y������O�����̋C�����������āA����ɂ������Đ����Ă�������Ȃ��Ǝv����ł��v
�u����N�͂ƂĂ�������Ă��܂��B������������������A�ŏ��Ɍ���������N�̗��������ɂȂ����Ă���̂��Ɗ����܂��v
�����͂��܂��A���C�Ȃ����̌��t�͎��Ɂu�K���v�Ƃ͉������C�Â����Ă���܂����B
�����Y���ʎx���w�Z�̏��э��F�Z���̖₢�́A�����Ɠ���B
�u�������ɂƂ��ď�Q�҂Ƃ͉��H�@�ƕ�����Ă��������o�Ȃ��B
���Ȃ��ɂƂ��ď�Q�҂��ĉ��ł����H�@�Ɛq�˂Ă������͕Ԃ��Ă��Ȃ��ł��傤�B
�l�X�̐S�̒��ɂ����Q�҂̎p�͂���30�N�̊ԁA�~�܂��Ă��܂��B
����N�̂��ꂳ��́A�����̐l�ɗ���N�̂��Ƃ𗝉����Ăق����Ǝv���Ă���ł��傤�B
�ł́A�������́A��́A����N�̉���������̂��H�@���̂��Ƃ�������Ȃ��B�v
�Љ�������Ƃ͂܂��R�̂悤�ɂ���܂����A�Ō�Ɉ�����A���ɂƂ��Ắu�ڂ���v�������b���Љ�܂��B
���i����́A�����A���펙����Ă邱�Ƃ͓���I�ŁA�ċz���t�����q���P�A���邱�Ƃ͔����I���ƍl���Ă��������ł����A
����́u������v�����݁v�������Ə����Ă��܂��B
�ڂ����͖{����ǂ�łق����̂ł����A���펙�ł��낤�Ə�Q���ł��낤�ƁA�q�ǂ�����Ă�Ƃ������Ƃł́A
�ɂ߂Čʂ̂��Ƃł���A���ꂼ��ɂ����ē���i���邢�͔����j�ł��B
���̂ǂ����Ⴄ�Ƃ����̂��B
�������ɁA���܂ꂽ����̎q�ǂ������݂͂ȒN���̎x�����Ȃ��Ɛ����Ă����Ȃ��B
����A��l�����Ă����ł��傤�B
�������́A��Q���Ƒ��̓�������܂�ɓ��ꎋ���Ă��Ȃ��ł��傤���B
����͂��Ԃ�A������������I�ɐG��Ă��Ȃ�����ł��B
�܂�A���펙�i�ҁj�Ə�Q���i�ҁj�̓���i�����j�����ꂷ���Ă���B
�����ڂ�����������Ɗ������̂́A���펙�Ə�Q�����čl���Ă������Ƃł��B
�q�ǂ��Ƃ���̂́A�y�����Ɍ��܂��Ă��܂��B
�����g�A���{�I�ȕΌ��Ɏ�������Ă���̂ɋC�Â����̂ł��B
����N�̕�e�́A
�u��Q���ɑ���Ό��Ƃ��A�O�o�̍ۂ̐l�ڂƂ��A���g�̋����v�������Ȃ�������Ȃ���{�̌����́A��������ɂ���Ǝv���܂��v�ƌ���Ă��܂��B
�u����̂悤�Ȏq�̑��݂�m��Ȃ��l�����Ԃɂ͑������܂��B��������������G�ꍇ���Ă���A�Ό����Ȃ��Ȃ�Љ�ɋ߂Â��͂��ł��v�B
���i����́A�l�͑����̏ꍇ�A�����Ӗ��ł������Ӗ��ł��A���������ĕ����ĐG�ꂽ���E�͈̔͂̒��Ő����Ă���������Ă����A�Ə����Ă��܂��B
���̒ʂ�ł��B
���������Ɛ��E���L���Ȃ�������܂���B
�{���́A�u����N��Ƃ͏��������ł���B2016�N���I��낤�Ƃ��Ă���B����N��14�̒a�������}�����v�Ƃ������͂ŏI����Ă��܂��B
���̈ꌾ�̂������ŁA�ƂĂ��~��ꂽ�C�����܂��B
�����Ȃ�܂������A������������������܂��B
���Ƃ����ŁA���i����͍�N�N���������͌��s�̒m�I��Q�ғ����{�݂ɒj���N�����A�����̗��p�҂��E�����������ɐG��Ă��܂��B
�����Ă������猩���Ă���A����Љ�̒��ɐ���ł���D���v�z�ւ̌��O�������Ă��܂��B
�������̐S�̉���ɁA�����D���v�z�����a���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ə��i����͖₢�����܂��B
�l�͑��݂��邾���ő���������A�Ə��i����͌����܂��B
���������v���Đ����Ă��܂����A���̍l���ł���Ȃ�Ɋ����͂��Ă��܂��B
�������A���i����A���������ƁA���͒p�������Ȃ���A�^�W�^�W���Ă��܂��܂��B
�{���́A�������̒��ɐ��ލ��ʎv�z�ɑ���J�E���^�[�u���[�ɂȂ邾�낤���B
����������̖{�ɂ��ꂾ���̗͂͂Ȃ���������Ȃ����A�\����M���Ȃ����Ƃɂ͐��E�͉����ς���Ă����Ȃ��B
���͋ɐM���邱�Ƃɂ���B
���i����́u���Ƃ����v�ł��������Ă��܂��B
�����A���i����ɕ���āA�ɂ����M���悤�Ǝv���܂��B
�������l�ł������̐l�ɁA���̖{��ǂ�ł��炦��Ǝv���܂��B
�����ċC�y�ɓǂ߂�{�ł͂Ȃ��̂ł����B
�����{�a�@�j�i���i���@�s���[���Ё@4000�~�j
�R�����O�ɓǂ̂ł����A���Ԃ���ꂸ�ɏЉ�x��Ă��܂��܂����B
���̖{�̒��҂ɂ͖ʎ��͂Ȃ��̂ł����A���̖{���o�ł����s���[���Ђ̍��������Ȃ�͂���ꍞ�{�̂悤�Ȃ̂ŁA�����Ŏ��グ�����Ă��炢�܂����B
��������͌����{������A�������ēǂ܂Ȃ��Ă������ł���ƌ����Ă��ꂽ�̂ł��炭���̏�ɒu���Ă����̂ł����A�ӂƎv�����ēǂ݂�������A���ɖʔ����āA�����Ƃ����ԂɓǂݏI���܂����B
�{�̏Љ�ɁA�u���߂Ă̖{�i�I�ȕa�@�̗��j�v�Ə����Ă���܂������A�܂��ɓ��{�̕a�@�ʎj�ł��B
�������q�́u�Õa�@�v�̘b����n�܂�܂��B
�a�@�o�c�w�̐��Ƃł��钘�҂��A���́A�a�@�j�Ɏ��g�̂��B
���̗��R�₻�̎��g�ݕ��́A�{���̏����ɏڂ�������Ă��܂��B
���̏�����ǂނ����ł��ƂĂ���������̋C�Â������炦�܂��B
�������ʔ��������̂ŁA�����{�����ǂ݂����Ȃ�A�C�Â�����Ǘ����Ă��܂����B
�a�@�́A���̎��̐����̐��A�o�ϊ��A�����A�Љ�v�z�A�l���\���A���a�\���Ƃ������Љ��Ղ̏�ɑ������Ă��邩��A�a�@��_����Ƃ��ɂ͂��̎���̔w�i�ƈ�Ð���̗����Ȃ��ɂ͌��Ȃ��A�ƒ��҂͌����܂��B
�{����ǂނƁA���̂��Ƃ��悭�킩��܂��B
����͓����ɁA�a�@�̂���悤����Љ�����Ă���Ƃ������Ƃł�����܂��B
�����l����ƁA�����̈�Ð��x��a�@�Ƃ������̂𑨂��鎋�삪�L�����Ă��܂��B
�a�@���ǂ��ʒu�Â��邩�ŁA��Â̂���������܂��Ă���B
����ɁA��Â̖�肾���ł͂Ȃ��A�Љ�̖��A�܂莄������l�ЂƂ�̐������̖��ɂ��Ȃ����Ă����B
�{����ǂ�ŁA���̂��ƂɋC�Â��܂����B
�Ȋw�Ɠ��l�A��Â��܂��푈�ɂ���Ĕ��W���Ă��܂����B
�×��A���{�ł͉��f��Â����S�ł������A�������疾���ɂ����Ă̓���ɑΉ�����R���{�݂Ƃ��Ė����ېV��ɕa�@������ꂾ�����̂ł��B
�����āA�e�n�Ή��̋~�}����ł͊�����͖��ɗ����Ȃ����߂ɁA���ǁA���{�̌��I��Ð��x�͊�����w�Ƃ͌��ʂ��Ă��܂����̂ł��B
�������u�q���v��u�\�h��w�v�Ƃ������������܂��B
����Ɋւ��Ă��A���̔w�i�ɁA���Ƃ̌����������傫���e�����Ă��܂��B
����E����A�f�g�p�����{�̈�Â��ǂ��ς��Ă������B
����Ɋւ��Ă��ƂĂ��킩��₷����������Ă��܂��B
���@�������ł����A�f�g�p�͂�������̍K�^����{�l�ɗ^���Ă��ꂽ�C�����܂��B
�f�g�p�ŎЉ�ۏ��S�������N���[�h�E�T���X�����҂̗Տ����s����t�������������ŁA���̓��{�ł́A���a�\�h�A���ÁA�Љ���A�Љ�ۏ�̂S����̃o�����X�ۂ����������ł��o���ꂽ�̂ł��B
���Ƃ̂��߂̐�������Â��琶���̂��߂̕�����Âւƕς�����Ƃ����Ă������ł��傤�B
��ÎY�Ɖ����܂��A���̂������ŏ������݂Ƃǂ܂����Ƃ����Ă�������������܂���B
�����������30�N���ŁA���������܂����B
���������`�ŁA���{�̕a�@�j�ƈ�Ð��x�̕ϑJ���킩��₷���Љ��Ă���̂ł��B
�{����ǂ�ŁA���{�̈�Ð��x�̌����Ă�������ɁA�܂��܂��S�����܂�܂����B
�����g�̕a�@�Ƃ̕t�����������A�����ς��悤�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
�C�y�ɂ����߂ł���悤�Ȗ{�ł͂���܂��A���ɂ͂ƂĂ������ɕx�ޖʔ����{�ł����B
��Ð��x�̊S�̂�����ɂ́A�����߂��܂��B
���u�J��H�c�̐l�X�v�i�L���E�W�q�����@�n�N�Ё@2000�~�j
�n�N�Ђ̑��c���ŋߏo�ł����u�J��H�c�̐l�X�v�Ƃ����{�������Ă��Ă���܂����B
�J��H�c�Ƃ����Ă��킩��ɂ����ł����A�P�\���H�ƒc�n�Ƃ����킩��l�������ł��傤�B
�k���N���A�؍��̊�Ƃ�U�v���Ėk���N�����ɂ������H�ƒc�n�ł��B
��N�A�����̊W��������؍����������グ��Ȃǂ̃j���[�X������Ă��܂������A�����g�͂��̎�����قƂ�ǒm��܂���ł����B
�Ƃ������A�V�������̂܂���Ă��܂����B
�����Ċ؍��̐l�������݂�Ȗ����ɋA���ł����炢���ȂƎv���Ă��܂����B
�P�\���H�ƒc�n���Ƃ�2000�N�Ɏn�܂�A��k�W�̈����ɂ���Ă��܂������]�Ȑ܂��o�Ȃ�����A2016�N2���܂ő����Ă��܂����B
���̖{�́A���̃P�\���H�ƒc�n�œ����Ă����؍��l�̏،��̋L�^�ł��B
�͂��߂́A�؍��̐l���k���N�̐l���A���݂��ɑ�����p�̐������S���炢�Ɏv���Ă��������ł��B
���������ł���Ȃ���A�قȂ鐭���̉��Ō𗬂��Ȃ�50�N�ȏ���߂��������ʁA�S��������l���ɂȂ��Ă��܂��Ă����̂ł��B
�ł�����ǂ��ڂ��Ă������킩��Ȃ������悤�ŁA������Ƃ����������傫�Ȗ��ɂȂ����Ă��������Ƃ��������悤�ł��B
�������A�s�������Ă��������ɂ��݂ɗ������i�݁A���̓s���ŕ��ɒǂ����ꂽ��A���ƍĊJ�ŋv���Ԃ�ɍĉ�����ɂ́A�����I�ȏ�ʂ������������悤�ł��B
���̖{������c����͂��������Ă��܂��B
���E���ɂ͂��܂��܂ȑΗ��╴��������A�����ɏo���������Ȃ���Ԃ������Ă��܂��B���ꂩ�琢�E�́A�����̓G�Ɓu�G�v����̂ł͂Ȃ��A�u�����v������@��͍����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���̃q���g�Ƃ��āA���̊J��H�c�ł̑̌��k�́A�ƂĂ��d�v�Ȏ�����^���Ă����͂��ł��B
�i�����j
���ЁA�����̕����J��H�c�ɂ��Ēm���Ă��������āA���܂œG���Ă����l�X���݂��ɋ��͂������鐢�̒���n�邫�������ƂȂ�A�Ǝv���܂��B
�P�\���H�ƒc�n�ɂ́A�����ɂȂ���傫�ȃq���g������Ƃ����̂ł��B
�u�����v�ւ̓�����́A���ۂɈꏏ�ɉ����Ɏ��g��Łu�����v���邱�Ƃł��B
�����ł͂���܂���B
�{����ǂ߂A���c����̎w�E�ɋ����ł���Ǝv���܂��B
�{����ǂ�ŁA���͎����������ɖk���N���u�����̊�v�Ŕ��f���Ă��Ă������ɋC�Â�����܂����B
���҂͂��������Ă��܂��B
�؍��Љ�́u���R�v�̊T�O�Ɩk���N�Љ�́u���R�v�̊T�O�͈Ⴄ�B
�u�J���v�Ɓu�ٗp�v�A�u�o�ρv�̊T�O���Ⴄ�B
�k���ɂ́u�����v�Ƃ����T�O�͂͂��߂���Ȃ��A�����u������v�Ƃ����T�O������݂̂ł���B
��X�͂��̂��ׂẮu�Ⴂ�v���u�Ⴂ�v�Ƃ��Č����ɁA�u�ԈႢ�v�Ƃ��Ĕے肵�Ă��܂��B
���ǂ��́u�ے�v���~�ς���āu���̓I���m�v�ɔ��W����B
�u�Ⴂ�v���u�ԈႢ�v�ƍl���Ă��܂��B
��������s�K�ȕ��f���͂��܂��Ă����킯�ł��B
�����k���N�ɕ����Ă����C���[�W���A������������������܂���B
���҂́A�u���ݑ��d�v�݂͌���G�����Ȃ����Ƃ��ƌ����܂��B
���͉ʂ����āA�k���N�̎�̐��d���������ŁA�k���N�̂��Ƃ𗝉����悤�Ƃ��Ă����̂��B
�p�������Ȃ���A�����̐��E�̊�Ŕ��f���A�k���N���u�x�ꂽ���v�Ƃ݂Ă���������ے�ł��܂���B
�ނ��낻���Ɏ������̖���������̂ł͂Ȃ����B
���Ƃ��Ύ��̂悤�Șb�ɂ́A���܂̓��{�̕Ǐ�Ŕj����q���g������悤�ȋC�����܂��B
�R�O��̎�҂̑̌��k�B
���{��`�ƃJ�l�ɑ���l�����͂������Ⴂ�܂��ˁB
����Ƃ��u�ǂ����ĕK���ɋ��ׂ������悤�Ƃ���̂ł����v�ƕ����ꂽ���Ƃ�����܂��B
�u�����҂��Ȃ���ΐH�ׂĂ����Ȃ�����Ȃ��ł����v�ƌ�������A�u��X�͂���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă��H�ׂĂ����܂��v�ƌ�����ł��B
����Łu��X�͂����Ƃ�����炵�����邽�߂ɋ����҂����Ƃ��Ă���̂ł��v�ƌ�������A�u�����ł��܂���v�ƌ����Ă��܂����B
���͂�����̎Љ��`�̊T�O���{���ɗ����ł��܂���B
�ł�����ŁA�؍��ł͂���ȂɈꐶ���������Ă���̂Ɏ����̉ƈ�Ȃ��̂ɁA�k���̐l�X�͏��Ȃ��Ƃ�����ȐS�z�͂��Ȃ��Ő����Ă���낤�ȁA�Ǝv����������܂��B
�`�[�����Ƃ��ċΖ������l�̘b�B
������͎Љ��`�Ȃ̂ňꐶ���������Ă��C���Z���e�B�u������܂���B
���������Ɏd�������Ă��A��X�ɐl�������Ȃ����߂ɐ��قł��Ȃ��̂ł��B
���ꂾ����d�����ł��Ȃ��l���ł���l�ɍ��킹��̂ł͂Ȃ��A�ł���l���ł��Ȃ��l�ɍ��킹��悤�ɂȂ�܂��B
����ȏ�Ԃ������Ɛ��Y��������ꍇ���o�Ă��܂��B
��X���]�ސ��Y�͂ɓ��B���悤�Ƃ���A�l�����[���邵������܂���B
��̃��C���ɓ쑤�ł�12�����K�v���Ƃ���A�J��ł�15��������Ƃ����ӂ��ɂł��B
��������Đ��Y����100���ɍ��킹�Ă��܂��B
�ǂ���̔��z���A���������K���ɂ���ł��傤���B
�ނ炩��w�Ԃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤���B
���҂͂���ɑ����̎�ނ��o�����ʂƂ��Ă��������Ă��܂��B
��{�I�ɖk���̐l�X�͓쑤�̐l�X�������l�ɑ��ė�V�������D�ӓI�ŏ������B���p�őP�ǂŐ������B��X�̂悤�ɍ��x�Ȍo�ώЉ�Ő����Ă����l�X�ł͂Ȃ��̂Ōl�I�ȋ����S�͂��܂�Ȃ��B�����W�c�I�ȋ����S�͕����ł͂Ȃ��B�����Ǝ��{�̉��l�T�O���Ȃ̂������ł���B�ނ�̗��ꂩ�猩��Ή�X�쑤�̐l�X�́u���ׂĂ̂��ƂɃJ�l�A�J�l�A�J�l���肱�����{���ɏ�̂Ȃ�����Ȑl�X�v���B
�����Ē��N����Ɋւ��Ă��������Ă��܂��B
�i���N����́j�u���ݑ��d�v����������̂��B�����͈�K��������Ȃ��B�����p�͋��\�ł���A�R�ł���B���܂ő��̓I�Ȗk���N���m�ɂ���ČR���I�ȍГ�̊댯���͂�݂��������Ȃ̂��낤�H�@���ݑ��d�̌������������Γ�k�̕i�i�̂��镽�a����ɉh���Ƃ�������邱�Ƃ��ł���B�{���ɈՂ����ĊȒP���B���ݑ��d���B
�u��k���Λ����Ȃ��畐�͂ŋ������đΌ�����������܂Ŕ��Ɍ��R�Ƒ����Ă��܂��B���̖{�����̂悤�ȗ₽���Η���Ŕj�����]�̎�ƂȂ�A�������Ԃ��Ƃ��ł����炤�ꂵ���ł��v�Ƃ����̂����҂����̊肢�ł��B
�ƂĂ��������܂����B
�P�\������w�Ԃ��Ƃ́A���ɂ���������܂����B
���̖{��ǂނ܂ŁA�k���N�Ƃ���������������͎̂��Ԃ̖�肾�Ǝv���Ă��܂������A�����������犢������͎̂������̎Љ������Ȃ��Ƃ����v��������������ł��܂����B
���E�������L���������������܂��B
���u��Ð��x���v�̔�r�����v�i�Ί_��H�@�t���Ё@5400�~�j
��Ð���ɊS�������Ă���Ί_��H����i�R��������w�y�����j�̔��m�_�����{�ɂȂ��ďo�ł���܂����B
�T���̘A�x�ɓǂ܂��Ă�������̂ł����A���Ԃɒǂ��ďЉ��̂��x��Ă��܂��܂����B
1990�N�ォ��2000�N��ɂ����āA���Đ�i���͂�������A��Â̎������߂Ȃ����Ô���팸����Ƃ����ۑ�Ɏ��g�݂����܂����B
���{���A�͓����ł����B
�{���́A�āE�p�E����3�����́A����������Ð��x���v���A��Â̕W�������w������u�f�ÃK�C�h���C���v���߂��鐭��ɏœ_�������āA��r���͂��Ă��܂��B
�����f�ÃK�C�h���C��������哱��������s�����č��A���哱�̍���ɐ��������ۓI�ɒ��ڂ��W�߂�p���A�f�ÃK�C�h���C������ɍ������܂�֗^�ł��Ȃ����{�Ƃ������A�O�ҎO�l�̂����������A���������Ȃ���A��Ð��x���v�̐��ۂ����߂�v�������o�����ƂƂ��ɁA��Ð���̈Ӗ�������Ă��܂��B
������ꂩ��̕������Ɋւ��鎦����������Ă��܂��B
���m�_���Ƃ����w�p�I�ȓ��e�ł����A���v�̌o�܂���̓I�ɂĂ��˂��ɐ�����Ă��܂��̂ŁA�ǂݕ��Ƃ��ēǂ�ł��ʔ����ł��B
��r�����_�A���邢�͓����_�Ƃ��Ă������ɕx��ł��܂��B
��Â̂悤�ɋZ�p�I�Ȑ�含�������A�s�m�����̍�������̐����͂ǂ��W�J����̂��A�����ɂ��āA����̐��E�����ւ̖���N�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
�ƂĂ������[�������̂́A���Ắu�v���t�F�b�V���i���E�I�[�g�m�~�[�v�Ɠ��{�́u�v���t�F�b�V���i���E�t���[�_���v�̘b�ł��B
�f�ÃK�C�h���C������́A�v���t�F�b�V���i���E�I�[�g�m�~�[���߂����Đ��E�ƍ��Ƃ��Λ����A��啪���������E���K�o�i���X�̃C�j�V�A�e�B�u���Ƃ����Ƃ������Ƃł����A���{�̏ꍇ�́A���炭���{��t��v���t�F�b�V���i���E�t���[�_������Ă����ƒ��҂͌����܂��B
�v���t�F�b�V���i���E�I�[�g�m�~�[�ƃv���t�F�b�V���i���E�t���[�_���B
���͂���܂ł��܂�ӎ��������Ƃ�����܂���ł������A���̎��_�ōl����Ƃ����Ȃ��̂������Ă���悤�ȋC�����܂��B
�Ί_����͂����ŁA�u�F�������́v�Ƃ����T�O�����p���܂��B
�F�������̂́A�����ȂǂŌ��ꂾ�����T�O�ł����A�Ί_����́u�w���X�T�[�r�X�i�g�r�j���������́v����A���ꂪ���ꂩ��̈�ÃK�o�i���X�̃A�N�^�[�Ƃ��ďd�v���ƒ��Ă��܂��B
���Ɛ���̘g�̒��ōl���Ă���Ƃ���ɏ�����a��������܂����A�Ί_����̎��̎w�E�ɂ͋������܂��B
��Âł͂Ȃ��ɂ��Ă��A��͂�Z�p�I�Ȑ�含�������s�m������������������A�Ⴆ�A�G�l���M�[����A����2011�N3��11���ɋN���������{��k�Јȍ~�c�_�����������Ă���A���q�͔��d�̗L����_�_�Ƃ����G�l���M�[����̂悤�Ȑ�����c�_����ۂɂ��A���I�m���₻��������炷�A�N�^�[�̂����A�ǂ̑g�D���邢�͒N��I�����ׂ����������ł͂Ȃ����Ƃ������B������������ߒ����l�@�����ł��A�{�_�Ŏ������g�r���������̂̊T�O�͗L�v�ł���ƍl������B
�{���͂܂��A��Ãp���_�C�����ǂ��ς���Ă��Ă���̂��i���҂͂d�a�l�iEvidence-based medicine�j�ւ̈ڍs����ɒu���Ă��܂����j�A��Â̕W�����Ƃ͉��Ȃ̂��A�Ƃ�������Ð�����Â��̂��̂̂���悤���l����q���g��^���Ă���܂��B
�����Ƃ��A�d�a�l�ɂ��W�����i�f�ÃK�C�h���C������j�̓p���_�C���V�t�g�Ƃ��������A���m�x�[�V�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���͂����������܂̃G�r�f���X�͎{�p���̎��_�ł���A���ꂪ���������m�a�l�inarrative-based medicine�j�Ɉڍs������Ǝv���Ă��܂����A���̐�ɂ�����Ð��x���Ð���̃p���_�C���V�t�g���c�_�����ׂ��ł͂Ȃ����A�ƍl���Ă��܂��B
���������₩�Ɋւ���Ă���F�m�Ǘ\�h�Ɋւ��ẮA�G�r�f���X���������҂̐������P�ɒ��ڂ��Ă��܂��B
���̐ςݏd�˂ŁA�V�����G�r�f���X�̑��������������L�����Ă��Ă���悤�Ɏv���܂����A����͓����G�r�f���X�ƌ����Ă��v�z�i���_�j���Ⴄ�悤�Ɏv���܂��B
����͓����ɁA��t���S�́g������Áh����Ō�t���S�́g�������Áh�ւ̕ϊ��ɂ��Ȃ���ƍl���Ă��܂��B
�����āA�f�ÃK�C�h���C�������ꂪ�哱���邩�Ƃ������ɂ��Ȃ����Ă����܂��B
����������a�����������Ƃ���������܂������A�S�̂Ƃ��ẮA�ƂĂ������ɕx�ށA�[���������e�̖{�ŁA��Ð���ɊS�̂���l�ɂ͂��Гǂ�łق����Ǝv���܂��B
���͈�Âɂ���Ð���ɂ��傫�ȊS�������Ă��܂��B
����́A���̐����������ł͂Ȃ��A�Љ�S�̂ɑ傫�ȉe���������Ă��邩��ł��B
����ɐ��E�����ɂ��Ď��͔ᔻ�I�ł��̂ŁA���̎��_������ƂĂ������[���ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�{����ǂ�ň�ԋ����������̂́A���{�̈�Â͂�͂�u������Áv�Ƃ��������ېV���̈�Ãp���_�C���i�u���������v����j���甲���o���Ȃ��܂܂��Ƃ������Ƃł��B
��ÃK�o�i���X�̓]����������ł͂Ȃ����ƍl���Ă��鎄�ɂƂ��āA���̍l����[�߂�Ƃ����Ӗ��ŁA�ƂĂ��C�Â�����邱�Ƃ̑����{�ł����B
������ƃn�[�h�Ȗ{�ł����A�C���������炨�ǂ݂��������B
���������̃T�����ł��b��ɂł���Ǝv���Ă��܂��B
���u�l���̏C�ߕ��v�i���^��@���{�o�ϐV���o�ŎЁ@1500�~�j
�ŋ߁A�悭�b��ɂȂ�u�I���v�̑���Ɂu�C���v�Ƃ������t���Ă��Ă�����^�炳�A���o�d�q�Łu���C�t�v�i��NIKKEI STYLE�j�ɘA�ڂ��Ă����R�������P�s�{�ɂȂ�܂����B
�������̘A�ڃR�����͑�l�C�ŁA�����̐l�ɓǂ܂ꂽ���ʂł��B
�^�C�g���́u�l���̏C�ߕ��v�B
�u�C�v�͎��̖��O�Ȃ̂ŁA�ǂ܂Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B
�ʂ����Ď��́A������Ɛl�����u�C�߂āv���邩�ǂ����B
�������́A���炭��M���Ă������Ƃ�����܂��B
���M�ĊJ�̍ŏ��̖{�̂P�����u�K���_�v�Ȃ�ʁu�V���_�v�ł����B
�������́A�u�l�͘V����قǖL���ɂȂ�v�Ə����Ă��܂����B
���������A����Љ�̓����ɐϋɓI�ȈӖ��������Ă��܂����̂ŁA�Ⴂ���ォ�炻�������咣���o�Ă������Ƃ͊��}�ł������A������a�����������̂��L�����Ă��܂��B
�V����قǖL���ɂȂ�ɂ́A�V�����Ƃ������̂�����A������x����Љ�̂���������ɂȂ邩��ł��B
�V���͌l�̖��ł����āA�l�̖��ł͂Ȃ��Ƃ����̂��A���̍l���ł����B
���̌�A�������͂�������̎��M���������Ă��܂������A�����������Ŏ��̈�a���͉�������Ă����܂����B
�������̎v�����A���X�Ƌ�̓I�Ɍ��ꂾ��������ł��B
���������̈���ŁA�V����L���ɂȂ���Љ�̎d�g�݂́A�t�ɂǂ�ǂ��Ă��Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��B
�����ł�������A�������̖₢�������ẮA�܂��܂����l�����������Ă���̂ł����B
�������́A�u�P�l�ł������̍���҂̕��X�ɔ������l�����C�߂Ă������������v�ƔO���Ă��܂��B
�{���̓ǎ҂Ƃ��āA����ҁA�������͍�����}������l���ӎ����Ă���悤�Ɏv���܂��B
�ł������ł��傤���B
���͂ނ���A�Ⴂ����̐l�ɂ����A�{����ǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B
���Ԃ�������������v���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�������l�����C�߂�͍̂���ɂȂ��Ă���̘b�ł͂���܂���B
�l�����͂��߂��Ƃ�����A�C�ߕ��͎n�܂��Ă���B
�����g�́A����ɋC�Â��̂����������x�����܂����B
�l���̏C�ߕ��́A�Ⴂ����ɂƂ��Ă���ȃe�[�}�Ȃ̂ł��B
������A�Ⴂ����̐l�ɂ����ǂ�łق����Ǝv���̂ł��B
�������́A�{���́u�͂��߂Ɂv�ł��������Ă��܂��B
�悭�l����A�u�A���v���u�����v���L���Ӗ��ł́u�C���v�ł���Ƃ����������ł��܂��B
�w������̎������C�߂邱�Ƃ��A���ł���A�Ɛg����̎������C�߂邱�Ƃ�����������ł��B
�����āA�l���̏W�听�Ƃ��Ắu�C�������v������܂��B
���Ă̓��{�l�́A�u�C�Ɓv�u�C�{�v�u�C�g�v�u�C�w�v�Ƃ������t�ŏے������u�C�߂�v�Ƃ������Ƃ�[���ӎ����Ă��܂����B
����͈��̊o��ł��B
���A�����̓��{�l�͂��́u�C�߂�v�o���Y��Ă��܂����悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B
�܂����������ł��B
���́u�I���v�ł͂Ȃ��A�������ł��B
�����������_���Ȃ��u�I���v�_�́A���ɂ͂���߂Čl�I�Șb��ł�������܂���B
�������́A�����炱���A�u�I���v�ɑ����āu�C���v�Ƃ������t��I�сA����Ɂu�l���̏C�ߕ��v�ƕ\�������̂��낤�Ǝv���܂��B
�������l�����C�߂�̂́A����҂����̖��ł͂Ȃ��̂ł��B
�����āA�������l�����C�߂Ă���A���̂��ƖL���Ȏ����}���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
�{���ɂ́A�u�L���ɘV����v�����āu�������l�����C�߂�v���߂̃q���g����������܂��B
���Б����̐l�ɓǂ�ł������������Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA���̘b��������Əo�Ă��܂��̂ŁA���������C�p���������̂ł����B
�������́A�u�V���v�͐l�ނɂƂ��ĐV�������l���Ƃ����܂��B
������w�E���Ă���悤�ɁA�u����҂ɂƂ��āu�V���v�́u�����v�ƂȂ��Ă���̂�����v�ł��傤���A�u�V���v���V�������l���Ƃ���A�V���������̒n�����傫���J���܂��B
����ȑ傫�ȃe�[�}�ɂ��A�{���̂S�O�҂̘b��ǂ݂Ȃ���A�v�����߂��点�Ă��炢�܂����B
�����������Ƃ̃q���g���܂��A�{���ɂ͎U��߂��Ă��܂��B
�R�����Y���X�ōw��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4532176182

�������i�{���]�@�n�N�Ё@1800�~�j
����͎��̗F�l�̒����ł͂Ȃ��̂ł����A�ƂĂ�����������e�̖{�s�l�̑��c���炢���������̂ŁA�Љ���Ă��炢�܂��B
����́u�_�C�o�[�V�e�B�����ݏo���V�������w�ɂ̊�Ձv�ł��B
�����w�ɂɂ��Ă͂����m�̕�������ł��傤���A
1974�N�ɒ��쌧�̏��J���ŋ{������Y�������グ���A�Ⴊ�������l�̂��߂̎��Y�{�݂���n�܂��������ł��B
���O�́A�u���͎Љ�v�u���萶���v�u�������Ɓv�u�^�̕��a�Љ�v��ڎw���u���J�����v�B
�Љ���@�l��m�o�n�@�l�Ƃ��āA���܂��܂Ȋ����Ɏ��g��ł��܂����A���Ƒ̂Ƃ��������R�~���j�e�B�ƌ����Ă����ł��傤�B
�z�[���y�[�W�ɂ��A�u�Ɨ�������ڎw������Љ�A�����W�c�A�_�ƉƑ��v�ł��B
�ڂ����́A�����w�ɂ̃z�[���y�[�W���������������B
http://www.kyodogakusya.or.jp/about/plan01.html
�{���́A�{������Y����̒��j�̋{���]���A�݂����炪�k�C���̐V�����ŗ����グ���u�V�������w�Ɂv�ł̂���Ύ��H���ł����A
����͓����ɁA���҂��Ō�Ɋm�M�������Ė������Ă���悤�ɁA���ꂩ��̎Љ�̃��f�����������Ă���Ǝv���܂��B
�������A�����ɂ͎�������l�ЂƂ�̐������͂������ł����A��Ƒg�D�̂�����ɂƂ��Ă������ɕx�m�E�n�E��m�������ӂ�Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA�����m�̕�������Ǝv���܂����A�V�������w�ɂł����Ă���i�`�������`�[�Y�͐������̍��ۏ܂���܂��Ă��āA�r�W�l�X�Ƃ��Ă��������Ă��܂��B
�{�̑т̌��t���A�{���̂��ׂĂ�����Ă��܂��B
����Ȃ��l�ԂȂ�Ă��Ȃ��B
���̂��͋��������A�ō��̃p�t�H�[�}���X������B
�������̂������c��A��C���̂��̂Ă���Љ�͖{���ł͂Ȃ��B
�������A�����{���Ƀn�b�Ƃ�����ꂽ�̂́A���҂̎��̌��t�ł��B
�l�́A�Ⴊ���҂�ア����ɗ��l�͂ނ���ϋɓI�ȈӖ������������݂��Ǝv���̂ł��B
���҂́A����҂Ƃ���Ă���l�X�̒��ɂ����A���̎�����J���킪����Ƃ����̂ł��B
�ƂĂ������ł��܂��B
�����ł����l�͂��Ж{�������ǂ݂��������B�m�M�͂���ɐ[�܂�ł��傤�B
��a����^����������l�����Ж{�������ǂ݂��������B�[�����Ă��炦��Ǝv���܂��B
�����ЂƂA�����S���������̂́A�V�������w�ɂ̎��H�̒ꗬ�ɗ���鎩�R��l�Ԃւ̐[���M���Ə_��ł��B
�{���]����̓A�����J�̃E�B�X�R���V����w�ɗ��w���Ĕ_�w�Ǝ��R�Ȋw���w��ł����l�ł����A
���̋{������A�u���^�T�C�G���X�v�Ƃ��u�V���^�C�i�[�_�@�v�A����ɂ́u�J�^�J���i�v�Ƃ��������t���������܂��B
�����������ْ̈[�ƌ����Ă������̂ł����A����҂͂����Ǝ��H�ɂȂ��Ă���̂ł��B
���̈���ŁC�G�R�c�[���Y���Ƃ��������l�̓����Ƃ���������ƂȂ����Ă����̂ł��B
���́u�����������v�Ɓu���Ȃ₩���v�ɂ́A�������܂��B
�{���]����́A�u�������K���ł���v�Ɗ������鐶�������A��l�ЂƂ肪�����Ăق����Ǝv���A
���̂��߂ɁA�݂�Ȃ��K�������������Ղ����낤�Ƃ��Ă���킯�ł����A�����ŗL���Ȃ̂́A�������̂Ɗւ�邱�Ƃ��Ƃ����܂��B
�����ɂ��A����̒����ɍR���傫�Ȏv�z�������܂��B
�����w�ɂ̑n�Ǝ҂̋{������Y����́A
�u���l�ł���̂Ɉ�v����Ƃ��ɂ������l������l�Ԃ̐����v�Ƃ������t���c���Ă��܂����A
���̎��H�ҋ{���]����́A�S�g�ɂ��낢��ȍ����������l������70�l�ȏ�W�܂��ĕ�炵�Ă��鋤���w�ɐV���_��ł́A
�u�S�̂̂��߂Ɉ�l���a���ɂȂ�̂ł͂Ȃ��A���ꂼ��̌��̖{�������Ȃ���A�����Ȃ��ł���͈͂ŁA��l�ЂƂ肪�����������������Ă����B
����ƑS�̂����炵��������悤�ɂȂ�A�l�̐l�Ԃ̕����L�����Ă����܂��B
�S�̂̒��ő��l�Ȃ��̐l�炵�����ێ����Ă������炱���A���܂������������Ƃ��ɂ��炵�����E������܂��v
�ƌ���Ă��܂��B
����Ƃ͐^�t�ɂ����v����u�_�C�o�[�V�e�B�헪�v�Ɏ��g��ł��錻�݂̑��Ƃ̌o�c�҂ɕ������������t�Ǝ��H�ł��B
�����܂ł�����܂��A�u�S�g�ɂ��낢��ȍ����������l�����v�������Ă���̂��A�������������Ă���u�Љ�v�ł��B
�V�������w�ɂ́A���ɓ���̐��E�ł͂Ȃ����ƂɁA�������͋C�Â��Ȃ�������܂���B
���e���Љ�������炫�肪�Ȃ��قǎ����ɕx�ރG�s�\�[�h���R�ς݂ł��B
����炪���ׂāA�V�������w�ɂ́u��Ձv�ɂȂ����Ă���B
�ǂ�ł��邤���ɁA�ǎ҂��܂��A���̐��E�Ɂu���v���Ă����B
�ƂĂ��ǂ݂₷���{�ł��̂ŁA���Б����̐l�ɓǂ�ł������������Ǝv���܂��B
�����āA�����ł��ł��邱�Ƃ������Ăق����Ǝv���܂��B
���Ԃ�ɂ���āA�������ς���Ă����͂��ł�����B
�R�����Y���X�ōw��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4885032393

���u�V�v������`�̎v�z�i��{���@���Ώ��X�@2400�~�j
���́|�R�[�i�[�ł����т��яЉ�Ă����{������̑O���u�E�X���ɑł����V���Ȏv�z�v�ɂÂ��u�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v�̑�Q�e�ł��B
������`�̍ő�̌��_�͎Љ�N�w�������Ă��Ȃ����Ƃɂ���A���̂��߂ɑS�̎�`�ւ̗��j�̗�����~�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�S�̎�`�ɑł������߂ɂ́A�u�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v�̎��_�����邱�Ƃ��K�v���Ƃ����̂��A�{���̃��b�Z�[�W�ł��B
����܂ł̎�����`�Ɓu�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v���������ꂽ�A�V����������`�������A�S�̎�`�ւƌ��������j�̒�����ς��Ă����Ɛ�{����͍l���Ă��܂��B
��{����͂܂��A����܂ł̎�����`��}���N�X��`�̖��_�����A����炪���ʓI�ɂ͑S�̎�`�ւ̗���ݏo���Ă������Ƃ��킩��₷���������Ă���܂��B
�����āA�l�Ԃ̑������u�����v�Ƃ��A�������牉㈂��Đl���v����u���a�̂��߂̊v���v�▯���`�̔��W�Ȃǂ̘_����Nj����Ă����u�l�Ԃ��N�_�Ƃ����Љ�N�w�v����܂��B
�o���_�ɐ_�⎩�R�@��u���̂ł͂Ȃ��A�l�̎�������_��W�J���Ă���Ƃ���Ƀ|�C���g������܂��B
�l�Ԃ̎������l���Ă����ƁA�u���������̂Ȃ����ҁv���v����鎩�Ȃ̐������ɂ��ǂ���B
�܂�A�l�̎��_�ōl����ƁA�ɂ߂ċ�̓I�ȁu���������̂Ȃ����ҁv�̑��݂������Ă��܂��B
�l�́A���������u���������̂Ȃ����ҁv�̑��݂ɂ���āA�������Ă��邩��ł��B
�����āu���������̂Ȃ����ҁv�̐�����Ɋg�債�Ă����A���̌��t���Ɍ��l�Ƃ��āu�l�Ԃ̑����v�ɂȂ�Ƃ����̂���{����̍l�����ł��B
���ꂪ�A��{����̐l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�̊j�ɂȂ��Ă��܂��B
��������A�����ɂƂ��Ắu���������̂Ȃ����ҁv���u���������̂Ȃ����݁v�Ƃ��Ĉ�����悤�ȎЉ�A���ՓI�ȎЉ�Ƃ��Č��o���Ă���킯�ł��B
�������āA������`�Ɛl�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�Ƃ����邱�Ƃɂ���āA������`�́u�V�v������`�ւƒE�\�z����Ă����܂��B
�Љ�̂�������l�̐��������K�肷��̂ł͂Ȃ��A�l�̐��������Љ�̂�������K�肵�Ă����B
�����������n�Љ�ɂ����āA�{���Œ���Ă���u�V�E������`�v�ɂ͋������܂��B
�{���͂��������v�z�𒊏ۓI�Ɍ���Ă��邾���ł͂���܂���B
��R�͂ł́A���������u�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v�̎��_����A���{�^�S�̎�`�̍l�@���s���܂��B
�����āA�u���{�l�͂��̐푈�ʼn��Ȃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������̂��v����̓I�ɉ𖾂���Ă����܂��B
��������́A�܂��Ɏ����������ꂩ��ǂ������v�z�Ɋ�Â��āA�S�̎�`�̗���ɑł������Ă�������������������Ă��܂��B
�����ȒP�ɓǂ߂�{�ł͂���܂��A���Б����̐l�ɓǂ�ł������������Ǝv���Ă��܂��B
�������Ƃ��Ă͂��������̈٘_������̂ŁA�����ň�x�A��{�T����������Ă��炤�\��ł��B
�S�̂���l�͂��A������������A�ʂɈē��������グ�܂��B
�Ȃ��{���̑�S�͂́A�����̃T�����ł̍u���^�ł��B
���̏͂́A��{���Ȃ��u�V�E������`�v�Ƃ����l���ɂ��ǂ�������̌o�܂�������Ă��āA��{����̐l�����܂߂āA��{�v�z�̑S�̑����Ղł�����e�ɂȂ��Ă��܂��B
�R�����Y���X�ōw��

���u�V���_�v�i���^��@�O�����@5500�~�j
���^�炳�A�u�V���_�v�������グ�܂����B
�������́A�{���𑗂��Ă��Ă����������莆�ɂ��������Ă��܂��B
�������ɂ���A���V�ɂ���A�V���̈Ӗ��Ƃ������̂��ǂ�ǂ�y���Ȃ��Ă���������{�ɂ����āA���Ȃ�̔ߑs���������ď����܂����B
�V���̌y���́A�����I���ނ��̂��̂ł��邩��ł��B
�킽���́A�l�Ԃ͐_�b�ƋV����K�v�Ƃ��Ă���ƍl���܂��B
�Љ�Ɛl�����������݂̂ɂȂ�����A�l�Ԃ̐S�͔ߖ��グ�Ă��܂��ł��傤�B
�������́u�ߑs���v�͂ƂĂ������ł��܂��B
���{�̎Љ�ɂ́A���łɁu�ߖ��グ�Ă���S�v�����ӂ�o���Ă���悤�Ɏv���܂��B
����͌l�̖��ł��邱�Ƃ��z�������A���܂�Љ�̂��̂�傫�������悤�Ƃ��Ă��܂��B
��������������A�V���Ɍ������ŐH���~�߂���̂��B
�������̋V���_�́A�P�Ɍ����̏��ł͂Ȃ��A�Љ�̂�����ւ̑傫�Ȗ���N�̏��Ȃ̂ł��B
�����ɂ��ǂ݂������������̂ł����A
600�y�[�W�Ƃ������̌����Ǝ���Ԃ̍L���������������̌n�I�ȍ\���̖ڎ������āA���������Ђ��ł��܂��܂����B
����͌y���C�����ł͓ǂ݂����Ȃ��ȂƎv���Ȃ���A���炭�p�\�R���̑O�ɒu���Ē��߂邾���ɂ��Ă��܂������A
�悤�₭�ǂދC�ɂȂ��āA�������߂���C�����������ɁA�͂��Ƃɂ������Ə������Ȃ���ǂ݂����܂����B
�������A�e�͂Ƃ����e�̖��x�ƍL����ɁA�����ȒP�ɓǂݐi�߂܂���B
����ɂ����Ɍ��y����Ă���Q�l�������ǂ݂����Ȃ��Ă��܂��̂ł��B
���̂܂܂��ƁA���̃R�[�i�[�ł̏Љ�N���ɂ͂ł��Ȃ��ȂƋC�ɂȂ��Ă����̂ł����A
���܂��܍��T�ǂu�S�̏K���v�Ƃ����A30�N���O�ɃA�����J�ŏo�ł��ꂽ�{�́A���{�łւ̏����ɁA����ȕ��͂�����܂����B
�{�������[���X�A���Ȃ킿�u�S�̏K���v�ɏœ_�����ĂĂ��邱�Ƃ������A
�́u��v�ɏƉ�������̂��A�����J�����̂Ȃ��ɒT���������Ƃ������̂Ƃ������邩������Ȃ��B
�u�V��v�̌���L���Ӗ��ŗp����Ƃ���A�������̓A�����J�l�̐����̋V��I�p�^�[����`���o�����Ƃ����ƌ�����B
�S�̒�ɐ[���������낵���l��`�̂䂦�ɁA�A�����J�l�͎��������͓����I�ɐ����Ă���̂ł����āA
�V��ȂǂɎx�z����Ă͂��Ȃ��ƍl���悤�Ƃ���B
�������A�����͂����ł͂Ȃ��B
���̓_�����A�{���̒��S�I�Ȏ咣�̈�ł���B
�������̃��b�Z�[�W���v���o���܂����B
�u�S�̏K���v�̒��҂̃��o�[�g�E�x���[�́A���̖{�̒��ŁA�A�����J�Љ�̐�s���ɑ傫�Ȍ��O��\�����Ă��܂����A���̊�Ղɂ�����̂��A�������ƒʂ��Ă���̂ł��B
�x���[�́A���������Ă��܂��B
�������̊����̂��ׂĂ͑��҂Ƃ̊W�ɂ����āA�W�c�⌋�Ђ⋤���̂̂Ȃ��ŌJ��L�����Ă���B
�����Ă��������W��W�c�⌋�Ђ⋤���̂͐��x�I�\���ɂ���Ē����Â����A
�����I�ȈӖ��p�^�[���ɂ���ĉ��߂���Ă���B
�܂��ɁA�V��ƋV���B
�������́A�V���ƋV��Ɋւ��Ă��������Ă��܂��B
�V��Ƃ͕��������炵�߂���́A����Ȃ��u�����v�̓��`��ɋ߂����̂ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�V���Ƃ͂������ۉ�������́A�܂蕶���́u�j�v�ɂȂ���̂ƌ����Ă������낤�B
�����āA�莆�ɂ��������Ă��܂����B
�킽���́A�V�����s�����Ƃ͂��Ȃ킿�l�ނ̖{�\�ł���Ɗm�M���Ă��܂��B
�����āA�V���̑��݂������l�ނ̖ŖS��h���ł����ƍl���Ă��܂��B
�����ł��B���������l���Ă��܂��B
�{���̏Љ�ɁA�u�V�����l�ޑ����̂��߂̕������u�ł��邱�Ƃ��𖾂��A
�V���y���̕����Ɍx����炷�A�Ӑg�̏������낵�v�Ƃ���܂����A
�V����V��́A�������������邱�Ƃ̊�Ղ��x���Ă���Ă��܂��B
����́A�u�V���_�v�̖ڎ�������悭�킩��܂��B
���͎��͂܂��悤�₭�V�͂ɂ��ǂ蒅�����Ƃ���ł��B
�ł�����{���̓��e�Љ�͈������̃u���O�ɂ��C���������Ǝv���܂��B
http://d.hatena.ne.jp/shins2m+new/20161101/p2
����ɂ��Ă��A�h���I�Ȗ{�ł��B
�������́A�V���Ɋ֘A�������܂��܂ȕ���̕����⎖��܂��āA�l�ނɂƂ��ċV���Ƃ͉����̒m�����W�听�����̂ł��B
���̋V���G���T�C�N���y�f�B�A�Ƃ������ׂ��{����ʂ��āA�ǎ҂͂���ɂ��܂��܂ȕ���ւƒm�̗����ł���͂��ł��B
�ł�����A�������܂�}�����ɁA�������ƁA��蓹���Ȃ���A�{����ǂݐi�߂悤�Ǝv���܂��B
�݂Ȃ�����A�悩�����為�Ђ��ǂ݂��������B
�����āA�u�V���v�Ƃ������Ƃɂ��Ă̎v����[�߂Ă��炦����ꂵ���ł��B
���Ԃ�A���E�̌������������ς��A���������ς���Ă���͂��ł��B
�ǂ܂Ȃ��ŁA���̏�ɒu���āA���߂Ă��邾���ł��A�S���L���ɂȂ�܂��B
����Ȗ{�ł��B
�R�����Y���X����w��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4335160844

���u�����ɖ������{�l�v�i���^��
vs ���c�T���@�O�܊ف@1200�~�j
�w�����́A�v��Ȃ��x�w�O���x�ȂǂŒm����u���V�s�v�_�ҁv�̓��c�T������ƁA
�w�����͕K�v�I�x�w�i�����x���������u���V�K�v�_�ҁv�̈��^�炳�A
�������ȂƑΒk�Ő^���ʂ���_�����A���ꂩ��̑��V�ɂ������b���������A�ƂĂ��h���I�Ȗ{�ł��B
�Q�l�Ƃ��A�������ōl���Ă���l�ł͂���܂���B
��������A����̖��Ƃ��āA�^���ɂ��̖��Ɏ��g��ł���l�����ł��B
���́A����܂œ��c����̎咣�ɂ́A�����X����C�ɂ����Ȃ��Ă��Ȃ������̂ł����A���̑Βk��ǂ�ŁA
���c���Ȃ������l����悤�ɂȂ������������킩�����悤�ȋC�����܂��B
�����ɁA�������̎v���̗����������[�܂����悤�ȋC�����܂��B
�٘_���Ԃ������Ƃ������Ƃ̑�����A���߂Ċ����܂����B
���ӂ���̐^���Ȏ��g�݂Ɍh�����܂��B
���Ȃ݂ɁA���́A�������Ɠ������A���V���ɑ傫�ȈӋ`�������Ă��܂��B
�����A�ǂ�ł݂Ċ�����̂́A�ӂ���̈ӎ��̑傫�Ȃ���ł��B
���c����́A������q�ϓI�Ɏe��Ȃ���A���̂Ȃ��ł̍œK�������߂悤�Ƃ��Ă��܂��B
�܂�A�S�����݂ɂ���B
����A�������́A�����ᔻ�I�Ɏ~�߁A���Ƃ������ς��Ă������Ƃ����p�������������܂��B
�S�͖����ɂ���ƌ����Ă������ł��傤�B
���Ԏ������낦��ƁA�ӊO�ƈႢ�͏������̂�������܂���B
���_�����Ⴂ�܂��B
���c����͎��҂̎��_�A�������͎c���ꂽ�l�̎��_�ɁA�d�_��u���Ă��܂��B
�������A�Q�l�Ƃ��A���̑o���ւ̎���͂�������Ƃ������ł����B
�����A�����炩�ɈႤ�_������܂��B
���c����́u�����Ă���l������ł���l�ɔ�����̂��Ă��������v�ƌ����A
�������́A�u�����Ă���l�Ԃ͎��҂Ɏx�����Ă���v�ƍl���Ă��邱�Ƃł��B
�����Ƃ�������A���������c�_��[�߂�A�Ȃ����Ă���悤�ȋC�����܂��B
����ɁA�u������v�Ɓu�x������v���A�R�C���̗��\��������܂���B
�Ȃ������������́A�������̌��t���A�S�ɂЂт��܂��B
���̐l�����܂��ɂ���������ł��B
�u�������́A���҂ƂƂ��ɐ����Ă���v�Ƃ������t���A���ɂ͂ƂĂ������ł��܂��B
�����A���c�������悤�ɁA���҂ɔ����Ă���l������ł��傤�B
�Ƃ���ŁA�Βk�̍Ō�ɁA�u���f�v���b��ɂȂ��Ă��܂��B
�������̌��t�ɂ͎������̐������ւ̑傫�ȃ��b�Z�[�W�������܂��̂ŁA������ƒ����ł����A���p�����Ă��炢�܂��B
�u�Q��҂̕��ɖ��f�����������Ȃ��v�Ƃ������R�ʼnƑ�����I�����Ă��܂��B
�u���f�v�͖����Љ�̃L�[���[�h�ł��ˁB���ׂẮA�u���f�v�����������Ȃ������߂ɁA
�l�ԊW���ǂ�ǂ�����A�Љ�̖��Ή����i��ł���悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B�i�����j
�u���f�����������Ȃ��v�Ƃ������t�́A����̓��{�Љ�ɂ�����l�ԓ��m�̊ȁu�Ȃ���v���ے����Ă��܂��B
���́A��������̐l�ɖ��f�������Ȃ��琶���Ă��܂��B
���ꂩ��������ł��傤�B
�������A�����ɂ�������̐l����������u���f�v��������Ă��܂��B
���ꂪ���̐l����L���ɂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�������������������Ă��邹�����A�����̑��V�̂��Ƃ��l�������Ƃ͂���܂���B
�ł��A���̑��V���Ƒ���F�l�m�l�Ɂu���f�v�Ɠ����ɁA�����Ɖ����́u���𗧂��v�ɂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
���������������ł��肽���Ǝv���Ă���̂ł��B
�u�������v���e�[�}�ɂ����b�������ł����A�������̐������⎀���ςɑ傫�Ȏ�����^���Ă����{�ł��̂ŁA���Б����̐l�ɓǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B
�����āA����̐��������A������ƍl���Ă��炤�̂��A�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�R�����Y���X�iamazon)����w��

���u�������z����f��K�C�h�v�i���^��@���㏑�с@1400�~�j
�w�����|���Ȃ��Ȃ�Ǐ��x�����������^�炳�A���x�́A�w�������z����f��K�C�h�x���㈲���܂����B
����́u���Ȃ��̎����ς��ς�鋆�ɂ�50�{�v�B
�u����z���v�u���҂����߂�v�u�߂��݂�����v�u�������v�u������͂�v�Ƃ����A�T�̃e�[�}�ɉ����āA50�{�̉f���i���Љ��Ă��܂��B
�������́A�f��͐l�Ԃ́u�s���ւ̓���v�����ݏo�����Z�p���ƌ����܂��B
�f��́A�u���Ԃ��߂�ɂƂ����|�p�v�ł���A���������̂Ȃ����Ԃ����̂܂܁u�ۑ��v����Ƃ����̂ł��B
�������ɂ��̒ʂ�ł��B
����Ɉ������́A�l�Ԃ̕����̍���ɂ́u���҂Ƃ̌𗬁v�Ƃ����ړI������A�f��́u���҂Ƃ̍ĉ�v�Ƃ����l�ޕ��Ղ̊肢���������郁�f�B�A�ł�����ƌ����܂��B
�u�f��قƂ������A�̓����ɂ����āA�킽�������͗Վ��̌�������悤�Ɏv���܂��v�Ƃ����A�����̂ł��B
�������́A�f��ւ̎v������������܂��B
��i�̈�ЂƂ̏Љ�́A�������̎v�����d�˂Ȃ���A�����ς�₢�����Ă������e�ɂȂ��Ă��܂��B
�ʓǂ���ƌ������́A�f��̃^�C�g�������Ȃ���A�C�����������ɓǂ�ŁA����ɋC�������Ήf�������Ƃ����A�܂��ɃK�C�h�u�b�N�ł��B
50�{�̍�i�̏Љ�̂��ƁA�������́u���Ƃ����v�ŁA����1�{�A�Љ�Ă��܂��B
����́A�i�����l�ḗu���̓��v�ł��B
������w�����������̉f��ł��B
����́A���˓��C�ɂ���A���ݐ��͂������A�����Ă鐅�����ׂ̓�����^��ł��Ȃ�������Ȃ������ȓ��ɏZ�މƑ��̘b�ł��B
���̉Ƒ��̑��q���}�����A���̂��������`����Ă��܂��B
���̂����������āA�������́A���������̂ł��B
�킽���́A����Ȃɑe���ȑ�����m��܂���B
����Ȃɔ߂���������m��܂���B
�����āA����ȂɖL���ȑ�����m��܂���B
�n�������̕n�����v�w�̊Ԃɐ��܂ꂽ���N�́A���e�A��A�搶�A�������Ƃ����A�ނ��������A�܂������ꂽ�A�����́g������тƁh�āA���̐��ɗ������čs���̂ł��B
����قǖL���ȗ�����������ł��傤���B
�����āA���������܂��B
�u���̓��v�́A����Ɍ��܂łɖ��ʂȂ��̂���������������炱���A�l�ԂɂƂ��Ė{���ɕK�v�s���Ȃ��̂�m�邱�Ƃ��ł���̂ł��B
�����āA���̕K�v�s���Ȃ��̂����A���Ƒ����ł����B
�ڂ����͈������̃u���O�����ǂ݂��������B
http://d.hatena.ne.jp/shins2m/20100228/1267364286
�u���̓��v�̏Љ��ʂ��āA�������̎����ς̐^�����`����Ă���悤�ȋC�����܂��B
�f��D���ȕ��́A���ЁA��Ɏ���Ă݂Ă��������B
�R�����Y���X����w��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4774515930

���u�u�_��ƎZ�Ձv�̌o�c�v�i�c���G�i�E��������E�a���r�v�Ғ��@���F�ف@1800�~�j
�ŋ߁A���{�̌o�ς́A�}�l�[���{��`�ɕ���ꂻ���ȏɂȂ��Ă��Ă��܂����A���܂������߂āA�o���ϖ��̗��O�ŁA���{�̎��{��`����Ă��a��h����v���o���K�v������܂��B
�����v���Ă������ɁA�����������A���Ԃƈꏏ�ɂ���Ȗ{���������ƌ����āA�����Ă��Ă��ꂽ�̂��{���ł��B
������A�Ҏ҂ɂ����M�҂ɂ��A���̒m�荇�����܂܂�Ă��܂����B
�����A��������̏��������̂���ǂ܂��Ă�������̂ł����A�ƂĂ��ʔ����A���ǁA�ꋓ�ɑS����ǂ�ł��܂��܂����B
�a��h��ɂ��ẮA���܂����������܂ł��Ȃ��ł��傤���A�������ɂ�������̊�Ƃ̑n�ƂɊւ��A���{�̎��{��`�̕��ƌ���ꂽ�l�ł���A���̒����u�_��ƎZ�Ձv�ł́A��ƌo�c�̗��O�m�ɐ����A�o�c�w�҂̃h���b�J�[�ɂ��傫�ȉe����^�����l�ł��B
���́A15�N�قǑO�ł����A���R�ɁA�a��h��̂�������i�ƌ����Ă����������Ȃ�N��̏����j�ƒm�荇���A���̂��Z�܂��������K�˂������Ƃ�����܂����A������Ȃ��̕���舒B���ɂ͊��������L��������܂��B
���̕��̂��b�����܂�ɖʔ��������̂ŁA�F�l�ɗ���Ŏ�ނ��{�ɂ����Ă��炢���������̂ł����A�������̕s�K�Ȏ���d�Ȃ�A�����ł��܂���ł����B
�Ԃ��Ԃ����c�O�ł����B
�{���̖ʔ����́A���܂��܂ȗ���̐l���A���܂��܂Ȏ��_����A�a��h��̎v�z�Ǝ��H���A�����Ă��邱�Ƃł��B
�ڎ�������A���̑��l���͂킩���Ă��炦��Ǝv���܂����A�͂��ƂɎ��M�҂��Ⴄ�̂ŁA���ꂼ��V�N�ɓǂ߂܂��B
�e�[�}�����邱�ƂȂ���A���M��18�l�́A���ꂼ��́u�a��h��_�v�ɐG����܂��B
���ʊ�e�@�a��h��Ɠ��{���{��`(�a�V��)
�v�����[�O�@����ɐ�����u�_��ƎZ�Ձv�̌o�c
��1�́@�l�ԁu�a��h��v�̑f��Ƃ����내��
��2�́@�a��h��̊w��I��b
��3�́@�a��h��ƐE�Ɨϗ�
��4�́@�a��h��̋���C�m�x�[�V����
��5�́@�a��h��ƃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X
��6�́@�a��h��ƎЉ�v������
��7�́@�a��h��Ɛ_�{�n���E�i���̓m
��8�́@�h���b�J�[�������a��h��̖���
��9�́@���Ƃ����̖{/�������H��c��
��10�́@�����Ƃ����Ɠ����𖾂邭������/�����K�X
��11�́@�Z�Պ��肾���ł͂Ȃ���ƌo�c/IHI
��12�́@�܂��Â���ɐ�����a��h��̗��O/�����}�s�d�S
��13�́@�w�q�����L�x����w�ԃA�f�����X
��14�́@�u�����o�ύ�����v����w�Ԗ��̑f
�G�s���[�O�@���H�Ő������u�_��ƎZ�Ձv�̌o�c�@�`�F�b�N���X�g
�t�@�^�@�a��h��̊֘A�N�\
�`���ɁA�a��h��T��ڎq���̏a�V�������ʊ�e����Ă��܂����A���ꂪ�ƂĂ��ʔ����ł��B
�����ʔ��������̂́A�a��h�ꂪ�悭����Ă����Ƃ����u���{��`�v�ƁA�a��h��͎g�����Ƃ��Ȃ������Ƃ����u���{��`�v�Ɋւ��錾�y�ł��B
���{��`�ɂ́A�u��H��H�̓H���W�܂��đ�͂ɂȂ�v�Ƃ����C���[�W������Əa�V������͏����Ă��܂����A���̗��R�͖{�������ǂ݂��������B
���̏���ȉ��߂ł́A���{��`�͊w�҂̑���Ώە��A���{��`�͌���̐l������ł��B
�u�Ƃ̗́v�Ɓu���̗́v���ʔ����b�ł��B
�u�_��ƎZ�Ձv�Ɓu�_�ꂩ�Z�Ձv�Ƃł͑S������Ă��܂����A��������ʔ����b�������o����Ă��܂��B
�Ō�ɁA���H�Ő������u�_��ƎZ�Ձv�̌o�c�`�F�b�N���X�g�܂ł��Ă��܂��B
��Ƃ̌o�c�����̐l�ł���A���Ў��Ђ̌o�c���`�F�b�N���Ă݂Ă��������B
�͂��ƂɊ������Ă��܂��̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
�a��h��̓��发�Ƃ��Ă��A���E�߂��܂��B
�R�����Y���X�ōw��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4496051974

���u�o�c���@�S�Ɠ��̌o�c�v�i�s��o���@�v�m�o�Ŏ�
1500�~�j
���{�o�c������̎s�삳��̍ŐV�̒���ł��B
�����K�V����{�c�@��Y�̋����A�ߍ]���l�⏤�Ƃ̉ƌP�Ȃǂ�R�����Ȃ���A��ƌo�c�̊j�S���킩��₷���A�����H�I�ɐ����Ȃ���A��ƌo�c�̃��[�_�[�Ƃ��Ắu�S�̂�����v��₢�����Ă���Ă��܂��B
�����̓��{��Ƃ̎�����݂�ɂ��A���߂Ďs�삳��̒���u�o�c���v�A�u�o�c�̐S�Ɠ��v�̑���������܂��B
�ƂĂ��C�y�ɓǂ߂�{�ł��̂ŁA�����̌o�c�����݂̂Ȃ���ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�s�삳�u�o�c���v�����Ɏ��g�܂ꂽ�̂́A���܂������30�N���O�ɂȂ�܂��B
�R��o�c�����������_�ɂ��āA�o�c���t�H�[�������N�����܂����B
���͋��R�ɂ��A���̍ŏ��̃v���O�����ɎQ�������Ă�������̂����ɂȂ�A���̌���ւ�点�Ă��炢�܂������A����̗v���������āA���̃v���O�����͈炿�����܂����B
�������A�s�삳��́A����ɑ傫�ȍ\�z��`���A����̐��E���L���邽�߂ɁA��b�R�A����R�A����R��1200���̍r�s���d�˂܂����B
�{���ɂ́A���̑̌����瓾���A���̃��b�Z�[�W���������܂��B
���{�o�c��������ݗ�20���N���}���܂����B
�s�삳��3�N�Ԃ̎R�̍s���I���Ė߂��Ă������̂��Ƃ��A���܂��N���ɋL���ɂ���܂��B
���ꂩ��20�N�B�s�삳��̊����̏�͑傫���L�����Ă��܂��B
���ꂵ�����Ƃł��B
�s�삳��̎咣�ɂ́A�l���ɂ���A�a���d��A�l�X���K���ɓ������Ƃ������A�o�c�̖{�����Ƃ������b�Z�[�W�����߂��Ă��܂��B
���܂̓��{�̊�Ƃ́A�����Ȃ��Ă��邩�B
�����A���������u�o�c�̖{���v�����낻���ɂ���Ă��邱�Ƃ������A���܂̊�Ƃ̎����ɂȂ����Ă���ƍl���Ă��܂��B
��Ȃ̂́A�o�c�Z�@�ł͂Ȃ��A�o�c���O�ł��B
�o�c�Ɋւ��݂Ȃ���ւ̂��E�߂�1���ł��B
���u�Ј��Q�d�I�l�Ƒg�D��������H�X�g�[���[�v�i����N�Y
���{�o�ϐV���o�Ŏ� 1800�~�j
��N�A���̃R�[�i�[�ŏЉ���u���[�_�[�̌��t���͂��Ȃ�10�̗��R�v�ɑ����A
������Ѓ`�F���W�E�A�[�e�B�X�g��\����N�Y����́u�g�D�J���v�V���[�Y��Q�e�ł��B
�O���Ŏ����ꂽ�A�r�W�����Ɍ����ĉ�Ђ�傫���ς��Ă������߂̎��H��@�u�o�C���f�B���O�E�A�v���[�`�v���A
�ˋ�̊�Ƃ�ɁA���ۂɓW�J���镨��Ƃ��āA�����ɂ܂Ƃߏグ���̂��{���ł��B
����́A�ϊv�̐i���ɉ����ĂT�͂ɕ������A���ꂼ��Ɂu����N�Y�̑g�D�J���m�[�g�v�Ƃ����A��������Ă��܂��B
�Տꊴ���鏬����ǂ݂Ȃ���A���コ��̊J�������g�D�J����@�u�o�C���f�B���O�E�A�v���[�`�v�����H�I�Ɋw�ׂ�Ƃ����d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��B
�o�C���f�B���O�E�A�v���[�`�Ƃ́A�v����Ɂu�g�b�v�_�E���v�Ɓu�{�g���A�b�v�v���u�o�C���f�B���O�v�A �܂�u�����v�������@�ł����A
�ڂ����́u���[�_�[�̌��t���͂��Ȃ�10�̗��R�v�ɑ̌n�I�ɐ�������Ă��܂��B
�����g�A����30�N�ȏ�O�ɂȂ�܂����A�����Ƃ�����ЂŁA
�܂��Ɂu��ƕ����ϊv�v���W�F�N�g�v�Ɏ��g���Ƃ�����܂��B
���̑̌����A���܂�ɑ傫���������߂ɁA���͉�Ђ����߂邱�ƂɂȂ����̂ł����i����̐������̖��ɂԂ������̂ł��j�A
�����̂��Ƃ��܂��܂��Ƒh���Ă���V�[��������܂����B
�܂�Ŏ����̂��Ƃł͂Ȃ����Ǝv����V�[��������܂����B
�����炭���コ����A���������V�[����������̌����Ă���̂ł��傤�B
���ۂɑ̌��������ꂩ�猾���A�����������Ƃ����܂��^�т����Ă���悤�Ɏv���܂������A�{�ɂ͋����ł��܂����B
���コ��͖{����͂��Ă��ꂽ���ɁA�{���ŐV�����u���{�^�̑g�D�J���_�v���N�����������ƁA�b���Ă���܂������A
�����ɁA�u�g�D�J���̃��[�_�[�V�b�v�_�v����肽�������Ɩ{���̂��Ƃ����ŏ����Ă��܂��B
���̖ړI�́A�ʂ���Ă���悤�Ɏv���܂��B
�g�D�J���̃��[�_�[�V�b�v�_�̗v�f����������Ɩ��ߍ��܂�Ă��܂��B
�{���̏����́u�Ј��Q�d�v�́A���コ��̑���ł��B
�����̍Ō�ɎЈ��̌�����o�Ă������t�Ƃ��āA�Ō�ɓo�ꂵ�܂��B
���̊T�O�́A���͎��������̑̌�����l���Ă����T�O�ł��B
���n�����Љ�̊�Ƃɂ����ẮA�o�c�҂ɂƂ��Ă̎Q�d�Ɠ������A�Ј��ɂƂ��Ă��Q�d���K�v�ł��B
�Ј���l�ЂƂ�̗͂������o���A�g�ݍ��킹�Ă�����ł́A�l���N�_�ɂ����Q�d�������ʓI�ł��B
���̎��_�ŁA�{����ǂނ̂������Ǝv���܂��B
����̓W�J�ɂ́A���X�����Տꊴ������A�����[���ǂ߂܂��B
��Ђ̕ϊv�Ɏ��g��ł�����ɂ́A��������̎�����E�C���^���Ă����ł��傤�B
���܂��܂ȃV�[���œo�ꂷ��A�o�c�Ɋւ�����H�I�ȃq���g��v�l��[�߂邽�߂̃L�[���[�h�Ȃǂ��A���H�I�Ȃ��̂������A�ǂސl�̎v�l���h�����Ă����͂��ł��B
�g�D�J���m�[�g�������ɂƂ�ł��܂��B
�����炩������܂��A�ǂݏI����Ċ�����̂́A��R�e���ق����ȂƂ������Ƃł��B
�{���ł́A�t�H�[�}���g�D�ƃC���t�H�[�}���g�D�̑g�ݍ��킹��A��ƕ����Ɗ�ƋƐтƂ̂Ȃ���Ȃǂ��A�b��ɂ���Ă��܂����A
���̂�����̓W�J�́A�܂��܂���葫��Ă͂��Ȃ��C�����܂��B
�����̒��ł��A���ꂪ�����o���Ă���̋�̓I�Ȍ���̕��ꂪ�A���������ǂݑ�����܂��B
���コ��ɂ́A���ЃV���[�Y��R�e�������Ăق����Ǝv���܂��B
�Ƃ���ŁA�{���̎�l���̎p�W��́A���̕ϊv�v���W�F�N�g������������A�Ȃ�����Ђ����߂āA�u�V�����g�D�J���̎��H�̓r�ɂ����v�A�Ə�����Ă��܂��B
���ꂪ�����̌���ɂȂ��Ă��܂��B
������������A���コ��́A���łɑ�R�e����������ŁA���̕z�Ƃ��āA�������������ɂ����̂�������܂���B
���Ȃ݂ɁA�����A��Ђ̊�ƕϊv�v���W�F�N�g���ߖڂ������ɉ�Ђ����߂����Ă��炢�܂����B
���̏ꍇ�́A�v���W�F�N�g��ʂ��Đ��E���L�����Ă��܂��A�u�V�����Љ�ϊv�̎��H�v�ւƐ�������ς��܂����B
�ł�����A�V�����g�D�J���̎��H�Ɍ���������l���̂��̌�ɂ͊S������܂��B
�{�C�Ŋ�ƕϊv�Ɏ��g�l�ł���Ȃ�A���E�͕K���ς���Ă��܂��Ă���͂�������ł��B
�Ō�ɗ]�v�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��܂������A���܂̊�Ƃ̏ɋ^��������Ă���l�ɂ́A���Ђ����߂��܂��B
�����āA���Љ�ЂɐV���������N�����Ăق����Ǝv���܂��B
���{�̊�Ƃ́A�����ƌ��C�ɂȂ��͂��ł�����B
���ǂ݂ɂȂ������̊��z���������������ł��B
�R�����Y���X�ł̍w��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4532320771

���u����-���ꂩ�猩������{�̕��i�v�i���쐳�m�@�����Ё@1500�~�j
���̗F�l���������{�ł͂Ȃ��̂ł����A����l���炢���������{���Љ���Ă��炢�܂��B
�P�����قǑO�ɁA���s�łs����ɂ�����܂����B
�s����́A���q����������őr���Ă��܂��B
�s����́A�����Ȃ�r���Ă��邱�Ƃ������m�ł��B
������l��r�����l�́A�ǂ����ŐS���ʂ��܂��B
���s�w�߂��̋i���X�ʼn�����s����́A�ʂ�ۂɂ��̖{�����ɉ��������̂ł��B
���n�ɍ��Łu�����v�Ə����ꂽ�����̖{���̕\���́A�ǂގ҂Ɋo������߂܂��B
���̂��߂��A���������Ă���P�����߂��A�ǂ߂��ɂ��܂����B
�������߂Ȃ���A�悤�₭�ǂ߂��̂����T�ł����B
�����g���������Ă���Ȃ��ŁA�Ȃ����ǂދC�����܂�܂����B
�ǂ�Ő����z�b�Ƃ��܂����B
�s����̏h�肪�ʂ������C����������ł�����܂����A�{���̓��e�Ƀz�b�Ƃ����̂ł��B
�{���̕���A�u���ꂩ�猩������{�̕��i�v���Ă��˂��ɏ�����Ă�������ł��B
�������猩���邱�Ƃ͂�������̂ł����A���X�ɂ��Ď����Ƃ�������Ȏ����ɁA���̕��i�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ƃ����Ȃ�����܂���B
���҂̐��삳�A���܂��܂ȕ��i�����Ă��Ă��邱�Ƃ��`����Ă��܂��B
�ŏ��̕��ɏo�Ă��鎩���������Z���̎c�������̈ꕔ�����p�����Ă��炢�܂��B
���̐��͔߂��݂Ɗ�т����邩��������B
�U�̔߂��݂ƁA�S�̊�сB
���ꂪ�A���̒��̂��̐��̔䗦�B
�Ȃɂ��Ȃ��B�O
���ꂪ�A���̒��̎��Ƃ����l���B
�U�̔߂��݂ƂS�̊�т��A�N�����Ȃɂ��Ȃ��O�B
���a�Ȏ��́A�O�ցB
���̐��͔߂��݂Ɗ�т����邩��������A�ƌ����Ă����҂��A�Ȃ�������I�̂��B
��������I���Ɍ����A�����Ă���l�����������ł���̂��Ƃ�������C�����܂��B
���������l�⎩������}�����l�̘b���o�Ă��Ă��܂����A�݂�Ȃ��ꂱ���A�ƂĂ��悭�����Ă��邱�Ƃ��������܂��B
���������l�̕������������Ɛ����Ă���B
�Ȃ�Ƃ����傫�Ȗ������I
���삳��́A�u���E�v�Ƃ������ƂłȂ��u�����v�Ƃ������t�ɂ�������Ă��邱�Ƃ����������A�u�w�Z�Ǝ����v�u�E��Ǝ����v�u�@���Ǝ����v�u���_��ÂƎ����v�u�ӔC�Ǝ����v�u����҂Ǝ����v�u���������v�Ƃ��܂��܂Ȍ��ꂩ��u�����v�̖������グ�Ă����܂��B
�l���������邱�ƁA�C�Â�����邱�Ƃ���������܂��B
���܂��܂Ȍ���������A���삳��͂��������Ă��܂��B
�u�����v�͖{�l�ɂ����킩�蓾�Ȃ��A����A������������{�l�ł����C�Â��Ă��Ȃ����G�ȗv�������ݍ����ċN�������Ȏ����Ȃ̂�������Ȃ��B
���������Ӗ��ŁA������ؓ�ł͂����Ȃ����Ƃ͂悭�����ł���B
���������ɁA���݁A���{�ŋN�����Ă���u�����v�̑����ɒʒꂷ��v��������Ƃ��������B
�����Z�����t�ŕ\������A�u�o�ό������ŗD�悷��Љ�v�ł���B
�܂����������ł��B
�u�o�ό������ŗD�悷��Љ�v��ς��Ȃ���A���͉������Ȃ��B
�K�v�Ȃ̂́A���E�h�~��ł͂Ȃ��A��������l�ЂƂ�̐������̌������Ȃ̂ł��B
���삳��́A�q�ǂ���������w�Ԋ�т�D���Ă������Ƃ��w�Z�ł̂����߂ɂȂ����Ă���Ə����Ă��܂��B
��l�������A������т�D���Ă��܂��Ă���B
�w�Ԃ��Ƃ��������Ƃ��A�{����тɒʂ�����̂������̂ɁA���܂₢������X�g���X�̂��Ƃɂ����Ȃ��Ă���B
���������Љ�̂������₢�����K�v������܂��B
�{���̍Ō�����p�����Ă��炢�܂��B
���ꂾ���Љ�L���ɂȂ����ɂ�������炸�A�����̎����҂����݂���Ƃ����������A�������͒������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�u�����v�̍ő�̖��_�́A���́u���ɕ��v�ɂ���̂ł͂Ȃ��B
�u�����v��I������������Ȃ������u���v�A����������A�u�����v��I���������u�Љ�v�ɖ�肪����Ǝv�����炾�B
�u������I���������Љ�v�������Ă���̂́A�������ł��B
���Б����̐l�ɖ{����ǂ�ł��炢�����āA�����ďЉ���Ă��炢�܂����B
�{���������Ă����������s����Ɋ��ӂ��܂��B
�R�����Y���X�ł̍w��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4794969244

���u�q�ǂ���������ɑ���Ȃ��E�C�v�i���c���F�@WAVE�o�Ł@1500�~�j
�����J�[���N���u��\�̕��c���F���A�V���u�q�ǂ���������ɑ���Ȃ��E�C�v�������܂����B
���݂̈��{�����́A���@���Ȃ�������ɂ����\�����~�߂Ȃ���A���������Ȃ������ɁA�������͎q�ǂ���������ɑ��邱�ƂɂȂ邾�낤�ƁA���c����͗J���Ă��܂��B
�����āA�����ł�������A������t��ɂƂ��āA���R�ŕ��a�ȕ�炵���ł��鐭���̐���z�����߂ɓ����o���ׂ����ƍl�����̂ł��B
���ꂪ�A�����{�͏����Ȃ��ƌ����Ă������c���A�Ăі{���o�ł������R�ł��B
���c����́A�����̃T�����̏�A�̈�l�ł�����̂ŁA�������̕��������ł��傤���A�ނ̓r�W�l�X�̂������A�ݖ�Ŗ����`�������ƌ������Ă����l�ł��B
�ꎞ�́A����c���������������J�[���N���u���W�J�A�����������璼�ږ����`�ւ̉\�����Ă��Ă����̂ŁA�ŋߖS���Ȃ����u��R�̔g�v�̒��ҁA�A���r���E�g�t���[�ɂ��S�������ꂽ�l�ł��B
�����g�́A�����J�[���N���u�����グ���Ɏ����ǒ�������Ă������Ƃ�����A���c����̎v���₱��܂ł̎��g�݂͂��Ȃ�킩���Ă��܂��B
�K�������ӌ��͓����ł͂���܂��A���c����̎咣�ɂ͊�{�I�ɂ͋������Ă��܂��B
����A�}篁A�o�łɓ��ݐ����̂́A�����܂ł�����܂��A���݂̎Q�c�@�I���A�����ė��N�̏O�c�@�I�����A���{�̖��������߂邱�ƂɂȂ邾�낤�Ƃ����A���O����ł��B
�{���̕���́u���{�����̓ƍِ������~�߂āA��]�̍��ɁI�v�ƂȂ��Ă��܂��B
���܂܂��ɁA���{�́u�傫�Ȋ�H�v�ɗ����Ă��܂��B
���̎��̃z�[���y�[�W�ł��A�����}�̌��@�����Ăɂ��ẮA������A�����Ă��Ȃ�ڂ������������Ƃ�����܂����A�����}���@�Ăɏ�����Ă�����{�ւ̓��́A���܂����ŕ����Ȃ���A�i�`�X���~�߂��Ȃ������j�[�����[�̓�̕��ɂȂ�ł��傤�B
����ɋC�Â��Ă��炤���߂ɂ��A�{������l�ł������̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���Ă��܂��B
�{���̓��e���o�ŎЂ̃T�C�g������p�����Ă��炢�܂��B
���{�����̓ƍِ����͑���n�߂Ă��܂����B
�{���͂��̋��낵���𖾂炩�ɂ��āA���̂܂܂��Ɠ��{�͂ǂ��Ȃ�̂��������A���������Ȃ����߂ɁA�{���̖����`���Ƃ�z���ɂ͂ǂ�����������Ƃ����Ƃ���܂Œ��������̂ł���B
�L���Ɍ����邱�̐��E�����n�߂Ă��邱�Ƃ�����������m��A���a����邽�߂̍Ō�̐�D���ǂ��g�����B
�\��������{�����Ɏ��~�߂������A�����������S���čK���ȕ�炵���ł��鍑��z�����߂̋�̍������Ă���B
�{���̃|�C���g�́A�����ɏ�����Ă���u���a����邽�߂̍Ō�̐�D�v�A�����āu���̂��߂̋�̍�v�ɂ���܂��B
�ڂ����͖{����ǂ�ł������������̂ł����A���c����͖����u�������쌛���v�ȂǂƒP�������܂���B
�����`�ƕ��a��`����{�ɒu�������@���A���܂̂悤�ɂȂ�������ɂ����̂́A�ǂ����Ɍ��ׂ��������͂����ƌ����̂ł��B
�����āA�u�c������`�v����ɂ��A�u���s�̋c������`�𐳓������ۏ�����{�����@���̂��̂ɂ����ׂ�����v�A�����āA�u���̌��ׂ��A���{�����̌��@�j���U�������v�ƁA���c����͎w�E���܂��B
�ł͂ǂ������炢���̂��B
���̓����͖{���̒��ɏ�����Ă��܂��B
�u��O������v���v�\�z�ł��B
�u����v���̐^�̖ړI�́A���{������|�����Ƃł͂Ȃ��A���i�������A�������������S���čK���ȕ�炵���ł��鐭���̐���z�����Ƃł��v�ƕ��c����͏����Ă��܂��B
�u���{�����@���́u�c������`�v�Ƃ������x�̍��{�I�Ȍ��ׂ��������邱�Ƃ���O������v���̑��̖ړI�A�{���̖����`�����������邱�Ƃ����̖ړI�v�Ȃ̂ł��B
�ڂ����͖{�������ǂ݂��������B
�ƂĂ��ǂ݂₷���{�ł��B
���c����̓Ƒn�I�Ȏ��_���Ă�����܂��B
���Б����̐l�ɖ{����ǂ�ł������������Ǝv���܂��B
���Ȃ݁A�{���̏o�ł��L�O���āA�����ŕ��c������͂ރ~�j�u�����J�t�F�T����������J�×\��ł��B
�����܂��Ă���̂��A7��9���̃~�j�u������7��24���̃T�����ł����A�p���I�ɊJ�Â��Ă����܂��B
����ɗ��T�ڂ������\�ł���Ǝv���܂����A���c����̌����u��O������v���v�Ɍ����Ă̊������n�߂邽�߂ɁA���炭�x��ɂȂ��Ă��������J�[���N���u�������ĊJ���܂��B
�܂�����r���ł����A�����J�[���N���u�̃z�[���y�[�W���ł�����܂��B
http://lincolnclub.net/
�����̐l�ɓ���Ă������������Ǝv���Ă��܂��B
�����ł��{���̔̔������Ă��܂��̂ŁA�����ɗ����琺�������Ă��������B
�R�����Y���X�ł̍w��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4866210184

���u�����͂��߂�����|����̎��R�Ɨ��j�E�����ĕӖ�Áv�i�����C�@�ԓ`�Ё@1500�~�j
��������́A���������L�҂Ȃǂ��o�āA1999�N��艫���w�����Ƃ��ĉ���ɓ]�����܂����B
���݂́A���A�W�A�����̌������̗����E����Z���^�[���Ƃ��āA����̎���M�������Ă��܂��B
��������́A�u�{�y�v�ōs���Ă��鉫��֘A�̕Ɖ��ꌻ�n�ł̕����܂�ɂ��Ⴄ�̂ŁA�����ɑ傫�Ȋ�@��������Ă���悤�Ɏv���܂��B
���X�A�����ɗ��鎞�ɁA����̐V���������Ă��Ă���܂����A�������ɑS���Ⴂ�܂��B
�����G����Ⴆ�A���̑�������ӎ����ς���Ă����ł��傤�B
��������́A���Ԃ̂��Ƃ����O���Ă���̂ł��B
����Ȃ��Ƃ������āA��������́A�����̃T�����ɂ����X�b�����ɗ��Ă����̂ł��B
���̏������A�u����̒u����Ă���v�������ƒm���Ă��炨���Əo�ł����̂��{���ł��B
���ܘb��̕Ӗ�Â̖�����ł͂Ȃ��A����ɂ���悤�ɁA����̎��R�Ɨ��j�Ɋւ��Ă����y����Ă��܂��B
�Ӗ�Â̖��́A���{��������ǂ��l���Ă����̂��̗��j�Ɩ����ł͂���܂���B
��������́A�u���S�N���A���{������ɑ��čs���Ă������Ɓv����������m��Ȃ���Ζ��͌����Ă��Ȃ��ƍl���Ă���悤�ł��B
�������ɖ��̍��͐[���A�������͂��܂�ɉ���̂��Ƃ�m��Ȃ��̂ł��B
��������͂��������܂��B
�u���{������܂ʼnB���ʂ��Ă����R������ł͂Ƃ����ɂ�Ă��܂��A���̉e�������{���ɍL���肻���ȋC�z�v�ł���A���݂̈��{�����́A������뜜���Ă���̂��낤�A�ƁB
���ꌧ�͓��Đ��{�Ɠ����A�Ӗ�ÐV��n���݂�S�͂őj�~���悤�Ƃ��Ă��鉫��̎����`���邱�Ƃ́A���{�̖����ɂƂ��Ă��傫�ȈӖ������B
��������́A���������̃~�b�V�������ƍl���A��N����A�u���A�W�A�����̃j���[�X�}�K�W���v�ɖ��T�A���ꌻ�n�łȂ��Ƃ킩��Ȃ��悤�ȍׂ������Ƃ��܂߂āA�u����m�[�g�v����e���Ă��܂��B
�{���́A�������������܂��ẮA��������������̕ł��B
�P�Ȃ錻��ł͂Ȃ��A�������猩���Ă��鉫��̗��j�⎩�R������Ă��܂��̂ŁA���𗧑̓I�ɑ������܂��B
����ɁA����������Ő������A�����������n�ɏo�����Ă����Ă̕ł��̂ŁA�ƂĂ���̓I�Ȃ̂ł��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���{�ł��̂ŁA���Б����̐l�����ɓǂ�ł������������ł����A�u���Ƃ����v�ɏ����ꂽ�u���̂悤�Șb�v�����A������ƒ����ł����Љ�Ă����܂��B
�����Ŗ��̂悤�Șb������B�������ꂪ�A�����J�̈�̏B�ɂȂ��Ă�����c�B����Ɠ��{�̗���́u��q�v�t�]�A���{�̎��Ăт��āA�������O�̂Ƃ���ɂ͋��͂��Ȃ��A���ꂩ��̂��Ƃ͎����B�ōl����A�Ɛ錾����B�N�����{�Ȃ�����Ă����̂��B�����ő����̏Z�����E���A���S�̂��u�����m�̎̐v�ɂ��������Ă�����̂������B
�A�����J�Ȃ̂�����哝�̂ɂ�������������B�Î�[��n�͂����ɖ��ԍq��@�̏������������B�S���E����l���W�߂�헪��i�߂�B���ۉ�c�A�G�R�c�[���Y���A�}�����X�|�[�c�ȂǂȂǁA�ǂ��������؍݂��Đ���A���C�����\���Ăق����B���̂��߂ɂ̓r�[�`��Ɛ肵�Ă���ČR��n�͓P���B�C�����͂��Ƃ��ƕs�v�B���{�Ƃ��Ŋ�n������������悤�Ȓm���͗��I������B��@�E���@�ɑ��荞�c���̓��V���g���Ń��r�[������W�J���A�A�W�A�E�����m�̊y���Â����簐i����B�����̍��Ǝ�Ȃ��؍��̎��C�����ɗ��Ă��炢�A���������l�ł̂�т���ی�̘b�ł��o�����̂ł͂Ȃ����B
����ɁA�Ɨ�������Ƃ������̘b��������Ă��܂��B
�Ō�ɏ�������͂��������Ă��܂��B
���̖{�������ł�����̌���𗝉�����肪����ƂȂ���ꂵ���B
�Ӗ�Â܂ŏo�����ĉ������悤�Ƃ����l������A�����̎�����łȂɂ���낤�Ƃ���l�����邾�낤�B
��l�ЂƂ�̗͂Ō��݂̈������������A����������������Ɍ��������Ƃ��o����K�����B
����̐l�����͊撣���Ă��܂��B
���������A�����ł��邩�����ꂼ��̒n��ōl���Ă��������Ǝv���܂��B
���̂��߂ɂ��A���Ђ݂Ȃ���ɂ��ǂ�ł������������Ǝv���܂��B
�Ȃ���������A����́A���70�N�̉��ꂩ��̌���̂���ŏ����n�߂����߁A����̕����ʂ̖��͂��قƂ�Ǐ����Ă��Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
�ł����炫���Ƌ߂������ɁA����̕����𒆐S�ɂ�����Q�i���o�ł���邩������܂���B
�R�����Y���X�ł̍w��
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4763407775

���u���k�Ŏa�鎩���}�����ā\���ꂪ�ނ�̖{�����v�i���эN��@�V���{�o�ŎЁ@2016�j
����́A���̒m�荇���̖{�ł͂Ȃ��̂ł����A
���̃R�[�i�[�ł����������Љ���Ă�����Ă���ٌ�m�̑�삳��i���Ƃ����u�ٔ��ɑ�����������v�͂��Гǂ�łق����{�ł��j����͂����{�̏Љ�ł��B
��삳��̑����ɁA�u���̌Â�����̗F�l���{���o���܂����B��Ԑ�ɁA�M�Z�ɑ��点�Ă��炤���Ƃɂ��܂����v�Ə����Ă���܂����B
�����ɍ��߂�ꂽ�Ӗ����A���ɂ͂Ȃ�ƂȂ��킩�������̂ł�����A�����ɓǂ܂��Ă��炢�A�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
���҂̏��т���Ƃ͖ʎ��͂Ȃ��̂ł����A�����Ă��炦��ł��傤�B
���҂̏��т���́A30�N�ȏ�ɂ킽���ĘJ���g���Ŋ���������A
55�œ]�g�A��ƂƂ��ĉ��|�̐��E�ɓ���A
1998�N�ɂ́A��܂��̏���͂��邨���W�c�g�H�[�h��ݗ����܂����B
http://show-kobo.co/index.html
�����2012�N�A�����}���u���h�R�ێ��v�L�������@�������Ă\�����̂ɋ�����@��������A
���@���k�u���ꂪ�A�x����̖{�����v�����������Ƃ��_�@�ɂȂ�A73�ɂ��āA�݂�������u���@�|�l�v�Ƃ��ăf�r���[�����Ƃ����l�ł��B
���̖��k���D�]�ŁA������50������̂ŁA�����Ƒ����̐l�����ɂ��ǂ�ł��炨���Ƃ܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�����́A�����}�����Ă��u�ᔻ������e�Łv�ƍl���������ł����A
�����@�ƂƂ��ɐ��������{�l�̌��@�ɑ���M���v����`���邱�Ƃ�����Ƃ����v���ɂȂ�A
����̔����L�Əd�˂Ȃ���A���̎v�������܂��܂Ȑ���Ŗ��k���Ɋy���������Ă��܂��B
�ǎ҂́A�ƂĂ��y�����ǂ�ł��邤���ɁA
���{�����@�ɍ��܂�Ă���A��l�ЂƂ�̐l�Ԃ��ɂ��闝�O��m��ƂƂ��ɁA
�����}�����Ăɐ���ł���u�ނ�̖{���v�ɋC�Â������Ƃ����킯�ł��B
�܂��ɁA���т��Ӑ}���Ă���u�ʔ����āA������Ղ����@������v�ɂȂ��Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA��܂��̏���͂���H�[�́A
�w�Z�A�o�s�`�A�J���g���A�J�����ɂȂǂ���̈˗��������A
����������3000����A����グ���ڕW�̋g�{���Ƃɋ߂Â��Ă��邻���ł��B
���т���͂��������Ă��܂��B
�g�{���N����500���~�A����ɑ��H�[�͖�499��7000���~�����A���葝�₹�g�{�ɕ��ԂƂ���܂ŗ��܂����B
�u���ƈꑧ���v�Ɗ撣���Ă��܂��B
�Ȃ�قǁA�u���ƈꑧ�v�ł��ˁB
���ɋ����ł��锭�z�ł��B
�{������������̐l�������ǂ�ł����A�����}�ɂ������̖\���j�~���u���ƈꑧ�v�ɂȂ邩������܂���B
�����Ȃ�悤�ɁA���Б����̐l�����ɖ{����ǂ�ł������������Ǝv���܂��B
�z�[���y�[�W�����Ă��炤�Ƃ킩��܂����A���т����͂ǂ��ɂł��o�����āA��܂��̏���͂��Ă����悤�ł��B
�H�[���g�{���Ƃɒǂ������Ƃ��A���Љ������Ă��������B
��������A�u���ƈꑧ�v�ł�����B
���̂܂܂����A�R�����Y���X�i�y�V�j�ł��w���ł��܂��B
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22/detail/4406060081

���u�Z�p�҂̗ϗ������T�Łv�i���{���E����d���@�ۑP�@1800�~�j
�m�o�n�@�l�Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[������\�̐��{�����A�S�����߂Ď��g��ł���Z�p�җϗ��̃e�L�X�g���A��T�łɂȂ�܂����B
����ɉ������A�ƂĂ��킩��₷���{�Ȃ̂ŁA�ǂނ����ōl����͂����Ă��܂��B
���Б����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���Ă��܂��B
�{���̓��e�Ɋւ��ẮA��R�ł̏Љ��ǂ�ł��������B
����́A�����Ɍ��т��ؓ��𖾂炩�ɂ�������ւƂ���Ɉ���i�߁D���e���啝�ɏ[������Ă��Ă��܂��B
�V�������M�w��������Ă��܂��B
��T�łւ̐��{����̎v���Ɩ{���̍\���́A�u�͂��߂Ɂv�ɂƂĂ��킩��₷��������Ă��܂��̂ŁA��������p�����Ă��炢�܂��B
���ʂ̓��{�l���A����̐�����Ɩ��ɂ����Ė��ɂԂ������Ƃ��ǂ����邩�B
�ʏ�A�w���������o���čl����悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����̂��B
�L���̂Ȃ��ɉ������Z�b�g����Ă��āA�\�������ӎ��̂����ɂȂ����B
����Ȃ�A���̎d�g�݂��ȒP�ȁu�C���[�W�v�Ɏ��߂āA���ʂ̐l�Ȃ炾��ł��L���̂Ȃ��ɃZ�b�g�ł��A���ӎ��̂����ɓ����悤�ɂ���Ƃ悢�B
���ꂱ�����A�ϗ����l����o���_�ł���ƁA���{����͍l���Ă��܂��B
�����āA���́u�C���[�W�v���ӎ����Ȃ���A�{���͍\������Ă��܂��B
���́u�C���[�W�v�͖{���̑�4�͂ŋ�̓I�ɐ�������Ă��܂��B
����ɐ��{����́A�G���W�j�A�̐Ӗ��Ƃ��āA�����������Ă��܂��B
�Ȋw�Z�p�Ɏ��g�ގp���ɂ�����邱�Ƃ́A�܂��G���W�j�A���ӔC�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
2011�N�ɓ����{��k�Ђɔ������̂��N���A���̌�A�����s�����Љ���ƂȂ�A
���{�ł��A�Z�p�҂⌤���҂��ϗ���g�ɕt���Ă��邱�Ƃ����R�̑O��Ƃ����悤�ɂȂ����B
�G���W�j�A�́A�G���W�j�A�̗ϗ����A����z���ׂ��ł���B
���̍��̐l�X�ɍL���������悤�ȗϗ����A����z���Ӗ�������D
�܂����������ł��B
����ɋ������āA�����m�o�n�@�l�Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[�����ɎQ�������Ă�����Ă��܂��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���͗��ĂɂȂ��Ă��܂��̂ŁA��Ƃ̃G���W�j�A�̕��ɂ����Гǂ�łق����{�ł��B
������x�[�X�ɂ����Z�p�҃T�����̊J�Â��A�l�������Ǝv���Ă��܂��B
���u�L�Ə��@�}���^���w�L�v�i���Ƃ��[�q�@�������o�Ł@2015�j
����A20�N�Ԃ肭�炢�ɉ�����A���Ƃ��[�q����{�������Ă��܂����B
�u�L�Ə��@�}���^���w�L�v
���Ƃ�����́A�v�����Ƃ����āA��N�A50��ɂ��āA�}���^�ɉp��Z�����w�̂��߃z�[���X�e�C�����̂ł��B
�{���͂��̋L�^�ŁA�I���f�}���h�ł̏o�łł��B
amazon�Ɍf�ڂ���Ă���{���̏Љ�L�������p�����Ă��炢�܂��B
50��̕M�҂́A�Ɛg�ЂƂ��炵�B
�e�������������ƁA�n���C�ɂ���}���^���ɂP�����̉p��Z�����w�ɏo�������B
�z�X�g�z�[���Ŏl�ꔪ�ꂵ�Ȃ��珉�̊C�O������̌����A�w�Z�ł͂��܂��܂ȍ��̊w���ƈꏏ�ɉp����w�B
���{�̉p��w�K�Ƃ̈Ⴂ�A�O���l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̓���A�z�X�g�z�[���̐����̌��A�}���^���̋H�L�ȗ��j��l�X�̗l�q�Ȃǂɂ��ĒԂ�B
���Ƃ�����́A�v���̃��C�^�[�ł���ҏW�҂ł��B
�ł�����{�����A�S�T�ԂƂ����Z�����Ԃɂ��ւ�炸�ɁA�ҏW�҂̎��_�ŁA���x�̍������e�ɂȂ��Ă��܂��B
������A�ƂĂ���̓I�ɏ�����Ă��܂��̂ŁA���ꂩ��z�[���X�e�C����l�ɂƂ��ẮA�ƂĂ��Q�l�ɂȂ�ł��傤�B
�����āA�}���^�̗��j�ƕ��y�Ɛl�X�̐����Ԃ���A�`����Ă��܂��B
���Ȃ݂ɏ����́u�L�Ə��v�́A�S�T�Ԃ̃}���^�����̖����A���Ƃ����ڂɂ����ɂ������Ƃ̏ے��ł��B
�z�[���X�e�C�����Ƃ̂������ɂ��鋳��̏��̉��ŁA�����ߑO�U���ɖڊo�߁A�����J���āA�Ȃ������������ɂ���L�́u���[�����v�ɂ��������邱�Ƃ���A���Ƃ�����̂P�����n�܂��Ă����悤�ł��B
�������A���Ƃ�����͂Ȃ��T�O��ɂȂ��Ă���p��Z�����w�ɏo�������̂��B
���Ƃ����A���̂��Ƃɂ��ď����Ă��邱�Ƃ��A�����������ł����A���p�����Ă��炢�܂��B
�ꕔ�A���͂��ȗ������Ă�����Ă��܂����B
50���߂��ė��e�������������ƁA�ĎG�Ȏ葱������Ƃ̌�ЂÂ��Ȃǂ��S�ďI���A���C�͊��ɏP��ꂽ���Ƃ�����B
�e���q���Ȃ��Ɛg�Ƃ�����ԂɂȂ�A�₵���C�����ɂȂ������Ƃ����邵�A���߂āg�ЂƂ��炵�h�Ƃ�������ɂ��čl�����B
���̂܂܍��Ƃ��Ă������Ƃɕs�������������Ƃ�����B
�������ɂ܂��g�V��h�̏�����{�i�I�Ɏn�߂�ł͂Ȃ��B
���Ƃ����ĎႭ���Ȃ��B
�ǂ̂��炢���N�������c���Ă���̂��͕�����Ȃ��B
��������A�g���ЂƂ肳�܁h������ł��邱�Ƃ����Ă݂悤�ƍl���n�߁A�v�������̂��g���w�h�������B
�c��̐l�����A�����悤�ɗ^����ꂽ�d�������Ȃ��Ă��������ł����̂��Ƃ����v��������A�C�����͂ǂ�ǂw�ւƌX���Ă������B
�������A�C�O�����A�v�X�̊w�Z�ȂǕs�����炯�ŁA�C�������h�ꓮ�����Ƃ����������A�����̃`�����X������ꐶ�ł��Ȃ���������Ȃ��ƁA�v���邱�Ƃ��ł����B
���Ƃ�����̋C�����ƂĂ��悭�`����Ă��܂��B
�u���̂܂܍��Ƃ��Ă������Ƃɕs���v�B
�����悤�Șb���A�Љ�I�Ɋ��Ă���T�O��̐l��������A����܂ł������������Ƃ�����܂��B
���̃e�[�}�ŁA�����ŃT�������J�Â������Ƃ�����܂��B
���̂��Ƃ��v���o���܂����B
�{���̓��e�Ɋւ���Љ�����Ă��܂��A����͂��Гǂ�ł��炤�Ƃ��āA���Ƃ�����̊��������Ƃ��Q�����A���t�ʂ�Љ�Ă����܂��B
�u����ς�A�o�[�`������胊�A���B������܂������������Ƃ��B�v
�u������K���̈Ⴄ�l�����ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ邱�Ƃ͊ȒP����Ȃ��B�v
�Ō�ɂ��Ƃ��������A�u�}���^���w���ʁv�ɂ��Ă��B
����̒Z�����w�ŁA�l���̃��Z�b�g���ł������ǂ����͕�����Ȃ����ǁA�V�������Ƃɒ���ł����̂ŁA������Ƃ������M�ɂ͂Ȃ����B�܂��܂��C�P��I�Ƃ����C�������łĂ����Ǝv���B
����ɁA����Ă����]�����������ꂽ�悤�Ȋ����͂���B
50���N�����Ă���ƁA�ǂ����Ă��ߋ��̌o�����玩���̍l�����Â�ł܂肪���ɂȂ�B
����v�����ă}���^�ɍs�������ƂŁA�����Â肪�ق��ꂽ�悤�ȋC�͂���B
���Ȃ��Ƃ������_��ɂ��Ȃ���Ɗ���������A�}���^���w���ʂ͂������̂��낤�B
���āA�T�O��݂̂Ȃ���B
�������ł����A�C�O�ւ̃z�[���X�e�C�́H
���u���ʂ܂łɂ���Ă�������50�̂��Ɓv�i���^��@�C�[�X�g�E�v���X�@1400�~�j
���N�A�������Ղ̎��_����A�l�̐������⎀���ς��l���Ă��Ă�����^��i���v�ԗf�a�j����̍ŐV��ł��B
����́u�l���̌㔼��������Ȃ����C�t�v�����̂�����v�B
����̂Ȃ��l�����A�����čŊ��̏u�Ԃ𐴁X�����}���邽�߂�50�̃q���g���A���̂T�̕���ɕ����āA���v�Ԃ����g���ӂ�Ă�����̗��G�s�\�[�h�Ȃǂ��܂߂Ȃ���A�ƂĂ���̓I�ɁA��Ă��Ă��܂��B
�E���C�t�T�C�N���Â���ɕK�v��6�̂���
�E���{�Ƃ��Đg�ɂ��Ă�������16�̂���
�E�Ŋ��܂Ŋy���ނ��߂ɂ���Ă�������11�̂���
�E���̒��̂��߂ɂ���Ă�������10�̂���
�E���X�����Ŋ����}���邽�߂ɂ���Ă�������7�̂���
���v�Ԃ���́A���d�����i�������Չ�Ђ̎В��ł�����܂��j�A���낢��ȕ��̍Ŋ��ɗ�������Ƃ������A���̂Ȃ��Ŏ��ɂ���̐l��⑰�̌���̔O�ɐG��邤���ɁA���������v�������Ē�Ă��邱�ƂŁA��l�ł������̕����A����̂Ȃ��l�����A���X�����Ŋ��̏u�Ԃ��}������悤�ɂȂ�Ƃ����v���ŁA�{���������グ�������ł��B
���v�Ԃ���́A�����m���Ă��钆�ł��Ƃтʂ����Ǐ��ƂŁA�u���v�Ɓu���v�Ɋւ���Í������̕�����ǂݍ���ł��܂��B���v�Ԃ���̓��̂Ȃ��ɂ́A�l�ނ̒��N�̒m�����ǂ���������Ă��܂����A���̒m���������ɎU��߂��Ă��܂��B
���������v�Ԃ���́A�{���Łu���ׂ����Ɓv������Ă���̂ł͂���܂���B
�������c���Ȃ��悤�ɁA�u��肽�����Ɓv������悤�ɁA������ӎ������悤�Ƃ�����Ă����Ă���̂ł��B
�{�����ǎ҂ɌĂт����Ă���̂́A���ʂ܂łɂ���Ă����������Ƃ���̓I�ɍl���܂��傤�Ƃ����Ăт����Ȃ̂ł��B
�����āA�������I�ɂ��������Ă����ׂ����Ȃǂƌ����Ă���̂ł͂���܂���B
����������A�݂�Ȃ����Ɩ��������܂��傤�Ƃ������Ƃ�������܂���B
���v�Ԃ���́A���Ƃ����͕̂K�������ł���Ɗm�M���Ă��܂��B
�������A���̖���������ƈӎ������������Ȃ���A�����ɂ͌�����Ȃ��ł��傤�B
������܂��͂T�O�A�����o���Ă݂悤�ƌĂт����Ă���̂ł��B
�{���͂��̃q���g�W�ł��B
�Ō�ɍ��v�Ԃ����g�̂T�O�́u��肽�����Ɓv�i���j���������Ă��܂��B
���o�������Ȃ�悤�Ȃ��̂�����܂����A�{���ŏ����A���Ԃ��̐l�����̂悤�ȓ��e�ɂȂ邾�낤�ȂƎv���邱�Ƃ����������Ă���܂��B
�����āA���������������Ă݂悤���Ƃ����C�ɂȂ�܂��B
�܂��ŏ��͂P�ł������ł��傤���A�����o�����������Ă��B
�����āA�����ł��C�Â��Ȃ����������ɋC�Â���������܂���B
�����v���ƁA����͍ŋߘb��̃G���f�B���O�m�[�g���̂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂɋC�Â��ł��傤�B
�Ƃ���ŁA�{���ɂ͂Ȃ�Ǝ����o�ꂵ�܂��B
�T�O���ڂ̈���u��ɖS���Ȃ�����Ȑl�Ɏ莆�������v�Ȃ̂ł����A�����ɏo�Ă���̂��A�Ȃ�S�����Ĉȗ��A�������������Ă����u���O�u�ߎq�ւ̔҉́v�Ȃ̂ł��B
���̂��Ƃ��Љ�Ă��ꂽ��A���v�Ԃ���͂�����Ă��Ă��܂��B
�u�킽���́A������l��z���ĖS�����ւ̎莆�������Ƃ������Ƃ��Ă��܂��B�v
�܂�����Ȋ����ŁA�T�O�̃q���g���������Ă���̂ł��B
�Y��Ă��������ɏo�������ɂȂ邩������܂���B
���̖{����A�����Ȃ��Ƃ��ł������ȋC�����܂��B
�R�����Y���X����w���i�������N���b�N�j

���u���P�̋}���v�i�`���K�v�@���{�o�c����������o�ŋǁ@2012�j
���u���傱���Ɖ��P�v�i�`���K�v�@�o�c�A�o�Ł@2012�j
����́A�ŋ߁A�m�荇�����`������̂Q���̖{���Љ�܂��B
��Ƃœ����l�ɂ͂����ɂł��𗧂{�ł����A���ꂾ���łȂ��A�������̐������ɂ����Ă��A�ƂĂ������ɕx�ރ��b�Z�[�W���܂܂�Ă��܂��B
�Љ��C�ɂȂ����̂́A�u������Ƃ��������ȉ��P����������Ɛi�߂Ă����ƑS�̂��傫���ς���Ă�����ł���v�Ƃ����`������̌��t�ɁA�ƂĂ�������������ł��B
��肩���߂̎Ԓ��Ŋ`������Ƙb���Ă������ł����B
����Ɋ`�����u���傱����v�Ƃ������t���g�����̂ɂ��������Ђ���܂����B
�u���傱����v���ĂȂ낤�A�Ǝv�����̂ł��B
�`������́A���N�ɂ킽��A�S���̍H�ꌻ����w�����Ă������P�R���T���^���g�ł��B
�Ƃ���������ɒ��ڍs���̂���D���̂悤�ł��B
������������������������Ƃ̈�ł��B
���̐M���́A�u����ɂ�����������v�ł��̂ŁB
�`������́u���P�v���A�u�P�Ȃ��ƌ������グ��A�C�f�A��A���v��P�o���邽�߂̍�������v�ł͂Ȃ��A�u��БS�̂̕�������̎���ς��Ă����l������v�z�����v�Ƒ����Ă��܂��B
���́A���P�Ɖ��v���A�Ƃ�����Εʎ����̂��̂Ƒ����Ă��܂������A�`������͂�����Ȃ��đ����A���P���ʖ��̉����ɂƂǂ߂đ����Ȃ��̂ł��B
���̈Ӗ��́A�ƂĂ��[���傫���ł��B
�ق��̐l���������t������Ă����̐S�ɂ͋����Ȃ������Ǝv���܂����A���̘b�ɂȂ�O�̊`������Ƃ̘b���A���̐[���Ӗ��ɋC�Â����Ă��ꂽ�̂ł��B
���̎�̖{�����̃R�[�i�[�ŏЉ�邱�Ƃ͂߂��炵���̂ł����A�Q���̖{��ǂ�ŁA�`������̒��N�̎��H�I�N�w�̌����̂悤�Ɋ����āA�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
��Ƃ̌o�c�Ƃ͊W�Ȃ��l�ɂ��A������m�b��^���Ă����{�Ȃ̂ł��B
���e�������Љ�܂��B
�u���P�̋}���v�́A�`������̑̌��m����́u101�̉��P�̋}���v���A���ɂ킩��₷����̓I�E���H�I�ɏ�����Ă��܂��B
�u�{���Ɏ����̊�Ō������ƂƁA�����łȂ����Ƃ���ʂ���v�Ƃ��u�l�s���Ǝ�s���ɕ����čl����v�Ƃ��A�u�@�B�͐��i�����邪�A�l�̎�͉��l������v�A�u���m���̂Ă�ƃ`�G���o��v�ȂǁA�����Ă������炫�肪����܂��A�����u�Ȃ�قǁv�Ǝv�������̂�������Љ�܂��B
����́u�������s�͏�������B�ォ��l�������Ɛ��s������v�Ƃ������Ƃł��B
����͎����Ȃ�ƂȂ��v���Ă������Ƃł����A�`�����͂�����w�E���Ă����ƂƂĂ��[���ł��܂��B
�`������͂��������Ă��܂��B
�������s�́A�����ɂ��邱�Ƃ���n�߂�Ƃ��܂������B
�������A�D�G�Ȑl���珇�ɔ����ď��������Ă������Ƃ��|�C���g���B
�l�͉��l���W�܂�ƁA���݂��ɖ���������₤�悤�ɂȂ����������B
10�l����`�[���ŁA�i���o�[�������ꂽ�`�[���́A����܂ł̃i���o�[�c�[�����[�_�[�Ɉ�B
�t�ɁA�ł��o���Ȃ��l���ƁA�����}�V�������l���_���}���Ƃ��̂悤�ɃY��������B
�ǂ���̕��@�ł��X�l�̃`�[���ɂȂ邪�A��҂̕��@���ƑS�̂̃��x���͉������Ă��܂��B
���s���ɂ́A�E�C�������ėD�G�Ȑl���甲�����Ƃ��B
�ǂ��ł����B���ɔ[���ł���ł��傤�B
�������A���ۂɂ�������l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�{����ǂ�ŁA��������������Ƃ�����܂��B
����͊`������̊�Ɗς�l�Ԋςł��B
�}���̈�ɁA�u�K�����S�A�y���S�ŕ]������v�Ƃ����̂�����܂��B
�����ɂ��������Ă���̂ł��B
�l�͋@�B�ƈ���Ĉӎv�⎩����������B
������A��Ƃ��y�Ŏd�����y�����A���̐l���K�����ǂ�����]������w�W���K�v���B
�]�ƈ����ꂼ��ɉۑ肪�^�����A���ꂼ��Ɋ撣����������A�����Č��ʂ��o����K���ق߂��A����������`���Ă�����̐�������B
�F�����������ӗ~�I�ɉ��P��i�߂�A��Ђ͎��R�Ɛi�����シ��B
�����Nj��ƍK���Nj��A�O�҂ɕ肪���ȉ�Ђ��������A�l�͎���̍K���̂��߂Ɏ����I�ɓ����������Ƃ��A�����قǑ傫�ȗ͂�����B
�`�����A���߂čD���ɂȂ�܂����B
�Ƃ���ŁA�u���傱����v���o�Ă��܂��A����͂���1���́u���傱���Ɖ��P�v�ɏo�Ă��܂��B
�{���ɂ�����Ƃ������P�A�C�f�A���݂�ȂŎ��s���āA������ȒP�ɗp���ɏ����ĕ���d�g�݂��u�`���R�Đ��x�v�ł��B
�u���傱���Ƃ����Ă����s���ĕ���v����`���R�ĂŁA�u�`���R�ƃA�����ꏏ�Ȃ̂łƂĂ��Â��A��Ɏ����Ȃ��v�Ƃ����Ӗ�������܂��B
����܂ł̌��ꂵ����Đ��x�ƈႢ�A���|�I�ɋC�y�ŋC�y�ł��B
���̃`���R�Đ��x�ɂ́A���ꂪ�l���Ă�����₻�����Ǝv����u���P�̐S�ɉ�����v�S�̌������܂܂�Ă���Ɗ`������͏����Ă��܂��B
���̌�͖{�������ǂ݂��������B
�u�`���R�āv�ŁA��Ђ��ς����������Љ��Ă��܂��B
�H��Ǘ��ɊS�̂���l�ɂ͋������E�߂ł����A�����łȂ����ɂ����E�߂��܂��B
�R�����Y���X�ōw��

���u�u�����̒n���Ɂv�\�啧�Ǝq�̐��U�\�v�i���c���A�@�}�n���o���Ɂ@�Q�P�U�O�~�j
�����̃T�����ł����b���������������Ƃ̂���@���c���A���A�����g�̂���l�̂��Ƃ�{�ɂ���܂����B
�u�����̒n���Ɂ\�啧�Ǝq�i�����炬�������j�̐��U�\�v
���c����ɂ��Ă���}�n���o���ɂ���̏o�łł��B
1960�N��A70�N��ɎЉ�I�Ɋ����������̕�����Ă����A�]����ҏW�c�u���ł̉�v������܂����i���݂��S�����ł̉�Ƃ��Ă���܂��j�B
���̊����̏o���_�ɂȂ����̂��A���c����̂����l�̑啧���S�ɂȂ��ĊJ�����u�}�n���o���R���j�[�v�ł��B
�}�n���o������ł̉�ɂ��ẮA��������{���o�Ă��܂��̂ŁA�����m�̕������Ȃ��Ȃ��ł��傤�B
��N�W���ɁA���c����Ƀ}�n���o���̘b�����Ă���������Ƃ������̂ł����A���̎��A���c����͂����������Ђŏ�����Ă��邱�Ƃɂ́u�����v��������ƌ����Ă��܂����B
�������ɁA���c���璼�ڂ��b�����������āA���̈Ӗ��������킩��܂����B
�����҂���邱�Ƃ̑�����A���߂Ēm��܂����B
�{���́A����܂ł��܂����邱�Ƃ̂Ȃ������A���c����̂���l�̑啧�Ǝq����̐��U���܂Ƃ߂��{�ł��B
���c����́A���������Ă��܂��B
���������ł����A���p�����Ă��炢�܂��B
�����A��̐��U��Ԃ��Ă݂����Ǝv���悤�ɂȂ����̂́A���������炾�����ł��傤�B
�e�ɂ��ĕ��͂ɂ���Ȃ�āA���l�l�ɂ͓ǂݓ�͂���̕����������̂ł͂Ȃ��Ƃ͍l�����̂ł����A��ɂ͕��A�啧�����i�W�܂��͋�j�ɓY�������A�Љ�̕ϊv�̂��߂̈�𓊂��������Ȃł��������Ƃ��A�̑傾�ƍl���Ă̂��Ƃł��B
����ł����鎛���J�����č݂����]����҂̋����R���j�[�ŁA�]����҂ւ̏��Q�������N�����A�Y�ɏ�������s�������������A��������������v�z���Ƃ��ɂ��A�Љ�I�ɑa�O�����邱�ƂȂ��A�������p���������Ȃł������p�ł��B
���ɂ��Ă͊���̏o�ŕ����o�Ă���̂ł����A���̎v�z���x���A�����𐬂藧�����锺���ł������l�̂��Ƃ��܂��A�L�^�Ƃ��Ďc�������ƍl�����̂ł��B
�����āA53�Ƃ������̑�����A���l�ɂȂ��Ă���́A�Ɨ������������A��l�ł͂ł��Ȃ����̂��ƌ��Ă����̂��A��ɂ��ď����\���������R�̈�Ȃ̂ł��B
�{����ǂނƁA�����������c����̎v���̈Ӗ����킩��܂��B
���c����́A���[���ł������b�Z�[�W�𑗂��Ă��Ă���܂����B
�k�C���̐Ύ땽��ɗ�����[�z�����Ă������̎q�B��Ќǎ��@�̗���ƂȂ�A�����āA���ł͂��܂�����Q�҉^���B
�ӔN�̙l�ߎ����ٔ���Q�Ҏx���Ȃǂ̓��X�����������Ă܂Ƃ߂܂����B
���݁A�Љ�I�ۑ�ɂȂ��Ă���A�n����i���A�Љ�I�r���Ƃ������̂ɑ��āA�l�݂̍���Ƃ��Č��������Ă��������L�^���A���A�����グ�Ă���Ⴂ����ւ̗�܂��Ƃ������ƍl���Ă��܂��B
���肰�Ȃ����i�̒��ɁA����̑�������邱�Ƃ̖{����������������{�ł��B
�l���������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B
���e�̏Љ�͂����Ă��܂��A�{���̍ŏ��ƍŌ�ɏ�����Ă���Q�̕��͂������Љ�Ă����܂��B
���c����̂��l���Ɩ{���ւ̎v�����ے�����Ă��܂��̂ŁB
�l�͗��j�̏،��҂ƂȂ����u�Ԃ���A������Ƃ��߂ɂ��đn�삵�Ă������̂ł���ƍl���Ă��܂��B�����Ƃ����̂͌l�I�Ȏ�ςɂ���ďq�ׂ�����̂ł��B��Q�҉���^���ɂ��Č��ɂ́A�s�^�ɂ����S�҂ł��������ɂ͑��������Ȃ����Ƃł��B
��̂ǂ̎��������Ă��A�ꏏ�ɋ��Ă��ꂽ�l�����ɏ������Ă���̂ł��B�����āA���������ɐ����Ă���B���͏��������Ȃ������̐l�Ɋ��ӂ��܂��B�l�͊F�A���܂�Ɋւ�炸���̗^����ꂽ���̑����ɂ����āA���͂Ȃ��̂ł��B
�����ĉ߂����Ă����l���̒��ɁA�����̉߂����A���r����ߋƂ��A���炩�ɂȂ鏊�͖����̒n���ƍl����̂ł��B�����ɗ����ɒH����A�����čs���̂ł��B
�{���̍w���́A���c����̃}�n���o���ɂ̃z�[���y�[�W���炨�肢���܂��B
http://www.bunko-maharaba.com
���s���̕��͎��ɂ��A�����������B
�����܂����c����̃T�������J�Âł���Ǝv���Ă��܂��B

���a�����߂��i���^��@�O�܊ف@2015�j
�{�����A�w������߂āx�w�������߂āx�ɑ����A���퐶�����ނɂ��ē��{�������l����������̃G�b�Z�C�W��R�e�ł��B
�w������߂āx�ł͎I�Ȃ��̂��A�w�������߂āx�ł͕����I�Ȃ��̂��厲�Ɍ���܂������A
����́w�a�����߂āx�́A�_�����厲�ɏ����ꂽ���̂𒆐S�ɕҏW����Ă��܂��B
�������́A�u�u�a�v�͐_���̊j�S���Ȃ��R���Z�v�g�v���Ə����Ă��܂����A
�����ɁA�u�a�v�͐_�������܂����A���{���n��グ�Ă������{�����̊j�S�ł�����A���{�����́A�܂��Ɂu�a�̕����v���Ƃ��l���Ă���̂ł��B
�u��v�u���v�ɑ����R�ڂ̃L�[���[�h���u�a�v�ƒm�������ɂ͐����������q���������̂ł����A
�l���Ă݂�A���̃V���[�Y�̊����҂Ƃ��Ắu�a�v�ɗ��������̂́A�ƂĂ��[���ł���b�ł��B
�������́A������������A�ŏ�����u�a�̕����_�v�����b�Z�[�W���悤�Ƃ��Ă����̂�������܂���B
������A�V���[�Y�̊����҂Ɂu�a�v��u�����̂́A������̈Ӗ�������悤�ł��B
�{���̕���́A�u���{�l�͂Ȃ����a��������̂��v�ƂȂ��Ă��܂��B
�����āA�������͖{���𑗂��Ă��Ă��ꂽ����ɁA���������Ă��܂����B
�u�a�v�Ƃ͑�a�ɂ����a�ɂ��ʂ��܂��B���܌��@�����̋c�_�������ł����A
���q�̐��肵���u�\�������@�v�����͕��a���ƁE���{�̃V���{���ł���Ǝv���܂��B
���{�́u�a�v�̎v�z�����E���~�����Ƃ�����āA�܂����70�N�L�O�o�łƂ��āA�{���������܂����B
�܂�A�{���́u�a�v�ɍ��߂��������̎v���́A�u��a�́u�a�v�ł���A���a�́u�a�v�v�Ȃ̂ł��B
�Ƃ����킯�ŁA�{���́A�������́u���{�_�v�Ɓu���a�_�v������ɂ������A���{�����_�ɂȂ��Ă��܂��B
�O�̂Q���Ɠ������A����̐g�߂ȑ�ނɁA�u�a�v�ɂ��āA���܂��܂Ȑ���A���Ƃ��A�u�̕���v�u�\�v�u�告�o�v�ƌ������`�������̐����A�u���s�v�u����v�u����R�v�u�x�m�R�v�ƌ����������̏W�ς��Ă���n��A�u�I���v�u�����Љ�v�Ƃ������������ۂȂǁA�Ȃ��݂₷���������A�����̂悤�Ȍy���ȁu������v���W�J����Ă��܂��B
�e�ҁA�������Ă���̂ŁA������Ƃ������Ԃ̍��ԂɁA�S�ɔC���Ăǂ�����ł��ǂ�ł�����X�^�C���ł��B
�C�y�ɓǂ݂Ȃ���A���낢��ȋC�Â���V�����m���ɂ��o���͂��ł��B
�����āA���ꂩ��̐��E�ɂƂ��āA�������̓��{�����������Ă��邾�낤�u���l�v�ɋC�Â����Ă��炦�邩������܂���B
���ݘb��ɂȂ��Ă���u���ۖ��v�ւ̍l�����́A���Ԃƈ������͈Ⴄ�Ǝv���܂����A�u�a�̓��{�����v�̒��ɂ���A���a�ւ̉��l�Ɋւ��ẮA�ƂĂ������ł�����̂�����܂��B
�{���́u�͂��߂Ɂv�́A�������̉r�̂Œ��߂��Ă��܂��B
�_�̓��@���̓��ɐl�̓��@�O�̓����a�Ō��с@�f��
�f���́A�������́u�̉r�݂̉덆�v�ł��B
�������̎v�������߂��Ă��܂��B
�R�����Y���X����w��

���������ɂ���u�n���v�i�吼�A�@�|�v���Ё@2015�j
��l�̎������̌�肪�A���͑�D���Ȃ̂ł����A�{���͂܂��ɂ��������{�ł��B
���҂͂m�o�n�@�l���������T�|�[�g�Z���^�[�E���₢�������吼�A����ł��B
�u�n���v�����{�͂�������܂����A�ǂ����u���l���v�̖{�������A�ǂݏI�������A
�������肵�Ȃ��C���ɂȂ邱�Ƃ������̂ł����i������������ς̂��߂ɁA���̖{��1�����߂��ǂ߂��ɂ��܂����j�A
�{���͂���Ƃ͑S���Ⴂ�A�ǂݏI������Ɍ��C���o��u�n���Ɋւ���{�v�ł��B
�Ƃ����Ă��A���҂̑吼�������́u�n������v������Ă���̂ł͂���܂���B
�Ȃɂ���吼����́A���܂��܂�20��̎�҂ł����A�u�o�ϓI�ɍ����v���Ă���킯�ł�����܂���B
���Z2�N�̎��A�ŏI�d�Ԃɏ��x��č����Ă������ɁA�z�[�����X�̂�������ɏo������̂����������ŁA�吼����͐V�������E�Ɋւ�肾���Ă����܂��B
���̌o�܂͖{���ɏ�����Ă��܂����A���̎��A�z�[�����X�̈�l����A��������ꂽ�����ł��B
�u�Z�����A�ǂ�Ȏ�����邩�͒m��Ȃ������͂܂��Ⴂ�B�������݂����ɂ́A�Ȃ�Ȃ�v
���́u���t�v���A�吼����̐S�ɉ������̂�������܂���B
�����āA�吼����́u�L�����ւ̗��v�i���̏���ȕ\���ł����A��ňӖ��������܂��j���n�܂�܂��B
�吼����́A������_�@�ɁA�z�[�����X�x�������Ɋւ�肾���܂��B
�����āA�����̏o������l�����Ƃ̌𗬂�ʂ��āA�̌��������Ƃ�C�Â������Ƃ��A�f���ɏ����Â����̂��A�{���ł��B
�ł�����A�ǎ҂͈�l�̎�҂��A�Љ�Ɗւ��Ȃ���A�������ĂĂ��������ǂނ��ƂɂȂ�܂��B
�����ɂ͂��܂��܂ȃh���}������A�G�s�\�[�h������A���Ԃ�O���邱�Ƃ͂���܂���B
���͂��ǂ݂₷������łȂ��A��҂炵�����炩���������Ă��܂��B
�C�������Ȃ���A�Ă炤���Ƃ��A���Ƃ����Ƃ��Ȃ��B
���ɏ������Ȃ邱�Ƃ�������A�C�����̂������͂ł��B
�������A�ǎ҂́A���Ԃ�{������2�̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃł��傤�B
�ЂƂ́A�������̓���ׂ̗ɂ���Ȃ���A�Ȃ��Ȃ������Ȃ��Ȃ��Ă���A���{�Љ�́u�n���v�̎����B
�����ЂƂ́A�u�L�����v�Ƃ͉����Ƃ����A�u�n���v�̂�����̑��ʂł��B
�吼����Ƃ�����҂̐������ƃz�[�����X�ƌ�����l�����̐������̊ւ�荇����ʂ��āA�u�n���v�Ɠ����Ɂu�L�����v�̎p���_�Ԍ����Ă��܂��B
�Ȃɂ����A�吼����̐��������L���ɂȂ��Ă����̂��������܂��B
�������ނ̍��z�͕n�����܂܂̂悤�ł����A�ނ̐l���͖L���ɂȂ��Ă��Ă���悤�ȋC�����܂��B
�吼����́A�Љ�̎����Ɗւ�邱�ƂŁA����̋��ꏊ����ĂĂ��Ă���̂ł��B
�u�n���v�͎������̕�炵�̂������ɂ���܂����A������������u�L�����v���܂������悤�ɁA�������̕�炵�̂������ɂ���B
�{����ǂ݂Ȃ���A���͉��߂Ă����v���܂����B
�吼����́A����̕�炵�́u�L�����v�Əo����Ă������̂ł��B
���ꂪ��قǏ������u�L�����ւ̗��v�Ƃ������Ƃł��B
�u�n���v���u�L�����v���A���l��̖��ɂȂ����Ă��邱�Ƃɂ��C�Â�����܂��B
�{���̓��e�ɂ��Ă͏Љ�Ȃ��܂܂ɁA���X�Ə����Ă��܂��܂����B
�l�b�g�ł̖{���Љ�L������Q���p���܂��B
�Ђ��Ȃ��Ƃ���H��x���̍őO���ɔ�э���҂����ʂ����Љ�̌����B����̃��A����O�ꂵ�ĕ`���Ռ��̃��|���^�[�W���I
6�l��1�l���n���B�L���ȓ��{�̌����Ȃ��n���ɁA20��ɂ���NPO�@�l�u���₢�v�������̒��҂�����A�Ռ��̃m���t�B�N�V����!!
�܂��ɂ��̒ʂ�ł����A�܂��́u�܂������v�̂U�ł̃G�s�\�[�h��ǂ߂A�����炭���̐悪�ǂ݂����Ȃ�ł��傤�B
�吼����́A�u�܂������v�̍Ō�ɁA���������Ă��܂��B
�u�n�����ĂȂ낤�H�v
���̂Ƃ炦�ǂ���̂Ȃ��₢�ɑ��铚�����A�݂Ȃ���ƈꏏ�ɍl���Ă�������������ł��B
�Ƃ����������̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�������������Ă���A���܁A�����̎Љ�̎����������Ă��邩��ł��B
�吼����͍Ō�ɂ��������Ă��܂��B
�l�́A���̓��{�Ƃ����Љ�̂Ȃ��ŁA�����ĐV�h�̘H��ŁA�n���Ƃ������ɋC�Â��Ă��܂����B�����Ő�����l�����̐l����m���Ă��܂����B
�m��Ȃ������ӂ�����Đ����Ă������Ƃ́A�����ł��Ȃ��B���ߑ�����̖������B
�ł��A�O�ɐi�܂Ȃ��Ƃ����Ȃ��B
�����A�O�ɐi�����Ǝv���܂��B
�ŋߓǂ��ŁA��ԁA�S�ɋ������{�ł��B
���Ђ݂Ȃ������Ɏ���Ă݂Ă��������B
�Љ�ւ̊፷���������ς�邩������܂���B
����͂����ƁA����ւ̊፷���ɂȂ����Ă����͂��ł��B
��҂���w�Ԃ��Ƃ́A��������܂��B
���u�悶�܂��E�悶�����̍�@�v�i���^��@�t�o�ŎЁ@850�~�j
����Ɋւ��ẮA��ۂɎc���Ă��邱�Ƃ�2����܂��B
�ЂƂ́A�X�C�X�̃`���[���b�q�x�O�̕�n��u�˂����ł��B
��n�ɓ������r�[�ɁA�܂��ɂ����ɂ́u���҂̐����v������Ɗ����܂����B
�Ñォ��Â��A�l�N���|���X�̕������A�܂��܂��Ɗ����܂����B
���̂���̋���Ȉ�ۂ͌����ĖY����܂���B
�����ЂƂ́A�����{��k�Ќ�A1�N���قnjo�߂������̓쑊�n�Ō�����n�ł��B
���ӂ̏Z��͂��ׂČ��A�y�䂾�������c���Ă��܂���ł������A
���̈�p�ɁA������Ɛ������ꂽ��n�������܂����B
�ʂ肷����ɉ������猩�������ł����̂ŁA�s���m�ȋL���ł����A����炻������������ꂳ��Ă����悤�Ȉ�ۂł����B
����2�̗Ⴉ���ʉ����邱�Ƃ͂ł��܂��A��n�₨��ɑ���މ�̈Ⴂ�����������܂��B
�����āA�����ɂ́A���҂Ƃ̊W�����ǂ��l���Ă��邩�����m�ɕ\��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�����܂ł��Ȃ��A����͂��܂�����̂̐������ɐ[���Ȃ����Ă��܂��B
�B���_�����������^�炳�A����Ɋւ���A�킩��₷����@���������܂����B
����ƌ����Ă��A�Ⴂ����ɂ͂��܂�S���Ȃ���������܂��A���鐢�ォ��͋t�ɑ傫�ȊS���ɂȂ���ł��B
�l�b�g�ł̖{���̏Љ�L���ɂ͂�������܂��B
����Ɍ��������u������v�Ɓu�������v�B���q����A�j�Ƒ������i�݁A����̔Y�݂������l�������Ă���B
��c�̂���������z������u�悶�܂��v�A�V���ɂ��������u�悶�����v�\����̂����������l�����鍡�A�ǂ̂悤�ȑI��������Ό�����Ȃ��̂��B
���ꂩ��̂���̂�������l����B
�������́A����Ƃ͋��{�̏ꏊ�A�F��̑Ώۂ��ƍl���Ă��܂��B
�����āA����͕K�������̂���ł���K�v�͂Ȃ��Ƃ����܂��B
��c�Ɋ��ӂ���A���҂����{����C����������A����́u�������v�ɂ������K�v�͂Ȃ��B
����́A�O���u�i�����v�Ȃǂł�����Ă���������̑��V�ςɂ��Ȃ����Ă��܂��B
�������A�����炱���A�ނ���u��@�v����ɂȂ��Ă���B
���ꂪ�{�����������������̖ړI�ł��傤�B
����Ɋւ��āA�ƂĂ��킩��₷���A�����Ȏ��_����������Ă��܂��B
�u���V�Ɩ����̎�ށv��u����I�у`���[�g�v���f�ڂ���Ă��܂��B
�������A�{���͒P�Ȃ��@���ɂƂǂ܂炸�A���ꂩ��̂�����n�Ɋւ�����ł�����܂��B
���Ƃ��A�Љ�̕ώ��ɂ�閳����̑����ɂǂ��Ώ����邩�Ɋւ��ẮA
���a�̂͂��߂ɒ�Ă��ꂽ�ז�_�O�́u�ꎛ��搧�v��Z�����ׂĂ𑒂鍇����Ƃ��Ắu�s�s��v�Ȃǂ��Љ�Ă��܂��B
����ƕ�n����v����A�R�~���j�e�B�P�ʂ̂���ł��B
����́A�P�ɂ�����n�̘b�ł͂Ȃ��A���Ԃ���҂����̐������̖��ł�����A
����ɂ͎��҂Ƃ̂Ȃ����ʂ��Ă̖����Ƃ̂Ȃ�����������Ă���悤�Ɏv���܂��B
���Ȃ݂ɁA���ɏ������X�C�X�̕�n�́A���҂Ǝ��҂���v�z�������܂������A���{�̂���͐��҂Ǝ��҂��Ȃ���v�z�������܂��B
�������́A���̖{���Љ���u���O�ɂ��������Ă��܂��B
�킽���́A�l�ԂƂ͎��҂ƂƂ��ɐ����鑶�݂ł���Ǝv���܂��B
����́A�l�ԂƂ͂����K�v�Ƃ��鑶�݂��Ƃ������Ƃł�����܂��B
������l���邱�Ƃɂ���āA���܂̐������Ɋւ��āA�C�Â����Ƃ͏��Ȃ�����܂���B
���u���s��o�ρ@���������łȂ��u���n�Љ�v�̎���v�i���R�߂ق��@�p��V���@800�~�j
���܂̎Љ�ɐ����Â炳�������Ă���l�͏��Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂����A�����������ŁA�V�����������������ڎw���l�������A�����������Ă��Ă��܂��B
�����̐l�����́A�Љ�ɍ��킹�Đ����Ă��܂����A�����܂ł��Ȃ��A�Љ�͂�����\�������l�ЂƂ�̐������̏W�ςł�����A���������V�������������Љ��ς��Ă������ƂɂȂ�܂��B
����̐�������ς��邱�Ƃ͓�����Ƃł����A����ł��Љ��ς��邱�Ƃɔ�ׂ�ł��Ȃ����Ƃł͂���܂���B
�����āA�����������Ƃ��\�ɂ�����A���܂�Ă��Ă���̂������ł��B
�����Â炢�Љ��Q���̂ł͂Ȃ��A���������悤�ɐ����邱�Ƃ��l�����ق��������B
�����v���čs�����N�������l�������A�Љ��ς��Ă�����������܂���B
�{���́A���������v���������Ă���l�����ւ̉����̏��ł��B
�����̃T�����̏�A�̈�l�ł����鐙���w������A�Љ�ɍ��킹�鐶�����ł͂Ȃ��A����̔[���ł��鐶�������������Ă����l�ł��B
���̐�����������M�҂̈�l�Ƃ��āA�Q�������̂��{���ł��B
�S�̂�����Â��Ă���̂��A�u���̓N�w�ҁv�Ƃ���������R�߂���ł��B
�ŏ��ɓ��R���A�o�ρi���`�j�̓W�J�ƎЉ�̑n������̉�������o�ς̂��������������Ə����Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA�u���s��o�ρv�́A���������̎s��o�ςɊւ��Ȃ�����A���ǂ�����������ǂ��Љ�����낤�Ƃ���o�ς̉c�݂Ɛ�������Ă��܂��B
�܂�A�{�����ڎw���Ă���̂́A�V�����o�ϊw�ł͂Ȃ��A�V�����Љ�A���邢�͌o�ς̂�����A�����Ă��̊�{�ɂ��鎄�����̐������i�o�ς̉c�݁j�Ȃ̂ł��B
��2�͂ł́A���������u���s��o�ρv�̊�������Ƃ��āA�u�Љ�~�b�V�����v�Ɓu���Ɛ��~�b�V�����v�̗������Nj�����u�Ȃ�킢�v�Ƃ��ẴG�V�J���E�r�W�l�X������܂��B
��4�͂ł́A�������������̔w�i�ɂ���A���E�I�ȃE�F���r�[�C���O�ւ̒����ƁA���s��o�ς̊����������N�����\�[�V�����E�C�m�x�[�V��������̓I�Ɍ���Ă��܂��B
�����ɏo�Ă���Q�̃L�[���[�h�i�T�O�j�����ɂ͂ƂĂ�����������܂����B
�u���L�v�Ɓu�Y��i�ނ��сj�̗́v�ł��B
����͎��������Ǝu�����Ă��邱�Ƃł����邩��ł��B
���̂Q�̏͂̊Ԃɂ���̂��A��������́u���݊��̂��鎞�Ԃ����߂āv�Ƃ����_�l�ł��B
��������́A���Ԃ����ɁA�������̐�������₢�����Ă����܂��B
�����āA���s��o�ς���������������w��Ŏx���Ă���̂́A�s��o�ςɊǗ�����Ȃ��琶����l�Ԃ����������݊��̂Ȃ����W�I�������������A���ꂪ�V�������������肾����ՂɂȂ��Ă���Ɛ�������͌����̂ł��B
�����Ő�����Ă���u���Ԙ_�v�͂ƂĂ��ʔ����ł��B
�u���L���ꂽ���ԁv�Ɓu���L���ꂽ���ԁv�Ƃ����������ŁA��������͐�������_���Ă����܂��B
�����āA���L�����͂��̎��Ԃ��A�ݕ��ɒu���������Ȃ�����D����Ă䂭�u���Ԃ̎��I���L�v�̃p���h�b�N�X����ɂ��܂��B
���Ԃ����L�����r�[�ɁA�������̐��͕��������Ă��܂��B
�����������x�A�u�݂�Ȃ̎��ԁv���l���������ƌĂт����܂��B
�r���v�������Ȏ��ɂ͂ƂĂ������ł��܂��B
���Ԃ͋��L����Ă����A�����Ă���̂ł��B
���R����͍ŏ��̏͂ŁA�u�K��������������͕�炵�̂Ȃ��ɏ[�����̂��鋏�ꏊ������Ƃ������Ƃ��v�Ə����Ă��܂��B
�ƂĂ������ł��܂��B
�{���́A���������u�[�����̂��鋏�ꏊ�v��ڎw���Đ����Ă���4�l�̎��H�҂����̘_���L�@�I�ɗ��ݍ����Ȃ���A�u���ꂩ��̎Љ�v�u���ꂩ��̐������v���������Ă���܂��B
�C�y�ɓǂ߂�{�ł����A��������̎�����^���Ă����{�ł��B
���Б����̐l�ɓǂ�ł��������A�u�[�����̂��鋏�ꏊ�v�Â���Ɋ������Ă������������Ǝv���܂��B
�u�[�����̂��鋏�ꏊ�v�̂���l������������A���ꂾ���ŎЉ�͖L���ɂȂ��Ă����ł��傤����B
���u�{���̈�Õ���͂��ꂩ�����Ă���I�v�i�{�c�G�@�m��Ё@1300�~�j
�����ŏ��ɖ{�c����ɏo������̂́A2002�N�̃I���^�i�e�B�u�E���f�B�X��������ŁA�{�c����̂��b���������������ł��B
�����Ŗ{�c����́A��Ð��x�ɂ�����v���̐[���Ɋ������܂����B
���̖{�c���A�O�Ȉ�����߂āA��Ð��x���v�̊����ɍēx���킷�邱�Ƃɂ������Ƃ�m��܂����B
���̌��ӂɊ�Â��ď������̂��{���ł��B
�{���̂��Ƃ����ŁA�{�c����́u�{���́A���X��u�����Ƃ����ӂ�����O�Ȉ�́A��ÊE�ւ́u�⌾�v�ł���A�V���Ȋ����Ɍ������u���M�\���v�ł�����v�Ə����Ă��܂��B
�o�Ō�A���N�ȏソ���Ă��܂��܂������A�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�{�c����́A���N�A��Ð��x���v�Ɏ��g��ł��܂����A�{�c����̉��v�̎��_�͋ɂ߂Ė��m�ł��B
�y�C�V�F���g�t�@�[�X�g�i���҂�����j�̈�Ñ̐������邽�߂Ɉ�t�𑝂₷�A���ꂪ�{�c����̎��g�݂Ȃ̂ł��B
���̔w�i�ɂ́A���{�̈�Ð���ƈ�Â̌���͌����Ċ��҂�����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ�������������܂��B
����́A80�N�㔼����̈�Ô�}����̂��߂Ɉ�t�{�������}�����A���{�̐l���������t���͐�i�����Œ�ł��邱�ƁA���̈���ō����̎��ȕ��S�͐�i���ō��ł��邱�ƂɌ���Ă���Ɩ{�c����͎w�E���Ă��܂��B
�~�}���҂̎��ꋑ�ۂɂ�鎀�S������A��Î��̖̂�肪�N����ƁA���_�͕a�@���t��ӂ߂܂����A�����������Ƃ̔w�i�ɂ͐�ΓI�ȁu��t�s���v�̌���������̂ł��B
���{�̈�t��11���l�s�����Ă���A�Ɩ{�c����͌����܂��B
���̈�t�s������������Ȃ�����A���{�̈�Õ���͎~�܂�Ȃ��B
�a�@�ɂ����������Ƃ̂���l�Ȃ�A�N���C�Â��Ă��邱�Ƃł��傤���A��t�͕s�����Ă��܂��B
��Ð���ɂ������t�s���ւ̊�@���͎����猩�Ă��s�v�c�ȂقNjH���ł��B
����ɑ傫�Ȗ�肪�ڑO�ɔ����Ă��܂��B
�s�s�o�ł��B
�s�s�o�ɉ�������A���{�̈�Â͐��E�ɊJ������邱�ƂɂȂ�܂��B
���̌��ʁA�ǂ��Ȃ邩�B
�s�o�o�́A���{����ĂĂ��������F�ی����x��ώ������A�Ă����Ɩ{�c����͌����܂��B
�u��i��Áv�̓����̒��ɁA���ɂ��̒���͌��������Ă���A�Ƃ��B
���Ȃ݂ɁA��N�S���Ȃ����A�����Ȃ��A�܂Ƃ��Ȍo�ϊw�҂̉F��O������́u�s�o�o�͎Љ�I���ʎ��{��j��v�ƌ����Ă��܂����B
�����āA�s�o�o�ɏے������u�s�ꌴ����`�̓��{�N�����A���{�̍����F�ی����x�̊��S�ȕ���ւ̌���I�Ȉ������ݎn�߂悤�Ƃ��Ă���v�A�Ɓu�Љ�I���ʎ��{�Ƃ��Ă̈�Áv�i2010�N�j�Ōx�����Ă��܂����B
�ł͂ǂ��������Õ���͎~�߂���̂��B
�{�c����́A����܂ł̊����̑̌��܂��āA���{�l�̈ӎ����ς��Ȃ��ƈ�Â����{���痧�Ē������Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ��_���܂��B
����́A��Ð��x�̗��p�҂ł���A��������l�ЂƂ肪�A���܂̈�Ð��x�̖��_��m�邱�Ƃ���n�܂�ł��傤�B
�����āA�u��������l�ЂƂ�̊��҂̈ӎ��Ǝ�f�s����ς��Ă������������ŁA�n��̕a�@����邱�ƂɂȂ���v�Ɩ{�c����͌����܂��B
����͈�ÂɌ��������Ƃł͂���܂���B
�{�c����͂����Ăт����Ă��܂��B
�������̍K���ȎЉ��ڎw���ɂ́A���{�l��l�ЂƂ肪�A���悢�������邽�߂ɂǂ����ׂ������l���A�����̂ł��邱�Ƃ����s���Ă����K�v������B
�����Ȃ���A��Â����łȂ��A���{���̂��̂����Ă��܂��B
�����āA�{�c����́A�O�Ȉ�����߂邱�Ƃ����ӂ��A��Ö��A�Ђ��Ă͓��{�Љ�S�̖̂��̉����̂��߂ɖ{�������Ď��g��ł������ƌ��ӂ����̂ł��B
�{�c����̃��b�Z�[�W�ɂ͐S���狤�����܂��B
�{���́A��Õ���̐^���ƈ�Ì���̎��ԁA���݂̈�ÊE�̖��ȂǂƂƂ��ɁA���̑ɂɂ���Ƃ�������L���[�o�̈�Â̕A����Ɉ�ÍĐ��ւ̋�̓I�Ȓ�ĂȂǂ��A�킩��₷��������Ă��܂��B
�����̐l�ɂ��ЂƂ��{����ǂ�ł��������A��Ð��x�ւ̊S�����߂Ă������������Ǝv���A�Љ���Ă��炢�܂����B
�R�����Y���X����w��

���u�q�ǂ��m�o�n�����Q�O�P�T�v�i���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�ҁ@�G�C�f���������@2500�~�j
�m�o�n�@�l���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�i��\�����F���ؔ���q����j���u�q�ǂ��m�o�n����2015�v�����������܂����B
���낢��ƌo�܂������āA���݁A���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�͓����̎��̃I�t�B�X�Ɏ����ǂ�u���Ă��܂��B
���̊W�ŁA�ꖱ�����̗���������Ƃ́A���b������@��������A���̔����ւ̎��g�݂����������Ă��܂����B
�o���オ���Ă��������������Ă��炢�A���������̎v���̐[�����������܂����B
����Ɠ����ɁA�Ȃ�����܂ł����������̂��Ȃ������̂��낤���Ɖ��߂ĕs�v�c�ȋC�����܂����B
���N�A���܂��܂Ȃm�o�n�ɂ����₩�Ɋւ���Ă��Ċ�����̂́A���{�̂m�o�n�����́u�Ȃ���̎コ�v�Ɓu�傫�ȗ��O�v�̕s�݂ł��B
�{���́A���̂Q�̉ۑ�Ɏ��g��ł���悤�ɁA���ɂ͎v���܂����B
�ҏW�ψ����̏�����́A�u���s�ɂ悹�āv�ł��������Ă��܂��B
�q�ǂ��̌������搂��g�q�ǂ��ŗD��h�̗��O�����ɂ��āA���ꂼ��̗̈�̊T���ƁA���̗̈悪������ۑ�̉����Ɍ��������f���I�Ȏ��H�����グ�邱�Ƃɂ��A�̈斈�̂���ׂ��p�A���������������Ƃ��ł��A�Ђ��Ắg�q�ǂ��m�o�n�h������H��ł��낤�����������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl�����̂ł��B���ЁA�q�ǂ��n�m�o�n�W�҂��͂��ߑ����̕��X���ANPO���Љ�I�ɉʂ����Ă����������������Ă��������A�V���ȃX�e�b�v�Ɍ������Ă���������Ɗ���Ă��܂��B
�u�q�ǂ��ŗD��v�Ƃ������O����{�ɒu����Ă��܂��B
�u�̈悪������ۑ�̉����Ɍ��������f���I�Ȏ��H�v�ɂ͓��R�̈���O�ł́u�Ȃ���v���K�v�ł����A���̂��߂ɂ͂܂��͎q�ǂ��̖��Ɋւ�邳�܂��܂Ȃm�o�n�����ւ̘��Ղ��s���ł��B
�{���͌����ɁA���̂Q�̉ۑ�ɉ����Ă���Ǝv���܂��B
�{����ǂނ��ƂŁA���ꂩ��̊����̕��������������A���C�Â�����l�������ł��傤�B
����͖{���̕ҏW���j�ł��������悤�ł��B
����������◧������Əo��������������́A�u�q�炿�x���v�Ƃ������t�ł��B
�����g�́u�q��Ďx���v�Ƃ������t�ɂ����ƈ�a�������������Ă��܂������A�u�q�炿�x���v�Ƃ������t�ɏo����āA�����l���Ă���l������̂��Ƃ��ꂵ���Ȃ�܂����B
���ꂪ������◧�������ł����B
�����Q�O�N�قǑO�̂��Ƃł��傤���B
���������́A�\�[�V�����E�t�H�X�^�[���Y���Ƃ������_�����ɕۈ���ɂ�������Ă��܂����B
�{���̓��e�͐��肾������ł��B
��I���ł́A�q�ǂ��m�o�n ���Ƃ�܂��������V�̎��_���������Ă��܂��B
����ɂ���āA���݂̎q�ǂ�NPO�̏Ƃ��ꂩ��̕��������Ղł��܂��B
��II���ł́A�X�̗̈�ɂ킯�āA�̈�ʂ̊T���Ǝ��H���A�ƂĂ���̓I�Ɍ���Ă��܂��B
��III���̎����҂ł́A�֘A�@�K�Ȃǂ̉��������Ă��܂��B
���Ȃ�Z�x�̍����{�ł����A�ǂ݂₷���H�v���Ȃ���Ă��āA�y�����ǂ߂܂��B
���{�ɂ�����m�o�n���Ԏx���g�D�́A����Ӗ��ł��̖������I���A���̃X�e�b�v�Ɉڂ��Ă��������ɗ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�{���́A�����������Ƃɂ���̕�������^���Ă���Ă��܂��B
�Ƃ�����Ɩڐ�̖��ɖ��v�������Ȃm�o�n�̎�����L���A�����̎Љ�����߂Ă����h����^���邽�߂ɁA���������u�����v�����́A���ꂩ��̒��ԑg�D�̑傫�Ȏg�����Ǝv���܂��B
���������ł��̂ŁA�v�]���Q�قǏ����Ă��������Ǝv���܂��B
�܂������������l�Ȃm�o�n�̐l�������Q�������̂ł���A�̈�������H�҂������A���̎q�ǂ�������Љ���ǂ��l���Ă��邩��b�������āA�u�q�ǂ��ŗD��v�Ƃ������O���@�艺����悤�ȍ��k���������ʔ������낤�ȂƎv���܂����B
����ɂ��̉����ɁA�q�ǂ��m�o�n�̊������A�O���i�q�ǂ��W�ł͂Ȃ��m�o�n�W�҂��܂߂āj�͂ǂ����Ă���̂��A�Ƃ������Ƃ��C�ɂȂ�܂����B
�q�ǂ��͎Љ�̊�{�ł��B
���̎q�ǂ��������A�q�ǂ��ɂ͒��ڂ�������Ă��Ȃ��l�����́A�ǂ��l���Ă���̂��B
�܂��A�q�ǂ��ɂƂ��Ă̊����̏�ł���Љ���A�q�ǂ������͂ǂ����Ă���̂��B
���邢�́A�q�ǂ������Ƃ̐ړ_�͗p�ӂ���Ă���̂��B
���͔F�m�Ǘ\�h�W�̂m�o�n�Ɛړ_������܂����A�����œW�J���Ă���F�m�Ǘ\�h�Q�[���Ŏq�ǂ������ƍ���҂̐ړ_������A�q�ǂ������Ɂu�₳�����v��̓����Ă��炤���������Ă���l�����܂��B
�Ώۂ��قɂ���m�o�n�������g�ݍ��킳�邱�ƂŁA�V�������E�������Ă��܂��B
���l�Ȗ�肪���ݍ����Ă���̂��Љ�ł�����B
����ɗ~�������A�q�ǂ������̒��ڂ̐������������C�����܂��B
�����������Ƃ͑�Q���ȉ��ɂ��Њ��҂������Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA��Q���́A�R�N���\�肵�Ă���悤�ł����A�}���ȎЉ�̕ω����l����ƁA�������������o���Ăق����Ǝv���܂��B
�����̐l�ɓǂ�łق��������ł��B
�q�ǂ��m�o�n�Ɍ��炸�A�����炭�s�������Ɏ��g��ł���l�͂������A�Љ�ɊS���������̕��ɂ́A���Гǂ�ł������������ł��B
�茳�ɂ����āA�C���������Ƃ��ɓǂޖ{�Ƃ��Ă����E�߂ł��B
���{�q�ǂ��m�o�n�Z���^�[�ł́A���̔����̏o�ł��L�O���āA���J�t�H�[�����̂悤�Ȃ��̂���悳��Ă���悤�ł��B
�S�̂�����͐���ɂ����Q�����������B
���e�����܂�����A�܂��ē������Ă��炢�܂��B
http://astore.amazon.co.jp/cwsshop00-22

���u���[�_�[�̌��t���͂��Ȃ�10�̗��R�v�i����N�Y�@���{�o�ϐV���o�ŎЁ@1600�~�j
��ƌo�c�Ɋւ���Ă���ƁA�悭�b��ɂȂ�̂��A�r�W�����◝�O���ǂ�������S�ЂɐZ���������邩�Ƃ������ł��B
��ЂɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́u�r�W�����v�ł��B
�������A����͂Ȃ��Ȃ��Z�������ɁA�G�ɕ`�����݂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B
����͂������\�N���O����̉ۑ�ł����A�����ɋc�_����Ă���Ƃ���ɂ����A�����̊�Ƃ�������{���I�Ȗ�肪����ƁA���͍l���Ă��܂��B
�������A�����ɂ����������Ɏ��g��ł����Ƃ�����Ƃ���A������������邱�Ƃ���ł��傤�B
���N�A���������e�[�}�Ɏ��g��ł����A������Ѓ`�F���W�E�A�[�e�B�X�g��\�̉���N�Y���A
����܂ł̊����̏W�听�Ƃ��Ď��炪�J�������u�o�C���f�B���O�E�A�v���[�`�v�����ɁA
�r�W�����Ɍ����ĉ�Ђ�傫���ς��Ă������߂̎��H��@��̌n�I�ɁA�������킩��₷�������グ���̂��{���ł��B
���コ��́A�r�W�������u�����̖ړI�n�v�u�g�D���܂Ƃ߂鎲�v�ƈʒu�Â��A����Ɍ����āA��Ђ��ǂ��ϊv���Ă������������A�ƂĂ����H�I�ɐ����Ă��܂��B
���コ��́u���Ƃ����v�ŁA����́u�Öْm�v�����H�҂ɓ`���邽�߂�
�A�P�[�X�X�g�[���[�A��ʃV�[���A��g�A���̌��̃G�s�\�[�h�A�c�{�ƃR�c�A���H�̋Z�@�ȂǁA���҂́u�q�b�v���ǎ҂ɓ͂��悤�ɍl���Ȃ��珑�����낵���A�Ə����Ă��܂��B
���Ƃ��A�O���͋�̓I�Ȏ���ɉ����Ẳ�Г��ł̘b��������A��Ђ̒S���҂ƊO���̃R���T���^���g�̘b����������b�^�ŏ�����Ă��܂��̂ŁA
�ǎ҂͎��炪�����҂ɂȂ����悤�ȗՏꊴ�������܂����A���ۂɃR���T���e�B���O���Ă���悤�Ȋ����ŁA���R�ƃ��[�_�[�V�b�v���ł�����H��@���g�ɂ��悤�ɍH�v����Ă��܂��B
�{���S�̂̍\�����A�ǎ҂��������Ȃ���ǂݐi�߂���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�܂����[�_�[�̃r�W�������Ј��ɓ͂��Ȃ��̂́A�A������10�́u�r�W�����̕ǁv�����邩�炾�B
���̕ǂ����z����ɂ́A10�̃c�{������B
����Ƀr�W������Z�������邽�߂ɂ�10�̎������K�v�ł���B
��������������ŁA���コ��́u�����������̃X���[�K���v����u���H����r�W�����v�ɂ��邽�߂̃A�v���[�`�Ƃ��Ẵo�C���f�B���O�E�A�v���[�`���Ă��܂��B
�����āA�r�W�����������������߂�6�̃��\�b�h�Ƃ��āA�u�n���v�u���f�v�u�O�q�v�u�K���v�u�x���v�u���ȁv��������A���̉~�̗�������Ă������ƂŁA�r�W�����̐Z�����m���ɓ͂��悤�ɂȂ�ƌ����܂��B
�����āA�r�W�����Z���̃J�M�́A�o�C���f�B���O�E�A�v���[�`�́u�蒅�v�ɂ���ƌ��_���Ă��܂����A���̊m�M�͒��N�̉��₳��̎��H�̐��ʂ��痈��̂ł��傤�B
��̓I�ȓ��e�́A�{����ǂ�ł��炤�Ƃ��āA��g�̍\���͂��킩�肢��������Ǝv���܂��B
�������ɋ������������̂́A�`�[�������o�[�́u7�̖����v�Ƃ����Ƃ���ł��B
����́A�o�C���f�B���O�E�A�v���[�`�́u�x���v�̂Ƃ���ŏ�����Ă���̂ł����A���₳��͂��������Ă��܂��B
�D�ꂽ�`�[���A���ʂ��o���g�D�œ����l�����̓���������ƁA�L�[�p�[�\���łȂ��Ƃ��A����u�����v��₢�����Ȃ���A�x�������A�d����i�ߍ����Ă����B
�܂�A��l�ЂƂ肪��������������āA����������̂��B
�������s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̖����́u�Öق̒m�v�ł���A�u���t�v�ɂȂ��Ă��Ȃ������̂ł���B
�܂��ɁA���{�ɂ�����g�D�̕������A���́u�Öق̏������������v�ݏo���Ă����̂��B
���̈Öق̖����͂V�������B
�ƂĂ������ł��܂��B
�V�̖����̓��e�ɂ��Ă͖{�������ǂ݂��������B
���₳��́A���̏���������t�H�[���[�V�����������A�r�W��������������E�ꌋ���͂Ȃ̂��ƌ����܂��B
�{���ɏ�����Ă��邱�Ƃ́A�P�Ɋ�Ƃ����̘b�ł͂Ȃ��A�m�o�n���܂߂āA���܂��܂ȑg�D���������Ă���l�ɂƂ��Ă��A�����ɕx��ł��܂��B
���҂́A���Ƃ����ŁA��l�ЂƂ肪�l�Ԃ̐������ʂ����A�ڂ̑O�ɂ���A�����̃r�W���������������邨��`�������邱�Ƃ��A�{���ɍ��߂��u�r�W�����v�ł��A�Ə����Ă��܂��B
�܂�A���̖{��ǂ�́A�ǎ҂�����ɂȂ��āA������N�����Ăق����Ƃ����킯�ł��B
���ЁA�݂Ȃ�����{����ǂ�ŁA����̑g�D��ς��Ă����A�`�F���W�E�A�[�e�B�X�g�ɂȂ��Ăق����Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA���₳��́A�����g�D�ɂ����ĒN�����n�߂���u�o�C���f�B���O�E�A�v���[�`����ҁv�Ƃ��āA
�w�����͂̋������x�i�_�C�������h�Ёj�������Ă��܂��B����������ēǂ�ł���������Ǝv���܂��B
�R�����Y���X����w��


���u�miko�ɂ��J���{�W�A�v�i��Ӂ@���|�Ё@2014�j
����A�����ɂ���Ă����A�miko����A���Ə������q���炢���������{�ł��B
��N�o�ł��ꂽ�{�ł����A���Љ�Ă����܂��B
��������́A2010�N�A32�N���������w�Z���@��ސE���A�����Ȃ����t�c�̈���Ƃ��āA�Q�N�ԁA�J���{�W�A�ŋ����{���{�����e�B�A�����Ă��܂����B
���ꂪ�ƂĂ��y�����h�������������ŁA���������A�u���O�ɏ�������ł����L�^�����ƂɁA�A����A�{�ɂ܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�������Ă����̂́A�v�m���y������100�L�����ꂽ�X�������Ȃ��c�ɒ��v���C�y���B
���{�Ƃ͑S����������E�ɔ�э���ŁA�˘f���Ȃ�����A�ƂĂ��y���������Ǝd����2�N�Ԃ̋L�^�ł��B
���̂Ȃɂ��Ȃ������L�^�̒�����A����Ƃ͉����A�Љ�Ƃ͉������l����������{�ł��B
���������g���A���̑̌��ɂ���āA������ς�����ƌ����Ă��܂��B
2�N�Ԃ�œ��{�ɖ߂��Ă������ɂ́A�����̓��{�l���Â���ʼn��������ĕ����A�X�}�z�������Ă��邱�ƂɁA�傫�Ȉ�a���������ꂽ�悤�ł��B
���Ԃ�A�J���{�W�A�ɍs���O�̓��{���A�����������̂��낤�Ǝv���܂����A�����ɋ���Ƃ��̈ٗl���ɋC�Â��Ȃ��̂�������܂���B
���������̌�����A���ꂩ��̓��{������܂ňȏ�ɋC�ɂȂ肾�����悤�ł��B
�����āA���{�ł��ł��邱�Ƃ����낢��Ƃ���̂ł͂Ȃ����ƁA���܂͂��܂��܂Ȋ����Ɏ��g�݂����Ă���悤�ł��B
����o�ł̖{�Ȃ̂ŁA���܂�ڂɓ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂��̂ŁA�����ďЉ���Ă��炢�܂����B
�������A�}�]��������w���ł��܂��B
�J���{�W�A�ɊS�̂���l�͂������A����ɊS�̂�����ɂ������߂��܂��B

���u�B���_�v�i���^��@�O�܊ف@1800�~�j
���^�炳�A�������Łu����܂ł̎��M�����̏W�听�v�Ƃ����قǁA�v�������߁u�B���_�v���������܂����B
���̎v���̐[���́A�u�B���_�v�Ƃ��������ɂ��\��Ă��܂��B
���E�ρA���j�ρA�����Đl�ԊρB
�����������̂̊��Ɂu���v��u�����A���^��̐��E�������ɕ`���o����Ă��܂��B
�u���v�Ƃ͂Ȃɂ��B
�������́A�l�Ԃ̂��ׂẲc�݂́u���v�Ƃ����R���Z�v�g�ɏW���ƌ�����܂��B
�\����ς���ƁA�u���V�Ƃ͐l�ނ̑��݊�Ձv�ł���Ƃ����̂ł��B
�P�Ȃ�s�ׂł͂Ȃ��A���݊�Ղł���A���W��Ղ��Ƃ����̂ł��B
�����āA�u���Ƃ����s�ׁv�ɂ͐l�ނ̖{�����B����Ă���Ƃ�����_�ɗ����āA���E�Ɛl�ԁA�����ƕ����A�����ĉߋ��Ɩ����������ق����Ă����̂ł��B
�{���͂P�W�͂���Ȃ��Ă��܂����A�ŏ��ɒu����Ă���̂́u�F���_�v�B
�����čŏI�͂��u���V�_�v�B
���ꂱ���}�N���R�X���X����~�N���R�X���X�܂ł��A�Ȃ���Ȃ���c���ɘ_�����Ă����܂��B
������P�Ȃ鎄���̓W�J�����ł͂Ȃ��A��l������Ă������Ƃ�~�ς���Ă������j��l�Êw�̒m���܂��Ȃ���A�_��W�J���Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA�{���̍\���́A
�F���_�^�l�Ԙ_�^�����_�^�����_�^�_�b�_�^�N�w�_�^�|�p�_�^�@���_�^���E�_�^�Վ��_�^���k�_�^�H��_�^���Ҙ_�^��c�_�^���{�_�^��[�_�^�ߒQ�_�^���V�_�ł��B
���̖ڎ������ł����|����܂��B
�l�ނ̕������������A���̔��W�̍���ɂ́u���҂ւ̑z���v���������ƈ������͌����܂��B
�������A�����ׂ��́u���v�ł͂Ȃ��u���v�B
������w�B���_�x�ł͂Ȃ��w�B���_�x���Ə����Ă��܂����A�w�B���_�x�Ɓw�B���_�x�ł́A�x�N�g�����܂�������������E�ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���܂��B
����ɁA�u�B���_�v�́A�u���v�̖{���ɂ���u�W���v����A�_������Ԃ��čL�����Ă����܂��B
���Ƃ��A���ɂ���āA�l�ނ͊��Ƃ��ė^����ꂽ���R���E�Ƃ͕ʂ́A�u������̐��E�v��n�����A����̐����鐢�E�̎�����L���ɂ����Ƃ����c�_���L����̂ł��B
�u���v���N�_�ɒu�����Ƃɂ���Č����Ă���_�C�i�~�Y���ɋC�Â�����܂��B
�u���v�Ɋւ��Ă͂悭����܂����A�u���v������قǍL�͈͂ɁA�܂��̌n�I�A�N�w�I�Ɍ��ꂽ���Ƃ��A���͉Ǖ��ɂ��Ēm��܂���B
���́A��������̎����ƋC�Â������炢�܂����B
���Љ�������b�Z�[�W�͂�������܂����A�ƂĂ����̒Z���Љ�L���ɂ͏����܂���B
���Ж{�������ǂ݂���������Ǝv���܂����A������A�{���ɖ��ߍ��܂�Ă��锚�e�̂悤�ȕ��͂��Љ�Ă����܂��B
�����ɁA�{���̂�����̈Ӗ����ǂݎ���Ǝv������ł��B
������ƒ����Ȃ�܂����A�{��������p���܂��B
����́u���v�����u���v���N���[�Y�A�b�v����邾�낤�B
�u���v�Ƃ������ɂ͑�����ނ肪����悤�ɁA���̉��A�܂�n���Ɏ��҂߂�Ƃ����Ӗ�������B
�u���v�ɂ͂��܂ł��n����A�z������u�n���ւ̂܂Ȃ����v���܂Ƃ����B
����A�u���v�͓V���ɍ��𑗂�Ƃ����u�V��ւ̂܂Ȃ����v�ւƐl�X�����R�ɗU���B
�u���ւ̑����v�ɂ���āA���V�́u���V�v�ƂȂ�A�����́u�����v�A�����đ��Ղ́u���Ձv�ƂȂ�B
����I�ȃ��b�Z�[�W�ł��B
�������́A�u���v���N�_�ɐ��E�����Ȃ���A�u���v���u���v���Ƃ����̂ł��B
�u�B���_�v����Ȃ���A�u���v�����u���v�H�@�������܂��B
���́A��������Ɏ~�߂܂����B
�������̒���u�B���_�v�́A���̍����ɂ���u���v���̂��̂��܂��A��ɑ��������Ă����Ƃ����_�C�i�~�Y������݂��Ă���̂��A�ƁB
���́A�������͂����ƈȑO����A�u���ʑ��v��u�V�v����Ă���̂ł��B
�������́A�{��������܂ł̏W�听�ƈʒu�Â��܂����B
����͓����ɁA���ꂩ��̏o���_���Ƃ������Ƃł��傤�B
�{���́A���E�̐V�������������������Ă���܂��B
�����{����ǂ�ŁA����̐��������܂߂đ傫�Ȏ��������炢�܂����B
�������A�����Č����A���̐��E�ρA���j�ρA�l�ԊςɊ�Â����A���^�炳��̐��E����j�Ɍ����Ắu�B���_�v�I���b�Z�[�W�����҂������ł��B
���R�������͂������l���ł��傤���A���삪�y���݂ł��B
�����{�ł����A�͌��ĂɂȂ��Ă���̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
���Ђ���Ɏ���Ă݂Ă��������B
���u�i�����v�i���^��@���㏑�с@1200�~�j
�ʖ�����ʎ����s�킸�Ɉ�̂��Α���ɒ��s�����ďċp����u�����v�B
����ɁA��̂��ċp��A��D�������A�炸�Ɏ̂ĂĂ��܂��u�O�i�[���j���v�B
�������������������Ă��邻���ł��B
���V�s�v�_����������炸����Ă��܂��B
�������������ɑ��āA�Ăш��^�炳�A���V�̈Ӗ����Ă��˂��Ɍ���Ă��ꂽ�̂��A�{���ł��B
���łɁA���������u�����͕K�v�I�v���㈲���Ă��܂����A�{���́A�l�Ƃ͉����A�Ƃ����Ƃ���܂ł����̂ڂ��āA
���V�̖{���Əd�v�������ƂƂ��ɁA�������̐������⌻�݂̎Љ�̂������₢�����A����ɂǂ������炻���������甲���o���邩���������Ă���܂��B
�������́A���V�Ƃ����c�݂���߂�A�l���l�łȂ��Ȃ�Ƃ����܂��B
�l�ԂƂ́u�z���E�t���[�l�����v�i����l�ԁj���Ƃ����̂��������̑O�X����̎��_�ł��B
�������A���V�ɂ���āA�L���̑��݂ł���g�l�h�́A�����̑��݂ł���g���h�ƂȂ�A�i���̖���B
���V�Ƃ́A���́u���v�̃Z�����j�[�ł͂Ȃ��A�u�s���v�̃Z�����j�[�ł���A�l�͉i���ɐ����邽�߂ɑ��V���s���A�Ƃ����̂ł��B
�ƂĂ������ł��邾���łȂ��A�����ɖ������l����傫�ȃq���g�������܂��B
�������́A���V�͎c���ꂽ�l�X�̍��ɂ�������G�l���M�[��^���Ă����Ƃ������Ă��܂��B
�����A�����̑̌����炻���m�M���Ă��܂��B
�����ł���A���V�͐l�ނ̔��W�̌����͂ɂ��Ȃ��Ă����ƌ����Ă����ł��傤�B
�������́A���V�����l�ނ̖ŖS��h���m�b�������Ə����Ă��܂����A
�������V�̕����������A�l�ނ̖����͂ǂ��Ȃ�̂��B
�Z����I�ɁA���V�s�v�_��V�ȑf���_�������镗���ɁA�����傫�Ȋ뜜�������܂��B
�g�߂Ŏ����ŋߑ̌����܂������A�������O�����A�D���D��ł������Ă���l�͏��Ȃ��͂��ł��B
�{���́A�݂�Ȃ�����Ƃ������V���s�������̂ł��B
���������ł���A�N�������V���s����Љ��ڎw���K�v������܂��B
�������́A�{���ŁA�u�킽���́A�Ȃ�Ƃ��A���S���ĘV���邱�Ƃ��ł���Љ�A���S���Ď��ʂ��Ƃ��ł���Љ�A�����Ĉ��S���đ��V����������Љ���������邨��`�����������Ǝv���Ă��܂��v�Ə����Ă��܂��B
�N�����A���S���đ��V����������Љ�B
���̂��Ƃ��������͂����Ɛ^���ɍl����ׂ��ł͂Ȃ����B
�������g��ł��Ă��銈�����A�����ɂȂ���̂ł͂Ȃ����B
���ꂪ�{����ǂ�ŁA�����C�Â������Ƃ̂ЂƂł��B
�������́A���̂��߂̃L�[���[�h�Ƃ��āu�i�����v������Ă���܂����B
�ƂĂ������͂����郁�b�Z�[�W�ł����A�����������Ԏ��ɉ����Ă������Ԏ��Ƃ��āA�u�Љ�v�Ƃ������_�����邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
����Ԃ����Љ�������ł���A�N�������Ɗ�{�I�l���Ƃ��Ă̑��V���������邩������܂���B
����Ȃ��Ƃ܂ōl����������{�ł��B
���Ȃ݂ɖ{���ɂ́A���{���������u�����̎v�z�v�Ƃ��������l���i���ɋ��{����d�g�݁A�����ĉi�����̋�̓I�Ȓ�Ă��킩��₷��������Ă��܂��B
����ɍŌ�̏͂ŁA�������͎��炪�ւ���Ă������d���ł��銥�����Ռݏ���̊�����U��Ԃ�A���ȂƂƂ��Ɍ��ӂ��q�ׂ��Ă��܂��B
���̈Ӗ��ŁA�{���͐ӔC�ӎ��Ɏx����ꂽ�A�M���ł��郁�b�Z�[�W�ł��B
�����ȑ��V�s�v�_�ŎЉ���Ă������ӔC�ȕ����ɍR���Ă���������ɔ���𑗂肽���ł��B
�P�Ȃ鑒�V�_�ł͂���܂���̂ŁA���Б����̐l�����ɓǂ�ł������������ł��B
�ڂ������e��������̎v���́A�������̃u���O�����ǂ݂��������B
http://www.ichijyo-shinya.com/message/2015/07/post-775.html
���u�ٔ��ɑ�����������v�i���^�Y�@���{�]�_�Ё@1700�~�j
���Z���ゾ�Ǝv���܂����A�u�^���̈Í��v�Ƃ����f����ς܂����B
����́A���Ђ낵�́w�ٔ��]�l�̖��͌��͂ŒD������̂��x�ŁA�l�ߎ����Ƒ����ꂽ���C�������ނɂ������̂ł��B
�l�ߎ����̋��낵�������A���ɕ`�����ƂƂ��ɁA������Ȍx�@�̑{���������������e�ŁA�Љ�h�f��̑�\�I����ƕ]���ɂȂ����f��ł��B
�f����ς��A�蓹�A�����Ƌ����{�肩��������܂���ł����B
���ꂪ�A�����u�����v�i�ٌ�m�ł͂���܂���j�ɂȂ낤�Ǝv�����ŏ��̂��������ł����B
�����āA�@�w���ɓ��w���܂������A���낢��Ƃ����āA�@���E�ւ̓��͒f�O���܂����B
��w����̓������̈�l���A���̖{�̒��҂̑�삳��ł��B
��w�𑲋ƌ�A�v���Ԃ�ɉ�������ɂ́A�ނ͓��{�ٌ�m�A����̎��������ł����B
�ނɉ��������A��삳��͎������ւ����������{�ɂ����u�L���Y�Ɣp�����s�@���������v�𑗂��Ă��Ă���܂����B
���̒��ŁA�ٌ�m�Ƃ����d���̑������������ς��܂����B
�{���́A���̑�삳����܂Ŋւ�����V�̍ٔ��ɂ��Ă܂Ƃ߂��S���ڂ̒����ł��B
�͂������ŁA��삳��͂��������Ă��܂��B
�@�����ٌ�m�����̂Ȃ��ŁA�ٔ���ʂ��āA���X�̂�����Ė��͓I�Ȑl�X�ɏo������B
�@�����̂Ȃ����������̏�ŁA���X�̎��������z���������҂�̂悢�M�O�A�E�C�A�E�ρA���f�A�����ĂȂɂ��l�Ԑ��ɐS��ł��ꂽ�B
�ŏ��Ɏ��グ���Ă��鎖���́A�����̂Q�N�����͔ƍ߂Ɠ����������ł��B
�ǂ�ł��āA�܂��ɂ��́u�^���̈Í��v���v���o���܂����B
�v���Ԃ�ɂ܂��Ⴂ����̓{�肪�S�g�ɂ��݂������Ă���̂������܂����B
���Z���̍��̎v���͂ǂ��ɒu���Ă��Ă��܂����̂��ƁA�����������ӂ̔O�������т܂����B
�Â��āA�x�@�̖\�͂ɐE�ӂ���蔲�����ٌ�m�A�W�c�\�͂ɋ������E�ӂ��т����n���c���A��C�����ɗ����オ�����s�������A��Ƃ̕s���v�����������Ȃ����������J���҂����A���U�̈�Éߌ덐���˕Ԃ����S���O�ȋ����A��ʂɕs�@�������ꂽ�Y�Ɣp�����̓P�������ߑ��������������A�Ƃ������U�̎����L�^�������܂��B
��������킢��]�V�Ȃ����ꂽ�����҂����̋L�^�ł��B
��삳��́A���̓����҂����Ɋ��Y���Ȃ�����A�����I�Ɏ����̂ĂƂ��̈Ӗ��A�����ē����҂����̐�����������Ă��܂��B
�V�̎����ɋ��ʂ��Ă���̂́u�l�Ԃ̑����v�̉ł����A���ꂾ���ł͂���܂���B
�ٔ��̌��ʁA�V���ȗ��@�̌_�@�ɂȂ�ȂǁA�u�Љ�̑����v���܂����ꂽ�̂ł��B
��삳��͂��������Ă��܂��B
�@�����A�����҂炪�ٔ��ɗ����オ�炸�A�l���N�Q�ɋ����Ă����Ȃ�A
�@���炪�������s���v�����܂I����������łȂ��A
�@�@�ɂ���ĕۏႳ�ꂽ�l�����̂��̂������I�Ɏ����邱�ƂɂȂ�����������Ȃ��B
�����āA19���I�̃h�C�c�̖@���ƃC�F�[�����O�̖����u�����̂��߂̓����v�i���ɉ��������ł��j�Ɍ��y������A���������Ă��܂��B
�@�킪���̌��@���u���̌��@�������ɕۏႷ���{�I�l���͍����̕s�f�̓w�͂ɂ���ĕێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��Ă���B
�@�l���͏�ɐN�Q�̊댯�ɂ��炳��Ă���B
�@�l���N�Q�̕s�@�ɑ��ẮA�E���Ȃ������������߂��A���̂��������������̐l�̖_������邾���łȂ��A����������ɂ��悢�����ɐ����E���W�����邱�Ƃɂ��Ȃ�B
���܁A���̌��@���̂��̂���@�ɕm���Ă��鎖�Ԃ��������Ă��܂����A�C�F�[�����O�������悤�ɁA���@������͍̂����̕s�f�̓w�͂����Ȃ̂ł��B
�����āA�{���̂V�̕���́A���̗E�C���v���o�����Ă����ł��傤�B
���Б����݂̂Ȃ���ɓǂ�ł������������Ǝv���܂��B
�R�����Y���X����w��

�֑���t��������A�i�@�E�݂̂Ȃ���ɂ����Гǂ�łق������̂ł��B
��삳��́A�Ō�ɂ��������Ă��܂��B
�@21���I�ɂ����āA�i�@�͑��̐������͂���Ɨ����A�����̌����A���R�A�����`�̒S����Ƃ��āA���M������A���肪���̂��鑶�݂ɂȂ�˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
���������肢�܂����A�c�O�Ȃ��猻�݂̎i�@�E�́A����̑����������Ă��Ă���悤�Ɏv���܂��B
��삳��́A����u�i�@���v�v�ɂ����Ă��傫�Ȗ������ʂ����A���̌o�܂��ڂ����{�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B
�c�O�Ȃ���A���͂��̎i�@���v�͂��܂苤���ł��܂��i���O���������Ȃ�����ł��j�A�@���E�̐l�����ɂ́A���߂āu�i�@�Ƃ͉����v����������ƍl���Ăق����Ǝv���܂��B
���݂܂���B�܂��Ɏ֑��ł��ˁB
���u����ł��l���ɂx�d�r���v�i�x�~�N���@WAVE�o�Ł@1300�~�j
�����̎v�������߂āA���̖{��n�����ҏW�҂̋ʉz����A���̖{���o���_�ɂ��āA�x�d�r�^�����n�߂����ƌ����āA���̖{�����������܂����B
�����Ɏv���o�����̂��AV.E.�t�����N���́u����ł��l���ɃC�G�X�ƌ����v�ł��B
�����̐l�ɐ�����͂�^�����{�ł��B
�{�����܂��A�x�d�r�Ƃ����u���@�̌��t�v�Ŏ���̐l����ς��Ă����x�~����Ƃ����l�̑̌����琶�܂ꂽ�{�ł��B
�u����ł��l���ɃC�G�X�ƌ����v���{�łł��B
���Ԃ�x�~����Ƌʉz����̍��̏o�����A�{���͐��܂ꂽ�̂ł��傤�B
�ʉz����́A�u�����g���A��悩��ҏW�܂ň���s�����A�v������̋����{�ł��v�ƌ����āA���ɂ��̖{��n�����̂ł��B
����A�ʉz����̓��[���ł��������Ă��܂����B
��������������Љ�́u�I�A�V�X�v�A�S�D�����l�X�ւ́u�S�̏�v�ƂȂ�{���Ɗm�M�������܂��B
���̖{�̃V���[�Y����ɂ����u�x�d�r�^���v����{���ɍL�߂悤�Ə������ł��B
�ʉz����̎v�����`����Ă��܂��B
�������Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B
�x�~����͖{���́u�͂��߂Ɂv�ł��������Ă��܂��i�v�Ă��܂��j�B
�uYES�v�Ƃ������t�ɂ́A�s�v�c�ȗ͂�����Ǝ��͎v���܂��B
�uYES�v�̂������ŁA�����g�Ó]���������l�������x���D�]�����A����▜���s���ďI�����邩�̂悤�Ɍ������l�����A�����E�Đ������A�������g�𗧂����点�Ă�������ł��B
���Ă̎��́A�l�����m�肵�����Ƃ�����܂���ł����B
�c�����A�d�a�œ��@���Ă������Ƃ��Â������������̂ł��B
����ƎЉ�ɏo�Ă��A�����̐l��������ے肳�ꑱ���A�l���̂��ׂĂ�ے肵�Đ����A�S�͘c�݁A�a�I�ƂȂ�A�s�K�̉�ƂȂ��Ė����𑗂��Ă��܂����B
���͎Ⴂ���ɁA���ׂĂ̖��Ɗ�]���������̂ł��B
���̕x�~����̐l����ς����̂��A�uYES�v�Ƃ������t�ł��B
�����āA�x�~����́A�u���̐g�ɋN�������ƁA���ۂɋN�������o�����ɉ����āA�����~������ʂ̌��t�������A��ɒ��J�ɁA�S�����߂Ĉ���̖{�v�ɂ܂Ƃ߂��̂ł��B
���̊����I�Ȃ��b�́A���Ж{���ł��ǂ݂��������B
�ʉz����́A�x�~����̌Ăт������āA���E�ɁuYES�^���v���L�������ƍl���Ă��܂��B
�܂��L���Ăт����͎n�܂��Ă͂��܂��A�쐬���̎�ӏ���ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�ƂĂ��킩��₷���A�������A�ƂĂ����H�I�ȌĂт����ɂȂ��Ă��܂��B
�W�́u�x�d�r�v�̌��t����Ă���Ă��܂��B
��������ɂ����ŏЉ��킯�ɂ͂����܂��A�߁X���J�����ł��傤�B
�x�~����́A�u���̂W�̌��t���u�x�d�r�v�^���̂͂��܂�ɂȂ�܂��B���E���̑����̐l�X�����̌��t���g�����������Ɋ�]�������A���a�ݏo���܂��v�Ə����Ă��܂��B
���S�̂�����́A�ʉz����ɂ��Љ�܂��B
�ł����̑O�ɁA���Ж{����ǂ�ł݂Ă��������B
���Ȃ��̐l����ς��Ă���邩������܂���B
����Вn�f�C�Y�i��獎��Ғ��@�O�����@2400�~�j
��N�o�ł��ꂽ�{�̏Љ�ł��B
�������g��ł���u�R���P�A�����v�̃��[�����O���X�g�����o�[���A�����̐l�ɓǂ�łق����Ƒ����Ă��Ă���܂����B
�ǂ܂��Ă��炢�A���������̐l�ɓǂ�łق����Ƃ����C�ɂȂ����̂ŁA�Љ���Ă��炢�܂��B
�{���́A�u����QUEST�v�V���[�Y�̑�1���ł��B
���̃V���[�Y�́A�u�����̂Ȃ��₢���l����v���Ƃ�ړI�ɑn�����ꂽ���̂ł����A
�{���́A�w�N���X���[�h�x�ƌĂ���@���q���g�ɁA
�ǎ҂����闧��ɂȂ�������ŁA�ЊQ���̃W�����}���l����h�ЃQ�[���̃X�^�C�����Ƃ��Ă��܂��B
�S����31�̖₢��������A�����^����ꂽ�u����v�ɗ����āA�܂��͉��A���ꂩ�����L����ǂނ킯�ł��B
��l�̂ōl���Ȃ���ǂނ��ƂɂȂ�̂ŁA�����̖��Ƃ��Ă�������ƍl�����܂��B
1���̖{���A���������X�^�C���œǂ̂͏��߂Ăł����A
�ǂ�ł��������ɁA�u�����̐������v�������ł��A���߂Ď����₢�������悤�ȋC���ɂȂ�܂����B
���̂������ŁA�u�ЊQ���ɂ�����m�b�v�ȏ�̂��̂��C�Â����ꂽ�C�����܂��B
�{����31�̖₢�́A��_�W�H��k�Ђ̎���Ɋւ��čs��ꂽ�A��Ў҂ւ̕�����蒲���f�[�^�܂��č쐬����Ă��邻���ł��B
���̂������A����͂������ăV���v���Ȃ̂ł����A������������������Ă��܂��B
����ɁA�����̎��₪�A���Ԏ��ɉ������u�ЂƂ̕���v�Ƃ��ĕҏW����Ă���Ƃ���������ł��B
���w���K�X�^�C���Ŋw�Ԃ��Ƃ��ł��܂����A�����݂�Ȃōl����A�m�o�n�ł̊w�т̃e�L�X�g�Ƃ��Ă����ʓI�ł��傤�B
����́u�ЊQ�ҁv�ł����A�u���ҁv�u�Ō�ҁv�ȂǁA�����ȕ���ł́u����QUEST�v�V���[�Y���҂��y���݂ł��B
�m�o�n�����Ɏ��g��ł���l�����́A�ڐ�̖������ŖZ�����ł��傤���A
���ɁA���������u�N���X���[�h�E���[�N�V���b�v�v�����ƁA���̊���������Ɍ��ʓI�Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�ȂƎv���Ȃ���A�ǂ܂��Ă��炢�܂����B
���Б����̐l�����ɓǂ�łق���1���ł��B
�{���̓��e�̐����́@���[�`���[�u�ł̏Љ����܂��̂ŁA��������Ђ������������B
https://www.youtube.com/watch?v=q16pIM8dIcI
���Љ�Ȋw�Ƃ��Ă̕ی��_�i�{�ԏƌ��@�����Ё@1983�N�o�Łj
���̃R�[�i�[�́A���̗F�l�m�l���ŋߏo�ł����{���Љ�Ă��܂����A�����30�N�O�ɏo�ł��ꂽ�{�̏Љ�ł��B
���҂̖{�ԏƌ�����i�R�w�@��w�����j����ŋ߂����������{�Ȃ̂ł����A�ǂ�ł݂āA���܂Ȃ��i���܂����j�ǂމ��l������Ƃ����v������Љ���Ă��炢�܂��B
����ɖ{�Ԃ���́A�u�ی��������Ƃ͖����̂��̂Ǝv���Ă���l�тƁA�ی������������̌����ΏۂƂ͂�����肪�Ȃ��ƍl���Ă��錤���҂����ɂ���Ă����A�{�����ǂ܂�邱�Ƃ���]����v�Ə�����Ă��邱�ƂɁA������������ł��B
����ɁA40�N�O�ɖS���Ȃ����������������іk��Y����Ƃ̋����Ƃ����`�Ŗ{�����o�ł��A����̐������܂ł��ς��Ă������{�Ԃ���̐��������A�����̐l�ɒm���Ăق�����������ł��B
���{�ɂ�����ی��́A���܂ł͂������S�ȋ��Z���i�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂����A�{���A�����ɂ́u�댯��S�ۂ��A���������肳����v�Ƃ������O���������͂��ł��B
�{���̖`���ŁA�{�Ԃ���́u����̔��B�������{��`���ɂ����āA�ی����ʂ����Ă���L�͂��d�v�ȋ@�\�ɂ��āA�����ے肷��҂͊F���ł��낤�v�Ə����Ă��܂����A�������̐������x���Ă���̂��u�ی��v�ł��B
���Ƃ��A���������Ԕ����ی����x���Ȃ�������A�����Ԃ��C�y�ɉ^�]���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤�B���N�ی����Ȃ���A�d���a�C�ɂ����邱�Ƃ������̔j�]�ɂȂ���ł��傤�B�������̐����́A�ی��ɂ���Ďx�����A�Љ�̈���͕ی��ɂ���Ĉێ�����Ă���ƌ����Ă������ł��傤�B
�������A���́u�ی��v���A�傫���ώ����Ă��Ă��܂��B
�{�Ԃ���́A���N�A�ی��̗ɑ��錜�O��\�����A�Љ�ɒ��Ă����l�ł��B
�o���ϖ��������̊�{�ɒu���Ă���A�����Ȃ��o�ϊw�҂ł�����܂��B
�{���̏o�ł̗��R���A�u�]���̕ی��w�̂��肩���Ƃ��̌o�ϊw�ɂ�����ʒu�v�ɑ���^�₩��A���̌��ׂ𖾂炩�ɂ��A�o�ϊw���̂��̂�����ɒu�����A���ꂩ��̕ی��_���\�z���邽�߂��Ɩ�������Ă��܂��B
30�N���O�̘b�ł����A���������ƂɁA�͂��܂ނ��눫�����Ă��܂��B
�{�Ԃ��A���������ۑ�����C�t���[�N�ɂ��邱�ƂɂȂ����_�@�̂ЂƂ́A80�N�O�i����E���O�ł��j�ɏ����ꂽ�ݖ�̕ی������ҁA���іk��Y����̘_���Ƃ̏o��ł��B
���т���́A�}���N�X�o�ϊw�̎��_�ɗ����āA�ی��̂�����A�ی��J���̂�����A�����Čo�ς�Љ�̂������_�l���Ă��܂��B
�{���́A���т���̘_�l���2���ɒu���A��1���Ŗ{�Ԃ����̗v�|��������A��������{�Ԃ���́u�Љ�Ȋw�Ƃ��Ă̕ی��_�̓W�]�v�������Ă��܂��B
�w�p���X�^�C���Ȃ̂ŁA�C�y�ɓǂ߂�{�ł͂���܂��A���т����{�Ԃ���̐[���v�����`����Ă��܂��B
�{�Ԃ���⏬�т���́u�ی��_�v�͖{����ǂ�łق����ł��B
���Ȃ݂ɁA���̐S�ɋ������A�u���Ƃ����v�̖{�Ԃ���̕��͂����Љ���Ă��炢�܂��B
�����Ȃ����̂�������悤�ɂ��邱�ƁA�ڂ̑O�̍��ׂƂ������ۂ̐��E����{�������������ƁA���̂��߂̊�͂��₵�Ȃ����Ƃ������Ȋw�ł���Ƃ���Ȃ�A�ی��́A�Ȋw�̐��E����Ȃ�Ɖ������݂ł��������Ƃ��B�����āA���̂��Ƃ��A�Ȋw�ɂƂ��Ă̑傫�ȕs�K�ł��������Ƃ��v�킸�ɂ͂����Ȃ��B

���P�A�̎n�܂�ꏊ�i����i�q�E�|������ҁ@�i�J�j�V���o�Ł@2015�j
���M�҂̈�l�ł����G�����炢���������{�ł����A�薼�����ɖ��͓I�ł��B
���̖{�̘b�͓킳�炨�������Ă��܂������A�܂������������^�C�g�����Ƃ͎v���Ă��܂���ł����B
���́A21���I�̑傫�ȗ���́A��]�I�ϑ������߂āu�}�l�[����P�A�ցv���Ǝv���Ă��܂����A�܂��ɂ����������̎v�l����������^�C�g���ł��B
�{���̎��M�҂������܂��A21���I�̓P�A�̎���Ƃ������_�ɗ����Ă���悤�ł��B
����Ɂu�N�w�E�ϗ��w�E�Љ�w�E����w�����11�́v�Ƃ���悤�ɁA�{���͂��܂��܂ȕ���̌����҂ɂ����H�I�P�A�����̘_�l�W�ł����A���̓��e���^�C�g���ȏ�ɖ��͓I�ł��B
�������A�u�P�A�v�����Â̐��E�ɕ����߂Ă��Ȃ��Ƃ���ɋ����ł��܂��B
�P�A�́A���������g�̐����邱�Ƃɓ��݂��Ă�����̂ł����āA��҂ւ̎v�����Ƒ����Ă��܂����r�[�ɁA���������Ȃ��Ă������Ƃ��A���͑̌����Ă��܂����B
�ł�����u�������͓��X�N�����P�A���C�N���ɃP�A����Ă���v�Ƃ����Ƃ��납��o�����Ă���{���̎p���ɋ��������������܂��B
�������A�{�����u�P�A�̎n�܂�ꏊ�v�Ƃ��ĂƂ肠�������̂́A���킩������܂ŕ��L���A���҂ւ́u���݁v��ЊQ�ɂ���Ă����炳�ꂽ�u�ɂ݁v�ɂ܂ŋy��ł��܂��B
���ɁA����ւ̃P�A(���̃e�[�}��킳���M���Ă��܂��j���܂܂�Ă��邱�Ƃɋ����ł��܂��B
���ׂẴP�A�́A����ւ̃P�A����n�܂�Ƃ����̂��A���̍l��������ł��B
���ꂼ��̘_�l�̒��ɁA�_�҂̈�l�̓I�ȓ����҈ӎ��������邱�Ƃ������ł���Ƃ���ł��B
11�̘_�l���Љ�����Ƃ���ł����A���̃R�[�i�[�͏��]�ł͂Ȃ��̂ŁA�ڎ������̏Љ�ɂ����Ă��炢�܂��B
��������{���̎p���⎷�M�҂����̈ӋC���݂���������Ǝv���܂��B
��1�� �R�~���j�P�[�V�����Ƃ��ẴP�A
��2�� �����I�`���_�ɂ�����o���̒��ڐ��Ɓq��r
��3�� �q�����Ă���r�i���V�V�Y���Ɓq���A����r�i���V�V�Y��
��4�� �D�P�̐g�̐��\�t�F�~�j�X�g���ۊw�̊ϓ_����㗝�o�Y���l����
��5�� �q���x�����Y���̐��B�_�r����q�P�A�ϗ��̐��B�_�r��
��6�� �u����v�Ɓu�P�A�v���߂��鑊���\�u�c�ۈꌳ���v�̌�������
��7�� �W���Ƃ��ẴP�A�\�u���v�̌��т��Ɓu�����v�̊W�\�z
��8�� ���҂ƃP�A�\�P�A�ɂ����đ��݂����鎀��
��9�� �u���X�N�v�Ƃ�������ɓ鉻��������Љ�
��10�� �q�j�Ёr�Ɓq���̂��r�̑I��
��11�� �P�A�̎v�z�ƗՏ��m���Ȃ��\���Ȃւ̃P�A/�L���̃P�A��
���ꂼ�ꂪ���������_�l�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����̂���Ƃ��납��ǂ܂��Ƃ����ł����A���͂��������ǂݕ����珇�s���œǂ�ł��āA���ǁA�C�������炷�ׂĂ�ǂ�ł��܂��Ă��܂����B
�{���̏Љ�L���ɁA�u�P�A�̎�O�ɂ�����́v�ւ̎�������A�Տ��I�P�A���W�[�̃t�����e�B�A��A�Ƃ���܂��B
�܂�A�{���̈Ӑ}�́A�u�P�A���n�܂�ꏊ�v�ł́u�Տ��I�����I�Ȑ��v�̒���ł��B
���̂��߁A���̐��̕ҏW�ɂ͎����Ă��܂���B
�ǎ҂Ƃ��ẮA�ǂݏI�������ɂ���������Ǝv���܂��B
�Ō�̘_�l�ŁA�Ҏ҂̋���i�q���A�����������ƂɌ��y���A�P�A���W�[�̊T�ϐ}���܂Ƃ߂Ă��܂��i�{��232�Łj�B
���ɂ킩��₷���A�܂�����I�ȃr�W�����������܂��̂ŁA���ꂾ���͂�����ƈ��p�����Ă��炢�܂��B
���낢��Ə������������ł����A���]�ł�����L���ł��Ȃ��̂ō����T���܂��B
�u�傫�ȕ����v�𗝔O�ɃR���P�A�����ɂ����₩�Ɏ��g��ł��鎄�ɂƂ��ẮA���ꂼ��̘_�l���ƂĂ������[�����̂ŁA����Ӗ��ł͂��܂��܂Ȑ��Əꏊ���Ȃ��Ȃ���A�P�A�}�C���h���ӎ���������_�@�ɂȂ邩������Ȃ��Ǝv���Ȃ���A11�̘_�l��ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�ł���A����܂��Ă�11�l�̗��ݍ����Ȃ���̘b�������̑��҂������Ăق����Ǝv���܂��B
�Љ���Ɏ��g�ސl�����ɓǂ�łق���1���ł��B
�����������̂���_�ł����B

���u�����ĂȂ�����]�W���p�j�[�Y�E�z�X�s�^���e�B�̐^���v�i���^��@���ƔV���{��
1000�~�j
�u�ό��v�����߂Ē��ڂ��ꂾ���Ă��܂����A������A
����܂ł̘_�l�Ƒ̌��m�𒍂����u�ό��N�w�v�Ƃ������ׂ��u�����ĂȂ��_�v���A���Ղȓǂ݂₷���{�ɂ܂Ƃ߂Ă���܂����B
�u�����ĂȂ��v�̐S�i���_�j�Ƃ������i���H�j�̏��ł��B
�{���ւ̈������̎v����{���̓��e�́A�������̃u���O�̋L�����ƂĂ��Ȍ��ŕ�����₷���̂ŁA��������ǂ݂��������B
http://d.hatena.ne.jp/shins2m+new/20150217/p2
�������͐��͓I�Ȏ��M���������Ă��܂����A�������Չ�ЃT�����[�̎В��ł�����܂��B
���Ђ̃~�b�V�����́A�u�l�ԑ��d�v����{�ɂ����z�X�s�^���e�C�E�T�[�r�X�̒ł��B
�������͂܂��A�������Ղ̍��{���Ȃ��u��v�̐��_�ɂ����w���[���A���{�����_�ɂ��ʂ��Ă��܂��B
�u�����ĂȂ��v�͓��{�Љ�̊j�S�ł�����Ǝv���܂����A���������Ӗ��ł͖{���͓��{�����_�̓��发�ł���Ƃ�������ł��傤�B
�{���̒��ň������͂��������Ă��܂��B
���{�l�́g������h�́A�_���E�����E�̂R�̏@���ɂ���Ďx�����Ă���A�u�����ĂȂ��v�ɂ������̋��������荞��ł��܂��B
�u�����ĂȂ��v�́A���{�������̂��̂ł��B
���Ă̓��{�́A�����̍��Ƃ��āu�W�p���O�v�Ə̂���܂����B
���ꂩ��́A�����ĂȂ��̐S�Łu������̃W�p���O�v��ڎw���������̂ł��B
�ڎ������Љ�܂��B
�͂��߂Ɂ@�u�����ĂȂ��̎���`������̃W�p���O��ڎw���ā`�v
��P�́@�u�����ĂȂ��v�Ƃ͉����`�W���p�j�[�Y�E�z�X�s�^���e�B
��Q�� �@�u�����ĂȂ��v�̃��[�c��T��`�z�X�s�^���e�B�̌��������߂�
��R�� �@���{�l�́u�����ĂȂ��v�̐S�`�n�[�g�t���E�}�C���h�̂�����
��S�� �@�o�c�ɂ��K�v�ȁu�����ĂȂ��v���o�`�z�X�s�^���e�B�E�}�l�W�����g�̂�����
��T�́@�������ՂƁu�����ĂȂ��v�̍�@�`���}������@�̉��`
�����Ɂ@�u����`�����ĂȂ��̐V�����R���Z�v�g�v
�������ɋ������������̂́A�Ō�́u����`�����ĂȂ��̐V�����R���Z�v�g�v�ł��B
���Ȃ݂ɁA���́u�����Ɂv�́A�{���̃G�b�Z���X�̗v��ł�����܂����A���������ł������̐l�̓ǂ�łق����Ǝv���܂����B
���ׂĂ͏Љ�ł��܂��A�����ň������́A�u�b�_�̐����u���v�ƍE�q�̐����u��v�����т��āu����v�Ƃ����V�����R���Z�v�g����Ă��܂��B
�������́A���������Ă��܂��B
�u����v�܂�u�����݂Ɋ�Â��l�ԑ��d�̐S�v������A
�S�̂����������A�A�����V�A�Ί�A�����Ă�����T�[�r�X�̒��\�ƂȂ�܂��B
�����āA�u����v���A����̐����A�r�W�l�X�̐��E�ŕ\���������̂��u�����ĂȂ��v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����Ə����Ă��܂��B
���������Ȃ������A�������́u����v��_���ǂ߂邱�ƂƊy���݂ɂ��Ă��܂��B
�C�y�ɓǂ߂܂��̂ŁA�悩�����炨�ǂ݂��������B

���֒�_�Ɖ��l�؋��i�u�֒�_�Ɖ��l�؋��v�ҏW�ψ���ҁ@���݊�����Ё@3900�~�j
�Ƃ�ł��Ȃ��{�����������܂����B
���������́w����N����150���N�L�O�@�֒�_�Ɖ��l�؋��x�B
�F�l�̍��{�v�Ȃ��ҏW�ψ��ƂȂ���3�N������Ŋ��������{�ł��B
���{����̎�ɂ��鎩�݊�����ЂŔ��s���܂����B
���l���؊X�ɂ���֒�_�́A�����ېV�̏����O�ɑn���܂����B
http://www.yokohama-kanteibyo.com/
�����ɂ��A���������o�܂ł��B
���{�̊J�`�ƂƂ��ɁA����5�����̐l���������{�ɋ����\���f�Ղ��J�n���܂������A
���̒����l�������S�̎x���Ƃ��Ċ���N���J�����̂��A���l�֒�_�̎n�܂肾�����ł��B
2011�N���A���̒���150�N�ɓ�����܂��B
���̋L�O�Ղ̈�Ƃ��Ċ�悳�ꂽ�̂��{���ł����A
�\�z������傫���Ȃ��āA���ɍ�N�A�咘�Ƃ��Ė{�����������������ł��B
���{�v�Ȃ��炢���������ȏ�A������Ɠǂ܂Ȃ�������Ȃ��Ǝv���Ȃ���A
���܂�̌����i�`�S��347�ŁI�j�Ɉ��|����ĊJ���Ȃ������̂ł����A
���Ԃ̍��ԂɂӂƊJ���Ă݂���A�ʔ����čŌ�܂Łi������Ƃł͂���܂��j�ڂ�ʂ��Ă��܂��܂����B
���肾������̓��e�ŁA�O���邱�Ƃ�����܂���ł����B
�{���̓��e�́A���݊�����Ђ̃z�[���y�[�W�ɔC����Ƃ��āA�������ɖʔ��������_���R�_�����Љ�܂��B
���̑O�ɁA�֒�_�̐������K�v�ł��ˁB
�֒�_�͊���N���J��_�ł����A����N�Ƃ͎O���u�ŗL���Ȋ։H�ł��B
�։H���Ȃ��J���邱�ƂɂȂ����̂����ʔ����b�ł����A�ڂ����͓����ɔC����Ƃ��āA�։H�͒����ł͏����̐_�l�Ȃ̂ł��B
���̂��߁A�؋��̐l�����͊C�O�ɈڏZ����Ƃ܂����Ă�̂��֒�_�Ȃ̂������ł��B
���ċC�ɂȂ���3�_�ł��B
���݂̊֒�_��1990�N�ɍČ����ꂽ4��ڂ̌����ł��B
���̗��j���܂��h���}������܂����A�����A���l�؋��͑嗤�h�Ƒ�p�h�ɕ��Ă��������ł��B
�C�O�ɏo�Ă��Ă���؋��ɂƂ��Ă��A�̋��̒����̐������s�K�ȕ���������N�����Ă���Ƃ����Ƃ���ɁA���͊S�������܂����B
���ꂪ�P�_�ڂł��B
������l���Ă��������ł��A���ƂƂ͉����������Ă���悤�ȋC����������ł��B
����ɑ��锽�Ȃ���A�݂�Ȃ��͂����킹�Ċ֒�_���Č����悤�Ƃ��������ɂȂ����킯�ł����A�Č��݂͂�Ȃ̊�t�Ŏ������܂����B
���̊�t�҂̖��낪�{���̍Ō�ɏo�Ă��܂��B
3100���~�̊�t�҂���200�~�̊�t�҂܂ł������ɋL�ڂ���Ă���̂ł��B
���Ɋ������܂����B
���ꂪ�����S��������2�_�ڂł��B
�����ɉ؋������̑f���炵���������܂����B
������́A����150���N�L�O�s���̊J�Â�2011�N�ł����B
���̔N�͓����{��k�Ђ̂��߂ɁA���{�����������ȍÎ������l���Ă��������ł����B
���l�؋��̐l�����́A�������������ł�������A���C���݂�Ȃɗ^�������ƌ����āA�\��ʂ�L�O�s�����͂Ȃ₩�ɓW�J���܂����B
�ǂ��炪��Ў҂ɂ悩�������́A���̌�̓���������Ό����Ă��܂��B
�`����`�̓��{�l�Ǝ�����`�̉؋��̐l�����̈Ⴂ�������܂��B
�{���̓��e�Ɋւ���Љ���������������Ă����܂��B
�֒�M�̗��j�⌻�݂̐��E�̊֒�_�Ȃǂ̏Љ���ʔ����ł��B
�Ȃ��ɂ́A�֒�_�쌱�L�ȂǂƂ����L���܂ł���܂��B
�܂��A���l���؊X�̗��j�Ƃ������_����̋L��������܂��B
������Ԗʔ��������̂́A���܂��܂ȉ؋��̐l�����̋L�^��ʂ��āA���{�Ƃ������̎������_�Ԍ������Ƃ��Ƃł��B
���݁A�����W�����܂�悭����܂��A�؋��̐l������ʂ��āA�����ł��邱�Ƃ��������肻�����ȂƊ����܂����B
�����͔��s���������Ȃ��̂œ���͓����������܂��A���݊�����Ђ̍��{����ɖ₢���킹��A�w���ł��邩������܂���B
�������邾���ł���A�����ɂ����Ă���܂��B
�ς邾���ł��y�����{�ł��B
����ɂ��Ă��A�؋��̃p���[�����������邷�����{�ł��B
������ ��C�̌��t�i���^��ďC
KK�x�X�g�Z���[�Y1500�~�j
���^�炳��̊Ė�ɂ��w����@��C�̌��t�x���A����R���������J�n1200�N�ɂ�����2015�N��O�ɂ��ďo�ł���܂����B
��C�̖��O��m��Ȃ��l�͏��Ȃ��ł��傤���A��C���c�������t�́H�Ɛu�����Ɠ�������l�����Ȃ��ł��傤�B
��C�ɂ͈ꎞ���A�������ꂽ���Ƃ̂��鎄�́A���ʂ��炻���u�����Ɠ����邱�Ƃ��ł��܂���B
�{���́A��C��201�̌��t���A����X�^�C���ŏЉ�Ă���܂��B
�{���̓��e�́A���҂̈������̃u���O�ɏڂ����̂ŁA����������Ђ��ǂ݂��������B
http://d.hatena.ne.jp/shins2m+new/20141210/p1
������A���̎d����S������ň����A�v�������߂ĊĖꂽ���Ƃ��f���ɓ`����Ă��܂��B
���̃u���O�ŁA�������͂��������Ă��܂��B
����ɂ�݂���������C�̃��b�Z�[�W�͂����Ɠǎ҂݂̂Ȃ���ɂƂ��Đ������ł̑傫�ȃq���g�ƂȂ�͂��ł��B
201�̃��b�Z�[�W�́A���ꂼ��ƂĂ��Z�����̂ł��B
���ׂĂ�1�y�[�W�P�ʂɂȂ��Ă��܂��B
������C�y�ɂς�ς�ƊJ���āA���R�J���ꂽ�Ƃ���𐺂ɏo���ēǂނ̂������ł��傤�B
���́A�����ɖ{����u���Ă����A���N�������ƐQ��O�ɁA���������ǂݕ��ŁA���J���Q���ǂ�ł��܂��B
������܂�������Ə��]����Ƃ���܂ł����Ă��܂��A���̓ǂݕ���������ƋC�ɓ����Ă��܂��B
�݂Ȃ���ɂ������߂ł��B
���Ԃ낢��ƋC�Â�����邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B

���i���̒m�I�����i���^��~�n������@���ƔV���{�Ё@1000�~�j
�������́A���́u�Ǐ��ˑ��ǁv�Ƃ����قǂ̓Ǐ��Ƃł��B
���̈�����A15�����̑������������̓n�����ꂳ��ƑΒk����܂����B
�����܂ł��Ȃ��n������ƌ����A�u�m�I�����̕��@�v�Ƃ����x�X�g�Z���[�E�����O�Z���[�̒��҂ł�����܂��B
�������̓Ǐ��D���́A���́u�m�I�����̕��@�v�Ƃ̏o�����n�܂����悤�ł��B
���ӂ���Ƃ��A��̈����Ƃł�����A�Βk�̎n�܂�́u���ւ̂��鐶���v�ł��B
�{�D���Ȑl�ɂ́A�ǂ�ł��邾���Ŋy�����Ȃ�悤�ȑΘb�ł��B
��������b�́u�m�I�����v�ւƍL�����Ă����܂��B
�ꗬ�ɂ���̂́u�l�͎��ʂ܂Ŋw�ё�����B���ꂪ�ō��̍K���v�Ƃ����A���ӂ���̐������ł��B
�Θb��i�߂Ȃ���A���ӂ��肪�ǂ�ǂ�オ���Ă����A�ƂĂ��e���ȊW�����܂�Ă����̂��A�ǂ�ł��Ă悭�킩��܂��B
�Βk��5���Ԃɂ��y�����ł����A�r���œn���������́u��F�v���̂��قǂ̐���オ����������悤�ł��B
�b�̓��e������ɂ킽��A�����ς���{�l�_�ɂ܂ōL�����Ă����܂��B
�Βk���y����ł��邨�ӂ���̋C�������`����Ă��āA�����ǂ�ł���ق����y�����Ȃ�܂��B
�n������͌���84�B95�܂œǏ��𑱂��A�w�ё�����Ɛ錾����Ă��܂����A���̐�������95�ł͎~�܂�Ȃ��ł��傤�B
�������́A�n������̑f���炵�����ɂɈ��|���ꂽ�悤�ł����A������������A��������鏑�ɂɒ��킵�������ȂƁA�ǂ�ł��Ċ����܂����B
�Βk�̒��ň������́u���ւÂ���͐l������邱�Ɓv���Ƙb���Ă��܂��B
���������v���܂��B
�����A�����������������A�ŋ߂ł͂Ȃ��Ȃ���邱�Ƃ��c�O�ł��B
���́A���̂��Ƃ��A�Љ��ώ������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�������Ă��܂��B
�Ǐ��̊y�����������Ă����{�Ƃ��āA�Љ���Ă��炢�܂����B

���u�I������v�i���^��@���ƔV���{�Ё@2014�j
���^�炳��̐V���ł����C���̎�̃^�C�g���̖{�ɂ͂���������R������A�����Ă��炢�Ȃ���ǂ܂��ɂ����Ă��܂����B
����A����{��ǂ�ŏ����C���ς��A�C�ɂȂ��Ă����{����ǂ݂܂����B
�������炵�����b�Z�[�W�����߂��Ă��܂����B
�������́A�u�I���v���u�l���̏I�����v�ł͂Ȃ��u�l���̏C�ߕ��v�Ƒ����Ă��܂��B
�u�l���̏C�ߕ��v�B
���������A���ɂ͂��̎��_���܂������Ȃ����ƂɋC�Â��܂����B
�f���ɐ����A���R�Ɏ���ł����̂��A���̗��z������ł��B
�������A����ł͎���̐l�����ɂ͑傫�Ȗ��f��������ł��傤�B
��͂肫����Ɓu�C�߂Ȃ��v�Ƃ����܂���B
���̖{�́A�������A���������Ӗ��ł́u�C�ߕ��v�̖{�ł͂���܂���B
�u�C�ߕ��v�ł���B�ނ���������̂ق��̒���̂ق��������ɕx��ł��܂��B
���̖{�́A�ނ���u�l���̒��߂�������v�Ƃ����Ӗ��ł́u�C�ߕ��v�����Ă���Ă��܂��B
����A�u�C�ߕ���b�ҁv�ł��B
���e�́A�G���f�B���O�m�[�g�̑I�ѕ�����A���V�₨��A���{�@��Ƒ��ւ̋��K�Ȃǂ̎c�����Ȃǂ�������Ă��܂��B
�����������Ƃ����ɂ��āA�u�V�v�Ɓu���v�̊Ԃ��ǂ��߂����������b�Z�[�W����Ă���̂ł��B
�{����ǂނ��ƂŁA�����Ȏ��_����Ǝv���܂��B
�������Ƃ��ẮA�������ɂ́A���̊�b�҂̑����Ƃ��āA���߂āu�l���̏C�ߕ��v�̏��������Ă��炢�����Ƃ����C�����܂��B
���u�^���̎q�@�g���\�~�[�v�i���i���P�@���w�ف@1500�~�j
��T�J�Â����u�}�n���o���v�̏W�܂��ɎQ�����Ă������������i���P����Ƃ����������܂��B
�u���O�Ȃǂ�ǂ܂��Ă��炢�A���̊����ɋ����������܂����B
��ԋC�ɂȂ����̂́u�g���\�~�[�v�Ƃ������t�ł����B
�ȑO�A�m�o�n�ւ̎��������v���O�����̎����ǂ�����Ă������ɁA�g���\�~�[�W�̃O���[�v����̉��傪����A���̎��ɏ��߂āu�g���\�~�[�v�Ƃ������t�ɏo������̂ł����A�c�O�Ȃ��炻�̎��ɂ͎x���ΏۂɑI�ׂ��ɁA�����ƋC�ɂȂ��Ă����̂ł��B
����ŏ��i����̐V���u�^���̎q�@�g���\�~�[�v��ǂ܂��Ă��炢�܂����B
��N�̏��w�كm���t�B�N�V������܂̎�܍�ł����B
���i����̌����ȕM�͂̂������ň�C�ɓǂ߂܂������A�T���̃}�n���o�̏W�܂�ł�������C�Â��Ɛ[���Ȃ����Ă��邱�ƂɋC�����܂����B
���̏�Q�Җ��ւ̗����������[�܂����̂ƁA�Љ�Ƃ͉����ւ̗������L����܂����B
���Б����̐l�ɓǂ�ł��炢�����āA���̃R�[�i�[�ŏЉ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�{���̓��e�̏Љ�́A�A�}�]���̏Љ�L�����ƂĂ��킩��₷���̂ň��p�����Ă��炢�܂��B
�l�Ԃ̐����́A���e�����{�����F�̂��p���a�����܂����A���F�̂��R�{�ɑ����Ă���a�C���g���\�~�[�ł��B�ُ�̂�����F�̂̔ԍ��ɂ���āA�u13�g���\�~�[�v�u18�g���\�~�[�v�u21�g���\�~�[(�ʏ́E�_�E����)�v�Ȃǂ�����܂��B13�g���\�~�[�̐Ԃ����́A�S���̊�`��]�̔��B��Q�����邽�߁A������1�����قǂŁA�قƂ�ǂ�1�܂łɎ��S���܂��B�{���́A�����O�Ȉ�ł��钘�҂��u�n���̎厡��Ƃ���13�g���\�~�[�̐Ԃ����̖ʓ|���݂Ăق����v�Ƌߗׂ̑����a�@����˗�����A���z(������)�N�Ƃ��̗��e�ɏo��Ƃ��납��n�܂�܂��B���z�N�̗��e�͉䂪�q���e��A����֘A��ċA�舤��𒍂��܂��B�����ď�Q���������������Ƃ̈Ӗ��������ɒT��܂��B���҂͒��z�N�̎���֖K�������Ԃ��A�Ƒ��ƑΘb���d�˂Ă����܂��B�܂��A���̑��̏d�x��Q���̉ƒ�ɂ��K��āA�u��Q������e����v�Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂����l���Ă����܂��B�₪�Ē��z�N�̕�e�́A���z�N���u�Ƒ��ɂƂ��Ă̍K���̈Ӗ��v�������Ă����^���̎q�ł��邱�ƂɋC�t���܂��B
�M�҂̏��i����́A��t�Ƃ��Ċւ���Ă���̂ł����A�P�Ȃ��t���āA��Q����Ƒ�����M������A����Ӗ��ł́u���ԁv�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�{������`����Ă��܂��B
������A�悭�������܂łƎv����悤�ȁA�{���I�Ȃ��Ƃ����ꉻ���Ă��܂��B
�����āA���ꂪ���܂�ޏ��ɂ͂Ȃ��悤�Ȑ[���₢�����ɂȂ��Ă��܂��B
�����������i����̎p���́A���Ƃ��Ύ��̕��͂ɓǂݎ���ł��傤�B
��Q����������Ƃ͈�̂ǂ̂悤�Ȃ��ƂȂ̂��낤���B���̕s�𗝂ȏd�݂ɐl�͑ς�����̂��H�@�e��A���z���邱�Ƃ́A�N�ɂł��\�Ȃ��ƂȂ̂��낤���H�i�����j����13�g���\�~�[�̐Ԃ����̉Ƒ��̌��t�Ɏ����X���A���̌��t�̈�ЂƂJ�ɂ������グ�Ă����A���炩�̓�����������̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���������B�����ĉƑ�����b���Ă������Ǝ��̂��A13�g���\�~�[�̐Ԃ����̐������ە����A�Ƒ��ւ̗E�C�ɂȂ�ƍl�����B
���̏��i����̎��݂́A�{���ɂ����Č����ɐ������Ă���Ǝv���܂��B
���Б����̐l�ɓǂ�ł������������{�ł��B

���u�~�����}�[���������`���E���a�p�S�_�̉\���v�i���^��ق��@���㏑�с@1000�~�j
���N�O���炻���ґz�@�����{�ł��b��ɂȂ�L���肾���Ă���̂�����������ł��B
�~�����}�[�����́A������������������̗�������ނ��̂ł���A�߉ނ̋����ɋ߂��Ƃ����Ă��܂��B
���̃R�[�i�[�ł��悭���グ�����Ă�����Ă�����^�炳�A���̃~�����}�[�����Ɋւ���Ă��邱�Ƃ�m�����̂́A�ȑO�Љ���u�������߂āv��ǂ�ł���ł��B
�������́A���Z�܂��̖k��B�s�ɂ���A���{�B��̃~�����}�[�����@�ł��鐢�E���a�p�S�_�̊����ĊJ�ɂ��s�͂���A����������̍��{�o�T�ł���u���o�v��V���Ɏ��R�ꂽ�肵�Ă��܂��B
��N�A�k��B�s�Ńp�S�_�ĊJ���L�O�����u���������𗬃V���|�W�E���v���J�Â���܂������A�{���͂��̋L�^�ł��B
�����A�u���������E���~���v���e�[�}�Ƀp�l���E�f�B�X�J�b�V�������s���܂������A���̂S�l�݂̂Ȃ��A�ƂĂ��킩��₷���~�����}�[���������ƂƂ��ɁA���̎��_���炳�܂��܂Ȗ���N�ƒ�����Ă��܂��B
���E�B�}������i����R��w���w�������j
�V��a������i�u�݂�Ȃ̎��v�V��E��Ɓj
����a�q����i�{�����e�B�A�O���[�v�[�����j
���^�炳��i��ƁE������ЃT�����[�В��j
�p�l���X�g�݂̂Ȃ���́A�݂�Ȏ��H���d��������̂悤�ŁA���ꂼ��̂��b�������Ƃ������������Ǝv�킹��قǁA�ƂĂ����͓I�Șb������Ă��܂��B
���́A�^���@�k�ł����A����̏@�h�⋳�c�ɂ�����邱�ƂȂ��A�_����܂ł��g�ݍ��u���{�̕����v����M���ɂ��Ă��܂����A�{���Ō���Ă���~�����}�[�����͈�a���Ȃ��S�ɋ����Ă��܂��B
����܂œ��{�ōL���肾���Ă������������ɂ́A�m���s��������A���܂�ǂ��C���[�W�������Ă��܂���ł������A�������̖{��ǂ�ł���C���[�W���ς�肾���A�{����ǂ�ł���Ɉ�a�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�ڂ������e�Ȃǂ́A�������̃u���O�����ǂ݂��������B
http://www.ichijyo-shinya.com/message/2013/11/post-622.html
�ƂĂ��ǂ݂₷���{�ł��̂ŁA�������S��������ǂ݂��������B
���������A���̗F�l���X�������J�ɒʂ��Ă��܂��̂ŁA�����X�������J�̕������w��ł݂����Ǝv���o���Ă��܂��B
���u�݂��ׂɂ͂��܂����q��ĂЂ�v�i�V�V�����@�g�����o�ŕ��@1800�~�j
�u�݂��ׁv�Ƃ́A�����̍]����̖؏�̐쉈����1999�N�ɋ��c��ɂ���ꂽ�u���z�q�ǂ��ߒ��x���Z���^�[�v�̈��̂ł��B
���́u�݂��ׁv�̑n�݂Ɋւ��A�����߂��̂��A�{���̒��҂̐V�V����ł��B
�V�V����́A���L�F�̉e�����āA�ۈ�̐��E�ɂ͂������Ƃ��������Ă��܂��B
�����o��������ɂ́A���L�F���n�������_���ۈ牀�̉����ł����B
�ۈ牀�ł�������V�V����̏Ί�͍��ł��Y����܂��A���̏Ί�̂������ŁA���͕ۈ�̐��E�ɂ����₩�Ɋւ�邱�ƂɂȂ�A���ꂪ���̐�������傫���ς��Ă��܂��܂����B
�_���ۈ牀�̂���n��́A�����m�푈�̎��̑��P�ʼnƂ��Ă�����e�̐E���������l���������������Ƃ���ł��B
�_���ۈ牀�́A�ۈ�̎{�݂Ƃ��������A���������n��̏Z���������Ȃ��u�Ђ�v�Ƃ��āA�ŏ�����n��ɊJ���ꂽ�u�݂�Ȃ̉Ɓv�������悤�ł��B
���Ȃ��Ƃ��V�V�����͂��������v���ʼn����^�c���Ă����Ǝv���܂��B
�_���ۈ牀�́A�������f���������i20�N�ȏ�O�j���A���łɂ��Ȃ�V�������݂Ɏ��g��ł��܂����B
���̈���A�������}�X�^�[�̋i���R�[�i�[�ł����B
�V�V����ɂ́A��������u�Ђ�v�̊��o������̂ł��B
�u�݂��ׁv�́A���������V�V����̎v���ƕۈ牀�ł̎��H�܂��āA�n�܂�܂����B
�����āA�q�ǂ������͒��N����Ɓu�����݂͂��ׂɍs���v�ƌ����A�u�݂��ׁv�͐e�q�Œʂ���ɂȂ��Ă����܂����B
�u�q��Ăɍ�������݂��ׂɍs���Ă݂Ȃ����v�Ƃ݂�Ȃ������قǁA�Љ��قǁA�]����Ŏq��ĂɊւ��l�����ɂƂ��Ă͐g�߂ȏꏊ�ɂȂ����̂ł��B
�����āA���ł͍]����ɂ͂S�́u�݂��ׁv���ł��Ă��܂��B
���������u�݂��ׁv�ł̎q��ĂЂ�̍L����̕�����܂Ƃ߂��̂��A�{���ł��B
�����ɂ́A�V�V����̎q��ė��_�i�N�w�j����������ƁA��������̓I���H�I�ɏЉ��Ă��܂��B
�����Ɋւ���Ă����l�����̍��k������^����Ă��܂��̂ŁA����炪�A���ʓI�ɐ��������Ɠ`����Ă��܂��B
�q�ǂ��Ɋւ�銈���Ɏ��g��ł���݂Ȃ��܂ɂ͂��Гǂ�łق����P���ł��B
�V�V����ɁA��x�A�����Řb�����Ă��炨�����Ƃ��l���Ă��܂��B
�������̂�����́A���A�����������B

���u����Ŋ������Փ���v�i���^��@���ƔV���{�Ё@800�~�j
�������Ղ́u�����̊j�v���Ƃ������^�炳��́A�������Ղ̕���Ŏ��H�ƌ����ƌ[�������Ɏ��g�܂�Ă��܂��B
�{���͂��̈�����������u�������Ձv�ɂ��Ă̊�{�I�ȃ��[����}�i�[���Љ����发�ł��B
�������́A�������Ղ̖����Ƃ��āA���̂��Ƃ������Ă��܂��B
�܂��A�������Ղ͐l�������Ă��邽������̉������������̉�����Ƃ����܂��B
���̐��ɖ����̐l�Ȃǂ��Ȃ��Ƃ����������̍l���ɋ���������̂Ƃ��ẮA�ƂĂ��[���ł��܂��B
�܂��A�������Ղ́A�u���Ԃݏo���v�u���Ԃ��y���ށv����������ƌ����܂��B
������ƂĂ��悭�킩��܂��B
���Ԃɗ����ꂪ���Ȍ���l�ɂ́A�ƂĂ��傫�Ȍ��p�������Ă��܂��B
�������́A���������Ă��܂��B
���{�ɂ́u�t�ďH�~�v�̎l�G������܂��B�V���Ƃ������̂́u�l���̋G�߁v�̂悤�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B���O��l���A�����j���Ƃ������l���V��Ƃ͐l���̋G�߁A�l���̉w�Ȃ̂ł��B�킽�������́A�G��̂���o��ŋG�߂����ł��悤�ɁA�V���ɂ���Đl���Ƃ������Ԃ����łĂ���̂�������܂���B
�����āA���������܂��B
����͂��̂܂܁A�l�����m�肷�邱�ƂɂȂ���܂��B�����A�V���Ƃ͐l�����m�肷�邱�ƂȂ̂ł��B�������ՂƂ́A���ׂĂ̂��̂Ɋ��ӂ���@��ł�����܂��B
���������悤�ɍl���Ă����ƁA���Ԃ�A�������Ղ̃C���[�W���傫���ς���Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���̂�����̐[�����@�́A�������̂ق��̒���ɔC����Ƃ��Ă��A�܂��͊������Ղ̊�{���[���ƃ}�i�[�̓��发�Ƃ��āA�{���������߂��܂��B
�������͂��������Ă��܂��B
�������Ղ̊�{���[���͕ς��܂��A�}�i�[�͎���ɂ���ĕω����Ă����܂��B
��{�ƂȂ郋�[�����u�����ݒ�v�Ȃ�A�}�i�[�́u�A�b�v�f�[�g�v�ł��B
�{���́A������{�̊������Ղɂ�����u�����ݒ�v�Ɓu�A�b�v�f�[�g�v�̗������킩���������߂����܂����B�{������Ɏ��ꂽ�݂Ȃ��A�������Ղ̎����[�����E��m���Ă��������A�����ł��S�L���ɂȂ��Ă���������A����قNJ��������Ƃ͂���܂���B
�ƂĂ��X�}�[�g�ȓ��发�ł��B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u���ꂪ���E�h�~�������I�v�i�K�Y�@���z�o�Ł@1500�~�j
����̓��q�V�Ŏ��E�h�~�̂��߂̌���芈�������Ă������̍ŐV�̊����L�^�ł��B
����̊����������P�O�N�ɂȂ�A���̊ԁA500�l�߂��l�ɑ������A���̐l�����̑��k�ɏ���Ă��Ă��܂��B
�����ŁA����Ɖ���Ă��Ă��A���܁A����̌g�ѓd�b�ɑ��k�̓d�b���������Ă��܂��B
���������������P�O�N�������Ă���Ƃ����̂͑�ςȂ��Ƃł��B
���ꂪ�����ł��Ă���̂́A����ɂ͐M�O�ƂԂ�Ȃ��������邩��ł��B
����́A�����̊������u���E�h�~�����v�Ƃ͑����Ă��܂���B
�u�l���~�������v���Ƃ����̂ł��B
�{���Ŗ���́A���������Ă��܂��B
�������Ƒ��������l�̑����́A�{�l�ЂƂ�̃J�ł͎����������Ă���Y�݂��Ƃ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ���ԂɂȂ��Ă���̂ł��B
�������A����̐l�́u��܂��v�u���B����v�u�����v�u�w���v�u�����v�����邾���ŁA������݂����Ƃ����A�{�l��ӂ߂邾���ł��B
����ł����̂��A�Ɩ���͌����܂��B
��ꂫ���Ă���{�l�����̃J�ł͂ƂĂ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�������u���Ă���̂́A�u�Љ�I�E�\���I�ȑg�D�ƍ��v���B
�����Ă����킯�ɂ͂����Ȃ��Ƃ����̂ł��B
�����Ă����ẮA�u�Љ�I�E�\���I�ȑg�D�ƍ߁v�ɉגS���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
�����́A���q�V�ő��������l�������炶������Ǝ��Ԃ������Ď��E�Ɏ��������@�⌴�����o���A���������łł���x��������������A����u���Ă��܂����B
�܂��A�ً}�O�{���Ƃ��āu�ً}���v�u�����l�v�u�x���Ă����l�v���K�v���ƍl���A���̃l�b�g���[�N����ĂĂ��Ă��܂��B
����Ɏ���O�{���Ƃ��āA�u�Y�݂��Ƃ̉����܂��͌y���x���v�u�����x���v�u�����^���w���X�v�̑�ɂ����g��ł��܂��B
�����̂������������ŁA��������̐l�������ďo�����Ă���̂ł��B
��x�A���E���l�������A���ł͋t�ɁA���E��h�~���銈���Ɏ��g��ł���l�����܂��B
�{���͂������������̕ł��B
����́A���̖{���o���邾�������̐l�����ɓǂ�ł��炢�A�����ɂ��ł���u�l���~���v�����������Ăق����ƍl���Ă��܂��B
�N�ł��ł��邱�Ƃ͂���͂��ł��B
���̗ւ��L����A���E�ɒǂ����܂��l�͌����Ă����͂��ł��B
�����A���̍l���ɋ������āA�����ƈꏏ�Ɂu���E�̂Ȃ��Љ�Â���l�b�g���[�N�v�𗧂��グ�A���N�A���J�t�H�[�����Ȃǂ𓌋��ŊJ�Â��Ă��܂����B
�Ƃ���ŁA�����̊��������N�łP�O�N�ł����A������L�O���āA�T���P�V���ɕ���Ō��J�V���|�W�E�����J�Â��܂��B
����ɐ旧���A�o�ł����̂��{���ł��B
�V���|�W�E�����͕���ł����A���S�̂�����͂��Q�����������B
���m�点�̃R�[�i�[�Ɉē����f�ڂ��Ă����܂��B
�܂��{����ǂ�ŁA���Ј�x�A���q�V�Ń{�����e�B�A������̌��������ƌ�������������A���A�����������B
����ɂ��`���������܂��B
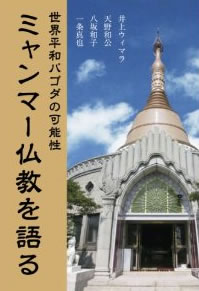
���u�E�X���ɑł����V���Ȏv�z�v�i��{���@���Ώ��X�@2014�j
��{������́A���N�A�Ǝ��́u�V�v�Љ�_��_�ɗ����āA�u���a�v�̖����l�@���Ă��Ă���v�z�Ƃł��B
���a�̂��߂̌o�ϊw����w�Ɋւ���{�������Ă��܂����A���E�̖����\�z�Ƃ����傫�Ȗ�肩��A�����̂悤�ȋ�̓I�Ȗ��ɂ܂ŁA�����̒��삪����܂��B
���̃R�[�i�[�ł��A����܂łقڂ��̑S�Ă��Љ�Ă��܂����B
�{���́A��{����̍ŐV��ł��B
�ŋ߂̓��{�Љ�́u�E�X���v��J���Ă̌x���̏��ł����A�P�Ȃ�x�����ł͂���܂���B
����̑傫�ȗ����W�]���āA�u�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v�Ɋ�Â��ĎЉ�̂������ς��Ă������ƒ��Ă��܂��B
��{����́A�u�E�X���̗���̒��ɐg���ς˂邱�Ƃɂ���āA���{�l�́u�ւ�v��u�S�̈���v�邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��v���A���������E�X���̗U�f�ɑł������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����܂��B
�ł́A�ǂ�����đł������B
���������c�_�̍���ɂ���̂��A�u�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v�ł��B
�����āA���\�[�Ƃ͈Ⴄ�A����ɂ̓z�b�u�X��b�N�Ƃ��Ⴄ�A�V�����Љ�_��������̂ł��B
��{�����������V�Љ�_�������������̂͂���15�N�قǑO�������Ǝv���܂����A
����ɂ��̍l���͎v�z�I�ɐ[�߂��A����́u�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v�Ƃ��āA���Ȃ�S�̑��������Ă����悤�Ɏv���܂��B
�u�l�Ԃ��N�_�Ƃ���Љ�N�w�v�ɂ����ẮA���ׂĂ̐l�Ԃ̑������s���ł��B
���̂��߂ɂ́A�푈�͂����Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł��B
��{����́A���N�A�u���a���v����{�I�l���ƈʒu�Â��Ă��܂��B
�����āA�u�푈���ł��鍑�Ɓv�̓A���V�����E���W�[���i�����x�j���ƌ����܂��B
���̃A���V�����E���W�[������̗��E���A��{����̖ڎw���Ƃ���ł��B
��{����́A�O���w�u�V�v���a��`�̘_���x�ŁA�푈���̂��̂�ے肷�銴�o���A���̓��{�l�̒��ɂ͏[�����Ă������Ƃ��ڂ����_�l���Ă��܂��B
����́A�i�쐳������̑̌��I�F���Ɠ����ł��B
���̓��{�l�̊��o�����S�X�ɒu��������̂��A��{����̃��C�t���[�N�Ȃ̂ł����A�����̓��{�́A�ނ���u�푈���ł��鍑�Ɓv�ւ�簐i���Ă��܂��B
�܂��ɓ��{�͗��j���t�s���Ă���킯�ł��B
��{����̊�@�����A�悭�킩��܂��B
�K�������ǂ݂₷���{�ł͂���܂��A���Гǂ�łق����{�ł��B
������Ƃ��낪��������A��{����̂����Ȓ�����ǂ�ł݂Ă��������B
�{����ǂ܂ꂽ���𒆐S�ɂ��āA��{������͂ރJ�t�F�T�������J�Â������Ǝv���Ă��܂��B

���u���o ���R��v�i���^���@�O�܊ف@1000�~�j
����������̍��{�o�T�́u���o�v�i���b�^�E�X�b�^�j�Ɋւ��ẮA���^�炳��̒����u�������߂āv�ɏЉ��Ă��܂����A�������ɂ��A���̎��R�o�ł���܂����B
�������r���[�Ȑ�������������A������瑗���Ă�����������A���������ł����A���p�����Ă��炢�܂��B�u���o�v�i���b�^�E�X�b�^�j�́A����������̍��{�o�T�ł���A��敧���ɂ�����u�ʎ�S�o�v�ɂ��䌨������̂ł��B�l�͉��̂��߂ɐ�����̂��A�l���ɂ����鎊���̐��_���Â���搂��Ă���A�l�́u����ׂ��p�v�A����u�l�̓��v�����Ղɐ�����Ă���o�T�ł��B
�킽���́u���o�v���E�q�̌��s�^�ł���w�_��x�A�C�G�X�̌��s�^�ł���w�V���x�̓��e�Ƃ��d�Ȃ镔�����������Ƃɒ��ڂ��A���E�ł����ƂȂ��_�Ȏ��R������݁A�u���E���a�v���F�O���邽�߂ɏ㈲�������̂ł��B
���́u���o�v�̋����́A�V���䂭�ҁA���ɂ䂭�ҁA�����ĕs���������������ׂĂ̎҂ɁA�S�̕�����^���Ă����Ǝv���܂��B�����Љ���V�l�Y���Љ�������鋳���Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�u���o�v�́A�u�b�_�����H�����������̋��菊���A10���ڂɋÏk�������̂ł��B
�����ɗ���Ă���̂́A�u�����݂̐S�v�ł��B
10���ڂ́A���ɂ킩��₷���A�S�ɋ����A�N�ł����̋C�ɂȂ�A���H�ł�����̂ł��B
�����A�����͂����Ă��A����͂����ȒP�ł͂���܂���B
�����ɂ����A�����邱�Ƃ̓����ʔ����A�߂������Ԃ�����悤�Ɏv���܂��B
�ނ��낱�ꂱ�����A��敧���̌o�T�ɂӂ��킵���悤�ɂ��v���܂����A����͎��̏���Ȏv���ł��B
�������́A�k��B�s�ɂ���A���{�ŗB��̏�����������@�u���E���a�p�S�_�v���x������ߒ��ŁA���̃��b�^�E�X�b�^�ɏo������悤�ł����A���ꂪ�{�������܂��_�@�ɂȂ��������ł��B
������A�v�������߂Đ��Ȃ����ł��낤�A���������͂ɁA���T�E���I�[�g����̔������ʐ^���Y�����Ă��܂��B
�Z�����o�ł����A������3��قǁA�J��Ԃ����͋傪����܂��B
���ׂĂ̐����Ƃ���������̂�
�K���ł���
�����ł���
���炩�ł���
���̋F�肪�A��������炩�ɂ��Ă���邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�������̎v�����A���E�ɍL���邱�Ƃ��A�����F�肽���Ǝv���܂��B
�R�����Y���X����w��
���u�������߂āv�i���^��@�O�܊ف@1500�~�j
��N�A�E�q������܋L�O�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�u������߂āv�ɑ����A���^�炳��̃G�b�Z�C�W�ł��B
�O���́A�u�_��v�Ɍ���Ă���u��v����ȃe�[�}�ł������A����͕����ɂ��Ȃނ��̂������A�u���v���e�[�}�ɂȂ��Ă��܂��B
����i�{���͍��v�ԗf�a�j����͖k��B�s�ɖ{�Ђ̂��銔����ЃT�����[�̎В��ł�����܂����A�k��B�s�̖�i�̘a�z�������ɂ́A���{�ŗB��̃r���}�i�~�����}�[�j�����@�u���E���a�p�S�_�v������܂��B
�r���}���{������Ɠ��{�̗L�u�ɂ���ď��a32�N�i1957�N�j�Ɍ������ꂽ�����ł��B
�{���ɂ��o�Ă��܂����A�ꎞ������Ă������E���a�p�S�_����������̐s�͂ŁA���܂͍ĊJ����A�~�����}�[�Ɠ��{�̕����E�̌𗬂��n�܂��Ă��܂��B
�~�����}�[�͏���������̍��ł��B
���̂����ŁA�������͂��܁A����������̍��{�o�T�́u���o�v�̎��R��Ɏ��g��ł��邻���ł��B
���o���Љ���{�́u�����v�ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă��邻���ł��B
�����̂Ȃ���@���ꂽ���߉ނ��܂́A�l�Ԃ���炩�ȍ����S�邽�߂ɁA���ׂĂ̐����̈��y��O����q�����݁r�����D�����A�������S����Ă�w���o�i���b�^�X�b�^�j�x������ꂽ�̂ł����B���b�^�[�i�߂��݁j�́A�傢�Ȃ�F��Ƃ���܂��B�w���ׂĂ̐����Ƃ���������̂́A���₩�ł���A�댯���Ȃ��A�S���炩�ɍK���ł���܂��悤�Ɂx�ƔO���邨�o�ł��B
�������́A�{���ł܂��A�V�����R���Z�v�g����Ă��܂��B
�u���v�Ƃ������t�́A���̌��t�ƌ��т��܂��B���Ƃ��A�u�߁v�ƌ��т��āu���߁v�ƂȂ�A�u���v�ƌ��т��āu�����v�ƂȂ�܂��B�킽���́A�u���v�Ɓu��v�����т������ƍl���܂����B���Ȃ킿�A�u����v�Ƃ����V�����R���Z�v�g��������Ǝv���܂��B
�u���疳��v�Ƃ������t�����邭�炢�A�u��v�Ƃ������̂͂ǂ����Ă��`����`�ɗ��ꂪ���ł��B�܂��A���̌��ʁA�S�̂������Ă��Ȃ����A�A�����V�A�Ί炪����Ă��܂��܂��B
�t�Ɂu����v�܂�u�����݂Ɋ�Â��l�ԑ��d�̐S�v������A�S�̂����������A�A�����V�A�Ί炪�\�ƂȂ�܂��B
���̕��͂�����A�������̎v�����`����Ă���ł��傤�B
�����́A���`�������߂̓����ɂ��܂��A���܁A���E�ŋ��߂���ׂ����́A���`�̓���芰�e�̓��A���邢�͎��߂̓��ł��B���̊��e�̓��A���߂̓��������ɂ͂悭������Ă���̂ł��B�킽���́A�����̎v�z�A�܂�u�b�_�̍l���������E���~���ƐM���Ă��܂��B
�O���������ł������A�{���̍���ɗ����̂́A�������̐V�����������_�ł���A����Љ�_�ł��B
��A���B���Ď��Ɉ�����I�ԁu�ꕶ���v�͂Ȃ�ł��傤���B
�ǂݏI���Ă̎��̈�Ԃ̊S�́A���̂��Ƃł��B
���̗\�z��������Ƃ����̂ł����B
�O���Ɠ������A�ƂĂ��ǂ݂₷���A�S�ɋ����܂��B
�悩�����炨�ǂ݉������B
���u�t���ʗւ͂���Ɏ������v�i���h��Y�@�ҏW�H�[�m�A�@�i�j
����͎��̗F�l������o�ł����{�̏Љ�ł��B
�i�ł��̂ŁA�Љ�Ă��Ӗ��͂Ȃ��̂ł����A�Ȃ��Ȃ��ʔ����{�Ȃ̂ŁA����Ȗ{������Ƃ������ƂŏЉ���Ă��炢�܂��B
�������S������Β��҂����Љ�܂��B
��T�A�u�I�����_����̔����˗���v�Ƃ����h�L�������^���[���Љ���̂ł����A����Ƃقړ��������ɓǂ̂ŁA���̊S�����ɍ��܂����̂�������܂���B
���҂̓v���̃��C�^�[�ł͂Ȃ��̂ŁA�d�グ�͖��n��������܂��A���ɂ͂��̑f�������ƂĂ����͂Ɋ����܂����B
���҂̉��h��Y����́A���̉�Ў���̓������ł��B
�ނ͌����҂ł����̂ŁA���Ƃ͂܂������Ⴄ����ł������A�g�D�Ƃ̋����������ƒʂ���Ƃ��낪����A���Ȃ������₩�ȕt������������܂��B
�ނ͎R�o�肪��D���ŁA�R�Ɋւ���{���o�ł��Ă��܂����A����͎Ⴍ���Ē���̌����̔픚�ŖS���Ȃ����f���̋L�^�ł��B
���̃R�[�i�[�ɏ����C�ɂȂ����̂́A���҂��킸������̏����q���g�ɁA�f���̑��Ղ�H���Ă����v���Z�X�̖ʔ����Ƃ��ɒ���̐}���قŏf���̍Ō�Ɋւ���L����������Ƃ����h���}����ۓI����������ł��B
����܂��āA�L�^�Ƃ͕ʂɁA��Q���Ƃ��ď����d���Ăɂ��Ă��邱�Ƃɂ������������܂����B
�L�^�Ə����Ƃ����Q�̃A�v���[�`�ŁA����������̗l�q�ⓖ���̔w�i�������Ɠ`���Ă���Ă��܂����A���̌������������������ɑe�G�����������v���m�点�Ă���܂��B
�����ɁA���ɂƂ��ďՌ��I�������̂́A60�N�O�̓��{�̎Љ�ƌ��݂Ƃ̂��܂�ɂ��傫�ȈႢ�ł��B
�����ŏ�����Ă���́A�����g�̋L���ɂ��������Ɏc���Ă��錻���ł��B
�Ƃ�����A�����g�A���̈Ⴂ��Y��邱�Ƃ�����܂��B
�����āA����������ƂƂ��ɁA���̋L���͂܂��Ȃ������Ă��܂��ł��傤�B
���̋L������������Ǝc���Ă������Ǝv�������҂̎v���ɁA�n�b�Ƃ�����ꂽ�̂ł��B
���`���⏑���`���Ƃ������Ƃ̑���́A����Ȃ�ɔF�����Ă������ł������A���������Ă��Ȃ��������Ƃւ̉���������܂��B
���̗��e����������Ă����ׂ��������Ǝv���܂����A��������������܂���B
���w���̍��A��c���ׂ��������Ƃ�����܂��B
����Ȃ�ɖʔ����������Ƃ��o���Ă��܂����A�������ɂ͂�����܂������`���Ă��܂���B
�ŋ߁A�����j���o�ł���l�������Ă���悤�ł����A���j���l�����ւ̊S�Ǝ����j�Ƃ͂܂������Ⴄ�悤�Ɏv���܂��B
100�N��ɂ������̖{���c���Ă����Ƃ�����A�ƂĂ������u���j�����v�ɂȂ�ł��傤�B
�{���͔i�œ���͍���ł����A����ɐ��s���d�˂ďo�ł��Ăق����ƒ��҂ɂ͓`���Ă��܂��B
�������ꂪ����������A���߂ďЉ���Ă��炢�܂��̂ŁA�y���݂ɂ��Ă����Ă��������B
���́A���҂������ЂƂ��肵�Ă���邩�ǂ����ł����B
���u�I�����_����̔����˗���v�i����D�@���㏑�ف@2000�~�j
���炭�����������Ă������䂳��A�u�I�����_����̔����˗���v���o�łł����Ƃ����A������������̂́A�����Q�����قǑO�ł��B
���̃e�[�}�͂��Ȃ�O����̕��䂳��̃e�[�}�ŁA�����b�������Ă��܂����B
�����ɓǂ����Ǝv�����̂ł����A�����g�������������Ԕj�Y�𑱂��Ă��āA�ς܂܂ɂȂ��Ă��܂����B
���̏T���A�v���o���ēǂݏo������A���̓��e�Ɉ������܂�Ă��܂��A��C�ɓǂ�ł��܂��܂����B
�{���́A�I�����_���n�̕��e�T���̕���ł��B
�ƌ����Ă��A�Ȃ�Łu�I�����_���n�v�����{�l�̕��e���A�Ǝv���l�������ł��傤�B
�����A�ŏ����̘b�����Ƃ��ɂ����ɂ͗����ł��܂���ł����B
����͂����ł��B�{���̈ē���������p���܂��B
�����m�푈���A�I�����_�̓��C���h�i���݂̃C���h�l�V�A�j�ɐN�U�������{�R�B�푈���ɂ��ւ�炸��r�I�������L�x�ŁA�u�Ɋy���v�Ƃ��Ăꂽ�C���h�l�V�A�ŁA���n�̃I�����_�n�����Ɠ��{�l�̖�ɑ����̓��a�������B���{�̔s���A�C���h�l�V�A�̓Ɨ��푈���n�܂�A�I�����_�n�̐l�X�́A���n�̎q�ǂ������ƈꏏ�ɖ{���Ɉ����g�����B�ނ�͑�l�ɂȂ�A���{�̕��e��{���n�߂���̂́A���̎��g�݂͍�����ɂ߂��B�������A�ނ�̊肢����1�l�̓��{�l�������B
�{���́A���̓��{�l�A���R�]����̃q���[�}���h�L�������g�ł��B
���҂̕��䂳��̃��C�t���[�N�́u�q�ǂ��̎Љ���v�ł����A�u�q�ǂ��ɂƂāA���e�͂ǂ�ȑ��݂Ȃ̂��v�Ƃ����A�u���Ǝq�v��u�Ƒ��v�Ƃ����e�[�}���A�{���̒ꗬ�ɗ���Ă��܂��B
���R����̐l���⊈���́A�{���̏��͂Ɍ����ɕ`����Ă��܂��B
�Ȃ�ł��Ȃ��s��̐l���A�R�����������ƂɁA��l�Œn���ɕ��e�₻�̊W�҂�T���čs���p�͌h���������܂����A����ȏ�ɁA�����Ŗ��炩�ɂȂ邳�܂��܂Ȑl�Ԗ͗l�͊����I�ł��B
�l�ԂƂ������̂̈������Ƃ₳�����A�����Ă��炵���������Ă���܂��B
�{���́A���R�����g���e�������̂������̕�����Ƃ肠���Ă��܂����A�����ɓo�ꂷ�邳�܂��܂Ȑl������́A����ɖ|�M�����l�Ԃ̎コ�Ɠ����ɁA�l�ԂƂ������̂̂��炵���⋭�������������Ă���܂��B
���Ƃ��A�����������ٕ�Z�킪�A���G�Ȏv�����āA�S�����������܂ł��Љ�Ă���u�j�b�s�[�̗܁v�́A�ǂ�ł��āA�����g���܂��o�Ă���قNJ����I�ł��B
�e�[�}�̏d�݂ɂ�������炸�A���������������������܂��B
�������A�ߌ��Ƃ��������Ȃ��悤�Ȍ����̎��������܂����A���䂳��͂����āA�l�̎��₳������\���̂ق����������邱�ƂŁA�Ƒ��̖��̑��������������Ă���Ă���悤�ȋC�����܂��B
���R����ƕ���ŁA�{���ɂ͂����P�l�̎�����o�ꂵ�܂��B
�A���X�e���_���ݏZ�̓��n�̃q�f�R����ł��B
�ޏ��͓�������̐l�����ɐ��������āA�I�����_�œ��{�̕��e�������������n�߂܂��B
���R����ƃq�f�R����́A���{�ƃI�����_�őS���ʁX�Ɋ������n�߂�̂ł����A�������1983�N�O��ł��B
����ɂ��̂Q�l���A���R�ɂ��o��̂ł��B
�s�v�c�Ȃ��̂������܂��B�Ȃɂ��傫�Ȉӎv�������܂��B
���R����͍��N��87�ł����A���܂����n�̎q�ǂ������̂��߂̕��e�������Ɏ��g��ł��邻���ł��B
�������A�قƂ�Ǖ\�ɏo�邱�ƂȂ��B
���䂳�قꍞ�̂���������܂���B
�悩������ǂ�ł��������B
���낢��ƍl���������邱�Ƃ̑����{�ł��B
�R�����Y���X�ōw��
���u������m���̌��t�v�i�z�n�{�莛�������r�n�[���ҁ@���o�Ł@1300�~�j
��T�A���^�炳����u�����|���Ȃ��Ȃ�Ǐ��v���Љ�܂������A�����悤�Ȍ��C�Â�����{���Љ�����Ǝv���܂��B
�F�l���ҏW�Ɋւ�����{�ł��B
���̗F�l�Ƃ́A���o�ł̓�������ł����A�������炱��ȃ��[�����͂��܂����B
�u�����l�B�ɁA���V����͂ǂ�Șb�����Ă���̂��낤�H�v�B���̎v�������[�ŁA�w������m���̌��t�x������܂����B
�z�n�{�莛�����_�ɏI���P�A�̊�������m���̕��X�A�����Ĉꕔ�A�Ƒ���{�l�̘b�����^���Ă��܂��B
�o�Ōシ���ɁA�{����ǂe�l�����̔ԑg����҂���o��҂̈�l�ɐ��o���̈˗�������ȂǁA�{���͂��łɂ��܂��܂ȂƂ���Ŏ��グ���Ă��܂��̂ŁA�����ǂ܂ꂽ�������邩������܂���B
��y�^�@�{�莛�h�ł́A1987�N�ȗ��A���{�e�n�Ńr�n�[�������i���V�a���̋ꂵ�݂�߂��݂�������l�X��S�l�I�Ɏx������P�A�����j��W�J���Ă��܂��B
�u�r�n�[���v�Ƃ́A�T���X�N���b�g��Łu���Z�v�u���炩�v�u���낮�v�Ƃ����Ӗ��ŁA�r�n�[�������Ƃ́A�z�X�s�X��^�[�~�i���P�A�̕����łƌ����Ă������ł��傤�B
��̓I�ɂ́A�m���A��t�E�Ō�t�A�����m�Ȃǂ��`�[����g�݁A�x�������߂Ă���l�X���s���ƌǓƂ̂Ȃ��ɒu������ɂ���Ȃ��悤�ɁA���������̋�Y�����A����̖��Ƃ��ċ��ɕ��ފ����ł��B
�u�����r�n�[���v�́A���̂悤�Ȋ��҂���̐S�Ɋ��Y�����߂ɐ��܂ꂽ�g�D�ŁA�@���E�@�h���킸�A����ł��Q���ł����荇��������ł��B
�{���͂������������̂Ȃ��ŏW�߂�ꂽ�u�S�ɂ��ݓ���b�v��I�肷���������̂ŁA�u���̕ǂ��z����G�b�Z���X�v���l�܂��Ă��܂��B
�����r�n�[���ɏW�܂��Ă���l�������A�������Ɠ������A�u���͔s�k�ł���v�Ƃ͍l�����A�u���͕K�R�ł���v�Ƒ����Ă��܂��B�����āA���������Ă��܂��B
�������Ƃ��Ă���l�X�͉����l���Ă���̂��A�������߂Ă���̂��A�W�܂����W�҂͉�����肩���Ă���̂��B�{���́A���҂�Ƃ�ɂ��Ȃ����߂̒m�b���W�߂����̂ł���B�����āA����O�ɖ�����Ă����l�̐S���̕ω���m�邱�Ƃ́A�܂������Ȃ��l�ł����Ă��A�Y�ꂵ�ސS�ɐ��݂킽��A���炬�����������Ă����B
�{���́u�s�K�Ȑl�����̘b�v�ł͂���܂���B
�ǂݎ�ɂ��A�傫�Ȉ��炬�ƌ��C��^���Ă����{�ł��B
����L���ɐ����邽�߂ɁA�����߂�1���ł��B
�R�����Y���X����w��
���u�����|���Ȃ��Ȃ�Ǐ��v�i���^��@���㏑�с@1400�~�j
���^�炳��̍ŐV��ł��B
�W���ɑ����Ă�����Ă����̂ł����A���Ԕj�Y�𑱂��Ă��āA�Љ�ł����ɂ��܂����B
���܂�x���Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂ŁA�܂�������Ɠǂ�ł͂��Ȃ��̂ł����A�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�{���̕���́A�w�u������v���u���Ȃ��݁v�������Ă����u�b�N�K�C�h�x�Ƃ���܂��B
���̕��肪�Ȃ��Ɩ{���̓��e�͂悭�킩��܂��A�������̈ē������{���̓��e��I�m�ɐ������Ă���Ă��܂��B
������ƒ����ł����A���p�����Ă��炢�܂��B
�����l�ނ̗��j�̒��ŁA���ȂȂ������l�Ԃ͂��܂��A������l��S�������l�Ԃ������ɂ��܂��B���̗�R�Ƃ��������������Ă����{�A�u���v�����邩��u���v������Ƃ����^���ɋC�Â����Ă����{���W�߂Ă݂܂����B����܂Ő�����Ȃ��قǑ����̏@���Ƃ�N�w�҂��u���v�ɂ��čl���A�|�p�Ƃ����͎���̐��E��\�����Ă��܂����B
�i�����j
�Ȃ��A�����̈�����҂��˔@�Ƃ��Ă��̐��E���������̂��A�����Ă��̎������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��B����قǕs�𗝂Ŏe�ꂪ�����b�͂���܂���B�{���ɂ́A���̕s�𗝂��e��āA�S�̃o�����X��ۂ��߂̖{����������Љ�܂����B
�܂�A�{���́A�u�����|���Ȃ��Ȃ�v�{���Љ��u�b�N�K�C�h�Ȃ̂ł��B
������A���ɑ����ʂ���̖{���T�O�������グ���Ă��܂��B
�������̊S���́u�K���v�ł��B
����܂ł̐l�ނ̂��܂��܂ȉc�ׂ́A���ׂāu�l�Ԃ��K���ɂ��邽�߁v�������̂ł͂Ȃ����ƈ������͍l���܂��B
�����āA���̐l�Ԃ̍K���ɂ��čl���āA�l���āA�l�����������ʁA���̍���ɂ́u���v�Ƃ������̂����R�Ƃ��č݂邱�Ƃɂ��ǂ�����ƁA�{���̍ŏ��ɏ����Ă��܂��B
���ƍK���B
�������́A�l���S���Ȃ����Ƃ��Ɂu�s�K���������v�ƌ������ƂɈ�a�����������ł��B
�������́A�u���v���u�s�K�v�Ƃ͐�ɌĂт����Ȃ��Ƃ����܂��B�Ȃ��Ȃ�A�����Ău�Ԃɏ����킽���͕K���s�K�ɂȂ邩��ł��B
���͂������ĕs�K�ȏo�����ł͂Ȃ��B
���l���A�ǂ��~�߂邩�́A�܂��Ɏ������̍K���ɂȂ����Ă����܂��B
�������́A���ʂ��Ƃ́u������v�ƁA������l���S���Ȃ����Ƃ��́u���Ȃ��݁v���������n���āA�Ō�ɂ͏����Ă䂭�悤�Ȗ{��I�ƌ����܂��B
�����āA���������{��ǂނ��ƂŁA���ʂ̔߂��݂�����u�O���[�t�P�A�v�ɂȂ�ƌ����܂��B
�������́A�͂��߂ɂŁA���������Ă��܂��B
�{�����Ō�܂œǂ܂ꂽ�Ȃ�A�����₩�ȁu���ʊo��v�Ɓu�̂������o��v�����R�ɐg�ɂ����邱�ƂƎv���܂��B����ƂƂ��ɁA���Ȃ����u�������]�v�������ĉ��������Ȃ�A���҂Ƃ��Ă���قNJ��������Ƃ͂���܂���B
�����l���邱�Ƃ́A�����l���邱�Ƃł��B
�u�����|���Ȃ��Ȃ�Ǐ��v�Ƃ����^�C�g���ɁA���͂ǂ����Ă���a��������܂����A�ނ���{���́u���悭�����邽�߂̓Ǐ��̂����߁v�ł��̂ŁA���ւ̕|��̂Ȃ��l�ɂ������߂��܂��B
�R�����Y���X����w��
���u���v�I ���ȐS�̓t�F�C�X�u�b�N�őގ�����!!�v�i�l�c�K��@���V�@1400�~�j
�����g���u���v�œ��@�����o���̂���l�c�����̂��V���[�Y��Q�e�ł��B
�O���u���Ȑl�قǐ����ł���v�Ɠ������A�����g�̑̌��܂����{�Ȃ̂ŁA�ƂĂ��킩��₷���A�����͂�����܂��B
����ȏ�ɁA�Ƃ������ǂ�ł��Ċy�����{�ł��B
��������̂͂��A�Ȃɂ���l�c����́A�����m���Ă���Ȃ��ł���тʂ��Ċy�����v���[���e�[�V�����̃v�����̃v���Ȃ̂ł��B
�l�c����ɉ�����ŁA���C���o�Ă��܂����A���̖{��ǂ����ł������甲���o���邩������Ȃ��Ǝv���قǂɁA���邢���b�Z�[�W���͂��Ă���{�ł��B
�����Ƃ��A�{���́u���v���̖{�ł͂���܂���B
�l�c����́A�������́u���v���甲���o���ŁA�t�F�C�X�u�b�N���傫�Ȗ������ʂ������̌����������ł��̂ŁA��l�ł������́u���v�C���̐l�Ƀt�F�C�X�u�b�N�̌��p��m���Ăق����Ǝv���āA�{�����������̂ł��傤���A���Ɩ����Ȑl�ɂƂ��Ă��A�l�c���̃t�F�C�X�u�b�N���p��͎Q�l�ɂȂ�ł��傤�B
�t�F�C�X�u�b�N���g�����߂A���E�͂�F�ɂȂ�Ǝv�킹��قǂ́A���ꂱ�݂悤�ł����A���ꂪ�܂��Ȃ��Ȃ������͂�����̂ł��B
�Ȃɂ��낷�ׂĂ��l�c����̎��H�Ɋ�Â��Ă̘b������ł��B
�������A�u�t�F�C�X�u�b�N�v���p���{�ɂƂǂ܂��Ă���킯�ł��Ȃ��̂ł��B
����́u����̓r�W�l�X���C�N����r�W�l�X�k�n�u�d�̎���ցv�ƂȂ��Ă���悤�ɁA�r�W�l�X�̑������̖{�ł�����̂ł��B
���₳��Ɍ����A�������̖{��������܂���B
�v����ɁA����t�F�C�X�u�b�N�ɊW�̂Ȃ��l���ǂ�ł��A��������̎����邱�Ƃ̂ł���{�Ƃ������Ƃł��B
�Ƃ������l�c����炵���A�T�[�r�X���_�����ȁA���C�̂����{�Ȃ̂ł��B
���e�̏Љ�����Ȃ��Ƃ����܂��A�����o���Ƃ��肪�Ȃ��̂ŁA�ڎ����Љ�Ă����܂��B
����łȂ�ƂȂ��킩���Ă��炦��ł��傤�B
��1�� �g���h�a�\�g�ǂ��h����̗�����
��2�� ��]�̌��g�t�F�C�X�u�b�N�h������ė���!!
��3�� �t�F�C�X�u�b�N���ǂ��g��?
��4�� �t�F�C�X�u�b�N�ɂ͂܂�
��5�� �t�F�C�X�u�b�N�́g�����h�̑�������
��6�� �l�c���g�t�F�C�X�u�b�N�̎g�����h5�僋�[��
��7�� �Ȃ��A�l�c��ẪC�x���g�ɂ͐l���W�܂邩?
��8�� �g�r�W�l�XLOVE�h�̎��オ����ė���!!
����܂�{�̏Љ�ɂ͂Ȃ�܂���ł������A���C�ɂȂ肽���l��t�F�C�X�u�b�N���͂��߂����l�ɂ́A���ɂ����߂̂P���ł��B
���Ȃ݂ɁA�l�c����̘b�͎��Ɋy�����A������������ł�������̌��C�����炦�܂��B
�܂��l�c����̂��b�������Ƃ̂Ȃ����͂��Ј�x���b���Ƃ����ł��B
���ꂾ���ŁA���ȐS�͂����ƂԂ�������܂���B
�݂Ȃ���̃O���[�v���Ђł��A���Еl�c����̍u������J���Ă��������B
���Ԃ���ӂ��p�b�Ɩ��邭�Ȃ�悤�ȁA����Ȍ��C�����炦��͂��ł��B
�{�������߂ł����A�u���������߂ł��B
�����l�c����ɂ���������Ȃ�����A�C�y�ɂ��A�����������B
�܂��y�����l�ł��B
���u���ɂ͑���������v�i���^��
vs ��쒼���@�o�g�o�������@1200�~�j
�{���́A�u�l�͎��ȂȂ��v�̒����������t�̖�삳��ƋߔN�O���[�t�P�A�̕��y�ɐs�͂���Ă���������̑Βk�ł��B
���Q�l�Ƃ��A��̓Ǐ��ƂŁA���������z���ƂĂ��_��ł��B
�ł�����A�b�͑���ɂ킽���Ă��܂����A�傫�ȃ��b�Z�[�W�͂Q�ł��B
�u���͏I���ł͂Ȃ��v
�u���͕s�K�ł͂Ȃ��v
�����̐l�́A������̃��b�Z�[�W�͑f���Ɏe����Ȃ���������܂��A
�{����ǂނƔ[�����Ă��炦��Ǝv���܂��B
�e����Ȃ��Ƃ����A�{���ł́A�썰��H��A�߈˂���̘b���o�Ă��܂��B
�����������Ƃ��e����Ȃ��l�����Ȃ��Ȃ��ł��傤���A
���Q�l�͎���̑̌��܂��āA���������ƌ���Ă���Ă��܂��̂ŁA
�ǎ҂ɂ͂��Ԃ��a���Ȃ������Ă���ł��傤�B
�����Ȃ�����������A���������̑̌������Ă��܂����A���Ǝ��ɗ������������d��������Ă��邨�Q�l�͂�������̑̌�������Ă���͂��ł��B
�Βk��ǂ�ł��āA���ꂪ���R�ɓ`����Ă��܂��B
�{���́A�O���[�t�P�A�̖{�ɂȂ��Ă��܂����A���ɂ͂ނ���A���������Y��Ă��܂����u��Ȑ������v���v���o�����Ă����{�̂悤�Ɏv���܂����B
���������ł����A���������������̂ЂƂ����p���܂��B
���h���t�E�V���^�C�i�[���Q�Ƃ��Ȃ���A�b�������Ă���Ƃ���ł��B
����F�킽�������́A���܂�ɂ����̐��̌����ɂ�����肷���Ă���̂ŁA���҂Ɉӎ���������]�T���قƂ�ǂȂ��ł���ˁB���҂ǂ�
�납�A���̐��ɐ����Ă���ғ��m�̊Ԃł��A���l�̂��Ƃ��l����]�T���Ȃ����炢�̐��������Ă��܂��B����ǂ��A�������Ƃ����āA�������g�ƂȂ炵��������������Ă��邩�Ƃ����ƁA�����ł�����܂���B�قƂ�ǂ̐l�́A�������g�ɑ���ԓx���A���҂ɑ���W�����r���[�Ȃ܂܂ɐ������Ă����Ԃł��傤�B
�ǂ�������A���̐��̐l�Ԃ͎��҂Ƃ̌��т������Ă�̂��B�V���^�C�i�[�ɂ��A�����������Ƃ��l����O�ɁA���ҁ��썰�������ɑ��݂��Ă���ƍl���Ȃ�����A���̖��͉������Ȃ��Ƃ����܂��B
����F���ҁ��썰�̑��݂�F�߂邱�Ƃ��O��ł���ˁB
����F�Ƃ��낪�A�����̑m���ł����A���ҁ��썰�Ƃ����̂́A�킽�������̐S�̒��ɂ������݂��Ă��Ȃ��Ƃ����l�������Ƃ����̂ł��B���������m���́A�l���S���Ȃ��ĕ��d�̑O�ł��o��������̂́A���̐��Ɏc���ꂽ�l�Ԃ̐S�̂��߂̋��{���Ƃ����̂ł��B
�����A���������Ӗ��ł��o�������Ă���̂Ȃ�A���҂ƌ��т������Ƃ��Ǝv���Ă��A���l���u���҂Ȃǂ��Ȃ��v�Ǝv���Ă���킯�ł�����A���т��̎����悤������܂���B
����ł��A�l�Ԃ͎��҂Ƃ��Đ����Ă��܂��B�������A���̎��҂Ǝ����Ƃ̊Ԃɂ́A�܂��͂����肵���W���ł��Ă��Ȃ��ƍl���邱�Ƃ��O��ɂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B
����F�킽�����w�l�͎��ȂȂ��x�Ō��������������Ƃ́A�܂��ɐl�Ԃ͎��ҁi���E�̐l�j�Ƃ��Đ����Ă���Ƃ������Ƃł��B
���͖����A�Ȃ̈ʔv�̑O�œnjo���Ă��܂����A�����Ď����̐S�̋��{�ł͂���܂���A
���̎��Ԃ́A�܂��ɍȂƂ̌𗬂̎��Ԃł��B
���ꂪ�ł���̂��A�Ȃ��܂��A�p�����Ⴆ�ǐ����Ă���Ɗm�M���Ă��邩��ł��B
��������p���Ă���A�V���^�C�i�[�̌��t���Љ�Ă����܂��傤�B
�����A�������Ă��錾�t�ł��B
���̂킽�������̐l���̒��ŁA���҂�������̗�I�ȉ��b���Ȃ��Ő������Ă���ꍇ�͂ނ��돭�Ȃ����炢�ł��B�������̂��Ƃ��A���̐��ɐ����Ă���l�Ԃ̑����͒m��܂���B�����āA���������̗͂ł��̐l���𑗂��Ă���悤�Ɏv���Ă��܂��B
���p�������Ȃ��Ă��܂��܂����B
�{���̐��藧������e�Ɋւ��ẮA�Βk�҂��������̃u���O�����ǂ݂��������B
������̂ق����A�{���̓K�ȏЉ�ł��B
����ɁA�{���Ƃ͂܂�������ʔ���������܂��̂ŁA�����߂��܂��B
�O���[�t�P�A�ȂǕK�v�Ȃ���ƌ����l�ɂ��A�����߂̈���ł��B
���t�N�V�}�������`�F���m�u�C��26�N�ڂ̐^���i�@���Ǖہ@�����Ɂ@2013�j
�A�[�g�Z���s�X�g�̒������D���A�y�C�t�H���[�h�����ł��̖{���L�������Ƃ����āA�����Ă��Ă��ꂽ�̂��A���̖{�ł��B
�o�ŎЂ�ސE���A���܂͕����ɏZ��ł���@���Ǖۂ��A�v�������߂Ď���o�ł����{�ł��B
�����ɓǂ܂��Ă��炢�܂����B
�����m��Ȃ����Ƃ�������Ă��܂����B
������ƂĂ��Ռ��I�Ȏ����ł��B
�`�F���m�u�C�����Ǘ�����E�N���C�i�̊�����A���{�̊�͂��܂��Ƃ��������ł��B
�{���̋L���̈ꕔ�����p���܂��B
�E�N���C�i�@�ł́A�ڏZ�`���]�[��������0�D57�}�C�N���V�[�x���g�B�ڏZ�����]�[���i������n��ŁA��������{������̏Z����j������0�D11�}�C�N���V�[�x���g�B
2013�N1��1���̌S�R�s�͖���0�D55�}�C�N���V�[�x���g�A�����s�͖���0�D63�}�C�N���V�[�x���g�ł����B�E�N���C�i�@��K�p����Ε����s�͋������n��A�S�R�s�͎�����n��ł��B�����ɂ��܂��ɑ����̎s������炵�Ă���̂ł��B
���Ȃ݂ɁA��t���䑷�q�s�ɂ���킪�Ƃ̒�́A��N�̑���ł͏��Ȃ��Ƃ�0�D11�}�C�N���V�[�x���g�ȏ�ł��B��̎Ő��̕\�ʂő����0.3������܂����B
�{���́A2012�N9���ɏ@�������Ԃ����ƈꏏ�ɁA26�N�O�Ɍ������̂��N�������`�F���m�u�C���ɍs���āA���n�����āA���n�̐l�������畷���Ă������Ƃ��܂Ƃ߂����̂ł��B
�@������́A���������Ă��܂��B
�������̏Ռ��I�Ȏ�����ڂ̓�����ɂ��܂����B�t�@�C���_�[��ʂ��Đ������ʐ^�ɂ́A�߂����^���������܂��B
�������̂���26�N�������݂ł��A�`�F���m�u�C���̓��ʋ��́u�]�[���v�ƌĂ�A�L�h�S���̃t�F���X�ŋ���A��������֎~�ƂȂ��Ă��܂��B�����Č�������k��350km�ɂ͖�100�J���̃z�b�g�X�|�b�g���_�݁A���̍��Z�x�����n��ł͔_�Ƃ�{�Y�Ƃ��֎~����Ă��܂��B
�ʐ^���炽������̃��b�Z�[�W�������Ă��܂��B
�������łȂ��A�����̐l�ɁA���̃��b�Z�[�W��`�������B
�������A���ɂ��̖{�������Ă��Ă��ꂽ�Ӗ����킩��܂����B
�����{�����L���邱�Ƃɂ��܂����B
�悩�����為�Ў�ɓ���Ă��������B
������@�͂��܊m�F���Ȃ̂ł����B
�@������͕������S�R�s�̂��o�g�������ł��B
��N���ɉ�Ђ�ސE���A�u�t�N�V�}��炵�v���n�߂������ł��B
�u�t�N�V�}��炵�v�Ƃ������t���S�ɋ����܂����B
���̌��t�ɖ����Ȑl�͂��Ȃ��͂��ł��B
���u������ ��������ƃ}�i�[�v�i���^��ďC�@�˓`�Ё@�T�V�P�~�j
���^�炳��̊ďC���ꂽ�{�͉������o�Ă��܂����A����̖{�͂�����Ɩʔ����̂ŁA�����ŏЉ���Ă��炢�܂��B
�����ʂ�A���ؒ��̐��������̔�r���܂Ƃ߂��n���f�B�u�b�N�ł��B
�ŋ߁A���{�Ɗ؍��A���{�ƒ����́A�̓y���Ȃǂ�ʂ��āA���܂�W���悭�Ȃ��ɂȂ��Ă��܂����A���ؒ����Ȃ������ɑ��w�̐[���������Ƃ��ẮA�ƂĂ��c�O�Ȃ��Ƃł��傤�B
�{���̂͂������ŁA�������́u�{���ɓ��{�E�����E�؍��̗ǍD�ȊW�\�z�Ɠ��A�W�A�̕��a�ւ̊肢�����߂܂����v�Ə����Ă��܂��B
�̍��{�ɂ���u��v�Ƃ́A���Ƃ���2500�N�O�̒����̏t�H�퍑����ɂ����āA�����̗̓y��N���Ȃ��Ƃ����K�͂Ƃ��Đ��܂ꂽ���̂������ł��B
���Ƃ�����A�ŋ߂̓����̑����́A�����ɂ��������b�ł��B
����͂Ƃ������A�u��v����́A���܂��܂ȁu��������v���h�������ƈ������͌����܂��B
���ꂪ�����ł́A�����Ɉ���Ă��Ă���킯�ł����A���̈Ⴂ��m�邱�Ƃ͂ƂĂ������[���ł��B
���ꂾ���ł͂Ȃ��A��������������Ƃ����Ⴂ���A�����̂��������ɂ��傫���e�����Ă��邩������Ȃ��Ǝv���ƁA���̈Ⴂ�Ƌ��ʓ_��m���Ă������Ƃ̑�����悭�킩��܂��B
�{���́A�u���C�t�X�^�C���v�u�������Ձv�u�`���s���v�u�q��ĂƋ���v�u�r�W�l�X�}�i�[�v�Ƃ������T�̃p�[�g�ɕ����āA���ꂼ��̕���́u��������v���Љ��Ă��܂��B
���^�̕��ɖ{�Ƃ͂����A���Ɂu�������Ձv��u�`���s���v�͗ޏ��ɂȂ��ڂ����ł��ƈ������͏����Ă��܂��B
�ڂ��������邱�ƂȂ���A�S�̑��������Ă��邱�Ƃ��A�{���̋��݂ł��傤�B
������؍��ɗ��s�����ꍇ�ɂ́A�ƂĂ��֗��ȃK�C�h�ɂ��Ȃ�܂��B
�o�����鎞�́A�Y�ꂸ�ɁA�ł��B
���Ԃ̂��鎞�ɁA�C�y�ɓǂ�ł����ƁA�����ȋC�Â��������Ėʔ����ł��B
�� �u�l���Ȃ��_�v�i�������H�@�A���}�b�g�@1300�~�j
��������͎��Ɍ��I�Ȑl���𑗂��҂ł��B
�R�s�[���C�^�[�ł�����A�V���K�[�\���O���C�^�[�ł�����A�u���E�v���e�[�}�ɂ��������҂ł�����܂��B
�t���[�^�[���ƋΖ���̌�������A���܂͑�w�@�̔��m�ے��ɂ��܂��B
���́A��������̏C�m�_����ǂ܂��Ă��炢�܂������A���ꂪ�ƂĂ��ʔ����A�����{�ɂ�����Ǝv���Ă����̂ł����A���̑O�ɁA�����Ɩʔ����{���o���Ă��܂��܂����B
���ꂪ�A���́u�l���Ȃ��_�v�ł��B
���N�O�ɐ�������̏����Ă��������̃u���O��ǂ܂��Ă�������Ƃ��ɂ��ʔ��������̂ł����A�Ȃ��Ȃ��X�V���Ȃ���Ȃ��̂œǂނ̂���߂Ă�����A���̊Ԃɂ�����ȗ��h�Ȗ{�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
�����āA���ɖʔ��������͂�����A�[�������ɕx��ł���̂ł��B
�\���Ɂu�Y�܂Ȃ���Γ�����������I�v�Ƃ��u����̂܂�܂ŋ@���悭�����锭�z�@�v�Ə�����Ă��܂����A�܂��ɂ����������e�p�ł��B
�������A�P�ɂ��ꂾ���ł͂���܂���B
������Ǝ����������̂œǂݗ��Ƃ������ł����A�N�w�҂̓��R�߂������������Ă��܂��B�u�����Ƃ��������R�Ȑl������ɓ���邽�߂ɎႢ�����������グ���V��������̐l���_�v�B
�Ȃɂ��ǂ݂����Ȃ�܂��ˁB
��������́u�͂��߂Ɂv�̌��t�����p���܂��傤�B
�قƂ�ǂ̐l���A�q�ǂ��̂��납��u�l���邱�Ƃ̑���v���������Ĉ���Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�u�������莩���ōl���Ȃ����v
����Ȍ��t���A���x���ɂ��Ă������Ƃł��傤�B
�������ڂ����A�����f���ɕ����Ĉ炿�܂����B����A�ނ���l���݈ȏ�Ɂu�l���邱�Ɓv�Ɉˑ����Ă����l�Ԃ�������܂���B�l���邱�Ƃ���߂�ƁA��������������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�ȁA����ȋC�������Ă��܂����B
�ł�����Ƃ��A�ǂ�Ȃɍl���Ă����܂������Ȃ��Ɋׂ��Ă��܂����̂ł��B�l����l����قǂɁA�S�Ă����܂������Ȃ��B�قƂقƍl���邱�Ƃɔ��ʂĂāA�����̓��̒���������߂��x�z�����Ƃ��A�ʂ̍l�����t�b�ƕ�����ł��܂����B
�u�ǁ|���l���Ă����܂������ւ�̂������A������܂������t�̂��Ƃ�����Ă݂悤�v
���̑̌����琶�܂ꂽ�̂��{���ł��B
�S�V�̏͗��ĂŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
�N�w�I�Șb������Δ]�Ȋw�̘b������B
�������o����A�������o����B
������|�̘b������A������Ɓu�l������ł��܂��v�b������B
�������u�l���Ȃ����߂̎��H�@�v������܂��B
�Ƃ������ǂݏo���Ƃ����ƈ�C�ɓǂ�ł��܂����͂�����܂��B
��������́A���̖{���y���݂Ȃ�����肠�����ȂƎv���قǁA�y�����{�ł��B
�l���邱�Ƃɔ�ꂽ�l�͂������ł����A�l���Ȃ��Ő����Ă����l�ɂ������߂̈���ł��B
���u70�������e����������72�̕��@�v�i���c���b�q�@���o�Ł@1400�~�j
�u����ĕ�炷�e�̃P�A���l�����p�I�b�R�v�����_�ɒ��N�A���u�n���̖��Ɏ��g��ł��鑾�c���A����܂ł̎��H�����������u�ʋ����̈��S�ǖ{�v�������܂����B
���ꂽ�Ƃ���ɏZ��ł���e�̉��̂��߂ɁA��Ђ����߂���Ȃ������F�l���A���ɂ����l�����܂����A���ꂩ�炻�������l�͂���ɑ����Ă�����������܂���B
����͓����҂ɂƂ��Ă͂������ł����A�Љ�ɂƂ��Ă��傫�Ȗ��ł��B
���c����́A�����������ɑ�������C�Â��A�����̐l�̑��k�ɏ���Ă��܂����B
�{���̑тɁA����������Ă��܂��B
�u�d���𑱂��Ȃ���A�e�Ɨ���Ă��Ă��A���Ȃ��ЂƂ�ł��A�����܂łł��܂��v
�{����ǂ߂A���̗F�l�������A�������������Ђ����߂Ȃ��ł悩������������܂���B
��Ђ����߂邱�Ƃ́A�ЂƂ̑I�����ł͂���܂����A����ɂ���Ď������̂����Ȃ�����܂���
����Љ�ɓ���A����҂̐������x���邳�܂��܂Ȏd�g�݂����܂�Ă��Ă��܂��B
�������A�u�V�����e����������͎̂q�̖����v�Ƃ����Љ�ň���������́A���������d�g�݂����܂����p�ł����ɂ��܂��B
����A���̐����e�Ɏ�����́A�e�̉������������d�g�݂ɂ䂾�˂邱�ƂɁu�����ځv�����������ł��B
�����́u���ȐӔC�v���z�̕������A��������������ɋ��߂Ă���̂�������܂���B
���������̎d�g�݂��������ꂸ�A�t�ɖ��G�ɂ��Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�����ł��傤�B
���c����́A�d���Ƃ̗����ɔY�ސl�������A ���b����q����������Ԃ̃g���u���������A�ߎS�ȏɂȂ�P�[�X�����Ȃ��Ȃ��A�Ə����Ă��܂��B
�������Ɏ��̎��ӂɂ��A�����悤�Ȗ��������l�͏��Ȃ�����܂���B
�������A�����������k�ɏ���Ă������c����́A���������̂ł��B
�@�ł����v�B�l�̗͂����Ɏ������̂ł��B
�@�e�͂�낱�Ԃ��A���Ȃ��������ƃ��N�ɂȂ�܂��B
�@����Ȓm�b���Љ�܂��B
���́A���̌��t�Ɂu���̉��l�v�������܂��B
�͂�݂��Ă��ꂽ�l���܂��A�K���ɂȂ邩������܂���B
���������Ȃ�A�܂��Ɂu�O���悵�v�ɂȂ邩������܂���B
���́u��삵�Ă��v�����ł͂Ȃ��A�u��삳���Ă��v�Ƃ����A�傫�ȗ͂������Ă��܂��B
����ɋC�Â��A�����̑������͈�ς��܂����A�ǂ�������������l�͑����͂���܂���B
���̕�����ς��Ȃ�����A�Љ�͏Z�݂悭�Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂����A������������A���u�n���ł̑̌��������������ƂɋC�Â����Ă���邩������܂���B
����͂Ƃ������A���������L�����Ă��������̐����x���̎d�g�݂����܂����p���Ă����A�������Ȃ��Ă��ł��邱�Ƃ͂�������̂ł��B
���ꂾ���ł͂���܂���B
�t�ɂ��������d�g�݂����p���邱�ƂŁA�e�q�Ƃ��ǂ����C�ɂȂ�����łȂ��A�V�����l�̂Ȃ��������Ă���̂ł��B
�u�e�̉��v�������ƍm��I�ɑ��������ƁA���͎v���Ă��܂��B
�u��삷�鑤�̐S�I�s���A�g�̓I�E���K�I���S���y�����邽�߂̕���ɂ��ċ�̓I�ɏq�ׁA
�e�̋C�����d���Ȃ���A�����������̉Ƒ����K���ɂȂ����@�v���܂Ƃ߂��A�Ƒ��c����͏����Ă��܂��B
�܂�A�{���́u�Y�݉����̏��v�ł͂Ȃ��A�u�K���ɂȂ�鏑�v�Ȃ̂ł��B
�ڎ������Ă��炤�ƁA���̓��e���悭�킩��Ǝv���܂��B
�P�́@�e���q�����N���悤�I�\�����͎���ɂ��Ď�`��
�Q�́@�e�̊y���݂���������\�����������K������Ȃ�
�R�́@���ꂽ�܂܂ʼn�삷��\�߁E���������炳������
�S�́@���̏o��������������\���n�R�ɂȂ�Ȃ����߂�
�T�́@�e�̈��S�E���S����������\�g���u�����N�����Ȃ�
�U�́@�e��Z����e���Ԃ̃C�U�R�U�\���ꂪ�[���Ȗ��
�V�́@�e�̉��Ǝ����̎d���𗼗�������\���ꂪ�ő�̃e�[�}
����������c����̒��N�̑��k�����Ɋ�Â������̂Ȃ̂ŁA�ƂĂ���̓I�ŁA�����ɂ�����������̂�����܂��B
�����e�̉�삪�C�ɂȂ��Ă���l�ɂ́A���Ђ����߂ł��B
���͎��͂���70�����ł��̂ŁA������ƕ��G�ȋC���œǂ܂��Ă��炢�܂������B
�R�����Y���X����w��
���u�n��ŗV�ԁA�n��ň�q�ǂ������v�i�[���Y�ق��@�w���Ё@1900�~�j
�q�炿�w�̍l���ŁA�q�ǂ������Ɋւ���Ă���[�삳���̐V�����{���ł��܂����B
����́u�n��v�Ɓu�V�сv���e�[�}�ł��B
�ŋ߂ł́u�q�炿�x���v�Ƃ��������t�����Ȃ�g����悤�ɂȂ��Ă��܂������A
�u�q��Ďx���v�Ɓu�q�炿�x���v�̈Ⴂ�́A�v���I�Ȕ��z�̓]���Ƃ����ׂ��ł��傤�B
�q��Ďx�����A���Ɂu�q�炿�v���ז����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ͌����܂���B
�u��Ă�ΏۂƂ��Ă̎q�ǂ��v�ł͂Ȃ��A�u���̂Ƃ��Ă̎q�ǂ��v�ւƔ��z��ς���ƁA
�q�ǂ��Ƃ̊W�����ς��A�x���̂�����͑傫���ς�܂��B
�����������_����A20�N�قǑO����[�삳���͊������A���z�]���̑���𐢂ɖ₤�Ă��܂����B
����I�ɐ��ʂ��o�ł��Ă��Ă���̂��A���������^���̂ЂƂł��B
���̈�A�̒�����ŏ����炸���Ɠǂ܂��Ă�����Ă���ǎ҂Ƃ��ẮA
���̐i���̂قǂ�����y���݂Ȃ̂ł����A����͊��҂�����[�܂�������܂����B
�{���͕����̎�茤���҂���H�҂���e���Ă��܂����A�P�Ȃ�W�ߘ_�W�ł͂���܂���B
�ҏW�ψ���������W�܂��ċc�_���A���H��⎷�M�҂�I��ł������̂ł��B
���̂������ŁA�S�̂������ɂ܂Ƃ܂����ЂƂ̃��b�Z�[�W���Ă��܂��B
����ɗ����̂́A�u���̂Ƃ��Ă̎q�ǂ��ɑ��ĉ����ł��邾�낤���v�Ƃ����A�q�ǂ��ւ̂��������Ȗڂł��B
���������M�҂����́A����ɑ��铚�Ƃ��Ď��H�I�ȋ�̍���y�������Ɍ���Ă���̂ł��B
���ꂼ�ꌻ��������Ď��H���Ă��鎷�M�҂����̎��M���`����Ă��āA�ǂ�ł��Č��C���łĂ��܂����A
�q�ǂ������̑f���炵���������ł���ł��傤�B
�{���͂R���\���ł��B
��P���̑��_�҂ł́A�u�V�сv�Ɓu�n��v�Ɋւ��ۑ�Ƙ_�_����������A
�V�т�ʂ����q�炿�x����u�n��̃W�����}�v�����̕���������������Ă��܂��B
��Q���̎��H�҂́A���̕�����������Ă���T�̎��Ⴊ�Љ��Ă��܂����A
�����ʂ��āA�q�炿�x���̈Ӗ������ɂ�����͂��ł��B
��R���̊e�_�҂ł́A�u�n��v�Ɓu�V�сv���A����ɐ[������Ă��܂��B
���̂R�����A�S�̂Ƃ��Č����ɕҏW����Ă��܂��B
�܂��{���̑傫�ȓ����́A���M�҂Ƃ��āA�q�ǂ��������Q�����Ă��邱�Ƃł��B
�u�q�ǂ��̎Q��v�ɂ�������Ă���[�삳��̎v�������߂Ď������܂����B
�[�삳��͂��������Ă��܂��B
�q�ǂ��̗V�т�̌����n�������Ă���Ƃ̖��S����A���݂��܂��܂Ȏ��H�����g�܂�Ă��܂����A�q�ǂ��̗͗ʌ`���ƂƂ��ɁA��������l�̗͗ʌ`�����K�v�Ȃ̂ł��B�u�q�ǂ�����́v�Ƃ������Ƃ���ɐ����Ďq�ǂ�����������n�����鐢�E��ۏႵ�Ă������ƁA�����āA�q�ǂ��̐��E�ɕK�v�ȏ�ɉ�������ɐM���Č����▭�ȁu�������v��{�����Ƃł��B���̂��Ƃ��A�n���ɗV�т�ʂ����u�q�炿�x���v�ɋ��߂��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�������܂��B�{���́A�܂���P���ŁA����܂ł̊����̎��H����Љ�Ȃ���A
�u�n��ł̎d���������v�̈Ӗ��Ǝ��g�ݕ����Ă��˂��ɐ������Ă��܂��B
�����đ�Q���ł́A�d�����������[�N�V���b�v�̐i�ߕ�����̓I�Ɍ���܂��B
�L�x�Ȏ��H�������Ă����u�P�ؗ����[�N�V���b�v�v�ł�����A�ǂ�ł��āA���ۂ̏�ʂ���������Տꊴ�Ƌ��ɁA
�P����̒n��ւ̎v������₨�l�����`����Ă��܂��B
�ǎ҂��A�n��ł̎d���������̖��͂�Ǒ̌����Ȃ���A���H�I�Ȓm�b���K���ł��܂��B
��������܂œǂ��[�N�V���b�v�ɊW����{�̒��ŁA��ԕ\����������{�ł��B
�������A�����{���ɖ��͂��������̂́A���ꂾ���ł͂���܂���B
�{���ɗ����A�P����̒n���d���Ɋւ���l�����ł��B
�����́u�܂��Â���v��u�\�[�V�����r�W�l�X�v�Ɋւ���c�_����H�ɁA���͑傫�Ȉ�a���������Ă���̂ł����A
�P����̂���͎��ɐS�ɋ����܂����B
�P����́A���������Ă��܂��B
������ƒ����ł����A�P����̕��͂��Ȃ��ŁA�Љ�܂��B
���́A�s���������I�ɎЉ�̌��v�Ɏ����鎖�Ɓi��c�����Ɓj���N�������Ƃ���s�����u�s������̎d���������v�ƕ\�����Ă��܂��B
���������s�����L���邱�Ƃɂ��A�s��D���`�ɂ��c�Љ�̌��ׂ������ƂƂ��ɁA�V�����Љ�ւ̏����ƂȂ��̂��`������Ă������Ƃ�W�]���Ă��܂��B
�i��̓I�ɂ́j�n��ɏ������܂��d���ݏo���Ă������Ƃ��n��̌o�ϓI�Ȏ����𑣂��A�n��Љ���x������╟���Ȃǂ̊�����K�v�Ƃ��A�x����̂��ƍl���܂��B
�i����́j�c���{��`�o�ς�y�䂩��ϊv����Љ���ł���Ƃ̎u�������āA���ꂱ����d�̐��_�Œ��킷�钇�Ԃ��L���Ă��������Ǝv���܂��B
�u�s������̎d���������v�́A�P����ɂƂ��āA�u�n��̎��������������̎�Ŋ������Ȃ���A�����Ɛg�߂Ȑl�����̂��߂ɓ����Ƃ����^���v�Ȃ̂ł��B
�����āA�P����͂����������܂��B
�u�d�����̂��̂̂Ȃ��Ɉӎ��I�Ȋ��o�̊�т�����v�悤�Ȏd�����A���������̎�Ő��ݏo���^�����L���Ă������ƂŁA�n��̐����̎������߂Ă������Ƃɍv���ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă��܂��B
���̍l���Ɋ�Â��āA�P����͒n��ɖ߂��Ċ������d�˂Ă����̂ł��B
���̐��N�A�P����ɂ�����Ă��܂��A�{����ǂ�Ŗ����ɂ���������Ȃ�܂����B
�ƂĂ��ǂ݂₷�����͓I�Ȗ{�ł��B
���ꂩ��Љ�ɏo�čs���Ⴂ����A�Љ�Ŕ��Ă����l�����A��Ђ𑲋Ƃ��Ēn��Љ�ɓ��낤�Ƃ��Ă���l�����A�݂�Ȃɂ��E�߂̖{�ł��B
���Ȃ݂ɁA�P���������g��ł���A�u���邭��G�R�v���W�F�N�g�v�u�̉ԃG�R�v���W�F�N�g�v�Ƃ����Q�̊��������X�����Љ��Ă��܂��B
��������w�Ԃ��Ƃ���������͂��ł��B
�����̐l�ɓǂ�łق����A�Љ�ϊv�̂��߂̏��ł��B
�R�����Y���X����̍w��
���w�h���b�J�[ 2020�N�̓��{�l�ւ́u�a���v�x�i�c���퐶�@�W�p�Ё@1400�~�j
���҂̓c���퐶����́A���{�̂m�o�n�����̍L����ɐs�͂��Ă����l�ł����A
��Ƃ̃}�l�W�����g�_�ō����ȃh���b�J�[�̈���q�ł�����܂��B
������P�Ȃ�搶�Ɛ��k�̊W�ł͂Ȃ��A�c������̌��t�����A
�u���i���̉�b��ʂ��Ă̌𗬁v�������悤�ŁA����̐������ɂ��Ă������̂��Ƃ��w��ł����悤�ł��B
���̓c�����A�c������łȂ���Ώ����Ȃ��h���b�J�[�������Ăق����ƌ����ď������̂��{���ł��B
�������ɖ{���ɂ́A�u����܂œ��{�ł��܂����Ă��Ȃ��h���b�J�[�v������Ă��܂��B
���ꂾ���ł͂���܂���B
������ԋ��������̂́A�c���������̎v������������ƕ\�����Ă��邱�Ƃł��B
�܂�A�����̎v�����d�˂Ȃ���h���b�J�[������Ă���̂ł��B
���҂̎v���̂������Ă��Ȃ��{�͎��ɂ͑ދ��ł����A�{���ɂ͒��҂̎v�����ӂ�ɂ������Ă��܂��B
�������̕��A�������ǂ��������܂������A�����ɂ܂��c������̐l�Ԗ��������܂����B
�c������́A���Ƃ����Ŏ���̐S�̓��������\�����Ă��܂��B
�܂��A�{���͎����ɂƂ��Ắu���z���̒��v���Ƃ����̂ł��B
�c������炵���A���������́u�V�Ԃ�v�������܂����A���ɂ��ꂵ�����t�ł��B
���̎���A�l�͐��Ȃ�������Ȃ��Ǝ��͂����Ǝv���Ă��邩��ł��B
�c������́A�u�h���b�J�[�̃i�`�X�̔ᔻ�������i�߂邤���Ɂv�A�u�����̓��{�̐����E�L���҂̍����A�Љ���̍������݂�ɂ��A�h���b�J�[�̌��t��`���˂Ȃ�Ȃ��v�Ǝv�����Ə����Ă��܂��B
���ꂪ�{���̏����ɍ��߂��v���ł��B
�c������͂��������̐S���f�I���Ă��܂��B
����́u���S�̍߂Ƃ̊����v�ł��B
�u�{���̏d�v�ȃL�B���[�h�̂ЂƂ́u���S�̍߁v�ł��B
���́A���̍߂������g���Ƃ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƔY�݂Ȃ���L���Ă��܂����B
����ɁA�u���́A�ʒu�Ɩ����������Ă��������Ɛ����Ă��邾�낤���H�v�Ƃ����^�₪���т��ѓ����悬��܂����v�B
�����Ă��������Ă��܂��B
�u�h���b�J�[�̎v�z�̌��_��T��ɂ�A�������g�ɑ��Ė₢��������Ȃ��Ȃ��Ă䂫�܂����B
�����炭����́A�Ⴋ�h���b�J�[���A���M��ʂ��āA�������œ����Ă�������Ŋ���������ł��B
�����āA���̂悤�ȃh���b�J�[�̎v�����F�l�ɓ`����Ă����K���ł��v
�ǂ��ł��傤�B�ǂ܂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B
�Ƃ���ŁA�{���̓��e�ł����A���ꂩ��̎Љ�̂�����A���̂Ȃ��ł̊�Ƃ��c���g�D�̂�����Ɋւ���A�ƂĂ���̓I�ȃ��b�Z�[�W��������Ă��܂��B
�������A�ƂĂ��V�N�ȃL�[���[�h����������܂܂�Ă��܂��B
�c������͂��łɉ������̃h���b�J�[�̒����̖|��⎩��̂m�o�n�_�̎������o���Ă��܂��̂ŁA
�����������ƂɊւ��ẮA�����ł͐G��܂��A�h���b�J�[�v�z�̌��_�ƃh���b�J�[�̃r�W�����������Љ�Ă����܂��B
�h���b�J�[�̎v�z�̌��_�́A�u�i�`�X�̑S�̎�`�ւ̔ᔻ�ł���A���̔ᔻ���N�_�ɐ��܂ꂽ�V�����Љ�v���Ɠc������͌����܂��B
�����̎Љ�̒��ŁA�h���b�J�[���u�ʒu�Ɩ����������Ȃ���ΎЉ��܂͂����ɂ����v�u���Ƃ͐l�ƎЉ�Ƃ̐ړ_�����łȂ��A�Ƒ����J�����j��B�l�X�͂₪�āA���S�ɂȂ�A���������Ȃ��Ȃ�v�Ɣ������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��܂��B
�Љ�Ƃ̐ړ_�������A�u�ʒu�Ɩ����v���������l�́A���_�I�ɂ����������B
���������āA�h���b�J�[���߂������Љ�́A�u��l�ЂƂ�̐l�Ԃ��ʒu�Â��Ɩ����������A�Љ�I�Ȍ��͂��������������ċ@�\���鎩�R�ȎЉ�v�ł��B
���ꂾ���ŁA�h���b�J�[�̃}�l�W�����g�_�ւ̗������L����܂��B
�h���b�J�[�̊S�́u��ƌo�c�v�ł͂Ȃ��u�Љ�̓����̂��肩���v�������̂ł��B
������ۂɎc�������͂��B���ƂQ�����Љ�܂��B
�u�R�~���j�e�B�Ƃ͖��ŔώG�Ȃ��̂�����ǁA����a�����邽�߂ɕK�v�Ȃ̂́A���ǂ͎v�����Ȃ̂��B�v
�ŋߘb��ɂȂ肾���Ă���u�P�A�����O�E�G�R�m�~�[�v���v���o���܂����B
�u�ȑO�̖����Ƃ͒n�k��䕗�Ȃǎ��R�̂��̂ł��������A�i�푈�Ⓑ�����ƂƂ����j�u�l�H�̖����v�́A��������l�����������̂ł���A�����炱������ׂ����ЂƂȂ����B�v
���̌��t�ł͍��b��ɂȂ��Ă��錴�����v���o���܂����B
�ق��ɂ��Љ�������Ƃ͂�������̂ł����A����ȏ㏑���ƒ����Ȃ肷���ł��̂ŁA���Ƃ͂��Ж{����ǂ�ł��������B
�m�o�n�W�ҁA��ƊW�҂͂��Ƃ��A���̐����Ă���l���ׂĂ̓ǂ�łق����{�ł��B
���Ђ���ɂƂ��Č��Ă��������B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u�܂��Â���ҏW��c�v�i�݂́`�ꕨ�ꐧ��ψ���@���{�n��Љ�����@1800�~�j
��錧�����ʎs�ɂ��镶���Z���^�[�u�݂́`��v�́A�����m�����A��Ԍ��C�Ȓn�敶���Z���^�[�ł��B
10�N�O�ɁA�Z��������ɂȂ��Ă���A���������_�ɒn��̕����������ɑ傫������Ă���̂ł��B
���i�K���玄�͊ւ�点�Ă�����Ă��܂����A���̌o�܂͂��̃T�C�g�ɂ����낢��Ə����Ă��܂������A�Z���ƈꏏ�ɖ{�ɂ����܂����B
�u�������݂́`�ꕨ��v�ł��B
���́u�݂́`��v���P�O�̒a�������}���܂����B
������_�@�ɁA�܂��{�����肽���ƏZ���������l���܂����B
��������Đ��܂ꂽ�̂��A�{���ł��B
�u�݂́`��v���ł��āA�����Ɗւ�邱�ƂŁA�l����ς����l���������܂��B
�u�݂́`��v�����_�ɁA��������̖L���ȕ���������Ă��Ă��܂��B
�{���́A���������u�����Z���^�[�ɂǂ��l�����̕���v�ł��B
�Z�����������������e��ǂ�Ŋ������邱�Ƃ����������܂����B
�����āA�����Ɂu�܂��Â���v�̖{���������܂����B
�u�݂́`��v�̌��݂��c�_���ꂾ�������ɁA���̓A�h�o�C�U�[�Ƃ��ČĂ�܂����B
���������Ő\���グ���̂́A�u�����Z���^�[������̂ł͂Ȃ��A������n��̂ł��v�Ƃ������Ƃł��B
�n�R���m�Â���̕����ɂ�焈Ղ��Ă��܂������A�n�R���m�̌��p�̑傫�����A���͊����Ă��܂����B
���̖{��ǂ�ł��炤�Ƃ킩��Ǝv���܂����A���̂��̎v���͌����Ɏ�������Ă��܂��B
�����Ă��܂₱�̒��i�����͔��엢���A���܂͏����ʎs�j���傫����Ƃ��Ƃ��Ă��܂��B
�{���́u����ҁv�Ɓu�L�^�ҁv�̂Q���\���ł��B
�u����ҁv�ł́u�݂́`��v�Ő��E���L�����W�l�̕���𒆐S�ɁA�Z������̂��܂��܂Șb���Љ��Ă��܂��B
�u�L�^�ҁv��10�N�ԂɎ��g��ȃC�x���g�����Ă����O���[�v���Љ��Ă��܂����A�����ł�����͏Z�������ł��B
���́A�ҏW�Ɋւ��܂������A�Z���݂̂Ȃ���ƈꏏ�ɖ{�Â���Ɏ��g�ރv���Z�X�͎��ɖ��͓I�ł��B�r���œ����o�������Ȃ������Ƃ�����܂������A�Z���݂̂Ȃ���̃G�l���M�[�ɂ͒E�X�ł����B
�݂Ȃ���̔M�ӂ��A�ƂĂ��ǂ��{�ݏo�����Ǝv���܂��B
�����Z���^�[�݂̂Ȃ炸�A�܂��Â���ɊS�̂���l�����ɁA���Гǂ�ŗ~�����ł��B
�ǂ�ł���������A�Ȃ��������u�܂��Â���ҏW��c�v�Ȃ̂����������Ă��炦��Ǝv���܂��B
�܂��́A���܂��܂Ȑl�̕���Ő��藧���Ă���̂ł��B
���̕��ꂪ�A���ꂼ��ɖL���ŁA�Ȃ��肠���Ă���A�n����t���ȂǓ��Ăɂ��Ȃ��Ă��A�܂��͖L���Ɉ���Ă����̂ł��B
�{�͏Z���������݂�ȂŔ����Ă������ƂŁA��p��������悤�Ƃ��Ă��܂��B
�����S�������Ă�����������A�����ʎs�́u�݂́`��v�ł��̔����Ă��܂��̂ŁA�����ɍs���Ă��������B
�����̐l�͎��ɂ��A�����������B
�����C�ւ̃��[��

���u�n��E�{�݂Ŏ����Ŏ��Ƃ��v�i���������Ғ��@���Ώ��X2300�~�j
�{���́u�Ŏ��̋��ȏ��v�ł��B
���Ƃ̂��߂̋��ȏ��ł���Ɠ����ɁA���ׂĂ̐l�����ɓǂ�łق����A�����߂̂P���ł��B
��������́A�����Ȃ������������Ƃ��A���̉ߒ����܂߂āA�悭�m���Ă��܂��B
�Q�N�قǑO�ł��傤���A��������u�����Ŏ�邽�߂̃e�L�X�g�v��n�肽���̂����A���͂��Ă���Ȃ����Ƃ����܂����B
���ɂ́u�����Ŏ��v�Ƃ������o���S���Ȃ������̂ŁA���f�肵���̂ł����A
��������́u�Ŏ��v�ւ̎v�������Ă��炢�A��������̈Ӑ}�����������ł��܂����B
��������̍l����u�����Ŏ��v�Ƃ́A
�s�t�I�Ɏ��Ɍ������l���A�����Ȃ�����S���ł���悤�ɁA��������Ƃ��̐��Ɋ��Y�������Ȃ̂ł��B
������A�{���̕���́u���̂��Ǝ��Ɍ��������x���v�ƂȂ��Ă��܂��B
���ɂ́A�ނ���u�����Ŏ��v�Ƃ����\���̂ق����҂����肵�܂����A
����͂Ƃ������A�e�L�X�g����肽���Ƃ�����������̎v���ɂ͋����ł��܂��B
����ł��ƂĂ������ŏ����C�ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ŁA��ނ̌`�ōޗ�������Ă��炤�����ŋ����Ă��炢�܂����B
���̏�������̎v���̂��������{���������܂������A�����ɂ͓ǂ݂����܂���ł����B
�����W�҂̋��ȏ����Ƃ����v��������������ł�����܂����A
����ȏ�ɁA���ɂ͂�����ƋC�̏d���e�[�}����������ł��B
�������A�ӂ������ēǂݏo������A�ƂĂ��f���ɓǂݐi�߂�̂ł��B
�����āA�݂�Ȃɓǂ�ł��炢�����Ƒf���Ɏv���܂����B
��������́A��������̐��Ƃł����A�ώ@�ғI�ɂł͂Ȃ��A
�����g�̐����ɏd�˂Ȃ��炵������Ǝ��H�I�Ɏ��g�܂�Ă�����ł��B
�{���̎��M���A��������̌l�I�ȑ̌����N�_�ɂ���܂��B
������M���ł��܂��B
�̌��Ɋ�Â��Ȃ������_�⋳��_�́A���ɂ͑ދ��ł��B
��������͂��������Ă��܂��B
�@�Ŏ��͈�Â̐ꔄ�����ł͂Ȃ��A
�@�����̌���Ɍg���x���҂���������ɓ���čl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��e�[�}�ƂȂ��Ă����B
�����̌���Ɍg���x���҂ɂ́A�Ƒ���F�l���܂܂��ł��傤�B
���ꂪ�{����ǂ�ŁA���̈�Ԃ̋C�Â��ł����B
���������Ƒ����ǂ�ł����悩�����Ǝv���܂����B
��������̈Ӑ}���A�ǂ�ł݂Ă͂��߂Ă킩�����̂ł��B
�{���ł́A�����̂��܂��܂Ȍ���ł̎��H��Ƒ��̎�L�╨���y��ɂ��āA
�T�̎��_����u���̂��Ǝ��Ɍ��������x���v������Ă��܂��B
�T�̎��_�͎��̒ʂ�ł��B
�@�@���_1�@�l�͎����ǂ��Ō}���Ă���̂�
�@�@���_2�@�Ŏ��̂͂��ꂩ
�@�@���_3�@�{�݂Ō}���鎀
�@�@���_4�@������Ӗ����玀���l����
�@�@���_5�@�I�����Ɏx���҂͉����ł���̂�
���ꂼ��Ɏ����̌��k�Ȃǂ��p�ӂ���Ă���̂ŁA�ƂĂ��킩��₷���A�����I�ł��B
�{���łƂĂ������������Ƃ�������Љ�܂��B
��������́A�����̘V���̔ے肷�镗���Ɍ��O��\���܂��B
������X�����v���Ă����l�ł����A
�u�����ݏo���A�Љ�ɑ��čv���ł��邱�Ƃɉ��l��u���Љ�S�̂̉��l�ς�]�����Ȃ�����A
�V���邱�ƂŎЉ�����������A�Ƒ������ʼn���������݁A�Ǘ������鍂��҂́A������̂ł͂Ȃ����v
�Ƃ�����������̈ӌ��ɓ����ł��B
����Җ��͔��z�����{����ς��Ȃ�������܂���B
��������͂܂��A
�u���ɑ���̌������Ȃ��A�����B���ꂽ�Љ�ł́A���ɂ��čl���A��������@��Ȃ����Ƃւ̊뜜�v
���\�����Ă��܂��B
�܂����낢��ƏЉ�������Ƃ͂���̂ł����A���肪����܂���B
���Ж{�������ǂ݂��������B
��������͍Ō�ɂ��������Ă��܂��B
���Ǝ��Ɋւ��邱�Ƃ́A�ȒP�ɔ[���̂��������������o���܂���B
����������̂����肩�ł͂Ȃ��A�{�����A�܂��r��ł��B
�������A�����o�����A�₢�����A�n�������邱�ƂŎv�l�͐[�܂�A�V���Ȓn���������Ă��܂��B
�ǂ����A���߂Ŏ��ƌ��������A�l����_�@�ƂȂ�Ȃ�A�{����҂҂Ƃ��āA����ɏ����т͂���܂���B
����́A���Ԃ҂Ƃ��Ă̏�������̉ۑ�ł�����ł��傤�B
��������������Q�X�g�ɁA���̖���b�������ꂪ�ł���Ǝv���Ă��܂��B
�R�����Y���X����w��
���u���ꂩ��̋���Đ��v�i�܌����j�@�������폑�X
2400�~�j
�T�ԕɏ������܌������̒���ł��B
�{�̑тɖ{���̓��e�Ɋւ���Ȍ��ȏЉ������Ă��܂��B
�u��@�I�ȏɂ��鋳��̏�ŁA�����q�����ƂƂ��ɁA����܂��^���̒T���𑱂��Ă����x�e�������ꋳ�t�̎��H�L�^�Ɩ����ւ̒v�B
�|�l�Ȃ��ɁA���̒ʂ�̖{�ł��B
�����e���~���肷���Ă��āA�Q���ɕ������ق��������悤�ɂ������܂������A�ǂݏI����Ă݂�ƁA����炪�g�ݍ��킳���Ă��邱�Ƃ������A�{���̓������Ǝv�������܂����B
�܂�u�T�ϓI�Ȏ��_�����܂������猻��̎��ԁv�Ɓu�����ł̎��H�̑̌��Ƃ��̋�̓I�ȋ��ށv���A�������������ɑg�ݍ��܂�Ă���̂ł����A����炪��ɋ��U���āA���҂̃��b�Z�[�W���ƂĂ����������ƐS�ɋ����Ă���̂ł��B
�P�Ȃ鎖������ł��A���H�ł��Ȃ��A���Ɏ��炪���k�ɂȂ����悤�ȋC���ɂ����Ȃ��Ă��܂��s�v�c�Ȗ{�ł��B
����W�҂̋���Đ��_�ւ̕s�M�������������A�{������C�ɓǂ�ł��܂����̂́A�u�͂��߂Ɂv�̒��̎��̕��͂ɏo���������ł��B
�u�����́A�Ȃɂ����ڂ̑O�ɂ��鐶�k�ɂ����w�ԁB���k�d���A���k�̗����ȁA���邢�͍T���߂Ȕ������݂āA�����̋�����m���Ȃ��̂ɂ��Ă������Ƃ������̂��B�v
����ɐ܌�����͂��������܂��B
�u��X�����k�ɕK�v�Ȓm����A���̂̌����A�l��������A��������Ƃɍl���A���f������ۏႵ��������A���k�����͎����Ő^����Nj����A������n���Ă������Ƃ���B���̂悤�Ȑ��k������ڂ̑O�ɂ���ƁA��҂ւ̐M���ƁA�~���ƁA��]���o����̂ł���B�v
�u��҂ւ̐M���ƁA�~���ƁA��]�v�B
���̐l�͐��k��M�����A���k�������Ă���B����͓ǂ܂Ȃ�������Ȃ��Ɗ������̂ł��B
�킪���̊w�Z����̌���Ɋւ��ẮA�����{�ŏ����͓ǂ�ł��܂����A���������̒��Ō���̋��t����̓I�ɂǂ����k�Ɛڂ��Ă���̂��́A�Ȃ��Ȃ������ł��܂���ł����B
�����⌳�����̖{���ǂ��Ƃ͂���܂����A�����͑�ςȂ̂��Ƃ킩���Ă��A����������Ƃ҂�Ɨ��܂���ł����B
�������A�{���͈Ⴂ�܂����B
�܌�����́A���l���I�Ɂu��ς��v�ȂǂƂ͌���Ȃ��ŁA�ނ��닳���邱�Ƃ̊y�������A��̓I�ɓ`���Ă��Ă����̂ł��B
����Đ��Ƃ́A�w�Ԃ��Ƃ��y�������邱�Ƃ���n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă��鎄�ɂ́A�����{�@�́u�����v�ŁA�����w�Z�͍Đ����悤���Ȃ����낤�Ǝv���Ă��܂����A����������ƁA�܂����߂邱�Ƃ͂Ȃ��̂�������܂���B
�܌�����́A���͖ʔ����Ċy�������̂��A�l���Ă��܂��B
�ƂĂ������ł��܂����A���������܌������M���ł��܂��B
�w�Ԃ��Ƃ��y�����Ȃ��͂�������܂���B
�y��������̂ł͂Ȃ��A�y���܂Ȃ�������Ȃ��B�����v���܂��B
���̌��_��厖�ɂ��Ȃ���A���������w�т̏�ȂǑ����ł��܂���B
�������Ȃ����w�Z�̕����y�����Ǝv���Ă���l�͏��Ȃ��悤�ł��B
�܌�������A�c�O�Ȃ���u�����͕��͋ꂵ�����̂ɂȂ��Ă��܂��Ă���v�Ə����Ă��܂��B
�������A�܌�����͂��̂Ȃ��ł��i�ꂵ�݂Ȃ���A��������܂��j�y�������Ƃ��Ă���̂��`����Ă��܂��B
���́A�w�Ԃ��Ƃ��������Ƃ��y�����ƁA�����v���Ă��܂��B
�y�����Ƃ������Ƃ́u�y������v���Ƃł͂���܂���B
�y����42�L���ł����ƁA�V�h�j�[�I�����s�b�N�̃}���\���ŗD�������������q����͌����܂����B
�������Ƃ��u�J���v�Ƃ����l�����Ȃ��o�c�҂���Ђ����߂ɂ����悤�ɁA�w�Ԃ��Ƃ��y�����Ǝv��Ȃ������͊w�Z�������ł��傤�B
�����������邱�Ƃ��u�y�����Ȃ��J���v�ɂ��Ă��܂����̂́A�N�Ȃ̂��B
���ȏȂ̖�l�⋳��ψ���̈ψ������ł͂Ȃ��ł��傤�B
�w�Z���Đ����A������Đ�����̂́A��l�ł͂Ȃ��A���k������������܂���B
�w�т̎�̂��A����ɂȂ�͓̂��R�ł��B
�����Ƃ��A�܌����`���ɏ����Ă���悤�ɁA���������k����w�Ԃ̂ł���A�������w�т̎���ł��B
�{���̍Ō�ŁA�܌�����́A����Đ��V�i���I�Ƃ���13���ڂ������Ă��܂��B
�ƂĂ������ł��܂����A�v��A�u�w�Z���A�l���Ǘ��������������ł͂Ȃ��A�l��M�������݂��������������y�����w�т̏�ɂ���v�Ƃ������Ƃł��傤���B
�܂����������ł��B�����Ȃ�A�q�ǂ������̕\����߂��Ă���B
�����߂����E���A�������ڂ����A�s�o�Z���A�Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
�����̂����ߑ�Ȃǂ́A�ނ��낢���߂���������悤�ȋC�����܂��B
�{���̊��ɗ���Ă���̂́u���a�v�ł��B
�����������҂��{�����������������ɂȂ����̂́A���a�Ɋւ���Q�̘_�������������Ƃł��B
�����A���̘_�����G���œǂ�ł��܂������A�ƂĂ������͂̂���u���a�_�v�ł����B
���̐���ς����邽�߂�������܂��A�{���͋ɂ߂Ď��H�I�ȕ��a�̏����Ɗ����܂����B
����͕��a�ɐ[���Ȃ����Ă��܂��B
�{���I�ȕ��a�^���́A�����܂ł��Ȃ��A����ł��B
�o�ςɂȂ��鋳��ł͂Ȃ��A���a��ڎw��������A�������͂�����x�ł��邩�ǂ����B
���܂܂��ɁA�������́u�傫�Ȋ�H�v�ɂ��܂��B
�����ɂ͂���₷��������v�⋳��Đ��̗����ς��Ȃ��Ƃ����܂���B
���̂��߂ɂ��A��l�������̐l�ɁA�{����ǂ�łق����Ǝv���܂��B
�R�����Y���X����w��
���u����S���O�Ȉ�̍ٔ��[��Ñi�ׂ̋��P�v�i���^�Y�@���{�]�_�Ё@1700�~�j
�ٌ�m�̑��^�Y�����3���ڂ̖{�ł��B
�P���ڂ��u�L���Y�Ɣp�����s�@���������v�͊����B
�Q���ڂ́A�܂��ɖ{�Ƃ��u�i�@���v�v�B
�����č���͈�Ñi�ׂ̖��ł��B
��ނ͕���11�N�ɋN�������ߋE��w�t���a�@�ł̐S����p�ɂ�鎀�S�����ł��B
���a�@�̐S���O�ȕ������������G�������������������҂��A�p��A���S�����̂ł����A�⑰���牜�������i����ꂽ�����ł��B
������}�X�R�~�͐^�����m���߂邱�ƂȂ��A�傫�����グ�܂����B
���Ɂu�A�T�q�|�\�v�́A�����L�����y�[���u�w��ҁx�ɎE�����v�V���[�Y��g�݁A�u���X������ɂ����S���O�ȋ������Ȃ��f�߁I�v�ȂǂƏ������Ă܂����B
�V�����A�قړ����悤�ɉ������̈�Éߌ�Ɗ��Җ����̕����Ă����悤�Ɏv���܂��B
�����A���̋L����ǂ����A������������̂��o���Ă��܂��B
�������{����ǂ�ŁA�Ǝ����Ƃ͑S������Ă������Ƃ�m��܂����B
�������Ɉ�Éߌ�͂���A���̂��ߋߋE��w�t���a�@�͈Ԏӗ����x�����܂������A�퍐�ƂȂ����������Ɋւ��錙�^�͍ٔ��łقڐ��ꂽ�̂ł��B
�⑰���A�����������Ƃ��킩���āA�������ւ̍T�i����艺���Ă��܂��B
�������A�������͒P�ɑi�����Ă����ł͂Ȃ��A�����m�ɂ��邽�߂ɁA�������̑i�ׂ�������N�����܂����B
�}�X�R�~�A�����ƂȂ����厡��A�⑰�㗝�l�ٌ�m�����i�����̂ł��B
�ق��ɂ���������ǂ����Ƃ����Ƃ��铯�ƈ�t�Ƃ̓���������܂����B
�����ɑ��āA���ׂĐ��ʂ��瓬�����̂ł��B
���̂������ŁA���߂Ĉ�Ñi�ׂ��Â̎��Ԃ������Ă��܂��B
�{���͂��̋L�^�ł��B
�ٔ��ɂ͏��������̂́A�������Ƃ��̉Ƒ��̐����͖��c�ɂ��ł���܂����B
�S���O�Ȉ�Ƃ��ĕ]���̍��������������̈�Ís�ׂ��A���̌�͍s���邱�Ƃ͂���܂���ł����B�Љ�I�ɂ��傫�ȑ����ƌ����ׂ��ł��傤�B
�ٔ����I�������ɁA�������́w���\�̗��x�Ƃ������Ɩ{���o�ł��Ă��܂����A�����Ŕނ��`�����������̂́A�u����g�D�̌��͂̑O�ł́A��l���@���ɐƎ�ȑ��݂ł��邩�v�Ƃ������Ƃ������悤�ł��B
��삳��́A�{���̔w��ɎR��L�q�̖����w���������x�̂��Ƃ��w�i�̂��������Ƃ��������킹��A�Ə����Ă��܂��B
���́A��삳��͉������Ƌ����������ł��B
���̂������A��O�҂̎�����݂�Δ퍐�ւ̎v����������������܂��B
�������A��삳��͔퍐�̖��_�҉�̂��߂ɖ{�����������킯�ł͂���܂���B
�u���̓����́A���ɒm�点�鉿�l�̂�����̂��Ƃ����m�M�v���A��삳��ɖ{���������������R�ł��B
���̂��Ƃɂ͎����������܂��B
�{���̍Ō�ɁA��삳��́u���̎����̋��P�v�Ƃ��āA��t�A�}�X�R�~�A�a�@�A�ٌ�m�ƍ��ڂ��āA���P���܂Ƃ߂Ă��܂��B
�����ɂ́A���ꂩ��̈�Â��Ñi�ׂ��l���邽�߂̂��܂��܂Ȏ�����������Ă��܂��B
��Ñi�ׂ́A��Â̐��E�̌�����ے����Ă��܂��B
��Ñi�ׂ̎��_����A��É��v���l���Ă����A���Ԃ܂Ƃ͈������É��v�������ł���͂��ł��B
���̂��Ƃ͈�ÂɌ���܂���B
��삳�O���Ŏ��グ���u�i�@���v�v�ɂ������邱�Ƃł��B
�i�@���v���܂��A�u�l�߁v��u�i�@�s�M�v��u�i�@�i�ׁv�i����Ȍ��t�͂Ȃ��ł��傤���j�̎��_����l����K�v������ł��傤�B
�{���́A�u���v�v�Ƃ������̂Ɏ��g�ގ�����^���Ă���܂��B
�{����ǂ�Ŋ��������Ƃ͂��������܂��B
��삳��́A���Ƃ����Łw���́A�����āu��l�Ƃ��ĐƎ�v�ł͂Ȃ������B���܂��܂ȋꋫ�����z���A�����ȓ����������x�Ə����Ă��܂��B
�u����g�D�̌��͂̑O�ł͈�l�͐Ǝ�ȑ��݁v���Ƃ��Ă��A���͂ł͂Ȃ��B�������Ƃ��ł���̂��Ƃ������Ƃ��A�������͎��H�������Ď����Ă���Ă��܂��B
�����A��ԍl��������ꂽ�̂͂��̂��Ƃł��B
�ƂĂ��l����������{�ł��B
�ł���Έ�x�A�{����ǂl�����ŁA��Ñi�ׂɂ��Ă̘b�������̏�����������Ǝv���Ă��܂��B
�R�����Y���X����w��
���u�����Љ��L���Љ�ցv�i���^��ق��@���j�Ё@800�~�j
���������Q�����Ă�����k��̋L�^���x�[�X�ɁA�����҂����M���ĕҏW���ꂽ�{�ł��B
�e�[�}�́u�����Љ��L���Љ�ցv�B
�{���̃J�o�[�ɂ͂��������Ă���܂��B
�@ ���N�R���l�ȏオ�g�ǓƎ��h���邱�̍����A��k�Ђ��P�����B
�@ �U�l�̘_�q���g�L���̖����h��͍�����B
�U�l�̘_�q�Ƃ́A���^�炳����͂��߂Ƃ��āA�z�[�����X�x���Ɏ��g�މ��c�m�u����A�N�w�҂ɂ��ď@���w�҂̊��c����A�@���j��X�s���`���A���e�B�̕���ɑ��w�̐[�������i����A�Ƒ��_�Ŋ��Ă���R�c���O����A�C�[�E�[�}����\�̍��X�����肳��ł��B
�u�����Љ�v�ƌ������t�������Ă̋c�_���ʔ����ł����A������ԋ������������̂́A�������̎��̔����ł��B
�ݏ���̑��݂́A���̓��{�Љ�ɂƂ��đ傫�ȈӋ`������܂����B���Ɍݏ�����������̂́A�l�X����������߂��Ƃ�������I�E�Љ�I�w�i������܂����B�����ݏ���������Ă��Ȃ���A����������Ɉ�w�u������n���̊��v�͐[���������̂�������܂���B
�������A���̈���ŁA�������͂����������Ă��܂��B
�����炭�A�ݏ���͕֗��������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������ɂ���A���V�ɂ���A�̂͂ƂĂ���ςȎ��Ƃ������B�e���⒬���̐l���݂�Ȃ��������ɏW�܂�悤�ȁA��厖�̃C�x���g�������B���ꂪ�A�ݏ���ɂ��������Ă����A�����������Ō�͉������Ȃ��Ă�OK�A�����������V����������Ƃ������o�ݏo���Ă��܂����B���̂��Ƃ��A���ʂƂ��āA������n���̊����������\���͂���Ǝv���܂��B
�������́A�S���{�������Ռݏ�����̗����ł��B
�����Ė{���́A���̑S���{�������Ռݏ������Â̌��J���k��̋L�^�Ȃ̂ł��B
�����������Ƃ܂��čl����ƁA�u�����Љ�v�ƌ�����悤�ȏݏo�����ӔC�̈�����ݏ���ɂ���A�Ƃ����������̔����͎��Ɏh���I�ł��B
�������A�����炱���A�������Ռݏ���͐V�����Љ�I�����Ǝg����^���ɍl���Ȃ�������Ȃ��ƌ����Ă���킯�ł��B
�������́A���������V�������g�݂��n�߂Ă��܂��̂ŁA���̔����ɂ͐����͂�����܂��B
���̔��������u�ƊE�v�݂̂Ȃ��������Ă����Ƃ����̂ł����B
���̋C�ɂȂ�A�傫�ȕ����N������ł��傤�B
�������c�O�Ȃ���A���͂Ȃ��Ȃ��N�����Ă��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
����A��N�̒Ôg�ł��ׂĂ̏Z�����������������ꂽ���n�̂͂炪�܍`�ɍs���܂����B
�Z��̓y�䂵���Ȃ��W���̈�p�ɁA���ꂢ�ɏC�����ꂽ������n������܂����B
�Z�މƂ����A�܂��͂�����C�������Ƃ����A���t�̂��b���Ċ������܂����B
�쑊�n�̏����n��ɂ����܂����B�܂����ː������ŏZ�����߂�Ȃ��̂��߂��A�W���̈��ɂ������M�D�_�Ђ��r�ꂽ�܂܂ł����B
����A����������Ă��āA���ꂪ��Ԉ�ۂɎc�������Ƃł����B
�������́A�u�������Ղ��s����Ƃ��A�u�v�Ƃ������ۓI�T�O�����̉�����A���������v�ƍl���Ă��܂��B�����āA���ꂩ��̌ݏ���̖����́A����������悤�ɂ��A�ǂ����Â���̂���`�������邱�Ƃ��ƍŌ�ɘb���Ă��܂��B
�����A�������Ղ̈Ӗ��₠������A���߂Ė₤�ׂ�����ɂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
������Ɠ���Ȗ{�̂悤�Ɏv���邩������܂��A���������l�����ł̎�������R�܂܂�Ă��܂��B
���u�����E����Ȃ��v�Ŏd���͌��߂Ȃ����i���J�^��@�Z�p�]�_�Ё@1580�~�j���J���{�������M�������@�́A�Ⴂ����̐l�����ɁA�u�K���ȏA�E�v�����Ăق����Ƃ��������v�����炾�����ł��B
���d�����A�����łȂ�����ɐG��邱�Ƃ������̂ł��傤�B
���J����́A�u�L����w�𑲋Ƃ��A�L����ƂɏA�E���邱�Ƃ��u�K���v�ɂȂ���Ȃ���𐔑������Ă��܂����v�Ə����Ă��܂��B
�������ɁA�u���O�v�Ƃ�����悤�ɁA���������A�E������Ђ𑁁X�Ǝ��߂Ă��܂���҂������̂������ł��B
���Ȃ݂ɁA�u���O�v�Ƃ́A���w�A���Z�A��w�̑��ƌ�A�R�N�ȓ��ɗ��E���銄�����A���ꂼ���V���A�T���A�R���ƂȂ��Ă��錻�����w���Ă��܂��B
����́A�{�l�ɂƂ��Ă͂������ł����A��ƂɂƂ��Ă��A�Љ�ɂƂ��Ă��傫�ȕs�K�ł��B
�Ȃ��A�Y�ƊE�⋳��E�������������A���N���u���Ă���̂��A�ƂĂ��s�v�c�ł��B
�����ȑO�A��x�A���������e�[�}�̃t�H�[�����Ɋւ�������Ƃ�����܂����A���Ԃ͕ς���Ă��܂���B
�N���������o���Ȃ�������܂���B
�{�����A�������������ւ̈�ɂȂ�Ɗ��҂������ł��B
���J���l����u�K���ȏA�E�v�Ƃ́A�u�����̂�肽���d���ɏA���āA���̎d���Ŋ��邱�Ɓv�ł��B
���́A�u�d���v�Ƃ́u�����邱�Ɓv�̓��`�ꂾ�Ǝv���Ă��܂��̂ŁA���̍l���ɋ������܂��B
�d���Ƃ͉�Ђɓ��邱�Ƃł��A���������炤���Ƃł��Ȃ��A�����̂�肽�����ƂɌp���I�Ɏ��g�߂邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
����́u�����邱�Ɓv���̂��̂ƌ����Ă�������������܂���B
�������A�����͌����Ă��A�u�����̂�肽���d���v���킩��Ȃ��Ƃ����l�����Ȃ��Ȃ��ł��傤�B
���������l�̂��߂ɂ��A�{���͂ƂĂ��L�v�ł��B
�㔼�́u�K�E�}�b�v�v�ŁA�����Ǝ����̂�肽���d���̃q���g��������ł��傤�B
�{���͂Q���\���ɂȂ��Ă��܂��B
�O���́u�����d���v��I�Ԃ��Ƃ̑���Ƃ��̑I�ѕ����A�ƂĂ��킩��₷���A�������Ă���Ă��܂��B
���̉ߒ��ŁA��ЂƂ͉������A�w���ɂ��悭�킩��悤�ɉ������Ă��܂��B
�㔼�́A���ۂɂǂ������d��������̂��A�����Ă��̎d���ɂ͂ǂ������\�́E�����≿�l�ς����߂��Ă���̂����킩��u�K�E�}�b�v�v�ł��B�S���ŁA�U����V�W�E�킪�A���ꂼ��̎d���̌ڋq��r�W�l�X���f���������ł���悤�ɊȌ��ɐ�������Ă��܂��B
�V�����A���K�C�h�Ƃ��āA�{�������N�A�X�V����Ă������Ƃ����҂��܂��B
�����āA�{�������������A���܂��܂Ȏd�g�݂���Ă����ȂƎv���܂��B
�����ɁA�����̕s�K�ȁu��ЂƊw���̃~�X�}�b�`�v��ς��Ă����u��v�����҂������̂ł��B
���J����ɂ́A���ЂƂ��{�������������V�����d�g�݂Â���ɂ����g��łق����Ǝv���܂��B
���J����́A�{���̒��ŏ����Ă��܂��B
�u��҂͉��ł��ł���v�u�l�ɂ͖����̉\��������v�Ƃ������t�͂ƂĂ��O�����ŁA�����Ă��Ď���肪�ǂ��A�N�����_���܂���B�������A�����Č����܂��B�l���͗L���ł���A�l�ɂ͍����d���ƍ���Ȃ��d��������܂��B
���̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
���Б����̎�҂ɁA�����ɍ������d���������Ă��炢�����Ǝv���܂��B
�����āA�����������k�ɏ�邽�߂ɂ��A�����̐l�ɖ{����ǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B
�R�����Y���X����w��
���u������߂āv�i���^��@�O�܊ف@1575�~�j
���^�炳��́A�E�q�ƃh���b�J�[�ɋ������A���̒m�������Ђ̌o�c�ŁA�܂�����̐������Ŋ������Ă���A
�܂��ɒm�s��������H����Ă�����ł��B
���̈������Q��E�q�����܂���܂���܂����B
��܂̗��R�͂��낢�날��ł��傤���A���́A�������̓��퐶�������̍ő�̗��R�ł͂Ȃ����ƁA����ɐ������Ă��܂��B
���ꂵ�����Ƃł��B
��܂̋L�O�ł͂Ȃ��ł��傤���A���������������̓���I�Ȑ�������l�����A����I�Ƀj���[�X�T�C�g�́u���������v�̃R�����Ɋ�e���Ă������̂��A���M����Ė{�ɂȂ�܂����A
���ꂪ���̖{�ł��B
�������̏��Ђ͂���܂ł���������Љ�Ă��܂������A���̖{�͈������̐l���������ʂ��āA�����������Ђ���̃��b�Z�[�W�����H�I�Ɋ��������Ă���܂��B
36���ڂɂ킽��A�u�_��v�Ɍ���Ă���u��v����{�ɂ����āA���܂��܂ȓ���I�ȃe�[�}���N�₩�Ɍ���Ă��܂��B
��������ƂĂ��ǂ݂₷���A�S�ɋ����܂��B
���Ƃ��A����ȃe�[�}�ł��B
�@�Ԃ͓V���̂��́\���V�����`�q�s
�@�����͕K�v�I�\���V�͐l�ނ̑��݊��
�@���Ɛl�ԊW�\�����͐l�Ԃ��ɂ��Ă����
�@�A�����̒��Ő����Ă���\��c��q���ւ́u�܂Ȃ����v
�@�ǓƎ��\��Օ��c�n�E�ǓƎ��[����ڎw����
�@���E�̂Ȃ��Љ�\�x�������A���S���ĕ�点��Љ��
�@�אl�Ղ�\�u�ǓƎ��v���Ȃ������߂̕��@�̈�Ƃ���
��������������̐����̕��͋C���`����Ă��āA�e���݂����Ă܂��B
�����ŋ߁A�E�q�ɋ����������邱�Ƃ������̂ł����A�������̐V�����������_�ɂ������������邱�Ƃ������ł��B
�����̊�{�́A�������Ղɖ��ߍ��܂�Ă��܂�����A�������猩���Ă��邱�Ƃ͑����ł��B
�R�[�q�[�ȂLj��݂Ȃ���A�C�y�ɓǂނ��Ƃ����E�߂��܂��B
�u������߂āv
���u�k���Љ�ւ̓��v�i���v���Ғ��@�����H�ƐV���Ё@1600�~�j
�T�ԕł������܂������A�F�l�̍������m������Q�����Ă���k���Љ����̃����o�[���{���o�ł��܂����B
�k���Љ����́A2008�N�ɃX�^�[�g����������ł��B
�o�ϐ����ւ̎������̂ĂȂ�����A�Љ�̔j�ł͖Ƃ�Ȃ��B
�����{�C�Ŏ����\����ڎw���̂ł���A�k���Љ��ڎw���ׂ����Ƃ������z�Ŏn�܂���������ł��B
���m����́A�ȑO���炨�b�����������Ă��܂������A�����ł̋c�_�̈ꕔ���{�ɂȂ�܂����B
�{���ł́A���̏k���Љ�̗��O�Ǝ����̂��߂̓�������Ă��܂��B
�{���̔F���͎��̒ʂ薾���ł��B
���̎����\�������邽�߂ɂ͎Љ�̏k�������Ȃ��B
�k���Ƃ́u�l�Ԃ����p���镨������уG�l���M�[�Ǝ��R���ɔr�o����p�����̗ʂ����R���̎����\�������Ȃ��Ȃ��͈͂ɗ}����v���Ƃł���B
�����������_����l����ƁA�����̓��{�̐l�������X���́A�܂��ɎЉ�̘g�g�݂�ς����D�̃`�����X�Ȃ̂ł��B
�����ɁA�������̎����Q��^�̐��������������Ȃ�������܂��A������܂��A�����̌������̈ȗ��̎Љ�̕����́A���������ӎ������߂Ă���悤�Ɏv���܂��B
�����������Ȍo�ϐ����_�͔ے肳��Ȃ�������܂���B
�����{��k�Ђʼn������������A�w�Z�̑̈�قŔ��������Ă����l�������e���r�ǂ̎�ނɓ����āA�u���Ȃ��Ă����������Α���邪�A�����Ă���荇���Α���Ȃ��v�ƌ���Ă����b���{���ŏЉ��Ă��܂����A�����������ƂɎ������͂悤�₭�C�Â������Ă��Ă���̂ł��B
�{���̗ǂ��͒P�Ȃ闝�O�̏��ł͂Ȃ����Ƃł��B
���Ƃ��A���m����́A�u�k���Љ�̋Z�p�v�Ƃ����^�C�g���ŁA�k���Љ�Ɍ����Ă̋Z�p�̂�������Ă��Ă��܂��B
�����\����ڎw���̂ł���A�P�Ȃ邨��ڂł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ���̎�����Ŏ��ۂɓ����o���˂����܂���B
���邢�͓����o���A�������������ɕς���Ă����ɂ���̂ł��B
�u�k���v�Ƃ������t�Ƀ}�C�i�X�C���[�W�����l�����邩������܂��A�ߏ�ɂȂ肷�����c���Љ��K�x�Ȃ��̂ɖ߂��ƍl���Ă������ł��傤�B
�{���ɂ͎������̐�������₢�����q���g�����낢��Ɗ܂܂�Ă��܂��B
�Ȃ��A�{���̕Ҏ҂ł�����k���Љ�����\�����v���V���V���̌�����ōu������܂��B
���m�点�Ɉē����f�ڂ��Ă��܂��̂ŁA���S�̂�����͂��Q�����������B
�����Q������\��ł��B
�R�����Y���X����w��
���u�������������v���猾���邱���i�㓡���u�@�N�������n�E�X�@500�~�j
��������q�̓v�����g�v�Z�p�҂Ƃ��āu���q�̓����v�̈�l�������A�㓡���u����̍u���̋L�^�����Ƃɂ����u�b�N���b�g�ł��B
�u�����x�[�X�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
���͊�{�I�ɁA���q�̓����̐l�����⌴�q�͊W�̊w�҂̘b�͐M���Ă��܂��A
3.11�Ȍ�A����������Ȃ��čs�����N�������l�̘b�ɂ͎����X����悤�ɂ��Ă��܂��B
�u�������܂���v�Ƃ����v���͐@���܂��A��l�̎������Ō���Ă���l�̌��t�ɂ͐^���������܂��B
�㓡����́A3.11�Ȍ�A�����������[�`���[�u�Ȃǂŏ�M���Ă����l�ł��B
�������[�`���[�u�ł́A��������b�����Ă��炢�܂����B
�܂��A�㓡����́A�X�g���X�e�X�g�����̈ψ��̈�l�ł�����܂��B
�O�ɂ��̃u���O�ł��������悤�ȋL��������܂����A���ԂƂ�������ψ���̗���ɓ{��̍����������ψ��̂���l�ł��B
�㓡����́A��N���ɁA�m�o�n�@�l�`�o�`�r�s�𗧂��グ�āA
�������܂ތ���Ȋw�Z�p�̂�����ƁA�K���ȃG�l���M�[����Љ�����Ɍ����Ă̒���������[�����ƂɎ��g�݂����Ă��܂��B
���̌㓡����N8���ɍu���������̂��{���̊�{�ɂȂ��Ă��܂��B
���ܓǂ�ł������ɕx�ޓ��e�ł��B
���͍ŋ߁i2012�N5��12���j�A�㓡����̍u���ڂ��������܂������A��|�͂܂������ς���Ă��܂���B
�㓡����̐M�O�������܂��B
�㓡����͌��q�F�i�[�e��̐v�̐��Ƃł����B
���̂����ꂩ��A�{���ł͌����̖{����������Ă���Ă��܂��B
�����Č��_�́A�u�����̈��S���͊m�ۂł����A���}�ɒE��������K�v������v�Ƃ����܂��B
�����������̂Ɋւ��Ă��A�܂����肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��A�s���͑傫���Ə����Ă��܂��B
�����������Ƃ��A�ƂĂ��킩��₷���A��̓I�ɏ�����Ă��܂��B
60�y�[�W�قǂ̃u�b�N���b�g�ł��̂ŁA�C�y�ɓǂ߂܂��B
���Ђ��ǂ݂��������B
�q�ǂ��̍��A���͌����ɂȂ肽���āA��w�͖@�w����I�т܂����B
�������u���`�̎d���v���Ǝv���Ă����킯�ł͂���܂���B
�ނ���t�ŁA���ƌ��͂̑���ɂȂ��Ă��錟���̐��E�𐳂����������̂ł��B
���̂��������́A�u���C�����v�Ƃ����f��ł��B
���̉f��͎��b�Ɋ�Â����̂ł����A�l�߂����������f��ł����B
���w����ɂ�����ς����ɁA�S�g���k���܂����B�S��A���͂ւ̓{��������܂����B
���ꂪ���́A���̌�̐l�������߂��̂�������܂���B
�������A�c�O�Ȃ��猟���ɂ͂Ȃ�܂���ł����B
�����āA���̌����������̍ٔ��̕s�𗝂��݂Ă��܂����B
�ٌ�m�̕v�Ƃ̗����ٔ����N�������m�l�͂Ђǂ����������悤�ł����A�ŋ߂��l�߂łЂǂ����������Ƃ����l���炨�b�����������܂����B
�i�@�E�ɂ͗F�l�m�l�������̂ł����A�l�̖��Ƃ��������A���x�Ƃ��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�������A���������u�������Ȏd�g�݂̐��E�v�Œ��N����ƁA�l�܂ł����������Ȃ��Ă����܂��B
�����Ȑl�����܂����A�����łȂ��l�����Ȃ�����܂���B
�p����́A���ƈႢ�A�ٔ��ɐ��`�����҂��Ă����̂ł��傤�B
�i�@�E�̐l�����ɂ��A�����҂Ƃ��Ă̏펯������Ǝv���Ă����̂ł��傤�B
���������ƈႤ�Ƃ���ł��B
�p����́A���������Ă��܂��B
���ۂɍٔ�������Ă݂āA�����܂����B
�ٔ��̌����́A�@�����ɏ�����Ă��邱�ƁE�@�w�҂̎v�l�Ƃ́A�܂������Ⴂ�܂��B
�@���͕����Ă��A�@�̐��_�ȂǕ��������Ƃ̂Ȃ��i�@�W�҂͑����悤�Ɏv���܂��B
�p������{���ŏ����Ă���A�u�@�Ƃ������̂��s���̏펯�̊�b�̂����ɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��������𗝉����Ă���i�@�W�҂͌����đ����͂Ȃ��悤�ł����A���[�K���}�C���h�Ȃǎ������킹�Ă��Ȃ��i�@�W�҂��قƂ�ǂ�������܂���B
�g�����ۏ���Ă����ɁA���ԓ��̑��ݔ�]�⑊�݊w�т����̕����͑S���ƌ����Ă����قǂ���܂���B
���Ԃ��������Ȃ��Ƃ����Ă��Ă��A�ᔻ����悤�Ȃ��Ƃ͐悸����܂���B
�ᔻ�̂Ȃ����E�͌��S�ł���͂�������܂���B
�p����͂����������Ă��܂��B
��X�́A�u�ٔ��M�̐_�b�v���̂āA�ٔ����Љ�o�������Ȃ��u�ٔ����Ƃ������̂�t����ꂽ���ƌ������E�����̍s���Ă���P�Ȃ�s�ׁv�Ƃ����ϓ_�Ɋ�Â��A�q�ώ�����K�v�����낤�B
���������p����̌��t��������@�����Ƃ���A�p���̌������ٔ��́u�x���ŗ�v�������悤�ł��B
���̑̌�����A�ٔ����ɂ́u�i�؋���]������\�͂��܂ށj�ٔ�������\�͂��^�⎋���ē��R�ł���Ƃ������_�v��̂ł��B�����āA
�����҂͎��ԂƋ��������āA�����E�l���E���Y���Ɋւ��Đ^�����������Ă���ɂ�������炸�A����ȍٔ�������Ă��邱�Ƃm�ɂ��āA�ٔ����́A�u�܂Ƃ��ɍٔ��������ȁA�܂Ƃ��Ȕ������R���������ȁv�Ƃ����咣�����Ђł��邱�Ƃɂ��܂����B
�Ƃ����킯�ł��B
�{���́A�������ٔ��̌���ǂݕ����ɏ��������̂ł͂���܂���B
�{���̕���ɂ���悤�ɁA�u�̌��I�ٔ����ᔻ�_�v�ł��B
�ŏ��ɖ{�����ق���эō��ق𒆐S�ɂ��čٔ����̎v�l�̖��_��_���A���ɖ{���Ɋ֗^�����ٔ����̔������̈�@������̓I���ו��ɂ킽���Č��B�����Ă����܂����i�@���v�ւ̎��_���܂Ƃ߂Ă��܂��B
���̑̌�����A�Ō�Ɂu�i�@�ƍ����Ƃ̑��݃R�~���j�P�[�V�����E�V�X�e���̊m���v���āA����Ɋ֘A���ă��f�B�A�̖����Ɋւ��Ă����y����Ă��܂��B
�y���ǂ߂�{�ł͂���܂��A�̌�����̋M�d�Ȕᔻ�̏��ł��B
�s�𗝂ȍٔ��ɋ����Q���肹���ɁA��������Ɣᔻ�����݂��p����Ɍh�ӂ�\���āA�{�R�[�i�[�ŏЉ���Ă��炢�܂����B
�������P�Ȃ鎖��W�ł͂���܂���B
�����ɂ́A�l����������̌o�c�R���T���e�B���O�������N��ނ��A�o�c�̑��k�ɂ�����Ă������ʂ܂����A�o�c���l����p���_�C������������Ɗ������܂��B
���������A�{���̑薼�ł���u�Ƒn����v�ɂ��[���v�������߂��Ă��܂��B
�o�c�R���T���e�B���O�������̎��{���P����́A�u�͂��߂Ɂv�ł��������Ă��܂��B
�ȑO�A������ƌo�c�҂�ΏۂƂ����u����̏�ŁA�Q���҂���u������ƂƂ����Ăѕ���ς������B�����ӂ��킵���Ăі��͂Ȃ����̂��v�Ƃ�������������������B����̈Ӑ}�́A���݂̒�����Ƃ��u����Ă��錵��������z�N����钆����Ƃ̃l�K�e�B�u�ȃC���[�W�@���A�����ƃ|�W�e�B�u�ȑ��݂ɂ������A�Ƃ����v���ɂ����̂Ɨ��������B
���̎���ɑ��āA���́u�Ƒn��ƂƌĂт����v�Ɠ������B�Ƒn��ƂƂ́A�u�Ǝ��̉��l��n���A�����Ɓv���Ӗ�����B
�����āA�Ƒn��Ƃ̓����Ƃ��āA���̂T�������Ă��܂��B
���N�̊������瓾��ꂽ�A��̓I�����H�I�ȓ��e���A���ꂼ��ɍ��߂��Ă��܂��B
Vision�@ �u�̍����g�D
Alliance �헪�I�l�b�g���[�N�g�D
Learning �w�K����g�D
Uniqueness �Ǝ��̗͂����g�D
Execution ���s��������g�D
�������ۓI�Ȃ̂́A���{���A���܂��܂ȃX�e�[�N�z���_�[�i���Q�W�ҁj�ɂƂ��Ă̊�Ɖ��l�i�o�ω��l�E�Љ�l�E�ڋq���l�E�g�D���l�j���d�����Ă��邱�Ƃł��B
�����āA���̂悤�����Ă��܂��B�ƂĂ������ł��܂��A
���ꂩ��̌o�c�ɂ́A�o�ϖڕW�̂��ƁA�q�g�A���m�A�J�l�Ƃ������o�c�����������Ɍ����悭�R���g���[�����邩�Ƃ������}�l�W�����g����A��ɁA�����S�̉��l����Ȃ��Ƃ̓Ǝ��̉��l�̑n���������N�}�[���i�w�W�j�Ƃ��Ĉӎv���肵�A�s�����Ă����}�l�W�����g�����߂��Ă���B
�T�̓Ƒn��Ƃ̓������ƂɂR�`�T�Ђ̊�Ƃ��Љ��Ă��܂����A�ǂ̊�Ƃ����͓I�ł��B
���H�I�ɏЉ��Ă��܂��̂ŁA���H�̂��߂̃q���g���R����ł��B
�܂��e����̍Ō�ɁA�u���{���P�̓Ƒn��ƂɊw�ԁv���t���Ă��܂��B���ꂪ���ɖʔ����Ď����ɕx��ł��܂��B
���ꂾ����ʂ��ēǂ�ł��ʔ����ł��B
��ƌo�c�҂͂������ł����A��ƂŎd��������Ă���l�����ɂ��E�߂̂P���ł��B
���u���ڂ��̂���Â߁v�i����
�₷�Ȃ�@�@����Y�@�r�[�i�C�X�@1200�~�j
�̉��Ί����Y�͍���̒Ôg�ɏP���A�H��͐Ռ`������������Ă��܂��܂����B
�e���r�ŋ���Ȋʋl�����|���ɂȂ��Ă��镗�i�������l������ł��傤���A���ꂪ���Ђ̃V���{���ł����B
��Ђ͂������U���Ƃ����b�܂ł����������ł����A��ՓI�ɍɂ��Ă����ʋl���H��̊��I�̒����炽��������܂����B
��������h���}���n�܂�܂��B
�����m�̕��������ł��傤�B
���̘b�́u��]�̊ʋl�v�Ƃ��ėL���ɂȂ�܂����B
�����I�Șb�Ȃ̂ŁA���ЃT�C�g���������������B
http://kibounowa.jp/seisan-kinoya.html
���I�̒�����@�肾���ꂽ�ʋl�́A�ʂ͎K�т���ւ��肵�Ă��Ă��A�ʂ��J����Ζ��킢�͂��̂܂܁B�����ŁA���̖��������Ƃ���A�����ւ̊�]���J�^�`�ƂȂ������̊ʋl���w������Ƃ����x�����S���ɍL�������̂ł��B
���̃h���}���A���Ђ̃t�@���������v���W�F�N�g��g��Ŗ{�ɂ����̂��A���̊G�{�ł��B
�G�{�Â���̃v���W�F�N�g���܂������I�ł��B
���͍�N�̏H�A���Ђ̎В��ƃp�l���f�B�X�J�b�V���������ꏏ�����Ă��炢�܂����B
���ɖ��͓I�ȎВ��ŁA���������l���В��ł���A�x���������N����̂��悭�킩��ȂƎv���܂����B
���̎��Ɉꏏ�ɂ���������Ђ̏��F���{�𑗂��Ă��Ă��������܂����B
���F����̂��莆�ɂ��A�H��Č��܂łɂ͂܂�1�N�قǂ̎��Ԃ�������悤�ł��B
�����������̃t�@���Ɏx�����āA���Ђ͑O�Ɍ������Đi�݂����Ă��܂��B
�{�������̉�����S���Ă��܂��B
�{���͑S���̈ꕔ���X�ōw���ł��܂��B�悩�������ɂƂ��Č��Ă��������B
���̏��͎��̂Ƃ���ɂ���܂��B
http://kibouno-canzume.benice.co.jp/
�G�{�Â���̃v���W�F�N�g�̌Ăт����ɂ��������Ă���܂��B
�@�Ôg�ɗ����ꂸ��
�@�c�������̂��������B
�@����́A��]�������B
�������̑�Ôg���A��]�����͗����Ȃ������悤�ł��B
�R�����Y���X�ōw��
���Z�p�җϗ� ���{�̎���ƍl�@�i���{�`���ق��Ғ��@�ۑP�o�Ł@3000�~�j
���{�ŋZ�p�җϗ��̋��炪�{�i�I�Ɏn�܂���10�N�ɂȂ�܂��B
���̂��������́A���̗����ł́A���{�Z�p�m��̐��{�������A�����J��1995�N�ɏo�ł��ꂽ�w�Ȋw�Z�p�҂̗ϗ��x��|��o�ł������Ƃł����i1989�N�j�B
���̏o�ł��_�@�ɁA���{����͂m�o�n�@�l�@�l�Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[�����𗧂��グ�܂����B
�������̒��Ԃɓ���Ă��炢�܂����B
�����Œm�荇�����̂��{���̕ҏW�ӔC�ґ�\�̋��{����ł��B
���̌�A���{�Z�p�m��̂Ȃ��ɋZ�p�җϗ���������������A���{�����S�ɂȂ��Ė����A��������J�Â��Ă��܂��B
�܂����܂��܂ȑ�w�ł̋Z�p�җϗ��u���̊J�݂ɂ����g��ł��܂��B
�������������܂��āA���{����⋴�{����́A����܂ł������̒������o�ł��Ă��Ă��܂����A�{���̓A�����J�̊�{�I�e�L�X�g�w�Ȋw�Z�p�҂̗ϗ��x�̓��{�ł��߂�������{�e�L�X�g�ł��B
���{����͖{���́u�͂��߂Ɂv�ł��������Ă��܂��B
�č��ň�����Z�p�җϗ��͂������ɗD�ꂽ���̂ł��������A����10�N�̌o������A���{�Ŏ������悤�ɂ��邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃ��킩���Ă����B
�����Đ��܂ꂽ�̂��{���ł��B
���{�Z�p�m��ɏ�������Q�O���̋Z�p�m���A�����o���ɂ��ƂÂ������p���Ȃ��玷�M���Ă��܂��B���グ���Ă��鎖��͓���̂��̂ł͂Ȃ��A���ʂ̋Z�p�҂�����A�o��悤�Ȏ���ł���_�������ł��B
���Ⴒ�ƂɌo�߂Ǝ����W���Љ��A���_�Ɣ��f������m�ɂ��ꂽ�����ōl�@���Ă����Ƃ����X�^�C�����Ƃ��Ă��܂��B�����ňӐ}����Ă���̂́A�����ł͂Ȃ��āA�������悤�ȍl������ǎ҂��w�Ԃ��Ƃł��B�ϗ��������d�g�݂�A�ϗ��̔��f��K�v�Ƃ���g�g�݂������ł���悤�ɍH�v����Ă���̂ł��B���{�ɓ��L�̕����I�E�Љ�I�w�i�܂����l�������d������Ă���̂������̈�ł��B
�������̎���́A�V�̌����A�X�̋`���ɂ��������Đ�������Ă���̂ŁA������`���ɂ��Ẵ��f���I�Ȕ��z���g�ɂ��A�Z�p�җϗ����\���I�ɑ�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
���{�����́A�{�����Z�p�҈ȊO�̐l�����ɂ��ǂ�ł��炢�A��ʂ̕��X���A�Z�p�҂̖����𗝉�����˂����ɂȂ��Ăق����ƍl���Ă��܂��B�Z�p�҂Ɍ��炸�A�d������̂Ȃ��ŏo����܂��܂ȗϗ����ɑΏ�������H�I�ȗ͂�{�����Ƃ��ł���Ƃ����Ӗ��ŁA�����̐l�ɓǂ�łق����P���ł��B
���Ȃ݂ɖ{�������ɂ��Ă���Z�p�҂����ׂ������Ƌ`���͎��̒ʂ�ł��B
���V�̌�����
�����������E�L�\�������E�^���������E�����������E�����������E���E����
���X�̋`����
�@���Ӌ`���E�K�͏���i�R���v���C�A���X�j�`���E���z���`���E�p���w�K�`���E���J���`���i�����ӔC�j�E�����`���E���`���E���ȋK���`���E�����`��
�R�����Y���X�ōw��
���u���͋�@��͑�n�v�i������q�ҁE��@�萳���@�p�����Ɂ@1700�~�j
1800�N���Ɏ푰�̓y�n�������\�����ꂽ�A�����J���{�ɑ��āA�C���f�B�A���̏U���E�V�A�g�����������莆�̘b�͗L���Ȃ̂ŁA�����m�̕��������ł��傤�B
���̎莆�̘b���A�V���Ȗ|��Ɨ͋����G�ŁA�܂��ɑh�点���̂��{���ł��B
�Ȃ������N�قǑO�A�t�F�C�X�u�b�N�Œm�荇������Ƃ̎肳�A�����́u���̂��v���e�[�}�ɂ����W�܂�ɁA���ɂ킴�킴�����Ă��Ă���܂����B
�V���ł͂Ȃ��A�o�ł͂���10�N�ȏ�O�ł��B
�ɂ�������炸�A����Љ���Ă��炤�̂́A���߂Ă��̕��͂�ǂ�ŁA�����̐l�ɂ��m�点�����Ǝv�������Ƃ����R�̈�ł����A��������R������܂��B
���͍ŋ߁A�_�b�w�҂̃W���Z�t�E�L�����x���́u�_�b�̗́v��ǂ�ł���̂ł����A�����ɂ��̈�b���Љ��Ă����̂ł��B
���傤�ǁA�����ǂ���Ɏ肳�炱�̖{����������̂ł��B
���R�̈�v�Ƃ͎v���܂���B
����ɁA�肳��̊G���A�ƂĂ��X�s���`���A���ŁA�`����Ă�����̂�����܂��B
����͏Љ�Ȃ�������Ȃ��Ǝv�����̂ł��B
���́A�V�A�g���U���̎莆�����Ȃ����ۂɂ͑��݂��Ȃ������Ƃ����Ă��܂��B
�ł����炱��͂ނ���A�����J����l�C�e�B�u�̍��̌���ꂾ�Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�����m�̕��������ł��傤���A���̈ꕔ�����p�����Ă��炢�܂��B
���V���g���̑�U�����A�y�n�������Ƃ����Ă����B
�ǂ�������@������Ƃ����̂��낤�H
�����āA��n���B
�킽���ɂ́@�킩��Ȃ��B
���̓�����@���̂���߂���
���Ȃ��͂��������@�ǂ�����Ĕ������Ƃ����̂��낤�H
����ȕ��͂��o�Ă��܂��B
��������̂��@�Ȃ����Ă���B
�킽���������@���̖��̐D�蕨��D�����̂ł͂Ȃ��B
�킽�������́@���̂Ȃ��́@��{�̎��ɂ����Ȃ��̂��B
���͂����ł���A�l�b�g�ł��ǂ߂邩������܂���B
�������{���́A�肳��̎v�������߂��A���Ɠ��̊G������ł��B
���̊G�����Ȃ���A�v����y���āA���͂�ǂނƁA�܂��ɍ��ւ̋���������܂��B
�����̐l�������A���̖{����������Ɠǂ�ł��ꂽ��A�Љ�͕ς��A���j�͕ς�邩������܂���B
����ȋC�����āA�Љ���Ă��炢�܂����B
�R�����Y���X�ōw��
�����Ȃ��̏Z�܂��̐k�Б��i�s���Y�R���T���Q�P������@�����Ё@2000�~�j
�T�ԋL�^�ɂ������܂������A
�C���L���x�[�V�����n�E�X�̃����o�[�̈�������������s���Y�R���T���Q�P������o�ł����{�ł��B
�s���Y�R���T���Q�P������͑��ʂȃ����o�[����Ȃ�O���[�v�ŁA
���z�m�A�s���Y�R���T���^���g�A�ŗ��m�A�y�n�Ɖ������m�A�t�@�C�i���V�����v�����i�[�A�s���Y�o�c�Ǘ��m�Ȃǂ���\������Ă���l�b�g���[�N�g�D�ł��B
�����{��k�Јȗ��A�k�Б�ւ̊S�͍��܂�܂����B
��펞�̂��߂ɔ�����h�ЃO�b�Y�������L���Ă���悤�ł��B
��������Ȃ͎̂������̐������̌������ł��B
���̐������ɂƂ��āA�u�Z�܂��v�͂ƂĂ��傫�ȈӖ��������Ă��܂��B
�܂���Ќ�̐������Ē����ɂƂ��Ă��A�u�Z�܂��v�͑傫�ȈӖ��������Ă��܂��B
�{���́A�k�Ђɔ����āA�Z�܂��Ɋւ��āA�����ǂ����Ă��������̂��A�܂���Ђ������ɉ����ǂ������炢�������A���܂��܂ȃe�[�}�ɉ����āA���Ƃ��p���`�`���ŁA�킩��₷����������u���S�E���S�̂��߂̈���i�k�Б�v�̃K�C�h�u�b�N�ł��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���̂������ł��B
�����ɂ́A�k�Б�`�F�b�N���X�g���f�ڂ���Ă��܂��B
���̃��X�g�ɂ��A�k�Бǂ��܂łł��Ă���̂��A�������肸�A�ǂ��܂ő�悢���Ȃǂ������ł��܂��B
�Z��ȂǂɊւ��ẮA�k�Б�ƌ����Ă�����������ǂ��̂��A�Ȃ��Ȃ��킩��Ȃ��̂ł����A
�����������Ƃ��l���邽�߂ɂ��֗���1���ł��B
�Z�܂��̂��Ƃ��C�ɂȂ��Ă�����͂��ǂ݂��������B
���e�Ɋւ��āA�������₢���킹�Ȃǂ���A���ł�����������Љ�܂��B
���M�҂̈�l�ł����鈢������́A��Ȃ͓̂����̐��������ƌ����Ă��܂��B
����������������̎v���Ɩ{���ɏ�����Ă���悤�ȋ�̓I�Ȑk�Б�Ƃ��Ȃ����悤�ȃ��[�N�V���b�v���J�t�F�T��������x��悷��\��ł��B
�S�̂�����͎��ɂ��A�����������B
�����{�̌������ϗ��i���{���@�n�p�Ё^�O�ȓ����X�@2000�~�j
�m�o�n�@�l�Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[������\�̐��{���A����̌������̌�A���q�͈��S��Ջ@�\�̈˗��ŁA�u���q�͈��S�K���Z�p�҂̂��߂̋Z�p�җϗ����C�v�����{���܂����B���̎��H�����܂��āA�������낵���̂��{���ł��B
���Ȃ݂ɁA���{����͋Z�p�җϗ��Ɋւ��Ă���10�N�ȏ�A������w�ł̍u�`�Ȃǂ�ʂ��āA�����������d�˂�ƂƂ��ɁA�Z�p�җϗ��̕��y�����Ɏ��g��ł��܂��B
�{���̑тɁA�u����܂Ō������ϗ��@�̂��ƂŁg�������ϗ��h�Ƃ���Ă����̂́u���ɓI�ϗ��v�������v�Ə�����Ă��܂����A�{���Ő��{���咣���Ă���̂́A�����������ɓI�ϗ������ł͂Ȃ��A�u�ϋɓI�ϗ��v�Ƃ���Ɋ�Â��u���������W�v�̕K�v���ł��B
���{����́A�Z�p�җϗ����l�����ł́upublic�i���O�j�v�Ƃ����T�O���J�M�ɂȂ�Ƃ��Ă��܂����A�������ϗ����l����J�M���upublic�v�i���{�ł́u�����v�Ɩ�Ă��邱�Ƃ������ł����j���ƍl���Ă��܂��B
���Ƃ��A���������̂ł��B
�������̐Ӗ��Ƃ��āA�u�����̗��v�̑��i�v�Ƃ����u�o���F�v�̖ڕW���f������́A�Q����₷�����O�ɑ���Ӗ��Ƃ��Đ����ق����K�ł͂Ȃ����낤���B
�u�����̗��v�v�͂킩�����悤�ł킩��܂���B���������O�A�܂莄�������ʂ̐����҂ɑ��Q��^���Ȃ��悤�ɂ���Ӗ��Ƃ����A�悭�킩��܂��B
����̌������̂��l����A����ɂ悭�킩��ł��傤�B
���Q��^���Ȃ����߂ɂ́A���������@�ߏ��炵��������Ηǂ��킯�ł͂���܂���B
�ނ���u���ׂ����Ƃ����Ȃ��v�s��ׂ������ӂ߂���ׂ��ł��傤�B
�����ɐϋɓI�ϗ��̈Ӗ�������܂��B
�����Đ��{����͂��������܂��B
���ɓI�ϗ��Ɏ��g�ޏꍇ�ƁA�ϋɓI�ϗ��Ɏ��g�ޏꍇ�Ƃł́A���̐l�̎p���ɑ傫�ȈႢ������B
��̓I�ɂ͂����������Ƃł��B
�������ϗ��̈ᔽ�s�ׂQ�U���ڂ́A������Ƃ��ɂ͂�������炷��悢�A����ȊO�̂��Ƃ͍l���Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��Łu�������v�̏��ɓI�ϗ��ɂȂ����B�@�߂ɒ�߂�ꂽ���Ƃ͂��̂Ƃ��肷�邪�A����ȊO�̂��Ƃ͋`���ł͂Ȃ��Ƃ����A���ɓI�Ȗ@�ߏ���i������j�ł���B���������p�����g�ɂ��ƁA�ϗ������ɂƂǂ܂炸�A�Ɩ���ʂɂ����āA����ꂽ���Ƃ́A���̂Ƃ��肷�邪�A����ȊO�̂��Ƃɂ͋C������Ȃ��Ƃ����A���ɓI�Ȏp�����������邱�ƂɂȂ�B
���܂̌������������Ă��܂��B
�����ƏЉ�����Ƃ���͂�������̂ł����A�����Ȃ�܂��̂ŁA������������p���܂��B������ԋ������������ł��B
�ϗ��́A�P�ɁA���Ă悢���ƁA���Ă͂����Ȃ����Ƃ̋K�͂ł͂Ȃ��B�ϗ��I�ɍs�����邱�Ƃ́A���̐l���A�l�Ƃ��đ��d����p�����Ӗ�����B����ɁA���_�Ɏ��g�ގ���I�A�����̎p�����Ӗ�����B����́A�ڂ���l�Ƃ̊ԂɁA�Θb�ƐM���̐l�ԊW��z���w�͂ɂق��Ȃ�Ȃ��B
���������W�̕K�v���Ɋւ��Ă���������p���܂�(������v��j�B
�����̕����ւ̊�^���ő�ɂ��邽�߂ɂ́A�s���������Ă�͂ƁA���Ǝ҂����Ă�͂Ƃ��A���҂̑���W�ɂ����čő���ɔ�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�s�����Ǝ��Ǝ҂Ɋ��҂����̂́A���������O�����̎p���ł���B
�{���ɂ͂܂�����̌������̂Ɋւ��b�����������łĂ��܂��B
���̎��_�œǂ�ł������̎����������܂��B
�������ϗ��̖{�ł����A�����̐l�ɓǂ�ŗ~�����{�ł��B
���u���{�l�͒E�������ł���̂��v�i��{���@���Ώ��X�@1600�~�j
���N�A���a�̖��Ɋւ��āu�V�����v�z�v��Nj����Ă�����{�����A
��N�̕����������̂����ɂ��āA����܂ł̐��ʂ��킩��₷���W�听�����{���o�ł��܂����B
�W����h���I�ł��B
�u���{�l�͒E�������ł���̂��v
�P�Ȃ錴�����̂Ɋւ����{�ł͂���܂���B
���肪�u�����Ǝ��{��`�Ɩ����`�v�ƂȂ��Ă���悤�ɁA��{����̖��ӎ��͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B
�u�E�����v�͌�����肾���ɂ͎��܂�܂���B����͎��{��`�o�ς̊Q���̒��ŋN����A�ߑ㖯���`�i�����^�����`�j�̌��_�̉��ŋN�����Ă��܂��B�ł�����u�E�����v�����߂�ȏ�A���́u�E�����v�����{��`�̊Q�����������Ă����ߒ��A�ߑ㖯���`�W�����Ă����ߒ��̒��Ɉʒu�Â��Ă����K�v������܂��B�i���Ƃ����j
��{����́u�v�z�v�́u�V�Љ�_��_�v�ł��B
�ꌾ�Ō����A���\�[�Ɏn�܂邱��܂ł̎Љ�_��_�͐��m�ɂ́u���ƌ_��_�v�ł����B
����ɑ��āA��{����́A��̓I�Ȑl�̂Ȃ���Ɍ_��̊�_��u���̂ł��B
�܂�A�Q�l�ȏ�̐l�Ԃ̊Ԃɉ��炩�̊W�����݂��Ă���ꍇ�A���́u�l�ԑ��݂̊W�ɂ���Đ������邻�ꂼ��̐l�ԂɂƂ��Ă̋��ʂ̐����̈�v���Љ�ƋK�肵�A�����ł̓����҂̊W����A�Љ�_����l���Ă����̂ł��B
����Ɋւ��ẮA���łɂ��̃R�[�i�[�ŏЉ�Ă����{����̑����̒����A�ƂƂ����u���{���܂�̐��`�_�v�Ȃǂ����ǂ݂��������B
�������{���ɂ��Ă��˂��ɐ�������Ă��܂��B
�{���̃^�C�g���u���{�l�͒E�������ł���̂��v�ւ̓����͂ǂ��ł��傤���B
���̌��ɂȂ�̂́A�u�u���҂́w�l�Ԃ̑����x�ɔz���������v���Ƃ��ł��邩�ǂ������Ɛ�{����͌����܂��B
�c�O�Ȃ���A����܂ł̓��{�l�̑����́A�����ł͂���܂���ł����B
�������A���{�l�͂��鎞���A�����Ȃ�������������Ɛ�{����͌����܂��B
����E��킪�I���������ł��B
�u�푈�̌���ʂ��Ċl���������{�����̐��́u���o�v�͑����̓_�ŁA���łɐ����^�����`��Љ��`���^�����`�̍l�������Ă����v�ƌ����̂ł��B
�������A�c�O�Ȃ��炻�̊��o�͒蒅�����ɏI����Ă��܂��܂����B
�����̌����A���ǂ͊�������Ȃ������B
�����āA�������e��Ă��܂����̂ł��B
�����S�������ł��B
������A�u���{�l�́u�E�����v���ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��v�Ɛ�{����͏����Ă��܂��B
�����āA�������甲���o���ɂ́u�V�����v�z�v���K�v���Ƃ����̂ł��B
���̐V�����v�z�́A���݂̎��{��`�̕��Q�������`�̌��_���������Ă������ƂɂȂ�B
����������A���ꂪ�Ȃ���A�E�����͂ł��Ȃ����낤�ƌ����̂ł��B
�܂�A�u�u�E�����v�͎��{��`�̊Q�����������Ă������Ƃ����^���ł���A�ߑ㖯���`�̌��_���������Ă������Ƃ����^���v�łȂ�������Ȃ��Ɛ�{����͍l���܂��B
���͍����̒E�����^���ɂ͑傫�Ȉ�a��������܂����A�{����ǂ�ŁA���̈�a���̗��R�������[���ł��܂����B
�㔼�́A���������܂ǂ���������c�_�������܂����A�ɂ߂Ė{���I�Ȗ���N���Ȃ���Ă���Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA��{����͕K�������y�ς͂��Ă��܂��A��H�ɂ�����{�l���u���҂́w�l�Ԃ̑����x�ɔz������v��������I��łق����ƔO���Ă��܂��B
�����A���҂����߂āA�����Ȃ��Ă������낤�Ǝv���Ă��܂��B
���Ȃ��Ƃ��A���͂������������������Ă��܂��B
�������u���ҁv�͓��{�l�����ł͂���܂���B
�x�g�i���ɂ������͗A�o���Ăق�������܂���B
�ł��邾�������̐l�ɁA�ǂ�łق����{�ł��B
�����ǂ܂�ĊS�������Ă��炦����A��{��������Ăт����T��������悵�����Ǝv���܂��̂ŁA��]�҂������炲�A�����������B
3�l�W�܂������悵�܂��B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u�ō��̐E��v�iM�E�o�[�`�F���{J�E���r���@�~�l�����@���[�@2000�~�j
�ŋ߂̓��{�̉�Ђ́A���Ȃ���Ă���悤�Ɏv���܂����A
��Ђ����C�ɂ��邽�߂ɂ́A�]�ƈ������������Ɠ�����E��ɂ��Ă����Ȃ�������܂���B
���������l������A���������̂���E����ЂN�������A
���܂��܂Ȓ��s���Ă���̂��A�����J�𒆐S�ɐ��E�ɍL�����Ă���Great Place to Work�i�f�o�s�v�j�v���W�F�N�g�ł��B
��N�A�A�����J�ŁA20�N�ɂ킽��f�o�s�v�̒������ʂ܂����{���o�ł���܂����B
�s�g�d �f�q�d�`�s �v�n�q�j�o�k�`�b�d�B
���{��ɖƁu�ō��̐E��v�ł��B
���N�������������Ɏ��g�݁A���{�ɂ��f�o�s�v���Љ�Ă��ꂽ�֓��q�������i�g�D�Ɠ���������������\�j�������A
���̘b��̖{��|��o�ł��Ă���܂����B
�����ɓǂ܂��Ă��炢�܂������A�܂��ɂ��܂̓��{�̉�ЂɕK�v�Ȏ������R�̂悤�ɐ��荞�܂�Ă���{���Ǝv���܂����B
�{���̕\���J�o�[�ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă��܂��B
�����ɎЈ��̃��`�x�[�V������ۂ��A�d���̌��������߂�ǂ��g�D�ƂȂ邩�A�ɂ��Ăǂ̂悤�ȍH�v�����Ă���̂��B
�����āA�Ј����A�����̉�Ђ��ւ�Ɏv���A�]�����Ă���̂͂ǂ̂悤�ȂƂ���Ȃ̂��B
�{���ł́A100�Ћ߂��P�[�X�X�^�f�B�����ƂɎ��H�ɂȂ��������s���A�u�ō��̐E��v�n�o�̔錍�𖾂炩�ɂ���B
�L�x�ȋ�̓I����̏Љ�ƃ��[�_�[�Ƃ��Ă̍s���̃`�F�b�N���X�g�ȂǁA���H�I�ȃe�L�X�g�ł�����܂����A
�P�Ȃ���H�̂��߂̃m�E�n�E�{�ł͂���܂���B
�ꗬ�ɗ����̂́A�o�c�v�z�̓]���ł��B
�����]�ƈ����N�_�Ɍo�c�̂�������l���悤�Ƃ����p���ɂ́A
�ŋ߂̓��{��Ƃ��Y�ꂪ���ȁu�l�ԁv�̎��_�������������܂��B
�܂�����܂ł̂悤�ȁA���@���Ȍo�c�_�ł͂Ȃ��A
���G���̉Ȋw�ł̋c�_������������_�C�i�~�b�N�Ȍo�c�_�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɂ������ł��܂����B
�{�����A�ō��̐E����������邽�߂ɏd�����Ă���̂͂R�̊W���ł��B
�u�]�ƈ��Ƃ��̃��[�_�[�Ƃ̊W�v
�u�]�ƈ��Ƃ��̎d���Ƃ̊W�v
�u�]�ƈ����݊Ԃ̊W
���̂R�������A�o�c�̗v�ƌ����Ă���̂ł��B
�Ƃ�����A�u�l�ԁv��Y�ꂪ���ȍŋ߂̊�ƌo�c�̗���̒��ŁA�����������_�͉��߂đ傫�ȈӖ��������Ă��܂��B
�R�̊W���́A�u�M���v�u�ւ�v�u�A�ъ��v�Ƃ����R�̐���ŋ�̓I�Ɍ���Ă��܂��B
�Ƃ��������ۂ̌���ł̑̌��m���x�[�X�ɂ��Ă��܂��̂ŁA
�ƂĂ��킩��₷���A�����͂�����A�܂����̋C�ɂȂ�A��������ł����g�߂���̂���ł��B
��Ƃ�s���ȂǁA�g�D�Ŏd�������Ă���l�ɂ͂��Гǂ�łق����{�ł����A
�W���̎��_���玩��̐�������₢�����Ƃ����Ӗ��ł́A���ׂĂ̐l�ɂ��E�߂������{�ł��B
���̖{��ǂ�ŁA����̐�������������ƕς��邾���ŁA���Ԃ���ӂ��ς���Ă���悤�Ɏv���܂��B
�R�����Y���X����̍w��
���u�̂����ꂽ ���Ȃ��ցv�i���^��@�o�ŎЁ@1500�~�j
���^�炳��̒����͂��̃R�[�i�[�ł�����Љ���Ă�����Ă��܂����A
����͈��^�炳��̃��C�t���[�N�ɂȂ���O���[�t�P�A���e�[�}�ɂ����{�ł��B
�������́u���{�ɃO���[�t�P�A�̕��������S�ɍ��Â����߂̈ꗱ�̔��ɂȂ肽���v�ƑO���珑���Ă��܂����A�{
���͂Q���ڂ̃O���[�t�P�A�̖{�ł��B
����ڂ��w������l��S�������l�ցx�i���㏑�сj�ł��B
�������ɖ{���������������̂́A3��11���̓����{��k�Ђ������悤�ł��B
�{���̕���́u�R�E�P�P ���̔߂��݂����z���邽�߂Ɂv�ƂȂ��Ă��܂��B
��Вn�ɗ��������̎v�����{���ɏ�����Ă��܂����A�������ՋƂ̉�Ђ̎В��Ƃ��āA���܂��܂ȑ��V�ɗ�������Ă���������́A�����ɂ�������̎v�����������Ƃł��傤�B
�����Ė{�����ł����������̂ł��B
�������͂����g�̃u���O�ɂ��������Ă��܂��B
�������A�ǂ̂悤�Ȍ��t�������������Ƃ��Ă��A�S���Ȃ������������Ԃ邱�Ƃ͂���܂��A���̔߂��݂����S�ɖ����邱�Ƃ�����܂���B�������A�����ł����̔߂��݂��y���Ȃ邨��`�����ł��Ȃ����ƁA�킽���͈ꐶ�����ɐS�����߂Ė{���������܂����B���ɂ́A�܂𗬂��Ȃ��珑���܂����B
�{����ǂ�ł��āA���X�A��Вn�̕��i���_�Ԍ�����C������̂́A���̂�����������܂���B
�������{���͂���ɂƂǂ܂�܂���B
�{���̑тɂ́u�O���[�t�P�A�̓��发�ɂ��Č���Łv�Ə�����Ă��܂����A����܂ł̈������̊����܂����Y���Ȓm���Ƒ̌�����A�O���[�t�P�A���x����d�g�݂�v�z���̌n�I�ɂ������菑�����܂�Ă��܂��̂ŁA�u���ׂẮg������l��S�������l�h�v�ւ̃��b�Z�[�W�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
����͎������̐��������̂��̂ւ̃��b�Z�[�W�ł�����܂��B
�ڎ��͎��̒ʂ�ł��B
��P�́F���V���ł��Ȃ��������Ȃ���
��Q�́F��̂�������Ȃ����Ȃ���
��R�́F���悪�Ȃ����Ȃ���
��S�́F��i���Ȃ����Ȃ���
��T�́F����ł��C�����̂��ꂪ�Ȃ����Ȃ���
�����āA�u���Ƃ����v�ɑウ�ĂƂ��āA�u�ʂ�̌��t�͍ĉ�̖v�Ŗ{�����т��A�����Ĉ������̃O���[�t�P�A���O�ł܂Ƃ߂��Ă��܂��B
�����炭�{����ǂ܂��Ƃ݂Ȃ���͐V�������������낢�날��͂��ł��B
�����Ă��낢��ȁu�������v�����邱�Ƃɂ��C�Â����ł��傤�B
�R�s�[���C�^�[�̖���ł�����������́A�h���I�ȃ��b�Z�[�W�����������Ă���Ă��܂��B
���Ƃ��A����ȃ��b�Z�[�W������A���Ȃ��͂ǂ��v���܂����B
�u�c���ꂽ���Ȃ�������̂ł��v�ƁB
���E�߂̂P���ł��B
�R�����Y���X����w��
�����l�E��т̏����ƕ��� �i��ђn��X�Â����
���l���ȑ�w�@1500�~�j
���݊�����Ђ̍��{����ҏW�̒n��w�V���[�Y�̑�Q��ł��B
����͉��l�̖�ђn�悪�e�[�}�ł��B
��т́A��������W���Y�o�[�ȂǁA500���ȏ�̂��X���Ђ��߂����l�̈�古�X�X�ŁA��ё哹�|�ł��L���ł����A���|��⌀��Ȃǂ������A���ʂȏ��������M���Ă���܂��ł��B
���؊X�⌳���ɔ�ׂ�Ƃ��܂�m���Ă��܂��A���l�̊J�`�����������ɂ��Ď��R�����I�Ɍ`�����ꂽ�X�ŁA���l�̃A�C�f���e�B�e�B�𗝉����邤���ŏd�v�ȊX�̂ЂƂƂ������Ă��܂��B
������2007�N����s���Ă���u��т܂��Ȃ��L�����p�X�v�ł́A2010�N�x�̍u�����܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�n���̏��X��A���y�j�ƁA�u��ё哹�|�v�̊W�҂Ȃǂ�����т̘b�́A���O�҂��ǂ�ł����ɖ��͓I�Ŗʔ����ł��B
�{���́A�u���j�ƊX�̐��藧���v�u��O�����ƌ|�\�v�u�����ƊX�̊������v��3���\���ł����A���̂��ꂼ�ꂪ�P�ɖ�тƂ����n��̘b�����ł͂Ȃ��A����������{�̗��j�╶�����_�Ԍ����Ă��܂��B
���l�Ƃ����n��̓����ɂ��̂�������܂��A���l�ɏZ��ł��Ȃ��҂ɂƂ��Ă��ʔ����ǂ߂܂��B
���{�v�Ȃ̕ҏW�̘r�ɂ��̂�������܂��A���������[���S�҂�ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�����ȈӖ��Ŗʔ����{�ł��B
�ŋ߁A�e�n�Łu�܂��Ȃ��L�����p�X�v��u�܂��Ȃ��J���b�W�v���L���肾���Ă��܂����A��т܂��Ȃ��L�����p�X�͂������������̂͂���̂ЂƂł��傤���B
���Ēn��w���L���������ɁA�������{�������Ȃ�s���܂������A�܂��Ȃ��L�����p�X�̋L�^�����������`�ł�������Ƃ܂Ƃ߂Ă���Ƃ���͂��������͂Ȃ��ł��傤�B
�ł�����A�{���͂��������u�܂��Ȃ��L�����p�X�v��������悷���ł��Q�l�ɂȂ�܂��B
���̈Ӗ��ŁA�܂��Â���Ɏ��g��ł���l�ɂ����E�߂�1���ł��B
��ђn��X�Â����Ɋւ��Ă̓z�[���y�[�W���������������B
���u�z�X�s�^���e�B�E�J���p�j�[�v�i���v�ԗf�a�@�O�܊ف@2100�~�j
���̃R�[�i�[�ł���������̒������Љ���Ă�����Ă�����^�炳��̖{���͍��v�ԗf�a����ł��B
�����č��v�Ԃ���͖k��B�s�ɖ{�Ђ����銔����ЃT�����[�̎В��ł�����܂��B
�{���́A���v�Ԃ��{���ŏo�ł���2���ڂ̖{�ł��B
�T�����[�́A�������ՃT�[�r�X�𒆐S�Ɏ��ƓW�J�����Ă����Ђł����A�ŋߒ��ڂ���Ă��Ă���u�אl�Ղ�v����{�ň�ԑ����J�Â��Ă����Ђł�����܂��B
���v�Ԃ���́A�u�����Љ�v�ȂǂƂ������t���L�����Ă��錻�݂̎Љ��ς��Ă������ƁA���Ƃ�ʂ��āA�܂����M��u��������ʂ��āA��������Ă���̂ł��B
�{���́A���̍��v�Ԃ��ŋ߂T�N�ɂ킽���āA�В��Ƃ��ĎЈ��̑O�Řb�������b�Z�[�W��{�ɂ������̂ł��B
���Ȃ݂ɁA���̑O�̂T�N�̃X�s�[�`�́A�ȑO�Љ���u�n�[�g�t����J���p�j�[�v�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B
���v�Ԃ���̃z�[���y�[�W�ł����J����Ă��܂����A���v�Ԃ��A�Г��Ɍ����Ă��Љ�Ɍ����Ă��ς�邱�ƂȂ��A���b�Z�[�W���o���Ă��邱�Ƃ��悭�킩��܂��B
�܂��Ɂu�m�s����v�B���̎p���ɋ����������܂��B
�Ј������̘b������ǂ������ւ̓��e���낤�ȂǂƎv���l�����邩������܂���B
���������l�ɂ����A�{����ǂ�łق����ł��B
�����Ō���Ă�����e�̐[����L���ɋ����͂��ł��B
�������S�̂��傫�ȃr�W�����ŕ�܂�Ă��܂��B
�܂��Ɂu�r�W���i���[��X�s�[�`�v�Ȃ̂ł��B
���v�Ԃ���́A�u�z�X�s�^���e�B�v�͍���̉�Ђ݂̂Ȃ炸�A�Љ�S�̂̍ő�̃L�[���[�h���ƌ����܂��B
�l�ނ�21���I�ɂ����ĕ��a�ōK���ȎЉ�����邽�߂̍ő�̃L�[���[�h���Ƃ����������Ă��܂��B
���̈Ӗ��́A���Ж{���œǂݎ���Ă��炦��Ǝv���܂��B
�X�s�[�`��{�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
�ʓǂ��Ă��悵�A���E�ɂ����ċC�̌����܂܂ɓǂ�ł��悵�A�ł��B
�Z����b��b���瓾�鎦���͌����ď��Ȃ�����܂���B
��ƌo�c�ɂ܂��{�̂悤�Ɏv����ł��傤���A�����Ă����ł͂���܂���B
���������l����������{�ł�����܂�����A���ׂĂ̐l�����ɂ��E�߂������{�ł��B
���Ȃ݂Ɏ������v�Ԃ���ƒm�荇�����̂��u�z�X�s�^���e�B�v�Ƃ������t�̂������ł��B
����10���N�O�ɂȂ�܂����A�k��B�s�Łu�ɂ��ɂ��z�X�s�^���e�B�^���v���W�J����܂������A���̃L�b�N�I�t�̏W�܂�ŁA�z�X�s�^���e�B�̘b�������Ă�������̂ł��B
�����g������̐������̊�{�Ɂu�z�X�s�^���e�B�v��u���Ă��܂��B
�z�X�s�^���e�B����{�ɒu���Đ����Ă���ƁA�������K�ɂ����܂��B
�݂Ȃ���ɂ����Ђ��E�߂������������ł��B
�{����ǂ�ŁA���̈�����n�߂Ă��炦��Ƃ��ꂵ���ł��B
���u�s���Љ���_�v�i�c���퐶
���Ώ��X�@2415�~�j
�c���퐶���A����܂ł̒������������܂��āA�܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�c������́A��w�]���E�w�ʎ��^�@�\ �]���������̏y�����ł����A
���{�̂m�o�n�Ɋւ��Ắu�v���v���u�m���v���ƂĂ��[�����̂��������ŁA
���̕���Œ��N�A�ϋɓI�Ȋ������d�˂Ă��Ă����܂��B
�����ŏ��ɏo������̂�1990�N����ł����A
���̎��ɓc�������g��ł����̂��A���Ă�A�W�A�́u�R�[�|���[�g�E�V�`�Y���V�b�v�v�̒����ł��B
�������������̂́A����ɂ�������ƌ��������p���ł����B
�ȗ��A���ɂ͊������܂�Ȃ���A���܂��܂Ȏ��g�݂������猩�����Ă�����Ă��܂��B
�{���́A���������Q�O�N�ɂ킽��c������̎v�����A���������u�{��v�����߂Ă܂Ƃ߂��Ă��܂��B
���́u�{��v�̂������Ŗ����ȃ��b�Z�[�W���`����Ă��܂̂ŁA���̂悤�ȁu���Ɓv�����Ȏ҂̐S�ɂ������Ă��܂��B
�u�͂��߂Ɂv�̃^�C�g�����u���{�͂Ȃ��{�����^���Y�����ޏk�������̂��v�ł��B
���̃^�C�g���ɁA�{���̊�{�p�����������܂��B
����Ƃ��āA�u3.11��̐��{�ANPO�A�{�����e�B�A���l���邽�߂Ɂv�Ƃ���܂����A
�����̐l�͍���̓��{��k�ЂŊ������Ă���{�����e�B�A�̕ɂ�������G��Ă��邱�Ƃł��傤�B
�ɂ�������炸�A�c������́u���{�͂Ȃ��{�����^���Y�����ޏk�������̂��v�Ɩ���N���܂��B
���������\�w�I�ȓ����ɗ�����Ȃ��A�������肵�����_�ɗ���������N���{���̍���ɗ���Ă��܂��B
����͖{���̖ڎ������������ł킩��܂��B
���̗����ł́A���̊j�S�ɂ���̂́u�s�����v�ł��B
�s���������߂Ă������Ƃ������A���{�̎s���Љ��̊�{�łȂ�������܂���B
��������30�N�����Ă���̂́A���̕����Ɣ��̐���̓����ł��̂ŁA�{���̃��b�Z�[�W�ɂ͂ƂĂ������ł��܂��B
�c������͖{�����o�����Ƃ����ē����ɂ��������Ă��܂����B
���{�̕������x���邽�߂ɂ͋����s���Љ�s���ł��B
���̂��߂ɁA�������͉���ڎw���˂Ȃ�Ȃ��̂��A���{�ɉ������߁A���߂�ׂ��ł͂Ȃ��̂��A
�F�l�ƂƂ��ɍl���Ă䂫�����̂ł��B
�{�������̈ꏕ�ɂȂ�K���ł��B
���̈Ӑ}�͌����ɉʂ�����Ă���Ǝv���܂��B
���́A�{����ǂސl�̊��x��������܂���B
�{���́A�c��������܂Œ��N�ɂ킽��n���Ɏ��g��ł����������ʂ����܂��Ă��܂��̂ŁA�����͂�����܂��B
����ɉ������A�c�����g�̌����f���ɏo�Ă��āA�y�����ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�c������͒��Ԃƈꏏ�Ɂu�G�N�Z�����g�m�o�n���߂������s����c�v�𗧂��グ�A�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�̕]��������p���āA�u�����s���Љ�v�ւ̗Ǐz�����o�����Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
�{���́A�������������̊�{�I�ȃe�L�X�g�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B
�m�o�n�W�҂��͂��߁A���ꂩ��̓��{�Љ�̂�����ɊS�̂���l�ɂ͂��Гǂ�łق����{�ł��B
�����āA����̐��������������_�@�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B
�R�����Y���X����w��
����W�u�܌����i�v�i�˒J���@�p�쏑�X�@2667�~�j
��Ў���̐�y�ł����˒J�������̑���W�ł��B
�˒J����͉�Ђ����ތ�A����Y�O����Ɏt�����Ĕo����n�߂܂����B
���̍ŏ��̋�W�ł��B
���ƒ˒J����̊W�͂���܂ł����T�Ԋ����ŏ������݂܂������A�˒J����Ђ̕ϊv�Ɏ��g���ɁA���������d�������ꏏ�����Ă��炢�܂����B
���̂����ŁA�������t�������������Ă��܂��B
���͔o��ɂ͂܂������S������܂���ł����B
�ł����炱�̋�W�𑗂��Ă��������Ă��A���ʂ͂ς�ς�Ƃ߂����������������ł��傤�B
����������́A�����́u�܌����i�v�̋����ɖ������Ă��܂��A�����ǂݏo���Ă��܂��܂����B
�����āA��C�ɍŊ��܂ŁA���ׂĂ̋��ǂ܂��Ă��炤���ƂɂȂ�܂����B
��W���A��������Ĉ�C�ɓǂނ̂������̂��ǂ����͂킩��܂��A�˒J����̐l����m���Ă��邩�炩������܂��A��̐��E�����������Ǝ����ł��܂����B
�͂��߂Ĕo��̐��E���A�����_�Ԍ����C�����܂��B
�r�܂ꂽ��ɂ́A���̐��E�Əd�Ȃ鐢�E������������܂����B
�]����C�m�ʼnr�܂ꂽ��ɂ́A����q����������܂����B
��S�s���Ɋ�Ɛ�m���ߏグ�Ă����l�̕����������܂����B
��Șb�ł����A�ǂݏグ����A�����g�A�S�̕������������܂��B
�F�l�����X�A��W�Ȃǂ𑗂��Ă���܂����A�����A���܂苻���������܂���ł������A����͂�����ƈႢ�܂����B
���ɁA��W���ǂ����̂��Ǝv���܂����B
�R�����Љ�܂��B
���̐S�ɋ�������ł��B
�@�Ђ��т��Ɂ@���c�����@������
�@�Ŏ�肹���@�ʂꂵ��́@����
�@�����́@�قɒ�����@�܌����i
�����R�ی앪��̎s�������̌����i���V�_�q�@���u���[�o�Ł@2800�~�j
�R���P�A���Ԃ̓����_�q����͗l�X�Ȋ����Ɏ��g�݂Ȃ���A��w�@�Ȃǂł̌������������N�M�S�ɑ����Ă��܂��B
���̃G�l���M�[�ɂ͓���������܂����A����A�o�ł����̂��u���R�ی앪��̎s�������̌����v�ł��B
���̖{����������A�Ȃ��u���R�ی�v�Ȃ낤�Ǝv�����̂ł����A�{����ǂ�ŁA���̗��R���킩��܂����B
�O�Y�������R�ی�̉�i50�N������j�̂����j�̊����ɒ��N�G��Ă����̂ł��B
���H�����ւ̋����ɗ��������ӎ������V����̎x���ɂȂ��Ă���̂ł��B
�{���͎��ۂ̎s�������̋L�^�������ɕ��͂��A��������s�������ւ̎��H�I�ȃq���g���������o���Ă��܂����A�ώ@�ғI�ł͂Ȃ��A�����ғI�Ȏ��_��������̂͂��̂�����������܂���B
���V����́A�{�����������ړI�Ƃ��Ď��̂Q�������Ă��܂��B
�܂��u�s�������̌���ɒ~�ς���Ă���m���̉����v�ł��B
������\�������Ă��������Ƃ����̂����V����̎v���̂悤�ł��B
������́u���݂���я�������̌����҂Ƃ̌����f�ނ̋��L�v�ł��B
�������Ɏs�������̎��H�L�^�͎U�킵�����ł����A�������W�Ă������ƂŁA�s�������̈ʒu�Â�������������Ă��邾�낤�Ɠ��V����͍l���Ă��܂��B
���̎咣�ɂ͂ƂĂ������ł��܂��B
�����A�u�V���������v�_���łĂ��܂����A����܂ł̌����T�O�Ƃ̈Ⴂ�����ɂ͌����܂���B
�����g�́u���v�Ɓu���v�Ƃ͎��������O���S���Ⴄ�Ǝv���Ă��܂����A�܂��Ɏ��H�̌��ꂩ��̒E�\�z��Ƃ��s���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���̈Ӗ��ł��A�{������w�Ԃ��Ƃ͏��Ȃ�����܂���B
�O���͓��{�̎s�������̊T�O�����Ɨ��j�I�ȊT���A�㔼�͎��ؓI�Ȏ��Ԓ����܂�������N�ɂȂ��Ă��܂��B
�T�̃P�[�X�X�^�f�B�͂��ꂼ��ɂ��Ȃ蓥�ݍ����̂ł��̂ŁA���ꎩ�̂�����w�ׂ܂����A������ʂ������V����̍\�������߂��������݁i���Ƃ��Β����p���I�Ȏs�������̓W�J�̂U�i�K���f���Ȃǁj�ɁA���͋����������܂����B
���R�ی앪��Ɍ��炸�A�s���������l���Ă�����ł̎��H�I�ȃq���g����������܂��̂ŁA���H�҂̕��̂悢�e�L�X�g�ɂȂ肻���ł��B
�������̖{��ǂ�Ŏv���o�����̂́A�C���@���E�C���C�`�������A�R�����B���B�A���e�B�ƃT�u�V�X�e���X�ł��B
�s�������̌p���v���Ɋւ��Ắu�y���݁v��u��сv�Ƃ����v�f���ł��d�v���낤�Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�{���ł́A���R�ی앪��̎s�������̒����p���v���Ƃ��āA�u���ꊴ�o�v�u���ʂ̖ړI��S�v�u�����ȗ���ł̗Ջ@���ςȖ������S�v�u�Ƒn�I�Ȏ��g�ݎ�@�v�u�L���v�̂T���������Ă��܂��B
�u���ʂ̖ړI��S�v�̂Ȃ��Ɂu�y���݁v�̗v�f���܈ӂ��Ă���悤�ł����A�����g�͂��ꂱ�����o���_���Ǝv���Ă��܂��B
���̈Ӗ��ŃC���C�`�̃R�����B���B�A���e�B�͎����ɕx��ł��܂��B
�����ЂƂ̃T�u�V�X�e���X�́A�E�s��o�ς̐���Ƃ��čŋߏ������c�_����n�߂Ă��܂����A�s���������x�����{�T�O�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����Ƃ̂Ȃ���A���邢�͌o�σp���_�C���̓]���Ǝs�������̊W�͑傫�ȉۑ�ł��B
���͍����̓��{�̂m�o�n���܂��s��o�ς̃T�u�V�X�e���ɂȂ��Ă���悤�ŁA��a�����傫���̂ł����A�Z�������Ƃ͈Ⴄ�Ƃ��Ă��A���̗��r�_�̓T�u�V�V�e���X�o�ςɂ������ׂ����Ǝv���Ă��܂��B
�T�u�V�X�e������T�u�V�X�e���X�ցA�ł��B
�������������p�����������ĂA�Љ�̃��t���[�~���O�̐땺�ɂȂ��͂��ł��B
���V����ɂ́A���Ђ������������ł̖���N�����͂��肢�������Ǝv���܂��B
���m�_�������ƂɂȂ��Ă���̂ŁA������ȋC�z�͂���܂����A�ǂ�ł݂�ƂƂĂ��킩��₷���ł��B
�s�������Ɏ��g�܂�Ă�����͂��Ђǂ����B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u�Ȃ��A�Ј��P�O�l�ł������肠���Ȃ��̂��H�v�i���o�g�b�v���[�_�[�ҁ@���oBP�Ё@1400�~�j
�u�C�z��~���[�v�̐�ƃ��[�J�[�A�R�~�[��������̏��{�R�В��́A
���̃z�[���y�[�W�ł͂����ς��u���ҁ[�Q�[���v�œo�ꂵ�܂����A�����h������o�c�҂̂���l�ł��B
������Ђɉ��f�킹�Ă�����Ă��܂����A�s�����тɐV��������������܂��B
��N���炢����e���r�ł�����Ɏ�肠�����Ă���̂ŁA���{�R�����R�~�[�̂��Ƃ������m�̕��������Ǝv���܂����A
�R�~�[�́u�C�z��~���[�v�͎������̎���ɂ�������܂��B
��Ԑg�߂Ȃ̂́A�`�s�l�̉�ʂ̏゠����ɂ����Ă���A�����ȃ~���[�ł��B
��s�@�ɏ��Ɠ���̉ו�����ɂ��R�~�[�̃~���[���t���Ă��܂��B
�R�~�[�͏������Ȃ���A���E�����щ��~���[�������Ă��鐢�E��ƂȂ̂ł��B
���̃R�~�[����ɂ��Ă���̂��A�u�R�~���j�P�[�V�����v�ł��B
�{���̑тɂ�������Ă��܂����A�u�����ȉ�Ђ������S���́A�Ƃ����̂͂܂������̌���v�Ƃ����̂����{�R����̌o�c�N�w�ł��B
���̓N�w�̏�ɁA�R�~�[�ł͎��ɂ��܂��܂Ȃ��Ƃ��s�Ȃ��Ă��܂��B
�{���ɂ́A���̎��g�݂Ƃ������瓾�����H�m����������Љ��Ă��܂��B
���{�R����́u���t�v�ɂ������l�ł��B
���s��ɂ͈����ɂȂ�����܂���B
���Ƃ��A�b�r�i�ڋq�����j�Ƃ������t������܂����A���{�R����́u�b�r��Njy���Ă�����R�~�[�ׂ͒�Ă����v�Ƃ����܂��B
�ł͉���Njy���Ă����̂��B
�R�~�[���Nj����Ă����̂͂t�r�A���[�U�[�̖����ł����B
�����ɂ́u����v�ł̑�ꎟ�����ŗD�悷�鏬�{�R����̏��ς�����܂��B
���{�R����͂܂��u����v���d�����Ă��܂��B
�ڂ����͖{����ǂ�łق����̂ł����A�ŋߗ��s�肾�����u�i���e�B�u�}�l�W�����g�v�𑁂�������H���Ă��܂��B
������{�R����́u�i���e�B�u�v�ȂǂƂ������t���ӎ����Ă����킯�ł͂Ȃ��A
�R�~���j�P�[�V�������d�������o�c���H�̒����琶�܂�Ă����̂��A�R�~�[�̕���d���o�c�Ȃ̂ł��B
�{���ɂ��o�Ă��܂����A�����K�V���͂悭�u�����͐l������Ă����Ђł��v�ƌ����Ă��������ł����A
���{�R������u�R�~�[�͕��������Ă����Ђł��v�ƌ����Ă��܂��B
���������R�~�[�̕���͂���10���z���Ă��܂��B
�R�~�[�̃z�[���y�[�W�ɂ��f�ڂ���Ă��܂��̂ŁA���Ђ��ǂ݉������B
���Ȃ݂ɁA�R�~�[�̕���̎�l���͎Ј���l�ЂƂ�ł��B
�����ɏ��{�R����̐l�Ԋς��ے�����Ă��܂��B
�{���́A�����������{�R����̌o�c�N�w�̎��H�̏�ł���R�~�[�̌o�c�̎��ۂ���̓I�ɏЉ�Ă��܂����A
���{�R����̌o�c�P���R�����ŏЉ��Ă��܂��B
���Ƃ̐l�ɂ��ƂĂ��w�Ԃ��Ƃ̑����{�ł��B
�����ƊW�҂����ł͂Ȃ��A�m�o�n��s���̐l�ɂ����Гǂ�łق����{�ł��B
���{�R���g�������Ă���U�ł́u���Ƃ����v��ǂނ����ł��l���������邱�Ƃ���������܂��B
�����߂̂P���ł��B
�R�����Y���X�ōw��
���u�אl�̎���|�L���Љ�̂�����v�i���^��@�O�܊ف@1500�~�j
�u�אl�Ղ�v�Ƃ������t�������Ƃ�����ł��傤���B
10�N�قǑO�A�p���Ŏn�܂����A�ߗׂɏZ�ސl�������C�y�ɐH�������Ȃ���A�𗬂���W�܂�ł��B
�����A�p�[�g�ɏZ�ޘV�l�̌ǓƎ���1���������u����Ă������Ƃɋ^�����������҂��Z�l�ɌĂт����ďW�܂���������̂��ŏ��ƌ����Ă��܂��B
���̌�A�t�����X�S�y�ɁA�����ă��[���b�p�A����ɐ��E���ւƑ傫�ȍL������݂��Ă��܂��B
���̗אl�Ղ���A���{�����ɍL���Ă��Ă��邨��l���A�{���̒��҂̈������ł��B
�������́A���̃R�[�i�[�ł��悭�Љ���Ă��������Ă����Ƃł����A
�����ɃT�����[�Ƃ����������Ռݏ���̉�Ђ̎В��ł�����܂��B
�������́A�����́u�����Љ�v�Ƃ������t�Ɉ٘_�������Ă��܂��B
�����������Ă��܂����A�Љ�́u�����v�ł��낤�͂�������܂���B
�������A�u�������v���铮�����L�����Ă���͔̂ے�ł��܂���B
�ݏ���Ƃ����������̎d���́A�܂��ɂ��������u�������v�̓����ɍR�������ł���A�������Ղ́u���v���ނ��d���ł�����̂ł��B
�������́A�ݏ���Ƃ����d�g�݂��g���āA���̋ߗׂ̏W�܂���L����Ƌ��ɁA�����g�ł����N��������̗אl�Ղ���J�Â��Ă��܂��B
��������������ʂ��āA�������͂��̎Љ��{���́u�L���Љ�v�ɂ��Ă������Ƃ��Ă���̂ł��B
�������͂܂����t�Â���̖���ł��B
�{���̃^�C�g���́u�אl�̎���v�́A�܂��ɂ��ꂩ��̎�����w���������L���b�`�R�s�[�ł��B
�����Łu�אl�v�Ə����Ă��܂����A�{���ł͈������́u�ƂȂ�тƁv�Ƃ��\�����Ă��܂��B
���s��ɂ܂łȂ����u�����Љ�v�͎����t�ł�������܂��A�u�אl�̎���v�͐����ē�����n�o���錾�t�ł��B
����ɂ�����u�ƂȂ�тƁv�ƕ\������ƁA�ق̂ڂ̂��������������������܂��B
�������́A���ꂩ��n�܂�̂́u�L���Љ�v�ł���A�u�אl�̎���v���Ƃ����܂��B
�����Ė{���ŁA�ƂȂ�тƂ̌������A�t�����������킩��₷�������Ă��܂��B
�������A�אl�Ղ�̊J�Â̂��߂̃q���g����������o�Ă��܂��B
�������������Ă���悤�ɁA�{���́u�ƂȂ�тƁv�ƒ��ǂ���炵�A�K���ɐ����邽�߂̖{�Ȃ̂ł��B
�����ɗ���Ă���̂́u���������́A�l�ނ̖{�\�ł���v�Ƃ����l�����ł��B
���܂��ܖ{���̏o�ł̒��O�ɓ��k�֓���k�Ђ��������܂������A�������͂����莆�ŏ����Ă��܂����B
�{���ɓ��{�j��ň��Ƃ�������ߎS�ȍЊQ�ł����B
�ł��A�킽���́A���̑�n�k�ɂ���ē��{�Ɂu�אl�̎���v���Ăэ��܂�邩������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B
���������v���܂��B
�������Ă������߂ɂ��A�����̐l�����ɂ��ǂ݂������������Ǝv���܂��B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u���{���܂�́u���`�_�v�v�i��{���@���Ώ��X�@2310�~�j
���a�̖��Ɏ��g��ł����{�����v���Ԃ�ɐV�����o�ł���܂����B
�����ɂ́u���`�_�v�Ƃ���܂����A�������s�̃T���f���́u���`�_�v�Ƃ́A�ꖡ����āA���a�ւ̋����v��������܂��B
��{����́A����܂ł̐��������a�_�E���@�_�̏W�听�ł�����܂��B
��{����́A���x�����Ō�̒���ɂȂ邩������Ȃ��Ə����Ă��܂����B
����́u�T���f���u���`�_�v�Ɍ����Ă�����́v�ƂȂ��Ă��܂��B
�����Ɏ�����Ă���悤�ɁA��{����͍ŋ߂̃T���f���u�[���Ɋ뜜�̔O�������Ă��܂��B
�{���̂͂������ɂ́A����������Ă��܂��B
�T���f���E�u�[���Ɋւ��Ď����悸�v�������Ƃ́A���݂̓��{�̎�҂��܂���������̎v�z���u���Ёv�Ƃ��Ď���A���́u�����Ƃ�����v���s���Ă��܂��̂��Ƃ������Ƃł��B
�u���O�ł������܂������A��{����̓R�~���j�e�B���ӎ����߂���T���f���̎咣�ɂ͎^�����Ă��܂���B
�W�c�ɑ���A�т̐Ӗ����������邱�Ƃ��A�푈�╽�a�̖��Ɋւ��ẮA�����S�ƌ��т��A����ɂ͒������Ƃ����т��Ƃ����̂ł��B
�܂�A�T���f���̐��`�_�́A��҂̔�������ʂ��ē��{�S�̂̔�����������ɑ��i����̂ł͂Ȃ����A�Ɗ뜜���Ă��܂��B
���́A�R�~���j�e�B����Ղɔ��z���Ă���̂ł����A�������ɃT���f���̋c�_�ɂ͂��̊댯���������Ă��܂����B
���������Z���I�Ɋ�����̂ł��B
�������A��{����́A�ᔻ�������Ă���킯�ł͂���܂���B
��{����́A�u���{�����͂��̓��{�����̐푈�̌���ʂ��āA�푈�ƕ��a�̖������܂ސV�������`�_���N���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƍl���Ă���̂ł��B
���̎p����10������A��{����̐��͓I�Ȏ��M�����̊�𐬂����̂ł��B
�{���͂Q���\���ł��B
�O���́u�l�Ԃ̑�������ѐl���T�O�̕��Չ��v�ł��B
�����ł́A���{�����̐��́u���o�v�����߂����`�_�ƕ��a�_��������Ă��܂��B
�{���̋c�_�̏o���_�́A���̓��{�����̐��́u���o�v�ł��B
�㔼�́u�u�v�V�v���͂̏��łƓ��{�l�v�ŁA���{�l���Ăю���푈���s���悤�ɂȂ��Ă��܂���������Ȃ��Ƃ����뜜������Ă��܂��B
��������A�Ǝ��̐�{���_�Ɋ�Â��Ă��܂����A�����ēƑP�I�ł͂���܂���B
�Ƃ���ŁA��{���d������u���{�����̐��̊��o�v�Ƃ͂Ȃ�ł��傤���B
�ނ͂��̊��o�Ɂu���S�X�v�Ƃ��Ắu���t�v��^���Ȃ�������Ȃ��ƌ����̂ł��B
�ނ̂��̐��N�̒��슈���́A�܂��ɂ��̂��߂ɂ������悤�Ɏv���܂��B
�{���͂���܂ł̐�{����̒���̃G�b�Z���X�����߂��Ă��邱�Ƃ������āA�����ȒP�ɓǂ߂�{�ł͂���܂���B
�������A���Б����́A�Ƃ�킯�Ⴂ����ɓǂ�łق����{�ł��B
��l�œǂނƍ��܂������Ȃ̂ŁA��{�����ǂ�œǏ�������悤�Ǝv���Ă��܂������A���k�֓���k�Ђ��N�����Ă��܂������߁A���炭�͎����ł������ɂ�����܂���B
�������A�Ĉȍ~�ɁA���ЂƂ��{�����ނɂ����b�������̏���J�Â������Ǝv���Ă��܂��B
��{����Ƒ��k���Ă܂����ē����܂��B
�������A���̑O�ɁA���Б����̐l�ɖ{����ǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B
��{�������悤�ɁA�u���{�����̐��̊��o�v�͖������J���͂������Ă���̂�������܂���B
�������c�O�Ȃ���A���̊��o�����S�X�ɂȂ�Ȃ��܂܂ɁA���̂܂܂��ƎU�݂��Ă��܂������ł��B
�Ƃ�킯�܂��ɂ��܁A���̊��o�͗��j�̊�H�ɂ���悤�Ɏv���܂��B
�{����ǂ܂�ĊS���������ɂȂ������́A���Ў��ɂ��A�����������B
���肢���܂��B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u�Љ�I���ʎ��{�Ƃ��Ă̐�v�i�F��O���E��F�F�ҁ@������w�o�ʼn�@4800�~�j
�����ږ�������Ă�����Ă����m�o�n�@�l�V�����ӂ̉��̑�\�̑�F����́A
��w�����ɂ��Ă͂߂��炵���A�m����������H�̐l�ł��B
���̐������ɂ����āA���͂������܂��B
���̑�F����ƉF���S�ɂȂ��āA�܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
14�l�̐��Ƃ��A����e�[�}�ɁA�R�����Y�̑���Ɖ\���A
�����Ă��ꂩ��̎������̖ڎw���ׂ��������i�Љ�̂�����j�̕�����������Ă��܂��B
���ꂼ��̘_���ƂĂ��ʔ��������ɕx��ł��܂��B
�����{�Ȃ̂ŁA�ǂݏo���܂ł�����ƒ�R���������̂ł����A�ǂݏo������A�ƂĂ��ʔ������A�ǂ݂₷�����Ƃ��킩��܂����B
����ɏ��C���ǂ�������܂��B
�������肵�����Ȃ����̂́A�֗NJ��́u�E�_������̃_���ցv�ł��B
���̐��\�N�̓��{�̐����o�ς̂����肵���]�����ƂĂ����C���ǂ��̂ł��B
���������w�҂�����̂��Ƃ��ꂵ���Ȃ�܂����B
�܂����̎v���ƑS�������Ȃ̂ŁA���ꂵ���Ȃ���������������܂��B
�Љ�I���ʎ��{�Ƃ́A�R�����Y�̂��Ƃł��B
�F��́A�Љ�I���ʎ��{���A
�u��̍��Ȃ�������̒n��ɏZ�ނ��ׂĂ̐l�X���A�䂽���Ȍo�ϐ������c�݁A�����ꂽ������W�J���A�l�ԓI�ɖ��͂���Љ�������I�A����I�Ɉێ����邱�Ƃ��\�ɂ���悤�Ȏ��R����Љ�I���u�v
�ƒ�`���Ă��܂��B
�����āA�Љ�I���ʎ��{�́A����ɏd�v�Ȋւ����������҂̏W�܂�₻�ꂼ��̕���ɂ�����E�ƓI���ƏW�c�ɂ���āA�Ǘ��A�^�c����邱�Ƃ��K�v���ƌ����̂ł��B
�܂��ɂ��ꂪ���̂���20�N�̃e�[�}�A�u�R�����Y�̋��n�v�A�܂�u�݂�Ȃ̂��̂��݂�Ȃň�Ă�v�ł����B
�c�_�͑���ɂ킽���Ă��܂����A�e�_�l�ɋ��ʂ��Ă���̂͌����̏o�����܂��Č��Ƃ����p���ł��B
������ǂ݂₷���A�����͂�����̂ł��B
�F��̏��͂ɂÂ��A����3���\���ł��B
��P�� �����\�Ȏ����Ɨ����̎��H
��Q�� ���x�����Y���Ƃ��Ă̒E�_���v�z
��R�� �R�����Y�ɂ���̋��L
��F����́u�Z�p�ɂ�����������v�Ƒ肵�āA�����Z�p�̓`���Ƌߑ�ɂ������Ă��܂����A
�����ɐ̂̎����Z�p�Ƃ��āA�}������̉�����́u��z�v�Ƃ����z����̘b���Љ�Ă��܂��B
�����z�������Ȃ���h�ł͂Ȃ��A�z���������ł��B
�ߑ�̊Ǘ��v�z�ł͏o�Ă��Ȃ��A�����Ȕ��z�ł��B
�u�������v�Ƃ����l�Ԃ̒m�b���o�ꂵ�܂��B
�Z�p�����̂��Ƃł͂Ȃ��A�������̐�������g�D�̂�������l�����ŁA
���������Y��Ă��܂��Ă������Ƃ����낢��Ǝv���o�����Ă���܂��B
�_�҂̒��ɉ��c��������̂����O�������܂����B
��������Ɉ�x�ړ_�������������ł����A�L���Ɏc���Ă�����ł��B
�u�T�����j���v�̕ҏW������ɂ����[�������������܂����B
���c����́u�Ȃ��_�����݂��~�܂�Ȃ��̂��v���ƂĂ���̓I�ɁA�W�҂̎����܂ŏo���ď����Ă��܂��B
�͐�H�w�҂ƍ����Ȋ����ƕW�҂̋����d�c���Ǝ��͎v���Ă��܂������A���̂��Ƃ������ɕ`����Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA��F����͉͐�H�w�҂ł����A���������l�����܂��B
�܂����c����̕��͂ɂ��o�Ă��܂����A��a���������Ă�߂��͐�s�����������܂��B
���̈�l�ł���{�{���i����́u����ɂ�����͐�s���̓]���ƓƑP�v�́A���ꂾ���ł��{����ǂމ��l������C�����܂��B
�����č����Ȃ̂ŁA����ɂł��E�߂���{�ł͂Ȃ��̂ł����A���ꂩ��̎Љ�̃r�W�����������{�ł��̂ŁA�����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�����č����Ȃ̂ŁA����ɂł��E�߂���{�ł͂Ȃ��̂ł����A
���ꂩ��̎Љ�̃r�W�����������{�ł��̂ŁA�����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA��F����\�����Ă���V�����ӂ̉�ł�3��19�`20���A�M�Z��Ɛ�Ȑ�ō��̒t�����������C�x���g���J�Â��܂��B
�ē������m�点�̃R�[�i�[�ɍڂ��Ă��܂��̂ŁA�悩������Q�����Ă��������B
�����Q�����܂��B
��100�Ԗڂ̃��b�Z�[�W�i���b�Z�[�W�v���W�F�N�g�@���o�Ł@1300�~�j
���̃z�[���y�[�W�ł��Љ�����Ƃ̂���w�������ɂ��u���b�Z�[�W�v���W�F�N�g�v�̖{���������܂����B
���̖{�Â���ɂ͎����F�l�𐔖��Љ�܂������A���̂ق��ɂ����̒m�荇�������l���o�ꂵ�Ă��܂��B
���̃T�C�g�ɂ��o�ꂷ���������_�肳������͂��Ă���܂����B
�o�ꂷ��̂́A�A�X���[�g�A���y�ƁA���p�ƁA�ʐ^�ƁA����ƁA�Љ���ƁA�E�l�A�N�ƉƂȂǁA���܂��܂ȃW�������̂X�X�l�ł��B
�{������悵���̂́A���t���Ɨ\��̊w�������ł��B������w���A�E����o���o����5�l���A��w�Ō�́u�w�сv��{�Ƃ����J�^�`�ɂ��邱�Ƃ�ڎw���Ď��������̂ł��B
�����āA99�l�̐l�����ɁA�Ⴂ����Ɍ��C�𑗂��Ă�������̂ł��B
���̃v���W�F�N�g��ʂ��āA�ނ炪���ɋC�Â������ς�����̂���m�肽���C�����܂����A����͂Ƃ������A���ʂȐl���o�ꂵ�Ă��܂��̂ŁA�ʓǂ���Ǝ���̋C�����������邩������܂���B
���T��2��11����12���ɏa�J�������_�{�O�߂���Campus Plus �łX�X�������������b�Z�[�W�̓W���ƌ𗬉���\�肳��Ă��܂��B
�w�������͂������A�{���ɓo�ꂵ���l�����̈ꕔ���Q�����邻���ł��̂ŁA�悩�����炲�Q�����������B
���u���������@���[���T���g���^�[�v�i���^��
vs ���c����@���j�Ё@�㉺�e1600�~�j
�s�v�c�Ȗ{���o�ł���܂����B
�Ƃ����Ă��A�{�̑̍ق�o�ł̂�������s�v�c���Ƃ����킯�ł͂���܂���B
�{���́A�Q�l�ٍ̈˂̉������ȏW�ł��B
�Q�l�Ƃ́A���̃T�C�g�ɂ��悭�o�ꂷ����^�炳��Ɓu�o�N�]�_���\���O���C�^�[�v�����̂���@���N�w�҂̊��c����ł��B
�ǂ����s�v�c���Ƃ����A�����Ō���Ă��鐢�E�̊���ł��B
����Ă���e�[�}�͎��ɕ��L���̂ł��B
������ƌ����āA���̓��e�����ꂩ�Ƃ����A�K�����������ł͂���܂���B
�쐫�v�z��@���V��Ȃǂ̘b�ɂ́A���������̓��ꐫ�͂��邩������܂��A����Ă���Ă���悤�ȓ��e�ł͂Ȃ��A�ƂĂ��킩��₷���A���A�����ɕx�ދ����ł�����e�������̂ł��B
�Ȃɂ������Q�l�̓���̐����ɗ������b������Ă��܂��̂ŁA����Ȃ藝���ł��܂��B
�b��͖z���ɔ�ь����̂ł����A��ɂ��Q�l�̂��ꂼ��̎��ۂ̐�����������Ȃ��ł��邽�߁A�ǎ҂����R�Ɛ��E���ь������Ƃ��ł���̂ł��B
�ł����猈���ē��ʂ̐��E������Ă���킯�ł͂���܂���B
�������A�����ʂ��ēǂނƂȂɂ��ƂĂ��s�v�c�Ȑ��E���_�Ԍ�����C������̂ł��B
������������A���̉������Ȃ������̖邲�ƂɌ��킳�ꂽ�Ƃ������ƂɊW���Ă���̂�������܂���B
��C�̋����Q�l�������ɗU���āA���E�����Ȃ��甭���Ă��郁�b�Z�[�W�̋������A�ǎ҂̗�C���h������̂�������܂���B
�����������̉������Ȃ́A���Q�l�̃z�[���y�[�W�ɂ������f�ڂ���Ă��܂����B
�ł����玄�͂��̂�������ǂ�ł����̂ł����A���߂Ė{����ʓǂ��Ă݂�ƁA�s�v�c�Ȗ��͂Ɉ������܂�āA�㉺���́A�����ĕ������������̂ŕ��������ƂĂ������{�Ȃ̂ɁA�Ȃ�����C�ɓǂ�ł��܂��܂����B
�����āA�{������̊�ȃG�l���M�[���������̂ł��B
�܂�����ȏЉ�����Ă��܂��ƁA���������Ă��܂���������܂���ˁB
���݂܂���B
�{������������ƏЉ��ɂ́A���̃p���[���s�����Ă���悤�ł��B
�������܂Ƃ��ȏЉ������A�@���N�w�҂Ɖ�Ќo�c�҂̌�荇������Љ�_�Ȃ̂ł��B
�o�ŎЂ̉���ɂ��ƁA�u���{�l�̐��_���E�A�����Љ�u���{�v�̖����A��҂����̈ӎ��A����Љ�̖��_�Ȃǁv���s���荞�܂�Ă���̂ł��B
�ǂ�ł݂Ď��������v���܂��B
���܂��܂ȃe�[�}����������ƂȂ���`�Ō���Ă��܂��̂ŁA�ދ��ɐ荏�܂ꂽ�ŋ߂̑����̋c�_�Ƃ͈�������E�������邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�b��͑���ɂ킽���Ă��܂��̂ŁA�ދ�����ɂ�����܂���B
������s�v�c�Ȗ{�ŁA���܂��Љ�ł��Ȃ������̂ł����A���ɂ͂ƂĂ��ʔ��������ł��B
�C�y�ɓǂ߂܂��̂ŁA��C�ɂȂǂƎv�킸�Ɂi���͂��������܂�Ă��܂����̂ł����j�������ǂ߂A��������̎����������邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
���Ȃ݂ɁA���Q�l�̖��������͍��������Ă��܂��B
�������̃T�C�g�����Ђ������������B
�����ƕs�v�c�Ȑ��E�������邩������܂���B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�̕]����i�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v���߂������s����c�@���_�m�o�n�@800�~�j
�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v���߂������s����c�͍�N11���ɔ������܂����B
��c���Z�N�^�[�ɋ����������炵�A�����L���Ȏs���Љ�Â���ւ̗NJ������邱�Ƃ����O�������ł��B
�R�A�����o�[�̈�l�ł���c���퐶��������b�����������Ă��܂������A���͎Q�����Ă��܂���B
��{�I�Ɏ��̔��z�Ƃ͂܂���������Ă��邩��ł��B
���̖{���A���̍l���Ƃ͑傫���Ⴄ���z�ɗ����Ă��܂��B
���A�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�Ƃ����\���́A���̔��z�ɂ͂���܂���B
30�N�O�ɗ��s�����u�G�N�Z�����g�J���p�j�[�v������m���Ă���҂Ƃ��ẮA��a��������܂��B
���e�Ɋւ��ẮA���낢��Ə����������Ƃ�����܂��B
�ɂ�������炸�A���̖{�́A���݂m�o�n�������Ă���l�ɂ͎��H�I�ȃK�C�h�ɂȂ邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
���܂̂m�o�n���Ԃ����Ă���ǂ��邽�߂ɂ͂ƂĂ��L�v�ȃe�L�X�g�Ƃ����Ă������ł��傤�B
���̎s����c�̑O�g�́A�R�N�O�ɔ���������c���g�D�]��������ł����A�R�N�Ԃɂ킽��m�o�n�̎��Ԓ����₳�܂��܂Ȏ��_����̋c�_�܂��Ă���ꂽ�]�������ɂ��āA���ꂩ��̔�c���Z�N�^�[�̂������������Ă��܂��B
�ł�����P�ɓ��ōl���������̂��̂ł͂Ȃ��A�̌��m���܂߂Ă̕]����Ȃ̂ł��B
�]����́u�s�����v�u�Љ�ϊv���v�u�g�D���萫�v�𒌂ɂ��āA���ꂼ��ɋ�̓I�ȕ]�����X�g����������Ă��܂��B
���Ȑf�f���X�g��33���ڂ������Ă��܂��B
����������N�u�]���v�Ɏ��g��ł����c������̒m������������̂ł��B
����Ɂu�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v���߂������߂̎��Ȑf�f���X�g�v�Ƃ���悤�ɁA���ۂɂm�o�n�����Ɏ��g��ł���l�̎��Ȋm�F��Ƃ̒ł�����܂��B
�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�錾�c�̂̌Ăт������s���Ă��܂��B
���Ȃ݂ɁA�{���͈ȑO�����ŏЉ���u�G�N�Z�����g�m�o�n�Ƃ͉����v�̑��҂ł��B
���������]����̍쐬�Ɋւ�����R�l�̐l���A�R�̕]�����Ɋւ��āA���ꂼ��̎v��������Ă��܂��B
�܂��Ō�ɂ͎���̑g�D�����Ȑf�f���郊�X�g���Ă��˂��ɉ������Ă��܂��̂ŁA���ۂɂm�o�n�g�D�Ɋւ���Ă���l�͎��ȕ]�������Ƃ����Ǝv���܂��B
�����ʂ��Ă��ꂩ��̉ۑ肪�����ł���͂��ł��B
�ǂɂԂ����Ă���m�o�n�W�҂̊F�����m�o�n�W�����Ă��������Ƃ����F����͂��ǂ݂ɂȂ�Ƃ����Ǝv���܂��B
�Ə����Ȃ���A�ȉ��͎֑��ł��B
�{���̏Љ�Ƃ͂�����ƈႤ�̂ŁA��قljɂȐl�����ǂ�ł��������B
�@
�{���͂ǂ������̔��z�ƈႤ�����������������Ă����܂��B
�����o���Ƃ��肪�Ȃ��̂ł����A�{���Ō���Ă���u�s���Љ�v�̃C���[�W���܂��͞B���Ȃ��Ƃł��B
�́A�c������̌Ăт����Łu�s���Љ����v�Ƃ����̂��������̂ł����A�����ł́u�s���Љ�v�͎Љ�̃T�u�V�X�e���Ƃ��Ắu�s���Љ�v�ł����B
�����o�[���قƂ�Ǒ�w��������������d�����Ȃ�������������܂���B
�����͂��ꂪ�嗬�ł������A���͎Љ�̂��̂̕ω��ɋ���������܂����B
�m�o�n��s�������́A�Љ�̂��̂����t���[�����Ă����Ƃ����̂����̔��z�ł��B
�t���[���̑g�ݑւ������ł͂Ȃ��A���R�A�Љ�\���������ς��܂��B
���̃T�C�g�̊�ł���A�g�D�N�_����l�N�_�ւ̓]����E�ݕ��u�����N����̂��낤�Ǝv���Ă��܂��B
�����������_�ł́A�u���l�ρv����ɂȂ�܂��B
�܂肢�ܕK�v�Ȃ̂́A��Ƃ̐��E��������A�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�ł͂Ȃ��u�r�W���i���[�m�o�n�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�r�W�������Ȃ���Ε]���͂ł��܂��A�ϊv���ł��܂���B
�܂�s���Љ�̃r�W�������ƂĂ��d�v���Ƃ������Ƃł��B
�u�g�D���萫�v�Ƃ����g�D�_�ւ̈�a��������܂��B
������Љ�̂�����Ɛ[���ւ���Ă��܂��B
�Ƃ����悤�ɁA�܂����낢��Ǝ��̐��E�ςƂ͂������Ƃ��낪����킯�ł��B
�Ȃɂ��E�߂Ă���̂��A�������Ă���̂��A��₱�����ł����A�E�߂Ă͂���̂ł��B
�����A���ЂƂ������������_�������ēǂ�ł��炦��Ɗ������Ƃ��������̘b�ł��B
���̐�̘b�ɋ����̂�����́A���Ж{����ǂƌ�œ����ɗV�тɗ��Ă��������B
���Ј��݂�Ȃ��₳�����Ȃ����i�n糍K�`�@���o�Ł@1400�~�j
���N�ŏ��̖{�̏Љ�͊�ƊW�̖{�ł��B
���������̗F�l�̒��҂ł͂Ȃ��A�F�l�����ҏW�����{�ł��B
�u�Ј��݂�Ȃ��₳�����Ȃ����v�B�ҏW��S�������F�l�͓�����v����ł��B
�����̉��ɕ��肪����܂��B
�u�Ⴊ���҂����Ђ��Ă���ĕς�������Ɓv�B
�u���Ђ��āv�ł͂Ȃ��u���Ђ��Ă���āv�Ƃ����Ƃ���ɁA�{���̃��b�Z�[�W�������܂��B
���҂̓A�C�G�X�G�t�l�b�g�O���[�v��\�̓n糍K�`����ł��B
�c�O�Ȃ��玄�͖ʎ�������܂���B
���̖{�͓����������悩������Ǝ����Ă��Ă���܂����B
����Ɏ䂩��ēǂ܂��Ă��炢�܂����B
�ƂĂ������ł��܂��B
����������c�����I�Ɍ����A�������g��ł���R���P�A�̗��O�ɂ��Ȃ����Ă��܂����A���̊�ƌo�c�ςɂ���v���܂��B
���҂́A�u��ЂƂ����̂͒P�ɓ����ꏊ�ł͂Ȃ��A�������ׂĂ̐l�̐��������A��肪������ޏꏊ���v�ƍl���Ă��܂��B�����āA�u��������������Ђ��A�Ј������̖��̎����ɖ𗧂��Ă���邱�Ƃ́A�����̊�тł��v�Ɩ������܂��B
���̗F�l�ɂ��A���܂��܂Ȃ������ŏႪ���҂̓�����Â���Ɏ��g��ł���l�����Ȃ�����܂���B
�����������̐l�͋�킵�Ă��܂��B
���̍ő�̗��R�́A���̌o�ς�Љ�̂�����ɋN�����Ă���悤�Ɏv���܂��B
���҂̓n糂���́A���������Ă��܂��B
���n�������Љ�̓����͑��l�����i�ނ��Ƃł����A���̎Љ�Ől�X���K������������悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�َ��Ȃ��̂ɑ���Ό����Ȃ����A�Ƃ��ɎЉ�����郁���o�[�Ƃ��ĔF�ߍ������Ƃ��s���ł��B
����͌��ǁA���{�̐̂̃X�^�C���Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B�����Z�܂��̐l�X���A�������������Ƃ�������������ɏ��������āA����I�ɏݖ��□�X��Z�ʂ������B�q�ǂ��̖ʓ|�͒����̑�l�����݂�ȂŌ���悤�ȁA�����������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���B
���̖ڎw���Ă��鐶�����ł���A�R���P�A�̗��O�ł��B
����ɂ��������܂��B
���܂̓��{�́A�ꉭ�����S�����i��ł��܂��B���S�ɂȂ����u�ԂɁA�l�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������Ȃ��Ȃ�܂��B���S�ɂȂ邱�Ƃ́A�����Ď�������l�Ƃ̂Ȃ�������ۂ��邱�Ƃł��B����́A�l�Ԃ��{�������Ă���אl�ւ̈������ۂ��邱�Ƃł��B�l�Ԃ��Љ�Ő����邽�߂̃x�[�X�͗אl�����Ǝ��͎v���̂ł����A��������ۂ���̂ł�����A�₪�Ă͐S���a��ł��܂��܂��B
�����Љ����Ƃ��A�Ǒ��Ƃ��A���ӔC�Ȍ��t������Ă���l�����ɓǂ܂������ł��B
���������Ă���ƁA����͊�ƌo�c�̏��ł͂Ȃ��A�������_��Љ�_�̂悤�Ȍ����^�����˂܂��A�{���͌o�c���Ȃ̂ł��B
���������M���Ɋ�Â��Ċ�ƌo�c�Ɏ��g��ł����n糂���̊�Ƃ́A���̕s�����ɂ����C�Ő������Ă���̂ł��B
���ꂩ��̊�ƌo�c�̐^�����A�����Ɏ�������Ă���悤�Ɏv���܂��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���{�ł��̂ŁA��Ƃ̐l�����ɂ����Гǂ�łق����Ǝv���܂��B
�R�����Y���X�ōw��
�������Ƃɏ��T�̖@���i�Ï��G�b�{�ʓc�r�����@���{�o�ϐV���o�ŎЁ@893�~�j
�j�`�d�̌o�c���t�H�[�����S�V���̌Ï�����̖{���o�ł���܂����B
�Ï�����Ɋւ��ẮA���x�����̃T�C�g�̏T�ԕł��Љ�Ă��܂��B
���Ƃяo���āA����̎u���������ׂ��A�m����������Ђ�ݗ����A�V���Ȃ�C�m�x�[�V�����Ɏ��g��ł���l�ł��B
�{���̃e�[�}�́A���K�͂̏����ȉ�Ђ����K�͂̑傫�ȉ�Ђ��āA���ƂW�����Ă������߂̍l�����ł��B
������Љ��Ă���̂ŁA�ƂĂ������͂�����܂��B
�T�̖@���͂��̒ʂ�ł��B
�i�P�j�N�����u�������v�ƌ������Ƃ����s����
�i�Q�j�g�̏����ڕW���f����
�i�R�j�����݂ɕς���
�i�S�j�ϐl���d������
�i�T�j�T�����C�����[�_�[�ɂ���
�����ɒʒꂷ��̂́A�u��݂͋��݂ɂȂ�v�Ƃ������z�ł��B
���������v���������t�]�̔��z���ł���Ƃ���ɁA���邢�͂���������Ȃ��Ƃ���ɂ����A�u�X���[�������b�g�v������Ƃ����̂ł��B
�X���[�������b�g�Ƃ������t�҂͉��g���Ă��܂����A���ʎg���Ă���X���[�������b�g�̔��z�ɗ��܂炸�A�����ɂ��t�]�̔��z������悤�Ɋ����܂��B
���Ƃ��A��R�̖@���̂Ȃ��ɁA�u���o���җL���̖@���v���o�Ă��܂��B
�u�o���҂͌o������w�ԁA���o���҂͗��j����w�ԁv�B�����炱���A���͖��o���҂قǑ����̌o���i���҂̌o�����܂߂Ăł��j����w�ׂ�͂����Ƃ����̂ł��B
��Ƃ̌o�c�����͓����ɂ��邾���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�ڋq���o�c�����ɂ���Ƃ����̂��������z�ł��B
�܂�K�͂̑傫����Ƃ̌o�c������m�I�������邽�߂ɂ́A�Љ�S�̂�����ɂ����āA���邢�͎��Ԏ�������Ĕ��z��������Ƃ����킯�ł��B
�ƂĂ��[���ł��܂��B
�{���͌o�c�_�ł���Ɠ����ɁA�l�ɂƂ��Ă̎d���ւ̎��g�ݕ��Ƃ��ēǂ�ł������ɕx��ł��܂��B
���Ƃ��A����Ȃ����肪����܂��B
�����̐l�͊w�Z�𑲋Ƃ���ƎЉ�l�ɂȂ邪�A���̑����́u�Љ�l�ɂȂ�v�̂ł͂Ȃ��A����̊�Ƃ̏]�ƈ��ɂȂ�P�[�X�������B�i�����j�w�Z�𑲋Ƃ������_�ɂ����铪�̒��͐^�����ȃL�����p�X�ł���A�F�X�Ȃ��̂�`�����͂��ł���B�������A��Ƃɓ��Ђ���ƕ`�����̂ɂ͐�������B
�S�������ł��B
���������u��Ɛl�v���W�܂��Ă���g�D�́A���ꂩ��̕ω��̎���ɂ͎c��Ȃ���������܂���B
�Ï�����̐l���������b��144�łɏo�Ă��܂��B
���̓��e�͂��Ж{����ǂ�ł��������B
�ƂĂ��ǂ݂₷���A�����ɕx��ł�����H�I�Ȗ{�ł��̂ŁA�ʔ����d�����������Ǝv���Ă���l�ɂ��E�߂��܂��B
���P�S�O���łԂ₭�N�w�i���^��@���o�o�Ł@�T�O�T�~�j
���E��₳�����N�w�̖{���o�ł���܂����B
���҂͈��^�炳��ł��B
�������́u�P�S�O���Ƃ͂������c�C�b�^�[���ӎ����Ă��܂����A���͓N�w��m��̂ɍœK�Ȏ������v�ƌ����܂��B
�{���́A���̂P�S�O������{�ɂ����A�Ԃ₫�I�ȑΘb�`�����Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�ƂĂ��͂���₷���A���炷��Ɠǂ�ł����܂��B
���������ɖ{�Ƃ�������ꂽ���ʂɂ�������炸�A�Í������̓N�w�҂��R�V�l�A����ɐ��E�̏@���A���{�̋ߑ�v�z���Ȃǂ��P�X�l���o�ꂵ�܂��B
���������l�������A���낢��ƂԂ₢�Ă����̂ł��B
�������͂�����̍H�v�ߍ���ł��܂��B
�]���̓N�w���发�Ƃ͈Ⴂ�A����̎�����`����͂��߂�̂ł��B
�ŏ��ɓo�ꂷ��̂̓L���P�S�[���ł��B
�܂茻��̓N�w�҂���n�܂��ČÑ�̓N�w�҂ւƑk���čs���X�^�C���Ȃ̂ł��B
�u����̐g�߂Ȗ�肩��N�w�ɐG��āA���̂������R�ɍ����I�ȃe�[�}�ɂ��Ċw�Ԃ��Ƃ��ł���v�悤�ɂ����̂ł��B
�����ɂ��������炵���X�^�C���ł��B
�Ԃ₢�Ă���̂́A�N�i�e�c�j����Ɗw�i�}�i�u�j����ł��B
�Q�l�̃��Y�~�J���ȂԂ₫�ɂ������Ă���ƁA���R�ɓN�w���܂ȂׂĂ��܂��Ƃ����킯�ł��B
�������l�ɂ���Ă͕�����Ȃ���������܂���B
�������A�N�w�̑傫�ȗ�����Ղ��邱�Ƃɂ͑傫�ȈӖ�������܂��B
�傫�ȗ���̒��ŁA���܂��܂ȍl���𑊑ΓI�ɑ����Ă������Ƃ́A���E���L���Ă����͂��ł��B
�N�i�e�c�j����́A�u�N�w��m�邱�ƂŁA���l���͐����₷���Ȃ�܂��v�Ɩ{���̖`���łԂ₢�Ă��܂����A���������ł��B
�C�y�Ȗ{�ł��̂ŁA�C�y�ɂ��ǂ݂��������B
�R�����Y���X
���u�p���ƃy���[�䗘�F�Ɓu�����Ёv�̓����v�i����䍲�q�@�u�k�Ё@2400�~�j
���N�͍䗘�F���a140�N�ɓ�����܂��B
�䗘�F�Ƃ����Ă��A�ŋ߂͒m��Ȃ��l��������������܂���B
�����吳���ɓ��{�̗ǐS�Ƃ������ׂ����݂������l�����́A���܁A�}���ɖY�������܂��B
�������������A�䗘�F�Ɋւ��ẮA�K���H���ƂƂ��Ɂu�����V���v��n�������Љ�^���ƂƂ��A���{���Y�}�̏���ψ������Ƃ��������Ƃ��炢�����m��܂���ł����B
����䍲�q���A���̍䗘�F���A�����ɑh�点�Ă��ꂽ�A���ꂪ�{���ł��B
�䗘�F�����ł͂���܂���B
���{���ǂ�����������A�܂��K��������܂��Ă��Ȃ����������㔼����吳�����A���܂��܂Ȑl�������A�V�����\��������āA�{���ɂ͓o�ꂵ�܂��B
���Ƃ��A�Ėڟ��ł��B
�䗘�F�Ɵ��͒��ډ�@��͂Ȃ������悤�ł����A��̎����L�̖��O�́u�i�c���v�ŁA���ꂪ�v��ʎ������N�����̂ł����A����ɑ�����̑Ή��͎��ɖʔ����A���̟��Ίς͈�ς��܂����B
���₳��̍�i�ɂ́A���������G�s�\�[�h�������L�x�ŁA���ꂪ�傫�Ȗ��͂̈�Ȃ̂ł����A�{���͂��������b������ɂ���̂ł��B
���̂������ŁA�����̎��オ�C�L�C�L�Ɗ������܂��B
�䗘�F�Ɣ��s�Y���̘b����������������܂��B
���ɂ́A���܂��������Ƃ�������̂悤�Ɋ����܂��B �l�Ԃ����܂����B
���₳��䗘�F�������ƕ������Ƃ��ɂ́A�Ȃ��䗘�F�Ȃ̂��Ǝv���܂������A�{����ǂނƂ����v�����̂��s�v�c�ȂقǁA����͂������₳��̐��E���̂��̂Ȃ̂ł��B
���₳��́A�{���̓��@�Ƃ��āA���Ƃ����ɂ��������Ă��܂��B
�䗘�F���K���H���Ƌ��ɓ��I�푈�ɔ����Đݗ����������Ђ̂��Ƃ́A����܂łɑ����̗��j�������グ�Ă���B����A�䂪�Љ��`�^���́u�~�̎���v��ς��������߂ɐݗ����������Ђ́A�قƂ�ǖ�������Ă���ɓ������B�����A���́u�����Ёv�Ƃ�����̋���ȃC���p�N�g�Ɏ䂫����ꂽ�B
�{���͍䗘�F�̕]�`�Ƃ��āA����܂łȂ��������ʂ�`���o�������͓I�ȁA�����ĈӋ`�����i�ł����A����ȏ�ɁA���ɂ͓��{�̗��j�̊�H��`���o�����A�D�ꂽ���j���ł���A���̓��{���鎄�����ւ̃��b�Z�[�W�̏��̂悤�Ɋ����܂����B
���₳�������������u�����Ёv�̘b���{���̒��S�ƌ����Ă�������������܂���B
�؉����]�B�����ӎO�A�V�n�ˈ�ȂǁA�o��l�������Ŗʔ����ł����A������ʒꂵ�Ă���̂́u�����Ђ̓����v�ł��B
�����̑���͓��R�A����̗���ł��B
����m�Y�́A�����i�ŁA�䗘�F�͑�Γ������ŁA�u�����Ёv�Ƃ����Ŕ��f���ē�������̎���҂��Ă����A�Ə����������ł��B
���e���Љ�������炫�肪����܂��A�{���͂��ꂩ�炳�܂��܂ȂƂ���Řb��ɂȂ�A�Љ�L������������o�Ă���ł��傤�B
�Ƃ������A�����ȍ�i�ł��B
�Ƃ������݂Ȃ���ɂ����Ж{����ǂ�ł��炢�����ł��B
�����ł����A���ɖʔ����ǂ݂₷���A�����Ƃ����Ԃɓǂ߂Ă��܂��͂��ł��B
���₳��́A�h�����a�����Ȃ���{���������グ�܂����B
�ǂ����Ă������Ă����Ȃ���Ƃ��������v�����A�{������`����Ă��������̃��b�Z�[�W�ł��B
�g����ȓǎ҂Ƃ��ẮA���₳��ɂ͂����Ƃ����Ə����Ăق����Ǝv���Ă��܂��B
�Ō�ɁA�䂪��������Ȃɓ��Ă����Ȃɏ�����Ă������t���Љ�Ă��������ł��B
�u�l��M����ΗF�A�l���^���ΓG������v
���₳��́A����͍䗘�F�̐��U�̐M���������̂ł͂Ȃ����Ə����Ă��܂��B
�Ȃ��A���m�点�̃R�[�i�[�ł��ē����Ă��܂����A�{���̏o�ŋL�O�����˂āA���₳��̍u�����������ƕ����ōs���܂��B
�����Ԃ�������Ђ��Q�����������B
�R�����Y���X�i�A�}�]���j�ōw��
���u�헪�l���_�v�i�{�c�q�q�@���{�o�ϐV���o�ŎЁ@2010�j
�R�w�@��w��w�@�����̐{�c����Ƃ͂���20�N���炢�̂��t�������ł��B
�ŏ��ɏo��������́A���{�\������́u�l�ދ���v�̕ҏW���ł����B
�Ƃ��낪������A����Ă��āA�C�M���X�ɗ��w���邱�Ƃɂ����ƌ����̂ł��B
�j���ƈ���āA�����̎v����̗ǂ��́A�����Α̌����Ă��܂����A���̎��ɂ́u�Ȃ��C�M���X�Ȃ̂��v�A���ɂ̓s���Ɨ��Ă��܂���ł����B
�\�z�ȏ�ɒ����C�M���X�Ō��������𑱂�����A��w�̐搶�ɂȂ�܂����B
�A����A�����ĂQ���̖{�i�u���{�^�������x�̍s���v�u�g�q�l�}�X�^�[�R�[�X�@�l���X�y�V�����X�g�{���u���v�j���o�ł��܂������A���̌�A�{�������Ă��Ȃ��ȂƏ����C�ɂȂ��Ă��܂����B
�Ƃ����̂́A�O���Ŗ���N����Ă����u�̌n�I�Ȕ��z�v�̑��������Гǂ݂�����������ł��B
�����̐l���Ǘ��_�́A����܂ł̊�Ƃ̘g�g�݂̒��Ō���Ă��邾���ŁA�傫�ȎЉ�ω��̗���̂Ȃ��ł́A�قƂ�LjӖ��̂Ȃ��b���肾�Ǝ��͎v���Ă��邩��ł��B
����Ȏ��ɁA�{���������ė��܂����B
�������҂��Ă������e�̖{�ł����B
���ɑ����̎����ɕx�{�ł��B
�Ȃɂ������������̂́A�����o�c�w�̐��E�ł͂Ȃ��A�o�ϊw��Љ�w�Ȃǂ̐��ʂ���荞�݂Ȃ���A���܂��܂Ȑ��x�Ƃ̂Ȃ���̂Ȃ��ŁA�l���}�l�W�����g�̗�������A�W�]���Ă���_�ł��B
�{�c����̓��[���ŁA���������Ă��܂����B
���{�̐l���̋c�_�͂��܂�ɋ����͈͂ŋc�_���Ȃ���Ă���Ƃ����̂��A�C�M���X�Ŋw��ł������̈ӌ��ł��B
�l�����l��������Ƃ̕��ɂ́A�g�D���O�̕��L�����A����Ɉӎ����Ȃ��̈���܂߂Đl�������肾�����J�j�Y�����l���Ăق����̂ł��B
�����g�́A���L�����삩��l�����Ƃ炦��ق��������Ɗy�������Ƃł����A����̕������������Ă���C�����܂��B
��������܂ł����Ɩ]��ł������Ƃł��B
�����������_�ōl����ƁA��������{�I�o�c�_�̈Ӗ����݂��Ă��܂��B
�����āA���ꂩ��̓W�]�Ɖۑ�A����ɂ͊�Ƃɂ�����l�ރ}�l�W�����g��ʂ��āA�Љ�ɂǂ��ւ���Ă����邩�������Ă���͂��ł��B
��Ƃ̎Љ�ӔC�_�i�b�r�q�j���b��ł����A���ɂƂ��ẮA�l�ރ}�l�W�����g���ǂ����g�ނ��������A��Ƃ̍ő�̂b�r�q�Ȃ̂ł��B
���̎��_���A���܂̌o�c�w�ɂ͊��S�ɔ����Ă��܂��B
�{���̖��ӎ��͂����ł��B
�l�ރ}�l�W�����g�͌o�c�헪�̈ꕔ�ł���Ɠ����ɁA�Ј��̐����ɒ������邽�߁A��Ƃ̘_�������ł͌���ł��Ȃ��ʂ��傫���A�o�c�헪�ʂ���݂�Εω����K�v�Ȃ̂ɂȂ��Ȃ����s�ł��Ȃ��B���ꂪ���݁A���{��Ƃ����ʂ��Ă����肾�낤�B
���̊ԑ���������邽�߂̑����́A��Ƃ̐l�ރ}�l�W�����g�̌`���E���H�ɉe����^����v���E���͂��I�ɒm�邱�Ƃ��ƕM�҂͍l����B
�����āA�헪�l���̕�I�t���[�����[�N���Ă��A����Ɋ�Â��āA���{�ɂ�����l�ރ}�l�W�����g�̗���ƌ���A����ɂ͓W�]�����Ă���Ă��܂��B
���̊�{���́u�������v�Ɓu�َ����v�ł��B
�u�헪�l���̕�t���[�����[�N�́A�������E�َ����i���邢�͎��ԉ��E���ى��j�Ƃ�����̑������鈳�͂���Ƃ̐l�ރ}�l�W�����g�ɂ͍�p���Ă���A���҂ɔz�����A�o�����X���Ƃ�Ȃ��玩�Ђ̐l�ރ}�l�W�����g���`���E���H���Ă������Ƃ��d�v�v���Ƃ����̂��A�{�c����̎咣�ł��B
�����āA��̓I�Ȍʐl���{����ޗ��ɂ��āA�ŋ߂̐l�ރ}�l�W�����g�̓����ԓI�ɕ]�����Ă��܂��B
���������Ƃ���J�ɓǂ�ł����ƁA����̑g�D�ɑ������u�����D�ʂ������炷�l�ރ}�l�W�����g�̕������v�������Ă���͂��ł��B
�{�c����́A�u�l�ރ}�l�W�����g�̕ω���\������͓̂���v�ƔF�߂Ȃ���A�u�l�ޗ��������i��ł���Љ�قǁA�e��Ƃ��Ǝ��̐l�ރ}�l�W�����g�{����Ƃ�₷���Ȃ�v�Ǝw�E���Ă��܂��B
�܂��ɁA�u�헪�l���v���K�v�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�O���[�o���[�[�V�����̓����ɂ͕q���łȂ�������܂��A�����K�������Ă����̂ł͂Ȃ��A�̌n�I�Ȕ��z�̂Ȃ��ŁA����̑g�D�̒u����Ă������������F�����Ȃ���A�Ǝ��̐헪�l���}�l�W�����g�̃V�X�e�����A�ЊO���������݂Ȃ���R�����Ă������Ƃ��A��Ƃ̋����D�ʂɂȂ����Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B
���e���ƂĂ��L�x�Ȃ̂ŁA���̏Љ�͊ȒP�ɂ͂ł��܂��A���ꂩ��̊�Ƃ̂�������l�����ł��傫�Ȏ����������܂��B
�����A�܂����̑�����ǂ݂����Ȃ�܂����B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u����c���܂Ƃ̂��������v�i���^��@�o�t�V���@840�~�j
�������Ղ̐��E�ŁA�V���������N�����Ă����Ɓi�T�����[�j�̌o�c�҂ł�������^�炳�A�ƂĂ��킩��₷���A�������ܒ~�̂���{���o�ł���܂����B
�^�C�g�������m�E�n�E�{�I�ȃC���[�W��^���邩������܂��A�{���͎������̐������̖{��������Ă��鏑�ł��B
�C�y�ɓǂ߂܂��̂ŁA���ЊF������ǂ�ł݂Ă��������B
�����ŏ�����Ă��邱�Ƃ̂��ׂĂɁA���͋������A����Ȃ�Ɏ����ł����H���Ă��܂��B
�u�����Љ�v������A�����������鍡�����A���{�Љ�̃������������Ă����u��c���h���v�Ƃ����ӎ����������Ȃ�������܂���v�ƁA�������͖{���𑗂��Ă��ꂽ�莆�ɏ����Ă��܂����A���ꂪ�{���������������@��������܂���B
���Ȃ݂ɁA�{���͑O�ɏЉ���u�����͕K�v�I�v�̑��҂ł����A�{����ǂނƁA�u�����Љ�v��ς��Ă������߂ɁA���ꂩ������̃V���[�Y�͑����悤�ł��B
�{���̓R���p�N�g�ł����A����܂ň�������܂��܂Ȏ��_���珑���Ă������Ƃ��A���̓I�ɕҏW����Ă܂Ƃ߂��Ă��܂��̂ŁA����܂ň������̖{��ǂ�ł����l�ɂ́A������[���h�i�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�j���Ղ���K�C�h�ɂȂ邩������܂���B
���Ė{���̓��e�ł��B
�u�킽�������́A��c�A�����Ďq���Ƃ����A�����̒��Ő����Ă��鑶�݁v�Ƃ����̂��A�������̏o���_�ł��B
�����āA�u�����ߋ��̐�c�A���������̎q���A���̑傫�ȉ̗͂���́u�������v��Y���Ă���v�Ƃ����l�����A���{�l�̐��������x���Ă����Ƃ����̂ł��B
���ꂪ���ܑ傫�����悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ɁA�������͊�@���������Ă��܂��B
���̔F���͎������L���Ă��܂��B
�]�v�Ȉꌾ�������A���̔F�����Ȃ�����A�����\���ȂǂƂ������t�͎g���ė~��������܂���B
���e����̓I�ɏЉ�����Ƃ��肪����܂��A���Ƃ��u���ȂȂ����߂̕��@�v�ȂǂƂ����͂�����܂��B
�s�V�s���̖�����߂��Ƃ����A�`�̎n�c��ɓǂ܂������Ƃ���ł��B
���Ɠ��A�܂�V�l�Ǝq�ǂ����Ȃ��A����́u�t�@�[�J���_�v�Ƃ������t�i�T�O�j���Љ��Ă��܂����A���̓���������̓��{�̎Љ�̎d�g�݂�ς��Ă����q���g���ӂ�Ɋ܂܂�Ă��܂��B
�@���w�҂̃����E�X�B���Q�h�[�́u�a�v�Ɓu���v�̕����̘b���o�Ă��܂��B
���̂悤�ɁA�{���̑O���́A�������̐������A�Љ�̂�����Ɋւ���[���c�_���A�ƂĂ��₳���������Ō���Ă��܂��B
�����Č㔼�́A����܂��āB��c�Ƃ��炷�����̂����߂��A��̓I�ɒ�Ă���Ă���̂ł��B
�]�v�ȏЉ��������A���{�̉��ꕜ�A�̒�Ă�����܂��B
�������͉�����l���鎞�ɁA�ό����n�Ȃǂł����l���Ȃ��ł����A�������͂��ꂩ��̓��{�A����ɂ͐��E�A�l�ނ̖�����n�肾���q���g������ɂ���ƍl���Ă���悤�ł��B
�܂����������ł��B
�Ō�̕��������p���Ă����܂��B
����Ӗ��ł́A�{���̑c��Ƃ͉ߋ��ɂł͂Ȃ��A�����ɂ���̂�������܂���B
��c�͎q���ƂȂ�A�q���͐�c�ƂȂ�B���ꂼ�A���̃G�R���W�[�ł��B
�傢�Ȃ鐶���̗ւ́A���邮��Ɖi���ɉ���Ă䂭�̂ł��B
�{����ǂ܂�邠�Ȃ����A ��c�ƂƂ��ɂ��炵�A�{���̈Ӗ��ōK���ɂȂ��邱�Ƃ�S������Ă��܂��B
���Ђ��ǂ݂��������B
�������̖����̂��߂ɁB
�Ȃ��A�����������Ă���R���������Гǂ�ł��������B
�R�����Y���X����̍w��
���u�����ƎЉ�ۏ�v���W���F�w���ς̓��������Ă͂Ȃ�Ȃ��I�p�[�g�R�x�i2100�~�j
����͎G���̓��W���̏Љ�ł��B
���s���ꂽ�̂�2010�N7���Ȃ̂ł����A�ł���Α����̐l�����ɂ��ǂ�łق����Ƃ����v���ŁA�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
���̃T�C�g�̏T�ԋL�^�ɂ������܂������A���N�̂R���Q�O���ɋ��ό�����̌��J�V���|�W�E��������܂����B
���ό�����̌��J�V���|�W�E���Ƃ��Ă͂R��ڂł����A����A�G���u�����ƎЉ�ۏ�v�����̋L�^����W�Ƃ��Čf�ڂ��Ă���Ă��܂��B
����̃V���|�W�E���̓��W��g��ł��ꂽ�̂��A�u�����ƎЉ�ۏ�No.1518�i�V�����{���j�v�ł��B
�V���|�W�E���̃e�[�}�́A�u���i�K�̖@�K�����Ɩ���鋤�ς̂�����\�ی��Ɩ@�E�����g���@�E�ی��@�Ƌ��ς̉ۑ�v�ł������A��N�͉��L�F���_�˂̃X�����ɐg�𓊂��Ă���100�N�ڂ��������Ƃ���A��u���ł͋��ό�����̑�\�ł�����{�ԏƌ����u���L�F�����ܖ₢��������́\���ς͂ǂ���������悢�̂��v�����b����܂����B
�{�Ԃ���̎v���������������鎦���ɕx�ލu���ł����B
�����ǂ�ł������������ł��A���Ђ��̓��W���̑��𑽂݂��̐l�ɒm���Ăق����Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA���L�F�́A�V�����@�C�c�@�[��K���W�[�ƕ���20���I�̎O���l�̈�l�Ƃ����A�m�[�x���܌��ɂ��Ȃ����l�ł����A�ŋ߂ł͂��̖��O�����m��Ȃ��l�������Ȃ��Ă��܂��܂����B
���a�^���A�n�����A���������g���^���ȂǁA���܂��܂ȎЉ�^���̐��҂ł��B
��u����̃p�l���f�B�X�J�b�V�����͉��L�F���痣��Ă��܂����c�_�ɂȂ��Ă���̂��c�O�ł����A����ł��A���̕���ւ̎v���̋������n�������u�ی��Ƌ��ς̖{���I�ȈႢ�v���킩��₷���b���Ă��܂����A�X�̈�t�̐X���F����i�S���ی���c�̘A���j�����勤�ϊ����Ɋւ��ĐS�ɋ����b������Ă��܂��B
�������@���x�̘b��������ƏЉ��Ă��܂��B
���ςƂ����Ƃ�����Ƌ����������邩������܂��A�v����Ɂu�x�������̕����v�ɍ��������d�g�݂ł���A�����҂̐��E�ɂ͂����Ƃ��葱�����d�g�݂ł��B�B
���̎d�g�݂����܊�@�ɕm���Ă���킯�ł����A����͎������̎Љ�̕���ɂȂ����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͊뜜���Ă��܂��B
���̂��Ƃ��u���O�Ȃǂʼn����������Ƃ�����܂��̂ŁA�悩������ǂ�ł��������B
�Ȃ��A���̃V���|�W�E���̂P��ځA�Q��ڂ����ꂼ����W���ɑS�����ڂ���Ă��܂��B
��P��V���|�W�E�����W�E�����ƎЉ�ۏ�P�S�U�P��
��Q��V���|�W�E�����W�E�����ƎЉ�ۏ�P�S�W�S��
�G���̓�����@�́A�o�Ō��̏{��Ђɒ������Ă��������Ă����\�ł����B���ό�����̖{�Ԃ������̐l�ɓǂ�łق����Ƃ������Ƃʼn������w�����Ă��܂��̂ŁA�����ǂ݂����Ƃ������������炲�A�����������B
�{�Ԃ��瑗���Ă��炤�悤�ɂ��܂��B
���i�Ȃǂ͑��k�����Ă��������B
���Ў���̐l�ɂ����E�߂��������B
���u�N���E�h�ʼn�Ђ��悭�����P�R�Ёv�i�����P�Y�@���b�N�e���R���@1050�~�j
�T�ԋL�^�ŏ����܂������A�e���r�ł��ꏏ�������Ƃ̂��钆�����L�x�ȑ̌������Ƃɍŋߘb��̃N���E�h�E�R���s���[�e�B���O�ɂ��āA���̌��p�𒆐S�ɂ܂Ƃ߂��{�ł��B
���ɂ͂�����������ł������A���ۂɓ������������E������Ƃ̓������Ⴊ���S�ł��̂ŁA�S�̂���l�ɂ͂킩��₷�����H�̏��ɂȂ��Ă�����̂Ǝv���܂��B
�{���̉�����Љ�Ă����܂��B
IT�ɋ��߂��Ă���̂̓r�W�l�X�ɂ����闘���p�ł����āA���̏��L���ړI�ł͂���܂���B���̓�����O�̂��Ƃ��A����܂ł͖����ɂł��Ă��܂���ł����B�����ɓo�ꂵ���̂��A�g�N���E�h�h�ł��BIT�ɓ���Y�܂���o�c�҂ɘN��ƂȂ����g�N���E�h�h�ł����A����͑��ƂɌ��肳�ꂽ�b�ł͂���܂���B�ނ���A�����E������Ƃɂ������ʂ����܂��B�{���ł́A�N���E�h���s���p���������E�������13�Ђ����グ�A���̑_���ƌ��ʂ𖾂炩�ɂ��܂��B
IT�̐��E�̓W�J�͎��ɂ͂Ȃ��Ȃ����Ă����Ȃ��قǂ̑����ł����A�Љ��傫���ς����邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�u�N���E�h�v�����t�����͂��Ȃ葁����������m���Ă��܂������A�T�O�I�ɂ͂Ƃ������A�r�W�����Ƃ��ĂȂ��Ȃ��܂������ł��Ă��܂���B
���҂̒�������́A�������̑̌�����A�N���E�h�����p����ƌ���Ɋ��C���o�Ă���Ƃ����Ă��܂��B
�r�W����������̓I�Ȏ��H����w�ق����͂₢��������܂���B
�����l���Ă�����ɂ͂ƂĂ������e�L�X�g�ɂȂ邩������܂���B
�ɂ��ނ炭�́A�����܂������s�\�ŁA�K�Ȑ��E���ł��Ȃ��̂��c�O�ł��B
�S�̂�����͂��ǂ݂ɂȂ��āA�܂����ɂ��t�B�[�h�o�b�N���Ă��������B
���u���������A�����ĂĂ����ł����H�v�i���s��@���j�u�b�N�X�@1300�~�j
���E�̂Ȃ��Љ�Â���l�b�g���[�N�ɂ��Q�����Ă��������Ă������E�h�~�l�b�g���[�N���̗������̎����{���o�ł���܂����B
������́A��t�����c�s�ɂ��钷���@�̂��Z�E�ł����A���N�A�n���Ȋ����Ɏ��g�܂�Ă��܂���
��N�H�ɊJ�Â������E�̂Ȃ��Љ�Â���l�b�g���[�N�̗����グ�̃t�H�[�����ł́A�ƂĂ������ɕx�ނ��b�����Ă��������܂����B
���̎����A���k�d�b�ŏo������l�����̘b���Љ�Ȃ���A���ꂩ��̎Љ�Ɍ����Ă̏���Ⳃ��܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
������̂��l���f���Ă��A���͂��₳�������邢�̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���A���������C�����炦�܂��B
�^�C�g�����A�ƂĂ��D�������Ă܂��B
����ɂȂɂ����A������̊o�傪�������܂��B
�����܂Ŏ�����J���ăR�~�b�g�ł���l�́A�����͂��Ȃ��ł��傤�B
���͍ŋ߁A�u���E�v��b��ɂ��邱�Ƃւ̈�a���������o���Ă��܂��B
���E�h�~�Ɋւ���{�́A�������Ȃ�ǂ݂܂������A�ǂނ̂ɂ��Ȃ�̗E�C���K�v�ł��B
���������������Ă�������u���E�������~�߂�I���q�V�̖���錾�v���A�F�l����ǂݏo�������C�����d���Ȃ肷���ēǂݐi�߂Ȃ������Ƃ����܂����B
���̓_�A�{���͓ǂނɂ�Č��C���o�Ă��܂��B
���ꂪ�ǂ�ł��A�����Ɖ����q���g����ł��傤�B
�����̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
�{���̏Љ�Ɂu�����邱�Ƃɖ����A��ꂽ�l�̐S�֓͂������A�~���̃��b�Z�[�W�v�Ƃ�������Ă��܂����A�܂��ɂ��̒ʂ�̖{�ł��B
�������̐��������l����q���g����������܂��B
������ƒ����Ȃ�܂����A�u�͂��߂Ɂv�̂Ȃ��̕��͂������v�ďЉ���Ă��炢�܂��B
�����ɁA������̎��g�݂̌��_�������邩��ł��B
���̐������ɂ��Ȃ����Ă��܂��B
�l�Ԃ́A�ЂƂ�Ő����Ă���킯�ł͂���܂���B
�u�����v�Ɓu�����ȊO�̐l�v�ƂƂ��ɐ����Ă���B
�����āA�����Ă�����܂��܂ȋ�Y�ƒ��ʂ��鎞�����������Ă���̂ł����A���̋�Y�����z�������������肷�邱�Ƃ́A�����ЂƂ�̃J�ł͓���B
�����A�����Ɗւ��̂���l�̃J����Ȃ���A���z�������������肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�܂�A�����Ǝ����ȊO�̐l���ǂ��ւ�荇�����A���݂������݂��̐l�����܂��Ƃ����邽�߂ɂǂ��ւ��̂��A���ꂱ�����l�Ԃ����܂�Ă����Ӗ��ł���A���l�ɂȂ�̂ł��B
���͑T�m�Ƃ��āA�Q�O�N�߂��u���v�����߂Ă���l�����Ƃ̑Θb���d�˂Ă��܂����B���̂Q�O�N��ʂ��Ď�������̂́A�ւ��Ƃ������̂��ƂĂ��ȎЉ�ɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ������ƁB
�ł͂ǂ���������̂��B
���͂悭�u�����Ƃ��߉���₯������Ȃ��ł����v�ƌ����܂��B
����Љ�ł́u���l�̂��ƂɌ����o���ȁv�Ƃ����������������A���߉�₫�Ƃ����̂͌����鑶�݂Ɏv��ꂪ���ł����A���͐l�Ɛl�Ƃ̊ւ��Ƃ����̂́A���߉�Ȃ��ɐ��藧���Ȃ��̂ł��B
�����āA������́A���炭�O�܂ł̓��{�͂��������Љ�����Ƃ����̂ł��B
�ߋ��ɂ͋ꂵ�݂������݂���т��K�����A���݂��ɕ�ݍ���ŋ��L���Ȃ��琶���Ă����Љ�Ƃ������̂�����������Ȃ��ł����B
���{�͂܂��ɂ���ȍ��������B
�����ł��B�����ĂÂ��܂��B
�{���l�Ԃ������Ă���͂��̂��������Љ�������Ă��܂��ƁA�l�͌ǓƂ�ʂ�z���ČǗ����Ă��܂��̂ł��B
�����Ă������@�u���v��g�߂Ɉ����Ă��܂��B
���́u���E�v�ł͂���܂���B
�Ǘ����L�����Ă��܂����Љ�̂��̂Ȃ̂ł��B
�����ς��Ă����͓̂���b�ł͂���܂���B
�܂��͎���̐�������ς��Ă������Ƃł��B
�N����ς���̂ł͂Ȃ��A�܂����炪�ς��B
�������炷�ׂĂ͎n�܂�܂�
���E�߂�1���ł��B
�R�����Y���X����w��
���u�Ўj�œǂޒ��茴���v�i���ҏW�ψ���@630�~�j
�T�ԋL�^�ɏ����܂������A����s����������N�ҏW�ψ��������A����Ō�����Q������Ђ̂����Ўj�����s���Ă���P�V�Ђ̎Ўj����A�����̋L���𒆐S�ɑ����m�푈�̂͂��߂���A�s�풼��܂ł̋L����ҏW���A�R�����g�������{�ł��B
�Ўj�ɂ͂��̉�Ђ̎p��������Ă��܂����A�����ɂ��̎���̋�C���������܂��B
�Ўj�Ɍf�ڂ��ꂽ�Ј������̑̌��L���A�ƂĂ������������Ă��܂��B
�����̐l�������A�ǂ̂悤�ȉ��l�ς������Ă��������`����Ă��܂��B
�܂��A����قǂ̎S���ł���Ȃ���A�픚�����܂߂āA����Ȍ���Љ�̒�������������ƈێ�����Ă��邱�Ƃɂ���������܂��B
�킸��100�y�[�W���x�̖{�ł����A��������̎����ƌ��C�����炦�܂��B
���I�ȃX�^�C���ł��̂ŁA�ŏ��͓���ɂ�����������܂��A�̌��҂̎�L������A���X������i�ɁA�����������荞�܂�Ă��܂��܂��B
�Y���ꂪ���Ȓ��茴���̑̌����B���Б����̐l�����ɂ�����x�A�v���N�����Ăق����Ǝv���܂��B
�T�ԋL�^�ɂ������܂������A
������Ԃ��l��������ꂽ�̂́A����قǂ̎S���ł���Ȃ���A�픚�����܂߂āA����Ȍ���Љ�̒�������������ƈێ�����Ă��邱�Ƃł��B
���������͂Ƃ������Ƃ��āA�������肵���Љ�������̂ł��B
�������A�����ł͊e�l����������Ɓu�����v���A�u��̓I�v�ɓ����Ă���̂ł��B
���̓��{�ł͉ʂ����Ăǂ��ł��傤���B
�ŋ߁A�Љ��ꂾ���Ă���Ǝv���Ă��鎄�Ƃ��ẮA�����������G�ȋC�����ł��B
�ҏW�ψ����\�̐X����Y����́A����H��ώ@�w��E�A���L���f�X�̉�ł�����܂��B
���̃u���O��T�C�g������܂��̂ŁA�悩������K�˂Ă݂Ă��������B
�u�Ўj�œǂޒ��茴���v�ҏW�ψ���ɘA������ƍw���ł��܂��B
�������܂߂�1000�~���x���Ǝv���܂��B
�ڂ����͎��̃T�C�g���������������B
http://arukime.blog118.fc2.com/blog-entry-139.html
�ҏW����̃A�h���X��
smoori@aqr.bbiq.jp
���Ï��̐X 疗y�i����䍲�q�@�H��Ɂ@3200�~�j
�Ï����Óǂ����A�G�����G�ǂ����B
����́A�����E�吳�̎��ƉƂŎЉ�ƁE�������ƂɎ��g�������P�̌��t�������ł��B
����䍲�q����̌Ï��R���N�V�����̓W����Œm��܂����B
���₳��̐��E���A�}�Ɍ����Ă����悤�ȋC�����܂����B
�{���́A���₳��̃u���O�u�Ï��̐X���L�v���x�[�X�ɁA�ҏW���Ȃ������{�ł��B
��ɂƂ��Ă݂�ƁA�{�D���̍��₳��Ȃ�ł̖͂{���Ǝ����ł��܂��B
���グ��ꂽ�{��220���B���㏇�ɕ��ׂ��Ă��܂����A�����o����ǂ�ł��邾���ł�����̗��ꂪ�����Ă���悤�ȋC�����܂��B
�w�҂Ƃ͈�����Ƃ���Ɏ��_�Ă����ƍ��₳��͏�X����Ă��܂����A�܂��ɂ��̍��₳��̎��_���������܂��B
�����ɁA���₳��̐��E���ǂ��L�����Ă��������ǂݎ��܂��B
����������A�{��ǂނ��Ƃ����E���ǂ��L���Ă������Ƃ����A�u�y�����Ǐ��̊��߁v�̂悤�ȃ��b�Z�[�W���`����Ă��܂��B
�Ƃ��������̒ʂ����A�v���̂��������{�ł��B
�͂��ƂɁA�u�Ï��W�߂���v�Ƃ����R�����i������u���O����̃��C�u�ȋL���ł��j�����Ă��܂����A�����ʓǂ��邾���ł����ɖʔ����ł��B
������ƃ}�j�A�b�N�ȌÏ��t�@���̐��E��g�߂Ɋ������܂��B
������悸�ǂ�ł���A�{���͂�����肵�����Ԃ̗���ɔC���ēǂނƁA�����ƂĂ��L���Ȏ��Ԃ��߂�����ł��傤�B
�I�ꂽ�{�̂قƂ�ǂ́A���ɂ͕��������Ƃ��Ȃ��������̂ł��B
�ɂ�������炸�A��������ʔ����ǂ߂�̂́A���₳��̐��E���ʒꂵ�Ă��邩��ł��B
���グ�Ă���{�͎��ɂ��܂��܂ŁA�G��������A����������܂��B
�����������̂�ʂ��č��₳���Ă��铖���̎Љ�ւ̖ڂ��܂����ɖʔ����̂ł��B
���₳�A�ǂ�قǖ{�������A�����吳�������Ă��邩���`����Ă��܂��B
�����ɂ͎��グ��ꂽ�{�̃J���t���ȃO���t�B�e�B������܂��B
���ɂƂ��Ă��A�ƂĂ����������������܂��B
�����̎G���Ȃǂ̃J���t�����Ƃ͂܂������Ƃ����Ă����قLjَ��ł��B
�{���̑тɂ��������Ă���܂��B
�T���g���[�w�|��܂̃m���t�B�N�V������Ƃ��A�Ï��W�ʂ��ŏo��������͓I�ȎG�������B
���̎G�����u�G�ǂ����v�ɁA�S��u���ǁv�������₳��̍K�����A�������L�ł���A�f�G�Ȗ{�ł��B
�ǂ܂Ȃ��Ă��A���ɒu���Ă��������ł��K�����`����Ă���悤�Ȗ{�ł��B
�{���D���Ȑl�ɂ͐�ɂ��E�߂ł��B
�{�̕����́A��͂���Ȃ��Ă͂����܂���B
���Ԃ�Ï��W�ɂ�������A�����l����ς��Ă��܂��悤�ȋC�����܂��B
�ł�����A���͍s���܂��B
�R�����Y���X������w���ł��܂��B
���u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�Ƃ͉����i��c���g�D�]���������@���_�m�o�n�j
�ƂĂ��ǂ��{�ł��B
�{���́A��c���g�D�]����������2�N�Ԃɂ킽��m�o�n�]����̌����̊������琶�܂ꂽ���̂ł���A�Q�������݂Ȃ��ꂼ��̎v�����������܂��B
���S�́A����Ƃ�������ƂȂ��������������Ă���5�̂m�o�n�̑�\�⎖���ǒ��ɂ����k��ł��B
�����ŁA�u�Ȃ����s���Љ�Ȃ̂��v�u�V���������v�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v���M������Ă��܂��B
���܂��܂Ȏ����Ǝ��_�Ō���Ă��܂��̂ŁA��������̎��������炦�܂��B
�Ȃɂ��������̂́A�S�̂��������肵�����ӎ��Ŋт���Ă��邱�Ƃł��B
�`���́u�͂��߂Ɂv�Ō��_�m�o�n��\�̍H�����S�̂̓W�]���A�܂������ŏ��̏͂Ō�����卸�̓c���퐶���u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�ɂ��Ă̍l���m�ɏ����Ă��܂��B
������ɂ�����̌�����������Ă̂������肵�����ӎ����������܂��B
���ꂩ��̎Љ�̂�����ɊS�̂���l�ɂ͂��E�߂̖{�ł��B
�ƌ����Ă���A���Ȃ�ᔻ�I�Ȃ��Ƃ������܂��B
�J��Ԃ��܂����A�ƂĂ������{�����炱���A�����̐l�ɖ��ӎ��������ēǂ�łق�������ł��B
�c������́A���̊������n�߂�O�ɂ��̎v�������������Ă��܂��B
���̎v���ɂ͋�������Ƃ��낪�ƂĂ�����܂����B
�������Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ���E�̊����Ȃ̂��Ɖ��ƂȂ������Ă��܂����B
�ǂ����Ⴄ���A�{���̃^�C�g�������āA����ɋC�Â��܂����B
�������^�C�g���ł͂���܂����A�����������炻���ɑ傫�ȈӖ�������̂�������܂���B
�{���̏����́u�u�G�N�Z�����g�m�o�n�v�Ƃ͉����v�A���肪�u�����s���Љ�ւ́u�Ǐz�v�����肾���v�ł��B
���ɍŏ��ɒ�R���������̂́u�����s���Љ�v�Ƃ������t�ł��B
���Ȃ�u�₳�����v�Ƃ��u�����₷���v�Ƃ������t��I�т܂��B
������Ђ����߂�_�@�ɂȂ����̂́A�b�h�����ł��B
���̖ڕW���u�₳���������₷����Ёv�ł����B
�Ƃ��낪�В��������āA�u������Ёv�����߂��܂����B
���ꂪ�A������Ђ����߂���������̗��R�̂Ȃ��̈�ł��B
�u�����v�Ƃ������t�́A���̐��E�̌��t�ł͂���܂���B
�b�h�v���W�F�N�g�ł͎��̕ҏW�Ŋ����j���[�X�����s���Ă��܂������A�ŏI���̃^�C�g���͂������u�₳�����������狭�������ցv�ł����B
����͎��̓����ւ̌��ʂ̃��b�Z�[�W�ł��������̂ł��B
�u�G�N�Z�����g�v���܂����̐��E�̌��t�ł͂���܂���B
���̌��t�ɔے�I�ɂȂ����͉̂�Ђ����߂Ă��܂��܂Ȍ���Ɋւ�肾���Ă���ł��B
��O�҂��ڐ������]������p���������Ă��܂����̂ł��B
�܂���������������������Ɠc������ɓ{��ꂻ���ł��B
�c������͖{���Łu�G�N�Z�����g�m�o�n�v�ɂ��Ē��J�ɒ�`���Ă��܂��B
����Ɉ٘_������킯�ł͂���܂���B
�H������́u�͂��߂Ɂv��ǂނƁA�m�o�n�̕]����Ƃ��āu�Љ�ϊv�v�u�s�����v�u�o�c�̈��萫�v���d�����Ă���悤�ł��B
����ɂ��٘_�͂���܂���B
�������́A���ꂼ��̈Ӗ������ł��B
���t�ɂ͈٘_�͋��߂܂��A��Ȃ̂͌��t�̊܈ӂ���������ł��B
�����s���Љ�ɂ��Ă��H������́u�L���҂����瓖���҈ӎ��������Ă��̍��̖����̂��߂ɐ�����I�сA����f����B�������������ƗL���҂Ƃ̊Ԃɋْ����̂���Љ�v�ƒ�`���Ă��܂��B
�����ł��u�����ƗL���҂Ƃ̊Ԃɋْ����v�Ƃ����������Ɉ�a����@���܂���B
������Љ�̑��������Ⴄ�̂�������܂���B
���ꂪ��a���̌����������悤�ȋC�����܂��B
�������J��Ԃ��Ζ{���͂����{�ł��B
�ł���������ł���A���̈�a���������������ɂ����Ă��������ēǂ�ł��炦��Ƃ��ꂵ���ł��B
�U�O�O�~�ł��̂ŁA����P�t���ōw���ł��܂��B
�ǂ݉����͂��Ȃ肠��܂����A���k����S�Ȃ̂œǂ݂₷���ł��B
��Ƃ̐l�ɂ����Гǂ�łق����{�ł��B
�R�����Y���X
���u���E�ł������Ђ������ȓ��{�l�v�i�֓��q���@���{�o�ϐV���o�ŕ��@1600�~�j
�Ռ��I�ȃ^�C�g���ł��B
������Ƃɋߏo�������i���a39�N�j�ɂ́u���E�ł������Ђ��D���ȓ��{�l�v�ƌ����Ă����̂ɁA
���ł͂��̏�������ɔ[���ł���ɂȂ��Ă���̂ł��B
�֓�����͒��N���{�\������Ŋ��Ă����l�����̐��Ƃł��̂ŁA
���̕ϑJ����������ƌ����ʂ��đ̌����Ă��Ă��܂��B
����ɍ֓�����́A�܂��ɂ��̃R�[�i�[�ł��Љ���u���������̂����Ёv�̒��҂ł�����A
Grate Place to Work �v���W�F�N�g����{�ɏЉ���̂��֓�����ł��B
�֓�����ɂ́A�u�]�ƈ��̎��_�v�ŁA��Ƃ̎��Ԃ��悭�����Ă���̂ł��B
�֓�����Ƃ̍ŏ��̏o��́A�����܂������ɂ������ł����A
���N�O�ɂ���ψ���ŋ��R�ɗׂ荇�킹�ɂȂ�A�܂����t���������n�܂�܂����B
������Ă��Ȃ�����20�N�̊ԁA���͊�Ƃ���ǂ�ǂ�O��Ă��܂��܂������A
�֓�����͍����O�̂�������̊�ƂƐړ_�������Ȃ���A���ƂƂ��Ă̒m�����Ă��Ă��܂��B
���̖L�x�Ȓm����Grate Place to Work �v���W�F�N�g�ł̂������肵�������ŏ����ꂽ�̂��{���Ȃ̂ł����A
���̃^�C�g�����u���E�ł������Ђ������ȓ��{�l�v���������ƂɎ��͑傫�ȃV���b�N�������܂����B
�����A��Ƃ̊O�����牽�ƂȂ������Ă������Ƃ���������ł��B
�������{���́A��������������ᔻ�I�ɏ����グ�����̂ł͂���܂���B
����Ƃ͋t�ɁA�����炱���݂�Ȃ��D���ɂȂ��Ђɂ��悤�ƍ֓�����͎v���Ă��܂��B
���������֓������N�߂Ă����g�D�𗣂�āA�g�D�Ɠ���������������ݗ������̂́A
�u���������̂����Ёv�𑝂₵�Ă��������v������Ȃ̂ł��B
�ǂ�������u���������̂����Ёv�ɂȂ邩�̏���Ⳃ��֓�����͂����Ă��܂��B
������ŋ߂̊�Ƃ̏́A�֓�����ɂ͎c�O�łȂ�Ȃ��̂ł��傤�B
���̎v�����A�{���̃^�C�g���Ɋ������܂��B
�L�x�Ȏ�ޒ������ʂ܂��āA�{���̑�2���ł́A���E�́u���������̂����Ёv�ɋ��ʂ��镶�����������Ă��܂��B
����́u�����l���K����������E�������12�̓�����v�ƌ����Ă������ł��傤�B
�ƂĂ����H�I�Ől�Ԃ��������������ł��B
������Ԉ�ۓI�������̂́A�֓����r�`�r��K�₵�����̘b�ł��B
������ƒ����Ȃ�܂����A���p�����Ă��炢�܂��B
���̃G�s�\�[�h��{���̂͂��߂ɏЉ�Ă���Ƃ���ɁA�֓�����̊�Ɗς�����v��������̂ł��B
�l�����̒S���������A��X�ɒ���������������B
����́A�u�F�����������݂ɂ������A������ɓX��I�т܂����H�v�Ƃ������̂������B
�˔�Ȏ���Ɏv�������A�ꏏ�ɖK�₵�������o�[�̒��Ɂu������l������X���Ȃ��v�Ɠ������l������B
�l�����̒S�������́u���̒ʂ�ł��B��͂�A������l������ꏊ����Ԃł��傤�B��Ђ������ł��B���Ƃ��Ήc�Ƃ̒S���҂��p�ɂɑ����Ă��܂��ƁA�ڋq�͊���������܂���B�e�����l�����Ȃ��Ɖ�ɂ������͂Ǝv���Ă���܂���B�M���ł���c�Ƃ̒S���҂����Ă����A�ǍD�ȊW���ێ��ł���̂ł��v�ƌ������B
�����܂ł��Ȃ��ł����A�������i�ɉ�����l������K���ł��B
���ȏꍇ�́A��Ђ������ɂȂ邩������܂���B
�P�Q�̓�������Q�l�܂łɏ����Ă����܂����A���ꂼ��ɋ�̓I�Ȏ���������Ȃ���A���H�I�ȃA�h�o�C�X��������Ă��܂��B
�݂Ȃ���̉�Ёi�E��j�͂������ł��傤���B�������Ă͂܂�܂����B
�@�P�@���l�ς����L�ł���l���̗p����
�@�Q�@���[�N���C�t�o�����X��O�ꂵ�Ă���
�@�R�@�_�C���N�g�ȑΘb������
�@�S�@�e�t�m��Nj�������
�@�T�@���j�[�N���ƌ��C������
�@�U�@�F�߁A���ӂ��A�̂���
�@�V�@�Ƒ��̂悤�ȉ�����������
�@�W�@�����ȓN�w���Z�����Ă���
�@�X�@�˂ɑ��҂Ɋw��ł���
�@10�@���������S������
�@11�@���l�������}����
�@12�@����܂Ȃ�����S������
�y�������������Ǝv���Ă�����͂��Ђ��ǂ݂��������B
�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
�R�����Y���X
���u�����͕K�v�I�v�i���^��@�o�t�V���@740�~�j
���u�Ŋ��̃Z�����j�[�v�i���^��@�o�g�o�������@1200�~�j
4���̃I�[�v���T�����ł��u�����͕K�v���v�ƌ����悤�ȋc�_������܂������A�ŋ߁A���܂�u�����v�����Ȃ��l�������Ă����Ƃ�������������܂����B
�������悭�����Ă݂�ƁA�����̃X�^�C���̖��ł����āA�������̂��̂�ے肵�Ă���̂ł͂Ȃ��悤�ł��B
�������͂��̖{�̒��ŁA
�u�l�ԂƂ̓z���E�t���[�l�����A�����A����������q�g�Ȃ̂ł��v
�Ə����Ă��܂����A���������v���܂��B
���������Ȃ����ƂȂǎ��ɂ͍l�����܂���B
�����ŋ߂̑��V�ɂ͈�a�����Ȃ��킯�ł͂���܂���B
�������͊������Ղ̉�Ђ̎В��ł����A�В��ɂȂ�O����u���V�v�̃e�[�}�Ɏ��g��ł��܂����B
1992�N�Ɂu�����f�U�C������@���V�Ƃ͉����v�Ƃ����Βk�W���o���Ă��܂��B
���̑Βk�̂Ȃ��ŁA�ƂĂ������ɕx�ރ��b�Z�[�W����������o���Ă��܂��B
�������V�ɊS���������_�@�ɂȂ���1���ł��B
���S�̂�����͂��Ђ��ǂ݂��������B
���V�͕s�v�ȂǂƂ����o�J�Ȕ����͂��Ȃ��Ȃ�ł��傤�B
�ƂĂ������ł��錾�t�����p�����Ă��炢�܂��B
���V�Ƃ́A�l�Ԃ̎��Ɂu�������v��^���āA���̐��ւ̗��������X���[�Y�ɍs�����ƁB
�����āA������҂������A�s���ɗh�ꓮ���⑰�̐S�Ɂu�������v��^���āA
���h���������A�߂��݂�������ƁB
�Ȃ����������҂Ƃ��āA�㔼�̂Q�s�ɂƂĂ��������܂��B
�������c�O�Ȃ��玄�̏ꍇ�́A���V�Ɋւ��鏀���������s�����Ă������߁A���������̉������c���Ă��܂��B
�����Ȃ�Ȃ��悤�ɁA�{�������������܂�邱�Ƃ����E�߂��܂��B
����������Ă���悤�ɁA�����u�s�K�v�ƍl���邱�Ƃ���߂��ق��������ł��傤�B
�N���}����u���v���s�K�ł���Ȃ�A���ɂ͖{���̊�т͐��܂�܂���B
���邭�ǂ߂�{�ł��̂ŁA���ЎႢ�l���܂߂ēǂ�ŗ~�����{�ł��B
�������ɂ́u�Ŋ��̃Z�����j�[�v�ƌ����{������܂��B
��N�o�ł���܂������B�����ǂ߂��ɂ����{�ł��B
�u�����͕K�v�I�v�ƌ����{��ǂ������ŁA����A�悤�₭�ǂނ��Ƃ��ł��܂����B
�u�������A���X�^�b�t�����������̎��b�W�v�Ƃ������肪���Ă���悤�ɁA�u������тƁv��������́u���v�̕ł��B
�{���̑тɂ́u�l���̍Ŋ��́A����Ȃɂ����ł��ӂ�Ă���v�Ə�����Ă��܂����A���Ǝ��͐藣���Ȃ��̂�������܂���B
�{���͓ǂނ̂͂���Ȃ�ɗE�C������܂����A���C�����炦�܂��B
�Ȃ��������͂��̕���̖{�������������Ă��܂��B
�u�܂���邩��v�Ƃ����t�H�g�u�b�N�����㏑�т���o���Ă��܂����A�c�u�c���o���Ă��܂��B
�������̃z�[���y�[�W�ɂ��낢��ƏЉ��Ă��܂��̂ŁA���S�̂�����̓A�N�Z�X���Ă��������B
�R�����Y���X
���u���E�������~�߂�I���q�V�̖���錾�v�i�K�Y�@�O�ȓ��@1600�~�j
����̓��q�V�Ŏ��E�h�~�����Ɏ��g��ł�������3���ڂ̖{�ł��B
����̂��Ƃ́A���̃T�C�g�ɂ��悭�o�Ă��܂����A�������t���������n�܂��Ă���6�N�قǂł��傤���B
�������̋��R���d�Ȃ��āA���̊����������₩�ɉ�������悤�ɂȂ�܂����B
��N�͖���ƈꏏ���u���E�̂Ȃ��Љ�Â���l�b�g���[�N�E�����������v�������グ�܂������A
�{���ł͂������������ɂ����y���Ă��܂��B
�����A�R���P�A�����̎��_����ꕶ����e�����Ă��炢�܂������A
�܂���N10��24���ɊJ�Â����W�܂�̋L�^���f�ڂ����Ă��炢�܂����B
����̊����́A�ŋ߂��������ߏ肷����قǂɃe���r�ŕ���Ă��܂����A
�e���r�Ȃǂ̓̕����p�^�[���ŁA����̖{���̎v���͂Ȃ��Ȃ��`����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B
�{���ɂ́A������������̖{���̎v���⊈���̎��Ԃ�������Ă��܂��B
�܂����E���l�������Ƃ̂���l�⎩���⑰�̐l�̃��b�Z�[�W����A
���������������Ă��邱�Ƃ���g�܂Ȃ�������Ȃ����Ƃɂ��C�Â�����܂��B
�u���E�v�ƌ����ƁA�������ʂ̖��ƍl�������ł����A����Ȃ��Ƃ͂���܂���B
�����ɂ͎������̐�������₢�����������b�Z�[�W���܂܂�Ă���̂ł��B
�悩�����炨�ǂ݂��������B
�����Ă����������Ă���������Ƃ��낪����A
�u���E�̂Ȃ��Љ�Â���l�b�g���[�N�v��u�R���P�A�E�l�b�g���[�N�v�ɂ��Q�����������B
��������A���Ȃǂ͈�Ȃ��A���[�����O���X�g�����̂��₩�Ȏx�������̂Ȃ���ł��B
����]�̕������Ƀ��[������������Ǝv���܂��B
�{���̖ڎ��͎��̒ʂ�ł����A��8�͂ɖ���́u�{��v�����߂��v�����o�Ă��܂��B
����̓{����A������Љ�Ă����܂��B
�i���E���������Ă���ɂ�������炸�j���̑���u�����A
���̕ی�̎�������L�ׂ��ɕ��u���Ă����s�ׂ͎E�l�߂ɂ��C�G����d�v�Ȕƍߍs�ׂƂȂ�A
�@���ᔽ�ɂȂ����Ǝv���܂��B�i�P�T�Q�Łj
���́A������������̓{��ɂق�����Ă��܂��Ă���̂ł��B
��1�́@���q�V�̐��ۂ̌��ꂩ��
��2�́@���q�V�ŏ��肠�����l����
�m1�n���d������̒E�o
�m2�n�p���[�E�n���X�����g����̒E�o
�m3�n�����ꂩ��̒E�o
�m4�n�ƒ����̒E�o
��3�́@���E���ĂȂɁH
��4�́@�ǂ�������ǂ��́H
��5�́@���E���l�����̌��҂Ƃ́u����v�̊J�Õ�
��6�́@���E�����ꏊ�ł̊����҃T�~�b�g�L�@
��7�́@�V�F���^�[�E�l�b�g���[�N�̍\�z�@
��8�́@���E�h�~�������A���܂��ɗ�������Ȃ��͉̂��́H�@
�R�����Y���X
���؍��̌o�ϔ��W�ƍݓ��؍���Ɛl�̖����i�i��T��Y�ҁ@��g���X�@3400�~�j
���ό�����̍��X���A���̋��n���Ɋւ�銈��������Ă��邱�Ƃ͂���ƂȂ����������Ă��܂����B
���N�̂͂��߂ɂ��哌������w�ł̃V���|�W�E���̂��ē������������Ă��܂������A�C�ɂȂ�Ȃ���Q���ł��܂���ł����B
���̍��X���炢���������̂��{���ł��B
���X��������M�ɎQ������Ă��܂����A���H�I�����҂̗���ŁA�{���̌��e�i�K�Œʓǂ���Ă��낢��Ƃ��ӌ����o���ꂽ�Ƃ������Ƃ��A�Ҏ҂̂��Ƃ����ɏ�����Ă��܂����B
���X����̂��������ȁA��������������Ƃ�����ڂ��S�҂ɍs���n���Ă���Ƃ����S���玄���ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�{���̕\�����̉�������A���̓ǂދC���N�����������R�ł��B
�ً��ō��ʁE�Ό��Ɠ����Ȃ���A�l��{�w�͂��A�`�����X������Ő���������Q�̍ݓ��؍���Ɛl����������B�ނ�́A�₪�āA�����n���̒��ɂ������c���E�؍��̌o�ϔ��W�ɁA�l�X�Ȍ`�Ŋ�^���Ă����B�A�C�f�B�A�A�Z�p�A�����̒A���Z�Đ��ȂǁB����͍����̊؍��o�ς̑b�Ƃ��Ȃ������A���Ԃ͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��B�{���́A���̒m��ꂴ����ؐ��W�j���A���{�E�؍��E�ݓ��̌����҂����������������̂ł���B
�ǂ��ł����A������Ƌ�������������ł��傤�B
�I�͂ł́A�ݓ��R���A���Љ�̉ۑ�ƓW�]�܂Ō���Ă��܂��B
������Ԗʔ��������̂́A�_�؋�s�̘b�ł��B
�_�؋�s�́A1982�N�ɍݓ���ƉƂ����ɂ���Đݗ����ꂽ�A�؍����̏������ԋ�s�ł��B
���̐ݗ��ɂ́A�ݓ��؍���Ɛl�����̐[���v�������߂��Ă��܂����B
�����Ă��̋�s���A24�N���2006�N�ɁA��s�؍��̋��Z���哱���Ă������j���閼��̒�����s���z�����������̂ł��B
�ǂݏo���O�ɂ́A���Ȃ�n�[�h���������A���X���ւ���Ă��Ȃ���Γǂ܂Ȃ����낤�ȂƎv���Ă����̂ł����A�ǂݏo������ƂĂ��ʔ����A�����I�Ȃ̂ł��B
��发�ł͂���܂����A�o�ς�ʂ������X�������؊W�j�ł���A�܂����ƂƂ͉����A�o�ςƂ͉������l����������h���I�Ȗ{�ł��B
�����̍ݓ��؍���Ɛl�̏Љ������܂��B
�����������ꂼ��̏Љ�L��������A���̋�J�Ə�M�Ǝu��m�邱�Ƃ��ł��܂��B
�y���C�����œǂ߂�{�ł͂���܂��A�Ǐ������Ȃ��Ȃ������{�̊�Ɛl�����ɂ��ǂ�łق����{�ł��B
�R�����Y���X
�����R�~���j�P�[�V�����i���������@���F�ف@2400�~�j
��T�̏T�ԕŏЉ��������������̍ŐV���ł��B
��������̎v�������߂�ꂽ�ӗ~��ł����A
�����ɂ���͐�������̂��ꂩ��̃R�~���j�P�[�V�����_�����̏o���_�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƁA���͏���Ɋ��҂��Ă��܂��B
����́u2050�N�Ɍ�������Ƃ̃T�X�e�i�R���헪�v�B
�V�������_������܂��B
��������́A���o�c����n�܂������R�~���j�P�[�V�����������A�]���̊�ƃR�~���j�P�[�V�����_��傫���L���Ă������낤�ƓW�]���Ă��܂��B
�{���̉���̕��͂����̂��Ƃ���肭�������Ă��܂��B
�����\�ȎЉ�`���Ɍ�������Ƃ̎�g���u�҂����Ȃ��v�̏��}���钆�ŁA
���J�����܂ޓ����I�R�~���j�P�[�V���������ւƔ��W��������R�~���j�P�[�V�������������Ԏ��Ƌ�Ԏ��ƂłƂ炦�����A
���̊����̘g�g�݂��������A���f�B�A���p��}�l�W�����g��@�����B
����ɍ���Ɍ����āA��Ƃ���̂Ƃ���T�X�e�i�r���e�B�E�R�~���j�P�[�V����(�T�X�e�i�R��)�̐헪�I�Ӌ`������B
�u���O�ɂ��������悤�ɁA�����������������̂́A�{�����P�Ȃ�L��_�ł͂Ȃ���Ƙ_��W�J���Ă��邱�Ƃł��B
���邢�͊�ƂƎЉ�Ƃ̊W�_���e�[�}�ɂ��Ă��邱�Ƃł��B
�܂����̓�����̋c�_�ɂƂǂ܂��Ă���Ƃ����C�����܂����A�V�����c�_�̒n���Ɍ����Ă̖���N�͂��܂��܂ȂƂ���Ɋ������܂��B
�ɂ��ނ炭�́A�I�͂́u���T�X�e�i�R���Ƃ��ẴR�~���j�P�[�V�����헪�v�����������@�艺���Ăق����������Ƃł��B
�u�����������f������V�X�e���ԃR�~���j�P�[�V�����ցv�A�����āu�V�X�e���ԃR�~���j�P�[�V�����̑��ݍ�p�v�ƁA������Ɗ��҂�����߂�����̂ł����A���r���[�ɂ͏����Ȃ��Ǝv�����̂��A���邢�͏�����ꂽ�̂��A��������͌y�������グ�Ă��܂��Ă��܂��B
�������~�����Ă͂����܂���B
�����́A��������̎����҂��܂��傤�B
�ڎ��͎��̒ʂ�ł����A��5�͍͂���͂�����Əڂ����\���҂Ǝ~�߂܂����B
�����Ɛ�������������l���Ă���ł��傤�B
�{���̋c�_�����ꂩ��ǂ��u�i���v���Ă������A�ƂĂ��y���݂ł��B
���̊��҂��܂߂āA��Ƃ̏��Q�d��o�c�Q�d���͂��߁A��Ƃ̂�����ɊS�������Ă���l�����ɂ����߂��܂��B
��x�A����������͂�ł̋C�y�Ȋ��R�~���j�P�[�V�����k�`���������Ŋ�悵�����Ǝv���܂��̂ŁA�S�̂�����͂��A�����������B
���� �ϗe����Љ�o�ςƊ��R�~���j�P�[�V����
��1�� ���R�~���j�P�[�V�����̍\�}
��2�� ��Ƃ̎Љ�I�R�~���j�P�[�V�����̌���Ɖۑ�
��3�� ���̌���Ɖۑ�
��4�� ���R�~���j�P�[�V�����̘g�g��
��5�� ���T�X�e�i�R���Ƃ��ẴR�~���j�P�[�V�����헪
�R�����Y���X�ōw��
���Ñネ�[�}�̃q���[�}�j�Y���i���щ�v�@�����[�@2010�j
����c��w�̏��ы������A����܂ŏ����Ă����q���[�}�j�Y���̘_�����܂Ƃ߂����܂����B
�{�̑тɁu���C�t���[�N���W�听���������v�Ƃ���܂����A�܂��Ɋ��҂ɂ�����ʓ��e�̖{�ł��B
����܂ł����т��瑡���Ă������������Ђ�_���ŁA���̈ꕔ�͓ǂ܂��Ă�����Ă��܂����A
�W�听�Ƃ��邾���ɂ��܂��܂Șb�肪���グ���Ă��܂��B
���т���Əo������̂́A���������ǒ������Ă����p�E�T�j�A�X�E�W���p���̊����̂Ƃ��ł��B
���т���̋����q����̃p�g���l�[�W�ŃM���V�A�ɍs���Ă�������̂����������Ǝv���܂��B
���̉�ł���Ă����T�����ɂ����Ă����������b�����������܂������A
���Ɠ����N���������Ƃ�����A�܂����̂��l�������ɐl�ԓI�Ŗ��͓I���������Ƃ�����A���t���������n�܂�܂����B
���������N�O�ɂ��a�C������A���̌��ǂ��c���Ă��܂����̂ł����A���̌�����т���炵�����Y���Ŋ�����W�J����Ă��܂��B
�{���̏Љ�ɂ́A���̂悤�ɂ���܂��B
�u�l�Ԃ炵���l�ԁv�̒Nj��\�\�����̔蕶�����̕��͂ƁA���[�}�̋��t���t�̎��Ԃ�J���ρE�����ρE�l���ς̌�������A�Ñネ�[�}���E�ɐ��������q���[�}�j�Y���̋N���𖾂炩�ɂ���B
�l�Ԃ炵���l�ԂƂ����A�܂��ɏ��т���ł��B
���̏��т���ȑO�A���[�}�̃q���[�}�j�Y���̂��b���A���������ڂ����m�肽���Ƃ����Ă�����A�����Ă��Ă����������̂��u�Ñネ�[�}�̐l�X�v�ł����B
���т��L�`�̃e�L�X�g�Ƃ��Ă��������̂ł����A����������e�ł����B
���X�����q���[�}�j�Y���_�ƍ��킹�ă��x�����A�[�c�_������Ă��܂����A���R�Ȃ��炻���͐[���Ȃ����Ă��܂��B
���т���̖{�̖ʔ����́A�������̐l�Ԑ��ɗ��r�����l�Ԃ̐�������{�ɂ���̂ŁA�ƂĂ����C�u�Ȃ̂ł��B
���̖{�̏Љ�̎��ɁA�u�c�O�Ȃ�����Ƃ̃e�L�X�g�Ƃ�������͖Ƃ�܂���B����܂��āA���ʂ��C�ɂ����ɁA���т���̎�ς��v���肢�ꂽ�{�����Ђ܂Ƃ߂Ă��炢�����v�Ə������̂ł����A�{�����܂��ɂ��̖{�ł��B
�{���̂�����̓����́A�Љ�Ɂu�����̔蕶�����̕��́v�Ƃ���悤�ɁA�c��Ȕ蕶�������瓖���̐����ɐZ���Ă��邱�Ƃ��炭�郊�A���e�B�ł��B
��P���ł̓q���[�}�j�Y���̗��j�ƃ��x�����A�[�c������A�Â��đ�2���Ń��[�}�̈�t�Ƌ��t�ɂ��ďڂ�������܂��B
�Ȃ��u��t�Ƌ��t�v�Ȃ̂��Ƃ������ƂɁA���͌Ñネ�[�}�Љ�̎����������Ă��܂��B
���т���ɂ��A�Ñネ�[�}�ł͈�t�Ƌ��t�͂����ЂƂ�����ł���Č��y����Ă��������ł��B
���̋��ʓ_�́A�قƂ�ǂ��M���V�A�l�ł���A�������Ⴂ�Љ�K�w�̏o�g�҂����������ł��B
�Љ�ɂƂ��āA��t�Ƌ��t�͏d�v�Ȗ����������E�Ƃɂ�������炸�A�Ȃ������������̂��B�����ɖʔ���������܂��B
��Q���̒��ɃM���V�A�l��t�A�X�N���s�A�f�X�̘b���o�Ă��܂��B
���[�}�Ő���������t�ł����A�ނ͂Ȃ������������A����̓w���j�Y���ł͂Ȃ����[�}��������ł��B
����ł͂킯���킩��Ȃ��ł��傤���A����ȋ�̓I�Șb����A�Ñネ�[�}�̃q���[�}�j�Y�����A�����ăw���j�Y���ł͂Ȃ����[�}���O���R�����j���哱���Ă������ƂɂȂ闝�R�܂ł����_�Ԍ�����C�����܂��B
���܂ɂ́A�����I�ȁA���������{��ǂނ̂��܂��y�������̂ł��B
�R�����Y���X
���P�A�v�����������ł��Ă�Ƃ��������i�������d�q�{���{�T�V�@�b�k�b�@1500�~�j
�R���P�A���Ԃ̑S���}�C�P�A�v�����E�l�b�g���[�N�̓�������Ƌ��{���{�������܂����B
�S���}�C�P�A�v�����E�l�b�g���[�N�́A
���ی��𗘗p���邽�߂̃P�A�v�����������ŗ��ĂĂ���l�����̂��炩�ȃl�b�g���[�N�g�D�ł��B
�Ƃ����Ă��A�����P�ɃP�A�v���������邾���ł͂���܂���B
�����ɁA���Ƃ͉����A�P�A�v�����Ƃ͉����A�����炩���l���Ă���l�����̗ւȂ̂ł��B
�{���ɂ͂U�l�̑̌����o�Ă��܂����A�݂�ȑS���}�C�P�A�v�����E�l�b�g���[�N�̒��Ԃł��B
���̂U�l�̘b���ĕ����������ʂ������̂��A���̃O���[�v�ōł��Ⴂ���{����ł��B
�Ⴂ���ĉ����炢���Ǝv���܂����H
30�́A�������j���Ȃ̂ł��B
���̌����́A���̎��̎Љ��S����҂ɂǂ��f��̂��B
�S���}�C�P�A�v�����E�l�b�g���[�N�̑�\�ł����铇�����A�{���̍Ō�́u�����Ɂv�ɏ����Ă��镶�͂Ɋ������܂����B
���������ł����A���p���܂��B
�������Ă���l���A���ԑ̂��C�ɂ��邱�Ƃ��悭����܂��B�i�����j
���͂����������Ԃ̖ڂ͂܂������C�ɂȂ�܂���ł������A����������A��ɋC�ɂ��Ă����g�ځh������܂����B
����́A�q�ǂ������̖ڂł��B
�e�̐���������납�猩�Ă���q�ǂ��̖ځB
�����ƍL�������ƁA���̐���̖ڂ��ƂĂ��C�ɂȂ����̂ł��B
���Ƃ����ǂ��悶�o�낤�Ƃ�����A���˕Ԃ��ꂽ��A��l�͕K���ɂ������Ă��܂����A���̎p�����̐��オ�m���Ɍ��Ă��āA�������牽������������Ă���͂��ł��B
�ǂ��ł����A
���͗܂��o�����ɂȂ�قǁA�������܂����B
���������v������l�����ɂ�����������A�Љ�͍��̂悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ������͂��ł��B
���̕��͂ɂ����������Ă�����������A���Ж{����ǂ�ł��������B
�K������̐��������l����q���g��������͂��ł��B
�߉��̋��{����͖{���̖`���ł��������Ă��܂��B
�����݁A���ɒ��ʂ��Ă���l�A�������g�̘V����ǂ������Ă��������ƕs���Ȑl�A������K��闼�e�̉����ǂ����悤���ƐS�z�Ȑl�A���Ȃ�Ă܂��W�Ȃ��Ǝv���Ă���Ⴂ�l�ȂǂȂǁA�����̐l�Ɏ�ɂƂ��Ă���������Ǝv���܂��B
�����A���Б����̐l�ɁA�Ƃ�킯���ԑ̂��C�ɂ��Đ����Ă���j�������ɁA�ǂ�łق����Ǝv���܂��B
����́u�P�A�v�����v�̖{�ł͂Ȃ��u���C�t�v�����v�̖{�Ȃ̂ł��B
����Ղ̒c�n�@�������J�Z���i�匎�q�Y�ق��@�����Ё@2000�~�j
�匎����Ƃ͔ނ���w�@���̎�����̒����t�������ł��B
�ŏ��͗F�l�̏Љ�ŁA�V�����ۈ�V�X�e���\�z�Â���̒��ԂɂȂ��Ă��炢�܂����B
���̉��ŁA���̌�A���낢��Ɗy�����v���W�F�N�g�����ꏏ�����Ă��炢�܂����B
���C�H��^�Z�܂�������ł��b�����Ă��炢�܂������A�ƂĂ��D�]�ł����B
�d���ł����엢���̓s�s�v��}�X�^�[�v�����Â���ł��ꏏ���܂����B
������ԍD���Ȃ̂́A�匎����̖ڐ��Ǝ��Ԋ��o�ł��B
�匎����͂��ܓ����w�@�̏y�����ł����A���܂��܂Ȍ���Ɋւ���Ă��܂��B
���ɔނ���������Ă����̂��A������A�p�[�g�ł����B
�����ł̏Z�܂����ɊS�������Ă����̂ł��B
���{�̌��z�Ƃ́A�����ɋ����������܂����A�����ʼnc�܂��l�̏Z�܂����ɂ͂��܂�ڂ������Ă��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
��Ԑv�ł͂Ȃ��A�g�g�ݐv�������悤�ȋC�����܂��B
�����L���l�̌��z�v���D���ɂȂ�Ȃ��̂͂��̂��߂ł��B
�������匎����͈Ⴂ�܂��B
���̑匎�����Ԃƈꏏ�ɂ܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�������J�Z��́A������ɂ��鏺�a33�N�v�H�̓��{�Z����c�̕����^�W���Z��ł��B
���̓����́A���w�Z��ɕ���ł���ꂽ2�K���ăe���X�n�E�X�^�C�v�̂ق��������\���ɂȂ��Ă������Ƃł��B
�e���X�n�E�X�͘a���p��ł����A�����͎��̂悤�Ȏq�ǂ��ł����A������������X�^�C���ł����B
����ɁA���d�����ꂽ��Ԑv�ŁA����{�ɂ��A���̗̋�Ԃ́u�l�̂��̂ł��Ȃ��A���Ƃ����ăp�u���b�N�ȏꏊ�ł��Ȃ��A�R�����v�ƈʒu�Â����Ă��܂��B
�����ɂ͓������ڂ���Ă����c���s�s�̃C���[�W���d�˂��Ă����킯�ł��B
���̈������J�Z����A�Z���͏�����ƍl������{�̏Z��ςɂ͍R���������A��N�A���đւ��v�悪���肵���̂������ł��B
��������Ď������͓s�s���Ă��Ă���킯�ł����A�匎�����͂������������ւ̉s�����_�𐘂��Ȃ���A��������߂Ĉ������J�Z��̈Ӗ��ƕϑJ�̕��������Ă���Ă��܂��B
�Ƃ������ʔ����ł��B
���{�̏Z��j�Ƃ��������A�s��ł̕�炵�̗��j��ʂ��āA���{�Љ�ǂ��ϑJ���Ă������������ł��܂��B
�����ʔ��������ł͂���܂���B
�������璘�҂����������Ă���̂́A�����Ɍ����ẮA���邢�͍����鎄�����̐������ւ̃��b�Z�[�W�ł��B
���Ԃ̂Ȃ��l�́A���Ж{���̑匎����̂��Ƃ��������ł��ǂ�ł��������B
���̎��Ԃ��Ȃ��l�̂��߂ɁA�����Ō���Ă��郁�b�Z�[�W��������Љ�Ă����܂��B������ƒ����ł����B
���������A�ߑ�I�s�s�v��́u��Ⴂ�Ȃ܂��v�������Ă��܂�Ȃ����߂̋Z�p�ł������͂����B
�i�����j
���a30�N��O���̒c�n�v�ŁA�ނ�i�v�ҁj�̕M�����������Ă����̂́A�u�o�ό����v�ł͂Ȃ��u�f���ȓs�s�v��v�Ƃ��������������ɈႢ�Ȃ��B���̎��ԂƂ͑ł��ĕς���āA���ł͐v�҂����M�ɁA�o�ώ����`�̐��E����̈�{�̋��͂Ȏ������т��Ă��āA�m�炸�m�炸�v���̐����������̐��E�Ɉ��������Ă��܂��Ă���悤�ȋC������B
�i�����j
�i���{�̍��̌��z�v�̌���́j�u��Ⴂ�Ȃ܂��v������Ȃ��悤�ɁA�Ƃ̎v���Ő��������Ă������Ƃ͊u���̊�������B
�i�����j�u�o�ώ����`�̐��E����̈�{�̋��͂Ȏ��v������A�����̐���ɂȂ��Ă��錻����Q���Ă���̂ł���A�����ɂ����A���Z��Ԃ̍ĕ҂𗊂邷�ׂ��Ȃ����{�����̊낤����Q���Ă���̂ł���B
�Ƃ����������̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
����̐������A�Z�܂����Əd�˂Ȃ���B
�������y�����i���^��@���㏑�с@1300�~�j
���^�炳��́u���{�l�̖����v�V���[�Y��4�e�ł��B
���ς�炸�̌��M�ɂ���������������ł����A���̃V���[�Y�����͂ƂĂ��y���݂ɂ��Ă��܂��B
�������̐�������o�Ă��镶���_�A�����_���������邩��ł��B
����͍���ł����A����ւ̊S�̍��܂�̔w�i�ɂ́A������`��ӓ|�̋ߑ��`�ւ̔��Ȃ�u�����Ȃ����E�v�ւ̎u��������A�ȂǂƏ������ƁA�܂��܂��ǂ݂����Ȃ��Ă��܂��܂��B
������܂��u����v�����Ɉ������̕����_���c���Ɍ����̂ł����A�����2�̂��Ƃ����͓��ɋ����Ă��炢�܂����B
�܂��u�����v�ł��B
�u���ȁv�ɑ�������u���ȁv�Ƃ����̂������āA�����ł́u�g���v�Ƃ����V�т�����̂������ł��B
���̍ō�����́u�������v�ƌ�������̂ŁA�T�̍��̑g�ݍ��킹�Ă���̂������ł��B
���̑g�ݍ��킹���͂T�Q�D���ꂪ��������T�S���̓��̂T�Q�ɑΉ����Ă���ƌ����܂��B
���̎�ނ́A�h�A�ÁA�_�A�������炢�A���5�������ł����A�����������ꂷ�玄�ɂ͂悭������܂���B
���ꂪ�n��ꂽ�͍̂]�ˎ��ゾ�����ł����A�]�˕����̐[�������߂Ďv���m�炳��܂��B
���{�l�̍���̕����̂������������܂����B
�Ƃ���ŁA�u�����v�́u����v�̂��ƂɂȂ鍁�͑S�ē��{�Y�ł͂Ȃ��A�A�W�A�e�n�̂��̂ŁA���{�ɂ͍����Ȃ������ł����A��������ɋ����[���b�ł��B
���{�́A�����炭����Ƃ����ʂł͂��ƂȂ������y�Ȃ̂ł��傤���A�����łȂ��������L�������̂��A�������s���܂���B
�u�v���[�X�g���ہv�Ƃ����̂������Ă��炢�܂����B
�L�o�ɂ���ĉߋ��̋L�����Ăъo�܂����S�����ۂ������炵���ł����A����̓}���Z���E�v���[�X�g�́u����ꂽ�������߂āv�̏����o���ɗR������̂������ł��B
�������ɍ��肪�̂̋L�����v���o�����邱�Ƃ͂悭����܂��B
�q�ǂ��̍��̐��E�̓���������Ɖ����ƂĂ����������K���ȋC���ɂȂ邱�Ƃ́A���̂悤�ȍɂȂ��Ă����邱�Ƃł��B
�ق��ɂ���������b���o�Ă��܂��B
�u���͗��̔��v�Ƃ����M���������̂ł͂Ȃ����Ƃ��������́A�����ɂ��������炵���ł����A���m�̍����Ɠ��m�̍����d�˂��u�������v�ƌ����̂����邱�Ƃ��m��܂����B
�㔼�ɂ́A���Y�Ƃ̌o�c�҂Ƃ̑Βk���f�ڂ���Ă��܂��B
�����q�ł͂���܂����A���̃V���[�Y�͂����킭�킭���Ȃ���ǂ܂��Ă��炦�܂��B
�����̂�����肵���C���̒��ŁA���ǂ݂Ȃ�ƁA�ŋ߂̎������̐������̂��������ɋC�Â���������܂���B
�����F���i���|��q�E���������@��g�u�b�N���b�g�@500�~�j
�s���������I�t�B�X�E�n�X�J�b�v��\�̏��|����̐��͓I�Ȋ����ɂ͂������S���Ă��܂��B
�R���P�A�Œm�荇�����̂ł����A���̃V���[�v�Ȏ��_�ƍs���͉͂�����Ƃ���ɓ`����Ă��܂����B
�����g���܂�ړ_�͂Ȃ��̂ł����A�Ȃɂ��킩��Ȃ����Ƃ͂������������Ɖ����Ă����Ƃ����A���ɂƂ��Ă͂ƂĂ����肪�������݂ɂȂ��Ă��܂��B
���̏��|���A5���ɔ��s�����w�����Q��A��2�Łx�̒lj����Ƃ��āA�܂Ƃ߂��̂����̊�g�t�b�N���b�gN0�D770�w���F��x�ł��B
���|����̂��莆������p�����Ă��炢�܂��B
���F���3�N���ƂɌ����J���ȗ߂Ō��������s���Ă��܂����A�i�����j10������Ăь������ꂽ���F�肪�͂��܂��Ă��܂��B
�s���������I�t�B�X�E�n�X�J�b�t�ł́A�����̐l����ɏ\���ȏ����Ȃ��܂��{����悤�Ƃ��Ă��錩�����Ɋ�@��������A����W��Ȃǂ��J�Â��Ă��܂����B
���̂Ȃ��ŁA���G�ȉ��F��̂����݂ɂ͂킩��Ȃ����Ƃ������ƍl���A�V���Ƀt�b�N���b�g���܂Ƃ߂܂����B
�i�����j
�{���������̐l�����F��̂����݂𗝉�����ꏕ�ɂȂ�A�����������̉ۑ���l���邳�������ɂȂ邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�Ȃ��A���|����o�R�Œ�������ƁA���Ҋ����i�Q�����A����ŕʁB30���ȏ�͑��������j�ōw���ł��܂��B
����]�̕��͏��|����ɂ��A�����������B
�s���������I�t�B�X�E�n�X�J�b�t�@���|��q
FAX�D03�|3303�|4739�@Mail�Ftoffice��haskap.net
�������܂��������������i�����H�Y�@����V���Ё@1300�~�j
�n��U���A�h�o�C�U�[�ň�x���ꏏ�������Ƃ̂��钆���H�Y����{�������Ă��܂����B
��������͒n��U���A�h�o�C�U�[�Ƃ��đS�����щ��Ȃ���A�n���̑����s�̏��H��c���̐ꖱ�����Ƃ��āA�����s�̂܂��������Ɏ��g�݁A�����Ȑ��ʂ����X�ɏグ�Ă���ꂽ���ł��B
������x�A���U�������̂ł����A���Ԃ��Ȃ��ĎQ���ł��������ɗ����Ȃ��܂܁A����10�N�ȏ�̂������������Ă��܂��Ă��܂��B
��������́A���͏��w���̍�����̃V���[���L�A���ł��B
���̓V���[���L�A���ł͂���܂��A��͂菬�w���̍�����V���[���b�N�E�z�[���Y�̑�t�@���ł����B
��������Ƃ̃z�[���Y�_�c���y�����v���o�̈�ł��B
�{���́A�������ǐ^�ɂ��đ̌����Ă��������̂܂��������̘b�̏W�听�łł��B
��������͂��łɑ����̂܂��Â���Ɋւ��Ă�2���̖{���o���Ă��܂����A���������������炵���ʔ���������܂����B
�v���Ԃ�ɏo�����{���́A���肪�u�V���[���b�N�E�z�[���Y�搶�ɕ����v�ƂȂ��Ă��܂��B
����ɂ��Ђ����Ƃ��낪����܂��B
�{���ɂ͑�����s�̘b���o�Ă��܂��B
�z�[���Y�̖`���k�̒��ł��L���Ȃ̂��A�w�Ԗёg���x�ł����A���̎����̕����1890 �N�̃����h���̋�s�ł��B
���̍��A������s�����܂ꂽ�̂������ł��B
����Ȃ��ƂɂȂ��Ȃ���A��������͂��������܂��B
�����́A���Z���{���M�����u���̂悤�ɐ��E��Ȋ����ĉv�X�I���Ȕƍ߂����s���Ă���B
����Ȏ���Ƀz�[���Y�搶�Ȃ�ǂ�ȉ��������Ă����̂��낤�B
���Ȃ݂ɁA������s�̕�̂́A1892�N�ɂł����u�����F���`�c�v�������ł��B
���Z���{��`�ƗF���B
�Ȃɂ�獡�̎���̖��҂�������Ă��܂��B
�ق��ɂ��A�u�R�R�E�t�@�[���v��u�܂��������T��c�v�u�ԉł̂܂��������v�ȂǁA�������ւ�����܂����������ꂪ����Ă��܂��B
�Z������̂܂��������̃q���g����������܂܂�Ă��܂��B
�e�n�ł܂��������Ɏ��g��ł�����ɂ͂��Ђ����߂������{�ł��B
�����l���؊X�̐��E�i���l���ȑ�w�ҁ@1500�~�j
���������̍��{�p������{�������Ă��܂����B
���ꂪ���̖{�ł��B
���{���A���l���ȑ�w�̊w�������̃L�����A�J���x���Ɏ��g��ł��邱�Ƃ͏��������Ă��܂������A�Ȃ�ł��ꂪ�܂����l���؊X�̖{�Ȃ̂��Ǝv�����̂ł����A���{����̎莆��ǂ�ŗ��R���킩��܂����A
���N�͉��l�`�J�u150���N�ɂ�����̂������ł��B
����ʼn��l���ȑ�w�ł́A�u���؊X�܂��Ȃ��L�����p�X�v�Ƃ������J�u������悵���̂������ł��B
�����āA���؊X�����܂�̋����������{���A���̃R�[�f�B�l�[�^�[���������̂ł��B
���J�u���ւ̎�u��]�҂͒����傫������A�Q���ł��Ȃ������l�����Ȃ��Ȃ��悤�ł��B
����������āA���̐��ʂ�������Ɩ{�ɂ��悤�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��傤�B
���̎�̌��J�u���̋L�^�́A����Ȃ��炠��܂�ʔ����Ȃ����Ƃ������̂ŁA�����ŏ��͂��܂苻���������Ȃ������̂ł����A�ς�ς�Ɩ{���߂����Ă݂�ƁA��ۂ���ς��܂����B
�{�̐����ɂ���ȕ��͂��o�Ă��܂��B
�u���؊X�̓��͂Ȃ�Ŏ�?�v
�u�����l�͂����炱�̊X�ɗ�����?�v
�u���ؗ����̓X���ĉ��������?�v
�u���؊X�̂��q����͔N�ɂǂ̂��炢���Ă���?�v
�c�c���؊X�ʂ̎��ґ���12�l���܂��̖��͂���j�A���������s�����B
���l���؊X�������A���̒n�Ŋ���l�������܂��̔閧��S�������܂�!
���؊X�ʂ̎��ґ���12�l���܂��̖��͂���j�A���������s�����B
�������ɍu���ł̘b����̐l�I�������Ă��܂��B
����ł�����C�ɓǂމH�ڂɂȂ��Ă��܂��܂����B
�e�u���Ƃ����ɖʔ����ł��B
���̖ʔ������e�������Œ��r���[�ɏЉ��̂͂�߂܂����A�I�͂ɏ�����Ă������Ƃ���ۓI�ł����̂ŁA���ꂾ�����Љ�Ă����܂��B
���؊X�͐��E�e���Ő��܂�Ă��܂����A�������{�́u���؊X����o��A�����Ď嗬�Љ�ɗZ�����߁v�ƌĂт����Ă��邻���ł��B���؊X�͐V���ɂ���Ă��������l�̈ꎞ�؍݂̏�ł�����A��������o���Ȃ��Ƃ����̂͌o�ϓI�ɐ����ł��Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���������{�ł́A�t�ɒ��؊X�ɓX���o�����琬���Ƃ���Ă���̂������ł��B
���{�ȊO�̍��̒��؊X�ł�9���̐l�������l�ł���̂ɑ��āA���l���؊X��9���ȏ�̂��q�����{�l�������ł��B
���̘b���炢�낢��Ȃ��Ƃ��C�Â�����܂��B
�܂�����Șb���A���̖{�ɂ͂��낢��Ƃ���߂��Ă��܂��B
�����ȑ�w�Ō��J�u���⊥�u�����J����Ă��܂����A�����炭����Ȗʔ����u���͂����Ȃ��ł��傤�B
���{����̃R�[�f�B�l�[�^�[�͂Ɋ��S���܂����B
�����̂�����͂��ǂ݂��������B
�R�����Y���X����w��
�������킸���肪�Ƃ��Ƃ��������Ȃ�����Â̂�����Ƃ����b�iCHOI�͂Ȃ���ԕҁ@���䏑�[�@1000�~�j
�����^�C�g���̖{�ł��B
CHOI�͂Ȃ���Ԃ́A���̖{�𐧍삷�邽�߂Ɍ��������O���[�v�ł��B
���̎����ǒ���������m�q����B
��Â����_�ɂ��܂��܂Ȋ����Ɏ��g��ł��錳�C�ȕ��ł��B
�������g��ł���R���P�A�̊����ŏo��܂����B
�y�₩�ɂ��܂��܂Ȋ���������Ă��܂��B
�����������̖{���ł���_�@�ɂȂ����̂��A�n����Â𑖂��Ă��鋞��d�Ԃ̉w��d�Ԃ�ɂ����M�������[�����ł��B
�����m�肠�������Ɏ��g��ł����u���̃I�A�V�X�v���������炵�������ŁA���X�X�̋X�܂����p�����M�������[���T�����̊����ł����B
���������������炳�܂��܂Ȗ{�����܂�Ă��܂����A���N��2���̖{�����܂�܂����B
�u�d�ԂƐt�{�����v�i�T�����C�Y�o�Łj�Ɩ{���ł��B
�{���͏����͒����ł����A�{���͂ƂĂ��Z�����͂Ǝʐ^�̑g�ݍ��킹�ł��B
���͂́u���肪�Ƃ��b�v�̌���ɉ����Ă��ꂽ��i�̒�����I�ꂽ���̂ł��B
�݂�ȐS���܂�b����ł��B
���Ƃ��A
���ɂP�`�Q��A�ߏ��̍���҂̂����K�₵�Ă��܂��B
�S�҂��ɂ��Ă���������������A�Ƃ��ɂ͕����ɏオ�肱�݁A���ꎞ�Ԃقǎv���o�b�����Ă����������Ƃ��B
�u�������肪�Ƃ��v�Ɏ������C��������Ă��܂��B
����Ȃ̂�����܂��B
�q�ǂ��B�ɂ͈��A�̑��������Ă��܂����B
����𒉎��Ɏ��s�������R�̖��ɂ́A�F��������������I�ߏ��̂�������A������Ƃ����ǂ��Ȃ����������ŁA�����Ă��炦����S�����炩�A���Â��Ȃ�����������̂��|���Ȃ��Ȃ�܂����B
���̖{�̖`���̍�i�����낢��ƍl���������܂��B
�S���ɐ���ʼn^�s���Ă����u�������ł��Ԍ����v�A�I�n����Ō��������̎ԑ������߂Ă����Q���̘V�w�l�B
�u�����ڂ��J���Ă��Ă��ق�Ƃ͌����ĂȂ��́B�ł������͍ŏ�����Ō�܂ō��������܂����B���肪�Ƃ��v
�������������{�����肽���Ƃ����Ǝv���Ă��܂����B
���䂳��A���肪�Ƃ��B
�����Ȗ{�ł����A�ƂĂ����C�����炦�܂��B
�������͂���������ł��܂��B
���܂͐��E�ň�ԏ����ȊC�i���^��@�O�܊ف@1300�~�j
�܂́u���E�ň�ԏ����ȊC�v�Ƃ́A�A���f���Z���̌��t�������ł��B
���̊C�́A������������u���E�ň�Ԑ[���C�v��������܂���B
���́A2�N���O�ɔ�����������܂������A���̑̌�����A�����Ƃ��Ă����v���܂��B
���̐[���́A�ފ݂ɓ͂��قǂ̂��̂ł��B
����͂Ƃ������A�{���́A�������́u�n�[�g�t���v�V���[�Y�A�n�[�g�t���E�t�@���^�W�[�_�ł��B
����́A�u�w�K���x�Ɓw���x���l����A��l�̓��b�̓ǂݕ��v�Ƃ���Ă��܂��B
���グ���Ă���̂́A�A���f���Z���i�u�l���P�v�u�}�b�`����̏����v�j�A���[�e�������N�i�u�����v�j�A�{���i�u��͓S���̖�v�j�A�T�����e�O�W���y���i�u���̉��q���܁v�j�ł��B
�������́A���̂S�l���[���Ȃ����Ă��邱�Ƃ������Ȃ���A�ނ炪�`���Ă��Ă��郁�b�Z�[�W��ǂ݉����Ă����܂��B
���Ȃ薾�m�Ɏ����̎咣���\�����Ă��܂����A���������ߌ��Ɏv����Ƃ��������܂��B
���������咣�́A�S�l����̃��b�Z�[�W��ǂ݉�������̃G�s���[�O�Ō���Ă���̂ł����A���̌����͂��Ȃ苭���ł��B
�����́u�t�@���^�W�[�v�f��̑�������焈Ղ��Ă��鎄�Ƃ��ẮA�������̎��̂悤�Ȏw�E�ɂ͂ƂĂ������ł��܂��B
�������Ɂu�w�֕���v�𒉎��ɉf�扻�����u���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�v�O����Ȃǂ̓A�J�f�~�[�܂�Ɛ肵�����������Ă��炵���N�I���e�B�̍�i�ł����B�������A���X�ƂÂ��X�y�N�^�N���Ȑ퓬�̏�ʂɂǂ��ɂ���a�����o���Ă��܂����̂́A�킽����l�����ł��傤���B�킽���́A�u�Ȃ��A�����ƕ��a�̃C���[�W��^���Ă����̂ł͂Ȃ��A�t�@���^�W�[�f��ɐ푈�̏�ʂ���o�Ă���̂��H�v�Ƒf�p�Ɏv���Ă��܂��̂ł��B
���̕��͂ɁA�������̃n�[�g�t���E�t�@���^�W�[�_���v��Ă���悤�ɂ��v���܂��B
�n�[�g�t���E�t�@���^�W�[�́A�u���v�̐^����u�K���v�̔閧�������́A�ƈ������͍l���Ă���̂ł��B
�K���͂킩��Ƃ��āA�Ȃ��u���v�Ȃ̂��B
����Ɋւ��ẮA���̈������̌��t�����ׂĂ�����Ă��܂��B
�����ǂ����Ă��C�ɂȂ������Ƃ�����܂����B
����́A���{�ł́A�l���S���Ȃ����Ƃ��Ɂu�s�K���������v�Ɛl�X���������Ƃł����B
�킽�������́A�݂ȁA�K�����ɂ܂��B���ȂȂ��l�Ԃ͂��܂���B
����A�킽�������́u���v�𖢗��Ƃ��Đ����Ă���킯�ł��B
���̖������u�s�K�v�ł���Ƃ������Ƃ́A�K���s�k���҂��Ă��镉����ɏo�Ă����悤�Ȃ��̂ł��B
�i�����j
�킽���́A�u���v���u�s�K�v�Ƃ͐�ɌĂт�������܂���B
�Ȃ��Ȃ�A�����Ău�Ԃɏ����K���s�K�ɂȂ邩��ł��B
���͂������ĕs�K�ȏo�����ł͂���܂���B
����������A���͍K���ɂȂ����Ă����͂��ł��B
�����āA�������Ɛ[���Ȃ����Ă��邱�ƂɋC�Â��ł��傤�B
�{�_�Ƃ͈Ⴄ���Ƃ��Љ�Ă��܂��܂������A�{���ł͂T�̃t�@���^�W�[��ǂ݉����Ȃ���A�������̐��E�ς�l���_������Ă��܂��B
����͂����炭������q�ǂ��̍����犵��e����ł����t�@���^�W�[�̍�i�̉e�����傫���ł��傤�B
�����̂��ƂƂ��Č���Ă��邱�Ƃɋ��������Ă܂��B
�������́A�t�@���^�W�[��i��P�Ȃ�ǂݕ��Ƃ͑����Ă��܂���B
�����ɂ́A�l�q�̐^���A�@����N�w�̐^���Ȃǂ̐l�ނ̕��Վv�z���A�N�ɂ��킩��悤�ɏ�����Ă���A�Љ�ɂ܂��e������Ȃ��O�̎q���������A����������i�ɂ��肰�Ȃ��G��邱�Ƃɂ���āA���͐l�ނ̕������������o����Ă���ƁA�������͍l���Ă���悤�ł��B
���E���̐l�������A�S��ʂ킹������̂́A�����������炻�̂�������������܂���B
����������A�t�@���^�W�[���������a����ĂĂ���̂�������܂���B
��l���A�t�@���^�W�[����w�Ԃ��Ƃ����Ȃ�����܂���B
�{���͂��̂��Ƃɂ��C�Â����Ă���܂��B
�C�y�ɓǂ߂܂��̂Őe�q�œǂ�Řb�������Ă�������������܂���B
�R�����Y���X����̍w��
���u�ނ��ттƁv�i���^��ҁ@�O�܊ف@952�~�j
���^�炳��̖{�̏Љ�����Ă��܂����A���T�����^�炳�ҏW�����{�ł��B
�����́u�ނ��ттƁv�B
�Ƃ����A�����܂ł��Ȃ��v���o���̂́u������тƁv�B
���������ӎ����Ă̈������炵�����ꂪ�u�ނ��ттƁv�ł��B
�������I�ɂ����A���ƍ������Ԏd�������Ă���A������E�F�f�B���O�v�����i�[�ƌĂ��l�����A���ꂪ�u�ނ��ттƁv�ł��B
�ȑO�������܂������A���^�炳��͊������ՊW�̉�Ђ̎В��ł�����܂��B
�ł�����A�������̎���ɂ́u�ނ��ттƁv���u������тƁv�������A��������̃G�s�\�[�h�Ɏ��͂܂�Ďd��������Ă���킯�ł��B
�����āA�����炭��������g���A�u�ނ��ттƁv�u������тƁv�����F����Ă���̂��낤�Ǝv���܂��B
������u�ނ��ттƁv���ǂ������Ă��邩�́A���̕��͂ł킩��܂��B
�����͈�̂��̂������u���v�̕Њ��ꓯ�m���A�ӂ����ш�Ɍ��т��u�Ԃ����炩��搂������邱�ƁA���Ȃ킿�u�����v�̂���`��������̂��A�{���̎�l���g�ނ��ттƁh�̎d���Ȃ̂ł��B
�u�����v���������̑���ł��B
�u�����_�v�Ƃ������������܂��B
�{���ɂ́A���������u�����v�ɂ܂��P�X�̕��ꂪ�Љ��Ă��܂��B
���ׂĎ����Ɋ�Â����̂ł��B
�����āA�����ɂ́u�ނ��ттƁv�����̔Y�݁A�s���A��сA����������܂����A��������ǂݏI�������ɁA�����ƂĂ����������ȍK���������܂��B
�P�X�̃G�s�\�[�h�Ə����܂������A���͂����ЂƂG�s�\�[�h���Љ��Ă��܂��B
�u���Ƃ����v�ň�����g���̌������u�S�̎d���v���Љ��Ă���̂ł��B
�����ł̃e�[�}�́u�Ƒ��v�ł��B
�u�����v����n�܂�̂́u�Ƒ��v�ł��B
���́A���̂��Ƃ��������͈�Ԍ������������̂�������܂���B
�܂����ʂ͂����ŏI���̂ł��傤���A�������͂���ɂ������������Ă��܂��B
�u������v�������d���̒��ł��g�ނ��ттƁh�����́A�ƂĂ���Ȃ��̂��Ă��܂��B
�킽�������̖{���̏��i�́A�u���a�v�Ƃ������̏��i�Ȃ̂ł��B
�������̉�Ђ̃X���[�K���́u�����͍ō��̕��a�ł���v�B
�٘_������ł��傤���A���͂��̒ʂ肾�Ǝv���܂��B
�R�����Y���X����̍w��
��������{���ʔ����ǂ߂���@�i���^��@�O�܊ف@1400�~�j
�{�Ƃ͐S�点��u������̐H�ו��v�B
�����l���Ă���������́A���ɑ�H���ł��B
�Ȃɂ��떈�N700������{��ǂ�ł���̂������ł��B
�얞�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ł����A�������̂�����̊�ł��鍲�v�Ԃ���Ƃ��ẮA�����������Љ�̒��ʼn�Ђ��o�c���A���܂��܂ȎЉ�������Ȃ��Ă��܂����A�����g�ł����X�Ɩ{���o�ł��Ă��܂��̂ŁA�����Ĕ얞�ɂ͂Ȃ�܂���B
���̏����͂͋��Q������̂�����܂��B
�{���́A���̈������̓Ǐ��_�ł��B
�P�Ȃ�Ǐ��p�̖{�ł͂���܂���B
�Z�p�тƎv�z�тɂ킩��Ă��܂����A�Z�p�тł��������������ȓǏ��p�ł͂���܂���B
�S�҂ɗ���Ă���̂́A�������̖{�ւ̈���ł��B
�{���ł��u�Ǐ��͗����v�Ə����Ă��܂����A����������͈̂������́u�Ǐ��v�Ƃ��������{��S�ꈤ���Ă���̂ł��B
�{�������Ă�������A�����s�ׂł���Ǐ��͖ʔ������́A�y�������̂ɂȂ��Ă��܂��B
���������������ւ̖{�ւ̃��u���^�[���A�{���ł��B
�����Ƃ̈������́A�{�������邱�Ƃ̈Ӗ���y�����𑽂��̐l�ɒm���Ă��炢�����Ƃ����v���ŁA���u���^�[�����J�����̂ł��傤�B
�������ƂĂ����H�I�ȓǏ��@���Љ��Ă��܂��B
���Ƃ��A�������͖ڎ����T���ȏォ���ēǂނ̂������ł��B
���͂����������Ƃ��������Ƃ��Ȃ������̂ł����A���̈Ӗ���{���Œm��܂����̂ŁA���ꂩ��͐S���������ł��B
����Ȗ{�̓ǂݕ����ƂĂ������ł��܂��B
�{�����P�Ȃ�l�I�ȃ��u���^�[�ŏI����Ă��Ȃ��̂́A�������̎��т��w�i�ɂ��邩��ł��B
�{���ł��Љ��Ă��܂����A�������͓Ǐ��ɂ���ē����u���Ƃ��v�Ɏx�����ĉ�Ђ����Ē����܂����B
�Ǐ���ʂ��āu���v�ւ̕s�����������܂����B
�����č��ł́u�Ǐ��v�������ŁA����̎u����ĂȂ���A����̒����u���Ȃǂ�ʂ��āA���ɔ��M���Ă���̂ł��B
���ւɂ������Ă���Ǐ��l�ł͂Ȃ��̂ł��B
�ł�����A�����ŏ�����Ă��邱�Ƃ́A�ƂĂ��e���݂����āA�܂����H�I�ł�����̂ł��B
�������͂��������܂��B
���Ȃ��́u�u�v�ނ��͓̂Ǐ��ł��B
���Ȃ��́u�u�v����Ă�̂��Ǐ��ł��B
�����āA���Ȃ��́u�u�v����������̂́A���Ȃ����g�ł��B
�������̓Ǐ��_�́A�l���_�ł�����̂ł��B
�{���̓��e�̏Љ�́A�o�ŎЂ̈ē���ǂ�ł��������B
���낢��Ȃ��Ƃ��C�Â����Ă����Ǐ��_�ł��B
���ŒZ�ňꗬ�̃r�W�l�X�}���ɂȂ�h���b�J�[�v�l�i���^��@�t�H���X�g�o�Ł@1500�~�j
�o�c�̐��E�ɑ���ȉe����^�����h���b�J�[�Ɋւ��鏑�Ђ͑����ł��B
�������A�l�ԓI�Ȏv�������߂ăh���b�J�[�̎v�z������Ă��鏑�Ђ́A���������͂���܂���B
���^�炳��́A���炪�h���b�J�[�o�c�w�̎��H�҂ł��B
���炪�o�c�����Ђ��A�h���b�J�[�̋����ɏ]�������ɗ��Ē����܂����B
�������A����͂����߂��炵���b�ł͂���܂���B
�����A�������Ɋ��S����̂́A�P�Ɋ�ƌo�c�̐��E�����ł͂Ȃ��A����̐������ɂ����Ă��h���b�J�[�ɋ������A���H���Ă��邱�Ƃł��B
�܂��ɒm�s����̌����ȃ��f���ł��B
�������́A�h���b�J�[�̎v�z�������ɏ������A���H���A����ɂ����Ɏ���̒m�Ɛ����d�˂Ă��Ă��܂��B
�{���́A���������������̃h���b�J�[�o�c�w�̌����_�ł̎��H�I�ȏW�听�ł��B
���̏����ɂ́A�R�͂Ȃ��Ǝ��͎v���܂��B
�{����ǂ߂A�h���b�J�[�̌o�c�v�z�̖{���ɐG��邱�Ƃ��ł���ł��傤���A���̒m�b�ɑ����̂��Ƃ��C�Â������ł��傤�B
���H�e�N�j�b�N�̏��́A���͍D���ł͂Ȃ��̂ł����A����́u�v�l���g�ɂ����H�e�N�j�b�N�v�Ȃ̂ł��B
�ނ���e�N�j�b�N�̏��ł͂Ȃ��A�v�l�̏��Ƃ��Ă��E�߂��܂��B
�������͎�����u�h���b�J�[�E�`�F���h�����v�Ƃ����قǁA�h���b�J�[�̃t�@���ł��B
�h���b�J�[�́u�l�N�X�g�E�\�T�G�e�B�v�Ƃ���������āA�u�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�v�Ƃ����A���T�[�u�b�N�܂ŏ����Ă���قǂł��B
���͐����A�h���b�J�[�̃t�@���Ƃ͒��������݂ł����A����ł����̖{��ǂނƃh���b�J�[�t�@���ɂȂ肻���Ȃ��炢�A�������̓h���b�J�[������̂��̂ɂ��Ă��܂��B
�������ƃh���b�J�[�́A�ƂĂ������������R���{���[�V�����������܂��B
�{����6�̏͂���Ȃ肽���Ă��܂��B
�u���Ȏ����v�u�}�l�W�����g�v�u�}�[�P�e�B���O�v�u�C�m�x�[�V�����v�u���[�_�[�V�b�v�v�u�����n���v�B
��������h���b�J�[�̎v�z�̃L�[�R���Z�v�g�ł��B
�ŏ��Ɂu���Ȏ����v���u����Ă���Ƃ���ɁA�������̖{���ւ̊�{�I�Ȏp�������������܂��B
�܂��́A�V���������ւ̋C�Â����Ăт����Ă���킯�ł��B
�{���́A�܂���Ƃ̐l�����ɂ��E�߂��܂��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��̂ŁA���ɖ{���D���łȂ��l�ł����Ă��A�Ō�܂œǂ߂�͂��ł��B
���ɂm�o�n�̐l�ɂ��E�߂������ł��B
��������ƌo�c�̖{��ǂ�Œ��肽�o���̂���l�ł��A�����Ɠǂ�ł悩�����Ǝv���ł��傤�B
���C�̂���s���̐l����v�@�l�̐l�ɂ����E�߂��܂��B
�����āA����̐������ɂ�����Ɩ����Ă�����ɂ����E�߂������ł��B
���������������h�肷���Ē�R������܂����A���g�͂ƂĂ��������肵�Ă��܂��B
���E�߂�1���ł��B
�����_�������͂��߂悤�i���R���N�@���o�Ł@1400�~�j
�T�ԋL�^�ŏЉ�Ă����؉��N���u�̑��R����̖{���������܂����B
���R�����ۂɎ��H���Ă���u���_�����v�̂����߂ł��B
�����悤�Ȗ{�͂�������o�Ă��܂����A
���̖{�͑��R����̐�������������Ɣ��f���Ă��܂��̂ŁA�R�U��̂Ȃ����H�҂̖{�ɂȂ��Ă��܂��B
�Ȃɂ����y�Ɩ�̂ɂ���������̂������ł��A
����ɍ����̎Љ����������ƈӎ����Ă��܂��̂ŁA�ǎ҂̓ǂދC���U���ł��傤�B
�{�̓��e�͏Љ�ɓI�m�ɂ܂Ƃ߂��Ă��܂��B
�����͓s��ʼn�Ћ߂����āA�T���͍x�O�̍؉��Ŋy���݂Ȃ���������B�����ĐH�ׂāA����B���ꂪ���_�T�����[�}�������ł��B���_�����̓J���^���B�������A�؉��ł̓K�x�ȉ^���ƈ�Ă����H�ׂ邱�ƂŌ��N�ɂȂ�A������������ŔN���P�O�O���~�A�b�v���B�{������ɁA���܂������_�������͂��߂悤�B
100���~�ȂǂƏ����Ă���Ƃ���͎��̎�ɂ͔����܂����A����͌����ĒP�Ȃ�L���b�`�R�s�[�łȂ����Ƃ́A�{����ǂނƂ悭�킩��܂��B
�ڎ����������������B
�ƂĂ����H�I�ŁA�ǂ݂₷���{�ł��B
�����āA�����u���_�������悤���v�Ƃ����C�ɂȂ��Ă��܂��{�ł��B
�P�@���_�����̓J���^���ɂ͂��߂���
�Q�@�����ʂ���͈͂Ŕ_�n��T����
�R�@�؉��łǂ�Ȗ�����邩�l���悤
�S�@�؉��̍L���ɉ����ē�������낦�悤
�T�@��ؕʃJ���^���͔|�̕��@�ƃ|�C���g
�U�@���_�����ň�Ă���͈ӊO�Ƃ悭�����
�V�@��������Δ��_�����Ō�10���~�҂���
���R����͎��ۂ̔_�����m�ۂ��āA�_�ƃN���u�̊������Ă��Ă��܂��B
���̏�A���_�����T�|�[�g�Z���^�[�������グ�܂����B
�����āA���̖{�̏o�łɍ��킹�āA���_�����T�|�[�g�Z���^�[��ÂŁA�u�݂�ȂŔ��_���C�t���y���ގ���ڎw���āv���e�[�}��9��29���Ƀt�H�[�������J�Â��܂��B
���m�点�̃R�[�i�[�Ɉē����ڂ��܂����B
���R����͂����Ăт����Ă��܂��B
�������͂�͂臀���R���̈���B
�_�앨����Ă�A���̎����Ɗ�т��킢�Ă��܂��B
�_�Ƃ���芪�������ς����褓s��̐�����d�������Ȃ���u�A�}�`���A�_�Ɓv������u���_���C�t�v�̂��������낢�됶�܂�Ă��܂����B
���̂ЂƂ́A����������Ă���u�_�ƃN���u�v�B
���S�҂ł��A�Z�����Ė��܂Œʂ������ɂȂ��Ƃ����l�ł��A�C�y�ɎQ�����č͔|���y���߂܂��B
��̃N���u�̂悤�ɢ�_�ƃN���u����L�����āA�����ʂ�����Ԃ��Ƃ�Ċy�������X�������l��������Ǝv���܂��B�u�_�ƃN���u��ɂ��Ēm�肽�����A�Ƃɂ��������ĂĂ݂����Ƃ������A���C�y�ɂ��Q�����������B
���̖{���炢�낢��ȕ��ꂪ�n�܂肻���ł��B
���R����́A�����Ăт����Ă��܂��B
���R����ɂ����؉��N���u�̃z�[���y�[�W�����Ђ������������B
�R�����Y���X����w��
���u���i������j�����̂��ށv�i���^��@���㏑�с@1300�~�j
�������́u���{�l�̖����v�V���[�Y��R�e�ł��B
����̃e�[�}�́u���i������j�v�B�܂��Ɉ������̐��E�ł��B
�u�V�̌��A�n�̓��v�Ƃ������͂ɑ����A�{�҂́u���̂����炵�v�Ƒ肵�āA�����̂悤�Ɉ������̐��E���c�����s�Ɍ���Ă��܂����A����̎���́u���E�\�N�v�ł��B
�ނ���u�������̂��ށv�ł��悩�������炢�A�����������ɖ�������Ă���悤�ȋC�����܂����B
�ȑO�A�u���O�Ń��E�\�N�̉��̂��Ƃ����������Ƃ�����܂����A���̎��A���������Ɉ�����烁�[�������܂����B
���E�\�N�̉��ɐl�Ԃ̍����h��͖̂{���ł���B
���X�̑��V�̒��ŁA���x���o�����Ă���܂��B
���̎����炫���Ƃ����u���̐��E�v�̂��Ƃ������Ă���邾�낤�ȂƊ��҂��Ă��܂����B
�{���́A������̗\���҂̂悤�Ȋ����Ŏ��͓ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�C�y�ɓǂ߂��y�Ȗ{�ł����A�����̂悤�ɂ��܂��܂Ȏ��������߂��Ă��܂��B
�������L�����h�����C�t��L�����h���������������a�^���̂��Ƃ���������o�Ă��܂����A
���Ɉ�ې[�������̂́A�t�@���f�[�́u���E�\�N�̉Ȋw�v�̂Ȃ��ɂ���L���ł��B
�t�@���f�[�́A���̖{�Ɏq�ǂ������ɘb�������Ƃ����^���Ă��邻���ł����A
�����Łu��{�̃��E�\�N�ɂ��Ƃ�����̂ɂӂ��킵���l�ɂȂ��Ăق����A
�����āA���E�\�N�̂悤�ɂ܂��̐l�тƂɑ��Č��ƂȂ��ċP���Ăق����v�Ƃ����悤�Șb������Ă��邻���ł��B
�����Ɏv���o���̂́u������Ƃ炷�v�Ƃ������t�ł��傤�B
���������A����ɂȂ��Ȃ���A���������Ă��܂��B
���z�͌�������܂��B
����́A���̑��z���˂��܂��B
�������A�n��̐l�Ԃɂł��邱�Ƃ͓����Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł��B
����́A�����₩�ȓ���������܂���B
���͂����������Ƃ炷���Ƃ��ł��Ȃ���������܂���B
���������A�����ɏ����Ă��܂���������܂���B
����ł��A�l�Ԃɂ͓����Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
����ɂ����t�������܂��B
���E�\�N�͎���̐g���ׂ点�ĔR������́B
���Ȃ��]���ɂ��Ď��͂��Ƃ炷���̂ł��B
�����Ђ����瑼�҂ɗ^���鑶�݂ł���A����́u�����v�̎��H�ɑ��Ȃ�܂���B
���ɂ��Љ�������Ƃ���������Ȃ�܂����A������������قǏ����Ă��܂��܂����B
����������Љ�āA���Ƃ͖{����ǂ�ł��炤���Ƃɂ��܂��傤�B
�푈�Ɗ����Ƃ����l�ނɂƂ��Ă̍ő�̓����������鎅�������E�\�N�̉��̒����猩������悤�ȋC������B
���O�����͒m���Ă����u���E�\�N�̉Ȋw�v���ǂ�ł݂悤�Ǝv���܂��B
�݂Ȃ�����悩������ǂ�ł��������B
����܂ł́u���{�l�̖����v�V���[�Y
���u�������̂��ށv�@�ďC���^��@���㏑��
���u�Ԃ����̂��ށv
�@���^��@���㏑��
�R�����Y���X����w��
���u�K���ƈꏏ�ɎR�o��v�i���K�Y�@���R���[�@2009�@1500�~�j
���҂̒�͎��̑�w�̓����ł��B
����A�����ɗ������ɁA���̖{�̘b���o�܂����B
����ɂȂ����Z���R�o��ŁA��������������Ƃ����b�ł��B
���҂��R�o��ɒ��킵���������������́A�u�R�����ꂽ�K���ɕ����Ȃ��E�C�v�i�����C��j�Ƃ���1���̖{�Ƃ̏o������������ł��B
��������́A�K�����҂ɂ͖����ȂƂ��v����x�m�o�R�A�����u�����o�R�ւ̒���Ől�Ԃ����������Ă��鎩�R�����͂����߂ăK�������������̂������ł��B
���̖{�Ɏh�����ꂽ�A���҂��o�R���J�n�A�ǂ����Ԃɏo������Ƃ������āA��N�A���ɓ��{�S���R�𐧔e�����̂ł��B
�݂̑S�E�o�Ƃ�����p�����Ă���7�N�ڂ̑s���ł��B
�{���́A���̎R���L�����S�ł����A���̑O��ɏ�����Ă��钘�҂̎v����m���ēǂ�ł����ƁA���낢��Ɵ��[�����̂�����܂��B
�ꖡ������o�R�L�Ƃ��Ă��ǂ݂���������Ǝv���܂��B
�̌���ʂ��āA���҂�����Ă��邱�Ƃ��ƂĂ������ɕx��ł��܂����A���̒����炿����ƒ����ł����A��������p�����Ă��炢�܂��B
���̒��ɂ́A���l���a���Ɠ����Ă���̂��A���͂̐l�B���S�Ȃ炸�����ʂƂ��āA�Ԃ��Ă��邱�Ƃ��������������̂ł͂Ȃ����낤���B�������A���̐l�Ƃ��ẮA���Ƃ����Ă��������A�ق��Ă͂����Ȃ��Ƃ����C�����Ȃ̂��낤���A�a���Ɠ����Ă��铖�l�̗���ɗ����Ă̏����Ƃ��������A���͂̐l�Ԃ̗���ɗ����Ă̏����Ɋׂ��Ă��Ȃ����낤���B�a�l�Ȃ̂����疳�����������ɁA�Â��ɂ����Ă����������悢�A���͂Ō�����Ă����Ȃ���ƁA�����҂𗣂ꂽ���͂̏펯����ɂ��������Ɋׂ��Ă��Ȃ����낤���B
�{���A�����҂������̏͂�����悭�������Ă���B�l�Ԃ͎v�����������x�ɂł��Ă���悤���B
�����҂ł�������A�����͂�����܂��B
����ƑΛ����Ă���l�����ɗ͋����G�[���̏��ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�������������������̖{�ɏo����Ă���Ɖ���܂�܂��B
�R�����Y���X�ōw���ł��܂��B
���u��蕔�ƂƂ��ɕ����F��Ó��v�i���o�Ł@1600�~�j
���o�ł̓������炨�b�����������Ă������M��̖{���o�ł���܂����B
���̖{�̖��͂́A�R�l�̃v���t�F�b�V����������Ԃ����o�[�`�����ȌF��Ó��̐��E��
�n�肠���Ă���Ƃ���ł��B
�u�ό��J���X�}�S�I�v�̂P�l�ɂ��I�肳��Ă���A�F��Ó���蕔�̍�{�M������B
���[���b�p�́u�l�ƕ����v�ɏœ_�ĂĊ������Ă���t�H�g�O���t�B�b�N�E���C�^�[�A���O���Y����B
�����āA�N�ǂ́A�u���ƕ���v�̘N�ǂ����C�t���[�N�Ƃ��āA����o���̖T��A�N�lj��u��������S���I�ɓW�J���Ă���A�O�i���̗��\�j����B
���̂R�l���A�ʐ^�ƕ��͂ƘN�ǂŃR���{���[�V�������Ă���̂ł��B
�u��蕔�ƂƂ��ɕ����v�Ƃ���悤�ɁA�Ó��ɉ������ҏW�ɂȂ��Ă���̂ŁA�ʐ^�����Ȃ���ǂݐi�߂Ă����ƁA����H������Ă���悤�ȋC���ɂ��Ђ���܂��B
���̕����̒��ő̊��ł���悤�ȁA���R�̉������ɂb�c���畷���Ă���ƍō��Ȃ̂ł����A�����܂Ŗ]�ނ̂͗~���[������ł��傤�B
�������A�ʐ^�݂͂�ȎB�艺�낵�Ȃ̂ŁA��삳��̑��Â����ƂƂ��ɁA���̕��i�̉��܂ŏ��������Ă���悤�ȗ������܂��B
�����āA�ʐ^�̐��E�ɓ������Ă��鎩���ɋC�Â��悤�ȑ̌����ł��܂��B
��{����葱���Ă���b�̒�����Q�S�b���A�����N�ǂ������̂��b�c�Ƃ��ĕt���Ă��܂��̂ŁA�w�i�ɗ����Ȃ���ʐ^�����Ă���ƁA���x�͎��Ԃ����A�����ЂƂ̌F��Ó��̐��E��̊��ł��܂��B
���̖{��Ў�ɌF��Ó����������A�����Ƃ���ɑ����̋C�Â�������ł��傤�B
�F��Ó�����������Ƃ̂�������ǂ�A���̎��Ƀ^�C���X���b�v�����悤�ȋC���ɂȂ�ł��傤�B
���������Ă������Ȃ��l�ɂ́A�������悤�Ȋ�т�^���Ă����ł��傤�B
�F��Ó���������l���A���������Ǝv���Ă���l���A�����ĂȂɂ����A�F��Ó�������Ȃ��l���A���ꂼ��Ɋ��\�ł��閣�͓I�Ȗ{�ł��B
��ꂽ���ɁA�������Ɩ��키�{�Ƃ��āA���E�߂��܂��B
���u�E�ꂤ�̐��́v
(�L����@���o�Ł@1575�~)
���҂Ƃ͖ʎ����Ȃ��̂ł����A���̗F�l���o�łɊւ���Ă���̂ƁA���̂Ƃ��낱�̘b��ł̑��k�������̂ŁA�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
���҂̍L�삳��́A�u���t�̐S���J�E���Z���[�v�������ł��B
�ŋ߁A�L�����Ă���u�E�ꂤ�v�̐��̂͐l�ԊW�a�A���̕a���ۂ́u���t�v�ł���A�Ƃ����̂��L�삳��̍l���ł��B
�{���͂��̍l���Ɋ�Â��A�E�ꂩ�炤�a���Ȃ����Ă������߂̋�̓I�ȏ���Ⳃ�����Ă��܂��B
�A���A���a���̖{�ł͂���܂���B
�����ł͂Ȃ��A���a���҂ݏo���Ă��܂��悤�ȐE��ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�E�ꂻ�̂��̂����C�ɂ��A���邭���邽�߂̎Е��ϊv�̏���Ⳃƌ����Ă�������������܂���B
���́A��Ђ��̂��̂��u���v�ɂȂ��Ă��錻���ς��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƍl���Ă��܂��̂ŁA�L�삳��̔��z�Ɏ^���ł��B
�ڎ������Ă��炦�킩��܂����A������u���a��v�̖{�ł͂���܂���B
�ނ���E������C�ɂ�����H�I�K�C�h�Ƃ���������������������܂���B
��������C�ɂ��Ă���邽�߂̃K�C�h�u�b�N�ƌ����Ă������ł��傤�B
�ڎ��͎��̒ʂ�ł��B
Part1�@���t���^����X�g���X�Ɓ�������
�@ �P�D�������a���}�����Ă���w�i�����Ă݂�
�@ �Q�D��������̌����Ɖ����̂��߂̃q���g
�@ �R�D����̊ώ@�Ł������M���͔����ł���
�@ �S�D�������ɒǂ����ތ��t�̈ӊO�ȁu���́v
�@
Part2�@�l���������ɒǂ����ތ��t�Ƙb����
�@ �P�D�u�f��v����Α�����������ǂ��߂�
�@ �Q�D�u�Ј��v����ΐ��_�����Ă���
�@ �R�D���l���u�ے�v����Ǝ������ے肳���
�@ �S�D�u���߁v����ь�����Ђɖ����͂Ȃ�
�@ �T�D�u����v�����肾�Ƒ����ǂ��߂Ă���
Part3�@�l������������~�����t�Ƙb����
�@ �P�D�O�����ȋC�����ƍs�����ĂыN����
�@ �Q�D���[�_�[�V�b�v�����b�@
�@ �R�D�قߌ��t���l�𗎂����܂��邱�Ƃ�����
�@ �S�D�قߌ��t�͐l���E������邭����
��Г��ɂ��a�\���R���}�����Ă���Ƃ����܂����A���������Ƃ���ɍŋ߂̊�Ƃ̍ő�̖�肪����Ă���Ƃ����Ă�������������܂���B
���a�̉����ɂȂ��Ă����Ƃ̌����ς��Ȃ���A��Ƃ��̂��̂������s���Ȃ��Ȃ肩�˂܂���B
���Ǐ�̑����́A���͊�Ƃ̐��x�╶���̖��ł��B
�{���͂ƂĂ��ǂ݂₷���A���H�I�Ȗ{�ł����A��Ђ̂�����⎄�B�̐������ɂ��A���܂��܂Ȏ�����^���Ă���܂��B
�悩������ǂ�ł݂Ă��������B
�R�����Y���X�ōw��
���F�m�Ǘ\�h�Q�[���q���ю������@�m�o�n�@�l�F�m�Ǘ\�h�l�b�g�@1000�~�r
����͈�ʏ��X�ł͍w���ł��Ȃ��{�̂��Љ�ł��B
���̃T�C�g�ɂ͂�����Ƒ��������Ȃ���������܂��A����������ނ̖{�����ꂩ�班���Љ�Ă��������Ǝv�������܂����B
���̖{�́A�T�ԕɏ������悤���A������s�ł���������҂̍��т��炢���������̂ł��B
�����āA���̃e�L�X�g�����܂ꂽ�o�܂Ƃ��̃e�L�X�g���琶�܂ꂽ��������낢��Ƃ��������܂����B
�F�m�ǂɊւ��ẮA���܂��܂ȃe�L�X�g�⏑�Ђ��o�Ă��܂��B
�{���Ɠ������u�F�m�Ǘ\�h�Q�[���v���������{������܂��B
�ɂ�������炸�A�������̖{�������ŏЉ�悤�Ǝv�����̂́A���҂̍��т���̔M���v��������������ł��B
���т���͎�����10�ΔN��ł�����A�Ԃ��Ȃ�80�ł��B
�F�m�ǂɊS�������o�����̂́A������30�N�ȏ�O�ɂ������̂��ꂳ�F�m�ǂǂ��A���ꂪ�_�@�ɂȂ����悤�ł��B
15�N�قǑO�ɁA�É��̍���҃��t���b�V���Z���^�[�̑��c���m�q����Ƃ��������J�����ꂽ�A�X���[�`�����̔F�m�Ǘ\�h�̍l�����ɏo��A���̍l���̗L�������������Ŋm���߂��Ă���A�����S���ɍL���Ă��������Ƃ����v������A���Ԃƈꏏ�ɂm�o�n�𗧂��グ�Ċ������J�n�����̂ł��B
���́A����10�N�A�e�n�ł̂��܂��܂ȕ����W�̊����ɂ����₩�Ɋւ�点�Ă�����Ă��܂����A���̂������Łu�z�����m�v�Ɓu�����łȂ����́v�Ƃ��������邱�Ƃ����������ł���悤�ɂȂ��Ă��܂����B
���ѕ����́A�w��I�ɂ͌�����Ă���킯�ł͂���܂���B
�����g�A���̐��ʂڒm���Ă���킯�ł�����܂���B
�ł��A���т���Ƙb���Ă���ƁA�Q�[���̐��ʁA���邢�͌��C�̐��ʂ��ڂɌ����Ă���̂ł��B
����ō��т����̊������ł���͈͂ʼn������悤�Ǝv�����̂ł��B
�{���̓��e�́A�����̒ʂ�A�Q�[���̐i�ߕ��̃e�L�X�g�ł��B
���������̑O�ƌ��ɁA��{�I�ȍl�������Ȍ��ɏq�ׂ��Ă��܂��B
�܂��A���̃e�L�X�g�̗��p�@�����J�ɏ�����Ă��܂��B
�ł���A�F����̂��Z�܂��̒n��ɂ���A�n���x���Z���^�[��f�C�T�[�r�X�{�݂ȂǂɁA���̖{�����Љ����������ꂵ���ł��B
���т������u�t�ɏ����āA�u�����~�j���C��Ȃǂ���悵�Ă��炦������Ƃ��ꂵ���ł��B
���т���ɘA���������ꍇ�́A���̓d�b�ԍ��ɂ��d�b���������B
���т���́A�ƂĂ��C�����ɓd�b�����Ă�������͂��ł��B
�O�V�V�S�|�S�T�|�Q�W�R�T
�{���̍w���́A�m�o�n�@�l�F�m�Ǘ\�h�l�b�g�̃z�[���y�[�W���炨�肢���܂��B
���̃z�[���y�[�W�ɂ́A�X���[�`�̍l�����⍂�т����̊������ڂ��Ă��܂��B
�����Ă�������������Ǝv���܂��B
���w�����p���`�x��2��
�i���|��q�@��g�u�b�N���b�g�@800�~�j
�R���P�A���Ԃ̏��|��q����i�s���������I�t�B�X�E�n�X�J�b�v��\�j���܂Ƃ߂��A�����̂킩��₷���u�b�N���b�g�w�����p���`�x�����e��V����������2�ł��ł��܂����B
���ی��̊�{�I�Ȃ����݂�����̋�̓I���e�A�������Ƃ��̉������@�A�֘A���Ȃǂ��A65�̗p��ɂ킯�āA���p����s���̗��ꂩ��������Ă��܂��B
���H�����̒����琶�܂�Ă��Ă���{�ł��̂ŁA���G�ɂȂ��āA�܂��܂��킩��ɂ����Ȃ��Ă��Ă����쐧�x�𗝉����邽�߂ɕK���𗧂Ǝv���܂��B
�s���������I�t�B�X�E�n�X�J�b�v�ł́A�����}�K�����s���Ă��܂��B
���̕���Ɋւ���Ă�����́A�����}�K���\�����܂��Ƃ����Ǝv���܂��B
�z�[���y�[�W����\�����߂܂��B
���̖{�̓e�L�X�g�Ȃǂɂ������Ă��܂��B
5���ȏゾ�ƒ��Ҋ��������p�ł��邻���ł��B
���������s���������I�t�B�X�E�n�X�J�b�v�܂ł��\�����݂��������B
���u�Z�p�ƃR���v���C�A���X�v�i���{���@�ۑP�@1500�~�j
���{�ł́u�R���v���C�A���X�v�Ƃ������t���ɂ߂Ă��s����`�I�Ɏg���Ă��܂��B
��ʓI�Ɂu�@�ߏ���v�Ɩ�܂����A�ʂ����Ă���ł����̂��Ƃ����Ǝv���Ă��܂������A����Ɋւ��Ă���߂Ė��m�ɁA���ꂪ��Ƌ����Ă��ꂽ�̂����{����ł��B
����Ɋւ��Ă͈ȑO�b�v�r�v���C�x�[�g�ł��Љ�����Ƃ�����܂����A���ꂪ�ƂĂ��킩��₷���{�ɂȂ�܂����B
��T�Љ���u�Z�p�җϗ��]�@�Ɨϗ��̃K�C�h���C���v�Ɠ������e�L�X�g���̃X�^�C���̖{�ł��B
����̕���́A�u�@�߂Ɨϗ��̃K�C�h���C���v�ł��B
�������A�����ɂ��e�L�X�g���Ȃ̂ŏ��������Ă��܂���������܂��A���e�͂ƂĂ��ǂ݂₷���A�����ɕx��ł��܂��B
���{���{�����������Ӑ}�͂Q����܂��B
�R���v���C�A���X�����ꂾ���b��ɂȂ��Ă���̂ɁA�K���s���@�Ɋւ�����发���Ȃ������̂������ł��B
���̂��߁A���{�̃R���v���C�A���X�����Ɋւ��鍬��������̂ł͂Ȃ����B���{����́A���̊Ԍ��߂��������̂ł��B
�Z�p�ƌo�c�Ɩ@�����A���ꂼ�ꂵ������Ɗw�ё̌����Ă������{����Ȃ�ł͂̓��发�ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
������́A�Љ�I�M���������Ă��Ă����Ƃւ̐M���̂��߂�
�A���̂���R���v���C�A���X�������L���Ă��������Ƃ����A���{����̐[���v���ł��B
����͐��{����̃��C�t���[�N�Ƃ����Ă����ł��傤�B
���̘b�����Ă���Ƃ��̐��{����́A���X�A�S�C����قǂ̔M�ӂ������邱�Ƃ�����܂��B
��Ƃ̋Z�p�҂݂̂Ȃ���ɂ́A���Гǂ�łق����{�ł��B
�ڎ����Љ�܂����A�e���ڂƂ��[�����e������߂ĊȌ��ɗv�_���܂Ƃ߂Ă��܂��̂ŁA�Z�����Z�p�҂ɂ��Z���ԂŃ}�X�^�[�ł��܂��A
�������A�ł���A��T�Љ���{�Ƃ��킹�āA���Њ�Ɠ��ł̓Ǐ���������n�߂Ăق����ł��B
�݂�ȂŘb�������ƁA�����Ƃ����ɂ��߂�ꂽ�[���Ӗ����w�ׂ�͂��ł��B
���t�����̂l�n�s�Ȃǂ����A��قlj��l������Ǝv���܂��̂ŁB
�ڎ��͈ȉ��̒ʂ�ł��B
��������Ă��A���{����̔��z�@���킩��Ǝv���܂��B
�P�@�R���v���C�A���X�̈Ӗ�
�Q�@�R���v���C�A���X���̎n�܂�
�R�@�s�����Ȗ@���͕s���̉���
�S�@�s���葱�@�͌��
�T�@���卑�̋K���s��
�U�@�s���҂Ǝ��Ǝ҂̊W
�V�@�K���@�߂Ƃ͉���
�W�@�R���v���C�A���X�̌o�c���f
���u�Z�p�җϗ��]�@�Ɨϗ��̃K�C�h���C���v�i���{�i�@�c���G�a�@���{�`���@�ۑP
1500�~�j
�Z�p�җϗ��̕�������{�̊�Ƃɒ蒅���������Ƃ����[���v������A
�����u���A������ȂǂŊ���Ă��鐙�{�����̒��삪������2���o�܂����B
����͂��̂�����1�������Љ�܂��B
���T�͎��Ԃ��Ȃ��āA1�������ǂ߂Ȃ���������ł��B
���{�����́A��w�������̃e�L�X�g�͂��łɊ��������Ă���A���̃R�[�i�[�ł��Љ���Ă��炢�܂����B
����I�ɂ��̓��e���������Ă���X�^�C���ŁA���łɌ��ݑ�4�łɂȂ��Ă��܂��B
���̃e�L�X�g���g���āA�������̑�w�ł��łɍu����W�J���Ă��܂����A��Ƃ̋Z�p�҂ɂ���������ƋZ�p�җϗ��̕�����蒅���������ƍŋ߂͊�Ƃł̌��C�Ȃǂɂ����g��ł��܂����B
�����Đ��{����炵�����\�h���W�[���J�����A���ʂ������Ă���Ƃ��������Ă��܂������A���̃e�L�X�g�����������̂ł��B
����1�����{���ł��B
�ł�����{���́A��ƂȂǂ̎����Ɏ��g�ސl��ΏۂƂ����{�ł����A��Ƃł̊����ɂ܂��u�@�Ɨϗ��v�ɂ��āA�ƂĂ��킩��₷���T�ς��Ă��܂��̂ŁA�����̊�Ɛl�ɓǂ�ł��炢�����{�ł��B
��̓I�Ȏ�����A�����������Ԃ̃n�u�j�����������A���{�①�̓������������A�ϐk�U�������ȂǁA�U�̎��������グ���Ă��܂��B
�ς��������Ƃ��ẮA������s�̂܂��Â����ጟ���ψ���́u���v�����v���������グ���Ă��܂��B
�u���v�����v���́A�����ŋߊS�������Ă���̂ł����A���ꂩ��̃R�~���j�e�B��A�\�V�G�[�V�������l����Ƃ��̃L�[���[�h�̂ЂƂɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�܂�����͂Ƃ������A�{���͂Ƃ������ǂ݂₷���A�e���߂܂��B
����͐��{����炵���A�p�����������ƍ\���I�ɒ�`���Ȃ���A�Ȍ��ɋL�q���Ă��邩��ł��B
�Z�p�җϗ��Ƃ����Ɠ�����ł����A�O�҂����Ղȓ����ŏ�����Ă��܂����A�b����R�~���j�e�B�Ƃ͉����Ƃ������b�܂ŕ�܂��āA�傫�Șg�g�݂Ō���Ă���̂��ƂĂ������ł��B
���e�I�ȏЉ�ɂȂ��Ă��܂��A�ǂ�������ǂ�ł��������B
������Ƃ̋Z�p�҂̕��ł���A���Ў��ӂ̋Z�p�҂ƕ���Ȃǂ�����Ă��炦����ꂵ���ł��B
�������{������u�t�ŌĂт����Ƃ������Ƃł���A���Ԃ��������A���{����͂����ƈ����Ă����Ǝv���܂��B
�܂��A����ȏ�A���{�����Z�����ڂɍ��킹�����Ȃ��̂ł����B
���T�́A����1���́u�Z�p�ƃR���v���C�A���X�v���Љ�܂��B
���x�͓��e���܂߂āB
���u�Ԃ����̂��ށv�i���^��@���㏑�с@1300�~�j
�O�ɂ��Љ���u�������̂��ށv�ɂÂ��A�u���{�l�̖����v�V���[�Y��2�e�ł��B
������O���������Ă���ȂƊ������̂́A���͂��S�̂̂P/�R���߂Ă��邩��ł��B
���͂́u���̂��������A�S�̖��\��v�Ƒ肳��Ă��܂����A�����Ɉ������̉Ԃւ̎v������C�ɏ�����Ă��܂��B
�������́A�����Ɗy����ŏ������̂ł��傤�B
�Ԃ͂��܂�ɍL���e�[�}�Ȃ̂ŁA�ǂ��荞�ނ��S�������Ă��܂������A�������炵���A�������Ղ����ɂ��ď����o���Ă��܂��B
�܂��Ɉ������̃z�[���O���E���h�ł��B
�����͂����Ă��A�������炵���A�b��͌Í������A���Ɍy�₩�ɍL�����Ă��܂�����A�����邱�Ƃ�����܂���B
�u�Ԃ͂��̐��̂��̂Ƃ��Ă͔���������v�ƈ������͏����Ă��܂��B
�n�b�Ƃ���悤�Ȍ��t�ł��B
�������A���̔������ɂǂ̂��炢�̐l���C�Â��Ă��邩�B
�����A�Ԃ̔������ɋC�Â����͍̂ŋ߂ł��B
����܂ł̓o���Ƃ��J�T�u�����J�Ƃ��A�u���O�̂���ԁv�ɖڂ��s�������ł������A���̂������A�ςȌ������ł����A�Ԃ͒P�ɉԂł����B
��R�ɍ炭�����ȉԂ��D���ł������A�������ƒ��߂����Ƃ�����܂���ł����B
���̖��͂������Ă��ꂽ�͍̂Ȃł����B
�Ԃ́A����Ώۂł͂Ȃ��A���ɂ��鑶�݂Ȃ̂��ƁA�Ȃ����Ȃ��Ȃ��Ă������ƋC�Â�����܂����B
�Ԃ̔������́A�S��ʂ킹�Ă͂��߂Č����Ă���A�����ɐ��ށu�₳�����v�Ɓu���Ȃ����v�Ȃ̂�������܂���B
�������́A�Ԃ͂��̂��̃V���{�����Ƃ����܂��B
���̂��̔������������Ă���Ă���̂�������܂���B
�Ԃ͂܂��l���Ȃ����̂ł�����܂��B
�������́A�Ԃ͕��a�̃V���{�����Ƃ������܂��B
3�N�O�ɐX�̎O��s�ŏZ�������̉Ԃ����ς������ɂ����₩�Ɋւ�点�Ă��炤���Ƃ�����܂����B
�u�Ԃ���Ă悤�v�Ƃ����v�����A�Z���������Ȃ������A���ł́u�܂�����Ă�v�����ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�܂��ɉԂ͕��a�ɂȂ����Ă��܂��B
���̂��ƕ��a�B
�{���͂������ɂ��āA�Ԃ̂��̂��ݕ������܂��܂Ȏ��_����Љ�Ă��܂��B
�e�[�}���L�����邱�Ƃ������āA�������̃��b�Z�[�W�������ア�̂��C�ɂȂ�܂����A���̕��A����Ȃ�Ɠǂ߂邩������܂���B
���l�ԊW��ǂ�����P�V�̖��@�i���^��@�v�m�o�ŎЁ@1400�~�i�ŕʁj�j
�������̍��N�ŏ��̖{�́u�l�ԊW�v�ł����B
�Ƃ����Ă��A�\�w�I�ȃe�N�j�b�N�_�ł͂���܂���B
�������Ȃ�ł͂̐l�ԊW�_�ł��B
�������́A�u�ǂ��l�ԊW�Â���v�̂��߂ɂ́A�܂��̓}�i�[�Ƃ��Ă̗�V��@���K�v���Ƃ����܂��B
�ł�����{���́A��V��@�̖{�ł�����܂��B
���܂����V��@�H�@�ȂǂƂ��킸�ɁA���Ђ��ǂ݂��������B
���܂�ɂ���{�����낻���ɂ���Ă���̂��A���̓��{�ł�����B
�{����ǂނƂ��낢��Ȃ��ƂɋC�Â������͂��ł��B
�������Ȃ��ׂ����Ƃ����낢��Ƃ���܂����B
�������͓��{�̗�@�̊�{�ł��鏬�}�����̖Ƌ��F�`��26�ŋ�����Ă��܂��B
�����āA��������ۂ̐������ƌo�c�̖ʂł�������Ǝ��H����Ă���̂ł��B
���}������@�̊�{�́A�u�v�����̐S�v�u����܂��̐S�v�u���݂̐S�v�Ƃ����R�̐S���ɂ��邱�Ƃ��ƈ������͌����܂��B
�������������Ǝ���Ă���A�l�ԊW�Ŕς킳��邱�Ƃ͂Ȃ��A�ނ���l�ԊW�Ɏx�����Ă����Ƃ����̂ł��B
���̂����₩�Ȍo��������ƂĂ������͂�����A���Ȃ����邱�Ƃ������ł��B
�Q�������p�����Ă��炢�܂��B
�����Ɉ������́A�l�ԊW�ς��o�Ă��܂��B
�{���ɑ�Ȃ��̂Ƃ́A�l�Ԃ́u������v�ɑ��Ȃ�܂���B
���̖ڂɌ����Ȃ��u������v��ڂɌ�����u�������v�ɂ��Ă������̂������A
�������U�镑���ł���A���A�ł���A�����V�ł���A���ł���A����Ȃǂł͂Ȃ��ł��傤���B
�����̂����@�Ƃ́A�܂�Ƃ���u�l�ԊW��ǂ����閂�@�v�Ȃ̂ł��B
���ǁA�l�ԊW��ǂ����邱�Ƃ͂������A
�S�䂽���ȎЉ�����邽�߂̍ő�̃J�M�����A�������̗�\�͂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���҂ւ́u�v�����v�̐S���炢��Ȃ��̂͂���܂���B
�X�^�C���X�g�̏�����ł���������́A�{���ł��X�^�C���ɂ�������Ă��܂��B
�{���̍\���́u�P�V�̖��@�v�ƃ^�C�g������Ă��܂��B
�����āA�P�V�̂��ꂼ��̏͂̍Ō�ɁA���e��v��������̒Z�́i���́j���f�ڂ���Ă��܂��B
������y���݂Ȃ��玷�M�������Ƃ��`����Ă��܂��B
�l�ԊW��P�Ȃ�l�̏����p�ƈʒu�Â��Ă��Ȃ��̂������ł��܂��B
�Ō�ɁA���E��ǂ����鋆�ɂ̖��@��������Ă��܂��B
�l�Ԃ͈�l�����ł͐����Ă����܂���B
�Љ�Ɗւ��K�v������܂��B
�Љ�̒��ɂ����āA���Ȃ����ǂ��l�ԊW��z���A���A���ׂĂ̐l���K���ɂȂ�铹�Ƃ͉��ł��傤���B
���̖₢�����Ɉ������́A���������Ă��܂��B
����́u�u�v�ł��B
�u�Ƃ́A�S���ڎw�������A�܂�S�̃x�N�g���B
�܂�{���͐������̎w�쏑�Ȃ̂ł��B
�y�����ǂ߂܂��̂ŁA���Ђ��ǂ݂��������B
�R�����Y���X
�����{�̖����Ǝs���Љ�̉\���i��c���g�D�]��������ҁ@2008�@900�~�j
����Љ���u�m�o�n�V����v�̒��҂̓c������ɂ��Ă����c���g�D�]��������ł̋c�_�𒆐S�ɁA�m�o�n�@�l�̌��_�m�o�n���u�b�N���b�g�ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B
�u�m�o�n�V����v�ł̘_�_�̔w�i��Ӗ��������A�c�_��ʂ��ē`����Ă��܂��̂ŁA���s���ēǂ܂��Ɩʔ����ł��B
������̃����o�[�ɉ����āA�Q�X�g�Ƃ��āA���c���l����A�����h�ꂳ��A�쒆�莟�Y����A���^��q����A�Ғ��L����A�E�H���t�K���O�E�p�[���Q�����Ă��܂����A���ꂼ��̎v�l���悭�����Ă��܂��B
�u�m�o�n�V����v�̏Љ�ł������܂������A�킪���łm�o�n�@���{�s����Ă���10�N�������܂��B
���̌��߂����Ȃ茩���Ă��܂������A����܂��ďZ��������s�������͂��ꂩ��ς���Ă����悤�Ɏv���܂��B
�������A�m�o�n���������Ă��Ă͂��Ԃ��͌����Ă��Ȃ��ł��傤�B
���̈Ӗ��ŁA�{���̂悤�ȕ��L���c�_�͎����ɕx��ł��܂��B
���{�ł́A�m�o�n�̈Ӗ��������܂��Ȃ܂܂ɂ��āA�Z�����z�̌��ꎋ�_�̂��̂��A�s���Љ�u���̂��̂��A�ꏏ�Ɍ���Ă��܂����A���҂͑S����������̂��Ƃ����C�����܂��B
�T�u�V�X�e���Ƃ��Ă̂m�o�n��s���Љ�_�ł͂Ȃ��A�C�m�x�[�V�����Ƃ��Ă̏Z��������s�������A���邢�͎Љ�̂��̂̊T�O�Ƃ��Ă̎s���Љ�ɁA���͊S������̂ł����A�����������_����{����ǂނƁA���ꂼ��̃Q�X�g�̖���N�͎����ɕx��ł��܂��B
�������ɖʔ��������̂́A�Ғ�����́u������A������̑��݈Ӗ��̑傫���v�Ɋւ���w�E�ł��B
�Ғ�����͂��������Ă��܂��B
��������͂��߁A���܂��܂Ȓc�̂����ׂĊ܂߂�ƁA���{�ł͂��̂������n��l�b�g���[�N������߂��炳��Ă��܂��B
��V�͔N�ԂQ���~�Ƃ��A���ꂩ�班���o��A�������������Ȃ����ŁA�����ψ��⍑�������̒������Ȃǂ��܂߂āA�F�������Ă���̂����{�̈�̌����ł��B
�����������]�[�~�b�N�Ȏs���Љ���m�o�n�@���Ă��܂����悤�Ȍ��O�����͎����Ă��܂��B
��삳��̎s���Љ�_���ʔ����ł��B
NPO�����ׂ����Ƃ́A�s���Љ�Ő���������ƒm��A�Љ�������ƒm��A�����ɐ����グ�Ă�����s��������Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ƃ������ƁB���ꂪ�m���v�E���t�B�b�g�Z�N�^�[�̐ӔC�ł��낤�Ǝv���̂ł��B
���̊S���Ƃ͏����Ⴂ�܂����A���̂m�o�n���z����ɂ���̂ł�������ł��܂��B
�{�������œǂ�ł��ʔ����ł��B
�R�����Y���X����������ł��܂��B
���z���N�n�C�}�[�̎Љ���Ə����h�C�c�Љ�w�i��G���@�Љ�]�_�Ё@3200�~�j
�v���Ԃ�Ɋw�p�I�Ȑ�发��ǂ݂܂����B
���҂̓킳��́A���̗F�l�̃p�[�g�i�[�ł��B
��x�A�킪�Ƃɂ����Ă��ꂽ���Ƃ�����܂����A
�킳������������̌����҂ł��邱�Ƃ͑S���m��܂���ł����B
���̓킳�A��N���ɖ{�����Ă���܂����B
���̕���͑傢�ɊS�̂���Ƃ���Ȃ̂ł����A�v���Ԃ�̐�发�ł���A�����A��킵�܂����B
�������A�m�荇���̏������{�͂�������Ɠǂ�ł��̃R�[�i�[�ŏЉ��̂����̃��[���ł��̂ŁA�ǂ܂Ȃ��킯�ɂ͂����܂���B
�N������ǂݏo���A�ɂ�������i�K���ɂ����Ȃ肠�����̂ł����j�{�����J���Ă��܂������A���ǂ̎�������ɐi�݂܂���B
�Ƃ��낪�A��S�͂ɂȂ��ēˑR���E���J�����悤�ɖʔ����Ȃ����̂ł��B
�ǂݏI������́A���̑������ǂ݂����Ǝv�����قǂł��B
����̎Љ��ǂ݉����q���g����������܂܂�Ă��܂��B
������x�̊o��͕K�v�ł����A����Љ�̐�s���ɊS�̂�����ɂ��E�߂��܂��B
�Ƃ���ŁA�z���N�n�C�}�[�͒p�������Ȃ���A���̓t�����N�t���g��w�̎Љ�����̏������������Ƃ����m��܂���ł����B
���̎咣��ƐтȂǂ͑S���m��Ȃ������̂ł��B
�ł�����{���͎��ɂƂ��ẮA���ׂĒm��Ȃ����Ƃ���ł����B
�������ǂ�ł��邤���ɁA�Ȃ����ƂĂ��e���݂������o���܂����B
���̎咣����@�_�ɂ��A�ƂĂ������ł��܂����B
�z���N�n�C�}�[�̓��_���n�̃h�C�c�̎Љ�w�҂ł��B
���܂��1895�N�B1930�N�Ƀt�����N�t���g��w�̎Љ�������̏����ɂȂ�A
�J���҂̌���ƃt�@�V�Y���I�ȐS����₤���ؒ����ȂǂɎ��g�h�C�c���\����m���l�̈�l�ł��B
�ꍑ���P�����t�@�b�V�Y���i�i�`�Y���j�ɑ��āA�����Ă���ɃX�^�[������`�ɑ��Ď��R�̂��߂ɓ������A�M�O�̐l�ł�����܂��B
������t�����N�t���g�w�h���\�����l�ł��B
�z���N�n�C�}�[�̌��������̏o���_�͌��ۊw�ł������A��������B���_�A�Љ�w�ւƍL����A�Љ�N�w�ւƌ������Ă����܂��B
�{���͂��������z���N�n�C�}�[�̎v�z�`���̉ߒ��J�ɒǂ������Ă����܂��B
�{���̑тɁA�u�Љ��ᔻ����Љ�v�z�̌��^�������яオ��v�Ə����Ă���܂����A�܂��ɂ��̒ʂ�ł��B
���e�͂��Ȃ���I�œ���̂ł����A�w���̍��w�����������O�����X�Əo�Ă��܂��̂ŁA�����[���ǂݐi�߂��܂��B
����ɁA���l�Ȏv�z���L���肾���Ă������C�}�[������̃h�C�c�̒m�I���̂Ȃ��ŁA�z���N�n�C�}�[���������^�����ӎ��́A�����Ɍ��݂̎Љ�Ɍq�����Ă���悤�Ɋ����܂��B
���Ƃ��A�ߑ�̗v�f�Ҍ���`�����z���j�b�N�Ȕ��z�ⓝ���҂̓N�w�Ƃ͑ΏƓI�Ȍ��ꂩ��̓N�w�̉�����������܂����B
�����Ƃ��A����͌�����Ă��钘�҂̓킳��̈ӎ����e�����Ă���̂�������܂���B
���邢�́A�����̎Љ�w�Ƃ̍��ى���ڎw���Ă����A�z���N�n�C�}�[�̎Љ���̓��B�_�̉f�����d�Ȃ��Ă���̂�������܂���B
�������A������ɂ���A�����Ō���Ă��邱�Ƃ͂��ꂩ��̎�����l�����ł̃q���g����������܈ӂ���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�㔼�ł́A�h�C�c�Љ�w�̐��藧���̌o�܂��_�Ԍ����܂����A����͂ƂĂ������[�������ł��B
���̕n��Ȓm�����A���낢��ȈӖ��Ŏh����^�����A���̒��ŏ�����݂������Ă���悤�ȋC�ɂ��Ȃ�܂����B
�z���N�n�C�}�[���A���̌㏑�����w�[�ւُؖ̕@�x���ǂ�ł݂����Ȃ�܂����B
���I�Ȋw�p���ł��̂ŁA�����ȒP�ɂ����߂͂ł��܂��A
�Љ������ڂ�{�����߂ɂ͂ƂĂ�������������܂��B
�悩�����炨�ǂ݂��������B
�����킳��ɘb�������Ǝv���Ă��܂��̂ŁA�ǂ܂ꂽ���ł���]�̕���������A�����Ă��������B
�ꏏ�ɘb�����������܂��傤�B
�R�����Y���X����������ł��܂��B
���Z�p�҂̗ϗ������S���i���{���E����d���@�ۑP�@2008�j
���N�ŏ��̂��Љ���Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[������\�̐��{����̐S�����߂��Z�p�җϗ��̃e�L�X�g�ł��B
�ȑO�A��R�ł��Љ���Ƃ��ɂ������܂������A���̖{�ɂ͐��{����̔M���v�����������Ă���̂ł��B
������邳��̎v���������ł����A���{����͓��u���������邳���2006�N�Ɍ������Ă��܂��B
�����Z���Ԃł͂���܂����A���邳��ƌ𗬂����Ă��炢�܂������A
���̂��l���͎��ɖ��͓I�ŁA�����������낢��Ƃ��b�������������������Ǝc�O�łȂ�܂���B
���̍��邳��̋Ɛтł�����]�ؔ��d����e�̔����̃G�s�\�[�h���lj�����Ă��܂��B
�Z���Љ�ł����A�����ɍ��߂�ꂽ���҂����̎v���͋��ɉ����܂��B
�{�̓��e�Ɋւ��ẮA��R�ł̏Љ��ǂ�ł��������B
�����̐l�ɓǂ�łق����{�̂P���ł��B
�����E�́u���l�v�u���l�v���悭�킩��{�i���^��ďC�@�o�g�o���Ɂ@648�~�i�ŕʁj�j
�u�_�Ђ֍s�����v�ɑ����A�������̍ŐV�ďC�{�ł��B
�������͗�ɂ���āA��������Ɓu�܂������v�������Ă��܂��B
�{���͐l�Ԃ̃J�^���O�Ȃ̂��B������A�ʔ����B
�u���l�v�ɂ���u���l�v�ɂ���A�ߏ�Ȑl�Ԃɂ��Ēm�邱�Ƃقǎh���I�Ń��N���N���邱�Ƃ͂Ȃ��B
�Ȃ��Ȃ�A�킽�������͐l�Ԃ����炾�B
�l�ԂɂƂ��Ĉ�Ԗʔ������̂͐l�ԂɌ��܂��Ă���ł͂Ȃ����B
�킽���́A�u�ʔ������l�ԁI�v�Ƌ��т����C���ł���B
�����ɂ��������炵���ł��B
����ɂ��Ă������Ȑl���o�ꂵ�Ă��܂��B
���̐��A���l66�l�A���l47�l�ł��B
���l�̐��������̂��s���ł����A
�������������Ă���悤�ɁA���l�Ɩ��l�͕\����̂̑��݂ł�����A
����Ȃ��Ƃ͋C�ɂ���̂��ԈႢ�ł��傤�B
���ɂ͖��O���m��Ȃ������l�����Ȃ�����܂��A
�܂����Ԃ̂��鎞�ɂς�ς�ƓǂނƖʔ����ł��B
���ɂƂ��ẮA�ǂ��炩�Ƃ����A���l�҂̂ق��Ɏ��グ��ꂽ�l�̂ق������͓I�ł����B
�C���]���ɁA���܂ɂ͂���Ȗ{���������ł��傤���B
113�l�̐��l���l�̃G�s�\�[�h���܂Ƃ߂ēǂނ̂́A�ӊO�Ǝh���I�ł��B
�m���Ă����悤�Œm��Ȃ��A�ʔ����G�s�\�[�h�ɂ��o��܂��B
�ދ����Ă���l�ɂ͂��E�߂��܂��B
���E��������ƍL���Ȃ邩������܂���B
�R�����Y���X
���m�o�n�V�����i�c���퐶�@���Ώ��X�@2008�j
�v���Ԃ�ɋ����ł���m�o�n�W�̖{��ǂ݂܂����B
�m�o�n�ƊE�{�ł͂Ȃ��A�s���Љ�Ɏ��_��u�����m�o�n�_�ł��̂ŁA
�m�o�n�W�҂����ł͂Ȃ������̐l�ɂ��Гǂ�ŗ~�����{�ł��B
�c������̂m�o�n�W�̖{�͉������ł��Љ�܂����B
���ɑO����u�m�o�n������������v�́A�m�o�n�ƊE�ɐV��������N��������̂ł������A
�{���́A���̖���������{�I�Ȏ��_�ƓW�]��^���Ă������̂ł��B
�m�o�n�_�Ƃ��������A�s���Љ�_�Ƃ��ēǂނ̂�������������܂���B
����́u�s�����n���̂��߂Ɂv�Ƃ���܂����A�c������͂����ɂm�o�n�̖��������҂��Ă��܂��B
�c������́A���������Ă��܂��B
�����̂m�o�n�Ōo�c�Z�p�⎑�����B���@���邢�͌ڋq�J����@�ȂǁA�Z�p�I�ȑ��ʂ���l�X�Ȏ��g�݂��Ȃ���A���ɗ������������Ă��܂��B
�����������ɁA���ꂾ���ł͖��̊m�M�ɓ͂��Ă��Ȃ��Ǝ��͊����Ă��܂����B
�����čs���������̂�
�u�m�o�n�Ƃ͖{�������߂����Ă����̂��B�ق���̂Ƃ��āA�߂����ׂ����f���͂ǂ��ɂ���̂��v
�Ƃ����₢�����ł����B
���̖₢�̐�ɂ������̂́A���{�̎s���Љ���ǂ��ĕ҂���̂��Ƃ����ۑ�ł��������̂ł��B
�c�����́A��t��{�����e�B�A�ɑ���ĔF�����Ăт����Ă��܂��B
�m�o�n�͎s�����n���Ƃ���������ʂ��ē��{�̎s���Љ�ĕ҂ɍv������Ƃ����A�傫�ȉ\�����߂Ă��܂��B
���������������ʂ������߂ɂ́A�܂��m�o�n���Q���҂Ƃ��Ă̎s���Ƃ̂Ȃ������葾�����䂭���Ƃ��d�v�ł���A
���̂��߂ɂ́A��������t���{�����e�B�A�Ƃ̂Ȃ�������ĔF�����邱�Ƃ��K�v�ł��B
�m�o�n�@�l�͋}�����܂������A�{�����e�B�A�l���͂ނ��댸�����Ă���Ƃ������v������܂��B
���ی����x�̓����ɔ����A�ߗׂ̎x�������������Ă��܂����Ƃ�����������܂������A
���{�^�̃{�����e�B�A�����͂m�o�n�̍L����̒��ŕω����Ă��Ă���̂�������܂���B
��t�����Ɋւ��Ă��A���{�^�̊�t�����������Ƃ���Ă���悤�Ɏv���܂��B
�����g�́A�c������Ƃ�����ƌ����̈Ⴄ�Ƃ��������܂����A
�c������̎咣�͐����͂�����A���H�I�ŁA�����ɕx��ł��܂��B
�o�r�s�i�p�u���b�N�E�T�|�[�g�E�e�X�g�j���d�����Ă���̂́A�c������̎��_�̏��݂��ے����Ă��܂��B
�o�r�s�𒆐S�ɂ������s���Љ�̕��������킩��₷����Ă���Ă��܂��B
�����������Ƃ͂��낢�날��܂����A
�������A���Ж{����ǂ�łق����Ǝv���܂��̂ŁA���r���[�ȏЉ�͍����T���܂��B
�m�o�n�W�҂͂������ł����A�m�o�n�Ɉ�a�����������̕��ɂ��A���邢�͊�ƊW�҂ɂ��A���E�߂������{�ł��B
����Œn���Ɋ������Ă���l�����ɂ́A���C��^���Ă����͂��ł��B
�R�����Y���X�o�R�ŃA�}�]��������w���ł��܂��B
�ڎ��Ȃǂ͂����Ō��Ă��������B
�������̂��삳���i����䍲�q�@�p��I��
2008�j
���j�́A���̎����Ǝ���ɂ���āA�S���ʂ̐��E�������Ă���܂��B
���₳��̌�閾���吳�ɂ́A�����V�N�Ȕ���������܂����A
����̃e�[�}�u�����̂��삳�܁v�́A���̃^�C�g�����炵�āA�V�������z��\���������܂��B
�������A�{�����J���܂łɂ͂��������̎��Ԃ��K�v�ł����B
���̖{�̓��e�Ȃǂ́A���₳��̃u���O�����Ă��������B
�����o�������@�₱�̖{�ւ̍��₳��̎v�����A���ɑf���ɏ�����Ă��܂��B
���₳��������Ă��܂����A�{���́A
�u�����j�����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A
���̓����̐V����G���Ɏ��ۂɏ�����Ă����L������ǂݎ��邱�Ƃ��A
�����Ȃ�ɐ������ď������v
���̂ł��B
�ł�������ɐ��������Ƃ��Ă��܂����A�����̂悤�ɁA�����ȃG�s�\�[�h�≡���̘b���ӂ�ɓo�ꂵ�܂��B
���₳��̖{�̖ʔ����̈�́A�����ɂ���Ǝ��͂����v���Ă��܂��B
����́A���₳�c��Ȏ����̒��ɖ�����Ȃ���A���̐��E���y����ł��邱�Ƃ̏؍��ł�����܂��B
���₳��́A�O�Ɏ��g���䌷�ցi�u�H���y�̐l�@���䌷�ցv�j�⍑�ؓc�ƕ��i�u�ҏW�ҁ@���ؓc�ƕ��̎���v�j���ҏW�Ɋւ�����A�����́w�w�l���E�x��w�w�l���x�����Ȃ�ǂ�ł���悤�ł��B
�܂�A���̎�����Ȃ���A���̖{���������̂��낤�Ǝv���܂��B
���₳��́A
�S�N�O�ɐ����Ă��Ȃ��Ă悩����
�ƌ����Ă��܂��B
�����ɂ��A�����Ċώ@�҂Ƃ��Ă����ł͂Ȃ����₳��̎p���������܂��B
��ɏ������悤�ɁA���₳��̖{�͂Ƃ������f�B�e�[�����ʔ����̂ł��B
�ł�������e�Љ�͓���̂ł����A����́u�ʔ����v�ɂ����āA���₳��͎��M�������Ă��܂��B
�u���O�ɂ��������Ă��܂��B
�ł��オ���Ă݂�ƁA�\�z�ȏ�ɖʔ����{�ɂȂ����̂ŁA�����ł��т����肵�Ă��܂��B�@�@
���₳��̎��M��ł��B
�ǂ����ʔ������́A���Ж{������Ɏ���Ă��������B
�u�����̂��삳�܁v��ʂ��āA�V���������A���邢�͍��̓��{�̒ꗬ�������Ă��܂��B
���̖{�����������ƁA���₳��̎��̖{�̎������W��������i�ƍ����x�ɂȂ�ł��傤�B
�܂莟�̍�i�̖ʔ����������Ă����Ƃ������Ƃł��B
���̈Ӗ��ł����ЊF����A�w�ǂ��Ă��������B
�R�����Y���X�ł��w���ł��܂��B
���₳����A�u���O�ŏ����Ă��܂��B
���ЁA�F�����Ă��������I
���w�Z�����߂܂��i���{��T�@�����o�Ł@1200�~�i�ŕʁj
2008�j
���̖{�͎��̗F�l�̒����ł͂Ȃ��A���܂��o�������{�ł����A�Љ���Ă��炢�����Ȃ�܂����B
����܂ł́A�����Č��݂̋�����v�̖{�����ǂݎ��邩��ł��B
�b�v�r�v���C�x�[�g�̋��玞�]�ł��Љ���Ă��炢�܂������A
���҂̓��{��T����́A1��N�܂ŁA�����s�̌������w�Z�̋����ł����B
���܂́A����ސE���A���m�u���Ⴊ�������キ�v���J���Ă��܂��B
���̖{�́A�����������{����̋L�^�ł��B
���݂̏����w�Z�̎��Ԃ�q�ǂ������̏����X�����`����Ă��܂��B
���̖{�̊ȒP�ȏЉ�͑O�q�̃u���O�����ǂ݂��������Ƃ��āA�����ł͖{���́u�͂��߂Ɂv�����p�����Ă��炢�܂��B
��͂蒘�Җ{�l�̌��t�ɂ������͂�����܂��B
�l�������s�̌������w�Z�̋���������ސE����2006�N�A���Ȃ������s�ŐV�l�������Q�l�A���疽�������B
�l�̑ސE�͖{�ӂł͂Ȃ������B�l�͊w�Z�Ƃ����E�ꂪ�D���������B�u�ʐM����v�ŋ����Ƌ����Ƃ�����A�����̗p�����ɍ��i�������̊�т́A���ł��Y��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
���������Q�l�̎Ⴂ�������A�傫�Ȋ�]�����ɕ����Ă����̂��낤�Ǝv���B�Q�l�̉������́A�l�̉��{�A�ہA���\�{�������낤�B
�u���a�v�Ȃǂ̐��_�����ŋx�E�����������́A2006�N�x��4,765�l�ɂ̂ڂ�A�ߋ��ō����L�^�����i�����Ȋw�Ȕ��\�j�B
���A�w�Z����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��H
�u������v�v�̑傫�ȗ���̒��ŁA�w�Z�œ������E���͐��������Ɠ����Ă���̂��낤���B�����Ȃ�A�l�͑ސE��I�����Ȃ��������A���̓�l�̐V�l���������������Ȃ��������낤�Ǝv���B
�l�́A�l���g�̌o����ʂ��āA���̊w�Z���ꂪ�ǂ��Ȃ��Ă���̂�����悤�Ǝv���B����́A�l�l�̋L�^�ł͂��邪�A�����̌��ꋳ���́u���сv�ł�����B
�{���������������p�����Ă��炢�܂��B
���̊w�Z�́A�������q�ǂ��̂��ƂŔY�ނ��Ƃ��[���ɂł��Ȃ���Ԃɂ���B�}�X�R�~�Ȃǂ��A�q�ǂ���ی�҂��ς�����Ƃ����_����������ɗ����Ă��邪�A�q�ǂ���ی�҂��ς�����̂ł͂Ȃ��B���̋���s�����傫���ς�����̂ł���B
�ꌾ�Ō����Ίw�Z�Ɂu���������v���������Ƃ��B�q�ǂ��ɂ͊w�͌���Ƌ����ɂ͐E�K���i�����̊i���t�����x�j�ł���B
�݂Ȃ���̎���ł��N�����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��ł����B
�����������Ƃ́A�w�Z�݂̂Ȃ炸�A�Љ�̂�����Ƃ���ŋN�����Ă��邱�ƂȂ̂�������܂���B
�����v���ēǂނƁA���낢��Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B
���݂̋�����v�̖{���ɁA�������͋C�Â��Ȃ�������Ȃ��Ǝv���܂��B
����͌����Ďq�ǂ����������̖��ł͂Ȃ��̂ł��B
�ȒP�ɓǂ߂�{�ł��B
���Ђ��E�߂��܂��B
�R�����Y���X������ǂ����B
������15���Ԃ̉����i�S�������@�G�C�`�A���h�A�C�@1429�~�j
����A���{�o�c������̃t�H�[�����ł�������S�����ŋߏo�ł��ꂽ�{�ł��B
�S������́A����̍r�p�Ɋ�@���������āA�߂Ă�����Ђ����߂ĕS���n�����猤������ݗ����܂����B
����30�N�ȏ�O��1976�N�ł��B
����܂ł̊����U��́A�S���n�����猤�����̃z�[���y�[�W���������������B
�{���́A�S������̒��N�̎��т܂��āA�ƒ�̎������������^�̐l�ވ琬�@�ɂ��ďq�ׂ����̂ł��B
������ɂ߂Ď��H�I�ɏ�����Ă��܂��̂ŁA����ł�������������ł��܂��B
�S������̏o���_�́A�u�q��Ă͈̋Ƃ��v�ƌ����Ƃ��납��o�����܂��B
�����ē����ɁA�u�q�ǂ������͈̑傾�v�ƍl���Ă��܂��B
������������̂́A�܂��ɂ��̓_�ł��B
����2�_�����������肵�Ă���A�q��Ă͂��܂������ł��傤�B
����2�_���������肵�Ă��Ȃ���A���̓��{�̂悤�ɏ��q�����ƒ������w�Z�r�p������Ȃ��ł��傤�B
����̗v���́u�l�Ԋw�v�̊�{�̏C���ɂ���A�ƕS������͌����܂��B
�����āu�q�ǂ������͂��ƈȑO����u�l�Ԋw�v�̊�{��S�ꋁ�߂Ă����v�̂ɁA
���̐e�����݂̂Ȃ炸����W�҂����܂ł����A���̂��ƂɋC�Â��Ă��Ȃ������Ƃ����̂ł��B
���̓_�������ł��B
�q�ǂ������́A��l�ȏ�ɕ����̖{�������ɂ߂܂��B
���̎����ɂ����A�{��������ڂ��������邱�Ƃ͑�ł��B
���Ԃ�͂��A��l�������D��Ă���ł��傤�B
�ł́A��̓I�ɂ͂ǂ�����悢�̂��B
�S������̒�Ă�����@�͂������ĊȒP�ł��B
�u�l�Ԋw�v�̊�{�����������K�Ȏ�{�ƂȂ�{������I�сA������u�P�T���ԁv���ǂ��邱�ƁA
������p�����A���g���������蓪�ɓ���܂Łi�}�X�^�[�ł���܂Łj�ѓO���邱�Ƃł��B
���̍l���ɋ������Ď��H���Ă���w�Z������������܂��B
���ǂ���{�ɂ́A�S������̏������w�N�����͈̑傾�x���g���Ă��܂��B
�S������̒�Ẵ|�C���g�́A�w�N�����͈̑傾�x�̉��ǂ̊��߂ɂ���̂ł��B
���������ƁA�����̒����̊��߂ł͂Ȃ����Ǝ��l�����邩������܂���B
�������A�����ł͂���܂���B
�q�ǂ��Ɍ������l�Ԋw�̖{���܂߂āA���ꂪ�S������̒�Ă���q��Ė@�Ȃ̂ł��B
���H�����q�ǂ������̔����͂ƂĂ������I�ł��B
���̌��ʁA���̊����͍L���肾���Ă���悤�ł��B
�S������̒�Ă�����@�́A�q��ĂɌ������b�ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
��Ƃɂ�����l�ވ琬�ɂ��Q�l�ɂȂ�͂��ł��B
���ǂ̌��p�͑傫���͂��ł��B
�q�ǂ����������̕��⋳��W�҂ɂ͂��E�߂��܂��B
�R�����Y���X������w���ł��܂��B
���u�J�^�I�p���[�X�|�b�g�u�_�Ёv�֍s�����v
���^��ďC�@�o�g�o���Ɂ@533�~
����͂�����ƌy���{�̏Љ�ł��B
�ŋ߁A�Ⴂ�l�̒��Ő_�Ђւ̊S�����܂��Ă���̂������ł��B
����ȓ����ɍ��킹�ďo�ł��ꂽ�̂��A���̖{�ł��B
�ł�����Ⴂ�l�����̌y������ɂȂ��Ă��܂��B
�����Ƃ�����Ə�Ⴂ�̖{�ł͂���̂ł����A�ďC�����^�炳���ł���A
�����������D���Ȑ_�Ђ̊W�̖{�ł��̂ŁA�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
�������́u�_�И_�v������A�������낢�Ǝv���̂ł����A
����͊ďC�҂̂��߁A�����̂悤�Ȏ����ɕx�ސ_�И_�͂���܂���B
�������A���e�͌��\�������낭�A����u�_�Г��发�v�ɂȂ��Ă��܂��B
�S�̂́A�u�_�Ђ̂��ڂ��ȋ^��Q�O�v�u�V���ƍs���v�u���j�Ǝ�ށv�u�S���_�Ђ߂���v�̂S���\���ł��B
���ꂼ�ꂪ���ڕʂɁA�Ȍ��ɓǂ݂₷��������Ă��܂��̂ŁA�C�y�ɓǂ߂܂��B
���������������ڂ��ς�ς�Ɠǂނ̂������ł��B
���Ƃ��u���݂����̋g�Ƌ��̊����͂ǂꂭ�炢
�̕ł��J���ƁA���̋��̊�����30���A���}�_�Ђ͂O���Ȃǂƌ����}���o�Ă��܂��B
�Q�q�̍�@��j���̉��������܂��B
���̖{��ǂ�ł����ƁA�_�Ђ̕��i�������ǂ������Ă��邩������܂���B
�����������ɂ́A�{�i�I�Ȑ_�И_�����҂��Ă��܂��B
���w�Ȃ��A���u�q�炿�x���v�Ȃ̂��|�q�ǂ��Ƒ�l���炿���������݂Ƌ�ԂÂ���x
�q�炿�w�l�b�g���[�N�@�w���Ё@1900�~
���X�ƗF�l���{���o�ł���̂ŁA�������ւ�����{���Љ��̂��x��Ă��܂��܂����B
�o�ł���Ă���Q�������o���܂������A�Љ���Ă��炢�܂��B
�q�炿�w�l�b�g���[�N���ւ���ďo�ł����S���ڂ̖{�ɂȂ�܂��B
������A�[���Y����\���Ƃ߂�q�炿�w�l�b�g���[�N�̃R�A�����o�[�����S���M���Ă��܂��B
�����R�����Ɋ�e�����Ă��炢�܂����B
�[�삳��̏Љ�����p�����Ă��炢�܂��B
�u�q�炿�v���_�ɗ����A���܂��܂Ȏ��삩��q�ǂ����g����͂d�����n��ł̖L���Ȏ��H�Ɛ�[�̌�����ϋɓI�Ɏ�����Č��������Ă������Ǝ��̌����҂Ǝ��H�҂��W���A2�N�ȏ�̌𗬌����𑱂��Ă��܂����B
���̑z���ƌ��������̈�[���܂Ƃ߂����̂ł��B
3���\���ƂȂ��Ă��āA��P���̑��_�҂ł́A�u�q�炿�v�̊T�O������E���B�S���E������������T���Ă��܂��B
��Q���́A�S���e�n�Ŏ��g�܂�Ă���q�炿�x���̎��H����5�{��I�яЉ�Ă��܂��B
�����̎��H�ɂ́A�������̋��ʍ�������܂��B
����́A�q�ǂ��̈炿���x���邽�߂̎��_�ł���A����Ɏ��g�ޑ�l�̎p���ł�����܂��B
��R���́A�ҏW�ψ��ɂ�邻�ꂼ��̎��_����T��u�q�炿�v�̘_�l�ł��B
�q�ǂ��̈炿�́A����w��S���w�����͖ԗ��ł��Ȃ��w�ۓI�v�f������܂��B�����ւ̃`�������W�̈Ӗ������˂Ă��܂��B
�܂��r���o�߂ł��̂ŁA���_���t�قȈ��@������܂��A�ӋC���݂����ݎ���Ă��������A���݂̖������ӌ�������������Ǝv���܂��B
�����ǒ��̐����l����ɂ��u�q�炿�E�q��Ă��߂��鐭���15�N�j�v���f�ڂ���Ă��܂����A���Ƃ��Ă̎q��ēN�w���_�Ԍ����Ă��܂��B
���̏��q����ɂ͑傫�Ȉ�a������������܂���B
���삳��́A���������Ă��܂��i���͈͂ꕔ�ύX�j�B
���{�͎q�ǂ��̌��������y���Ă���̂ł����A���̌㌻�݂Ɏ���܂ŁA�����̗��O���ӂ܂��čs��ꂽ����͂���߂ď��Ȃ��̂������ł��B���A�q�ǂ��̌����ψ���ł��A��x�ɂ킽����{���{�ɑ��āA�����̌��O������\�����A�������s���Ă��܂��B
��������蒅���Ă��܂����u�S�̋���v�u��d�����v�Ƃ������L�[���[�h�̂Ȃ��ŁA���q���ւ̑�ƐV�����u�����v�̑n�o�Ƃ����u�Љ�I�v���v�̂Ȃ��ŁA�n��Љ��Ƃ����q�炿�E�q��Ċ֘A�̎{��Q���W�J����Ă��܂����A�����̎{��͈ˑR�Ƃ��āu��l�̓s���v�ōs���Ă����ɉ߂��Ȃ��Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�q�炿�E�q��Ď{�����������ɂ������Ắu�n�������v�̎��_��Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ�t�����Ă��������Ǝv���܂��B��b�����̂��ǂ̂悤�Ȏq�炿�E�q��Ẵv������`���Ă����̂��A�q�ǂ���e�A�n��Z���Ƃ̋����Ƃ������_���ӂ܂��Ȃ���A����̎��g�݂Ɋ��҂������Ƃ���ł��B
���삳��́A��̓I�Ȏ{��͂�����L���҂���łȂ��A�q�ǂ��̌���Ɋ��Y���Ă����E����n��Z���������āA�q�ǂ��̈炿����`�I�ɍl���������e�̂��̂��ł��o�����K�v���Ə����Ă��܂��B
�S�������ł��B
���N�A����Ɋ��Y���Ċ������Ă������삳��̌��t�ɂ́A�ƂĂ������ł�����̂�����܂��B
�����炱���A�q��Ď��_�ł͂Ȃ��A�q�炿�N�w���K�v�ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�q�炿�w�l�b�g���[�N�ł́A���̖{���e�L�X�g�̂������[�N�V���b�v�̓W�J�����������������ł��B
�����J�Â���悵�Ă����Ƃ��낪����A���A�����������B
���Ȃ݂ɉߋ��ɏo�ł��ꂽ�{�͎��̂R���ł��B
���u�q�炿�x���̑n���v
���ؔ���q�A�������A�[���Y�A�����l�Ғ��@�w���Ё@
���u�q�ǂ��̖L���Ȉ炿�ƒn��x���v
�[���Y�ق��@�w����
���u�q�炿�w�ւ̃A�v���[�`�v���ؔ���q
������ �[���Y�@�G�C�f��������
�R�����Y���Ќo�R�ŃA�}�]������w���ł��܂��B
����Ј��̂��߂̂b�r�q�o�c
���������ق��@���@�K�@1714�~
��T�A�Љ���b�b�헪�̖{�̒��҂̈�l�ł�����A����������Q�������@������w�ł̘A���u�������Ƃɂ��ĕҏW���ꂽ�{�ł��B
���͍����̂b�r�q�c�_�ɂ͑傫�Ȉ�a���������Ă��܂����A���̖{�͋����ł���Ƃ��낪���X����܂����B
�L�`�̋L�^���x�[�X�ɂ��Ă���̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���ł����A�ҏW�̎��_�ɍD�������Ă܂����B
���Ƃ��A�{���́u�����Ɂv�ɁA���҂̈�l�A���F��v�m�̑�v�ۘa�F����͂��������Ă��܂��B
���̌o�ώЉ���ꌾ�Ō����\���ƁA�u���m�ɂ��Č`����`�ɑ���A�Љ�S�̂��v�l��~��Ԃ�
�ׂ��Ă���v�ƕ\������������Ȃ��̂�������܂���B
�`���_���Ɛ��x�d���łb�r�q������Ă���l�������̂�焈Ղ��Ă��鎄�Ƃ��ẮA������Ǝv���܂����B
��v�ۂ���͖{���ŁA�b�r�q��������`���Ă��܂��B
��Ƃ��Љ��̊��҂�v���𐳂����������������ŁA
���Ɗ�����ʂ����Ή���}�邱�ƂŁA���ʂƂ��ē��Y�g�D�̎����I�������������邱�ƁB
������13�l�̐l���b�r�q�o�c�Ɋւ��Ę_���Ă��܂����A������ɂ��������肵�����b�Z�[�W�������܂��B
�b�r�q�_�c�̂��炢�Ȏ��́A��������̂Ƃ��낾���ǂ����Ǝv���Ă����̂ł����A��v�ۂ���̍ŏ��́u�o�c�̖{���Ƃ��Ă̂b�r�q�v�̃��b�Z�[�W�ɖ�����āB�����S������C�ɓǂ�ł��܂��܂����B
��@�Ǘ��ƃR���v���C�A���X�ɂ��Ă������M�Y�����m�ɐ荞��ł��܂��B
�����ŏЉ��Ă���s��Ǝ����̎��Ԃ͎��ɂ͂��������̋����ł����B
�܂��A����Ȗʔ������b�Z�[�W�����낢��Ƃ���܂��B
�ދ��Ȃb�r�q�_���������ŁA�{���̓��C�u�ŋ�̓I�A�������z���X�e�B�b�N�Ȏ��삪�������܂��B
�b�r�q�ɊS�̂�����ɂ͂��Ђ��E�߂������ł��B
��������́A�b�r�q�ƃR�~���j�P�[�V�����헪�������Ă��܂����A
�������ڎw���b�r�q���ƃR�~���j�P�[�V�����헪�̕����������m�Ɏ�����Ă��܂��B
�_�C�i�~�b�N�Ȃb�r�q�A�_�C�i�~�b�N�ȊW���𐴐�����̓��b�Z�[�W���Ă��܂��B
�T�ԕ��ɂ������܂������A���̕���Ő������V�������g�݂��n�߂�悤�ȋC�z�������܂��B
��������̎��̖{���҂��������ł��B
��ƊW�҂ɂ��Ђ��E�߂�����1���ł��B
�R�����Y���X������w���ł��܂��B
���u�b�b�헪�̗��_�Ǝ��H�|���E�b�r�q�E�����v
���������ق��@���F�ف@2600�~
���{�L��w���̗F�l�����������ŏ������A�R�[�|���[�g�E�R�~���j�P�[�V�����i�b�b�j�Ɋւ���ŐV�̏��Ђł��B
��ƂɂƂ��Ă̂b�b�헪�̏d�v���͂܂��܂����܂��Ă��܂��B
�����헪����헪���x���Ă����̂́A�܂��ɂb�b�����ł��B
�����d�v�Ȃ̂́A�b�b���u��Ƃ���̏�M�v�Ƒ�����̂ł͂Ȃ��A�u�g�D�Ɛl�Ƃ̊W���v�Ƒ����鎋�_�������Ƃł��B
���҂����́A���N�A��Ƃ̍L���̌���ɂ��ւ���Ă����l�����ł��̂ŁA
�{���ł͒P�Ȃ����_�ł͂Ȃ��A�������������̗���܂����A���C�u�Ȃb�b�_������Ă��܂��B
���ꂩ��̊�Ƃ̂�������l�����ł̎�������������ǂݎ��܂��B
�{���͊�ƍL���ɏœ_�����Ă����̂ł͂���܂���B
�ڎ�������킩��܂����A�s����m�o�n�̃R�~���j�P�[�V�����헪�ɂ����y���Ă��܂��B
�@��1�́@��ƎЉ�̕ϗe�ƍL��헪�ւ̎��_
�@��2�́@�R�[�|���[�g�E�R�~���j�P�[�V����
�@��3�́@��Ƃ̎Љ���ƃR�~���j�P�[�V����
�@��4�́@�V��������̍L��E�R�~���j�P�[�V����
�@��5�́@�s���ENPO�̃R�~���j�P�[�V����
�@��6�́@�L��E�R�~���j�P�[�V�����}�l�W�����g
�@��7�́@�L��E�R�~���j�P�[�V�����̗��_�Ɨ��j
�c�_�͍L�͈͂ɂ킽���Ă��܂����A���ꂼ��ɐV�N��������܂��B
�����Ɂu���E�b�r�q�E�����v�Ƃ��Ă���悤�ɁA�V�����b�����������Ǝ��グ���Ă��܂��B
����̍L���̐헪����ڎw�����̌n��������H�I�Ȑ헪�_�ł��̂ŁA
��Ƃ̌o�c�҂�o�c�Q�d�͑����̎��H�I�ȃq���g��������ł��傤�B
�������A���ꂾ���ł͂���܂���B
�L��E�R�~���j�P�[�V�����}�l�W�����g�ł́A�n�[�o�[�}�X�́u�R�~���j�P�[�V�����I���́v��n���i�E�A�����g�܂ŏЉ��Ă��܂����A
�I�͂́u�L��E�R�~���j�P�[�V�����̗��_�Ɨ��j�v�ɂ́A�v���g����A�E�O�X�`�k�X�܂œo�ꂵ�܂��B
������m�v�z�ɂ�����R�~���j�P�[�V����������Ă��܂��B
�{�����P�ɕ��Ȏ������ɂȂ��Ă��Ȃ��̂́A���҂����̎����Ă��鎋��̍L�����r�W�����̖L�����̕\���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�u�g�D�Ɛl�Ƃ̊W���v�Ƃ��ẴR�~���j�P�[�V�����헪�_�́A���ꂩ��̊�Ƃ̑傫�ȃe�[�}�ɂȂ�ł��傤�B
�����g�́A�R�~���j�P�[�V�����Ƃ͐M�����̌����ʂ��ĎЉ�R�X�g���팸���邱�Ƃ��ƍl���Ă��܂����A
���������ł���A�Љ�Ƃ̊W�A�l�ԂƂ̊W�ɂ����āA�����K�v������܂��B
�����������_������A���낢��Ǝ�����������b�b�_�ł��B
�R�����Y���X������w���ł��܂��B
�����j�̂����ɃO��������
����䍲�q�@���t�V���@800�~
���₳��̍ŐV��ł��B
���c�H��̑��䌷�ւ̕]�`���Ĉȗ��A���₳��͐H�ɊS��[�߂Ă���悤�ŁA�u�H��̃X�X���v�ɑ����H�V���[�Y��3�e�ł��B
�H�́A��������̊�{�ł�����A������ʂ��Ă�������̂������Ă��܂��B
��������Ԃ�u�{���v�Ō����Ă���̂��ʔ����Ƃ���ł��傤�B
�{���ł́A�����̃y���[���q����A�����ېV�A��Î����A�����E���I�푈�A���������̑�t�����܂ŁA�����̒����Ȑl���Ƃ��܂��܂Ȏ��������グ�Ȃ���A�H�Ɨ��j�𗍂܂��������[��12�̕��ꂪ����Ă��܂��B
���₳��́A�u�ߎ`����ӎ`���̃��j���[����́A��Î҂����̗�������ɂ��߂��v�����`����Ă��܂��B�����l�̃O�����x�̍����ɂ��������ɂ͂����܂���B���̈���ŁA�ߗ����e���̐H����ċ\�̐H�����A���܂��܂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B���ׂĂ����ɂ�āA����܂Œm���Ă�����肾���������̕ʂ̈Ӗ��ɋC�Â����ƂɂȂ�A��������̔���������܂����B�����点�Ȃ���A�y�����������Ƃ��ł��܂����v�Ə����Ă��܂����B
�ǂ�ł݂āA���̂��Ƃ��悭�킩��܂��B
���������G�s�\�[�h���ꏏ�ɗ��j���w�ׂ���A���j�D���̐l�͑�����ł��傤���A�����ƖY��Ȃ��ł��傤�B
���܂őS�����ɂ͑��݊��̂Ȃ������j�R���C�c���q�̕\��`����Ă��܂������A�{���ɓo�ꂷ��l�����ւ̍D���x�������܂����B
�����V�c�̐l�ԓI�ȑ��ʂ�����Ă��āA�ƂĂ��D�������Ă܂����B
���Ɉ�Ԗʔ��������b��������Љ���Ă��炢�܂��B
�K���H���Ɋւ��ď����ꂽ�u�A�i�[�L�X�g�̍ؐH�_�v�̒��ɏo�Ă���b�ł��B
����L���D���ȍ䗘�F�́A�����s�Җh�~��̉���ɂȂ������ƂŁA�������E���Ă��̓���H�ׂ邱�Ƃւ̊���s�q�ɂȂ����B�����A����ɎЉ��`�̎v�z����A���H���̂��̂ɑ���^�₪�����Ă����̂������B��ɂ��A���̋����_�҂͐����E�̐������������āA�l�ԊE�̊K�����x��n�x�̊i���F���Ă��邪�A�Љ��`�҂͎ア�҂ݓ|�����A���R�����̑���ɑ��ݕ}���ŁA���y�ŋ����̂Ȃ����E�����낤�Ɩ]��ł���̂��Ƃ����B
�@���̂��߁A�Љ��`������ł́A����̂悤�ɓ��H��肪�����オ��A�u�l�ԂƓ����Ƃ̋��E���͉����Ɉ������v�u���H��p�������ŁA�A������萶���ł͖������A�i�����j�R��ΐl�Ԃ͌��lj���H���Ƃ��ׂ��ł�����v�Ȃǂ̎��₪���������B
�Ȃ��ق̂ڂ̂��Ă��܂��B
���̂܂ܐi�߂A���{�̎Љ��`���V����������J���������ʂ������ł��傤�ˁB
���͂��Ȃ�{�C�ł����l���܂����B
���܂�^���͂��Ă��炦�Ȃ���������܂���ˁB
�y�����{�ł��̂ŁA�O�����ɋ����̂Ȃ��l�ɂ����E�߂��܂��B
�R�����Y���X����A�}�]���ł̍w�����ł��܂��B
���u���������̂����Ё]���{�ɂ�����x�X�g�Q�T�v
�֓��q���@�J���s���@2500�~�i�ō��j
Great Place to Work�i�f�o�s�v�j�͂Ƃ����̂������m�ł��傤���B
�]�ƈ��̓��������̎��_����A��Ђ�]�����A��Ђ������Ƃ����Ɩ��͓I�ɂ��Ă������Ƃ��������ł��B
�{���̓A�����J�ɂ���܂����A���̐��N���E���ɍL���肾���Ă��銈���ł��B
���̊�������{�ɏЉ�A���{�ł̊����𐄐i���Ă����̂��A�֓�����ł��B
�֓�����͂���܂œ��{�\������R���T���e�B���O�ŁA���̊����Ɏ��g��ł��܂������A
���x�A���Ђ���X�s���A�E�g���A���������̂����Ќ�������ݗ����܂����B
Great Place to Work�̎v�z������ɍL���Ă��������Ƃ����̂��֓�����̎v���ł��B
���̍֓����A�ŋߏo�ł����̂��{���ł��B
�_�ˑ�w��w�@�̋��䋳���́A�uGreat Place to Work�̓��{�f�r���[�Ɋāv�Ƃ������͂�{���ɊĂ��܂��B
�֓�����Əo������̂͂���20�N�߂��O�ɂȂ�ł��傤���B
�����A���͂܂���ƂɊւ��d���ɑ傫�Ȗ��͂������Ă���A���{�\������Ƃ����낢��Ɛړ_������܂����B
���̌�A�����g�͊�Ƃ̓����Ɏ��]���A�܂��Â����m�o�n�̐��E�ɂ̂߂肱��ł��܂������A
�֓�����̖��O�͎G���ȂǂŎ��X�͈ӌ����Ă��܂����B
���N�ł��傤���A������琬������ō֓�����ɋv���Ԃ�ɉ�܂����B
������Great Place to Work�Ɏ��g��ł��邱�Ƃ�m��܂����B
25�N�O�ɓ����Ŏ����������������Ƃ̈�ł��B
�֓�����͎��X����������Ă��܂������A�֓�������Ɨ����ꂽ�̂ŁA
��x����������Ǝv���Ă�����A�{���������ăI�t�B�X�ɗ��Ă���܂����B
���낢��Ƙb���Ă݂āA�ē�����̌o�c�ς͎��̂���Ƌɂ߂ċ߂����Ƃ��킩��܂����B
�{����ǂ�ŁA�܂��܂������v���܂����B
�{���́A�o�c�ɔ��z�̓]�������߂Ă��܂��B
���Б����̊�Ɛl�A���邢�͑g�D�l�i�s����m�o�n�j�ɓǂ�łق����{�ł��B
Great Place to Work�����i���������̂����Ёj�����́A1998�N�ȗ��A���N�A�����J�ōs���A
���̌��ʂ́u�t�H�[�`�����v�Ɍf�ڂ���A�b����Ă�ł��܂��B
�ȑO�A�]�ƈ��̃��`�x�[�V�����̍����ŃT�E�X�E�G�X�g�q�b��ɂȂ�܂������A
����͂��̒����̑�1��ڂŁA���Ђ��x�X�g�P�ɂȂ������炾�����ł��B
���{�ł��֓����������S�ɂȂ���3�N�O����n�܂�A���ʂ͖��N�A���o�r�W�l�X�Ŕ��\����Ă��܂��B
�{���͓��Ă̒������ʂ܂��Ȃ���AGreat Place to Work�̍l�����Ƃ��̎�����𗝘_�I����̓I�ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B
������L�x�ł����A�Ȃɂ�������܂ł̒������т܂��ẮA
�֓�����̌o�c�_�iGreat Place to Work�̗��_�I�w�i�ƌ����Ă������ł����j�������ɕx��ł��܂��B
�����Ȃ�̂ŁA���̂��������ӏ������ŏЉ�܂��B
�E�u���������v�ɂ͉�БS�̂��u�M���v�̕������s���ł���B
�EWork Harder���ォ��AWork Smarter������o�āA����Work Together�̎���B
�E�]�ƈ��ȊO�̉����V�������l�ݏo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�E�u�g�D�ɂ����铭�������v�Ɓu�d���̂�肪���v�͕ʂ̂��́B
�ǂ��ł����A�ǂ݂����Ȃ�܂��B
���{��Ƃ̋��݂Ǝ�݂Ɋւ��Ă��A��������̎����邱�Ƃ��ł��܂��B
���ɂ͋�������Ƃ��낪���ɂ�������܂����B
�����炭����́A���̒������u�]�ƈ��̐��̐��v���x�[�X�ɑg�ݗ��Ă��Ă��邩�炾�낤�Ǝv���܂��B
����ɂ����^���͂���B
����͎��̐M���̈�ł��B
Great Place to Work�����́A���N���炫���Ɩ{�i�I�Ɋg�����Ă����ł��傤�B
�����A�������Ȃ���A���{�̊�Ƃ͔敾���Ă�������ł��B
Great Place to Work�������A���{�̊�Ƃ�ς��Ă������ƂɊ��҂������ł��B
�֓�����ɂ�����Ă����Ȃ�������܂���B
�����܂��v���Ԃ�ɁA��ƂɊւ�낤���Ƃ����C���o�Ă����悤�ȋC�����܂��B
�R�����Y���X����A�}�]���ł̍w�����ł��܂��B
��Ƃ�ς������Ǝv���Ă�����͂��Ђ��ǂ݂��������B
�������������Ƃ킩���Ă��܂��B
���u�V�v���a��`�̘_��
�i��{���@���Ώ��X�@2008�j
���a�����C�t���[�N�ɂ���Ă�����{���A���悢����H�Ɍ����ē����o���i�K�ɓ���܂����B
�{���́A���̌��Ӑ錾���ł�����܂��B
��{����̒����Ɋւ��ẮA����A���̃R�[�i�[�ŏЉ�Ă��܂����B
����܂łɒ����͎����������������B
��{����́A����܂ł͎�Ɏ�҂Ɍ����Č�肩���Ă��܂������A���̂悤�Ȑ���̂��̂��ǂ�ł������ɕx�ނ��̂ł����B
�c�O�Ȃ���ǎ҂������Ƃ͂����Ȃ��ł��B
����́A�ǎ҂̃^�[�Q�b�g��ς��܂����B
����܂ł̒��슈���́A����ΏW�听�ł��B
��{����́A���Z�̋��t�ł����A����Ƃ��̊����Ƃ͏s�ʂ��čl���Ă��܂��B
�ł����炱��܂ł͎��M���������S�ł����B
�������A���̐�{������Ԃ��Ȃ���N�ł��B
���Ԃ���H�Ɍ������ł��傤�B
���̎���́A��������߂Ă��܂��B
���ܓ����Ȃ���A�܂��J��Ԃ��ł��B
��{����̐V���a��`�̓����͎���3�_�ł��B
�@�u�푈���̂��́v�u�푈���ł��鍑�Ɓv�̔ے�
�A�u��]���镽�a�v�ł͂Ȃ��u�l�����镽�a�v�Ƃ������a��
�B��{�I�l���Ƃ��Ă̕��a��
�����́A���̃T�C�g�⎄�̃u���O�̍���ɂ���A�g�D�N�_�̔��z����l�N�_�̔��z�ւƂ������E���̃p���_�C���V�t�g�ƕ������Ă��܂��B
�{���̓��e�̏Љ�͍���͂�߂܂��B
���Гǂ�łق�������ł��B
����ɑウ�āA�͂��߂ɂŐ�{��������Ă��邱�Ƃ����������ł����A�ꕔ���ȗ������Ă��炢�Ȃ���A���p�����Ă��炢�܂��B
�������N�̊Ԏ��́A��ɎႢ�ǎ҂�Ώۂɖ{�������Ă��܂����B
���ꂩ��̓��{�␢�E��S���Ă����Ⴂ�ǎ҂Ɏ��ƈꏏ�ɍl���Ă����ė~�����ƍl��������ł��B
�������A���̖{�́A�u�푈��m��Ȃ��w���x�q�������v�ł���킪�����Ώۂɏ����܂����B
���̗��R�́A���݂̓��{�̏����āA�������̐��オ�{���ɂ��̂悤�ȍ�����낤�Ǝv��������₢��������ł��B
�u�푈��m��Ȃ��w���x�q�������v�����́A�푈�̌���ʂ��Ċl���������{�����̐��́u���o�v�̐^�������ň���Ă��܂��B
�����āA�u�푈��m��Ȃ��w���x�q�������v�́A�w���^���Ȃǂ�ʂ��Ă��Ă͐��̓��{����낤�ƍl���܂����B
���̎������̐��オ�A�{���ɂ��̂悤�ȍ�����낤�Ǝv���Ă����̂��H
�h�q�����h�q�ȂɂȂ�A�C�O�h�������q���̖{���C���ɂȂ��Ă��܂������B
���ׂĂ̊w�Z�Łu�N����v���̂����Ƃ���������Ă��Ă�������ɂ���Ȃ����B
�u�����g�v�u�����g�v�Ƃ������t����e�͂Ȃ��g����悤�ɂȂ��Ă��܂������B
�n�x�̍�������قǂɊg�債�Ă��܂��Ă���̂ɘJ���g���������T�ς��Ă��邵���ł��Ȃ����B
�u�v�V�v�Ƃ������t���p�������A��吭�}����A����g�ނ��߂̎��݂܂ł����s���鍑�B
�����āA�������A�w�����҂������ɑ��Ă�����̈ӎv��\�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ă��鍑�c�c�B
�푈�̌���ʂ��Ċl���������{�����̐��́u���o�v�́A�����̓_�ł��łɐ����^�����`��\�A�^�Љ��`�i���Љ��`�^�����`�j�̍l�������Ă����B
�������A�킪�����͂����\�����t�i���S�X�j��_���i���S�X�j�╁�Ռ����i���S�X�j�������Ă͂��炸�A�����ł킪���́A���̓��{�����́u���o�v�Ƃ͈قȂ�����ւƕ��ނ��ƂɂȂ��Ă��܂����B
���������āA�u�푈��m��Ȃ��w���x�q�������v�͓��{�����̐��́u���o�v�Ɂu���t�i���S�X�j�v��^���Ȃ���Ȃ炸�A�����Ă������̂��Ƃ��\�ł���A���{�����͖{���̈Ӗ��ł̍��ۍv�����s����悤�ɂȂ�A���E�����[�h���邱�ƂɂȂ�B
�u�푈��m��Ȃ��w���x�q�������v�́A�q���̍��A�u�푈��m���Ă����l�����v�Ɂu�ǂ����Ĕ����Ȃ������̂��v�u�ǂ����Ē�R���Ȃ������̂��v�Ɩ₢�����܂����B
���̂��Ƃ���l��������������A���̂�������甭������u�푈���m��Ȃ������Ɂc�v�Ƃ������t�ɑ��āA�u�푈��m��Ȃ��q�������v�̉̂����܂ꂽ�̂ł����A�������A���ꂩ��͎������̐��オ�u�ǂ����Ĕ����Ȃ������̂��v�u�ǂ����Ē�R���Ȃ������̂��v�Ɩ��ꂩ�˂܂���B
�����Ŏ��́A���̖{�ł킪����ɖ{���ɂ��̂悤�ȍ�����낤�Ǝv��������₢�A�����āu�����{�̍č\�z�v���Ăт��������̂ł��B
�ǂ܂Ȃ���Ƃ����C�ɂȂ�����A���Ђ��ǂ݂��������B
���z�Ȃǂ��������Ă��炦��Ƃ��ꂵ���ł��B
��{����ɂ��肢���āA��x�A�b������J�Â������Ǝv���Ă��܂��B
�S�̂�����͂��A�����������B
�T�l�W�܂�����J�Â���\��ł��B
�R�����Y���X�o�R�ŃA�}�]������w���ł��܂��B
���u�����Ă݂悤 �܂��̈��S�E���S�}�b�v�v
�P�؍G�v�@�����̌����Ё@1333�~�i�ŕʁj
�P����́A���쌧�̑咬�s�ɋ��_��u���A�m�o�n�n��Â���H�[�̑�\�ł����A
�n���ł܂��Â��芈���Ɏ��g�݂Ȃ���A�S���I�ɂ����܂��܂Ȋ���������Ă��܂��B
�����m�荇�����̂́A�R���P�A�����̂������ł����A
�����ŎP����悵���v���W�F�N�g�ɊS���������̂��ŏ��ł��B
���̃v���W�F�N�g�͎c�O�Ȃ���\�z�O�́u�����v�ɂ���ĎP����̎v���悤�ɂ͓W�J�ł��Ȃ������̂ł����A
���̎��̎P����̑Ή��̎p�����ƂĂ��S�Ɏc�����̂ł��B
�v���W�F�N�g�͐�������ɉz�������Ƃ͂���܂��A
����ȏ�ɑ�Ȃ̂̓v���Z�X�ł���l�������Ǝv���Ă��鎄�ɂ́A�ƂĂ���ۂɎc��܂����B
���̌�A�P����Â����ɃQ�X�g�Ƃ��ČĂꂽ���Ƃ�����܂��B
�n��ɗ��r���āA�Z������̎p���Œn��Â���Ɏ��g��ł���P����̐������������܂����B
�������P����͂������������ƕ��s���āA�n��Â���W�̌������Ȃǂɂ��Q�����Ȃ���A
����ɖ��v���邱�ƂȂ��A���̐��E���L���[�߂Ă���̂ł��B
������u�y�̐l�v�ł�����u���̐l�v�ł�����̂ł��B
���̎P����A�V���������Ă��܂����B
���ꂪ�A���̖{�ł��B
�u���S�E���S�}�b�v�v�B�܂��ɂ��܊e�n�ŋ��߂��Ă�����̂ł��B
�P����̎��ۂ̑̌�����{�ɂ��������H���ł�����A�ƂĂ��ǂ݂₷�������͂�����܂��B
�������V�����i�K�ɓ����Ă����̂��ƁA���͂��̖{��ǂ�Ŏ������܂����B
���̖{�ŏЉ��Ă���̂́A�q�ǂ��₨�N��肪�ނ������ɂȂ��Ēn��Â���̎��g�ގ���ł����A�����ł͍s���哱�̌`���I�ȋ����̂܂��Â���ł͂Ȃ��A�Z�����m�̋����̎��H�ւ̓W�]�������Ă��܂��B
�n���Ȋ������d�˂Ă����P����Ȃ�ł͂́A�v�z��w�i�ɂ������H���ł��B
�u���S�E���S�}�b�v�v�́A���������}�b�v���d�v�Ȃ̂ł͂���܂���B
�}�b�v�Â���̃v���Z�X���ƂĂ��傫�ȈӖ��������Ă��܂��B
�������N�O�A����������������ɁA�u���S�E���S�}�b�v�v�̎��g�����Ǝv���܂����B
�c�O�Ȃ���A���̎��͎����ł��܂���ł������A���̖{������Ώ���������W�J���ł�����������܂���B
�������w�Z�A���邢�͘V�l��ȂǂŁA
���̖{���Q�l�ɁA�e�n�́u���S�E���S�}�b�v�v�Â��肪�L����Ƃ����ȂƎv���܂��B
�q��ĊW�̂m�o�n��O���[�v�ł��A���Ў��g�ނƂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����܂�{�̓��e�Љ�ɂ͂Ȃ��Ă��܂��A�ƂĂ��ǂ��{�ł��B
�܂��Â�����炵�ɊS�̂���l�ɂ��E�߂��܂��B
���u�V�E���킷��Ƒn��Ɓv
�l����������o�c�R���T���e�B���O���Ғ��@�v���W�f���g�Ё@1800�~�i�ŕʁj
��N�A���̗��ł����Љ���A�u���킷��Ƒn��Ɓv�̑��҂ł��B
�l����������o�c�R���T���e�B���O���́A�u�挩���Ƒn�����Ɛ�含�����A���L�����̒�ʂ��Ēn��̏����̔��W�ɍv������v���Ƃ��~�b�V�����ɁA��ɒ�����Ƃ�ΏۂɁA����ɑ��ݓ���Ă̖������x���̃R���T���e�B���O�����Ɏ��g��ł��܂��B
�����ŏo��������C�Ȋ�Ƃ��A���̓Ƒn���Ɏ�ɒ��ڂ��ďЉ�Ă���Ă���̂��{���ł��B
���̖{�̕ҏW�̒��S�ɂȂ��Ă���l����������̎��{���P����̃��b�Z�[�W���A�܂��܂��Ⴆ�Ă��Ă��܂��B
���{����́A����܂ł̖L�x�Ȏ���̌�����A���������܂��B
�Ƒn��ƂɌ���������I�Ȋ�ƕ����𒊏o���Ă����ƁA���߂ĐA���̐������Ɏ��Ă��邱�ƂɋC�Â��B
���������ω��̒��ɂ����āA�������i�O�����j�͂Ȃ��Ȃ��ς����Ȃ��B
�������A���̒�����i�g�D�\�́j��ς��邱�Ƃ͏\���\�Ȃ͂����B
�A���̐������ɂ��ʂ���A �Ƒn��Ƃ̊��Ή��̃}�l�W�����g�ɂ́A������Ƃ������E���W�������邽�߂̃q���g���B����Ă���B
����������Ă����P�́u�A���̐������Ɋw�Ԓ�����ƌo�c�v�́A�ƂĂ������ɕx��ł��܂��B
������ƌo�c�Ƃ���܂����A���ƂɂƂ��Ă��w�Ԃ��Ƃ͑����ł��B
�Â��āA�L�����ƋP���Ƒn���19�Ђ̎��Ⴊ�A�u�o�c���O�ƃr�W�����v�u���Ƃ̎d�g�݁v�u�g�D�ƃ}�l�W�����g�v�u�Z�p�ƋZ�\�v�u���i�i���i�j�J���́v�Ƃ����T�̐���ŏЉ��Ă��܂��B
������̎�����ʔ����ł����A���ꂼ��ɁA�O���Ɠ����悤�ɁA���{����̉��I�ȃR�����g�����Ă��܂��B
��������̊�ƌo�c����ɐG��A�����̊�ƌo�c�҂ɉ���Ă��鎛�{����̐S�g���甭�����Ă��郁�b�Z�[�W�����ɁA�����͂�����܂����A�ܒ~������܂��B
�ǂꂾ�������ł��邩�́A�ނ���ǎ҂̖�肩������܂���B
���{����́A�����������Ă��܂��B
���n�������Љ�ɂ����āA���I����͂��܂��܂ȋǖʂŖ���Ă���B
�������Ȃ���A��ƌo�c�̌���ł́A�܂��܂����㍂�A���Y���A�V�F�A�ȂǗʂ̒Nj��ɖ�N�ɂȂ��Ă���̂��������B
���̌��ʁA���i�����ɂ�闘�v�s�������ʉ������̕s���������Ƃ������z�Ɋׂ��Ă����Ƃ����Ȃ��Ȃ��B
�ʂ̒Nj��Ɍ���ɂȂ��Ă������A���i�����Ƃ����̗͏��Ր킩�甲���o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�o�c�����̗ʂő��Ƃɗ�钆����Ƃ��A�̗͏��Ր�ɒ���ł������ڂ��Ȃ��͖̂��炩���B
���n�o�ς̎���ɂ����ẮA�Ƒn���ɐ���������Ƃ����������E���W���������̂ł���B
�����ł��܂��B
�����Ă���́A�P�ɑ��Ƃɑ��钆����Ƃ̐헪�ł͂Ȃ��A��Ƃ��̂��̂̂�����ւ̃��b�Z�[�W���Ǝv���܂��B
��ƌo�c�Ɋւ��F����ɁA���Гǂ�ł�����������1���ł��B
����̒m���ӂ�Ɋ�������͂��ł��B
�R�����Y���X�o�R�ŃA�}�]������w���ł��܂��B
���u�t�c�v���\�v�����̕����v
���������{�������@���x���^�o�Ł@1800�~
�b�r�e���r�́u��݂�����j�b�|���v�̔ԑg�ŁA
�U�N�ȏ�ɂ킽���āA�t�c�D���j�o�[�T���f�U�C���Ɏ��g��ł���̂��A����ƈ�������ł��B
�������̔ԑg�ɂ͉��o�����܂������A
���Q�l�̊S�́A�f�U�C���ł͂Ȃ��āA�v�z�Ƃ��Ẵ��j�o�[�T���f�U�C���Ȃ̂ł��B
���������ē����͂��������̈�a��������܂������A���̂����ɁA�������̏�M�Ɏ�荞�܂�Ă��܂��܂����B
����ɂU�N���p�����Ď��g��ł���p���́A���ꂾ���ł����S���܂��B
���̂U�N�Ԃ̊����܂����A����Β��ԕ��{���ł��B
���Q�l�̃��j�o�[�T���f�U�C���_���ƂĂ���̓I�Ɍ���Ă��܂��B
�v�z�Ƃ��Ẵ��j�o�[�T���f�U�C���ł�����A
�v���_�N�g�f�U�C���̘b���������ƕ��L�����E������Ă��܂��B
�@�e���X�a�@��f�Ï��̘b�A�s����܂��Â���̘b�Ȃǂ��A�ƂĂ��킩��₷���Љ��Ă��܂��B
�˂��ꍑ��͂t�c�I�ȂǂƂ������b�Z�[�W������܂��B
�����ւ�������엢���i�������ʎs�j�̕����Z���^�[�̘b���o�Ă��܂��B
�Љ�h�W���[�i���X�g�̂���̃V���[�v�Ȗڂƃt�b�g���[�N���Q�̎Ⴂ��������̑f���Ȗڂ��A
�ƂĂ������o�����X�őg�ݍ��킳���Ă���悤�Ɏv���܂��B
���̔ԑg�Ɋւ�����l�����́A���ꂼ��̃��j�o�[�T���f�U�C���_������܂����A
���ꂼ�ꂪ����ɏ����Ă���̂������ł��B
���j�o�[�T���f�U�C���̖{���̈�́u���e���v�ł���A
�����̃��j�o�[�T���f�U�C���̓����ɂ͑��l�����������Ă���悤�ȋC�����Ă��鎄�Ƃ��ẮA
���̕����ɂ����A����̃��j�o�[�T���f�U�C���_�̖{����������悤�ȋC�����܂����B
�������A�����b�Z�[�W���������Ƃ͖��m�ł��B
�ŏI�͂ł���͂��������Ă��܂��B
�o�ϗ͂�R���͂��̖͂{���Ƃ��đ��݂��钆�ŁA
���ۓI�ȃ��[�_�[�V�b�v���Ƃ邽�߂ɁA���̓��j�o�[�T���f�U�C���������ɂ��Čf���邱�Ƃ�������B
�u����̗���ōl���v�u�Θb�ƎQ���v���ɂ��郆�j�o�[�T���f�U�C���̎v�z�́A
�n���l�ɂƂ��ĉ������厖�Ȓn���v���̉^���ɂȂ���B
�����Ƃ��Ẵ��j�o�[�T���f�U�C���Ƃ́A
���{�����ۑS��ϋɓI�ɐ��i���A���E���a�̂��߂ɐ푈���N�����ʒf�ł���p�����т����Ƃł���B
���̈Ӗ��œ��{�����@�́A���j�o�[�T���f�U�C���̎v�z���̂��̂��ƌ����邾�낤�B
����������āA�ǂ݂₷���{�ł��̂ŁA�ċx�݂̍��Ԃɂł����Ђ��ǂ݂��������B
�R�����Y���X�o�R�ŃA�}�]������w���ł��܂��B
���u�푈��łցA�l�ԕ����ցv
�ނ̂����� �@�����荕��䍲�q ��g�V���@2008
�u�H��̃X�X���v�̍���䍲�q����̐s�͂Ŏ��������A���Ԃ�㐢�Ɏc��1���ł��B
���₳��͂ނ̂���������̂��b���������Ă��܂����B
���������Ɩ{�ɂȂ邾�낤�ȂƎv���Ă�����A���₳������ɂȂ��Ă̖{�ɂȂ�܂����B
�ō��̕�����Ƃ߂��荇�����ނ̂���̍K���ƎЉ�̍K�^���ƂĂ����ꂵ���v���܂��B
�����J�߂����̂悤�Ɏv���邩������܂��A�{����ǂ�ł��炦��A�����Ɣ[�����Ă��炦��ł��傤�B
93�̂ނ̂���̑̌��ɗ��t����ꂽ���b�Z�[�W�͂�������S�ɋ����܂��B
�����Ċm�M�����������z�ւ̎p�����`����Ă��āA���C�Â����܂��B
���̖ڎw���������Ƃ���قǂɏd�Ȃ��Ă����̂��ƁA���߂ċ����܂����B
������͂܂��A���̖ڎw���������ɂ͒������������ł�������܂��A�ŋ߂��������߂��Ă����̂ŁA�傫�Ȍ��C����������C���ł��B
���{�͐V���@�Ŋ��S�Ɍ�팠��D��ꂽ�B���@�X���́A�R�����{�ɑ��鎀�Y�������Ƃނ̂���͌����܂��B
���Ƃւ̎��Y�����B
�A�����J�ɂƂ��ẮA���ɔ���Șb�ł����A���Ƃ�ے肳�ꂽ���{�̂��̌�̕��݂́A�܂��ɂ���ɕ������Ă��܂��B
�����āA�ނ̂���͂��������܂��B
�u�푈���i�v�ɕ�������v�Ƃ��������ʂ�ɁA���@�X�����������邽�߂ɂ́A��������l�ЂƂ肪�ǂ�Ȑ����������Ȃ�������Ȃ��̂��B������l����Ƃ��납��A�l�ނ̕��a�ւ̓�����ׂ������Ă���̂͂Ȃ����B
���Ȃ�ɉ��߂���A���Ƃ��玩�R�ɂȂ鐶�����ł��B
����ɂ����������܂��B
������x�A��l�A��A��Ƃ����Ƃ��납��n�߂悤�A�Ƃ������Ƃł��B
���ǁA�厖�Ȃ̂́A�����~����͎̂��ȊO�ɂȂ��Ƃ������Ƃł��B���͎��ł���A�����g��厖�ɂ��Ď����Ɍւ�������A�u�������Đ�����Ƃ������ƁB��������ƁA���̐l�̂��Ƃ��悭�l���邱�Ƃ��ł���B������厖�Ɏv���l�ԂłȂ���A���l��厖�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂���B���ǁA�l��ς�����̂͂�͂莩���ŁA���͂ɂ���Đl�͕ς��܂���B
���C�Â����܂��B
���ׂĂ̏o���_�́A�����̐������Ȃ̂ł��B
����̎Љ�ɑ��Ă��A�ނ̂���͏q�ׂĂ��܂��B
���͂���܂�93�N�������Ă�������ǂ��A���{�̎Љ����Ȃɂ����킻�킵�ė����������Ȃ��Ȃ����̂́A�������Ƃ��Ȃ��B�Ȃɂ��������א�ɐ�Ă��܂��āA�o���o���ɂȂ��Ă���B������A���܂̎Ⴂ����̐l�A20���30��̐l�������킪�g�𗎂������邱�Ƃ��ł����A���ɂ��킻�킵�Ă���Ƃ����̂́A�ނ炪�����̂ł͂Ȃ��āA�Љ�̏����������Ă���̂��낤�Ǝv���B
���̎��_�ɗ����Ȃ�����A�����̂��܂��܂Ȏ����̖{���͌����Ă��Ȃ��Ǝ����v���܂��B
���肪�Ȃ��ł��ˁB
�����ň��p�����Ă�������̂́A�ق�̈ꕔ�ł��B
�����������b�Z�[�W���ӂ�ɂ���߂��Ă���{�ł��B
������̍��₳��̔����ɂ���������̎����������܂��B
�P�Ȃ長����ł͂Ȃ��A���o����ł���A�ނ̂���Ɉق������邱�Ƃ��܂߂āA�ނ̂���̔����Ƌ��U���Ă���̂��ǂ�ł��ċC�����������ł��B
����ɗ��r���Ă��鍕�₳��̌���ւ̕�������Ɋ������܂����A�܂��A����͓ǂ�ł̂��y���݂ł��B
���Б����̐l�ɓǂ�łق����ł��B
�߂��̏��X�ōw�����ēǂ�ł��������B
�V���ł����炷���ǂ߂܂����A�R�[�q�[2�t���ōw���ł��܂��B
�߂��ɏ��X���Ȃ��ꍇ�́A�A�}�]���Ő\������ł��������B
���̂Ƃ��납��ȒP�ɐ\�����߂܂��B
�푈��łցA�l�ԕ����ց\93�E�W���[�i���X�g�̔���
(��g�V�� �V�Ԕ� 1140)
���Гǂ�łق���1���ł��B
�����Đ������������ł��ς��Ă��炦��Ƃ��ꂵ���ł��B
�������ɂ��鐶�����ɁA�ł��B
�������ɂł��邱�Ƃ́A�ق�Ƃ��ɂ�������̂ł�����B
�����₳�A���{�ߑ㕶�w�َ�ÁE�Ă̕��w�����ŁA.�u�P�X�O�T�N�A�����߉��̓����v�̍u�������܂��B
�@���͗L�y���w�����̃r�b�N�J����7�K�u��݂���z�[���v�B�ڂ��������{�ߑ㕶�w�ق̃z�[���y�[�W���������������B
�R�����Y���X�o�R�ŃA�}�]������w���ł��܂��B
���u�@���̖@���\�����́u�����v���邩�v
���^��@�O�܊ف@2008�N�@1500�~
�������{���������Ă������A�u����ς�v�Ǝv���܂����B
�������́A���̖{�̍\�z�͕��������Ƃ͂Ȃ������̂ł����A
���ƂȂ�����������������낤�ȂƎv���Ă��������̖{����������ł��B
�������ǂ�ł݂���A�����\�z���Ă������e���Ă��܂����B
���������܂ł����ƃ��b�Z�[�W���Ă������Ƃ����_�Ƃ��ď�����Ă����̂ł��B
����͈������́u���ɂ̐����@���v�ł��B
�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�̊�{�����ƌ����Ă�������������܂���B
�������́A���[���ł��������Ă��Ă���܂����B
�����肵���w�@���̖@���x�ł����A���R�Ȋw�E�Љ�Ȋw�E�l���Ȋw�̋��E�A
���邢�͕��n�E���n�̋��E�����u���x�����E�A�[�c�v�̏����ӎ����ď����܂����B
���_�͂����炭�ӊO�Ɏv���邱�Ƃł��傤���A�킽���̖{�S���̂܂܂ł��B
�w�ʎ�S�o�x�w�_��x�w�����x�ɁA�w���x�_�x�w�l���_�x�w���{�_�x�E�E�E�ƁA
�Í������̖������u�@���v�Ƃ����L�[���[�h�œǂ݉������A
�����Ȃ�̃O���[�g�u�b�N�E�K�C�h�Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B
��������̂��D���ȃA�_���E�X�~�X�́w��������_�x���o�Ă��܂���B
�{���́A�u�@�����ĂȂ낤�H�v�Ƃ����₢��������n�܂�܂��B
�����āA�u���ꂩ��A���ƈꏏ�Ɂu�@���v���߂���s�v�c�ȗ��ɏo�����܂��v�ƗU���܂��B
�����āA���̏I���ɂ́u���Ȃ��͂��ׂẮu�@���v���т��u�@���̖@���v�ɂ��Ēm�邱�Ƃł��傤�v�Ɩ��Ă����̂ł��B
���̖͏��Ȃ��Ƃ����ɂ͖����ł�����̂ł����B
�����Ƃ����܂�ɂ��f�������āA�s���Ȑl�����邩������܂���B
��������z���āA�������͎����Łu���_�͂����炭�ӊO�Ǝv����ł��傤�v�ƌ����Ă���̂�������܂��A
���ɂ͋ɂ߂Ĕ[���ł��錋�_�ł����B
�����������̐��E�ɂ͂܂��Ă��܂��Ă��邩�炩������܂���B
�������A���ꂪ�{���̌��_�ɁA����قǁu�������炩��v�ƒu�����Ƃ́A�v���Ă����܂���ł����B
���ꂪ�A���́u�\�z�v���Ă����Ƃ���ł��B
���́u���ɂ̐����@���v�͂Q����܂����A�����ŏЉ��͍̂����T���܂��B
�{����ǂ�ł����āA�����ɂ��ǂ蒅���̂���Ԃ����Ǝv���܂��̂ŁB
�����Ɏ���܂ł́u�@���̗��v�͖ʔ����ł����A�����ȃq���g�ɏo���͂��ł��B
�������̃L�[���[�h�������Ă����܂��B
�u���L���̖͂@���v����u�����̖@���v��
�u���߂�A����Η^������v�Ɓu�����m��A���ӂ̂�����v
�����p�Ɣ����p
�����ƌ��㕨���w
�Ȃ��ǂ݂����Ȃ�܂��B
�Ō�Ɉ������͂��������Ă��܂��i�ꕔ�ȗ��j�B
�킽���ɂ͂������̎����Ȃ�́u�@���v�̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
���������u�v�`�@���v�́A�킽���������Ă�����ő�Ȏx���ƂȂ��Ă��܂��B
���ǁA�u�@���v�͐l�Ԃ������Ă������߂ɖ��ɗ����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��ƁA���͍l���܂��B
�l�Ԃ��K���ɂ�����́A�l�Ԃ����C�ɂ�����́A�l�Ԃ��܂����́A
����ȁu�v�`�@���v���������ꂩ��������Ă��������Ǝv���܂��B
�����āA�݂Ȃ���ɂ��A�����Ƃ���ȁu�v�`�@���v������͂��ł��B
�@���́u��������́v�ł͂Ȃ��A�u�n����́v�ƍl����ƁA�Ȃ��킭�킭���Ă��܂��ˁB ���Ă�����́A���Ж{�������ǂ݂ɂȂ��āA���C�ɂȂ��Ă��������B
����������w���ł��܂��B
���u�ԈႢ���炯�̃����^���w���X�v
�v�ۓc�_��@�@���@1500�~
�ŋ߁A�����^���w���X���傫�Șb��ɂȂ��Ă��܂��B
���̌��t�Ɏ����ŏ��ɏo������̂�30�N�O�ł��B
�����A���{���Y�{���ł��̖��Ɏ��g��ł����v�ۓc���炨���������̂ł��B
�v�ۓc����́A�����^���w���X�����ψ���������A��ƂɁu�����^���w���X�f�f�v���L���悤�Ƃ��Ă��܂����B
�Ȃ��u�g�́v�I�Ȍ��N�f�f�͊�Ƃ�w�Z�ł��̂ɁA���_�I�Ȍ��N�f�f�͂��Ȃ��̂��B
�v�ۓc����̎咣�͐����͂�����܂����B
�������Ȃ����L����܂���ł����B
�����āA�����^���w���X�̑������͑S���Ⴄ�����ɍs���Ă��܂��܂����B
�v�ۓc�_������́A�����^���w���X�����C�t���[�N�ɂ���Ă��܂��B
���܂͂����g�������^���w���X�����������������_�ɂ��Ċ�������Ă��܂��B
�ŋ߂̃����^���w���X�́A�{���ŋv�ۓc���w�E���Ă���悤�ɁA�u�S�̕a�C�v���C���[�W��������̂ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B
�����g�A���������̈�a���������Ȃ�����A���������Ӗ��Ŏg���悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B
���Ȃ��Ȃ�������܂���B
�������A���c�����^���w���X�̋v�ۓc����͈Ⴂ�܂��B
�{���̕���́u�S���a�C�ɂȂ�O�ɁA�ł�͂Ȃ��̂��v�ł��B
�v�ۓc����̃��b�Z�[�W�͖��m�ł��B
�a�C�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ������A�����^���w���X��肾�낤�Ƃ������Ƃł��B
�S�����̒ʂ�ł��B
���̒�`���ԈႦ��A�����������Ƃ͂ł��܂���B
�܂��ɂ��܁A�������͂��������ԈႢ�Ɋׂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�{���́A����������ς��Ă������߂̌[���̏��ł���A���H��Ă̏��ł��B
���Б����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�v�ۓc����̒��N�̒~�ςƐ��Ԃ̗���ւ̉����H�������āA
�{���͂��������~���肷���āA�������u���x�v���������߁A�y���ǂނ͓̂����������܂��A
���܂��܂Ȏ����Ǝ��H�I�ȃq���g�����ڂ���Ă��܂��B
����ɒ��Ҏ��g�����̂��Ă���悤�ɁA�v�ۓc����͂��Ȃ�́u�ւ��Ȃ���v�ł��̂ŁA���t�����Ō��l������M�p���Ă��܂���B
�ł�����A���ɐh��Ȍ��t�Łu�펯�v���̂Ă邱�Ƃ�����܂��̂ŁA
���b�Ƃ���l�����邩������܂��A ���̎咣�͂ƂĂ����ɓK���Ă��܂��B
�O�t���X�Ə����Ă��܂��A�̐S�̓��e�̏Љ�ł��܂���ł������A
��Ƃ�w�Z�ŁA�v�ۓc����Ă���悤�ȃX�^�C���ł̃����^���w���X����ʉ����A�S�̑̑����L���邱�Ƃ����҂������ł��B
���܂̎Љ��ς��Ă������߂̃q���g���A�����ɂ���悤�Ɏv���܂��B
���e�Љ�̑���ɁA�{������Q�̕��͂��Љ���Ă��炢�܂��B
�S�̖����A�S�̕a�̖��Ƒ����̐l�͊��Ⴂ���Ă��܂��B
�S�̖��́A���N�Ȑl���܂߂����ׂĂ̐l�̖��ł���A
���ׂĂ̊�ƁE�g�D�E�W�c�̖��ł���A
���ׂĂ̊w�Z�A���ׂẲƒ�̖��ł��B
�S�̌��N�Ǘ��̃��f���͐g�̂̌��N�Ǘ��ɂ���܂��B
���������K�v�Ƃ��Ă���̂́A�g�̂̌��N�ł�����܂��A�S�̌��N�ł�����܂���B
���ʂ̐l�ɕK�v�Ȃ̂͐S�Ɛg�̂���̂ƂȂ����A��������l�ЂƂ�́u�l�Ԃ̊Ǘ��v�ł��B
���Ȃ݂ɁA�{���ɂ͒N�ł��ȒP�ɏK���ł���A�v�ۓc���J�������u�S�̏_��̑��v�̕��@���f�ڂ���Ă��܂��B
����������w���ł��܂��B
��������l��S�������l��
���^��@���㏑�с@2007�N 1100�~
�������ƁA���̏�ɒu����Ă������^�炳��́u������l��S�������l�ցv��ǂ݂܂����B
��N�������ꂽ�{�ł����A�܂��Ɉ�����l��S���������ɂ͊J���ɊJ�����ɂ������߁A�Љ�ł����ɂ��܂����B
�u���O���ߎq�ւ̔҉��ł������܂������A�u������l��S�������l�ցv�ƈꊇ���Č���邱�Ƃւ̈�a��������܂����B
���̎�̖{�́A�ނ��낻�̏ɂȂ��Ă���ł͂Ȃ��A���̏����ԉ����̎��ɂ��ł����̂������悤�Ɏv���܂��B
��x�ǂ�ł����A���ꂻ���Ȃ������ɂ������Ɠǂ߂�ł��傤�B
�{���́A���������{�̂悤�ɂ��v���܂��B
�܂舤����l������l�́A���炩���ߓǂ�ł������ق��������Ƃ������Ƃł��B
����ɖ{����ǂނƁA�l�ɑ���₳���������܂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�{���̑тɁu����l�̂��߂̐S�̏��v�Ƃ���܂����A�������ۂ��������̖{�������ɂ͂͂���₷���悤�Ɏv���܂��B
�{���̎��̓nj㊴�͈ꕔ�A�u���O�ɏ����܂������A�����ł͎��̐S�ɂ����Ɠ����Ă������Ƃ�����������Ă����܂��B
��4�͂́u���̂��[�i���ɂȂ����Ă��܂��v�Ƃ����^�C�g���ł��B
�����Łu�F�v�̎v�z������Ă��܂��B
���̂��͎��Ԃ��ĂȂ����Ă���A
�������͂��������Ă��܂��B
���ݐ����Ă���킽�������́A����̐����̎����������Ă����ƁA
�͂邩�ȉߋ��ɂ��A�͂邩�Ȗ����ɂ��A�c����q�����܂߁A�݂Ȃƈꏏ�ɋ��ɐ����Ă���B
�킽�������͌̂Ƃ��Ă̐����ł͂Ȃ��ЂƂ̐����Ƃ��āA�ߋ������݂��������ꏏ�ɐ�����킯�ł��B
�����āA�����l����A�u���v�ւ̂܂Ȃ����́u���v�ւ̂܂Ȃ����ւƈ�C�ɋt�]����A�Ƃ����̂ł��B
���ɂ͂ƂĂ��悭�킩��܂��B
�\��̃��b�Z�[�W�������ł����A�ނ��둽���̐l�ɋC�y�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
�������́A�O���[�t�P�A�̕������L�������Ǝv���Ă��܂��B
�{���������������������������邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B
�������̃z�[���y�[�W�����Ђ������������B
�����E�����������吹�l�|�l�ނ̋��t�����̃��b�Z�[�W
���^��@�o�g�o�V���@�V�O�O�~
�ŋ߂͂��܂蕷���܂��A�����q�ǂ��̍��͐��E�̎l�吹�l�Ƃ������t���悭�g���Ă��܂����B
���̌��t���v���Ԃ�ɕ������̂́A�������Q�N�O�A���v�ԗf�a����ł����B
�u�l�吹�l���ĒN�������o�����̂ł��傤�ˁv�Ƃ����b�ł����B
���������A���̑������͍l���Ă݂�Ǝ��Ɋ�Ȕ��z�ł��B
�܂��ɐl�ޓI���_���Ȃ���A���̂悤�ɕ�����@���������z�͏o�Ă��Ȃ��͂��ł��B
����܂őS���v���Ă����Ȃ������̂ł����A
�����������z�̍���ɂ́A�����ߑ�Ƃ͑S���ʂ̎��_������܂�����A
���ꂪ�����o�����̂��͋�������b�ł��B
�����v���܂������A�����ɂ��Â����t�ł��̂ŁA����ȗ���������Y��Ă��܂��Ă��܂����B
���������v�Ԃ���͂����ł͂���܂���ł����B
���^��͍��v�Ԃ���̃y���l�[���ł����A���̋^��W�����Ė{�������܂����B
���ꂪ���̖{�ł��B
���v�Ԃ����グ�����吹�l�́@�u�b�_�A���n���}�h�A�C�G�X�A���[�Z�A�\�N���e�X�A�E�q�A�V�q�A�����Đ������q�ł��B
���̐l�������u�l�ނ̋��t�v�ƈʒu�Â��A���̃��b�Z�[�W��ǂ݉������Ƃ����̂��{���ł��B
���̃��b�Z�[�W����A�l�ނ̖����̊�]�ɂȂ���q���g���ǂݎ���ƍ��v�Ԃ���͂����܂��B
�����Ă��̃q���g����̓I�Ɍ���Ă���܂��B
���̍���ɂ���̂́A���v�Ԃ���i�������j�̈�A�̒����ʂ��Č���Ă���A�����S�w�̗��O�ł��B
���ɂƂ��ċ����[�������̂́A�������q�̘b�ł����B
���v�Ԃ���̑��q�_�͏��߂ēǂނ悤�ȋC�����܂����A���v�Ԃ���͐������q�𗴂��Ƃ����̂ł��B
���ƂȂ�A���R�A�����o�Ă��܂����A
�l�ނ̌���𐅂Ɖ���ǂ݉����Ȃ���A�Ɛ����Ȃ��āA�ΐ��i���݁j�Ƃ����̂ł��B
�R���Z�v�g���[�J�[�ɂ��ăR�s�[���C�^�[�̈��^�炳��̖ʖږ��@�ł����A
�����ɍ��߂�ꂽ���v�Ԃ���̊肢�ɂ͋����ł��܂��B
����ɍ��v�Ԃ���́A�F�l�̊��c����́u�������q�͏W���I���ӎ��v�_�ɋ������āA
�u�������q�͐l�ނ̏W���I���ӎ��̌��^�i���^�j���v�ƌ�����܂��B
�����Ă��������܂��B
�u�������q�Ƃ������ݎ��̂�����ȈӖ����߂��l�ނւ̈Í��̂悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��v
�����������ꂽ��A���Ж{�������ǂ݂��������B
�����g�́A�u�s���e�ŕ���ꂽ���݁v����u���e�ȊJ���ꂽ���݁v�ւƏ@�����i������i�K�ɗ��Ă���Ǝv���Ă��܂����i��_���̂悤�ȏ����@���̖����͏I������悤�Ɏv���܂��j�A�܂������̌����u�������q�v�ɂ���Ƃ͎v���Ă����܂���ł����B
�������́u�������q�̓�v�����Гǂ�ł݂����Ǝv���Ă��܂��B
�������q�ɍ��߂�ꂽ�l�ނ̓�����Љ����������Ăق����ł��B
�����H�Љ������
�ʖ�a�u�@���E�v�z�Ё@2008�@2000�~
����͂�����ƃe�L�X�g���̖{�̏Љ�ł��B
�Љ���Ƃ́A�l�X�̈ӎ���s���Ȃǂ̎��Ԃ��Ƃ炦�邽�߂̒����̂��Ƃł��B
���v�w�Ɠ������A�Љ�����܂��ߑ�̐\���q�̂悤�ȋC�����܂����A
���������Љ���͘J���҂̐������Ԃ��������邱�Ƃ���n�܂����Ƃ���Ă���A
���̓_�ł͓��v�w�Ƃ͈���āA�l�Ԃ̎��_��厖�ɂ��Ă��܂��B
�����āA�l�X�̎�̓I�ȓ������x�����錹��ɂ��Ȃ����Ƃ���Ă��܂��B
�܂��Â����s�������ɂ����Ă��A�Љ���͌��ʓI�ȍޗ���^���Ă���܂����A
�ŋ߂ł͂������肵���Љ���ɑウ�āA�����ȓ��v�I���ł��܂��Ă��܂��ꍇ������܂��B
����ł́A�Ǘ��̂��߂̎��Ԕc���͂ł��Ă����H�̂��߂̎��Ԕc���͂ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�b���E�����Ă��܂��܂������A�Љ���͂��܉��߂ĕK�v�ɂȂ��Ă��Ă���悤�Ɏv���܂��B
�{���͂��������Љ���̓���e�L�X�g�ł��B
���҂̋ʖ삳��Ƃ͈��N�A�X�����O��s�̂܂��Â���v���W�F�N�g�ł��ꏏ���܂����B
���͂��̑O�ɁA�ʖ삳��̒����u�����̃��[�J���E�R�~���j�e�B�v��ǂ�ŁA
���ЂƂ��ʖ삳��Ƃ��ꏏ�������Ǝv���Ă����̂��K���Ɏ��������̂ł��B
�����ŋʖ삳��̂������ȏZ�����_�ƎЉ���d���̎p���������܂����B
�u�����̃��[�J���E�R�~���j�e�B�v���ʔ����������R���킩�������������܂����B
�������肵���Љ���܂��Ă�������Ȃ̂ł��B�������Z�����_�ŁB
�{���́A�Љ���̊�{�I�Ȏ�����ł����A
�P�Ɏ�@�������A�˂������ł͂Ȃ��A�Љ�������ۂɏd�˂Ă������H�҂̎v������������ƂƂ��ɁA
�Љ���Ɏ��g�ފ�{�I�Ȏp���Ɋւ��Ă��A���܂��܂ȃ��b�Z�[�W������߂��Ă��܂��B
���Ƃ��A�Ō�̕��ɂ���ȋL�ڂ�����܂��B
�Љ���͂˂ɐl�X�̎����I�ȋ��͂���悤�ɁA
������Ƃ��������ӔC���ʂ����A�����ꂪ�l�X�ɉ��炩�̃����b�g�������炷���̂ł��邱�Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Љ���̗ϗ��Ƃ́A�ꌾ�ł����A���̂悤�ȐM��������Ȃ��悤�ɐ����ɓw�߂邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B
�����Ă����������Ƃ̈�Ƃ��āA
�X�|���T�[�����̕��⌤���̂��߂̕��ɂƂǂ߂��ɁA�ΏێҌ����̕����쐬���邱�Ƃ��Ă��Ă��܂��B
�ƂĂ������ł��܂��B
�Ō�̃��b�Z�[�W���������܂��B
�J���ґ�O�����j�̕\����ɖ��o���ߑ�Ƃ�������ɐ��������Љ���̕��@���A
���{�ɂ����Ă��A����ꂪ�������g��m��A������Љ�S�̂̒��Ɉʒu�Â��铹��Ƃ��Ē蒅���Ă������Ƃ��A�Ɋ肤���̂ł���B
������ƃe�L�X�g���Ȃ̂ŒN�ɂł��Ƃ����킯�ł͂���܂��A
�܂��Â����Љ���̉����Ɏ��g��ł���l�����ɂ͂����߂ł��B
����������w���ł��܂��B
��������Ƃɂ����ł��Ȃ������\�^�Љ�̊�ƌo�c
�X���i�@�T�����C�Y�o�Ł@2008
���ꌧ�ɖ{�Ђ̂������V�]�B�̐X��́A��Ђ̌o�c�҂ł���Ȃ���A
�����̌o�ώ����`�̊�Ƃ̂�����ɑ傫�Ȉ٘_�������Ă��܂��B
�٘_�������Ă��邾���ł͂Ȃ��A���ۂɌ����ς��悤�ƐϋɓI�Ɋ������Ă��܂��B
���̃R�[�i�[�ł��O���u�z�^�Љ�����v�����Љ�܂������A�ŋ߁A�܂��{���o�ł���܂����B
���ꂪ�{���ł����A�����ł͓`���ɂ����ł����A�����\�ȎЉ�Ɍ����Ă̊�Ƃ̂�������Ă��Ă���{�ł��B
�ƂĂ��킩��₷���A���m�ł��B
���Ƃ����������Ă��܂��B
�o�ώ����`�Љ�́u��Ɓv�Ƃ����@�l�̗��v��ڎw�����̂ł���A
�����Ɋւ��l�X�̗��v��ڎw�����̂ł͂Ȃ��B
�R�X�g�_�E���ɂ���Ă����炳��郂�m�̖L�����́A�l�ԊW���ɂ��A�l�̃��m�ɑ��鈤�������킹�A���ʂƂ��ČÂ����́A���j�I�Ȃ��̂ւ̌y���B�V�������m�Ɉ͂܂�Ă���l�ԁA���ꂪ�펯�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B
���L���Ă����]�O�̒��Ԃ��A������Đ����c�邱�Ƃ�O��Ƃ��čl����̂́A���܂ł́A�o�c�w�Ř_������̂łȂ��A�P�Ȃ�ϗ��̖��Ƃ��ĕЕt�����Ă���̂��낤�B
�@�����ƂƂ��āA�@������͓��R�̂��ƂƂ��Ď���Ă��A�@���ɏ�����Ă��Ȃ��Љ��A�ϗ��A�������͂��߁A���ɂ����ǎ��ɂ���ĉ��߂��Ă��������̂悤�Ȃ��̂ɂ́A�قƂ�NJS���Ă��Ȃ��B��������Ε֗��Ŗ��ɂ������A��ʂɂ��邱�Ƃɂ���Đl�ԂɊQ��^������̂�A�s��̗v�������邩��Ƃ����āA�Љ�Ɛ����Ă���ɂ�������炸�A���������܂��ɑ�ʐ��Y�𑱂��Ă�܂Ȃ����Ƃ͂����ɑ������Ƃ��B
���p���������܂������A�ƂĂ������ł��܂��B
���{�o�c�A�̉�Ƃ͑�Ⴂ�ł��B
�V�]�B�͕���ނ�������Ђł���ɂ�������炸�A��͂ł��邾���Ȃ��ق��������Ǝ咣���Ă���̂ł��B
�����Ď��ۂɂ����������g�݂����Ă����̂ł����A�Ȃ��Ȃ��������Ȃ������悤�ł��B
����҂Ɋւ��Ă����������Ă��܂��B
�������������ɉ��v��ڎw���ēw�͂��Ă��A�����҂ł������҂̈ӎ���s�����ς��Ȃ��Ƒ吨�͕ς��Ȃ��B���̏���҂̈ӎ��́A�������̒����ɂ킽����]�Ƃ������錃������`�����̌��ʂɂ����̂ł����낤���A�u�������Ȃ��́A�i���̕ۏ��ꂽ���́A���ł��ق������ق����ꏊ�ŋ����������́v�B���̂R����������҂����ߑ����Ă������A��͂܂��܂��ߏ�ɂȂ�A�팸����邱�Ƃ͂܂��Ȃ��B
����������Ŕj����̂́A�܂��ɒ�����Ƃ��ƐX����͎咣���܂��B
�S�������ł��B
���Ƃ��哱����Y�Ƒ̐��̒��ł́A�����\�ȎЉ�Ȃǖ��̂܂�����������܂���B
������Ƃ̐l�ł͂Ȃ��A���Ƃ̐l�A�Ƃ�킯�o�c�҂��ʂ̐����҂ɓǂ�łق����{�ł��B
�X����͎��ꌧ�ŁA�l�n�g�^���Ƃ����̂�W�J���Ă��܂��B
���ЂƂ����̃T�C�g�����Ă��������B
��y�ɓǂ߂�T�C�Y�̖{�ł��̂ŁA���ЂƂ��ǂ�ł݂Ă��������B
���E�߂��܂��B
�w���̓R�����Y���X����ǂ����B
���u�_���܂������ς��v
�������@�����o�Ł@2004
2004�N�ɏo�ł��ꂽ�{�ł����A����̃R���P�A�t�H�[�����ŏo��������҂̕������炢�������A�ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�ƂĂ��ʔ����A���낢��Ȑl�ɂ��ǂ�łق����Ƃ����C�����āA�Љ���Ă��炤���Ƃɂ��܂����B
���̖{�́A��������10�N�قǑO�ɑ̌������J�i�_�̃J�\���b�N�n�̒m�I��Q�Ҏ{�݂ŁA��Q�҂ƈꏏ�ɉ߂��������N�Ԃ̐����L�^�ł��B
�тɂ���������Ă��܂��B
�u�f���ɐ����Ă����I�@
�m�I��Q�҂ƌĂ��ނ�B
�݂�Ȍ��I�B�����Ď�������B
�ł��A�݂�ȗD�����āA�݂�Ȏ����̐��E���Ă���v
���������D�������I�Ȑl�����Ƃ̌𗬂��A���ɐ��������Ƃ�������Ă��܂��B
�����āA���҂̕���������܂��A�ނ�ɕ������ɁA�f���ɐ����Ă��邱�Ƃ��A�f���ɕ\������Ă���̂ł��B
����10�N�قǑO�ɁA�m�I��Q�Ҏ{�݂ŏh�������Ă��炢�A�ނ�̗D�����Ɋ����������Ƃ�����܂��B
�ނ�����Ă���ƁA�������������Ă��邱�ƂɋC�t������܂��B
��������́A�U�����̃A�V�X�^���g���p���Ԃ̌�A���ǂ́u���فv�����̂ł����A���̓^�����ƂĂ����������Ə�����Ă��܂��B
���܂菑���Ă��܂��Ƃ��̖{��ǂޖ��͂������ꂩ�˂܂��A
���{�ɂ����镟���̂������m�o�n�̂�����ɑ��āA�ƂĂ��傫�Ȗ���N�����Ă���悤�Ɏv���܂��B
���ɂ͂������ʔ����{�ł����B
���̎{�݂ɖ{�̗p�ɂȂ邩�ǂ����̕]���̍ۂɁA��������͂���ȃR�����g�����炢�܂��B
�u�d���͂悭���Ȃ��Ă��邪�A�c�O�Ȃ��獡������Ȃ�����̃M�t�g���Ȃ�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��A�͂����肵�Ȃ�������v
�����ł����ł��Ȃ������A�����ł͂��ꂪ�u�M�t�g�v�ƌĂ�ł��d������Ă���A�ƕ�������͏����Ă��܂��B
�M�t�g�̎v�z�B
�������̐�������g�D�̂�������l�����ł̖{���I�Ȃ��̂��܈ӂ��Ă���悤�ȋC�����܂��B
����������A��������������肵�����Ƃ͂�������܂����A��������������܂��B
�{�݂̗��p�҂ł���A�u�m�I��Q�ҁv�����ɂ��Ă̋L�q�ł��B
�u�ނ炪�A�\�͂����������Ȃ��̂́A�ǂ��o�����̂��|������ł͂Ȃ��A����Ȃ��̂͐l�ԂƂ��Đ����Ă�����ŕK�v�Ȃ��A�Ɩ{�\�I�ɂƂ炦�Ă��邩��ł͂Ȃ����Ǝv���B���Ƃ��͂ł˂������邱�Ƃ��ł����ɂ��Ă��A����̐S�܂ł͌����ĕς�������̂ł͂Ȃ��A����ȑ��l���R���Ƃ��Ă܂ł��Ď�ɓ��ꂽ���炬�ɖ{���̊�т͂Ȃ��B�����������N���ɂ����̂ł́A�Ə�ɕs�������܂Ƃ��Ă������ƂɂȂ�v
�������̐����������Ȃ̂ł��B
���Б����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���A�Љ���Ă��炢�܂����B
�Ȃ��A���҂̎�ɂ��Ă���l�b�g���[�N�u�Ȃ��v�������ł��܂��B
�ǂ������猩�Ă��������B
���H��̃X�X��
����䍲�q�@���t�V���@850�~
�ŋ߂̐H��u�[���̂�����ɂ��������̈�a���������Ă�����̂Ƃ��āA
�u�H��v�Ƃ������t�ɂ͐H�����Ă���̂ł����A���̖{�͂��̎�̖{�ł͂܂���������܂���B
�ނ���u�H��v�Ƃ͉��Ȃ̂������N���Ă���{�Ȃ̂ł��B
���ۓI�Ȗ���N�ł͂���܂���B
�ɂ߂ċ�̓I�ɁA���H�I�Ƀ��b�Z�[�W���Ă��܂��B
���҂́A���N�O���w�u�H���y�v�̐l
���䌷�ցx�����������₳��ł��B
�����́A�H��̃X�X���ł����A����H�ׂ��炢���Ƃ��Ƃ����悤�Șb�ł͂���܂���B
�����̃x�X�g�Z���[�����u�H���y�v�̂��炷���̏Љ�����ɂ��āA�����̕��������������ƕ`����Ă��܂��B
�ǂ�ł���ƁA�ʂ����ē��{�̎Љ�͖����ȗ��A�i�������̂��낤���ƌ����^��������Ă��܂��قǂł��B
�u���̂��v�Ɓu���炵�v�ړI�Ɏx���Ă���H�͂��ׂĂ̕����̊�{���Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�H����Љ������Ɨl�X�Ȃ��Ƃ������Ă���A�܂��ɂ��̂��Ƃ������ɏؖ�����Ă���{�ł��B
���`�́u�H��v�ł͂Ȃ��A�L�`�́u�H��v�A�܂�A�����_�A�Љ�_�A�l���_�Ȃ̂ł��B
���܂̊Ǘ��u���̐H�甭�z�Ƃ͑S���Ⴄ�H�當�����W�]�ł��܂��B
�ǂݕ��Ƃ��Ă��ʔ����̂ŁA���Ђ݂Ȃ���ɂ��C�y�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
������S�ɒu����Ă���̂́u�H�v�ł��B
���̎Љ�ƂȂ��Ȃ���ǂނƁA�ʔ����͔{�����܂��B
���Ƃ��A�H�i�̌��������ƕۑ��@�̘b��ǂނƁA�H�����������Ɍ�ނ��Ă��邩���킩��܂��B
�����āA�����̐H�i�U�������̈Ӗ����邱�Ƃ������Ă���悤�ȋC�����܂��B
����ɂ����A�u�H��v�Ƃ������t�����Ⴆ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���Ă��܂��܂��B
��҂̏������A�����a�������r�C�̍����ɑ傫�ȉe����^�����b�������ɕx�݂܂��B
�����Ƃ͉������l���������܂��B
�u�H��v�̘b���o�Ă��܂��B
���炭�O�ɘb��ɂȂ����؍��h���}�u�`�����O���v�Łu�H���v���b��ɂȂ�܂������A
�����ł͈�t���A�H��A����Aᇈ�A�b���4�ɕʂ�Ă��āA
�H��̒n�ʂ��ł��������������ł����A����Șb���o�Ă��܂��B
���ւ́A���̖{�ŁA�ƒ�ɂ��H�オ�K�v���Ə����Ă��邻���ł����A�����܂����B
�ŋ߁A������Â��b��ł����A�ǂ������m��w�̑̌n�ōl�����Ă���悤�ȋC�����Ă���̂ł����A
����������a���̗��R�����ƂȂ��[���ł��܂����B
������Â̎��g�ݕ����������K�v������悤�ȋC�����܂����B
�܂��A����͗]�v�Șb�ł����B
���̂悤�ɁA�����o��������Ȃ��قǁA��������̘b�肪�߂��Ă���{�Ȃ̂ł��B
���ɂ��A����̘b�A������v�w�̘b�A���l�ɂȂ���@�A���N���Â̘b�A�Z��̑�����A�܂��A�b��͍L���ł��B
�H���̃��j���[��V�s������܂��B
�A�C�X�N���[����p���̍����܂ł���̂ł��B
���䌷�ւ͂��̏������u���P�����v�ƈӎ����Ă��������ł��B
���₳��́u�H�珬���v���Ƃ����܂��B
���͐������T�̖ʂ�����ȂƎv���܂����B
�o�ŎЂ̏Љ�L���ɁA�𗧂u�H�v�̃q���g�����ڂƂ���܂����A���̒ʂ�ł��B
�����Љ�ɂȂ�܂������A����Q�t���ōw���ł��܂��̂ŁA���Ѝw�ǂ��Ă��������B
�����Ƃ��ꂩ��b��ɂȂ��Ă����{���Ǝv���܂��B
���Ȃ݂ɁA�R���Q���܂ʼn��l�ɂ��錧���_�ސ�ߑ㕶�w�قŁA
�w�u�H���y�v�̐l ���䌷�ցx�̎����R���N�V�����W���J�Â���Ă��܂��B
�Q���Q���ɂ́A���҂̍��₳��̋L�O�u���������܂��B
�e�[�}�́u�H���y�Ɠ��I�푈�v�B
����������₳��̐V���̃e�[�}�ł��B
���m�点�͈ē��T�C�g�������������B
���S�̂�����́A���Ђǂ����B
���u���v����Ղ�����
�s�얾���@�V���Ɂ@2008
�ƂĂ��s�v�c�Ȗ{�ł��B
���҂̎s�삳�s�v�c�Ȑl�ł��̂ŁA
����ƕ�������̂ł����A���z���ǂ������Ă����������܂��B
���҂̎s�삳��͑��Ƃ̃G���W�j�A�ł��B
�c���̍����珑�ɐe���݁A���ɖ{���o���Ă��܂����̂ł��B
����ő����Ă��ꂽ�̂ł����A���ɕs�v�c�Ȗ{�Ȃ̂ł��B
�s�삳��ƒm�荇���Ă��Ȃ肽���܂��B
��ƕϊv�̒�Ă�ڎw���G���W�j�A�̌�����ŁA�ނ��I�e�[�}�����ՌA�ł��B
���{�뉀�ɂ���A���H�ɂ��Ղ̂悤�ȉ�����������d�|���ł��B
���ɐ����������܂��B������Г��ɒ�������ǂ����Ƃ����̂ł��B
�ƂĂ�������Ă������Ǝv���܂����A�����͂��Ȃ������悤�ł��B
�����̃I�[�v���T�����ɂ������܂����B
�������ɂ����Č��I�Ȃ̂ł��B��x�������Y����܂���B
���Ė{�̘b�ł��B
�\�����̂��̂��A�����ĕҏW���̂��́A���͂��̂��̂��A���܂�ǎ҂��ӎ����Ă��Ȃ��̂ł��B
�ŏ��́u��w���i�̌��L�v�ł����A���̕��͂��������̂�18�A�܂��Ɏ̑̌����������̎��Ȃ̂ł��B
�����Ă���ɑ����āA�u���U��Ԃ��w������v�Ƃ������͂������܂��B
�悭����p�^�[���ł͂Ȃ����Ǝv���ł��傤���A���e���s�v�c�Ȃ̂ł��B
�����p�̃��������̂܂W�߂��悤�ȓ��e�Ȃ̂ł��B
�Ƃ��낪�A���ꂪ��ɖʔ����̂ł��B
����ɑ����āA23�̎��ɏ������u�Ȋw�҂̕�i�����j��v�Ȃ鏬�_���o�Ă��܂��B
�����ɂȂ�ƁA����ȕ��͂��o�Ă��܂��B
�u�L�Ɩ��͓������Ƃł���v�B
�����Ă��ꂪ������Əؖ�����Ă���̂ł��B
�����Ď���ɁA���m�w�̘b�Ɉڂ�܂��B
���̂����肩�珑���o�Ă��܂��B
���� �蓇�E���́u����v�̎ʐ^���o�ꂵ�A���������̂�\���ł��邱�Ƃ�����܂��B
����Ȃӂ��ɂ܂��ɒ��҂̐l���^�Ȃ̂ł����A��т����ǂݕ��ɂ͂Ȃ��Ă��炸�ɁA
�ЂƂ育�Ƃ̂悤�ɂ��܂��܂Ȃ��Ƃ�����Ă��܂��B
������Ƃ��������A���낢��ȏ�ʂŏ����ꂽ�莆�⏬�_�A���邢�͏����W������Ă���ƌ����Ă�����������܂���B
�Ō�ɎG�L�Ƒ肵�ĂR�̏͂�����܂��B
���s�����^�Ɨ��s�L�Ɛl���̃e�[�}�ł��B
���̑�ɂ��ēǂނƌ���������H������C�����܂��B
�܂��A�����������ɏ����Ă���ƁA�킯�̕�����Ȃ��{�̂悤�Ɏv���ł��傤���A���ۂɂ킯�̂킩��Ȃ��{�Ȃ̂ł��B
�����̔��Y�^�ł͂Ȃ����Ƃ����C�����ēr���œǂނ̂��~�߂悤�Ƃ����̂ł����A
���ƂȂ��������܂�Č��ǁA�Ō�܂œǂ�ł��܂��܂����B
�����ēǂ�ł��܂��Ǝ��ɕs�v�c�Ȃ̂ł����A�s�삳��̃��b�Z�[�W���`����Ă����̂ł��B
�͂��߂ɁA�Ŕނ͂��������Ă��܂��B
���͊w�����炷��i�r���ȗ��j���s��w��w�@�@�B�H�w�����ȏC�m�ے����A
���̌�A�G���W�j�A�ɂȂ�B�ƌ����A���Ԃł̓G���[�g�I�ȑ��݂�������Ȃ��B
���A�������ꂾ���̐��E�����m��Ȃ�������A�����炭�����������c�̂ɓ����Ă������A
���܂��āA�ǂ����Łu�̂��ꎀ�v�ɂ��Ă������ǂ��炩�������Ǝv���B
���̐l�����Q�{�ȏ�ʔ����L���ɂ��Ă��ꂽ�̂���������т������芪�����E�Ƃ̏o��������B
���̖{��ǂ�Ŏs�삳��̂��Ƃ��悤�₭�킩�肾���܂����B
�O�̂��߂ɂ����A���Ɋւ��Ă͂��낢��Ɩʔ����b���o�Ă��܂����A�������邱�Ƃ����Ȃ�����܂���B
�s�삳�u���v��ʂ��ē����A��������́u�v������w�Ԃ��Ƃ͏��Ȃ�����܂���B
�s�v�c�Ȗ{�ł��B
�݂Ȃ���ɂ����߂��ׂ����ǂ��������܂����A
�܂��A���������{�̂��肩��������Ƃ������ƂŏЉ�Ă����܂��B
�݂Ȃ�����A�������̖{�������Ă݂܂��B
�s�삳���1����16������L�c�s�����p�ُ��O���ŌW���J�Â��܂����A
�����ɂ����Ǝs�삳��ɉ�邩������܂���B
�s�v�c�Ȑl�ł��B
��������낵�����`�����������B
���u�������̂��ށv
�ďC���^��@���㏑�� 2007
�������̊ďC�Ŏn�܂����u���{�l�̖����v�V���[�Y��1���ڂł��B
����Ɂu�n�[�g�t���e�B�[�̂����߁v�Ƃ���悤�ɁA
������ڎw���u�n�[�g�t����\�T�G�e�B�v�Ɍ����ẴK�C�h�u�b�N�ƌ����Ă������ł��傤�B
�����Ɉ�����u���̑傢�Ȃ鎜�߁v��������Ă��܂����A
�������炵���p�[�X�y�N�e�B�u�������������ɕx�ޕ��͂ł��B
�������̓R�[�q�[����D���Ȃ̂ł����A���������Ă��܂��B
�R�[�q�[���ӎ����u�O�v�Ɍ����킹����ݕ��Ȃ�A�Β��́u���v�ւƌ����킹�܂��B
�����������܂��B
�i�����̈��ݕ��ł���R�[�q�[�Ƃ͈Ⴂ�j�Β��́u�����v�̈��ݕ��ł͂���܂���B
�ނ���A�u�����v����̂��āu�ґz�v�ւƌ����킹��͂������Ă��܂��B
�����ɂ́u���a�v�Ɓu�����v���Ïk����Ă���ƈ������͂����܂��B
�����܂ł͂�������ȂƓǂݐi�߂��܂����A�������͂����ł͎~�܂�܂���
����ɁA�����Ƃ͂�����@������������ꏊ���Ƒ����܂��B
�萅���͐_���A�|���͕����A��@�͎A���p���ʂ͓����A�ގт̓L���X�g�����ے����Ă���Ƃ����̂ł��B
�@���ւ̑��w�ɐ[���������炵���b�ł��B
������Ƃ������ɂ̐l�ԊW�ݏo���̂��������Ƃ����܂��B
�܂����{�ł́A
�u���i���ł��������ł����{�����X�ł��A�X�ɓ���ƈ�t�̂������o�����B��������ŁA�����炨����肵�Ă��^�_�v
�Ƃ������Ƃɑ傫�ȈӖ���ǂݎ���Ă��܂��B
�����g���A�����������ɂ����A���{�l�̐���������{�Љ�̕����̖{��������悤�Ɏv���Ă��܂��B
�܂��Ɉ�������C�t���[�N�ɂ��Ă���z�X�s�^���e�B�̖{�����܈ӂ���Ă��܂��B
�ƂĂ��Z�����͂̒��ɁA��������̎��������߂��Ă��܂��B
���̗��j����p�A��������ނȂǂ̏Љ������܂��B
���N�����̐����̔��Ɏ��g��ł���ۓ����̎Ⴂ�o�c�҂���{���C���X�g���N�^�[�Ƃ̑Βk������܂��B
�ӂ��C�Ȃ�����ł��邨������߂Ă���傫�ȃ��b�Z�[�W�����߂čl����������D���ł��B
���̃V���[�Y�͂��ꂩ��u�ԁv��u���فv���v�悳��Ă���悤�ł��B
������n�肾���A�n�[�g�t�����C�t�̐��E������Ă����̂��y���݂ł��B
���u�ҏW��
���ؓc�ƕ��̎���v
����䍲�q�@�p��I���@1700�~�i�ŕʁj
���₳����2�N������Ŏ��g��ł����{���������܂����B
����͍��ؓc�ƕ��ł��B
�A���A���₳��̊S�́A��ƂƂ��Ă̓ƕ��ł͂Ȃ��A�W���[�i���X�g�E�ҏW�҂Ƃ��Ă̓ƕ��ł��B
���ɂ�������̐V��������������܂��B
���₳��̎莆�̈ꕔ�����p�����Ă��炢�܂��B
�����̓��I�푈���̑O��ɁA�ҏW���Ƃ��Đ������̎G����n�����A
���̌�͎���u�ƕ��m�v�@�������āA���F�̂���O���t�B�b�N�ȎG���s���������ƕ��B
���ׂ�ɂ�Ďv�������Ȃ����������X�ɂ킩���Ă��āA
�ƕ��Ƃ��̎��͂̐l�����Ɏ䂫�����邱�ƂɂȂ�܂����B
�������A�u�ƕ��Ёv�͔j�Y�Ƃ����ؖ����v���邱�ƂɂȂ�A
���̈�N�]��̂��ɓƕ���36�ŖS���Ȃ��Ă��܂��B
�ނ̋N���ɕx�l���̑唼�́A��M���ӂ��ҏW�҂Ƃ��Ĕ�₳�ꂽ�̂ł����B
���݁A�قƂ�ǖY����Ă���ƕ����肪�����G����u�ƕ��m�v�ɂ��āA
�{�������������ɒm���Ă���������A����قnj��h�Ȃ��Ƃ͂���܂���B
���傤�Ǘ��N�͍��ؓc�ƕ��v��S�N�̋I�O�̔N�ł��B
���̒��O�ɖ{�������s�ł������Ƃ��A�S���炤�ꂭ�v���Ă��܂��B
�ƕ��̎��ɖ��͓I�Ȑ��������A���������ƕ`����Ă��܂��B
���͓r��2��قǗ܂��o��قǂł����B
�������A����ȏ�ɋ������������̂́A���₳��炵���O��I�Ȓ����ɂ�邳�܂��܂Ȕ����ł��B
��������̎���ɂ��ʂ��郁�b�Z�[�W�������������̂����Ȃ�����܂���B
���オ�̂ĂĂ����Љ�̕�����l�ԓI�Ȑ��������v���o�����Ă���܂��B
���ؓc�ƕ��Ɋւ��ẮA���ɂ͎��R��`��ƂƂ������ƂƁu������v�����m��Ȃ������̂ł����A
�{����ǂ�ŁA�ƕ��̐������ɂ����傫�ȃ��b�Z�[�W�����邱�ƂɋC�Â��܂����B
�Љ������ڂ������ł��܂��B
�܂��ɍ��₳�����悤�ɁA�ҏW�҂ɂ��ăW���[�i���X�g�Ȃ̂ł��B
������ƈ�ʂ̐l�ɂ͌h�����ꂻ���ȏ����ł����A
�����������ɔY��ł���l��231�łɂ���ƕ��̎莆��ǂ�ł݂Ă��������B
���C�����炦�܂��B
���̑O�ɂ���u�ƕ��Ђ͎��R�̍��v�̂�����������ɕx��ł��܂��B
�i���Љ�ɕ��S���Ă���l�́A212�ł̒�ӎЉ�|���^�[�W���ւ̓ƕ��̎w�E��ǂ�ł��������B
�A�C�f�A�Ɍ͊����Ă���l�́A�ƕ��̃A�C�f�A�Ǝ��H�͂Ɏh�����Ă��������B
���܂��܂Ȓ�������Ă����ƕ��̎��Ɛ�͂ɂ͎h������͂��ł��B
�����Ƃ�������A���邢�͓��{�̎Љ�Ɉ�Ă��Ă������́A�Ȃǂ�m���ł���������ޗ�������������Ă��܂��B
���낢��Ƃ��Љ�����Ƃ���͂���̂ł����A���r���[�ȏЉ�����ǂ�ł��炤�̂���Ԃł��B
���͂͂ƂĂ��ǂ݂₷���̂ŋC�y�ɓǂ߂܂����A�Ȃ��ɂ́u������v������܂��B
�u��̏��ʐ^�t�v�̐��̂������ɉ𖾂��Ă����̂ł��B
�O���͍��₳��炵�����f�B�e�[�����L���߂���̂ŁA����Ă��Ȃ��l�͂�����Ɣ��邩������܂��A
���ꂪ�㔼�̖ʔ����ɂȂ����Ă����܂��̂ʼn䖝���Ă��������B
�㔼�͂����ƈ������܂�Ă����܂��B
���ꂪ����X�^�C���Ȃ̂ł��B
�����A�O����ǂ�A�����x��œǂ����Ǝv���Ă����ɂ�������炸�A
�㔼�ɓ������r�[�Ɏ~�߂��Ȃ��Ȃ�A�Ō�܂œǂ�ł��܂��܂����B
�Ō�ɁA�Ȃ������₳��͂��������Ă��܂��B
�W���[�i���Y���Ɛ푈�̊W�́A����ɐ����鎄�����ɂƂ��Ă��d�v�ȃe�[�}�ɂȂ��Ă���B
���������߂邾���ł͂Ȃ��A�Y�p����Ă���ߋ����ӂ�Ԃ邱�Ƃ��K�v�ł͂Ȃ����B
���߂Ă��܁A�����v�킸�ɂ͂����Ȃ��B
�����{����ǂ�ŁA���߂Ă����v���܂����B
�d���ɂ͂����ɂ͖𗧂��Ȃ���������܂��A���E�߂��܂��B
��������w���ł��܂��B
���u�킪�l���́u�������v�v
���v�Ԑi�@���㏑�с@1000�~�i�ŕʁj
���v�Ԑi����́A���̃R�[�i�[�ɂ悭�o�ꂷ�����v�ԗf�a�i���^��j�����̕���ł��B
���̓x�A���������͂���܂��ꂽ�L�O�ɁA�����g�̐�������U��Ԃ�A������u�������v�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��̂��{���ł��B
�ƂĂ��R���p�N�g�i�\�t�g�J�o�[�̐V���Łj�ŁA�C�����̗��������{�ł��B
�Ƃ����̂��A���e�́u������ɂ��݂��މ��������t�ƁA������������ʂ̎ʐ^�v�ō\������Ă��邩��ł��B
�ʐ^�͒��҂̗F�l�́A����̎ʐ^�ƁA���c�~�v����̉���̎ʐ^�ł��B
���̎ʐ^�ɓY����悤�Ȍ`�ŁA���ғƎ��́u�������v��������A���̍��ԂɃz�b�Ƃ��郁�b�Z�[�W��������Ă��܂��B
�ǂށA�Ƃ��������A���߂Ȃ���l����A�Ƃ����悤�Ȗ{�ł��B
���Ƃ��A����ȕ��͂��o�Ă��܂��B
�N���Ƃ�����A
�ЂƂA�ЂƂA�̂ĂĂ������ƁB
���ꂵ���Ȃ��B
���ꂪ�����A
�܂�����Ȃ̂�����܂��B
���肪�Ƃ��A�����
�ǂ��ɂł�
����ɂł�
���肪�Ƃ�
���肪�Ƃ��̐�����
���Ȃ��͍K���ɂȂ��̂�����
���҂́A���{�Ƀz�X�s�^���e�B�Y�Ƃ̑������̈�l�ł��B
10�N�ȏ�O�ɖk��B�s�Ŏn�܂����z�X�s�^���e�B�^���̃V���|�W�E���ɎQ�������Ă���������ɂ�����܂������A���̎��͖k��B�s�ό�����̉�ł����B
���ɑs��ȍ\�z�͂��������Ŏh�������炢�܂������A���̉��Ŏ��ƈ��^�炳��Ƃ̕t���������n�܂�܂����B
�ŋ߂͈������̖{����ǂ܂��Ă�����Ă��܂������A����͋v���Ԃ�ɍ��v�Ԑi����̖{�ł��B
�{�̍Ō�ɁA�u�z�X�s�^���e�B�Y�Ƃ̊m����ڎw���āv�Ƃ������_���ڂ��Ă��܂��B
�Z�����̂ł����A�ƂĂ������ɕx��ł��܂��B
���Ƃ��A�u�z�X�s�^���e�B�Ƃ͔������v�Ə����Ă��܂��B
�P�Ȃ�u�����ĂȂ��v�ł͂Ȃ��A����������ݍ���Łu�S������v���u���������o��v�A���ꂪ�^�̃z�X�s�^���e�B���Ƃ����̂ł��B
�������Ƃ����A���v�Ԃ���́A���}������@�ɂ��ʂ��Ă���A���݂͓��{�V�當������̉�ł�����܂��B
���v�Ԃ���̃z�X�s�^���e�B�_�������{�ɂ��Ăق����Ǝv���Ă��܂����A
���̖{�̍s�Ԃɂ͂��������z�X�s�^���e�B�̖{�������߂��Ă���悤�ɂ��v���܂��B
�����g�s���āA������Ƃ������Ԃ��ł������ɍD���ȃy�[�W���J���Ă݂�ƁA�����ƌ��C�ƒm�b�����炦��ł��傤�B
����Ȗ{�ł��B
�{���̍Ō�ɁA����ȕ��͂�������Ă��܂��B
�����Ƃ́A�������ǂ��܂ō��߂��邩�B
���̒��킪�A���̐l���ڕW�ł��B
��ꂽ��Ɛl�̊F����ɁA���ɂ��E�߂��܂��B
���u�b�r�q�C�j�V�A�`�u�v
���{�o�c�ϗ��w��b�r�q�C�j�V�A�`�u�ψ���@���{�K�i����@2600�~
�b�r�q�i��Ƃ̎Љ�I�ӔC�j�͌Â��ĐV�������ł����A���܂��ƂɂƂ��Ă͑������������헪�I�ȉۑ�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
�������A���t�̍L����̂��ɂ͎��̂͂��Ȃ�B���̂܂܁A�`���I�Ȏ��g�݂ɏI�n���Ă���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
���ɂƂ��ẮA���̖��́u�o�c�_�v�Ƃ��������u��Ƙ_�v���ƍl���Ă��܂��̂ŁA�����̎��g�݂ɂ͂ނ���傫�ȕs�M���������Ă��܂����A�o�c�_�Ƃ��Ă̂b�r�q�������Ɛ^���Ɏ��g�܂��ׂ����Ǝv���܂��B
�b�r�q�͑��Ƃ̓��y��C���[�W��͂ł͂Ȃ��A�܂��ɋƐтɒ��������肾����ł��B
���{�o�c�ϗ��w��ł́A���ł�2�N�O�ɁA��Ƃ��b�r�q��i�߂Ă�����ł̗��j�ՂƂȂ�A�o�c���O�A�s�����́A�s������u�b�r�q�C�j�V�A�`�u�v�Ƃ��Ă܂Ƃ߁A���\���Ă��܂��B
�{���́A���̎��H�I�ȃK�C�h�u�b�N�ł��B
���̋�̓I�ȓW�J���A�e�Ђ̎�����ӂ�ɏЉ�Ȃ���A����H�I�ɉ�����Ă���Ă��܂��B
�̌n�I�ȍ��ڗ��Ă��A�e���ڌ��J��2�y�[�W�Ƃ����X�^�C���ł܂Ƃ߂Ă��܂��̂ŁA�S�ɉ����Ăǂ�����ł��C�y�̓ǂ߂�Ƃ����b�r�q���T�ł�����܂��B
�Ҏ҂̈�l�ł����鐴����������́A�u�����Ɂv�ł��������Ă��܂��B
���ʓI��CS�q�R�~���j�P�[�V�����Ƃ́A����̃X�e�[�N�z���_�[�̕��X�Ɖ䂪�Ђ̐l�X�Ƃ��A�及�������猨�����t���ň���I�ɓ`����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
�ł��邾�������ڐ��ŁA���x�ł��J��Ԃ����b�Z�[�W��`���A�������J���l���A���P�̂��߂̍s�����s���A���̐��ʂ��܂��`���Ă����B
����A�l�Ɛl�Ƃ̏z�I�ȑ��ݍ�p�Ȃ̂ł���B
�����ł��B
�b�r�q�Ƃ́A��Ƃ̑�����ՂƂ��Ă̎Љ�Ƃ̃R���{���[�V���������Ȃ̂��Ǝv���܂��B
�{����ǂނƁA���̃R���{���[�V�����̐���������邩������܂���B
��������w���ł��܂��B
���u�ʔ�����
�l�Ԋw�v
���^��@���m�o�ŎЁ@1400�~
�������̍ŐV��ł��B
����Ɂu�l���̗ƂɂȂ�101���̖{�v�Ƃ���܂����A
30�N�ɂ킽���āA�l�̐������A�������Njy���Ă������m�o�ŎЂ̏��Ђ̒�����A
101���̖{���Ȍ��ɏЉ���u�b�N�K�C�h�ł��B
�l�Ԋw�Ƃ����ƂȂɂ�����������܂����A�������͐l�Ԋw�ɂ��āA���������Ă��܂��B
�l�Ԋw�Ƃ́A�l�Ԃ������ɐS�䂽���ɐ��������Ɛ����Ă��������l���邱�Ƃł���B
������A�l�Ԋw�͊y�������A�ʔ����B
�Ȃ��Ȃ�A�킽�������͐l�Ԃ����炾�B
�l�ԂɂƂ��Ĉ�Ԗʔ������̂͐l�ԂɌ��܂��Ă���ł͂Ȃ����B
�S�������ł��B
�����Ƃ����̖{����ɑz�肵�Ă���̂͊�Ƃ̌o�c�҂�o�c�����ł��B
�͗��Ă��A�u�鉤�w����v�u��l�Ɋw�ԁv�u�o�c�̉����v�u�S�䂽���ɐ�����v�u�l�Ԃ炵��������v�u���t�̕�Δ��v�ƂȂ��Ă��܂��B
1��2�y�[�W�ō\������Ă��܂��̂ŁA�C�y�ɓǂ߂܂��B
�������炵���K�C�h�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�킩��₷���ǂ݂₷���ł��B
��Ƃ̌o�c�����̊F����ɂ́A�l�Ԋw���l���邽�߂̃K�C�h�u�b�N�ɂȂ�ł��傤�B
���u�����ւ̗�
���{�E�A�����J�ҁv
�ܖ؊��V�@�u�k�� 1700�~
�u�����ւ̗��v�͉���肠�����̂ŁA�V���[�Y�ŏI���́u���{�E�A�����J�ҁv���Љ���Ă��炢�܂��B
�{���̂��Ƃ����ŏ�����Ă���悤�ɁA���̗F�l�̍��₳�ւ���Ă��܂��̂ŁB
�{���ł́A�e�a�Ƒ��͂�9.11��ʂ��āA�V���������̉\�������b�Z�[�W����Ă��܂��B
�ŋ߁A���܂�{��ǂދC�͂��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł����A���͂ɐ���������A�������C�ɓǂ߂܂����B
�����Ȃ�����S���Ď�����鎦��������������܂������A
����ɉ����āA����Љ�Ɍ����Ă̋���������s�ԂɊ����Ă��܂����̂́A���̌��݂̐S���̂�����������܂���B
9.11�����̑��������A�ƂĂ������ł��܂����B
�j���[���[�N�Ƀz�[�����X�����Ȃ��Ȃ��Ă������ƂɁA
�u���͂��������א��҂��{�C�ʼn�������낤�Ƃ���A�ǂ�Ȃ��Ƃł��\�ɂ��Ă��܂̂��ȂƁA���Â��Ɋ��������̂ł���v
�Ƃ����Ƃ����ǂ�ŁA9,11�����̌���Ōܖ��������Ă������A������������������ɑz�����Ă��܂��܂����B
�܂����q�������ŖS��������e�i�A�f�[������j���A
���̌�̃A�����J�̓����̂Ȃ��ŁA�u�������A�����J�l���������Ƃ����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ǝv���A
�A�t�K���̌��n�ɍs���A���a�̊����Ɏ��g��ł����Ƃ����b�́A
�܂��Ƀ}���`�`���[�h�̐��E�̍L�������������b�ł��B
���͂∫�l���@�̘b���ʔ����ł����A
�����������Ƃ������̐����Ɛ����Ɨ��ݍ����Ȃ������Ă���{������A
���������ڂ⎞�����m�b������������炦�܂��B
�����Ȃ���A�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
�ǂ�A���̃V���[�Y�͓��{�̕����E�ւ̖���N�̖{�ł͂Ȃ����Ƃ����C�����Ă��܂����B
�����̐V�����\��������������グ���Ă��܂����A
���{�̕����E��������������N���āA����̃r�W�����ƃ~�b�V�������L���Љ�ɔ��M���A�����o���Ăق����Ǝv���܂��B
�ł���A�ܖ���ɂ��A����N�����ŏI���̂ł͂Ȃ��A
�����E�̐l�����ƈꏏ�ɁA���H�Ɍ����Ă̐V�����������N�����Ăق����Ǝv���܂��B
�����N���b�N����ƃR�����Y���X��ʂ��ăA�}�]������{�����w���ł��܂��B
�u�����L�v�͂Ȃ��3��������Ă��܂��܂����B
���u�����L�v
�@���@�����o�Ł@2001�N 1600�~
����͎��̒m�l�ł͂Ȃ��l�̖{�̏Љ�ł��B
�Ȃ��P�����O�ɖS���Ȃ�܂����B
�ȗ��A�{��ǂދC�͂������Ă��܂������A
�ȑO�A�ܖ؊��V����́u�����ւ̗��v��ǂ�ŁA�C�ɂȂ��Ă����{������܂����B
�S���Ȃ����ȂƁA�����A�S��ʂ킹�����Ȃ��ŁA�Ȃ������̖{���v���o����܂����B
�����œǂ�ł݂܂����B
20�N�O�i��Ђ����߂��O��j����ȂƘb���Ă����A
�����ڎw���Ă��鐶�����������ɂƂĂ���̓I�Ɏ�������Ă��܂����B
�����܂����B
���́A�ڎw�������Ŏ��s�ɂ͂��ǂ���Ă��܂��A
�{���ɏ�����Ă���قƂ�ǂ��ׂĂ��A���̎v���ɏd�Ȃ�܂��B
���̖{�̌����������ꂽ�̂�1970�N��͂��߂ł��B
������30�N�ȏ�O�ł����A���̍��ɖ{���ɏo����Ă�����A���̐l���͑傫���ς���Ă����悤�Ɏv���܂��B
���҂̖@���́A�؍��̑m�ŁA�u�،��o�v�Ɓu���̉��q���܁v�����Ǐ��������ł��B
�����̊�{�M���́u�{�����ꕨ�v�B
�@���́A���������Ƃ������Ƃ́A����ł͉����Ɏ�����Ƃ������Ƃ��Ƃ����܂��B
�����āA���̂��ƂɋC�Â����B�@���́A�����S�Ɍ��߂������ł��B
�u���̎�����A���͂P���Ɉ��������������Ă��镨���̂ĂĂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƐS�ɐ������v�B
�����āA���H����܂��B
�{���́A���̖@�������X�̐����̒��Ō��������������Ƃ������W�߂����M�W�ł��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
�����I�ȑ}�b�����Ȃ�����܂���B
�D�_�̔�Q�����b���������o�Ă��܂����A���ɋ������܂��B
��l�ł������̐l�ɓǂ�ł��炢�����āA�Љ���Ă��炢�܂����B
�����Ɛ������ɁA�V�������_�������Ă����Ǝv���܂��B
���X�ł͌�����܂��A�A�}�]���ōw���ł��܂��B
�������N���b�N����Ƃ��ꂪ�ł��܂��B
���w�u���{�������v�̕��a�w�x
��{���@���Ώ��X�@2600�~�i�ŕʁj
���a�����C�t���[�N�ɂ��Ă�����{�������̍ŐV��ł��B
�{���́A��{���a���_�̏W�听�Ƃ������܂����A�����ɂ��܂̓��{�̏܂����u�x���̏��v�ł�����܂��B
�����������̕��a�ւ̎��g�݂ɑ��Ă��A�Ȃ����ꂪ�t�����Ă��Ȃ��̂��A��{����Ǝ��̎��_�ŗ��_�����Ă��܂��B
��҂��ӎ����ď�����Ă��܂����A�_�|�����ŁA�ƂĂ������͂�����܂��B
��҂����߂ɂ��Ă��܂����A������������ǂ݂����{�ł��B
��{����́u���a�v���u���O�̐푈�̋ꂵ�݂���̉������{�I�l���Ƃ��ĕۏႳ��Ă����ԁv�ƒ�`���Ă��܂��B
���̒�`�ɂ́A���ɂ��܂��܂Ȃ��Ƃ��܈ӂ���Ă��܂��B
�����������a���������邽�߂ɂǂ������炢�����B
����͖{����ǂ�ł��������B
����܂ł̑����́u���a�W�̏��v�Ƃ͈Ⴂ�܂��B
�ڐ�����ɐ����Ҍl�ɂ���̂ł��B
��{����͂������̋�̓I�ȊT�O���N���܂��B
���Ƃ��Ί�{�I�l���Ƃ��Ắu���a���v�A�����āu���O�̔����v�B
����܂ł̕��a�w����͏o�Ă��Ȃ����z�ł��B
�u���O�̔����v�Ƃ́A���O�����Ƃ̕����ɂȂ邱�Ƃ����ۂ��錠���ł��B
���O�ɂ��\�͂��֎~���A�\�͂�Ɛ肷�邱�Ƃɂ���āA�ߑ㍑�Ƃ͌��͂̊�Ղ��m�����܂������A
����͓����Ɂu������\�͂Ɏ��o�������v�̊l���ł�����܂����B
���̂��߁A����܂ł̕��a���_�̒��ł́u���O�̕������v�����ɂȂ�܂����B
���O����������̎��R�����߂āA�����オ�錠���ł��B
���̓T�^�I�Ȃ��̂��s���v���ł����A��{����͂��������u���O�̕������v�͂��͂�K�v�Ȃ��Ȃ����Ƃ����܂��B
�ނ��낻�������������͍��Ƃɑg�ݍ��܂�Ă��܂��A�����I�ɂ͍��Ƃɑ��镺���`���ɓ]�����Ă��܂����Ƃ����̂ł��B
���Ƃɂ��\�͍s�g�̎�͍̂����ł��B
���Ƃ��푈�𐋍s�ł���̂́A�����Ƃ��Ă̍��������R�ɖ\�͐��s�p���[�Ƃ��Ďg���邩��ł��B
�u�b�V���⏬�푈������킯�ł͂Ȃ��A���n�Ő킢��S���͕̂����⎩�q�����ł��B
�������ނ�͌����Ƃ��Đ��Ől���E�����Ƃ��܂߂��\�͂̍s�g�����ۂ��邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł��B
�����ł́u���a�̂��߂ɐl���E������v�Ƃ����������Ȃ��Ƃ��N����܂��B
�����ŁA���Ƃɂ��\�͍s�g�̂��߂ɋ�������邱�Ƃ����ۂ��錠���Ƃ��āA�������d�v�ɂȂ��Ă���Ƃ����킯�ł��B
����̓K���W�[�̔�\�͎�`�Ƃ��Ⴂ�܂��B
���̔����͐�{���a�_�̃L�[���[�h�̈�ł����A
���������������̏d�v�ȊT�O���������̐����̎��_�Ō���Ă���̂ł��B
�����āA���{�l�̋M�d�Ȑ푈�̌��܂��āA���a�ւ̊v�����X�^�[�g�����悤�ƌĂт����Ă��܂��B
���̑����́A�u�푈���ł��鍑�Ɓv�ɐ���������邱�Ƃ��Ƃ����܂��B
��̓I�ɂ́A�V�������a���@�̐���ł��B
���̓_�Ɋւ��ẮA���̓��{�̏͑S�����̕����������Ă���A
�푈�����₷�����悤�Ƒ����̐����Ƃ�o�ϐl�͍l���Ă��܂����A�����̍������܂�������x�����Ă��܂��B
��{����́A����������m���Ă�������A�����ĐV�������a�w����Ă���킯�ł��B
���Ȃ݂ɁA��{����͐V�������a���@���N�Ă��Ă��܂��B
����Ɋւ��Ă͂��łɕʒ��u�����ŏ������I���{�����@�����āv�������Ă��܂����A�{���ɂ���{���a���@�Ă��f�ڂ���Ă��܂��B
�ݖ�̌����҂̐V�������a�_�B���Б����̐l�ɓǂ�łق����Ǝv���܂��B
��{������܂ŏo�ł��ꂽ�{���A�����Ă��ǂ݂��������B
�������҂Ƙb�����������Ƃ������������炨�m�点���������B
��{��������Љ�܂��B
5�l�ȏ�W�܂�A��{��������Ăт��Ęb�������̏������悤�ɂ��܂��B
���܁u���a�v�̖�����������ƍl���Ă����Ȃ���A
���̐�100�N�A�������͂��Ԃa����ɓ���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂��B
�����Ȃ�Ȃ��悤�ɂ���̂��A���{�l�̃~�b�V�����ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�{����ǂ�ŁA���a�ɂ��Ă��Ѝl���Ă݂Ă��������B
���u�����ւ̗��@�u�[�^���ҁv
�i�ܖ؊��V�@�u�k�Ё@1700�~�j
�����V���[�Y�����N���������Љ���W�������āA�u�[�^���҂��Љ�܂��B
���̖{�Â���ɂ́A����䍲�q�������[���ւ���Ă��邩��ł��B
�������u�[�^�����ܖ���ƈꏏ�ɕ�����Ă��܂����B
���₳��̓t���[�̃m���t�B�N�V�������C�^�[�ł����A
�{���́u���Ƃ����ɂ����āv�Ōܖ����g���������ɂȂ��Ă���悤�ɁA�ܖ���̒���ɂ��̐��N�ւ���Ă��܂����B
����܂ň�x���Љ�邱�Ƃ͂���܂���ł������A����͏Љ���Ă��炢�܂��B
�Ƃ����̂��A���͖{�����Ă�����Ă��炵�炭�ǂގ��Ԃ��Ȃ������̂ł����A
���A�^�钆�ɖڂ��o�߂��܂����̂Ŗ��C���ĂыN�������Ɠǂݏo������A�������܂�Ă��܂��āA���ɓǂݖ������Ă��܂����̂ł��B
�����ڎw���Љ�̃r�W�����������Ɋ���������ł��B
�����ł�����ƐQ�s���œ�����������Ă��Ȃ��̂ł����A
����������Ȃ������ɁA���Ɏh�������Q�̂��Ƃ������Ă������Ƃɂ��܂����B
�ŏ��͗։��]���ƂȂ���̘b�ł��B
�u�[�^�������̊�{�ɂ͗։��]���v�z������܂�����A���҂�����߂����Ȃ��A��c���{���s��Ȃ��悤�ł��B
���̉����Ɂu�Ȃ���v���o�Ă��܂��B
�ƂƉ��N�ɂ���āA���ׂĂ̐�������̂͂Ȃ����Ă����܂��B
�։��]���Ƃ������Ԃ����c�̂Ȃ��肪�A���܌��݂̐����̂Ȃ�����ӎ������邱�ƂɂȂ�܂��B
���ׂĂ̐l�A���ׂĂ̐��������A������ĂȂ����Ă����킯�ł��B
��������o�Ă���̂́A�u�݂�Ȃ��K���łȂ���Ζ{���Ɏ����̍K���͂Ȃ��v�Ƃ������z�ł��B
�܂��Ɏ����ڎw���A��������Z�݂₷���Љ�ł��B
�`�x�b�g��u�[�^���ɂ��鉻�g�̍l���́A�����������Ƃ���l����Ɣ[���ł��܂����A
�Ƒ��̂�����A�Ƒ��ƎЉ�̂�����ɂ��������̔��z�Ƃ͑S������������������邱�Ƃ������Ă���܂��B
�����āA���̂��Ƃ̓u�[�^�������g��ł���u�������K�����iGNH�FGross
National Happiness�j�v�̃e�[�}�ɂȂ����Ă����܂��B
����Ɋւ��ẮA�{�������Гǂ�ł��������B
������l�ЂƂ�܂ł��f�m�o��ōl����悤�ɂȂ��Ă��܂������{�ƁA
�����܂ł�����l�ЂƂ�̐����̂f�m�g��ōl����u�[�^���B
���̈Ⴂ�ɂ́A���j�̊�H���܈ӂ���Ă��܂��B
�u�[�^���ɂ��ߑ㉻�̔g�������Ă��Ă��܂��B
���N�̐V�t�̃e���r�ŁA�ܖ���Ɖ��쎵������̑Βk������܂����B
�����ł��u�[�^���̍������K���ʂ��b��ɂȂ�A
���삳�A��x�A�����I������m���Ă��܂��A���͂�߂�Ȃ��ƕs����\������܂������A
�ܖ���͐V�������������Ǝ咣����Ă��܂����B
���͌ܖ���ɋ������܂��B
�u�[�^���̍������K���ʂ̎������A���j��ς��Ă������Ƃ����҂��܂��B
���̉\�����ŏ�������߂邱�Ƃ͂������͂���܂���B
���n�ő̌�����Ă������₳����ܖ�����A���{�̕����ƃu�[�^�������͈Ⴄ�Ƃ����܂����A
�{����ǂ�ŁA���͍l�����ɂ����ĂقƂ�Ǔ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B
�ނ��뎄�������Y�ꂽ��A�C�Â��Ȃ��Ȃ��Ă������{�Љ�̌Ñw���A�����Ɋ������܂��B
���̎v���Ⴂ��������܂��B
������ɂ���A�L���X�g���ƃC�X�������̑Η��ɐU�����ς��邽�߂ɂ��A
�����͑傫�Ȗ������ʂ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
����܂�{���̏Љ�ɂ͂Ȃ�܂���ł������A�Ƃ����������ɕx��ł��܂��B
�����̐������ւ̂�������̃q���g�������܂��B
�ǂ݂₷���{�ł��̂ŁA���Ђ��E�߂��܂��B
���u���ώ��ƂƓ��{�Љ�v
�������u�ďC�@���ό�����ҁ@�ی������V���Ё@1800�~
���܁A�l�X�̏��������ł��鋤�ς�ݏ�������̊�@�ɗ�������Ă���B
���肳�ꂽ�ی��Ɩ@�̒��g���m����ɂ�A�e��c�̂̓��O���������߂�^�����N�����Ă����B
���ς���邱�ƂŎ���̐����Ǝd���A�n��Љ����낤�Ƃ���l�X���A�g�D�������Ď���Ȃ����Ƃ��Ă���B
�{���̏o�ł́A���ώ��Ƃ��S���̐E��A�n��ɍL�����Â��č����̐������x���Ă��������`���A
�ی��Ɩ@����ɂ�鋤�ϋK�������������炷���Ƃ������ɑ��āA
���m�ȔF�����L���Љ�ɑi���悤�Ƃ�����̂ł���B
�{���́u���Ƃ����v�̏����o���̕��͂ł��B
�����ی��Ǝ҂��K������͂��̕ی��Ɩ@���肪�A���{�̌×��̕����ł�����A���܍Ăь������ꂾ���Ă������ϕ��������Ƃ��Ă��邱���Ɋւ��ẮA����܂ł��������Ă��܂����B
�{���́A�����������ƂɊ�@�������߂Ċ������J�n�������ό�����̃����o�[���ً}�o�ł������̂ł��B
���܂��܂Ȏ��т��d�˂Ă��Ă��錻�ꂩ��̕��܂߂āA���ϕ����̌����ƈӋ`������Ă��܂��B
�������A��������Ă��邾���ł͂Ȃ��A�����ɓ��{�Љ�̖����Ɍ����Ă̒��҂����̐[���v�����ɂ��݂łĂ��܂��B
�P�Ȃ�u���ώ��Ɓv�̖{�ł͂Ȃ��A�o�ώ�`��{���̍����̕����ւً̈c�\�����ĂƂ���ɕς��V�����Љ�̂�����ɂȂ���Ȃǂ����߂�ꂽ�A�Љ�ϊv�̏��ł��B
�����āA�������̎Љ��炵�̒��ň�ĂĂ����A�x�������̒m�b���A���߂Ďv���o�����Ă���鏑�ł�����܂��B
���ЂƂ������̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
�{�̓��e�͖ڎ�����ǂݎ���Ă��������B
�_�l�����������ɂ킽���Ă��܂����A�������A���ꂼ��̌���ɗ��r���Ă���l�����̃R���{���[�V�����̐��ʂł��邱�Ƃ����炵���ł��B
���Ƃ����ł�������Ă��܂����A���̖{�̏o�ł��̂��̂��A�V�������ϕ����̗\�������������܂��B
�����ЂƂ����A���Ƃ���������p�����Ă��������B
���ς́A�l�Ԃ̐������ɁA���́A�ЊQ�A�l���̃h���}�ɍ������Ă���B
���̂��Ƃ��炵�A�d���Ɛ����A���R�����Đl�Ԃǂ����̌��т��A�܂�́A�Љ�ƃ��X�N�̌����ɍ������Ă���̂ł���B
���̈Ӗ��ŁA���{�Љ�̊�{�`�Ɨ��j�I�n�w�E����f���A�x���Ă���B
�ƂĂ������ł��܂��B
�����g���A���{�̋��ϕ����̉�����Ă���҂̈�l�ł����A
����̕ی��Ɩ@���肪�A���ϕ����̌��Ă����Ƃ��A�傫�ȃ`�����X�Ƃ��đ����Ă������Ƃ�����Ǝv���܂��B
�܂��ɉГ]���ĕ��ƂȂ��A�ł��B
���̂��߂ɂ��A������ƍd���{�ł͂���܂����A�ł��邾�������̐l�����ɓǂ�łق����{�ł��B
�܂��S�̂�����́A���Ћ��ό�����ɂ����Q�����������B
�T�D���ϋK���̌o�߂Ɠ��e
�P�D���ώ��Ƃ̍����I�Ӌ`�Ɩ@�K�����
�Q�D���Ă̕ی��}�[�P�b�g�g��Ƌ��ϋK��
�R�D���ώ��Ƃ̗��j�Ƌ��ϋK���̗��j
�S�D���ϖ@�̌���Ɖۑ�
�U�D���ώ��Ƃ̉ʂ����Ă�������Ɖۑ�
�P�D���ώ��Ƃ̑S�̑�
�Q�D�����g�����ς̉ʂ����Ă�������Ɖۑ�
�R�D���ς̌o�c���Ɩ@�K��
�S�D���勤�ς̉ʂ����Ă�������Ɖۑ�
�T�D�J���g�����ς̉ʂ����Ă�������Ɖۑ�
�U�D���F���ς̘_�c�ƘA���̎��g��
�V�D�o�s�`�́u���S�ݏ���v�̉ʂ����Ă�������Ɖۑ�
�W�D�m�I��Q�҂́u�ݏ���v�̉ʂ����Ă�������Ɖۑ�
�X�D�J���A�̂b�b���ς̉ʂ����Ă�������Ɖۑ�
10�D���[���b�p�ɂ����鋤�ϑg�D�̈ʒu�Â��ƌ���
��������щ��
�ی��Ɩ@�������̌o�߂Ɣw�i����
���Ȃ݂ɁA�u��������щ���F�ی��Ɩ@�������̌o�߂Ɣw�i�����v�͊�삳��̗͍�ł����A�����ǂނ����ł��A���낢��Ȃ��Ƃ������Ă���͂��ł��B
�R�����Y���Ќo�R�ŃA�}�]������w���ł��܂��B
���u���n�ƃJ�G�T���v
�i���^��@�O�܊ف@1400�~�j
��������̍��x�̐V���́u�n�[�g�t���E���[�_�[�V�b�v�v�_�ł��B
���n�ƃJ�G�T���Ƃ����A���͓I�Ȑl���ɐ��������ނɂ��āA�l�ԓI���͂Ƃ͉������c���Ɍ���Ă��܂��B
���͎��͂܂����ǂ��Ă��܂���B
���̃R�[�i�[�ł͕K���ǂݏI������ŏЉ���Ă�����Ă��܂����A����͏��߂Ă̗�O�ł��B
�����ɒʓǂ���{�ł͂Ȃ��ƍl�����̂ł��B
���ܖ����P�O�ł��ǂ�ł��܂��B
�Q�ŒP�ʂł܂Ƃ߂��Ă���̂ŁA�ƂĂ��ǂ݂₷���̂ł����A���̂Q�y�[�W�Ɏ��ɂ�������̎��������߂��Ă��܂��B
�ł�����A�ނ���������Ɠǂ݂Ȃ���A�����~�܂��Ď����̐��������l����̂��悢�ƍl�����̂ł��B
���낢��ƍl���������邱�Ƃ������ł��B
�ǂ݂Ȃ���l����{�Ȃ̂ł��B
�S�̂͂S�ɕ������Ă��܂��B
�u���[�_�[�̗��z�v�u���[�_�[�̎����v�u���[�_�[�̎g���v�u���[�_�[�̏����v�ł��B
�S�̂𗬂��̂́A���n�ƃJ�G�T���ւ̒��҂̑z���ł��B
�������̒���̊�{�R���Z�v�g�̂ЂƂ́u�n�[�g�t���v�ł����A
���̂Q�l�͂܂��ɂ��̃R���Z�v�g��̌����Ă���u�n�[�g�t���E���[�_�[�v�Ȃ̂ł��B
�{���̖`���ŁA���҂͂��������Ă��܂��B
���[�_�[�Ƃ͂܂��A�l�����݂ł���A����䂦�l�������݂ł���ƌ�����B
�ł́A�ǂ�����Đl�����̂��B����́A���̐l�̐S���������Ȃ��B
�Ȃ�A�ǂ�����Đl�̐S�����̂��B
�u�l�̐S�͂����Ŕ�����v�ƌ������l������������ǂ��A�������A�l�̐S�͂����ł͔����Ȃ��B
�l�̐S�������Ƃ��ł���̂́A�l�̐S�����ł���B
�{���ł́A�O��I�Ɂu�S�v�ɏœ_�ĂāA���[�_�[�V�b�v�ɂ��čl���Ă݂��B
�{���́A�������̕����S�w�O����̂ЂƂA�u�E�q�ƃh���b�J�[ �` �n�[�g�t���E�}�l�W�����g�v�̑��҂Ƃ��ď�����Ă��܂��B
�E�q��h���b�J�[�������S�w�ɂ�����u�m�v�̕����̋�҂Ȃ�A���n��J�G�T���́u�s�v�̕����̋�҂��Ƃ����킯�ł��B
�����̊�Ƃ͂��܂��܂ȕa�����������Ă��܂����A����́u�S�v�������Ă��܂������炾�Ǝv���܂��B
��Ƃ��u�S�v�����߂��ɂ́A��Ƃ̃��[�_�[�����i�o�c�҂Ɍ���܂���j���A����̐S���Ăі߂��Ȃ��Ă͂����܂���B
�������̕����S�w�V���[�Y�Ɏ����������Ă��闝�R�̈�ł��B
��̓I�Ȏ�����ӂ�ɏo�Ă��āA
�W�W���ڂ̏����o���������ɕx��ł��āA�ڎ������邾���ł��ǂ݂����Ȃ��Ă��܂��B
��Ƃ̌o�c�҂�Ǘ��҂ɂ͂��ЂƂ����E�߂�����1���ł����A
�����̐�������������ƐU��Ԃ��Ă݂����Ǝv���l�ł���A����ɂł����E�߂������Ǝv���܂��B
�����āA���ЂƂ��A�ǂ݂Ȃ���l���Ă݂Ă��������B
�������̊֘A��������Ђǂ����B
http://www.ichijyo-shinya.com/books.html
���u������̒ʂ��Θb�@�v
���ǗY�@���܂��܂��@700�~�i�������݁j
�Θb�@�������̐��ǗY���A���炪�J�����ꂽ�u�Θb�@�v�̃e�L�X�g���I���f�}���h�o�ł���܂����B
���̃R�[�i�[�ł��ȑO�A���Љ���w�P���Đ�����x�i���|�Ёj�̑�Q����y��ɂ��Ă��܂����A���̌�̎��H�܂��āA���e�͂���ɂ킩��₷���A�����H�I�ɂȂ��Ă��܂��B�����^�тɂ��֗��ȏ����q�X�^�C���Ȃ̂����ꂵ���ł��B
�ڂ����͐�삳����Θb�@�������̃z�[���y�[�W���������������B
�I���f�}���h�o�łȂ̂ŏ��X�Ȃǂł͍w���ł��܂��A�z�[���y�[�W�ɂ͐\�����ݕ��@�Ȃǂ�������Ă��܂��B
�{���́u�͂��߂Ɂv�ŁA��삳��͑Θb�@�̊T�������������Ă��܂��B
�Θb�@�́A�u�����̍l����C�����������O�ɁA���肪�����������Ƃ̗v�_���A����Ɍ��t�Ŋm���߂�v���Ƃ������ɂ��Ă��܂��B����̉�b�̂Ȃ��ŁA�K�v�ȂƂ��ɁA���̌�������邱�Ƃɂ��A�X���Ɠ��l�A�����h������A�M���W���͂����ނ͂��炫������܂��B
�u�Θb�@�v�̌����̌㔼�̕������A�]���̌X���ɑ�������̂ł����A�u�Θb�@�v�ł́A���̊T�O�ƋZ�@���A�V���Ɂu�m�F�^�����v�Ɩ��Â��܂����B�X���Ƃ����Ăѕ��ł́A�u�����X���ĕ������v���Ƃ́u�����v�̏d�v�����ڂ₯�Ă��܂�����ł��B���̂悤�ɁA�i�Θb�@�j�ł́A�Θb�̌����m�ɂ�����A�V�����p��������ꂽ���Ƃɂ��A�X���Ƃ���ׂċZ�@�̗����ƏK�����e�ՂɂȂ�܂����B
��삳��͊e�n�Łu�Θb�@�v�̌��C���[�N�V���b�v��W�J���Ă��܂����A�{���ł́A��ʂ̎Q���҂�ΏۂƂ��čs�Ȃ������C��̗l�q���Č�����`�ŁA�u�Θb�@�v�����H�I�ɐ�������Ă��܂��̂ŁA���C��ɎQ�������悤�ȋC���ŁA���������Ɠǂ�ł����܂��B
��{�����}�X�^�[����A�N�ł��������̂��̂ɂł���̂��A�u�Θb�@�v�̓����ł��B
��삳��́A���̖{��ǂl�����ɂ���āu�Θb�@�v���S���e�n�ɍL����A���K�Ȑl�ԊW�ɗ��ł����ꂽ�A���S�ŏZ�݂₷���Љ�������邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�R�[�q�[�Q�t���ōw���ł��܂��̂ŁA���Ђ݂Ȃ�������ǂ݂��������B
����ɂ���āA�����ƊF����̎��ӂ͋C�����̗ǂ��Љ�ɂȂ��Ă����͂��ł��B
���u�̋��̐e���V�����Ƃ� �@�S�U�̉��������X�g�[���[�v
�i���c�����q �����@�K�o�� �@�P�U�W�O�~�j
�ŋ߁A�u���������v�Ƃ������t���悭�����悤�ɂȂ�܂����B
�j�Ƒ��Љ�̂Ȃ��ō�����i�ނƁA�e�̉����́u�����I�Ȏ����v�ɂȂ�܂����A
���̐e�Ƃ̐����ꏊ����������Ă���ƁA����ɖ��͕��G�����܂��B
�̋��ɏZ�ސe�̉��̂��߂ɁA��Ђ����߂ċ����ɖ߂����F�l���A���ɂ����l�����܂����A
�����Ȃ���T���͌̋��̎��ƂɋA�鐶�������Ă���m�l�����܂��B
��Ƃ�s���ɂƂ��Ă��A�u���������v�͐^���ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��e�[�}�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B
���́u���������v�Ƃ������t�ݏo�����̂��A�{���̒��҂̑��c����ł��B
1998�N�A�u�u���������v�̏��Ȃ����v�i���o�Łj���o�ł��A
����ĕ�炷�e�̃P�A���l�����p�I�b�R�i�m�o�n�@�l�p�I�b�R�̑O�g�j�������A
�ȗ��A���c����͉��������Ɏ��g�ނ�������̐l�����Ɖ�����Ă��Ă��܂��B
�{���́A������̏W�听�ŁA
�S�U�̉��������̎�����Љ�Ȃ���A���������̎�������̓I�ɒ��Ղ����Ă���܂��B
�{���̑тɏ�����Ă���悤�ɁA
�������������Ă���l�A����ĕ�炷�e�̘V�オ�C�ɂȂ�l�ɂ͂ƂĂ��Q�l�ɂȂ���e�ł����A
����ȊO�̐l�����ɂ����Гǂ�łق����{�ł��B
�̋��̐e���V����O�ɁA�ł��B
�{���̎��Ⴉ��́A���������Ƃ��������āA
�������̐������₢�܂̎Љ�̂�����ɑ��邳�܂��܂ȃ��b�Z�[�W���`����Ă��܂��B
�������̂悤�ɁA���łɐe�����������v�w�ɂƂ��Ă��A�l���������邱�Ƃ���������܂��B
���̖{��ǂ�A���������ς�邩������܂���B
���ꂩ��̎Љ�Ɍ����Ă̑傫�ȃq���g���ǂݎ��܂��B
�e�̉��ɂ́A���̐l�̐������≿�l�ς����o���܂��B
���邢�́A�����ʂ��āA����̐l�����l����_�@�ɂȂ�Ƃ����Ă������ł��傤�B
�����Ŗ����̂́A�e�̉��Ƃ��������A����̐������Ȃ̂ł��B
�������A����͂��������ς��āA�����ɂ܂��߂��Ă�����ł�����܂��B
�S�U�̕���́A����̐������Əd�˂ēǂނƁA���̂��Ƃ������ł���͂��ł��B
�u�e�q���v�̐�ɂ���u�v�w���v�̖����l����q���g�����肻���ł��B
���c����́A�{���̃v�����[�O�ŁA
�u���v�Ɂu�������v���������������̂悤�Ɏv��ꂪ�������A���́A����ȏ�̎v�������߂Ă���B
����܂ł́A���Ƃ����A�H�����g�C����Ȃǂ̐g�̓I��삪���S�ɂƂ炦���Ă������A
���������͂���ȊO�̈Ӗ����܂߂Ă���B
�Ƒ������ɂ����Ȃ�����A������u���v���K�v�ƂȂ�ȑO���獢�邱�Ƃ������͂��߂�B
�Ə����Ă��܂��B
�ǂݗ����Ă��܂������ȁA���̕��͂Ɏ��͍��̎Љ�̖{���I�Ȗ��������܂��B
�����āA�������ł͂Ȃ������ł��낤�ƁA���͓�����肪�N�����Ă��Ă���悤�ɂ��v���܂��B
�u���Ƃ͂Ȃ���̂��Ɓv���ƍl���Ă��鎄�ɂƂ��Ă��A�ƂĂ��l���������郁�b�Z�[�W�ł��B
������ɂ���A�u���v���͂��ׂĂ̐l�ɂƂ��āA�K�����̌�������ł��B
���ЂƂ������̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
�Ⴂ����ɂ����Гǂ�łق����Ǝv���܂��B
����̐��������l����q���g������������͂��ł�����B
���u�Ћ��m����́v�ւ��`�A�Ћ����Ă��������d���ȂI
�m�o�n�@�l�s���������Z���^�[�E�n���Y�I���I����@600�~
�R���P�A���Ԃ̃n���Y�I���I��ʂ̏o�ő�2�e�ł��B
�O����u���̂������ȏꏊ�\�����{�݂̎s���^�c���l����v�͂ƂĂ��D�]�ł������A
�{�������ݓI�Ȗ���N����������܂܂�Ă��鋻��������e�ł��B
�Ћ��A�܂�Љ�����c��́A�n�敟���̎���Ƃ��Ă�����Ă��܂������A
�ŋ߂͐V���Ȏ���ł���m�o�n�Ƃ̊W���K�������悭�Ȃ��A�ꍇ�ɂ���Ă͑Η��W�����N�����Ă���Ƃ��������܂��B
�����ŏ��́A�Љ�����c��̖����͂����I������Ȃƍl���Ă��܂������A
�R���P�A������ʂ��āA�����œ����Ⴂ�E���̏�M�ɐG��Ă��邤���ɍl�����ς���Ă��܂����B
���Ȃ��Ƃ�����܂ŎЉ�����c���ĂĂ����l�b�g���[�N��m�E�n�E�͑傫�ȎЉ���ł��B
�{���͍�ʌ����̎Љ�����c��̐E���L�u��NPO�̊W�҂��ꏏ�ɂ������{�ł��B
���̂�����ɂ����̒m�l�����Ȃ��Ȃ��̂ł����A
4�N�O���炶������Ǝ��g��ł��������̐��ʂł��̂ŁA���e�͂ƂĂ������ɕx��ł��܂��B
�Ȃɂ����J�W���A���ɖ{���Ō�荇�������e���A�ǂ݂₷���܂Ƃ߂��Ă���̂����ꂵ���ł��B
�n�敟���͂܂��Â��肻�̂��̂ł����A�������̐������ɐ[���Ȃ����Ă��܂��B
�������A���Ƃ��ΎЉ�����c��Ƃ������O����m��Ȃ��l�����Ȃ�����܂���B
���������l���܂߂āA
�Љ�����c��̊W�҂݂̂Ȃ���A
����ɂ͎Љ�����c��̌���y���̕����ɔ������Ă���l�A
�t�ɂm�o�n�̓ƑP�I�Ȏp���ɔ����������Ă���l�A
���邢�͋C�����悭��点��Љ������Ă���l�A
����Ȑl�����ɂ��Гǂ�ł����������������q�ł��B
���e�͎��̒ʂ�ł��B
�L���������̂P ��������{�����k����Ћ��m�d�����ĉ����H
�L���������̂Q �ǂ��Ղ藷���L�����m��T���ɐ���
�L���������̂R �������̘b�����n�敟���m���_�ɂ��ǂ�
�����ҁF��ʌ����̎Ћ��Ƃm�o�n�̋����Ɋւ��钲����
�Ћ��L�����N�^�[�R���N�V����2007�Ƃ����A�y�������ʕt�^�܂ł��Ă��܂��B
���X�ł͍w���ł��܂��A�n���Y�I���I��ʂɘA�����Ă��炦��w���ł��܂��B
��330-0063��ʌ��������s�Y�a�捂��2-10-6
���[��office@hands-on-s.org TEL/FAX
048-834-2052�i�S���F����j
���̖{������ɐV���������N�����Ă������Ƃ����҂��Ă��܂��B
���u�����Ȃ�̂��ʂ�v
�i���^��ďC�@�}�K�Ё@1400�~�i�ŕʁj
������ďC���ꂽ�{�ł��B
�ڂ��������́A
�w�u���̐l�炵�������ˁv�Ƃ����� �����Ȃ�̂��ʂ�@�������x
�ł��B
�{�̑тɏ�����Ă���悤�ɁA���܂́A�u����ꂩ���v�͎��������߂��鎞��Ȃ̂ł��B
�ďC�҂̈������́A�{���A���v�ԗf�a����ŁA���̃R�[�i�[�ł����������X�Љ���Ă�����Ă��܂����A
���̃e�[�}�͂܂��Ɉ������̓ƒf��ł��B
�{���𑗂��Ă��ꂽ�莆�ɂ���������Ă��܂��B
�{���́A���V��l�ԂɂƂ��Ă̋��ɂ̎��ȕ\���Ƃ��ĂƂ炦�Ă��܂��B
����̑��V�ɂ����邠������_��^��_�ɂ��L���ڂ�z��A
���ꂩ�獂��҂ƂȂ��Ă䂭�c��̐���̐V�������V�X�^�C���������Љ�Ă���܂��B
�i���j���̖{�ɂ���āA�����̓��{�l���u���v��u���v���^�u�[�������A
����I�ɍl���Ă���邫�������ɂȂ�Ɗ���Ă��܂��B
���������A����������̂������̃X�^�C�����l���邱�Ƃ́A�Ⴂ�Ƃ��قǁA���R�ɔ��z�ł���ł��傤�B
�����āA����͐������̖��ɂ��Ȃ����Ă����܂��B
���������Ӗ��ŁA���͂��̖{�����ЎႢ����̐l�����ɓǂ�łق����Ǝv���܂����B
�������A�g�߂Ȗ��Ƃ��čl������̂́A���̂悤�Ȑ��ォ������܂���B
�ŏ��͂�����ƕǂ����邩������܂��A�ǂݏo���ƁA�������Ȍ������ł����A�y�����Ȃ��Ă��܂��B
���ꂩ��̐��������l����h��������������炦��͂��ł��B
�������̊ďC�Ӑ}�͌����ɐ������Ă��܂��B
����̐��������l���邽�߂ɁA���E�߂������{�ł��B
���w�����p���`�x
�i���|��q�@��g�u�b�N���b�g�@700�~�j
http://www.iwanami.co.jp/hensyu/booklet/
�R���P�A���Ԃ̏��|��q���܂Ƃ߂��A�����̂킩��₷���u�b�N���b�g�ł��B
���ی��̊�{�I�Ȃ����݂�����̋�̓I���e�A�������Ƃ��̉������@�A�֘A���Ȃǂ��A
65�̗p��ɂ킯�āA���p����s���̗��ꂩ��������Ă��܂��B
���|����́A�s���������I�t�B�X�E�n�X�J�b�v����ɂ���A���ɐ��͓I�Ɋ���Ă��܂��B
�����ŏW�܂��������A�����݂̂Ȃ���́u���̂����炵�v�Ɋ��p���Ă��炦�邱�Ƃ�����āA���̖{���܂Ƃ߂��̂ł��B
�ƂĂ��ǂ݂₷���A�֗��ł��B
����ɏ��|����炵���A�ɂ߂Ď��H�I�ł��B
�{�����Q�O���ȏ�A�܂Ƃ߂čw�����ꂽ�����͏��|����ɗ��ނƕX��}���Ă���܂��B
���ɂ��A�����������B
���M���V�A�E���[�}�������S�ȁi�㉺�j
���щ�v�E�����r���Ė�@�����[�@�e4300�~
���ы������܂����͓I�Ȗ{��|��A�����Ă��Ă���܂����B
�Ñ㐢�E�̃p�m���}�̃��B�W���A���łŁA���Ɋy�����{�ł��B
�U�O�O�߂��ʐ^���A�Ă��˂��ȉ���Ƌ��ɍڂ����Ă��܂��̂ŁA���ꂾ�����Ă����Ă��M���V�A�E���[�}���E���[���Ɋ��\�ł��܂��B
�܂��P�Ȃ�ʎj�ł͂Ȃ��A�e�[�}�ʂɂ��Ȃ�ڂ������y����Ă��܂��̂ŁA�V������������������܂��B
�����㉺2���Z�b�g�Ȃ̂ŁA���͎������ǂ��Ă��܂��A�ƂĂ����ꂵ���̂́A�ʐ^�̉����R�����A����Ɋ֘A�����̏�������Ƃ���ɂ��邱�Ƃł��B�������A����炪���ɂł͂Ȃ��Ȃ��肠���`�ŕҏW����Ă��܂��B
���Ƃ��A��_�A�X�N���s�I�X�̐���ɗ��n���Ă���G�s�^�E���X�̖�O����̎ʐ^�̐������ɂ́A�u�ߌ��ɂ���Ċϋq�̐S�ɂ���Y�݂́u�����v����v�Ƃ����A���X�g�e���X�̃J�^���V�X���_���Љ��Ă��܂����A����Ɋ֘A���āA�������ɃA���X�g�e���X�̎��w�̏��ڂ��Ă���̂ł��B
�ł�����A��O����ƈ�ÂƂ̂Ȃ��肪��������ƌ����Ă��܂��B
�����ȑO�A�g���R�̃x���K�����̃A�X�N���s�I���i��Î{�݁j�ƁA���̏�̃A�N���|���X�ɂ��錩���Ȗ�O�����K�˂Ă��Ƃ�����܂����A���̓���u�����^���P�A�v�̎��_�łȂ��čl�������Ƃ͂���܂���ł����B
�A�X�N���s�I�����珬�����u�ɗ��匀��͌�����̂ł����A����ɂ��̌��ɂ̓g�����k�X�_�a���������悤�ȋC�����܂��B
�����l���Ă����ƁA�A�e�l�̃A�N���|���X�ɂ��A�V�����Ӗ��������Ƃ邱�Ƃ��o���܂��B
��������A�M���V�A�̈�ÂƂ͂Ȃ����̂����z�����L����܂��B
�ʂ̂Ƃ���ɏ�����Ă����w�̍��ڂ̖{���ɖ߂��ēǂݏo���ƁA�����ɃA���X�g�t�@�l�X�̊쌀�u�_�̕��v������Ă��܂��B
����ɍؐH��`�̂��Ƃ܂ŏ�����Ă��܂��B
�x���K�����̃A�X�N���s�I���ł́A����Ö@�≹�y�Ö@�̘b���܂������A���ꂾ���ł͂Ȃ��A�Ñ�M���V�A�̈�Â͓��m��w�ɂȂ���z���X�e�B�b�N�Ȃ��̂��������ƂɋC�Â��܂��B
�������̂��̂����ÂɂȂ��Ă��������ł̑̌����A����A�����̐��삳�����炨���������Ƃ���ł����A�M���V�A�̃A�X�N���s�I���ł́A�����������Ƃ��s���Ă����̂�������܂���B
���������ӂ��ɁA�Ñ㐢�E�̃p�m���}���ǂ�ǂ�ƍL�����Ă����̂ł��B
�D��S��c��܂��A���̍D��S�����Ȃ薞�������Ă����q���g���ӂ�ɍ��߂��Ă���A���ꂪ�{���̖��͂ł��B
�N�w�Ƌ���̏͂��A�ŋ߂̓��{�̋���_�c�ɏd�˂ēǂ�ł����Ǝ��ɖʔ����ł��B
����Ȃ킯�ŁA�{���́A�ǂޕS�Ȏ����ł�����܂��B
�ł�����A�ނ���ʓǂ���̂ł͂Ȃ��A�p�b�ƊJ�����Ƃ��납��ǂݏo���āA���������p���Ȃ���A�O�҂����R�ɔ�тȂ���ǂނ̂��A�{���ɂ͌����Ă��邩������܂���B
�Ǐ��T�[�t�B���O���y���߂�킯�ł��B
�Ė�҂̏��ы����́A���낢��Ɛg�̓I�ȏ�Q���������Ă���ɂ�������炸�A�Ƃ������O�����ɂ��낢��Ȋ����Ɏ��g�܂�Ă��܂��B
�����ĉ��l���A���̏��ы��������ɂ����������x���Ă���悤�Ɏv���܂��B
���ы����͂܂��A�ƂĂ��l�ԓI�Ȃ������������������ł��B
���������l�����A�����Ɩ{���ɂ��e�����Ă���͂��ł��B
������ƒl�i�������ł����A���݊��̂���{���̓��e���l����ƁA���ꂾ���̉��l�̂���{�ł��B
�p�E�T�j�A�X�W���p���̊F�����Ñ㐢�E�ɊS�̂���l�����A
�����Ă�����Ǝ��Ԃ��o���n�߂��c��V�j�A�̐l�����ɂ́A���Ђ��E�߂��܂��B
�}���قŎ�ēǂޖ{�ł͂Ȃ��A�w�����ėׂɒu���Ă����{�ł��B
��������w���ł��܂��B
���u�m���ăr�b�N���I���{�O��@���̂����v�v
���^��@��a���[�����핶�Ɂ@762�~�i�ŕʁj
���^�炳��̍ŐV��ł��B
�u���_���� vs �L���X�g�� vs �C�X�������v�i�����핶�Ɂj�ɑ������̂ł����A�����vs
�ł͂Ȃ��A& �łȂ���Ă��܂��B
�u�_�����������v�ł��B
�������̎莆�̕��͂��ꕔ���p�����Ă��炢�܂��B
��_�����m�̏Փ˂��l�ގЉ�̑��������������݁A�킽���������ڂ�������ׂ��Ȃ̂́A�@���̎����Ă��銰�e�����Ǝv���܂��B
�{���Ŏ��グ���_���A�����A�̎O�@���͂�������u��v��u���߁v��u�m�v�̐��_���d���A
�܂�͎v�����̐S���ɂ����@���ł���A
���̎O�@������ՓI�ɍ��̂��ʂ������������A�킽�������̓��{�ł��B
�O�@���͂܂��A���m���A�S�w�A�������ՂƂ������q�ǂ������ݏo���A���{�l�̐S�́u�������v�������Ă��܂����B
�����āA�������́A���������Ă��܂��B
�l�ނ̊�@���~���閧�́A�܂��ɓ��{�l�̏@�������̂Ȃ��ɐ���ł���Ƃ����m�M�̌��ɖ{���������܂����B
���E���̐l�X�̐S���u���v�Ŗ������A���h�t���E���[���h�ɂȂ邱�Ƃ�����ď����܂����B
�����Ɉ�a��������܂����i�������������������ł����j�A���g�͂������肵���{�ł��B
���{�̎O��@���́A�����܂ł��Ȃ��u�_���E�����E�v�ł����A
����炪�A���h�t���ɐ��݈�ĂĂ������E���킩��₷���`����Ă��܂��̂ŁA
�O���Ɠ��������ՓI�Ȑ��������邱�Ƃ��ł��܂����A�V������������������͂��ł��B
�Ȃɂ����A�����Ȃ���̃��b�Z�[�W��������̂������ł��B
�Ō�̂ق��ŁA�Γc�~��̐S�w������Ă��܂����A
�����Ō���Ă���u�S�v�������A�_���A�����A�����H�I�ɂȂ���v�ł���A
���ꂪ�������̎句���Ă���n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�ɂȂ��邱�Ƃ���������Ă��܂��B
����A�������ɂ���������ɁA�S�w�̘b���o�܂������A
�����Ƃ��������Ȃ������ɐΓc�S�w�Ɋւ���{���܂������̂ł͂Ȃ����Ƃ����\���������܂����B�y���݂ł��B
�����������W�����҂���郁�b�Z�[�W���A�{���ɂ͂��낢��ƍ��߂��Ă��܂��B
������Љ�܂��B
���������L�q������܂��B
���{�ɂ����ċ��������_���E�����E�̎O�@���́A�������Ղɂ����č��̂��ʂ������B
�������ՂƂ͉����B
����́A��������V�Ƃ������l���̓��ʉߋV��𒆐S�Ƃ��āA�l�X�̐S�ɋ����ݏo���������u�ł���B
�܂芥�����Ղ͓��{�̎O��@���̋Ïk���������ł���A
���ꂱ�������{�ő�̏@���ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ�������ƏЉ��Ă��܂��B
������g�́A�������Ղ́u�@���v���̂��̂Ƃ��������A�u�@�V�v�Ƃł��ĂԂׂ����̂��Ə����Ă��܂����A
�������Ղ͍��v�Ԃ���̓ƒd���ł��̂ŁA ���̋c�_�̔��W�͎��Ɋy���݂ł��B
�@�V�Ƃ����T�O�́A���Ɏ����ɕx��ł��܂��B���āA���̐悪�y���݂ł��B
���ɂ��h���I�ȃ��b�Z�[�W�┭�z�̃q���g�����낢�덞�߂��Ă���{�ł��B
���ɖ{�Ƃ�����y�Ȗ{�ł��̂ŁA�C�y�ɓǂ�ł݂Ă��������B
���u�����ւ̗��@���N�����ҁv
�ܖ؊��V�@�u�k�Ё@�Q�O�O�V�N
���̃R�[�i�[�ł͌����Ƃ��āA���̗F�l�m�l�̒����F�l���ւ�������Ђ��Љ���Ă�����Ă��܂����A����͔ԊO�҂ł��B
�ܖ؊��V����́u�����ւ̗��v�͑S�U���ł����A����A���グ��̂�3���ڂ́u���N�����ҁv�ł��B
���̑O�ɏo���u�C���h�ҁv�i�㉺�j�́A�F�l������䍲�q�������C���h��ނɓ��s���A�\�����S�����ꂽ�̂ł����A
����͍��₳��̒S���ł͂���܂���B
�ȑO�A���₳�u�C���h�ҁv���Ă������������ɁA���N�����҂ɋ���������Ƃ��`�������̂ł����A
���̂��Ƃ�m�����ҏW�̕����A�������v�w�Ƀv���[���g���Ă����������̂ł��B
���̂�������˂āA���̃R�[�i�[�ŏЉ�悤�Ǝv�����̂ł����A���̊ԁA���낢�날���āA�ǂނ̂��x��Ă��܂��Ă����̂ł��B
�����A�����N���ēǂ܂��Ă��炢�܂����B
�ǂ�ŁA�Ȃ����₳�������v�w�ɑ����Ă��ꂽ�̂��Ӗ����킩��܂����B
���܂̎������v�w�̐S���ɂ��̂܂܃Y�o�b�Ɠ����Ă��܂����B
���₳��ɁA�����ĕҏW�҂̕��Ɋ��ӂ��Ȃ�������܂���B
�{���̏Љ���������ƍی����Ȃ������ł��B
�ܖ���̌l�I�Șb�Ɗ؍��̕�������A�d�Ȃ�悤�Ɍ���Ă���̂ŁA
�ƂĂ��ǂ݂₷���A�������傫�Ȏ�����^���Ă���܂��B
���͊؍��̕�������⎛�@�̂��Ƃ�m�肽���Ƃ����̂����́u�����v�̓��e�������̂ŁA�����������@�̏�i��m�肽�������̂ł����A
�ǂݏI���Ă݂�ƁA�S�ە��i�I�Ɋ؍��̎��@���̊��ł����悤�ȋC�ɂȂ�܂����B
�{���́A�ܖ�������_�R�̒��ɂ���ʎ�R��C���i�A���`���N�T�j��K���Ƃ��납��n�܂�܂��B
�������Α��̖��ӕ��̎ʐ^���{���̌�\���ɍڂ��Ă��܂����A�ٌ`�ȕ��ł��B
�ʐ^�����Ă��邾���ł��A�܂��o�Ă���قǂɃ��b�Z�[�W�𑗂��Ă��镧�ł��B
���Џ��X�ŁA���̎ʐ^�����ł����Ă��������B
���́A����܂ł���Ȃɘb�������Ă��镧�ɂ���������Ƃ�����܂���B
�ޗǂ����щ@�̈���ɕ��ȏ�ł��B
�؍��̕����̍���ɂ́A�،��̎v�z�u�ꑦ���E������v�Ɓu�a�y�v�̎v�z�����邻���ł��B
�u�a�y�v�Ƃ́A���܂��܂Ȏv�z�⋳����Z�������Ă������Ƃ����p���̂悤�ł��B
�����炭�u�ꑦ���E������v�̎v�z����o�Ă���p�����Ǝv���܂��B
�����āA�{���̏I�͂́u���ׂĂ͂Ȃ����Ă���v�Ȃ̂ł��B
�����Ō����Ɂu�l���E���ĂȂ������̂��v�Ƃ����A�ꎞ�b��ɂȂ����c�_�ւ̖��m�ȉ�������Ă��܂��B
�ƂĂ������ł��܂����A�[���ł��܂��B
�،��ɂ��u�C���h���̖ԁv�Ƃ������b���o�Ă��܂����A������v���o���܂����B
�{���ɂ͂��ꂩ��̐��������l�����ł̂�������̎��������߂��Ă��܂��B
�����������ł͂���܂���B
�C���h�҂Ɩ{���Ƃ̋��ʓ_�́A�C���h�ł��؍��ł��������L����A�Љ�ɉe����^���Ă���Ƃ��������ł��B
����͖������l�����ŁA�傫�Ȏ�����^���Ă���܂��B
�������A�ܖ����g��������Ă���悤�ɁA�C���h�̓q���Y�[�̍��A�؍��͎̍��Ƃ����C���[�W�������ł��B
���̍���ŕ��������C�ɍL�����Ă��邱�Ƃ�m�邱�ƂŁA�����ւ̓W�]�͑S���ς���Ă���悤�Ɏv���܂��B
���{�̖������l�����ł��A�傫�ȉe��������Ǝv���܂��B
�������A�����{���ő傫�Ȍ��C����������̂́A�ܖ���̑���ł���u���ǐl���v�Ƃ������t�ł��B
�����܂ł��Ȃ������́u���Ǒō��v����n�������t�ł��B
����ȕ��͂�����܂��B
�����������遄���ƁA���ꂪ���܁A�����l���Ă��邢�����Ȃ��Ƃ��B�i197�Łj
���܁A�ƂĂ��[���S�ɓ����Ă��錾�t�ł��B
�����炭1�N�O�܂łł���A���ł����~�߂��Ȃ����t�������ł��傤���B
�ŋ߁A�悤�₭�u�����邱�Ɓv�̈Ӗ��������Ȃ�ɐ����ł��ė��܂����B
�d�����V�т��A�Љ�����A���ׂĂ͗]�Z�ł����Ȃ����ƂɋC�Â��܂����B
19�N�O�ɉ�Ђ����߂����ɁA
�u���ꂩ��͓����ł��Ȃ��V�Ԃł��Ȃ��A�w�Ԃł��Ȃ��x�ނł��Ȃ��A���������Ă������v
�Ɛ錾�������Ƃ̈Ӗ����A�Q���������̕��ɗ����Ă��܂����B
���[�Ƃ��ǂ��A���܂͐����邱�Ƃ������ɖړI�ɂ��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂����B
�����邱�Ƃ̈��������A�ŋ߁A�S�ɂ��݂Ă���悤�ɂ��Ȃ�܂����B
���̕��A���т��܂������ł���悤�ɂȂ�܂����B
�{�̏Љ�̂��肪�A�Ȃɂ��l�I�Ȋ��z�ɂȂ��Ă��܂��܂������A
�ƂĂ��ʔ��������ł��B
����ɂ��Ă��A ��C���̖��ӂ͖��f�I�ł��B
���u�c��̃~�b�V�����r�W�l�X�v��N��̎Љ�ƌ^�m�o�n�̂�����
���V�l�Ғ��@���{�n��Љ�����@�P�V�O�O�~�i�ŕʁj
�R���P�A�����̑��V�l���܂��V�����o���܂����B
�Љ�ɖ߂��Ă���c��V�j�A�ɁA����܂Œ~�ς��Ă����m����o�������āA
�n���Љ�ɖ𗧂V�������Ƃ��N�����Ăق����Ƃ����G�[���̏��ł��B
��삳��Ɋւ��ẮA����܂ł������̃z�[���y�[�W�ɂ��o�ꂵ�Ă��܂����A
�w�K�@��w���ƌ�A�،���ЂɂP�O�N�ԋΖ��B
���̌�A������w��w�@�ŁA�o�c���w�C�m���擾�B
����ɁA�č��I�n�C�I�B�̃P�[�X�E�E�F�X�^���E���U�[�u��w��w�@�ɗ��w���A��c���g�D�C�m���擾�B
�A����A���{�̑��̍��I�Ȃm�o�n�̃}�l�W�����g�T�|�[�g�ȂǂɎ��g��ł��܂��B
�R���P�A�Z���^�[�̃T�|�[�^�[�ł�����A
���݂̓V�j�A�R���T���^���g�Ƃ��āA�c��V�j�A�v���W�F�N�g�Ɏ��ۂɎ��g��ł��܂��B
�{���́A��N�A��삳���S�ɂȂ��čs�������ƌ^�m�o�n�N�ƍu���̍u���^���x�[�X�ɁA
�ꏏ�ɍu�����������m�o�n�@�l�C�[�G���_�[�̃����o�[�̋��͂āA�����������H�̏��ł��B
�������k��œo�ꂵ�Ă��܂����A��삳��̎v����m����̂Ƃ��āA
�ŏ����u���ɕς��ā^�c��̐V�������䂪�L���肾���Ă��܂��v�Ƃ�����������e�����Ă��炢�܂����B
���̃T�C�g�ɂ��f�ڂ��܂����̂ŁA���ǂ݂��������B
�����āA���������������Ă�����������A�{�������ǂ݂��������B
�{���̖ڎ��͎��̒ʂ�ł��B
��1�� �Ȃ��A��N�ސE��Ƀ~�b�V�����r�W�l�X��
��2�� ���ƌ^NPO�̂�����
��3�� NPO�@�l�����낤
��4�� NPO�@�l�̎����lj^�c
��5�� ���ʐM�Z�p���o�c������������
��6�� �T�[�r�X�ƌڋq�����x�����コ����ɂ�
��7�� �c��NPO�̐�������
��8�� �c���A��u������I�i�C�k�j
�{���́u�����Ɂv�ɂ����m���Ă��܂����A
�{���̏o�ł��_�@�ɂ��āA�o�O�u����c��V�j�A�m�o�n�C���^�[���V�b�v�Ȃǂ̃v���O�������n�܂�\��ł��B
�R���P�A�Z���^�[�Ƃ��Ă��S�ʓI�ɉ������Ă����܂��B
���S�̂�����́A�u�c���A��u������I�����ǁv�ɂ��A�����������B
�܂��A�u���⌤�C�v���O�������������ł���Ǝv���܂��B
�Ȃ��A�c��V�j�A�v���W�F�N�g���N�������߂̎������ɂ��邽�߂ɁA
�u�c���A��u������I�����ǁv�ł��{���̔̔����s���܂��B
�����ʓ|�ł����A��L�����ǂɂ���������������Ƃ��ꂵ���ł��B
�u�c���A��u������I�����ǁv�ւ̃��[��
���u���킷��Ƒn��Ɓ|�Ȃ��A���̉�Ђ̓L�����ƌ���̂��I�v
�l����������o�c�R���T���e�B���O���Ғ��@�v���W�f���g�Ё@1400�~�i�ŕʁj
����15�N�قǑO�ɏ������u�E�\�z�����ƌo�c�v�Ƃ����G���A�ڋL�����A���Ɖ�̗̂\���Ƃ��������o���Ŏn�߂܂����B
�Y�Ƃ̎���́A���Ƃ��璆����Ƃւƈڂ邾�낤�Ɗ����Ă����̂ł��B
�c�O�Ȃ���A�����͂Ȃ炸�ɁA���Ƃ͂܂��܂������Ȃǂ�ʂ��đ�K�͉����Ă��܂��B
�������A���܌��C�Ȋ�Ƃ͒�����Ƃ̂悤�ȋC�����܂��B
���Ƒg�D�͐l�Ԃ��v���蓭����Ƃ��Ă͐����肷���܂��B
���Ɏ���̕ς��ڂɂ́A��̓I�ɓ����Ј��������₷����łȂ��ƁA��Ƃ͌��C�ɂȂ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
���ۂɍŋߎ����o����C�ȉ�Ђ́A����������ƂƂ͂����Ȃ�����������Ƃ������̂ł��B
�����������C��Ƃ�20�Ђ��W�߂āA���̌��C�̎��ԂƗ��R�𖾂炩�ɂ��Ă����̂��{���ł��B
�P�Ȃ鎖����W�߂������̖{�ł͂Ȃ��A
���N�A������Ƃɂ�������Ɗւ���Ă����v���t�F�b�V���i���̖ڂ���̕]���Ɖ�������Ă���̂ŁA
��ƌo�c�Ɋւ��l�ɂ͐�D�́u�������e�L�X�g�v�ɂȂ�{�ł��B
�u������Ƃ̌o�c�ҁE�����K�ǁI�v�Ɩ{���̑тɏ�����Ă��܂����A
���͂ނ�����Ƃ̌o�c�����̊F����ɂ����ǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B
�o�c�̊�{�͋K�͂ɂ���ĕς��킯�ł͂���܂���B
�{�����܂Ƃ߂��o�c�R���T���e�B���O�������̎��{���P����Ƃ́A�������t�������ł����A
���{����͖L�x�Ȓm���Ə��܂��āA���H�I�Ȏ��_�ł���܂ő����̊�Ƃ̌o�c���k�Ɏ��g��ł����l�ł��B
���������{����͍D��S�������A�����M�S�Ȑl�ł�����܂��B
���{����͂���܂ł��A���{�̒�����Ƃ̑n�ӍH�v�⒧��ӗ~�̂������ɂ��āA���낢��Ǝh���I�Șb�����Ă�����Ă��܂����B
���{�̌o�ςW�����A�x���Ă����̂́A�����đ��Ƃł͂Ȃ��A������Ƃł���Ɗm�M���Ă��鎄�Ƃ��ẮA
����������܂Ƃ߂Ăق����Ǝv���Ă��܂����B
���ꂪ�Q�����������̂ł��B
���{����́u�͂������v�ŁA�u��ƌo�c�ɂ͕K���h���}������v�Ə����Ă��܂��B
�{���ł͓Ƒn�I�ȂQ�O�̗D�ǒ�����ƂɎ�ނ��A
���ꂼ��̃h���}���Љ��ƂƂ��ɁA��Ƃ̌��C�̗v������̓I�ɉ�����Ă���Ă��܂��B
������ʔ����A�����ɕx��ł��܂����A
���ꂼ��̉������̓I�ł킩��₷���A�������̌n�I�Ȃ̂ŁA
�����ǂނ����Ɍo�c�ɂƂ��Ă̑�Ȏ��_�����R�Ɗw�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��܂��B
���̂�����́A�L�x�ȑ̌��Ə����������̎��{����̓ƒd��Ƃ����Ă������ł��傤�B
���Ȃ݂ɁA�Ƒn�̌���Ƃ��āA���̂T�̗v�����グ���A����ɂ��������Ⴊ�W�߂��Ă���̂ł��B
�E �o�c���O�ƃr�W�����F��u������ė��O��`���A���s����B
�E ���Ƃ̎d�g�݁F���Ƃ̎d�g�݂ō��ʉ�����������B
�E �g�D�ƃ}�l�W�����g�F��{���ɂ��Čo�c�v�V�ɒ��ށB
�E �Z�p�ƋZ�\�F���̂Â���̌��_�ɋɂ������B
�E �`���Ɗv�V�F�ϊv�����ꂸ�A�V�܃u�����h�����B
������ɂ����H�Ⴊ��̓I�ɂ��Ă��܂��̂ŁA�ƂĂ��[���ł��܂��B
�l����������̎啑��Ƃ��Ă���_�ސ쌧�����ł�22����������Ƃ����邻���ł��B
�{���ɓo�ꂷ��̂́A����1000����1�ł�������܂���B
���ׂĂ̒�����Ƃ��Ƒn�I�Ō��C���Ƃ����킯�ł͂���܂��A
���̌������o�Ϗ̒��ŁA����̒m�b�Ɠw�͂Ōo�c�����������Ă����ɂ́A���ꂼ��ɓƎ��̎��H�����Ă����Ƃ͑����͂��ł��B
���ƂƈႢ�A������Ǝ��s�����肷��Ƃ������ܓ|�Y���Ă��܂��قǁA�������ْ��̘A���Ȃ̂�������Ƃł��B
�����������H�m����̃��b�Z�[�W�͐����͂�����܂��B
����Ɏ���ɏo�Ă���o�c�҂ɂ́A��������L���ȕ\�����̂ł��B
�ł�����ǂ�ł��āA���C�����炦�܂��B
�o�c�҂ɂ͐l�ԓI�ȕ\��Ȃ�������܂���B
�����ق߂����Ă��܂����ł��傤���B
�������A��ƊW�҂ɂ͂��E�߂̏��ł��B
�{�������ڂ����w�т������́A���Ў��{����̂Ƃ���̃R���T���e�B���O���Ă��������B
���{����̐����Ȃ��l���́A�����ۏ��܂��B
���{����̃u���O�����̃T�C�g�Ƀ����N���Ă��܂��B
���Ђ��ǂ݂��������B
���u�i�@���v�v
���^�Y�@�����V���Ё@2400�~�i�ŕʁj
���ܓ��{�̎i�@���x���傫���ς�낤�Ƃ��Ă��܂��B
�ꌾ�ł����A�u���̎i�@�v����u���̎i�@�v�ւ̓]���������ł��B
���̊�����M�S�ɐ��i���Ă����̂��A���{�ٌ�m�A����i���٘A�j�ł��B
�b�v�r�v���C�x�[�g�ɏ����܂������A
���̎i�@���v�̎R�ꂾ����2002�N����2004�N�܂ŁA
���٘A�̎��������߂��̂��A�{���̒��҂̑�삳��ł��B
��삳��Ǝ��Ƃ̊W�́A�b�v�r�v���C�x�[�g�����ǂ݂��������B
���٘A�̎i�@���v�ւ̎��g�݂Ɋւ��Ă��A�����ɏ��������܂����B
���̖{�������Ă������́A���͂܂��Ɏ����i�@�ւ̓{������������Ă������ł����B
���܂�̃^�C�~���O�̗ǂ��ɁA�����ǂ܂��Ă��炢�܂����B
�u���O�ɂ������܂������A�{���̕���ɂ���悤�ɁA
�i�@���v�́u���٘A�̒�������Ȃ��������v�������悤�ł����A
�����ɂ������{�̖@���E�̎��Ԃ��ے�����Ă��܂��B
�o�ŎЂ̕\���������A�{���́A
�ٔ������x�̓����A�@�ȑ�w�@�J�Z�ƐV�i�@�����A�i�@�x���Z���^�[�̑n�݁A�ٔ����E�ٌ�m���x�̉��P���X�A24���̊֘A�@���������邱�ƂɂȂ�����㏉�̎i�@����v�B
�u�s���̂��߂̎i�@�v����A��ڂ���ď��o�������{�ٌ�m�A����i���٘A�j���A���{��ō��فE���@�Ǝ��ɑΛ����A���ɑË����ĉ��v���������Ă������ߒ����A�q�ϓI����̓I�ɂ��ǂ�u���a�E�����i�@���v�v�ҔN�j�B
�ł��B
����͂ƂĂ����m�ȏЉ�ŁA�����̎����┭���Ȃǂ��Ă��˂��Ɉ��p���āA
�u�i�@���v�v�̌o�߂��q�ϓI����̓I�ɉ������Ă��܂��B
���҂̎v�����݂≟���t���͑S������܂���B
���҂̑�삳��̐l�������������܂��B���ɐ����Ńt�F�A�ł��B
��������g�����h�L�������g�Ȃ̂ŁA�i�@�E�ȊO�̐l�ɂ͂�����őދ��ł����A
���e���ɂ߂Đ����ł��̂ŁA�i�@�ɊS�̂���l�͂�����Ɠw�͂��ēǂމ��l������Ǝv���܂��B
���e�̂��邵�����肵���{�ł��B
�u�i�@���v�v�ƌ����Ă��A���{��ٔ����A���邢�͍��E�̎p���Ɠ��٘A�̎p���Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ���Ƃ��A�{����ǂނƂ悭�킩��܂��B
�O�҂́A�u����̕s���ȂƂ�����v�B
��ҁA�܂���٘A�́A�u���ׂč����́A�l�Ƃ��đ��d�����v�i���@�P�R���j�Љ�����邽�߂Ƃ����̂���{�p���̂悤�ł��B
���̈Ⴂ���{���ł̉��v�̌o�߂�ǂނƂ悭�`����Ă��܂��B
�i�@���v�Ƃ����ƁA�ٔ������x���b��ɂȂ肪���ł����A
�@�e���X�Ƃ����@�����k�̎d�g�݂̏[����[�X�N�[���̊g�[�Ȃǂ��d�v�ł��B
�u�����Ȏi�@�v�u�傫�Ȏi�@�v�Ƃ������t���o�Ă��܂��B
���ꂩ��̎i�@���l���Ă������߂̂�������̍ޗ����A���̖{�ɂ͋l�܂��Ă��܂��B
�������A���{�ł͂��łɁu�i�@���v�v�͋c�_�̒i�K���I���āA���x�I�ɂ͎��H�ɓ����Ă���킯�ł����A
���x���������̂͊W�ҁi�ő�̊W�҂͂�������ł��j�̈ӎ��ƍs���ł��B
�������͂����Ǝi�@�ɊS�������A���̎��Ԃ�m��w�͂����邱�Ƃ���ł��B
���̈Ӗ��ŁA���Ȃ�d���{�ł͂���܂����A�i�@�W�҈ȊO�̕��ɂ����E�߂̖{�ł��B
���̖{���e�L�X�g�ɂ����w�K����L����ƌ��ʓI�ł��ˁB
���Ȃ݂ɁA�{���ɂ͂�����l���̒m�l���o�Ă��܂��B
�e���r�ʼn����ꏏ�������ъ����ٌ�m�ł��B
�e���r�ɏo��^�����g�̂悤�ȕٌ�m�͍D���ɂ͂Ȃ�܂��A
���т���͑�삳��Ɠ����悤�ɐ�����������������l�ł��B
�����炭�e���r�Ō������Ȃ���Љ�����߂ɂ��Ă���ٌ�m�Ƃ͑S���Ⴄ��ނٌ̕�m���A
�i�@�̌�����ς��悤�Ƃ�����Ă���̂ł��傤�B
����Ȃ��Ƃ��l���������܂����B
����Ȃ킯�Ŗ{���͂��E�߂̖{�ł����i�ǂ����Ƃ����o��̂���l�ɂ����ł����j�A
���̎i�@�ւ̕]���͎c�O�Ȃ���ς��܂���ł����B
�u���O�́u�i�@���]�v�ŏ����Ă������Ƃ͓P��C�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B
�u���̎i�@���疯�̎i�@�ցv�u�s���̂��߂̎i�@�v�B
���ꂪ�ǂ��������̂��A���ɂ͂܂��킩��܂��A�����͊��}�ł��܂��B
���́A���̒��g�ł��B
�@�́A�Љ�̂�����ɂ���đS���ς���Ă��܂��B
�ǂ�ȎЉ��ڎw���̂��ɂ���āA�@�̖����͕ς��̂ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���܂��B
���́u�ǂ�ȎЉ��ڎw���̂��v�Ƃ����c�_�������Ă��Ȃ��̂���Ԃ̕s���ł��B
�����@���E�ɋ��߂�͉̂ߑ���҂��Ƃ���ꂻ���ł����A
�@���l����Ƃ������Ƃ͂����������ƂȂ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�悩�������u�i�@���]�v���ǂ�ł��������B
���Ȃ�̖\�_�W�Ȃ̂ł����B
��������w���ł��܂��B
���u�n�[�g�t���E�J���p�j�[�v
���v�ԗf�a�@�O�܊ف@2800�~�i�ŕʁj
���N�ŏ��̏Љ�́A���v�ԗf�a����́u�n�[�g�t���E�J���p�j�[�v�ł��B
���҂̍��v�ԗf�a����̃y���l�[���́A���^�炳��ł��B
���̃R�[�i�[�ɂ��т��ѓo�ꂵ�Ă���l�ł��B
���̈������́u�����S�w�O����v�̊����҂��{���ł��B
���Ȃ�O�ɂ��������Ă����̂ł����A���낢�뎖������āA�r���œǂނ̂��~�܂��Ă����̂ł��B
����Ɏ��ɓǂ݉����̂���{�Ȃ̂ł��B
�O��2���Ƃ͎���Ȃ�Ⴂ�܂��B
�{���͕���Ɂu�T�����[�O���[�v�̎u�ƒ���v�Ƃ���A���Җ����y���l�[���ł͂Ȃ��A�{���ŏo�ł��Ă��܂��B
�T�����[�͖k��B�s�ɖ{�Ђ�u���A�������Ղ����ƃh���C���Ƃ����Ђł��B
�O�ɂ������܂������A�������Ղւ̎v���̐[���ɂ����ẮA�T�����[�ȏ�̉�Ђ͂Ȃ��ł��傤�B
���v�Ԃ��\�z���Ă��銥�����Ղ̈Ӗ��́A���ɍL���[���̂ł��B
���v�Ԃ���A�܂�������̐��E�́A
���̃T�C�g�Ƀ����N���Ă��鍲�v�Ԃ���̃z�[���y�[�W��ǂނƏ��������ł��邩������܂���B
21���I�ɓ�����2001�N�A���v�Ԃ���͂��̉�Ђ̎В��ɏA�C���܂����B
�����ĎЈ������ɌĂт����Ȃ���A���v�Ԃ���炵����ЂÂ���Ɏ��g��ł��܂����B
���̗��O����@�́A���v�Ԃ�����܂Œ������l�X�ȏ����ɏ�����Ă��邱�Ƃł��B
�܂荲�v�Ԃ���́A�w���ƁA�l�������Ƃ��A����̉�ЂŎ��H���Ă����̂ł��B
�܂��ɍ��v�Ԃ��ڎw���m�s����ł��B
�����Č����ɃT�����[�̋Ɛт͌��サ�����Ă���̂ł��B
�{���́A���������T�����[�̌o�c���H���A�В��Ƃ��ĎЈ��ɌĂт����Ă������͂�b�̋L�^�𒆐S�ɂ܂Ƃ߂��{�ł��B
���n��œǂ߂邱�Ƃ����������߂܂��B���C�u��������܂��B
�ȂA�В��̌P���W���ȂǂƎv��Ȃ��ł��������B
���̎�̖{�Ŗʔ����{�͊F���ɋ߂��̂��m���Ă��܂��B
�������{���ɏo�Ă���b�́A���̃e�[�}�A�����b�����A�����̃X�^�C���ȂǁA���ɑ��ʂŖ���N�I�ł��B
��̓I�ɂ��āA���ՓI�Ƃ����Ă������ł��傤���B
�{�����[���������̂ŁA�Ȃ��ɂ͔�������Ȃ�悤�ȕ������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂ł����A
�Ƃ���ǂ���Ɍ��錾�t��S��������郁�b�Z�[�W������߂��Ă��܂��B
���������J�߂����̊�������܂����A
����܂ł̍��v�Ԃ���̒�����ǂ�ł������̂Ƃ��Ă͂ƂĂ��ʔ����ǂ܂��Ă��炢�܂����B
���������o�c�҂������Ƒ����Ă�����A���{�̎Y�ƊE�͑傫���ς��ł��傤�ˁB
��Ќo�c�҂̕��ɂ����߂�1���ł��B
�� �u���ɓ����ꂽ�ό��Đ��v
�������@����o�Ł@1400�~�i�ŕʁj
�u�ԃC�X�̐N�ɗ������������A
�N�ɋC�ɓ����悤�Ɠ������тɊ�Ղ��N�����B
�l�����A�������A�s�������A
�Ƃ��Ƃ����܂œ����o���B�v
�{���̑тɂ͂���������Ă��܂��B
����͈ɐ��u���o���A�t���[�c�A�[�Z���^�[�̒a���̕���ł��B
���҂͓��Z���^�[�̗������̒���������ł��B
��������Ƃ͒����j���[�X�^�[�̔ԑg�ʼn����ꏏ���܂������A���Ɋy�����l�Ȃ̂ł��B
��������̃u���O�����̃z�[���y�[�W�Ƀ����N����Ă��܂��̂ŁA���Ђ�������肭�������B
���Ȃ݂ɒ�������͐����قɂ��V���������N�������l�Ȃ̂ł��B
���̕���̂ق��ŗL���Ȃ̂ł����A����͈��������ł̒���ł��B
�{���̓��e�͑т̏Љ�ł��킩�肢��������Ǝv���܂����A
�u�o���A�t���[�v�u�ό��v�u�܂��Â���v�u�Љ�ϊv�v�u�m�o�n�v�Ȃǂ̃e�[�}�ɊS�̂�����͂��Ђ��ǂ݂��������B
�ƂĂ��C�y�ɓǂ߂�y�����{�ł����A
��������̃��b�Z�[�W�ƒ�āA���邢�͂��ꂩ��̎Љ���l�����ł̏d�v�Ȗ���N������߂��Ă��閧�x�̍����{�Ȃ̂ł��B
�܂��͏����o���̌��t���h���I�ł��B
���{�̑����̊ό��n�ł́A�܂��Â���Ƃ������̂��s���Ă��Ȃ��B
�S�������ł��B
�����������Ă��܂��B
���̏Z�����ւ�Ɏv��Ȃ��ό��n�ɁA�ό��q���W�܂�킯���Ȃ��B
�{���ɏZ���s�݂̊ό��s�����܂����Ȃ�����܂���B
���āA�{���ł����A���ꂪ�܂����ɖʔ����A�����ɕx��ł���̂ł����A
�ƂĂ��Ռ��I�������Ƃ����������Љ�Ă����܂��B
�Ԃ����ňɐ��_�{�ɓ���Ȃ������l�̘b�ł��B
�ڂ�������]���傱�����̃T�C�g���J���A
�E��́u�A���o�����݂�v�ŁA2003�N4��24����26����T���ēǂ�ł݂Ă��������B
�Ռ��I�ł��B���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��ẮA�Ռ��I�ł����B
�o���A�t���[�̖{������������Ă��鎖���ł��B
�Ȃɂ�玝���ĉ�����������ł����A�����̂�����͂��Ж{�������ǂ݂��������B
���̖{�̐^�����͂P�P�͂ł��B
����ȕ��͂�����܂��B
���Ă͍]�˂��������̏W�ςƔ��M�̒��S�n�������ɐ��B���̐������o���A�t���[�ό��ōČ��������B
���������́A�{�C�ł����l���Ă���̂ł��B
�����炱���A��̈ɐ��_�{�����͑傫�ȈӖ������������ɂȂ肦��̂ł��B
������Ɩ����������Ȃ��Љ�ł��݂܂���B
�Ƃ����� �A11�͂ɒ��������̑傫�ȍ\�z���ǂݎ���̂ł��B
���������́A���܂��̃v���W�F�N�g�ł��肠���Ă����A
�p�[�\�i���o���A�t���[���S���ɍL���Ă������ƁA���{�o���A�t���[����̐ݗ��Ɏ��g��ł��܂����A
���̉��ɂ͓��{�Љ�̃p���_�C���]���ւ̒��킪����̂ł��B
�u���Ƃ����ɂ����āv�Ƒ肵�āA�u�⊮���̌����v�ւ̒�������̎v����������Ă��܂��B
����܂��āA������x�A�{����ǂނƁA�����Ƃ���܂ł̂܂��Â���̌��E�⍡�̒n�������̂��������ɋC�Â��͂��ł��B
����1�N�A��������Ƃ͂�����Ă��܂��A��������炵���A���H�̏��ł��B
�������ǂ��Ȃ��ł����A���e�͂ƂĂ��悢�{�ł��̂ŁA�܂��Â����m�o�n�����Ɏ��g��ł���l�ɂ����߂������ł��B
��������̃u���O���ʔ����ł���B
���u�l���`���{��` �G�ΓI�l���`��O�p�����h�q�@�v
���q���j�@���m�o�ϐV��Ё@1700�~�i�ŕʁj
�T�ԕɂ��낢��Ə����܂������A���{�̂h�q�̑������̒ߖ�j�N���瑗���Ă����{�ł��B
�ߖ삳��̗F�l�̏��q���j����̍ŐV����ŁA�ߖ삳��̊������Љ��Ă��܂��B
�������{��`���A�����Ƃ����u���E���ʒʉ݁v�łl���`����ʉ��A�����������A
�j�b�|�����{��`��V�����ǖʂɓ����Ă����Ƃ�������̗���̒��ŁA
���{��Ƃ͂ǂ������炢�������킩��₷�����H�I�ɉ�����Ă��܂��B
���҂͕K�������������{��`�Ɏ^�����Ă���킯�ł͂���܂���B
�������A2007�N�ɂ�����O�p�����i�O����Ƃ����{�̎q��Ђ�ʂ��ē��{��Ƃ����邱�Ɓj���\�ɂȂ�A
���{�^�o�c�̎��~�߂̂������j�b�|�����{��`�́u�������{��`�v�ɂ͂�����ƈڍs����A
�܂苌���̃j�b�|��������Ђ͊��S�ɉ�̂���A�O���[�o���Ȏ��{��`�ɑg�ݍ��܂��Ƃ����W�]�̂Ȃ��ŁA
�������肵���R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̎d�g�݂𐮂��A
��Ɖ��l�i�K�������������l�ł͂���܂���j�����߂Ă����Ȃ���A
�C�O�̃n�Q�^�J�t�@���h�ɂ���Ă��܂��Ƃ����킯�ł��B
�ƂĂ������͂̂���b�ł��B
�W���[�i���X�g�Ƃ��Ă̒��҂̌������`����Ă��܂��B
��Ƃ̌o�c�����̕��ɂ͂�������Ɠǂ�łق����{�ł��B
�ڎ������Љ�܂��B
��P�́@�l���`�̊������Ɠ��퉻
��Q�́@�O�p�������ւ̋���
��R�́@�������������������l���`�������������炵��
��S�́@�u�������z�v���ǂ��l������悢�̂�
��T�́@��Ɖ��l�ɑ剻�͎���̌o�c�w�͂Ŏ�������
��U�́@�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����j�b�|�����{��`�̉ۑ�
��V�́@���唻�������A�v���L�V�[�E�\���V�e�[�V�����̐i��
��W�́@�g����Ɋ���������o�c�h�����l���`�h�q��
��X�́@�G�ΓI�Ȃl���`�ő_����̂́u��o�a�q��Ёv
��10�́@�g�n�Q�^�J�E�t�@���h�h�����ɑ_������Ȋl��
���Ȃ݂ɁA���͊������{��`�ւ̗���ł͂Ȃ��A
�L�`�̃X�e�[�N�z���_�[�̒����I�Ȏ��_�ɗ�������Ɖ��l�ɗ��r�����R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̎d�g�݂�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��Ă��܂��B
���̂��߂ɂ́A��Ƃ̑g�D������K�͂��傫���ς��K�v������悤�Ɏv���܂��B
�v���Ԃ�Ɋ�Ƙ_��ǂ�Ŏh�����܂����B
�݂Ȃ���ɂ������߂ł��B
���u�W���Z��̎��ԁv
�匎�q�Y�@�����Ё@�P�X�O�O�~�i�ŕʁj
���͈������Y�̌��z���D���ł͂���܂���B
�Ƃ����������ł��Ȃ��̂ł��B
���̈ӎ������m�ɂȂ����̂́A���˓��C�̒����̉ƃv���W�F�N�g�̋�Ԃ�̌������Ă�����Ă���ł��B
��������ƂĂ��f���炵����i�ł������A�ǂ�����a�����c�����̂ł��B
��Ԃւ̈�����������Ȃ��̂ł��B
�����D���Ȍ��z�̓z�b�Ƃ����Ԃ̂悤�ł��B
��ԂɐÂ��ȋL�����c���Ă����悤�Ȍ��z�ł��B
�{���́A�ۈ�v���W�F�N�g�����엢���v���W�F�N�g�Ȃǂł��ꏏ�����匎�q�Y�����̍ŏ��̒P�s�{�ł��B
�������ƂĂ��匎����炵���āA���ꂵ���Ȃ�܂����B
�тɂ���ȃ��b�Z�[�W��������Ă��܂��B
�Z���ȁu�����̋L���v�����p������
�Âт��W���Z��̌����̌����Ԃ�Ɏ����X���Ă݂悤�B
�ڂɌ����Ȃ����Ԃ̒~�ς𖡂키���͂ɐZ���Ă݂悤�B
�����̎q��Ă̂悤�ɗǂ����������Ăق߂Ă݂悤�B
�{���ɂ͐����̋L���𑶕��Ɋ���������Q�S�́u�W���Z��ƌĂԂ��Ƃ̂ł���v�������o�ꂵ�܂��B
�����āA�匎����Ƃ����v��������������ɂ���āA
���ꂼ��̐��������₻���ł̕��ꂪ�ƂĂ��l�ԓI�Ɍ���Ă��܂��B
��ЂƂ̕��ꂩ��A����܂ł̎���̐��������l�����������Ȃ郁�b�Z�[�W���`����Ă���̂́A���̐���̂����ł��傤���B
���ɉ��������A���ɒɂ݂������Ȃ���B
���ꂼ��̕���ƁA�����ɑ������匎����̃��b�Z�[�W�͖{����ǂ�ł��炤�Ƃ��āA
�����ł͂����ɒʂ��Ă���匎����̑傫�Ȏv���ɂ��ďЉ�Ă��������Ǝv���܂��B
����͎��������Ɗ����Ă����v���ł����邩��ł��B
�匎�����ɂ���̂́A�����ɂ����錸�����p�̔��z�ł��B
�匎����͂��������܂��B
���{�̌��z���ɂ����ẮA�u���Ԃ��o���Ƃ́A���l�������Ȃ��Ă������Ƃł���v�Ƃ����߂�������������̂ł���B
���̂����������āA���{�̓s�s�͏�ɋL���r���̊�@�ɕm���Ă���̂ł���B
�u���̂܂܍s���Γ��{�l�́u�������L���r���v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����v�Ƒ匎����͐S�z���Ă��܂��B
�S�z�͂��łɌ����ɂȂ��Ă���Ƃ����̂��A���̔F���ł����A
������������Ă���̂��A�������p�p���_�C���̌��z�T�O�ł͂Ȃ����Ƒ匎����͂����킯�ł��B
�����āA
�u���Ԃ��o�ĂΉ��l������v���Ƃ���ɐ������Ƃ����̂́A�Ȃ��ςȂ̂ł͂Ȃ����A
�Ƒ匎����͋^���悵�܂��B
�u���̌o�߂ƂƂ��ɉ��l�͌����Ă����v�B
�������ꂪ�l�ԂɓK�������Ƃ�����ǂ����낤���B
�u���Ȃ��̉��l�͔N���o�Ă������ƂɌ����Ă����A�U�O�ɂȂ�ƁA���l���[���ɂȂ�܂��v
�i�㗪�j�B
���낵���b���Ǝv���܂��B
�匎����́A������A�p�[�g�𒆐S�Ƃ����A�Â��W���Z��̎���������
�����ɏZ��ł����l�X�ւ̒�����蒲���Ȃǂ��Q�O�N�߂����g��ł��Ă��܂��B
����Ɋւ������_������������܂��B
�����������N�̌���̌����A������������N�̔w��ɂ���̂ł��B
�������ł��A���Ԃ̌o�߂����l�����߂鐢�E������܂��B
��Ղ���j�I�������ł��B
���̍D���Ȑ��E�ł��B
���̐��E�Ƃ͑S�������ɁA���Ԍo�߂��}�C�i�X���l�ɂ��Ă��܂����̂��A
���݂̎Y�ƎЉ�ł���A���{��`�o�σV�X�e���ł��B
�����ł́u�j��v��u�Q��v���u���W�v�Ɓu���Y�v�ɒu���������Ă��܂����̂ł��B
���Ԃ̊T�O���S���ς���Ă��܂����̂ł��B
����ȑ傫�Ȗ���N�������Ȃ���{����ǂނƁA
���߂č����̎������̕�炵�Ԃ������̕n�����������Ă��܂��܂��B
�ƂĂ������ɕx��ł���{�ł��B
���z�Ƃł͂Ȃ��l�����ɂ��A���Гǂ�ł��炢�����{�ł��B
���u���q�V�@���̓���v
�ΗL���v�@���z�o�Ł@1300�~�i�ŕʁj
�R���P�A���Ԃ̖���́A���䌧�̓��q�V�Ŏ��E�h�~�����Ɏ��g��ł��܂��B
���q�V�́A��i�̊ό��n�Ƃ��ėL���ł����A�����ɁA�ʖ��u���E�̖����v�Ƃ������Ă��܂��B
���{�C�ɓ˂��o�����f�R�̏�ɗ��Ƌz�����܂�Ă��܂��悤�ȋC�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B
����̂��Ƃ͂��̃T�C�g�ɂ������܂������A
�m�o�n�@�l�u�S�ɋ������W�E�ҏW�ǁv�𗧂��グ�A�n���Ȋ�����W�J����Ă��܂��B
�����̊����ŁA���E���v���Ƃǂ܂����l�͏��Ȃ�����܂���B
���N�A�u�����Љ�������v����܂���܂������A���̎��̃C���^�r���[�L�������ǂ݂��������B
����̂������������`����Ă��܂��B
����9���ɓ��q�V�ł�����܂������A���̎��ɍ��x�{���o�ł���Ƃ��b�ɂȂ��Ă��܂����B
���̖{���{���ł��B
���̖{��ǂނƍ��̎Љ�̂��������������Ă��܂��B
����͓��q�V�̂���O���x�@���ɋΖ������̂��_�@�ɂȂ��āA���̊������n�߂�̂ł����A���̌o�܂����̖{�ɏ�����Ă��܂��B
�ƂĂ������ł��܂��B
���̎����͕���15�N�ɋN����܂����B
����͓����A�O���x�@���̕������ł����B
���Â��Ȃ������q�V�̏��тŖق��ăx���`�ʼn�������Ă���N�z��2�l����ɏo������̂ł��B
�u���Ă݂�ƌo�c���Ă������X�����܂��������ɁA���q�V�Ŏ��E���悤�ƌ��߂Ă���Ă����̂������ł��B
�b�����Ă��邤���ɁA2�l�̎��ɃJ�~�\���Ő����܂��V�����������邱�ƂɋC�Â�������́A
�����ɒn���̕a�@�ɓ��@�����A����̕����ۂɁu���ݒn�ی�v�̎葱���𗊂݂܂����B
�����Ŏ����͏I���͂��ł����B
5����A����2�l����莆���͂��܂����B
����ւ̂���̎莆�ł����B
�������A2�l�͂��̎莆���o������A��݂莩�E�����Ă��܂����̂ł��B
���k�ɍs�����Ƃ��낷�ׂĂ��猩�̂Ă�ꂽ�̂ł��B
����͂��������Ă��܂��B
�������͌��E�̌x�@���ł����B
�S�Q�N�Ԃ̌x�@�������̒��Ŏ��́A
���{�Ƃ������́A�u�����Ăق����v�Ƌ���ł���l��������A
�ǂ����ł��ꂩ�������Ă����A���炵���@�����Ƃł���ƐM���Ă��܂����B
�����������͈���Ă��܂����B
�����Ă���l��ی삷��@���́A�����Ƃ���͂��Ȃ̂ɁE�E�E�B
���������ł����A�����Ĉ��p�����Ă��炢�܂��B
�x�@�͕ی삷�ׂ��҂������ۂ͑��₩�ɕ����@�ւɈ��p���`��������A
���p�������s���@�ւ́A�ی�����肵�ĕی���J�n���ׂ��`��������A
�����ӂ����҂ɂ͔������ۂ�����̂ł��B
���͂����M���āA�Q�l�Ɂu���ɕی�����߂Ȃ����v�Ə������܂����B
�Q�l�͎��̌��t��M���ė��𑱂����̂ł��B
�������k�����̉����ɂ�������ł́A�x�������Ă����ꏊ���P�ӏ����Ȃ������̂ł��B
���̂Q�l�ɂƂ��Ď��̑��݂͉��������̂ł��傤���B
���܂ł̋ꂵ�݂�����ɒ��������������̑��݂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
���͂���2�l�ɁA��d�̋ꂵ�݂�^���邾���̑��݂ɂȂ��Ă��܂����̂ł��傤���c�B
�����ƈ��p�����̂ł����A���肪�Ȃ��̂ŁA����͂��̖{��ǂ�ł��炢�����Ǝv���܂��B
2�l����̎莆���{�ɂ͏Љ��Ă��܂��B
���̎���������̐l����ς��܂����B
����͂��������Ă��܂��B
�ǂ�Ȏv���ł��̂Q�l�́A���Ɏ莆��������̂ł��傤�B
�������ނ̂͊ȒP�ł��B
���������ꂩ������A��O�̋]���҂����܂��̂��������āA���͐S���₩�ł�����ł��傤���B
�����ɂ͊W�Ȃ��A�����̐ӔC�ł͂Ȃ��ƁA���R�Ƃ��Ă�����ł��傤���B
�Ȃ��A��N���ԋ߂ɂȂ��āA����ȏo�������N�������̂��B����Ȍ�����m�����̂��B
�m���Ă��܂����ȏ�A������邵���Ȃ��Ƃ������ӂ��A�������ƌł܂��Ă����܂����B
10�N�Ԃ�253�l���̐l���ꂵ�݂Ȃ��玀��ł���B
���ꂩ��253�l�̑�َ҂ƂȂ萢�Ԃɑi���Ȃ���A���Ԃ̐l�͋C�Â��Ă���Ȃ��B
�u���Ȃ��Ȃ�ł���A���Ȃ�����邵���Ȃ��v�Ɣ��H�̖���Ă�ꂽ�悤�ȋC�����܂����B
����̎v�����ɂ��قǓ`����Ă��܂��B
�l�͂������Ď����̐l����ς��Ă����̂ł��B
���̖{�ɂ́A���̌��������l���̃P�[�X���Љ��Ă��܂����A
����͂�������������ł̒��ɕ����Ă͂����Ȃ��ƍl���܂����B
�����Ƃ݂�Ȃōl���Ȃ�������Ȃ����ł��B
�����R���P�A������ʂ��āA���܂��܂Ȑl���ɂ����₩�ɐG���悤�ɂȂ��Ă���A
����Ɠ����悤�ɖ��������ƃI�[�v���̏�ł݂�Ȃōl���Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B
����������ɖ����Ȗ��Ȃǂ͂��̐��ɂ͂Ȃ��̂ł��B
���ׂĂ��Ȃ����Ă��܂��B
���̖{�ɂ͂����ЂƂl���������镶�͂��ڂ��Ă��܂��B
����ƈꏏ�Ɋ������Ă����z����̑̌��k�ł��B
����Ɛ�z����B
��2�l�̎��̌��Ɋ�Â������ɐS����h�ӂ�\�������Ǝv���܂��B
���܁A���́u���̂��v�Ƃ������ɉ��߂Ē��ʂ��Ă��܂����A
���̖{��ǂ�ŁA���̖��̐[���Ɉ�������Ă��܂��B
�݂Ȃ���ɂ����Гǂ�łق����{��1���ł��̂ŁA�����ďڂ����Љ���Ă��炢�܂����B
����������w���ł��܂��B
���u�����̌��_�v
�r�c�O�i�@����Ɂ@1600�~�i�ŕʁj
���{�̏��l����o�c�N�w�����C�t���[�N�ɂ���Ă���r�c�O�i����̐V���ł��B
�r�c����͓��Y�����ԂŊ��ꂽ��A
�������̊�Ƃ̖����Ƃ��Ċ�ƌo�c�Ɏ��g�܂�Ă��܂������A
���������o�c�̎��H�܂��āA��ƌo�c�̌��ꂩ����ނ��ꂽ����A
���{�̌o�c�̂��肩���ɔM�S�Ɏ��g�܂�Ă��܂��B
������������̂͂���15�N�قǑO�Ȃ̂ł����A
���̍�����I�n��т����p���������������Ă��܂��B
�r�c����͊�Ƃ̌�������͌o�����ł����B
�o���̐��E�ɂ���Ɗ�Ƃ̎��Ԃ���������ƌ�����̂ł��傤�B
�ŋ߂̌o���̐��Ƃ͐���������ǂ��Ă���悤�ȋC�����܂����A
�r�c����͐����̔w�i�ɂ����ƌo�c�̎��Ԃ����Ă����̂ł��B
�����Ď���ɊS���o�c�N�w��ڋq���l�ȂǂɌ����Ă����̂ł��B
�{���͂��������r�c����̍ŐV�̌������ʂł��B
�{���̕���́u�]�ˏ��Ƃ̉ƌP�Ɋw�ԁv�ƂȂ��Ă��܂��B
�O��ƂɎn�܂�A�ߍ]���l�܂ŁA���ꂼ��̉ƌP���x�[�X�ɂ��āA
���{��Ƃ̌o�c�̊�{�N�w���ƂĂ��킩��₷���Љ��Ă��܂��B
����������������p����Ă���̂ōr�c����̃K�C�h�ł��݂��߂�̂������ł��傤�B
�ǂ߂Γǂނقǎ����������܂��B
�r�c����́u���сv�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă��܂��B
��Ƃ��Љ�ɑ���{���̖������ʂ����Ă������߂ɂ́A�W�ґS������v���čs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����ŁA��Ɨ��O�A�s���K�͂��K�v�ƂȂ�B
��Ƃ͗��O����̓I�ɕ����Ɏ������Ƃň�v�c�����A�s�����Ă�����̂ł���B
����ɂ����ẮA���O�������Ȃ����߂ɁA��Ƃ��������ׂ����������m�łȂ�������A
�����ȂǒP�Ȃ�^�c��i�ɂ����Ȃ����̂��A�ړI�ł��邩�̂悤�ɍ��o���Ă���P�[�X���A���܂�ɑ����B
���ʎЉ�𑛂��������́A���̌��ʔ������Ă���Ƃ����Ă悢���낤�B
��Ƃ͍������A���Ђ́q�ƌP�j���Ȍ��������Ɏ����ׂ��Ȃ̂ł���B
�]�ˏ��Ƃ̉ƌP��ǂ݉������ƂŁA�����Ƃ̂�������l����ꏕ�Ƃ������B
�����ł��B
�����̓��{��Ƃɂ͌o�c�N�w���s�݂ǂ��납�A
�o�c���s�݂ɂȂ��Ă���悤�ȋC�����ĂȂ�܂���B
��ƌo�c�Ɋւ����X�ɂ�������Ƃ��݂��߂Ă��炢�����{�ł��B
���u�m�o�n������������v
�c���퐶�@���{�]�_�Ё@2200�~�i�ŕʁj
���{�̂m�o�n�����ɓ�������ւ���Ă����c���퐶����̐V���ł��B
���肪�u�s���̉��������ɖ����͂Ȃ��v�ƁA���m�Ȏ咣�������Ă���{�ł��B
���̓c������̃��b�Z�[�W�͍�N�̂m�o�n���Ԓ��������~���ɂ��Ă��܂��̂ŁA�P�Ȃ�_�����Z�̃��b�Z�[�W�ł͂���܂���B
��̐�������̂ł��B
����ɔޏ��̒��N�̂m�o�n�Ƃ̕t��������ʂ��ē��B�������b�Z�[�W�Ȃ̂ł��B
�ł���������͂�����܂��B
���Ȃǂ͂ނ��뉺�����������m�o�n�����{�̃R�����Y�����߂ɂ���Ƃ����v���Ă��܂����A����͂��܂�����͂�����܂���B�͂��B
�m�o�n�Ƃ̕t�������̒��ŁA�ŋ߁A�c������́u�m�o�n�̉������ώ����Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ɗ����n�߂��̂��{���̎n�܂肾���������ł��B
�ޏ��Ƃm�o�n�̕t�������́A�`���́u�͂��߂Ɂv�ɏ�����Ă��܂����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��ʔ����ł��B
�c������Ƃ̕t�������͒����̂ł����A�{���̏����o���͏��߂ĕ����b�ŁA�ƂĂ������������܂����B
�m�o�n�O�j��c������͂��낢��ƌ������Ă���̂ł��B
�ʔ����̂͂������u�͂��߂Ɂv�����ł͂���܂���B
�{��������ƃ��b�Z�[�W�ƑS�̑������܂��ҏW����Ă��āA���͂����Ȃ�ēǂ݂₷���A�����������ɕx��ł��܂��B
�������D�������Ă��͖̂ڐ����������肵�Ă���A�w�E�����m�Ȃ��Ƃł��B
�m�o�n�ւ̈������������܂��B����ɂ���܂ňȏ�ɍ��������Ă���̂��`����Ă��܂����B
�����܂���Ƙ_�l�ɔ��͂��o�Ă��܂��B
�Ƃ��������ꂩ��̂m�o�n�̓W�J���l���Ă�����ł̂�������̎�����������A�m�o�n�W�̍D���ł��B
�m�o�n�W�҂͂��Ƃ��A�s�����Ƃ̐l�����ɂ����Гǂ�łق���1���ł��B
���u�Z�p�ϗ��@���{�̎��Ⴉ��w�ԁv
�������E���{���Ғ��@�ۑP�@2000�~�i�ŕʁj
�Ȋw�Z�p�҂̗ϗ����ɐ��͓I�Ɏ��g��ł������{��������
�k�C����w�̍��������������ƈꏏ�ɂ܂��V�����{���o�ł���܂����B
70����㔼�ɓ������͂��̐��{����̍s���͂ɂ͂�������������܂��B
���{����͓��{�̑�w�Ɂu�Z�p�җϗ��v�̍u�����L���悤��
�m�o�n�@�l�Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[�����̃����o�[�ƈꏏ�ɍu����W�J���Ă��Ă��܂����A
�{���͂��̃����o�[�����̋����ł��B
���M����Ă��܂����A���ɐ��{����̏����������ɂ͖��m�Ȏ咣�������܂��B
���Ƃ͏����l���̈Ⴄ�Ƃ�����Ȃ��킯�ł͂���܂��A
�咣�����m�ł��̂ŁA�ƂĂ��C�����悭�ǂ߂܂��B
�{���͑�w�̋��ȏ��Ƃ��ď�����Ă��܂��B
���{����͂��łɋ��ȏ��Ƃ����u�Z�p�҂̗ϗ�����v���o�ł��Ă��܂����A
�{���́u���w�I�ɋZ�p�ϗ��̊�{�I�ȍl�����A�ӎv����̎�@���K���ł���悤��
�w�K�v���O�������g�܂�Ă���v�Ə�����Ă���悤�ɁA
���ʓI�ȃO���[�v���c���ł���悤�ɕҏW����Ă��܂��B
�u�O���[�v���_�̐V�������f�����������v�Ƃ������҂����̎v�����A����܂łƂ͈Ⴄ���͂ݏo���Ă��܂��B
�������ɋ��������̂́A���グ������̍L����Ƃ��̎��グ���ł��B
���Ɂu����A�Ȋw�Z�p�͐l�Ԑ����ɍL���[���ւ��A������Ƃ���ɋZ�p�҂̐E�ꂪ����A�ϗ���肪���肦��B
�{�������グ�Ă���̂́A����̋Z�p�҂̐g�߂ɂ���ϗ����ł���v�Ə����Ă��܂����A
�I�ꂽ�����ǂނ����ł��A���҂����̃p�[�X�y�N�e�B�u�̍L������������܂��B
�Z�p�҂Ɍ��炸�A�ϗ����͓����҂̐��E�̍L���肾�ƍl���Ă��鎄�ɂƂ��ẮA�ƂĂ������ł���p���ł��B
�Z�p�җϗ��͌���ꂽ���E�Ō����Ƌt���ʂɂȂ肩�˂܂���B
�Z�p�҂̐��E���L���邱�Ƃ������A�Z�p�җϗ��̍ő�̉ۑ�ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂��B
����̒��Ɂu��������S���v�����グ���Ă��܂��B
��������S���́A�����d�S�����䌧���ʼn^�c���Ă����z�O�{����2�x�̎��̂̂��߂ɔp���ɂȂ����̂�
���䌧�Ɖ��������̂��ꏏ�ɂȂ��Čp��������R�Z�N�^�[�ł��B
��R�Z�N�^�[�Ƃ����Ƃ��܂�C���[�W�͗ǂ��Ȃ��ł����A
�����Z�����ꏏ�ɂȂ��āA�ƂĂ��f���炵���^�c�����Ă���悤�ł��B
�ǂ��f���炵�����͖{�������Гǂ�łق����Ǝv���܂����A�ꕔ�A���̂��������̃T�C�g�ł��ǂ݂��������B
http://www12.ocn.ne.jp/~shiokaze/newpage22.html
���{����͎��ۂɂ�������S���ɏ�Ԃ��A���̑̌������܂��Ė{���Ŋ��z��������Ă��܂��B
�ƂĂ��S�������܂鎖��ł����A������������ł��킩��悤�ɁA
�{�������グ�鎖���{���̃��b�Z�[�W�ɂ́A�l�Ԃ���̎��_���������܂��B
�Z�p�ϗ��ȂǂƂ����Ɠ���C���[�W������������܂��A
�v�͐������_���������莝���Ƃ��ϗ��̊�{�Ȃ̂��Ǝv���܂��B
�ڎ��̈ꕔ���Љ�܂��ƁA
�u�l�Ԑ����ɂ����钍�Ӌ`���v
�u�g�D�̂Ȃ��̌l�v
�u�R�~���j�e�B�̐l�ԊW�Ɠ��������v
�u�l�ԂƓ����̊W�v�ȂǁA���͓I�ȍ��ڂ�����ł��܂��B
���������̂��ׂĂ��������肵������𒆐S�ɂ₳��������Ă��܂��B
��w���Ɍ��炸�A�Z�p�҂�Ȋw�Z�p�Ɋւ��l�ɂ��ǂ�łق����ƒ��҂����͏����Ă��܂����A
���͋Z�p�҂Ɍ��炸�A��Ɛl����҂��ׂĂ̐l���傫�Ȏ�����{���Ǝv���܂��B
���Ɋ�ƌo�c�����̐l�����ɂ͓ǂ�łق����Ǝv���܂��B
�O���[�v���c�̃K�C�_���X�����p���Ȃ���A�b�������̃e�L�X�g�Ƃ��Ă��œK�ł��B
���Ȃ݂ɁA�����Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[�����̃����o�[�ł��B
�����������{�����̊���������ɍL���Ă������߂ɁA
2006�N11��26���ɁA�Z�p�җϗ��̖����炵�̎��_����l������J�t�H�[��������悵�Ă��܂��B
10���ɂȂ�����ڂ����ē������m�点�R�[�i�[�ōs�Ȃ��܂��̂ŁA���Ђ��Q�����������B
�S�̂�����͎��Ƀ��[����������A�ʓr���ē����܂��B
���u���a�̂��߂̐����w�v
��{���@���Ώ��X�@2600�~�i�ŕʁj
��{�������͐ϋɓI�Ɏ�Ҍ����ւ̕��a�̓������������Ă��܂����A����4�N��6���̖{���o�ł���܂����B
�������A�ɂ߂Ė��x�̔Z�����e���A���Z���ł����������������Ă�悤�ɁA�\���ə����{�ł��B
�P�Ȃ�m���������{�ł͂Ȃ��A��{����I���W�i���̃��b�Z�[�W������܂��B
��{����ւ̕��a�ւ̎v���̐[�����@���̋������`����Ă��܂��B
�{���͑O���u���a�̂��߂̌o�ϊw�v�̎o���҂ł����A����ɂ́u�ߑ㖯���`�W�����悤�v�Ƃ���܂��B
���Z�����w�����ӎ������������ɂȂ��Ă���A���t�̊T�O�������������肵�Ă��܂��̂ŁA
���t�����̋c�_�ł͂Ȃ��A���̋c�_���Ȃ���Ă��邱�ƂɍD�������Ă܂��B
�m���������Ă����l�����ɂ́A���ɋ��ȏ��I�Ȉ�ۂ�^���邩������܂��A
���������������������肵���{�𑽂��̑�l�����ɂ��ǂ�łق����Ǝv���܂��B
�����āA��Ҍ��������̖{�ł͂���܂���B
�����Ƃ͉����A���ƂƂ͉����A�����`�Ƃ͉����A�Ƃ�������{�I�ȊT�O���A
�������͂����܂��ɂ����܂܁A�����_�`�����A���a�_�c���������ł����A����ł͋c�_�͏o���Ă��s���ɂ͂Ȃ���܂���B
�{���̓��e�͕ʂ̃T�C�g�����ǂ݂��������B
http://www.hanmoto.com/bd/ISBN4-7503-2404-3.html
�����ʔ��������̂́A�u���O�v�u���O�v�u��O�v�u�Q�W�v�̋c�_�ł��B
�����������t�ɖ{�����܂܂�Ă��邱�Ƃ͏��Ȃ�����܂���B
�u�����`�͕��a�ƌ��т����Ƃɂ���Ĕ��W����v���ʔ��������ł��B
���ʂ́u���a�͖����`�Ɍ��т����Ƃɂ���Ĕ��W����v�Ƃ����c�_�������̂ł����B
�ŏI�̍��ڂ́u�ߑ㖯���`�͂��͂�w�x�ꂽ�����`�x�ł���v�ł��B
���ƌ����̍Ĕz���̒�Ă�����܂��B
�ǂ��ł����B�ǂ�ł݂����Ȃ�܂����ł��傤���B
���������������āA�������Ăق����ł����A�܂����������������Ίi���̖{�ł��B
���Z���ɖ߂�������ɂȂ��āA�ǂ�ł݂�ƂƂĂ��y������������܂���B
�����āA�ǂ琥��s���Ɉڂ��Ă��炦��Ǝv���܂��B
���a�Ɍ����Ăł��邱���͂�������܂� �B
���̓��{�́A�܂��ɗ��j�̋A�H�ɂ���܂��B
���Ȃ݂ɐ�{����̖{���ȊO�̍ŋ߂̂T���͎��̒ʂ�ł��B
��������u�b�N�̃R�[�i�[�ŏЉ�Ă��܂��B
���u���a�̂��߂̌o�ϊw�v
���u�����ŏ������I���{�����@�����āv
���p���`�u�V�v���a���@
�\ ���a�������Ƃ��Č��@�ɂ�������
���u�ǂ�Ȑ��E���\�z���邩�v
���u�ǂ�ȓ��{�����邩�v
��{������͂�ł̕��a�_�c�ɊS�̂�����͎��ɂ��A�����������B
�R�l�ȏ�̂���]������A��悵�܂��B
���u�I����q�����@��x�ڂ͂�邳��Ă��v
�L���ɕ��w�ق��I�s���̉��@700�~�@
�����L�^�ł��Љ���u�L���ɕ��w�ق��I�s���̉�v�̃u�b�N���b�g��1���ł��B
2005�N�ɊJ�Â��ꂽ�V���|�W�E���u�I����q�����v�̋L�^�𒆐S�ɁA�I������̍�i�Ȃǂ����߂��Ă��܂��B
���e�Ɋւ��ẮA�����V���̋L�����ƂĂ��悭�����Ă��܂��̂ŁA����Ɉς˂����Ǝv���܂��B
�u�I����q�������̃u�b�N���b�g�v
���́A���̃z�[���y�[�W�ɂ����܌����L�̕M�҂̐܌����瑡���Ă��炢�܂����B
�܌�����́A�I������̎��̒��Ԃł��錴�������炱�̖{�������Ă�������悤�ł��B
���͐܌�����ɂ�������ɂ��A���͂܂��ʎ����Ȃ��̂ł����A�s�v�c�Ȃ����������Ă��܂��B
�����q�ł����A���e�͂ƂĂ����x�������A�����I�ł��B
����͂��ʓ|��������܂��A�s���̉�Ŏt���Ă��܂��B
����ɐl�ɂ����߂Ă��炦��Ƃ��ꂵ���ł��B
���a�͂��܁A�傫�ȋȂ���p�ɗ��Ă���悤�Ɏv���܂��B
���߂����Ȃ�܂����A���̖{��ǂ�ŁA��͂���߂Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂����B
�א��҂ɂ��ǂ�ł��炢�����ł��B
���蕶���猩���Ñネ�[�}������
���[�����X��P�b�s�[�@���щ�v����c�m�u��@�����[�@2500�~�i�ŕʁj
�V���̃I�[�v���T�����ł��Љ�����ы����̍ŐV�̖|�ł��B
���͑���ꂽ���Ђ�1�T�Ԉȓ��ɓǂނ̂ł����A���̖{�͓ǂ݉���������A
�ǂݗ������Ƃ��ł����ɏЉ�x��Ă��܂��܂����B
�Ñネ�[�}�̐������Ɋւ��ẮA
���Ƃ��|��B����́u�f��̃��[�}�l�v�i�͏o���[�V�Ёj�Ȃǂ���܂����A
�����������̂Ƃ͂�����ƈႢ�A�蕶��ʂ����A������̃��[�}�s�����������Ă����̂ł��B
�蕶�Ƃ������̖̂��͂��`����Ă��܂��B
����ɂ��Ă��A�l�ԂƂ́u�����c�����ƣ�̍D���Ȑ����ł��邱�Ƃ��悭�킩��܂��B
���������܂߂āA������Ƃ���Ɂu���j�v���c���Ă���̂ł��B
�G�W�v�g�̃����m���̋����͏��w�Z�̎��ɏ�����́u�����̖����v�Œm���Ĉȗ��A���ꂾ�����̂ł����A
10���N�O�Ɋ����̏o��������܂������A�����ɂ͂�������̗�����������܂����B
�{���ɂ��A1000���闎���������邻���ł��B
�g���R�̃G�t�F�\�X�ł��������̗������̘b���K�C�h���畷���܂������A
���̖{��ǂ�ł�����A����������ʂ������Ɗy�����Ȃ����ł��傤�B
�p���b�J���̏��l�̕�̘b���o�Ă��܂����A�Ñ�n���C���E����D���Ȏ��Ƃ��ẮA
������Ƃ����L�q�̈����ƂĂ������[�����̂ł����B
���쎵������́u���[�}�l�̕���v�Ƃ́A�܂�������ʔ���������܂��B
���������ƒm�肽�������̂́A1818�N�N�ɔ������ꂽ�Ƃ����蕶�ł��B
�T��5�s�̎l�p�`�̌���w�ł����A���ꂪ�~�g���X�o��_�����k�֘A������Ƃ̐������邻���ł��B
�������������閧�߂������̂ɂ͂Ȃ����킭�킭���܂��B
���[�}�s�ɏڂ����l���ǂނƎ��Ɋy�����{�Ȃ̂ł��傤�B
���Z�i�̌ꌹ�ɂȂ����Ƃ����}�C�P�i�X�炵���l���o�ꂵ�܂����A��������ǂނƊy�����ł��B
�Ñネ�[�}�s�ɊS�̂�����ɂ͂����߂ł��B
�A���A��C�ɓǂނ̂ł͂Ȃ��A�C����������ʔ������ȂƂ����ǂ�ŁA
�Ō�ɏ����́u���j��h�肩����蕶���ǂނƂ����ł��傤�B
�Ȃ��{���̓��e�Ɋւ��ẮA���̃T�C�g���Q�l�ɂȂ�܂��B
http://www.augustus.to/books/archives/2006/08/post_27.html
���u���_����
vs �L���X�g�� vs �C�X�������@�@���Փ˂̐[�w�v
���^��@�����핶�Ɂ@762�~�i�ŕʁj
�܂��������̐V���ł��B
������Ƃ���܂ł̂��̂Ƃ͕��삪�Ⴂ�܂����A����܂��ӗ~�I�Ȓ����\�z�i���E�� "vs"�œǂ݉��������j�̍ŏ��̒���ł��B
�܂������̈ꕔ�����p�����Ă��炢�܂��B
���̑O�����̕��͂Ŏ��͂��̖{�̊�{�p���ɋ����������ēǂ܂��Ă��炢�܂����B
�{���́A�l�ނ̗��j�ɑ傫�ȉe����^���Ă����O�l�̎o���̕���ł���B
�����́A���_�����B�́A�L���X�g���B�����āA�O���́A�C�X�������ł���B
�����e�A�܂蓯����_���̐_��M���A�u�����v�Ƃ��������[�T��S�̂��ǂ���ɂ��Ȃ���A�����ݍ����A�E�������悤�ɂȂ������ɂ���ȎO�l�̎o���B
�i�����j
�o��炤�O���͓Ƃ͏��߂��炤�܂��t�������Ȃ������B�D��I�ȓ������U�����d�|���Ă���̂ŁA�d���Ȃ��ė��悤�ɂȂ����B
�i�����j
�{���́A���̂R�l�̖��̐�����������A���̐��_���E�܂ōL���T���Ă䂭�B
�O�o���@����m��A���E����������B
���͂P�O�N�قǑO�܂ŁA�M���V�A�ƃy���V�A�Ɋւ��āA����I�Ől�ԓI�ȃM���V�A�Ɛꐧ�I�Ŕ�l�ԓI�ȃy���V�A�Ƃ����C���[�W�������Ă��܂����B
�Q�O�N�قǑO�ɁA�y���V�A�j�̓��发��ǂ�ł��̃C���[�W���^�������܂����B
���̐��E�ς���j�F���́A�ߑ㐼���̉��l�ςɐZ�肫���Ă����悤�ł��B
����͂Ƃ������A�y���V�A�̂ق����l�ԓI�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����v�����ʂ�����܂���B
�L���X�g���ւ̃C���[�W���܂����̍�����傫���ς��܂����B
���܂̐��E�̍\���̌��������A���̋^��ɗ��r����ƃ}�X�R�~�Ƃ͑S��������悤�Ɍ����ĂȂ�܂���B
���]����Ƃ͋��낵�����̂ł��B���]����͉����k���N�����̘b�ł͂���܂���B
����A������������̖{���͐��]�Ȃ̂�������܂���B
�M���ł���F�l�ł��A���̍l�����ɂ����Ă͑S������Ȃ��ꍇ�����Ȃ�����܂���B
�l�������Ⴄ����Ƃ����āA�M���W���h�炮���Ƃ͂���܂��A
���X�A��肫��Ȃ��C�����ɂȂ邱�Ƃ͂���܂��B
���E�ς�l���ςɂ����Ė��߂������f��������邩��ł��B
����̈Ⴂ��������܂��A�����������狳����i�w�Z�����ł͂���܂���B
�ō��̋���̓}�X�R�~����̏��ł��j�̈Ⴂ��������܂���B
�Ƃ���Ŗ{���ł����A�R���p�N�g�ȕ��ɔłł����A���e�͗~�����Ă���Ƃ��������قǖԗ��I�ł��B
�����������ɒ��҂̃��b�Z�[�W�����߂��Ă��܂��̂ŁA�P�Ȃ������ł͂���܂���B�ł�����ʔ����ł��B
���ɂ͂���Ȗ{���������ł��傤���B
���ߑ��Ō����̂Ȃ��}�X�R�~�̘_���ւ̖Ɖu�����߂邽�߂ɂ��B
���u�E�q�ƃh���b�J�[�@�n�[�g�t���E�}�l�W�����g�v
���^��@�O�܊ف@1500�~�i�ŕʁj
���^�炳���ɋS�_�����ڂ����Ƃ����v���Ȃ��̂ł����A�܂��V���ł��B
�悭�������A���X�Əo�ł������̂��Ɗ��S���܂����A���̈��������ƂĂ���������Ă���A���H�I�ȃ��b�Z�[�W�ɖ����Ă���̂ł��B
��w�ɐЂ�u���A�����⎷�M���ƂƂ��Ă���̂ł���Εs�v�c�͂Ȃ��̂ł����A
�������͂�����Ƃ����N��200���~�̊�Ƃ̎В��Ȃ̂ł��B
�������A�����̂͂܂������̂ł��B
�{��������ĂP�T�Ԃ����Ȃ������ɁA����ȃ��[�������܂����B
�u�S�_�����ڂ����������A�����P���㈲�������܂����̂ŁA�܂����点�Ă��������܂��B�v
����͂�A�����̂���l�̍s���͂́A�v��m��Ȃ����̂�����܂��B
����͂Ƃ������A���̖{�͑O�ɏЉ���u�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�v�ɑ��������S�w�O����̑�Q�e�ł����A
�����ɂ܂��O����u�m�̋��l�h���b�J�[�Ɋw��21���I�^��ƌo�c�v�Ƃ��Z�b�g�ɂȂ��Ă��܂��B
�ƂĂ����H�I�ŁA���������O�I�ł��B
�ǎ҂͌o�c�̋Ɉӂ��w�ԂƂƂ��ɁA���̐������ւ̑傫�Ȏ�����͂��ł��B
�ҏW�̃X�^�C�����H�v����Ă��܂��B
�Ǐ������̍ŋ߂̊�Ɛl�ł��C�����A�����Ċy�����ǂ߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�S�̂��S�W�̏͂ɕ������Ă���̂ł����A
���̌��o�����A���Ƃ��A�u�m�v�u�`�v�u��v�ȂǂƂ��������ꎚ�ɂȂ��Ă��܂��B
�����ɂ��E�q���ȂƎv���邩������܂��A
���ɂ́u���v�u�^�v�u�{�v�u���v�u���v�ȂǁA����ӂ�Ɏ��グ���Ă��܂��B
��������ɂ̓h���b�J�[���o�Ă��܂��B
������M�Ă����N�����̘b����������o�Ă��܂��B
�ʔ����̂́A���҂̐����Ԃ���_�Ԍ����邱�Ƃł��B
�Ȃ����҂�����قǎ��X�ƒ�����Ă��邩�̔閧��������������Ă��܂��B
���̂��ω��ɕx��ł��āA�ʔ����ł��B
�����ƂĂ��C�ɓ������̂́A�u�ǁv�u���v�̏͂ł��B
���Ƃ��A�u�ǁv�͂���ȏ����o���ł��B
���́A�Ƃɂ��������A�ǂ�ł���B
����ǂނ��B�܂��A�{��ǂށB
�Â��͂́u���v�́A
���́A�Ƃɂ��������A�����Ă���B
�����������B�܂��A���e�������B
���ɃX�^�C���b�V���ł��B�C�ɓ����āA������ǂ�ł��܂��܂����B
���e�̏Љ�s�����Ă��܂��ˁB
���݂܂���B
���Ƃ������班�����p���ē��e�Љ�ɑウ�܂��B
�u�{���́A�����̏��ł���v�ƁA���Ƃ����͎n�܂�܂��B
�l�����Ƃ��̓T�^�I�ȓ�̕���̃A�i���W�[�Ƃ��āA
���z�Ɩk���̃C�\�b�v���b���g���܂����A�������͂��������܂��B
���X�g���̕��𐁂����Ј��������点��k���o�c�ł��Ȃ��A
�o�u���[�ɎЈ����Â₩�����z�o�c�ł��Ȃ��A
���߂Ɠ��������ĎЈ����₳������ݍ��ތ����o�c�B
���ꂱ���A�S�̌o�c�A�܂�n�[�g�t����}�l�W�����g�̃C���[�W���̂��̂ƂȂ�B
�{���́A���̌����o�c�̋Ɉӏ��Ȃ̂ł��B
�ڂ����͐���{�������ǂ݂��������B
���H�I�Ȍo�c��������Ă��܂��B
������肩�A���������l�����ł��A��������̃q���g�����炦��͂��ł��B
���E�̏��Ƃ��āA���X�A�C�̌������͂�ǂނƂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
��ƌo�c�҂ɂ͂������ł����A�m�o�n��s���̐l�����ɂ������߂������{�ł��B
�O�����ꏏ�ɐ��ǂ݂��������B
���Ȃ݂ɁA�������̌o�c�ς́A�u���߂Ɠ��������ĎЈ����₳������ݍ��ތ����o�c�v�ł����A
���̌o�c�ς��u���Ǝ����݁v�ł��B�֑��ł����B�͂��B
���u�z�^�Љ����v
�X���i�@�V���Ɂ@1200�~�i�ŕʁj
���X�v���Ă����Ȃ������{�ɏo�������Ƃ�����܂��B
����Љ���Ă��������{���́A���̗F�l���������{�ł���܂���B
����l���Ȃ��������Ă��Ă����������̂ł��B
�{�̓��e��������������A���̍l���ɂȂ����Ă���ƍl���Ă��ꂽ���炩������܂���B
���̖{�̂��Ƃ����ɁA���̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B
�z�^�Љ�̉^���͊v���I�]�����Ӗ����Ă���B
�o�ώ����`�Љ������A�u�o�ςɂ���Ă̂ݐl�͐�������Ă���v�Ƃ������l�ς���E�o��}��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����āA���̂��Ƃ̐V�������l�ς��������z�^�Љ�̎p�������Ă���B
�V�����̐��́u�j��Ƒn���v���琶�܂��B
���̂��߂ɂ��A�v�������E�C����u�j��v�̍s�����N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł���B
�z�^�Љ�����ɂ��Ȃ�����A�o�ώ����`����E�p�ł����ɂ���A�����̊�ƌo�c�҂����ɓǂ܂��������͂��Ǝv���܂��B
�Ƃ��낪�ł��B
���͂��̖{�͊�Ƃ̌o�c�҂��������{�Ȃ̂ł��B
���҂̐X���i����͎��ꌧ���V�]�B��������̉�Ȃ̂ł��B
�V�]�B�͕���ނȂǂ𒆐S�Ɏ��Ƃ��Ă���A�]�ƈ��P�O�O�l���̒�����Ƃł��B
�А��́u�ߋ��ɂ͊��Ӂ@���݂ɂ͐M���@�����ɂ͊�]�v�B
����̉�Ђ炵���A�ߍ]���l�̓`���́u�O���悵�v���ɂ��Ă���悤�ŁA�O���悵���H��ƂƂ��Ă��Љ��Ă��܂��B
��Ђ̏Љ�����Ȃ��Ă��܂��܂������A��ЂƂ��Ă�������Ƌ����𖣂���܂��B
���Ċ̐S�̖{�̘b�ł��B
���̖{�̕���Ɂu���������Ȃ��@���������܁@�قǂقǂ��v�Ə�����Ă��܂����A
���̂R�̃L�[���[�h�ɏz�^�Љ�̖{�����ے�����Ă���ƐX����͂��l���̂悤�ł��B
�܂��A���ꂾ���ł͗ǂ�����{�ł͂Ȃ����Ǝv���邩������܂���B
���������v���Čy���ǂݗ������Ǝv���Ă����̂ł����A
�ǂ�ł��邤���ɁA������Ă��邱�Ƃ����҂̎��ۂ̐����̌��⌻������ɗ��r���Ă���̂ɋC�Â������܂����B
�����Đl�ԓI�Ȋ፷���Ɠ����ɋ�����]����������Ȃ̂��`����Ă����̂ł��B
�r������݂𐳂��ēǂ܂��Ă��炢�܂����B
���Ɏ��ɂƂ��Ă͂ƂĂ������ł��郁�b�Z�[�W����������o�Ă���̂ł��B
���Ƃ��A�u�Ö��Y�Ƃ̂��܂����v�Ƃ����Ƃ���ł́A
�Ö��Y�Ƃɂ͑傫�Ȗ���������B���̔��W�̂��߂ɂ͔p�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝw�E���Ă��܂��B
���r�W�l�X�͉ߓn�I���ۂł���Ƃ���������Ă��܂��B
���͂������m�Ɍ��������o�ϐl��m��܂���B
�������X�������悤�ɁA�Ö��Y�Ƙ_�͂܂��ɂ��܂����ł�������܂���B
����10�N�ȏ�O���炻�������Ă��܂����A�c�O�Ȃ�����Y�Ƃ̃p���_�C���V�t�g�͋N�����Ă��܂���B
�܂��܂�����������������Y�Ƃ������Ă���悤�ɂ����v���܂��B
�u�X�̑�ł͑Ή��ł��Ȃ��Љ���v�Ƃ����͂�����܂��B
�܂��Ɏ������g��ł����傫�ȕ����Ɍ����ẴR���P�A�̍l�����ł��B
�u�l�Ԃ��J���l�Ԃ�n��v�Ƃ�����܂��B
�܂�Ŏ����ŏ������{��ǂ�ł���悤�ȋC�����܂����B
�������A���Ƃ͈���āA���[�J�[�̌o�c�҂Ȃ̂ł�����A���̔����̏d�݂͎��Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B
����������ꂽ����ł��B
���ɂ������ɕx�ގw�E���ӂ�ɏo�Ă��܂��B
�������A���ɗ͂������Ă��Ȃ����ՂȌ��t�Ō���Ă��܂�����A�ƂĂ��ǂ݂₷���ł��B
����Ɋe�͂̍Ō�Ɉꌾ�x�傪�Y�����Ă��܂��B
�������ׂ������ł���������̋C�Â������炦��͂��ł��B
�X����́A�u���������Ȃ��@���������܁@�قǂقǂɁv�̍l�����L���邽�߂ɁA
���̓��������Ƃ����u�l�n�g�̉�v�������Ċ�����W�J���Ă��܂��B
�܂荂簂ȕ]�_�ɂƂǂ܂�l�ł͂Ȃ��A���H�҂ł�����̂ł��B
�u�l�n�g�̉�v�͂��̖{�ł������Љ��Ă��܂����A�@������Ă����������ׂĂ݂悤�Ǝv���Ă��܂��B
�����Љ�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�j�H������Ă���悤�Ɍ���������̊�ƌo�c�����݂̂Ȃ���ɐ���ǂ�łق����{�ł��B
��Ƃɕs�M�������߂Ă���m�o�n�̐l�ɂ��ǂ�łق����ł��B
����A���ׂĂ̐l�ɓǂ�ł�����āA����̐�������������ƌ������Ă��炤�̂������ł��傤�B
�Ƃ����� �����߂̂P���ł��B
�u���������Ȃ��@���������܁@�قǂقǂɁv
�ƂĂ������ł���L�[���[�h�ł��B
�������������������Ȃ�������܂���B
���u�m�̋��l�h���b�J�[�Ɋw��21���I�^��ƌo�c�v
���^��@�S�}�u�b�N�X�@1200�~�i�ŕʁj
���̓h���b�J�[�����܂�D���ł͂���܂���ł����B
�����͂��Ȃ�ǂ�ł���̂ł����A�ǂ����Ɉ�a��������܂��B
���̗��R�͎����ł͂킩���Ă��܂��B
��Ђɓ��Ђ������A�h���b�J�[�́u����̌o�c�v�Ȃǂ�ǂ̂ł����A
�����ɂłĂ���u���ƂƂ͌ڋq�̑n���v�Ƃ������b�Z�[�W�ɑ傫�Ȉ�a���������Ă��܂����̂ł��B
���̍ŏ��̏o����A�����h���b�J�[�����ɂ��Ă��܂����̂ł��B
�������A�����������̎v���Ƃ͕ʂɁA�h���b�J�[�̒��҂͑����̌o�c�҂�\�[�V�����A���g���v���i�[�ɑ傫�ȉe����^���Ă��܂����B
�����āA���̎���ɂ���������̃h���b�J�[�M��҂����܂��B
��Ƃ̐��E�ɂ��m�o�n�̐��E�ɂ��A�ł��B
���̈�l�A���^�炳��i��ƌo�c�҂ł�����܂��j���A�h���b�J�[�̑S����������ɏ���������ŁA�ƂĂ����H�I�Ȗ{�ɂ܂Ƃ߂��܂����B
����������������{�łȂ���h���b�J�[�̉�����͓ǂ܂Ȃ������ł��傤�B
������炱�̖{�������Ă������ɂ��A��u�A�ǂ݂����Ȃ��ȂƎv�����قǂł��B
�������A�O���u�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�v�ɂƂĂ������������Ƃ�����A
�����Ă��ꂪ�h���b�J�[�̍Ō�̒����u�l�N�X�g�E�\�T�G�e�B�v�ւ̉��ł��邱�Ƃ�m���Ă������Ƃ������āA�ǂ܂Ȃ��킯�ɂ����܂���B
����Ɉ������͒P�Ȃ�]�_�Ƃł͂Ȃ��A�h���b�J�[���_�̎��H�҂ł��邱�Ƃ͒m���Ă��܂����̂ŁB
���H�҂̖{�́A�K���������܂܂�Ă��܂��B
���߂ēǂ�ł݂āA�����������玄�̃h���b�J�[�]���͔F���s����������������Ȃ��Ǝv���܂����B
�������܂��|�ӂ����킯�ł͂���܂���B
�Ȃɂ��뎄�́u�ڋq�̏��ł����Ƃ̖ړI�v�ƍl���Ă���l�ԂȂ̂ł��B
�܂��A�����ǂ��v�������Șb�ł��B
���̖{�̓h���b�J�[�̗��_���ɂ߂ĊȌ��ɁA�����H�I�ɂ܂Ƃ߂Ă��܂��B
��Ƃ̐l�ɂ͂������ł����A�m�o�n��\�[�V�����A���g���v���i�[�ɂ������߂̖{�ł��B
���̂P����ǂ߂A���݂̊�Ƃ�������d�v�Ȑ헪�e�[�}���{�I�Ȍo�c���_�̍\���������ł��܂��B
����Ɉ������̗v��́A���ɊȌ��ɂ��ėv�Ă��܂��B
�o�c�w�j���Ƃ��Ă��������Ă���悤�Ɏv���܂��A
���̖{��ǂ������ŁA�h���b�J�[�̏����̒�������߂ēǂދC�ɂȂ�܂����B
���������Ӗ��ŁA�h���b�J�[�ɂȂ��݂̂Ȃ��l�ɂ��A����݂������l�ɂ��A�����߂̌o�c���ł��B
�ŋ߁A���Ⴂ�����o�c���_�ɐU���Ă���s���̐l�ɂ������߂��܂��B
�ڂ����͉��L�T�C�g�����Q�Ƃ��������B
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4777103404/250-0578551-8678607#product-details
���u�Z�p�Ҏ��i�|�v���t�F�b�V���i���E�G���W�j�A�Ƃ͉����v
���{���@�n�l���ف@2400�~�i�ŕʁj
�Z�p�҂̗ϗ��̖��Ɏ��g��ł��鐙�{���A���x�͋Z�p�Ҏ��i�̖{���܂Ƃ߂��܂����B
�ϗ��Ǝ��i�A���̖��͐[���Ȃ����Ă��邱�Ƃ𐙖{����͉�������������Ă��܂����A
�{���́u�͂��߂Ɂv�ɐ��{����͎��̂悤�ɏ����Ă��܂��B
�č��Ƀv���t�F�b�V���i���E�G���W�j�A�Ƃ����Z�p�Ҏ��i���x������A���̐��x���܂��A�Z�p�җϗ�����ĂĂ����B
�Z�p�҂̗ϗ��Ǝ��i�Ƃ́A�Ԃ̗��ւ̊W�ɂ���B
�Ƃ����̂́A�Z�p�҂ɗϗ������߂�Љ�̎���܂��A�Z�p�Ҏ��i��K�v�Ƃ��邩��ł���B
�킪���̌���́A�Z�p�җϗ������������悤�ɂȂ�������ŁA�܂����̊ϓ_����̋Z�p�Ҏ��i�ɂ͖ڂ������Ă��Ȃ����A
���ӁA����ł͑���Ȃ����ƂɋC�����ɑ���Ȃ��B
���{����炵���A�_�������R�Ƃ��Ă��܂��B
�����������{����̃z���X�e�B�b�N�ȃo�����X���o�ɋ������邱�Ƃ������̂ł��B
���̖{�͂����I�ł���A�@��x�̉�������S�ł��̂ŁA�K��������ʓI�ȓǂݕ��Ƃ͂����܂��A
����ł����܂��܂Ȏ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�Q�����Љ�܂��B
�Ȋw�Z�p��Z�p�Ҏ��i�Ɋւ���@���͓��{�ɂ��A�����J�ɂ�����܂����A
���̗��O�Ɗ�{�p�����Ⴄ���Ƃ𐙖{����͖��m�ɂ��Ă���܂��B
���{�@�́A�Ȋw�Z�p�𗘗p���悤�Ƃ��Ă���̂ɑ��A�č��@�́A�Ȋw�Z�p�𐧌䂵�悤�Ƃ��Ă���B
�����āA���ꂪ�Z�p�Ҏ��i���x�ɑ傫�ȉe����^���Ă���Ƃ����̂ł��B
���ɂƂ��ẮA����͋����ׂ��C�Â��ł����B
����܂ʼn��ƂȂ����������Ƃ��Ă������Ƃ���C�ɕX�����ꂽ�悤�ȋC�����܂��B
�����ЂƂ����ɂ͑傫�ȋC�Â��ł����B
���i�ɂ́A���v�̑��ʂƌ��v�̑��ʂ����邪�A
���{�ł͎��v�̊ϓ_�ő������Ă�����v�̎��_�����v���Ă���ƌ����̂ł��B
�����Ă݂�Ƃ܂��������̒ʂ�ł��B
����͑傫�ȈӖ��������Ă��܂��B
�����܂ł��Ȃ��A���̂Q�͐[���Ȃ����Ă��܂��B
�����āA���̂Q�̎w�E���琙�{����̍l����p�����ǂݎ���ł��傤�B
���̂Q�̂��ƂɋC�Â������ł��{���͓ǂމ��l������Ǝv���܂��B
������ƌ����{�ł͂���܂����A
�Z�p�ɊS�̂������l�n�s�Ɏ��g�܂�Ă�����A
���邢�͊�Ɨϗ��ɊS�̂�����ɂ́A����ǂ�ł������������{�ł��B
���Ȃ݂ɁA���{����\���Ƃ߂�m�o�n�@�l�Ȋw�Z�p�ϗ��t�H�[�����ł́A
���N�x�A�Z�p�җϗ����e�[�}�ɂ������J�t�H�[�����̊J�Â��������Ă��܂��B
���̂��߂̋C�y�Ȍ�����������Ă��܂��B
�u���ɏW�܂��āA���������Ȃ���A�ǂ�ȃt�H�[�����ɂ��悤�����C�y�ɘb�������Ă��܂��B
��������m�点�̃R�[�i�[�ňē����Ă��܂����A�S���S���ł��B
�S�̂�����͂��Ђ��Q�����������B
�����ǂ͎����S�����Ă��܂��̂ŁA���[����������������ē������Ă��炢�܂��B
���u���a�̂��߂̌o�ϊw�v
��{���@���Ώ��X�@2500�~�i�ŕʁj
��T�A�T�ԕŏЉ����{������̐V���ł��B
����܂ł���{����̒���͐����Љ�Ă��܂������A
��{������قǒ��슈���ɗ͂�����̂́A�u���a�Ɋւ���V�����l�����v���L���Ă�����������ł��B
���̍l�������{����͎���3�_�ɐ������Ă��܂��B
�@���a�O�̉���̗��j�̒��Ɉʒu�Â���B
�A���O�̉���͊�{�I�l���ŕ\�����B
�B���a�͊�{�I�l���̌`�ɂ��Ė��O���l�����Ă����ׂ����̂ł���B
����3�_���x�[�X�ɂ��āA��{����͂���܂Ő��X�̒���������Ă��܂����B
�������A�����ƍL�����n�ŁA������o�ςɑ���l������`���Ă����Ȃ��Ƃ��߂��Ƃ������ƂɋC�Â��������ł��B
�����āA�V���ɏ������낵���̂��A�{���ł��B����͌o�ς������Ă��܂��B
��{�����z�̍���ɂ����Ă���Ǝ��̍l�����Q����܂��B
�u�l���v���v�Ɓu�V�Љ�_����v�ł��B
���̎��_����u���a���I��{���l���̂��߂̑�R�̊v���v�����N���Ă��܂��B
���t�������Ɠ`���ɂ����Ǝv���܂����A�����������z�̊�{�ɂ���̂́u���ׂĂ̐l�Ԃ̌l�̑����v�ł��B
�����̂��߂̊�{�I�l���▯���`�̌��E���{����͎w�E���܂��B
�����������Ƃ͂���܂ł̐�{����̒���ŏڂ����q�ׂ��Ă��܂������A
�{���ł��ŏI�́u���{��`�o�ςɘg�g�݂�^����Љ�I���l�v�ɊȌ��ɐ�������Ă��܂��B
���̕��͂�ǂ�ł��炦��A��{����̎����Ǝ���𗝉����Ă��炦��ł��傤�B
�ߑ㖯���`�́A�l�Ԃ̑����Ɗ�{�I�l����F�߂���l�X�͈̔͂��]��ɂ���������B
���{��`�̗��������́u���҂́w�l�Ԃ̑����x�ɑ���z���v���������o�ό����������I
�ߑ㖯���`���u���҂́w�l�Ԃ̑����x�ɑ���z���v�����������������������I
���̌������A��{����͂����̕����̃J�����@�j�Y���ɋ��߂Ă��܂��B
���������l������{�ɂ����āA�{���ł͌o�ϊw�̊�{���킩��₷��������Ă��܂��B
���a���l�����Ă������߂ɂ́A
��������l�ЂƂ肪�A�����̍l���Ɋ�Â��Ď�̓I�ɍs�����Ă������Ƃ��K�v�ł���A
���̂��߂ɂ͌o�ςɑ���m�����K�v���Ɛ�{����͌����܂��B
����܂Ŋw�Z�ŋ����Ă����o�ϊw�͉ʂ����ĕ��a�̂��߂̌o�ϊw�������̂��ǂ����A
�Ƃ����̂���{����̂����ЂƂ̖���N��������܂���B
�{���͐���Ⴂ�l�����ɓǂ�łق����{�ł����A
�u�o�ς�m���ĕ��a�╟���̂��Ƃ��l���悤�v�i�{���̕���j�Ƃ�����{����̌Ăт����́A��҂����Ɍ����Ă���킯�ł͂���܂���B
�ǂ�ł���������Ƃ��ꂵ���ł��B
�����ĕ��a�Ɍ����Ẳ����s�����N�����Ă����ƂƂĂ����ꂵ���ł��B
���u���Ȃ��̎q�ǂ������Q�҂ɂ��Ȃ����߂Ɂv
�����p�i�@�������Z���^�[�@2005�@1500�~�i�ŕʁj
�R���P�A�̌��J�I�l���ł�������̂���������ł��B
�����Ē��������炢�܂����B���ꂪ���̖{�ł��B
����Ɂu�v�����Ƌ����͂���Ă�P�V�̖@���v�Ƃ���܂��B
�q��Ă�ʂ��Ď����̐[����������Ƃ������ƂɎ����ŋߑQ���C�Â��Ă����̂ł����A
����Ȃ��Ƃ������ĕ\��Ɏ䂩��ċC�y�ɓǂݏo���܂����B
�������A�ǂݏo�����r�[�ɁA��������̂���ǂ����b�Z�[�W���S�ɐ[���˂��h����A��C�ɓǂݏI����Ă��܂��܂����B
���ɑ����̂��ƂɋC�Â�����鏑�ł��B
���̖{�ɏo���������Ƃ�[�����ӂ��܂��B
�q��Ă��������ł����A�l�Ƃ̊W�����l�����ŁA�ŋ߂������������Ă��������g�̖��𐳖ʂ���w�E���ꂽ�C�����܂��B
�����ւ̌������Ǝ��ȕϊv�̉\���ւ̊�]�ƌ����A����������̃��b�Z�[�W����������C�����܂��B
���܂�ɂ��l�I�Ȋ��z�������Ă��܂��܂������A���ׂĂ̐l�ɓǂ�łق����{�ł��B
���Ȃ��Ƃ��q��ĂɎ��g��ł���l�ɂ͐���Ƃ��ǂ�łق����ł��B
���̖{�̑�ނɂȂ��Ă���̂́A���S�K�N�������N���������N�Ƃ��̗��e�̘b�ł��B
���͂������������������I�ɂ��߂ŁA�������̂��̂Ɋւ����_�]���قƂ�Ǔǂ�ł��܂���ł����B
�����ē���Ȏ����ƍl���Ă��܂����B
�������蒼���Ĉ�C�Ɉ������荞�܂ꂽ�̂́A�ǂݏo���Ă�����15�Ŗڂł��B
�����ɂ́A�������N���������N�ƕ�e�Ƃ�������ɏ��߂Ėʉ�����̗l�q���A��e�̎�L����Љ��Ă��܂��B
�i���N�́j�u�M�����b�Ƃ����ڂ����v�u�������`���v�ōR�c����Ɠ����ɁA���̖ڂ���͗܂����Ă��܂����B
�����Ɉ�ꂽ��̌���B��e�́A�u�S�ꂩ�玄������ł���Ƃ����ځv�����ăV���b�N���܂��B
�����āA���N���u���[���Ƃ������߂āv�ώ@���A�{���{���Ɨ܂����ڂ��Ă���̂����āA�u����v�ƃn���J�`��n�����Ƃ��܂��B
���N�́A���̃n���J�`���u�o�[���ƌ����������̂��v�܂����B
��������͂��̏�i�ɁA���̖{����ǂݎ��A�������炳�܂��܂Ȃ��Ƃ�ǎ҂ɋC�Â����Ă����̂ł��B
���̊፷���͂܂��ɉ����Ȑl�Ԃ̖ڂł���S�ł��B
�����āA�������e�ւ̌��������b�Z�[�W���o���Ă���܂��B
���Ȃ��Ƃ����́A��������̃��b�Z�[�W��S�̒�܂Ŏ����������܂����B
�����ł��邩�ǂ����܂����M�͂Ȃ��̂ł����B
�q��Ă����̘b�ł͂���܂���B����͎Љ�̂�����ɂ��傫�Ȏ�����^���Ă��܂��B
����A�����g�̐����������߂čl���Ȃ�������Ȃ��Ǝv���m�炳��܂����B
�܂��܂����ɂ͊ώ@�҂���̒E�p�ł��Ȃ������A�����I�ɋ��ۂ�����̂��瓦�����Ă��܂����������܂��B
���N�̕�e�Ƃǂ�قǂ̈Ⴂ�����邩�A���M������܂���B
��l�ɂȂ邱�Ƃ��ɗ͊������Ă�������ł����A�����\���ɑ�l�ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂�������܂���B
�l�X�Ȃ��Ƃ��l���������Ă��܂��܂����B
�����āA������ƈ��������ݏo���_�@�����炢�܂����B
��������Ɋ��ӂ��Ă��܂��B
�{���Ɋւ���ڂ����ē���ǎ҂̔����Ȃǂ͒�������̃z�[���y�[�W�ɂ��f�ڂ���Ă��܂��B
���Ђ��ǂ݂��������B
http://www.jiritusien.com/familypsychology/book/index.htm
�܂��A��������́A���ɂ���������̃T�C�g�������Ă��܂��B
���Ȃ��̎����x���b�n�l
http://www.jiritusien.com/index.htm
�g�D���v���x���b�n�l
http://www.jiritusien.com/sosikikaikaku/index.htm
�Ȃǂ͂�����������ɕx�ޓ��e�����ڂł��B
�Ƃ��������͂�������̐l�ɂ��̖{��ǂ�łق����Ǝv���Ă��܂��B
���͂����ł������ł��B���Ђ��ǂ݂��������B
���z���������Ă��炦��A�����Ƃ��ꂵ���ł��B
����������w���ł��܂��B
���u�n�[�g�t���E�\�T�G�e�B�v
���^��@�O�܊ف@1500�~
���^�炳�߂��Ă��܂����B
���M���ĊJ���ꂽ�͍̂�N�ŁA��N��2���̐V���u�����_�v�u�V���_�v���������낵�܂������A�܂��{���̈������炵���������܂���ł����B
����̐V���͈������炵���傫�ȍ\�z�Ɋ�Â����͓I�ȐV��ł��B
�������̎莆�ɂ��A�u�n�[�g�t���E�}�l�W�����g�v�u�n�[�g�t����J���p�j�[�v�ւƑ����u�����S�w�O����v�̖��J���̏��ł��B
�҂��]��ł�������ł��B
�����������Əo������̂́A���Ԃ�k��B�s�ł̃z�X�s�^���e�B���e�[�}�ɂ����t�H�[�����������Ǝv���܂��B
���������Ȃ�10�N�O�ł��B���łɂ��̎��A�������͎��M��������߂Čo�c�ҋƂɐ�O���Ă��܂����B
�ނ̉������̒����ǂ܂��Ă��炢�A���̍L����Ɛ[���ɋ����������Ă������́A���Ў��M�ĊJ��]��ł��܂������A
���悢��{�i�I�Ȏ��M���ĊJ����A�ƂĂ����ꂵ���ł��B
���̊ԁA��Ќo�c��̌�����A�V���Ȏ��_����������Ă���͂��ł�����A����ȍ~�ւ̊��҂����܂�܂��B
�R����̂P��ڂɂ�����{���́A�h���b�J�[�́u�l�N�X�g�E�\�T�G�e�B�v�ł̖���N�ɑ����̓I�ȉ����ƒ��҂͈ʒu�Â��Ă��܂��B
���҂̈ӋC���݂��`����Ă��܂����A�ǂݏI���Ă��̎v�����ƂĂ��[���ł��܂����B
����قǑS�ʓI�ɋ����ł����{�́A���܂肠��܂���B
�������̂���܂ł̖{�ɂ́A���X�٘_���������̂ł����A�{���Ɋւ��Ă͑S�ʓI�ɋ������܂��B
���̍l������̓I�Ȋ�ƌo�c�ɔ��W�����Ă������삪���Ɋy���݂ł��B
�����Q�O�N�قǑO���u�Q�P���I�͐^�S�̎���v�Ƃ������_�������A
�����������Ă��������Łu�^�S�W��Y�Ɓv��u�f�f�B�P�C�e�b�h�E�}�[�P�e�B���O�v�Ȃǂ��Ă����肵�Ă��܂������A
���̖{�͂���ȏ�����q�Ș_���ł͂Ȃ��A���ɐ��^�ʖڂɗ��_�����A�S�L���ȎЉ�̃f�U�C����`���Ă��܂��B
����Љ�̎w�j�Ƃ��Ă̎��H�I�Ȏ����ɂ��x��ł��܂��B
���e�̖��x�������̂ŗe�Ղɂ͗v��ł��܂��A�n�ǂ���邱�Ƃ������߂���D���ł��B
������L���ł����A����炪�����ɂȂ����Ă��܂��B
�������́A�{���ŁA
�Q�P���I�ɂ����鎄�����̉ۑ�Ƃ����̂́A�����̂̐V�����`���\�z���Ă������ƂȂ̂��i87�Łj�B
�Əq�ׂĂ��܂��A�����Ă��̃��f���̈�Ƃ��āA������u�������Ă��܂��B
�S�������ł��B
�������g��ł���m�o�n������܂��Â���́A���ׂĂ��̎��_�ɗ����Ă��܂��B
���̃V���[�Y�͊�ƌo�c�ւƏ����i�߂��Ă����\��ł����A
�V���������̎Љ�ւ̓W�J�����Њ��҂������Ǝv���Ă��܂��B
�{���́A���������V�����傫�ȕ���̃v�����[�O�ł��B
������ƖJ�߂����̊�������܂����A���ǂݏI���āA���ɐS�����N���N���Ă��܂��̂ŁA�d��������܂���B
�{�̓��e�́A�o�ŎЂ̃T�C�g�Ō��Ă��������B
�Ƃ����������߂������P���ł��B
�����ǂ�ŁA���߂č�N�̂Q����ǂނƂ܂��������ۂɂȂ邩������܂���B
�R�����Y���X�ł̍w��
���u�푈���I����Ă��[�ڂ��̏o��������x���A�̎q�ǂ������v
�����M�T�@�|�v���Ё@1365�~
�ȑO�A���Љ���A�����J�ݏZ�̎ʐ^�ƁA�����M�T����̎ʐ^�G�{��2��ڂł��B
�O��́u�ڂ��̌����푈�v�͂ƂĂ��D�]�ŁA���̂Ƃ���ɂ�����������܂����B
����́A���������x���A�̓��풆�ɏo������q���B���l�̂��̌�̐�����ǂ����h�L�������^���[�ł��B
���ɂ͑O��ȏ�ɍl������������̂�����܂����B
�O������m�点���܂������A��������̃z�[���y�[�W�����Ђ������������B
�ƂĂ����C�u�ȓ����̂���ʐ^���炳�܂��܂ȃ��b�Z�[�W�����܂��B
�ʐ^�W�͐����������������Ă��炤���Ƃł��ˁB
���X�ɂ܂��o�Ă���͂��ł��B���Ђ���ɂƂ��Č��Ă��������B
http://www.kuniphoto.com
http://www.jmag.com/kuni.html
(kuni journal)
����ȑO�̂��̂͂������N���b�N