��g�D�Ȋw�(�g�D�w��@�֎��P�X�X�P�j
�m�v�|�n
�Љ�ɂ������Ƃ̑��݂����債�����ʁA��Ƃ��P�Ȃ�o�ϋ@�ւł��邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ȃ����B��Ɗ����̕]�����o�ϓI���_���炾���ł͂Ȃ��A�Љ�I�Ȏ��_����l���Ă����Ȃ���Ȃ炸�A�v���X�ʂ����ނ���}�C�i�X�ʂ��d�����Ă����K�v���o�Ă����B��Ƃ͂���܂ł̂悤�ȁu�Љ�s��v�ς��̂Ă�Ƌ��ɁA��Ɠ����ɂ������肵���Љ�o���m������K�v������B���̊�{�͊�Ɛl��l�ЂƂ�̐������ɂ���B
���L�[���[�h��
�@�@�@�@�@��Ɗ����̉��l�o�����X�C��ƕ]�����C�R�[�|���[�g�E�V�`�Y���V�b�v
�@�@�@�@�@��ƃp���_�C���]���C��Ƃ̎Љ
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���͂��߂Ɂ^�o�c�_�����Ƙ_��
�@��Ƃ�����Љ�̖ڂ��ς���Ă����B�������A����͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��B�n�抈�͂̏ے��Ƃ��Čւ�ł��炠�����H��̉��˂��A�����ɂƂ��Ă̖����̂ƂȂ�A����Ƌ��Ɋ�Ƃւ̔ᔻ�����܂肾�����̂́A����30�N���O�̂��Ƃł���B�����āA1970�N��ɓ���Ɓu������f�m�o�v�c�_���N�����Ă���B
�@ ���x�o�ϐ����́A�l�X�Ɂu�L���v�������炵�Ă��ꂽ���A�����ɘc�݂����肾�����B�u���n�ȁv��ƍs���i�Ⴆ�Ό����i���@�s�ׁj������������A��Ƃɑ���ᔻ�̍��܂�����N�����Ă���B
�@���̓s�x�A��Ƃ͎���̎Љ�I�ӔC��ϗ��𐳂����Ƃɓw�߂Ă������A��ƍs�����Љ�I�ɐ��n���Ă����킯�ł͂Ȃ��B�ނ���A��Ƃ̂�����͑S���Ƃ����Ă����قǕς���Ă��Ȃ��B�c�_�����̂́A�����u�o�c�҂̗ϗ��v�ł���u�o�c�̂����v�������B����{���I�Ȗ��͖₢������邱�ƂȂ��A���̌��ʁA�c�݂▵���͂܂��܂��~�ς���Ă��Ă���悤�Ɏv����B
�@ �����A��ƕs�ˎ��͌ʊ�ƃ��x�����玟��ɍ\�������Ă��Ă��邵�A�u���̒��̒���Ȃ��ʁX�v�͒��Ԃ𑝂₵�A�������m�M�Ɖ����Ă��Ă���B�u�ϗ��v��u�o�c�̂����v�̎����Ō���Ă���ȏ�A����͓��R�̋A�����낤�B�����ɐV�����o�c�p���_�C�������߂悤�ƁA��Ƃ̖������Ƃ̘_����₢�����Ȃ�����A���Ԃ͕ς��Ȃ��B�����č��A���߂Ċ�Ƃ̂���������ꂾ���Ă���B
�@����͑傫�ȕς��ڂɂ���B���E��Ȋ����������ߑ�́A���̐����̌̂ɁA���낻�뎞��̖������낻���Ƃ��Ă���B�ߑ㉻���i�̊j�ł�������Ƃ��A����̂���������{���猩�����ׂ��������낤�B����́u��Ƃ̎��s�v�̂��߂ł͂Ȃ��A�ނ���u��Ƃ̐����v�̂��߂Ȃ̂��B�����ɖ��̓��������B
�@ ���݂̊�Ɨ͂������Ă���A�ΏǗÖ@�I�ȑΉ��ł����ʂ̎��Ԃ͂����炭����邾�낤�B���ꂪ���܂ł̊�Ƃ̎p���ł������B�������A�ʂ��Ă���ł����̂��낤���B����͏�������������ɂȂ肻���ȗ\��������B���̗\����{���ɂ��Ă������ǂ������A��Ƃ̖��������߂Ă����̂ł͂Ȃ����B���̂��߂ɂ��A��Ƃ͂�������ƎЉ�̖ڂ��~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�Љ���܂���������Ɗ�Ƃ̎��Ԃ𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�o�c�헪�Ƃ��Ắu�����v���y�X�������ɂ�����A���邢�͎����ɂ̂��������Ȕ���Ƙ_���Ԃ����肷�邱�Ƃ́A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��Ƃ́u�Љ�̎q�v�ł���A�Љ����Ƃ������l�X���\�����Ă���Ƃ������R�̎�����Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@��Ƃ�����Љ�̖ڂ́A�����āu�o�c�_�v�ɂ���̂ł͂Ȃ��B�o�ϊ��������Ɍ����Ċ�Ƃ��l���Ă���킯�ł��Ȃ��B�Љ�̒��̊�Ƃ̃|�W�V���j���O��A�Љ�̂�����Ɋ֘A���Ă̊�Ƃ̂���������ɂȂ��Ă���B�c�_���ׂ��́u��Ƙ_�v�Ȃ̂ł���B
�@�o�c�_�Ɗ�Ƙ_�Ƃ́A���Ĕ�Ȃ���̂ł���B�Ⴆ�A�t�B�����\���s�[�i���P���_�j��{�����e�B�A�i�����I�s�ׁj�A���邢�͒n������肪�b��ɂȂ��Ă��Ă��邪�A�������u�o�c�_�v�ōl���Ă��܂��ƁA��ƃC���[�W�헪��Ј��������A���邢�͐V�K���ƂƂ��Ă̌��ʂ��c�_����邱�ƂɂȂ�B�����A�u��Ƙ_�v�ōl����A����͊�Ƃ̖�����Ɛъ�̑g�ݑւ��ɂȂ����Ă����B�������ς��A���R�A�o�c�̂������ς���Ă���B
�@ �������A�o�c�̂������ς�����Ƃ��Ă��A��Ƃ̖�����]����܂ŕς��킯�ł͂Ȃ��B�ނ���A�ړI��ς��Ȃ����߂Ɏ�i��ς���ƌ������z���낤�B���҂͖��ڕs���ł͂��邪�A�ǂ��Ɏ��_��u�����őS��������c�_�ɂȂ��Ă��܂��B
�@��Ƃ̐����Ɏh������āA��c���g�D�ɂ���ƌo�c�̂��������悤�Ƃ�������������B�ړI���c�_���ꂸ�ɁA��i�Ƃ��Ắu�o�c�v���M�҂𑝂₵�Ă��镗���ɂ͑傫�Ȋ뜜���ւ����Ȃ��B
�@ �i�q��m�s�s�̒a�����A�����������z�̋�̓I�Ȃ�����̂ЂƂł���B������u���c����Ɓv�́A�V������Ƃ̂�����i�Ⴆ�Ί�Ƃ̎Љ�̃��x���A�b�v�j�̒�Ăɐ��肦���ɂ��ւ�炸�A�����ɂ͂���܂ł̊�Ƃ̘_����M�S�ɒNj����Ă��邾���̂悤�Ɏv����B�����ł��A�c�_�́u�o�c�_�v�ł����āA�u��Ƙ_�v�ł͂Ȃ��B����͂������Ȃ��Ƃł���B����܂ł̖c��ȎЉ���Ɠˏo�����n�ʂ���l���āA�i�q��m�s�s�����c����A�Ɛт��グ�邱�Ƃ͓��R�ł���B�o�c�w�͂Ƃ͊W�Ȃ��B���́A����������Ƃ���C�Ɏ��I�ȋ��K�I���v��Nj����邾���ł����̂��Ƃ������Ƃł���B��ƂɂƂ��Ă̐V�������v�T�O��ƐъT�O�ɐV�������_�����邱�Ƃ��A����������Ƃ̖����ł͂Ȃ������̂��B���������̋@��ł������ɂ�������炸�A��Ƙ_�̓W�J���قƂ�ǂȂ��������Ƃ��A���̐[���������Ă���B
�@���܋c�_���ׂ����Ƃ́A�u�o�c�v�̂����ł͂Ȃ��u��Ɓv�̖����₠����ł���A�o�c�҂́u�ϗ��v�ł͂Ȃ���Ƃ́u�_���v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B���ꂪ�{�_�̊�{�I�Ȏp���ł���B
����Ƃ�����Љ�̖�
�@��Ƃɑ���Љ�̊��҂͑傫���ω�������B1989�N�Ɍo�ύL��Z���^�[���w���Ȃ�����Ƃɂ̂��ނ��Ɓx�Ƃ����e�[�}�Ř_�����W�����B�S������U�P�O�҂̘_������ꂽ���A�����Ō��ꂽ��Ƃւ̊��҂́A�Ⴆ�Ύ��̂悤�Ȃ��̂ł���B1)
�@�Љ��
�g��Ҍٗp�Ȃǂ̒��ړI���҂̂ق��A�����ƍL���͈͂ōs���Ɗւ���ĎЉ������̗��Đ��i�ɗ͂������ׂ����Ƃ����ӌ��������B��Ƃ̒m�b�Ɛl�ނ𓊓����Ȃ�����x��Ă��܂��Ƃ�����@����i����l���������B
�A��������
�����ւ̎x���⍑�ۓI�ȕ����𗬂���ƂɊ��҂��Ă���l�������B���Ɍ�҂ɂ��ẮA��Ƃ̎����͂␢�E�I�ȃl�b�g���[�N�̊��p�����҂���Ă���B
�B����
����ւ̊��҂������B���݂̊w�Z�����ƒ닳��Ɏ��]���A��Ƌ��炱���B��̗L���ȋ���Ǝw�E����l������B�Ј������ł͂Ȃ��A�c������A��ҋ���A�Љ�l����Ȃǂ̗l�X�ȖʂŁA��Ƃ��������ʂ������Ƃ����҂���Ă���B��Ƃ̂�����������c�߂Ă����Ƃ����ӌ������Ȃ��Ȃ������B
�C������
�s�s�ɗ𑝂₷���Ƃւ̋��͂⎩�R�����̌��݂Ȃǂ̎��R���ۑS�A���邢�͓s�s���̊X����x���`�A�g�C���Ȃǂ̌����{�݂̐�������ƂɊ��҂���l�������B
�D�n�搮��
�n��Â���ւ̊��҂������B���ɎЈ��̃{�����e�B�A�����ւ̎x���v�����������Ă���B��Ǝ{�݂̊J���̗v���������B
�E��������
�s���N�Ȑ���������������ւ̔ᔻ�͋������A���̈���ŁA��Ƃ͂����ƐϋɓI�ɐ����ɒ��Ă����ׂ����Ƃ����c�_�������B
�F�V���������n��
�V�������{�̍��ƃr�W�����Â����21���I�Ɍ����Ă̐V���������̒�Ă��A��Ƃɖ]��ł���l������B
�@���������ׂĊ�Ƃ������邱�Ƃ́A�����I�ł͂Ȃ����A�K�ł��Ȃ��B��Ƃ�����������L���邱�Ƃɂ��ẮA��Ƃ̎��_������A�Љ�̎��_������A�ᔻ���o����Ă���B�t���[�h�}����n�C�G�N���ɏo���܂ł��Ȃ��B���錤����ł��̘b�������r�[�ɁA�m�l�̌o�c�w�҂���u����Ȃ��Ƃ����Ă������Ƃ͂Ԃ�Ă��܂��v�ƈ�ɕt���ꂽ���Ƃ�����B���邢�́A��N���f���ꂽ�m�g�j�X�y�V�����u��ƎЉ��₤�v�ŁA�����Ƃ��u��Ƃ͂������̂����������Ă�������̂ł����āA�]�v�Ȃ��Ƃ�����ׂ��ł͂Ȃ��v�Ƃ�����|�̔��������Ă����B
�@�������A�����������ɑ��đ����̐l�X���s���������A�ǂ��ɂ����Ăق����ƍl���Ă���Ƃ��������͑�ł���B�ǂ��ɂԂ��Ă����̂��킩��Ȃ��A���������C������ƂɌ����Ă̊��҂ɂȂ����Ă���̂ł���B����������A���ꂾ����Ƃ̎Љ�I�Ӗ����傫���Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł���B������������Ƃ͕��u���Ă����Ă����̂��낤���B��Ƃ͗��v�Nj����ړI�ł���A���v���グ�Đŋ���[�߁A��͍s���̎d���Ɗ�����Ă悢�̂��낤���B��Ǝ��炪���ׂĂ���邱�Ƃ͖������Ƃ��Ă��A���̉����Ɍ����āA��Ƃ͉��炩�̖������ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���̓_�ɂ��ẮA�o�c�w�҂�L���҂����A��Ƃ̌������i��ł���B��Ƃ͒P�Ȃ�o�ϋ@�ւł͂Ȃ��A�Љ�@�ւł��蕶���@�ւłȂ���Ȃ�Ȃ��Ɣ�������o�c�҂��o�n�߂Ă���B���������_����s����͎̂d�����Ȃ��Ƃ��Ă��A����̕ς��ڂɂ����ẮA�����ɐ�s���鉼�����K�v�ł���B�Œ�I�Ȋ�ƃ��f�����Ɨ��_���玩�R�ɂȂ��āA�V������ƃ��f�����\�z���邱�Ƃ�����̉ۑ�ɂȂ��Ă��Ă���B�A�����[�j���O�����߂��Ă���̂͌o�c�҂����ł͂Ȃ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@
���L���Ȏ���̊�Ƃ̈Ӗ�
�@��Ƃɑ���Љ�̖ڂ��ς���Ă����̂ɂ́A���R����Ȃ�̗��R������B
�@�܂��A��Ƃ���芪���Љ�u���s���v����u���]��v�ւƕω��������Ƃ��A���̗��R�Ƃ��Ă�������B���s������̊�Ƃ̖ڕW�́u���̖L���ȎЉ�v�������B�����K�V���́u�����N�w�v�ɏے������u�ǂ����̂������Љ�ɒ���v�Ƃ�����Ƃ̖����́A���s������ɂ����Ă͑傫�ȈӖ������B�������ŋ߂̂悤�ɁA���s���ǂ��납�������ӂ��قǖL���ɂȂ��Ă��܂��ƁA���̈Ӗ��͕ς���Ă���B���������u�o�ς̘_���v��u��Ɛ��x�v�́A���s����O��Ƃ��č\�z����Ă������̂ł���B���]��̏̒��ŁC���̂܂܂̘_�����p�����邱�Ƃɂ͖���������B
�@�u���Y�����v���ɂƂ��čl���Ă݂悤�B�u���Y�v�Ƃ́u�ό`�ώ��v���u�o�ϓI���_�v����]���������̂ł���B���_��ς���A����́u����i�j��j�����v�ɂȂ��Ă���B���R�������Ƃ��ď���C�G�l���M�[�������B���Y�̉ߒ��ŏo���s�p���͔p������C���i�������p������邪�C����͊��̏���ɂȂ����Ă���B���̂����邱�Ƃ́A�����ɂ��̂����Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�u�ό`�ώ��v���̂ɉ��l������킯�ł͂Ȃ��B���s���̏̂��Ƃł́u���Y�I���ʁv���]�����ꂽ���A���]��̎���ɂ́u����I���ʁv���d�v�ɂȂ��Ă���B���ƍ�镨�Ƃ̉��l���t�]������ƌ����Ă������B����������ƍs���̗��`����F�������ɁC�u���̂����邱�Ƃ����[�J�[�̎g���v�Ƃ��蕨�Â���ɐ�O������A�����Ƃ����o�ς̊�{�ƍl���邱�Ƃ͊댯�ł���B���]�莞��i���R�͊�����j�ɂ́A���s������Ƃ͈������Ƃ̖����₠���������͂��ł���B
�@��Ƃ̊�������̍L������d�v�ȕω��ł���B��Ƃ̕t�������͋}���ɍL�����Ă���A��Ƃ�����ڂ͂���܂łɂȂ����l�����Ă���B�����āA���ꂪ��Ƃ̂������ς�����B���̂ЂƂ́A�O���[�o���[�[�V�����̐i�s�ł���B���{��Ƃ��ŋ߁A�R�[�|���[�g�E�V�`�Y���V�b�v�����ւ̊S�����߂Ă���̂́A���{��Ƃ̉��Ăł̊������_�@�ɂȂ��Ă���B���l�ɊC�O��Ƃ��܂��A���{�ł̊�����ʂ��āA�َ��Ȃ��̂��w��ł��邾�낤�B��Ƃ͂܂��ɁA�{�[�_�[���X��������n����ɁA�V����������J���敺�̖������ʂ�������B
�@�{�[�_�[���X�͍��������̖��ł͂Ȃ��B�C�O�ł̊����ɂ́A���R�̂��ƂȂ��當��������ւ���Ă���B���̈Ӗ��ł��A��Ƃ͌o�ς̐��E�ɂƂǂ܂��Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă���B��������ɂ����Ă����Ԃ͓��l�ł���B��Ƃ̍s���͌o�ς̊_���i�{�[�_�[�j���čL���肾���Ă���B���v�Ƃ͒��ڂȂ���Ȃ��Љ���╶���������s����Ƃ������Ă���B���̂��Ƃ́A���R�A����܂łƂ͈�������l�ςƂ̐G�ꍇ�����Ӗ����Ă���B�o�ς̘_���ŕ����╟���Ɋւ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��͂��ł���i�����ɂ́A���������Ă��܂��đo���������Ă���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��j�B
�@��Ƃ�����ڂ��ς���������ЂƂ̗��R�́A�Љ�ɂ������Ƃ̑��݂�����I�ɑ��債�����Ƃł���B�u��ƎЉ�v�Ƃ������t������悤�ɁA���܂�Љ�̎���͊�ƂɂȂ��Ă��܂����B�����l�̂W������ƂɌٗp����Ă���A��ƂƊւ��Ȃ��������邱�Ƃ͓���Ȃ��Ă����B��Ƃ̎Љ�I�ȉe���͂����債�A���̉��l�ς�s�����Љ�����E����Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B
�@�����Ȃ�ƁA�t�Ɋ�Ƃ͏���ȐU�镑�����ł��Ȃ��Ȃ�B��ɎЉ�I�ȉe�����l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��Ƃ̑��݂��������������͌������ꂽ���Ƃ��A���x�͌������]���̖ڂɂ��炳��邱�ƂɂȂ�B�ǂ�����Ђ����ł���Ă��镪�ɂ́A���ɂȂ�Ȃ����Ƃ��A�����̊�Ƃ����l�ȍs�����Ƃ邱�ƂŖ����N�������Ƃ�����B�u���������v�����̂����Ⴞ�낤�B�u�K�v�Ȏ��ɕK�v�ȗʂ�������v���Ƃ���{���O�Ƃ��A�Ƀ[����ڎw�����������́C���G�ȑg���Y�Ƃɂ�����ɊǗ��̃��_���Ȃ����A���Y��������ɑ傫�ȈЗ͂��������A�����̊�Ƃ��̗p���邱�Ƃɂ���āA�������̕s�s�����������邱�ƂɂȂ�B�ɕ⊮�̂��߂ɕ��i�𓋍ڂ����g���b�N�̉������������A���H��p�[�L���O�G���A�ɑҋ@����A���Ԃ�����Ƃ����{���]�|�̌��ۂ��o������B
�@��Ƃ̏��L����o�c�����ł��낤�Ƃ��A���͂�u��Ƃ̏���ł���v�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă���B�g�������Љ�ɑ傫�ȉe����^���邩��ł���B���̂��Ƃ�Y��āA�X�̊�Ƃ�����ȍs�����Ƃ������Ƃ��A�ŋ߂̃o�u���o�ςȂ̂ł���B�Љ�I�ɏd�v�ȈӖ������y�n���A�s�L�n������Ƃ����Ď��R�ɏ�����������u�����肷�邱�Ƃ͋�����Ȃ����A�����ɂ��Ă�����Ɏg���Ă����킯�ł͂Ȃ��B
�@��Ƃ̐������A�Љ�ɂ������Ƃ̈ʒu�Â���傫�Ȃ��̂ɂ��Ă����킯�����A���̌��ʁA��Ƃ͎��R�ɍs�����錠�����̂ł͂Ȃ��A�Љ�ɑ���ӔC���������̂ł���B������������Ă����ƌo�c�҂͏��Ȃ��Ȃ��B�o�c�҂��Љ���╶���ɔ������Ă����̂ł���A�s�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ȃ��Ƃ��A��Ƃ�����Љ�̖ڂ���������Ǝ~�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����ƕ]�����̕ω�
�@�Љ�̖ڂ̕ω��́A��Ƃ̕]�����_�̕ω��ɂ�����Ă���B�Ⴆ�A���o�r�W�l�X�̊�ƌ����̐���́A�ȑO�́u�����̌����v���������A�T�N�قǑO����u�ǂ���Ёv�ւƕς���Ă���B�u�����̌����v�ł́A���v����������邢�͍����̎��̌��S�����A��ƕ]���̎��_�������B�o�ς�g�D�̎��_�Ŋ�Ƃ��]������Ă����킯�ł���B�������A�u�ǂ���Ёv�ł́A�����₷�����ǂ����A�Љ�Ƃ̊W�͂ǂ����ȂǁA�Ј���Љ�̎��_���d������Ă���B�ŋ߂ł́A�u��������Ɓv�u�D������Ɓv�ȂǂƂ����\���������Ă���A���╶���̎��_�����܂��Ă���B�͂��T�N�قǂ̊ԂɁA��ƃ��f���́u������Ɓv����u�D������Ɓv�ւƌ��ς��A���̕]�����_�͔��ɑ��l�����Ă��܂����B����́A��ƂƂ͂����������������̂��Ƃ����c�_�ɂȂ����Ă���B
�@���j�̐i���́A�����ɏZ�ވ�l�ЂƂ�̐��������ǂ����̂ɂ��Ă������Ƃł���B���̂��߂ɂ́A�Љ��ǂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Љ��ǂ�������@�͂��낢�날�邪�A�Y�Ɗv����A�l�ނ��I�������V�i���I�͎Y�ƂW�����邱�Ƃł������B�����āA���̎�i�Ƃ��đn�o���ꂽ�̂���Ƃł���A�ݕ��o�ς̘_���ł������B���̊�Ă͐��������ƌ����Ă����B�Ƃ�킯�A��Ƃ̐����͖ڂ��܂������̂�����B�l��`�I���R��O��Ƃ����ݕ��o�ϑ̐��̊j�Ƃ��āA��Ƃ́u�L���ȎЉ�v�̎�����簐i���A�����A�����������߂��̂Ă���B�Љ�͖L���ɂȂ�A��X�̐������L���ɂȂ����B�����̘c�݂͂�����̂́A20�N�O�̐����ƍ��̐������r���čl����A���̂��Ƃ͔ے肵�悤�̂Ȃ������ł���B
�@�����A������L���ɂ��邽�߂̎�i�������Y�ƂƊ�Ƃ��A����ɖړI�����A���̊Ԃɂ��Y�Ƃ̔��W�Ɛ����̖L�����Ƃ��������n�߂��B�����āA�����̂��߂Ɋ�Ƃœ����Ă����l�X���A��Ƃ̂��߂ɐ������]���ɂ���悤�Ȃ��Ƃ��N���肾�����̂ł���B��ƌo�c�҂��A�Љ��L���ɂ���̂ł͂Ȃ��A�Љ���s��Ƃ��Ċ�Ƃ�L���ɂ��Ă����p�������߂Ă����B���̂܂܂����ƁA�Љ�̂��ׂĂ��s�ꉻ���ꂩ�˂Ȃ��B
�@�s�[�^�[�E�h���b�J�[�́A��Ƃ̖����́u�ڋq�̑n���v�ł���Əq�ׂ����A����͊�ƃT�C�h�̏���Ȍ������ł����āA�Љ�I�Ȏ��_�͔��o���܂܂�Ă��Ȃ��B�����́A����Ȃ�̈Ӗ����������̂�������Ȃ����A�����������z����ƂƎЉ�Ƃf���Ă������ƂȂ��ׂ��ł��낤�B��Ƃ̖ړI�́u�ڋq�̑n���v�Ȃǂł͑S���Ȃ��A�u�l�X�̐����̌���v�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�Y�Ƃ��D�悳�ꂽ�̂́A���ꂪ�l�X�̐�����L���ɂ��邱�ƂɂȂ���������ł���A�����Y�ꂽ�Y�ƗD��͈Ӗ����Ȃ��B���߂Đ����D��Љ����o�����Ӗ��́A�����ɂ���B
�@�Љ�̖ڂ̕ω��́A�l�X�̍s���̕ω��ɂȂ����Ă������A�V������ƕ]�����Â���̓����ɂ��ĐG��Ă������B
�@�č��̔�c���g�D Council of Economic Priorities �i�b�d�o�j�́A���N�A���Ҍ������|�[�g" Shopping
for a Better World "�\���Ęb����ĂB����܂ł̂悤�ȍ����w�W�⒊�ۓI�ȃC���[�W�Ŋ�Ƃ�]������̂ł͂Ȃ��A��̓I�ȕ]�����ڂm�ɂ��A����Ɋ�Â��Ċ�Ƃ̕]���\�����B�����āA����҂ɑ��āC�Љ�ɍv�����Ă����Ƃ��x�����Ă������ƌĂт������̂ł���B����͓����ɁA��Ƃ̂�����ɑ��郁�b�Z�[�W�i�K�C�h���C���j�ł��������B���̕]���(�\�P�j�ɂ��Ă͈٘_�����邾�낤���A���Ȃ��Ƃ������ɂ͐V������ƃ��f���ւ̒�Ă��܂܂�Ă��邵�A��̓I�Ȍ��t�Ŋ�ƂƑΘb���悤�Ƃ����p����������B
�@���l�Ȃ��̂Ƀo���f�B�[�Y����������B1989�N�A�G�N�\���Ђ̃^���J�["�o���f�B�[�Y��"���A���X�J���Ō������o���̂��N�������̂��_�@�ɁA�č��̊��ی�c�̂���Ă����u��Ƃ�����ۑS���Ă������߂Ɏ��ׂ�10�����v�ł���B������V������ƕ]�����̒�ĂɂȂ��Ă���B
�@���{�ł����l�ȓ�����������B�܂��\���Ȃ��̂Ƃ͌����Ȃ����A�Љ��Ƃɋ�̓I�Ȓ�Ă����͂��߂����Ƃ͕]�����Ă����ׂ����낤�B�������������ɑ����Ƒ��̔ᔻ�͂悭���ɂ��邪�A��Ƒ����炫����Ƃ����ΈĂ���o����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ŋ߁A��Ƃ͎Љ�Ƃ̑Θb�p�������߂Ă��邪�A���������e�[�}�������D�̃e�[�}�ł���͂��Ȃ̂ɁA��ώc�O�Ȃ��Ƃł���B
���\�P�� Shopping for a Better World�̊�ƕ]���v�f�i�P�X�W�X�N�Łj
�E���P�����̊�t���Ă��邩
�E�o�c�w�ɏ����͂��邩
�E�o�c�w�ɏ������������邩
�E����Ɋւ���Ă��Ȃ���
�E�������������Ă��Ȃ���
�E��Ə������J���Ă��邩
�E�n��ɍv�����銈�������Ă��邩
�E���q�͎Y�ƂɊւ���Ă��Ȃ���
�E��A�t���J���a���Ǝ�����Ă��Ȃ���
�E���ۑS�ɐϋɓI��
�E�Ƒ��ւ̔z���͏[����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
����Ƃ͉��l�̑n���҂�
�@���߂Ċ�Ƃ̖������l���Ă݂悤�B��Ƃ͘J���͂��͂��߂Ƃ������Y�v�f���g���āA���̂܂܂ł͐l�X�̖��ɗ����Ȃ����́i�����j���A�l�X�ɖ𗧂��i��T�[�r�X�ɓ]�����ĎЉ�ɒ���������ʂ����Ă���i��Ɗ������f���T�j�B��Ƃ͉��l�̑n���҂ł���A��Ɗ��������傷�����قǎЉ�͖L���ɂȂ�Ƃ������ƂɂȂ�B�Љ�͂��̌��Ԃ�Ƃ��Ċ�Ƃɗ��v��^���A���̊����̔��W���x������B���ꂪ����܂ł̊�ƃ��f���ł���A��Ɗ����͐��Y���Ƃ��đ������A��������������邱�Ƃ��o�c�ۑ�ł������B
�@���}�P���@��Ɗ������f���T
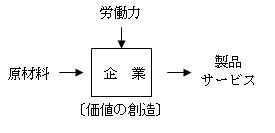
�@���̂悤�Ɋ�Ɗ������������l��n�����邾���ł���A���͊ȒP�ł���B��Ɗ����͐l�X�̐�����L���ɂ��A���{��Ƃ̐����͐��E���犽�}���ꂽ�͂��ł���B�����������ᔻ����邱�Ƃ��Ȃ��������낤�B�����Ȃ�Ȃ������̂́A���̃��f������Ɗ����̈�ʂ�������Ă��Ȃ�����ł���B��������������L���āA��Ɗ����������̂���Ɗ������f���U�ł���B
�@�@���}�Q���@��Ɗ������f���U
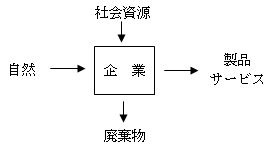
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�����͌��ǂ̂Ƃ��뎩�R�ɂȂ����Ă����B���R���H�����l�����������Ă��錻�݁A���R�̌������͕K�������v���X�̉��l�����ł͂Ȃ��A�u����I���ʁv�����߂Ă���B�܂��A�J���͂Ȃǂ̐��Y�v�f�͎Љ���ł�����B�l��̗]���Ă�������ɂ́A��Ƃ����������邱�Ƃ͎Љ�I�ɂ����l�����������A�l�s���̏ł͎���͔��]���Ă���B�l�����ł͂Ȃ��B�y�n�⎑�����A��Ƃ���荞�ނ��Ƃɂ���āA�����͑��̖ړI�ɂ͎g���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�܂�A�Љ�I�ɂ͋@����Ƃ������ʂ������Ă���B��Ƃ��������ǂ����p���邩�ɂ���āA���ꂼ��̉��l���������ꂽ��Q��ꂽ�肷�邱�ƂɂȂ�B
�@���i��T�[�r�X�̎Љ�ւ̒́A�����̒�Ăł�����B���s������ɂ́A����T�[�r�X�̋@�\���d�v���������A���]�莞��ɂ͋@�\�I���ʂ����Ӗ��I�����I���ʂ��d�v�ɂȂ��Ă���B���鏤�i��T�[�r�X���Љ�̕�����傫���ς�������͂�����ł�����B�Ȃ��ɂ́A���R�}�C�i�X�̉��l�i�@�\�ɔ�ׂĕ�����Ӗ��͌l�ɋA�����邽�߁A�Љ�I�]���͓�����j��^�����P�[�X�����邾�낤�B���i��T�[�r�X����邱�Ƃ��A���ꂾ���ʼn��l�������Ă�������͏I���A���̓��e���ᖡ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B����邩��A�ڋq�����߂邩��Ƃ����āA���i��T�[�r�X�������������킯�ł͂Ȃ��B�Љ�I���_�ɗ����������I�A�Z�X�����g���K�v�ɂȂ��Ă��Ă���B
�@���f���T�ƃ��f���U�̍ő�̈Ⴂ�́A�p����������ɓ���邩�ǂ����ł���B��Ƃ��Љ�ɒ��Ă���̂͐��i��T�[�r�X�����ł͂Ȃ��B�Љ�ɂƂ��ĕs���v�ɂȂ�悤�Ȕp�������o���Ă���B���[�J�[�����Ɍ���Ȃ��B�T�[�r�X�̂��߂ɂ��A�K���G�l���M�[�╨���̏������A��Ɗ����͕K���p�����ݏo���Ă���B��Ƃ̑��݂��������A���R�̏͂ŏ����ł��Ă�������͂悩�������A�����܂Ŋ�Ɗ������傫���Ȃ�ƁC�p�������������f���͂��肦�Ȃ��B
����Ƃ̉��l�o�����X
�@��Ɗ����̓v���X�̉��l�ƃ}�C�i�X�̉��l�����肾���Ă���B���f���U�Ɋ�Â��čl����A��Ƃ��ʂ��ĉ��l�̑n���҂ƌ����邩�ǂ����͋^��ł���B����܂ł̌o�c�w�̑����́A���f���T�Ɋ�Â��āA��Ɠ����̌o�ϐ��ƌ��������c�_���Ă������A���ꂩ��͂ނ��냂�f���U�Ɋ�Â����Љ�I�Ȍo�ϐ��ƌ��������l���Ă����K�v������B���̂��Ƃ́A�K�R�I�Ɋ�Ɨ��v�Ƃ���Ƃ̉i�����̌������ɂȂ����Ă����B
�@�Љ�I�Ȏ��_�ōl����A��Ɗ����̊g��ɂ�āA�v���X���l�̑����͒������C�}�C�i�X���l�͂���i�K����}�����邱�Ƃ����@�����B���f���I�Ɏ����A�}�R�̂悤�ɂȂ邾�낤�i�����ɂ͊�ƋK�͂⊈�������Ȃǂ�u���Ă������j�B����܂ł̊�Ɗ����́A�����炭�v���X���l�̑n���Ɏ��_���u����Ă����B�܂�A�}�̂`�̃��C������ɂȂ��Ă����B�������A����ł͊�Ɗ����𐳂����]�����Ă���Ƃ͌�����B�Љ��Ƃ�����ꍇ�́A�v���X���l�����ł͂Ȃ��}�C�i�X���l�̑n��������ɓ���āA���������������l�ŕ]�����邱�ƂɂȂ�B�܂�A�}�̂b�̃��C���ł���B��Ƃ̕]����̕ω��́A�`���C������b���C���ւ̈ړ��ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�`���C�����z�ł́A����ɐL�єY�ނƂ͌����A�E�オ��ɂȂ��Ă��邪�A�b���C���͂���Ƃ��납�琅�����ቺ���A���ɂ͐����}�C�i�X�ɂȂ��Ă��܂��B����i�K�A�}�̂w�|�C���g���z���ƁA�Љ�I�ɂ͗L�Q�ȑ��݂ɂȂ��Ă��܂��̂ł���B������A����܂ł̊�ƃ��f���ɂ͂Ȃ��������z�ł���B
�@�ǂ����Ɋ�Ɗ����̍œK��������͂��ł���B���̃o�����X���l���Ȃ���A��Ɗ����̌��E����@���Љ�I�Ɍ��肵�Ă������Ƃ��K�v���낤�B�g�厊���`�̓��{��Ƃ́A����������ƁA���̂w�_�Ɍ���Ȃ��߂Â��Ă���̂�������Ȃ��B���ɂw�_���z���Ă��܂�����Ƃ����邾�낤�B���ꂪ�A���{��Ƃ��ᔻ�����ЂƂ̗��R�ł͂Ȃ����낤���B��Ƃ͎���̓��ɁA�K���K�͎v�l�ߍ���ł������Ƃ����߂��n�߂��̂ł���B
�@���}�R���@��Ɗ����̉��l�o�����X�@
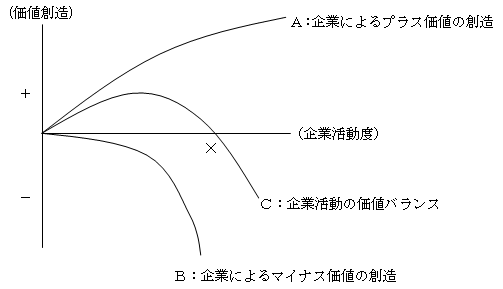
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�`���C������b���C���ւ̈ڍs�ɂ���āA�l�X�Ȍo�c�����͌����������߂��Ă����B���̊�{�͉��i����ł���B���݂̉��i�̌n�͂`���C�����x�[�X�ɂ��Ă���B�a���C���Ŕ��z����A���i�̌n�͑傫���ω�����͂��ł���B���i�̌n���ω�����A�����\������v�\�����ω����Ă����B�V������ƃ��f���ւ̈ڍs�́A���͐V�����Y�ƍ\���ւ̈ڍs�ł���A�V�����A�ƍ\���ւ̈ڍs�ł���B����͂��͂�ʊ�Ƃ̖��ł͂Ȃ��B�����Ƃ������A�b���C�����z�ɓ]���邱�Ƃ́A���ꂱ���u�~�������̃W�����}�v�i�~�����̒�������l���C���ɓM��Ă��鎞�ɁA������`�҂͐i��ŋ]���ɂȂ�A�����҂͎��Ȏ�`�҂ɂȂ��Ă��܂��j�Ɋׂ��Ă��܂����ƂɂȂ�B
�@�������A������Ƃ����āA�]���̔��z�Ń}�C�i�X���l�����������ׂ��ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�p�������Ɋ֘A���āu�Ö��Y�Ɓv���咣����l������B�u���܂ł̎Y�Ƃ́w�����Y�Ɓx�������B���̌��ʂ��܂��܂̔p�������o���Ă����B�w�Ö��x�͂��̔p����������������̂ł���B���ꂩ��́w�Ö��Y�Ɓx�̎���ɂȂ�B����������Ɓw�����Y�Ɓx�Ɠ������炢�w�Ö��Y�Ɓx���傫���Ȃ邩������Ȃ��B���z���傫���]�����āA�V�����}�[�P�b�g���ł���B�V�����Y�Ƃ����܂��v2)�Ƃ����̂����̗�ł���B�����ɓ���₷���c�_�ł͂���B�������A�傫�ȗ��Ƃ���������B
�@�Ö��Y�Ɣ��z��F�߂�A��Ƃ͉c�����Ƃɂ���ĎЉ�I���������i�ڋq�n���j�A���̖������i�ڋq�j�[�Y�ւ̑Ή��j�̂��߂ɐV�����c�����Ƃ���������Ƃ��������̎Y�Ɖ��̐��E�Ɋׂ��Ă��܂����ƂɂȂ�B����́A�܂��ɂ���܂ł̊�Ƃ̘_���ł������B�Ö��Y�Ƃ����R�A�p������r�o���邩��A�n�����͂܂��܂��������邱�ƂɂȂ�B���͐摗�肳��A��w�[���ɂȂ邾���̘b�ł���B�G���g���s�[�T�O�����čl����A���͂�薾�m�ɂȂ邾�낤�B�u���z��傫���]���v����Ƃ́A�Ö��Y�Ƙ_��F�߂邱�Ƃł͂Ȃ��āA��ƍ\����ς��邱�Ƃł���B���z�I�ɂ����A�p�����Ƃ������z�������Ȃ���ƃ��f�����\�z���邱�Ƃł���B
����Ƃ̎Љ���̑�����
�@��Ƃ̎Љ�I�v���̋c�_�Ɋ֘A���āA�R�[�|���[�g�E�t�B�����\���s�[�i���v�����j���ƃ��Z�i�i�����x���j���b��ɂȂ��Ă���B��ƕ]�����̕ω��ɑΉ�������Ƃ̓����Ƃ��Ē��ڂ���邪�A�����͊�Ɗ����̉��l�o�����X�̒��łǂ��l����������낤���B�@�}�R�ɑ����čl����A�ӂ��̍l����������B�ЂƂ́A��Ɨ��v���`���C���ւ̕�V�ƍl���闧��ł���B���̏ꍇ�́A���v�̎Љ�Ҍ��Ƃ������z�ɂȂ肪���ł���B�t�B�����\���s�[��Z�i�̖{���I�ȈӖ��͂����ɂ���B���v�̊Ҍ��ł��邩��A����Ӗ��ł́u���b�I�v�Ȃ��̂ł���A���̎g�r�����肳��邱�Ƃ͂Ȃ��B�o�ϊ����Ƃ��Ă̎��ƂƂ͒��ڊW�̂Ȃ�����ɂ��������邱�ƂɂȂ�B�P���N���u���ƃ��Z�i���c��́A���̔��z�̂��Ƃɍ\�z����Ă���B
�@��Ɨ��v���b���C���ւ̕�V�ƍl���Ă��A�t�B�����\���s�[��Z�i�𗘉v�̊Ҍ��ƍl���邱�Ƃ͂ł��邪�A��������z���o�Ă���B�a���C�������P����Ƃ������z�ł���B�����ł́A����̎��Ɗ����Ɋ֘A�����Љ���╶���x�����s���邱�ƂɂȂ�B���v�̎Љ�Ҍ��ł͂Ȃ��A�ނ��뗘�v��i�m�ہj���邽�߂̊����ɂȂ�B�������A����͒��ړI�Ɏ��Ɨ��v�ɂȂ���킯�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�^�����Ɖ�Ђ���ʈ⎙�x�����s���Ƃ����悤�ȃP�[�X���l���Ă݂�������낤�B�g�r�͌��肳��A�p���́u�����I�v�ɂȂ�Ƃ����_�ł`���C�����z�Ƃ͈قȂ������̂ɂȂ�B
�@�ǂ��炪�������Ƃ������ł͂Ȃ����낤���A�O�҂ɂ͂������̋^�`������B�Ȃ��A��Ƃ����ƂƊW�̂Ȃ����v����������̂��Ƃ������ł���B���̂��Ƃ́A���ɕč��ł����ɂȂ�A�t���[�h�}����̎茵�����ᔻ���o����Ă���B�ꉞ�A�ٔ��Ō��������Ă���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�i1953�N�̃X�~�X�����ō��ٔ����Ŋ�Ƃ̃t�B�����\���s�[���������������ꂽ�j�A����͂������������������ڂŌ���Ί�Ƃ̗��v�ɂȂ���Ƃ����F���i
enlightened self-interest�j�̂��߂ł���B������B���ɍl���Ă͂Ȃ�܂��B���v�̎Љ�Ҍ��́A�ꌩ�A�Ó��̂悤�Ɍ����邪�A�����̖����܂�ł���B
�@�Ⴆ�A���Z�i�Ɋ֘A���āA�u���{�̗D�NJ�Ƃ͍������w���f�B�`���x���āA���E���A�b�ƌ��킹�Ă͂ǂ����v�Ƃ�������������B3)���f�B�`�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ����l�T���X����̕����p�g�������������f�B�`�Ƃł���B�m���Ƀ��f�B�`�Ƃ͕����x���������������낤���A����ȏ�ɕ�����j�����݂ł���A���������̉A�ő����̐l�X���ߎS�Ȗڂɂ����Ă������Ƃ��A�����҂͂ǂ��l���Ă���̂��낤���B�t�B�����\���s�[��Z�i�́A�x�߂���̂̎{���ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@��Ƃ̎Љ�v���́A�����܂ł��{�ƂƂ̊ւ��̒��ōl������ׂ����낤�B�}�R�̂a���C��������Ƃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł���B���������������͓��y�ł��邩�{�Ƃ̃}�C�i�X�̖ƍߕ��ɂȂ�₷���B���������āA�������������͊�ƋƐтɂ���ċɒ[�ɑ������₷���B�Љ���╶���������b���C���ōl����A�ނ���Ɛт������邽�߂̊����ɂȂ邩��A�ƐтƂ̃����N�͕ʂ̌`�ɂȂ邾�낤�B
�@�����A��Ƃ����v�̎Љ�Ҍ�������̂ł���A���Ȃ��Ƃ����̉^�c�ɂ��Ă̎Љ�I�`�F�b�N�͎�ׂ��ł���B�u�A���v�Ƃ��ĎЉ�̖ڂɐG�ꂸ�ɎЉ�Ҍ�����Ƃ����l�������邪�A�Ƃ�ł��Ȃ��ԈႢ�ł���B�A�����]�������̂́A�����܂ł��l�̘b�ł���A�Љ�I���݂ł����Ƃ����ׂ����Ƃł͂Ȃ��B������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ЂƂ��ӂ��ׂ����Ƃ́A�o�ς̘_���ƕ�����Љ�̘_���͓����łȂ��Ƃ������Ƃł���B��Ƃɂ��P�ӂ̎Љ�����A�t�ɕ�����Љ�ɘc�݂��N�����P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B
�@��Ƃ��Љ���ɊS�������Ƃ͖]�܂����B�������A���̊ւ����͈����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ����A��ƃ��f���̂Ȃ��ł̂������肵���ʒu�Â����K�v�ł���B
�������Ɂ^��Ƃ̎Љ����Ɛi���̌�
�@��Ƃ��ς��ڂɂ��Ă��邱�Ƃ��l�@���A����Ɋ֘A�����Љ���Ƃ̐V���������ɂ��čl���Ă����B�V���������͂�����̂́A��ƕs�ˎ��͈���ɏ��Ȃ��Ȃ�Ȃ����A�ނ���\���������邱�Ƃ��w�E�����B��ƕs�ˎ����Ȃ��N����̂��ɂ��ẮA����ɂ����ЂƂ̘_�l���K�v���낤���A����܂ŏq�ׂĂ������Ƃ��瓚�͂قڈ����o�����Ƃ��ł��邾�낤�B��Ƃ̎����i��Ƃ̏펯�ƎЉ�̏펯�̘����j�A�o�ύ�����`�M�A��Ɛl�̐������o�̑r���Ȃǂ����܂�Ȃ�����A���Ԃ͕ς��Ȃ��B��Ƃ̎Љ���́A���͂���������Ƃ̘_�����������_�@�ɂȂ�Ƃ���ɍő�̈Ӌ`������B��Ƃ��Љ���A���̂��ƂɋC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���܁A��Ƃɋ��߂��Ă���̂́A������o�ϓI���݂���Љ�I���݂ւƐi�������邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ����낤���B���̂��߂ɁA��Ƃ͎���̎Љ���������A�����ƎЉ�ɊJ���ꂽ���݂ɂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɁA�ӂ��̂��Ƃ��d�v�ł���B
�@���́A��Ƃ̎Љ�ς̌������ł���B����܂Ŋ�Ƃ͎Љ���s��ƍl���Ă����B���Ђ̐��i��T�[�r�X���w�����Ă��炤�u���i�s��v�u�T�[�r�X�s��v�A�K�v�ȘJ���͂⎑������肷��u�J���s��v�u���Z�s��v�Ƃ����̂��A����܂ł̊�Ƃ̎Љ�ς������B�����炱���A��Ƃ͎Љ�Ƃ͂��ڐ��̈Ⴄ���݂Ɏ����u���āA�u�Љ���v��u�����Ҍ����v�����Ă����̂ł���B�u�����v�ł͂Ȃ��u�ώ@�v�ł���A��������u�����Ƃ�邩�v���ő�̊S�������B�����āA�Љ�̋��X���u�s�ꉻ�v���Ă����̂ł���B���ꂪ�u�o�ς̃\�t�g���v�̈�ʂł�����B
�@���낻��A���̍l�������̂Ă�ׂ����낤�B�Љ�͊�ƂɂƂ��āA�s��ł���O�ɁA����̑�����Ղł��邱�Ƃ�F�����ׂ��ł���B�����܂Ŋ�Ƃ��傫�ȑ��݂ɂȂ�A�Љ�̔Ďs�ꉻ���i�ނƁA�Љ���������Ȃ��Ĉ�ԍ���̂͊�Ƃł���B�č���Ƃ��Љ���ɍŋߗ͂����Ă������Ƃ̔w�i�́A�č��Љ�̍r�p�ł���Ƃ����w�E�����邪�A�܂��ɂ������肵���Љ�͊�Ƒ����̊�{�����ł���B�Љ�牽���Ƃ�邩�ł͂Ȃ��A�Љ�ɑ��ĉ����ł��邩���A��Ƃ̎Љ�ςłȂ���Ȃ�Ȃ��B����́A���{�ɂ��������l���̌��_�ł��������B
�@���́A��Ɠ����̎Љ�̌������ł���B��ƕ����Ƃ������Ƃ��ŋߐ���Ɍ����邪�A��Ƃ͂��ꂼ��Ɍ��I�ȎЕ��������Ă���B��������A�X�̊�Ƃ��ЂƂ̎Љ���`�����Ă���B���j��������Β����قǁA�܂��K�͂��傫����Α傫���قǁA��Ɠ����Ŋ���������Љ���݂���B�Ζ����Ԃ݂̂Ȃ炸�A�x���܂ŃS���t�Ȃǂʼn�В��Ԃƕt���������Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�Б�x�̂��߂ɁA�Ƒ��܂Ŋ������܂�Ă��邱�Ƃ�����B������Ј��̊ە����ł���B�Ƃ�킯���Ƃƌ������Ƃł́A�O���̎Љ�ƂقƂ�ǐړ_�������Ȃ��Ƃ��A�������Ă������Ƃ��\�ł���B
�@�����A��Ɠ��Љ�ƍL���Ӗ��ł̎Љ�Ƃ͕ʂ̂��̂ł���B��ƂƎЉ�̕ǂ����݂��Ă���ȏ�A���̊Ԃɂ��A��Ɠ��Љ�ƊO�̎Љ�Ƃ̘����������邱�Ƃ͔������Ȃ��B���̌��ʁA�Љ�̏펯�Ƃ͈������Ƃ̏펯�����肾����A���ꂪ��ƕs�ˎ��ɂȂ����Ă����B�Љ�ɑ��đ�����^�������łȂ��A��Ǝ��g�ɂ�������^���邱�Ƃ́A�ŋ߂̎��������m�ɕ�����Ă���B�d�v�Ȃ��Ƃ́A��Ƃ̓����Ɏ���ɑ������C�L�C�L�����Љ�m������Ă��邩�ǂ����ł���B�قƂ�ǂ̓��{��Ƃ́A�����͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�Ɏv����B��������̂܂܂ɂ��āA�R�[�|���[�g�E�V�`�Y���V�b�v����邱�Ƃ́A�ނ���댯�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����낤���B
�@��Ƃ́A����̐����̌̂ɁA�o�ς̐��E����L���Љ�ɏo�Ă��܂����B���͂�A�o�ς̘_�������Ŋ�Ƃ��l���邱�Ƃ͓K�ł͂Ȃ��B�Љ�╶���A����ɂ͐����Ɋւ��Ă��A��Ƃ͐ϋɓI�ȊS�Ɗւ��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă���B�o�c�w���܂��A��Ɠ�����s��W�����ɖڂ�����Ă��Ă͌����ɒǂ����Ȃ��Ȃ邾�낤�B��ƃp���_�C���̓]���͌o�c�w�p���_�C���̓]���ł�����B
�@�V��������Ɍ����āA��Ƃ͕ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̎p�͂܂����m�ł͂Ȃ����A�������͏����������Ă����B���܁A���オ���߂Ă��邱�Ƃ́A�u��Ƃ̎Љ�v�ł���B��Ƃ͎���̖ڐ����Љ�ɍ��킹�A����ƎЉ�̊Ԃɂ���ǂ����A������J���Ă������ƁA�����Ċ�Ɛl�͐����҂ł��邱�Ƃ����o���邱�ƁA���ꂪ���ꂩ��̊�Ƃ̎p���łȂ���Ȃ�Ȃ��B�u�����v�����o�c�҂͏��Ȃ��Ȃ����A�u�����v���Ă���o�c�҂͑����Ȃ��B����ł́A���ɂȂ��Ă���Ƃ͕ς��Ȃ��B
�@�����ɁA�Љ���܂��A�ς�낤�Ƃ��Ă����Ƃ��x�����Ă����K�v������B��Ɣᔻ�͊ȒP�Ȃ��Ƃ����A���ꂾ���ł͑O�i���Ȃ��B�Љ�Ƃ͕ʂɊ�Ƃ�����킯�ł͂Ȃ��B��ƂƎЉ�f����悤�Ȋ�Ɣᔻ�͔�����ׂ����낤�B�Љ�̑��ɂ��A��ƂƂ̋������u������p�����Ȃ���A��Ɛi���͐i�܂Ȃ��B��Ƃ̖��͎Љ�̖��Ȃ̂ł���B
�@1)�w�킽������Ƃɂ̂��ނ��ƕ��͕��x�ݾ���ܰ������
1989
�@2)�c������Y�w���{�Љ��ǂދ�̃L�[���[�h�x�����T���T�[��1991�N�Q����
�@3)�⟺���q�w�j���[���[�N�ߑO�O�����p�ق͖���Ȃ��x�����V���� 1989 �W�Ł@�@�@
�����C�^1990
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@