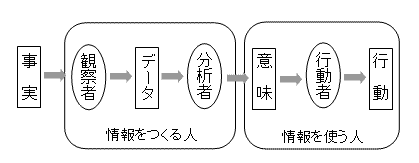
1.オーウェルの世界
産業革命以来、人々の生活を革新しつつあった近代西欧型工業化が、壁にぶつかっている。
近代西欧型工業化路線は、欧米先進国を中心として、物的豊かさを実現するのに大きな力を発彊したが、反面、資源問題、環境問題、南北問題などの様々な矛盾を露呈してきており、このままでは未来を開くことが難しくなってきている。
そうした中で登場したのが情報化社会論である。物財中心の発想から情報という目に見えないものを中心とした発想への転換である。トフラーのいう「第三の波」もまた、その根底には情報革命というべき変化が重大な要素として置かれている。
確かに、最近の情報技術の発展は革命的であり、産業革命に勝るとも劣らないインパクトを社会に与えることは間違いない。新しい時照の到来である。
新しい時代のイメージは、しかし、そう楽観できるものではない。工業化が様々な問題を引き起こしたように、情報化が社会的な矛盾をもたらすのではないかという危惧は決して少なくない。特に、作家たちの鋭敏な嗅覚は、管理社会化の予感へとつながっている。
すでにジョージ・オーウェルは、『1984年』の中で、情報を巧みに操る未来の国家を空想している。おそらく当時にあっては、一種のカリカチェアであったその世界は、現在においては決して絵空事ではなくなっており、不気味なほどに実在感を持っている。そこでの入間は、いわば情報処理機器の一端末機となっている。歴史すらが、為政者の意のままに改変される。為政者が認めたことのみが(事実の存在の有無にかかわらず)事実となるのであり、都合が悪くなれば、過去の事実まで変えられる。おそらく現在の情報技術をもってすれば、その種のことはある程度可能であろう。
情報社会のおそろしさの警告は、オーウェルにとどまらない。ハクスレイの『すばらしい新世界』、ザミャーチンの『われら』など、数えあげればきりがない。
眉村卓の『幻影の構成』はより示唆的である。そこには、自分にとって納得できないものや不都合なものが見えなくなってしまう社会が描かれている。もしかしたら、すでに私たちは、あるべきではないものは、見ても認識できなくなっているのかもしれない。
いずれにしろ、そうした社会にあっては、強力な情報管理が行われているのであり、一種の情報化社会といってよいだろう。しかし、そうした情報化社会が、人々にとって住みよいとは、とても思えない。
情報革命を経て、私たちの社会が何処に行こうとしているのかは、まだ明らかではないが、最近の状況を見る限り、その先行きについて、あまり楽観できないような気がする。
たとえば、教科書問題を考えてみよう。「侵略」か「進出」か、という問題、あるいは「被爆の図」が悲惨すぎるという問題、いずれもそこには事実の軽視が感じられる。いや、そんな難しい問題を持ち出すまでもない。視聴覚教育技術の進歩により、最近の学絞教育の実物離れは著しい。教科書に書かれたことやテレビ画面に映されたことが事実とされるのである。
オーウェルの『1989年』は、すぐそこに来ているような不安を感じざるを得ない。
2.情報とは何か
情報とは、「あることがらについてのしらせ」〈広辞苑)であるが、それを受けた人間または機械の動作に影響を与えるところに、意味があるといってよい。つまり、事実があり、行動(情報)がある時、それをつなげるものとして、情報が存在するのである。
図示すると次のようになろう。
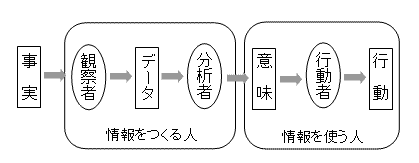
こうした過程を、情報化とよんでよいだろうが、情報化でもっとも重要なところは、情報をつくる人と行動者がもつ情報の意味である。この両者は、必ずしも一致しない。この点に、情報化社会の本質的な問題がある。
しかし、ここではこの点については深くふれない。ただ、情報化過程を整理しておくにとどめておく。
3.非情報化現象
ところで、情報化社会への移行が話題になっているが、その場合の情報化の意味は、充分議論され、明確になっているわけではない。注意深く観察すると、逆に情報化によって事実と行動との距離が拡大しているケースも少なくない。
いくつかのケースを指摘してみたい。
(1)情報競合
世間に流通する情報の量は加速度的に増加しているが、その結果、情報の単位当たりの価値の低下が生じている。情報間の競合も起こっているが、情報に対する我々の評価能力は必ずしも向上してはおらず、必要な情報を的確にキャッチしにくくなっているきらいがある。
よくいわれるように、情報は減るものではない。しかし、ある情報を手に入れることは、別の情報を捨てることでもある。
最近、流行しているウォークマンを考えてみよう。ウォークマンを利用することによって、今まで無為に過ごしていた時間に密度の高い情報を持ち込むことができたといえるかもしれない。しかし、果たして今までの時間が無為であったかどうかはよく考えてみる必要がある。確かに、ウォークマンから流れてくる情報は、音楽にせよその他の情報にせよ 情報密度は高いかもしれない。だが、実はウォークマンを着用している問、外部への関心は小さくなるだろう。街の雑音も入りにくくなる。ウォークマンを聴いている人は、要するに外部社会との接触(それこそ情報化活動の基礎である)を消極化させているといえよう。
情報の量的増大による情報不感症の増加という問題もある。あまりにも多くの情報に接しているために、情報に対する感覚が麻痺し、自分自身として情報を消化しなくなってしまう傾向が強くなっている。
先の情報化過程に即していえば、データの意味づけに際して行動者としての意味化が放棄され、分析者の与えた意味に従いがちになるということである。情報の持つ意味の画一化が進むこととなる。
いずれにしろ、情報化が、逆に情報の意味の希薄化に通ずる危険性は極めて大きい。もしだれかが意図的に情報操作をしはじめたら、事実と情報の乖離は急速に進むことは間違いない。
(2)情報化過程の分業化
情報をつくる人と情報を使う人とは、概念的には分離しうるが、実際には、従来は同じ人が行ってきた。事実を把握し、それに意味を与え、行動のための判断材料にしていたというのが、一般的であった。
しかし、最近の動きはそうではない。情報の作り手と使い手とは分離し、しかも両者の距離はどんどん離れている。見方によっては、そうした傾向を情報化社会の到来と称しているともいえよう。
こうした情報化過程の分業化は、さまざまな問題を提起している。
まず、だれにとっての情報化かという問題が問われることとなろう。情報化にとって、最も重要なことは「意味づけ」という点にあるが、その際だれにとっての意味かによって、事情は全く変わってくる。つまり、使い手を意識せずには、意味づけは不可能なはずである。それを無理に行うために、どうしても意味の希薄化が生ずる。
ひとつの別として、経済予測を考えてみよう。最近の経済予測は全くといってよいほど当たらない。データ自体は、以前よりも豊富になっているにもかかわらずである。天気予報の的中率の上昇とは対照的である。
あるエコノミストは、次のように述べている。
かつてエコノミストの多くは経済情勢を判断するため、自分でいろいろなデータを集め、それをグラフに書いて新しい変化やファクトを発見した。しかし、最近では、既存の公式データのワクの中だけで、経済分析をするため、かえって新しい変化やファクトを見落としがちである。(三橋規宏:1982年6月21日/日経新聞朝刊)
情報の把握の仕方や把握の単位が、どんどん小さくなっていることも、問題である。木を見て森を見ずのたとえのように、部分がよく見えても、全体がよく見えるとは限らない。しかも、各部分々々を、別々の人が扱うようになっているため、それを組み立てた全体像(情報の使い手にとっては、全体像が問題なのである)の意味は、必ずしも明確ではないケースも少なくない。
情報の作り手や送り手における技術の進歩が、情報を使いにくいものにしている傾向もある。先のエコノミストの感想もそうしたことを含んでいるが、情報技術のブラックボックス化は情報の意味を不安定にし、社会を脆弱にしがちである。いいかえれば、パニック化しやすい社会への移行である。豊橋信金取りつけ事件や地震予報パニックなど、現にその兆しは出ている。コンピュータ事故やコンピュータ犯罪などを持ち出すまでもなく、情報化社会の脆弱性の最大の原因は、情報不足であるというバラドクスがそこにはある。
以上の例は、いずれも情報化が、実は非情報化ともいうべき、情報障害を起こしている例であるが、今後、こうした例はますます増えていくのではなかろうか。
(3)情報世界と現実世界
情報の作り手と使い手の分化は、情報の画一化や標準化を引き起こすが、同時に、使い手にとって都合のよい情報だけがピックアップされる傾向が強まる。その結果、事実としての世界と情報から構築される世界とが分離されることになる。
情報と事実との乖離に加えて、情報の意図的収集が、世界を虚構することになる。しかも、情報通信技術の進歩が、虚構の世界までをも画一化してしまうのである。かつては、世界は各人各様であり、熱い息吹があったが、いまや一つの世界が時代を支配してしまうのではないかと思うほど、世界の表情は収斂している。ある時代に住むものすべてにとって、世界はひとつなのである。それも、事実とは切り離されて作られた世界といってよい。情報化社会とは、実はこのような世界なのではないかとすら思われる。
事実と無関係に世界が作られる例として、学校教育を考えてみよう。
もしあなたに小中学生のこどもがいたら、最近のテスト(国語か社会がわかりやすい)を見ていただきたい。たぶん答えを選択する問題があるだろうが、どれが正解かわからないような問題はないだろうか。考え様によっては、いろいろな正解が考えられるとしても、正解はひとつなのである。テストを作った人が正解と考えたものが正解で、それ以外はいかに正しくとも(正解以上に正しくとも)、間違いである。そんな例は、決して少なくない。
奈良女子大の村上哲見教授は、今年の共通一次試験の問題の中に同じような例をあげている。「科挙の制度によって採用された官僚の出身を示す語句として最も適当のものをひとつ選ベ」という問題である。「正解」は「商人や地主層」となっているが、それは事実に反するというのが、村上教授の指摘である。この例は、それほど私たちの生活には関係ないかもしれない。しかし、事実と関係なく「事実」が作られていくということの意味をよく考えておかねばならない。村上教授は次のように述べている。
いくつもの考え方がある場合に、教科書にそのすべてが列挙されるとは限らない。しかし試験、ことに正解選択方式による試験となれば、どうしても教科書に採られたものだけを正解とすることになろう。(中略)時には事実の誤りが、あるいはいくつも考えられる中のただひとつだけが、「正解」として天下にまかり通ることになり、入試センターは「教科書にこうあります」とすましていることができる。私は考えているうちに背すじが寒くなって来た。(1983年2月1日/朝日新聞夕刊)
冤罪事件や芸能界情報などで、私たちはすでに作られた世界と関わっているのだけれど、もっと生活的、日常的な部分においても、私たちの知らない内に、虚構の世界の拡大が進み、世界が入れ変わっているのかもしれない。
歴史の改変も、そう難しくもないだろう。
(4)情報資源論への疑問
情報の役割の高まりは、情報を一つの資源とみる考え方を発生させた。「知はカなり」というベーコンの言葉は、人類発生以前からの真理であるから、当然、情報を資源として考えることは重要である。
問題は、情報資源論の当然の帰結として、情報の機密化、私有化が起こるということである。いかに情報技術が発達しようとも、すべての人がその成果を平等に得るわけではない(そこにこそ情報資源論の拠所がある)。だれが、どうアクセスしうるのかが極めて重要な問題となる。
その結果、情報の独占が行われることになる。そして、企業、団体、国家などによる情報独占は、情報操作につながりやすい。ここでも、非情報化が発生する。情報公開は、実はそうした情報化社会の矛盾を解消するために問題化されているのである。
情報技術の発達が、情報ルートの独占につながるのか、または逆に情報の民主化につながるのかは、どちらとも言い難いが、放置しておけば、前者になりやすいであろう。世界電波会議の動きは、それを如実に示している。最近盛んにいわれるニューメディアも、同じ問題を抱えている。
情報化社会を、真に望ましいものとし、人類の未来を切り開く途とするためには、情報資源論の意味を真剣に考えなくてはならないのではなかろうか。短期的な視点からの対応は、危険である。
4。問題の本質
情報革命が、袋小路に入ってしまった近代西欧型工業化レジームを、新しい次元へと導くのではないかという期待は、理由のないものではない。
しかし、それ以上に、現在の情報革命が、社会から事実を抹殺し、事実とは切り離された「情報」による社会を構築してしまうのではないかという危惧がある。
そうした社会は、ちょうどテレビドラマの中の社会のように、住みやすく、面白く、安全かもしれない。しかし、それでよいのだろうか。少なくとも、そうした社会は人頚にとっては脆弱なように思われる。
いいかえれば、現在、進みつつある情報革命は、同時に非情報化革命という側面を持っているのではなかろうか。情報化社会ならぬ、非情報化社会の出現であり、それこそ、オーウェルやハクスリーが見た悪夢ではなかろうか。
問題は、今進められている情報化が、一体、だれにとっての情報化であり、何のための情報化なのかということである。どうやっての情報化か、ということも重要である。
以下、未完。項目のみ。
①Who:だれにとっての情報化
②Why:何のための情報化
③How:どうやっての情報化
5.見えない展望
世界がみえなくなってきた。
そのため、管理社会化はさらに進みかねない。
データどころか、行動の指針が与えられるようになる。
つまり、情報の意味づけまでもが行動者の手を離れていく。
6.今こそ、情報を取り戻すために「情報」を捨てる時!
どうやって?
具体的提言を行う。
経済スステムのパラダイムにつながっているのではないか。
〔未完〕